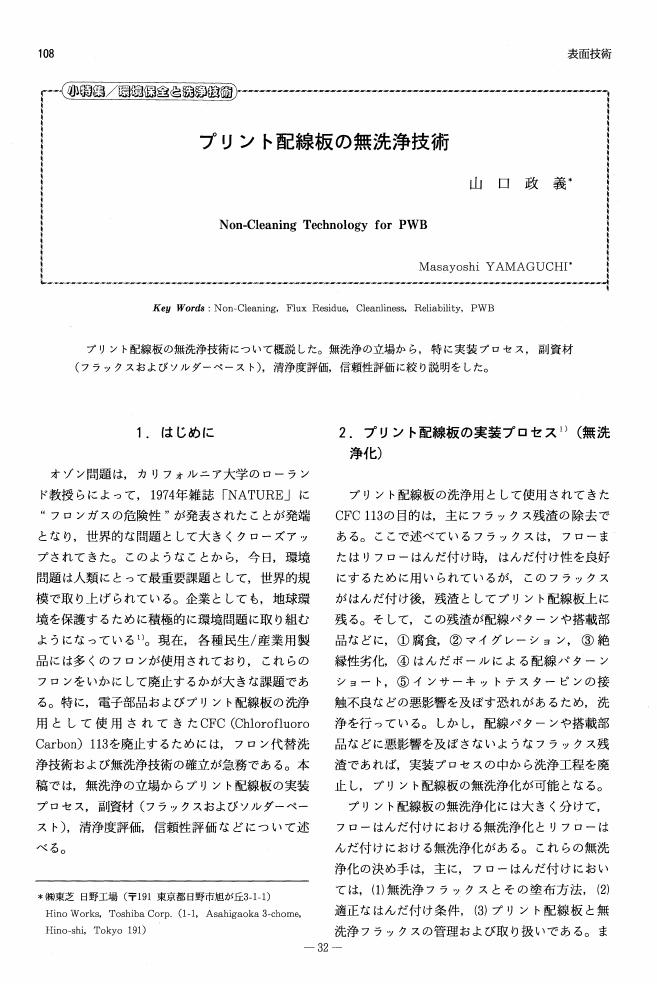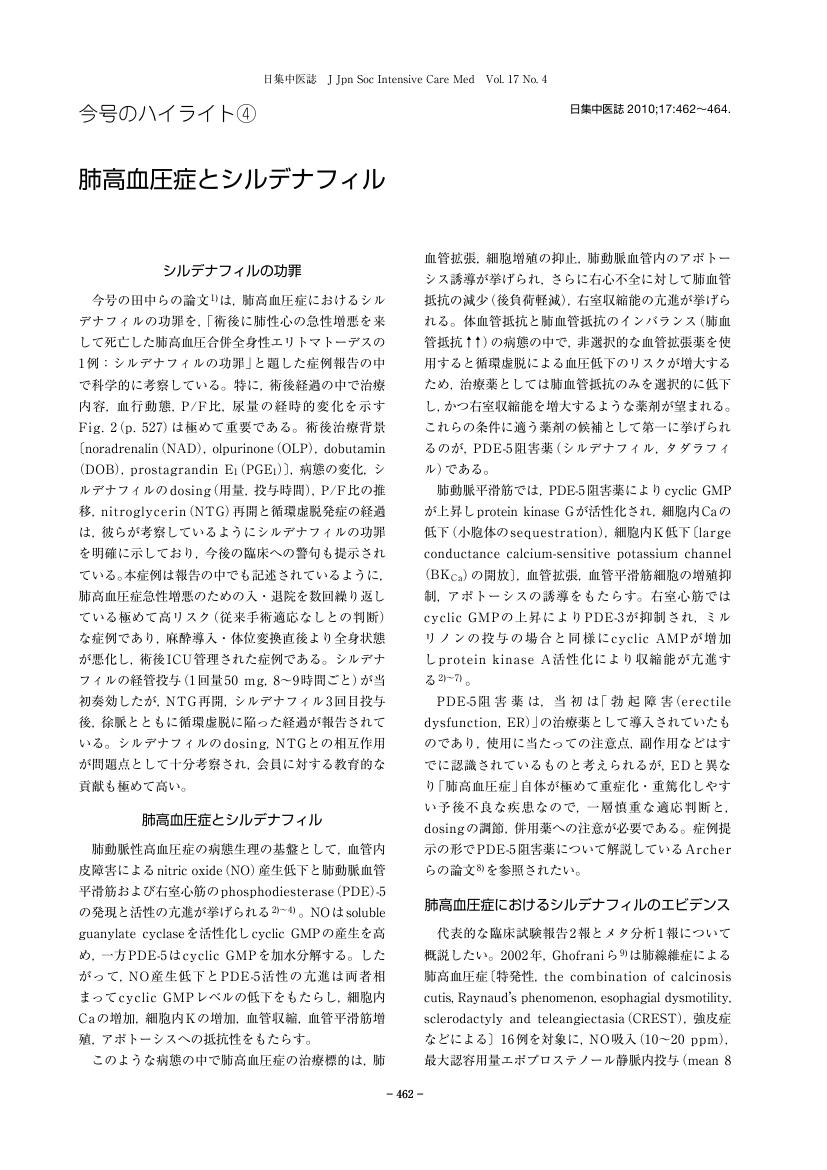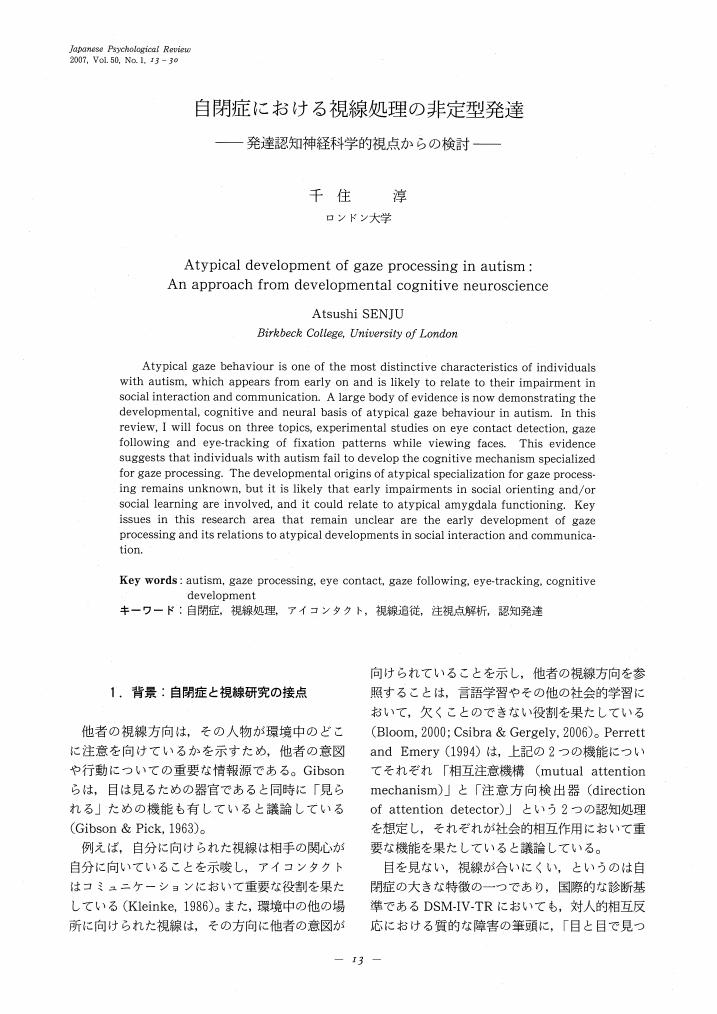1 0 0 0 OA 千葉県南部沿岸のアワビ浮遊幼生並びに着底稚貝の分布
- 著者
- 田中 邦三 田中 種雄 石田 修 大場 俊雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.9, pp.1525-1532, 1986-09-25 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 10 13
In the abalone habitat, the disturbed current is caused by the swell and eddy zones are made. The eddy zones acted to collect the swimming larvae. The authors studied the distribution chazacter of swimming and deposited larvae in the nursery ground. The research stations of eddy zones were stable distribution of swimming larvae in average number of 79 individuals per cubic meter of sea water. The density of shelled larvae deposited on the conglomerate in the reef, appeared less than the deposited shelled larvae in the downfall reef on the conglomerates. It was surmised that the swimming larvae were collected by some eddy current, and made abalone habitats. And we studied commonly that these depth were below 7m of open sea with rocky shore.
1 0 0 0 OA ホトトギスガイとコウロエンカワヒバリガイの D 型幼生から初期稚貝の形態
- 著者
- 木村 妙子 関口 秀夫
- 出版者
- The Malacological Society of Japan
- 雑誌
- 貝類学雑誌 (ISSN:00423580)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.307-318, 1994-12-31 (Released:2018-01-31)
ホトトギスガイMusculista senhousiaとコウロエンカワヒバリガイLimnoperna fortunei kikuchiiは, 静岡県西部に位置する浜名湖の奥部の潮間帯に優占するイガイ類である。筆者らはこれらの幼生を室内飼育し, 得られた試料をもとに2種のD型幼生から初期稚貝までの外部形態および交装を比較した。試料はSEMと光学顕微鏡を用いて観察した。その結果, D型幼生, 殻頂期幼生および初期稚貝のすべての成長段階で2種の間には, 形態に相違が認められた。D型幼生ではコウロエンカワヒバリガイの方がホトトギスガイよりも殻長が大きい傾向があったが, 計測値は重複しているので, D型幼生の種を殻長のみから同定することは困難である。しかし, D型幼生の交歯は, ホトトギスガイが14-15個であるのに対し, コウロエンカワヒバリガイでは9-11個と差異がみられた。殻頂期幼生では, ホトトギスガイの中央の交歯は小さくなり, 第1靱帯が交歯中央やや後方に形成される。殻の輪郭は卵型で, 殻頂は中央に位置する。これに対し, コウロエンカワヒバリガイでは, 殻頂期幼生の交歯は同大であり, 第1靱帯は交歯後端に形成される。殻の輪郭はほぼ三角形で, 殻頂は前方に偏る。初期稚貝では, ホトトギスガイは3種類の側歯を持つのに対し, コウロエンカワヒバリガイは側歯類を欠く。殻頂の位置は, コウロエンカワヒバリガイの方がホトトギスガイよりも前方に偏る。
1 0 0 0 OA 三河湾におけるアサリ浮遊幼生の時空間分布― 間接蛍光抗体法を用いた解析の試み―
- 著者
- 松村 貴晴 岡本 俊治 黒田 伸郎 浜口 昌巳
- 出版者
- 日本ベントス学会
- 雑誌
- 日本ベントス学会誌 (ISSN:1345112X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.1-8, 2001-07-15 (Released:2009-08-07)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 15 11
The clam Ruditapes philippinarum (Adams) is one of Japan's most important fisheries resources; recently, however, the anuual catch of this clam has declined to less than one quarter of its previous maximum. In order to implement more effective management of this resource, studies on early life stages, particularly the recruitment process that regulates subsequent population dynamics, are essential. To date, the recruitment dynamics of R. Philippinarum have been poorly understood due to a lack of basic information resulting from difficulties in identifying the larvae. To remedy this lack, we studied the recruitment process of R. philippinarum from April, 1998, to March, 1999, in Mikawa Bay, central Japan, using a new monoclonal antibody method. Our study revealed that R. philippinarum produces larvae from April to November in Mikawa Bay, in two discrete periods. An early spawning period occurred from April to July, with the peak abundance of larvae moving from the north-west to the eastern part of the bay. A later spawning period was observed in a relatively limited season from August to November. The distribution of larvae was basically controlled by the current system of the bay, although the larvae tended to become dispersed as they matured. The new monoclonal antibody identification method, applied for the first time in a study of a natural population, was found to be useful for studying R. philippinarum. It also proved to be an effective procedure for rapidly processing a large number of samples.
1 0 0 0 OA 自動運転自動車の走行経路高速生成法
- 著者
- 菅沼 直樹 松井 俊樹
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.6, pp.1281-1286, 2011 (Released:2012-01-10)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 7
本論文では自動運転自動車のための経路生成法として,経路上の曲率を三次スプライン関数で表現することで自動車が追従可能な滑らかな経路を生成する手法を提案する.本手法は,オンボードセンサにより計測した周辺環境の状況に適応して時々刻々とリアルタイムに更新した場合でも,曲率・曲率変化率が連続した経路を生成可能であり,自動運転自動車に適した経路生成法であるといえる.
1 0 0 0 OA 障害物回避自動走行のためのクロソイド曲線を用いた目標軌道生成と車両制御
- 著者
- 瀧山 武 藤田 純一
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.883, pp.19-00174, 2020 (Released:2020-03-25)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
In order to avoid an obstacle automatically for an automated vehicle, this paper investigated a method to generate a target trajectory using a clothoid curve and to control the vehicle. Although a mathematical constraints or a potential methods are often used to generate the target trajectory for an obstacle avoidance, it requires trial and error and experience, and it is also necessary to consider the vehicle’s drivability. The clothoid curve is often used for a road curve design, therefore, the curve is considered to be suitable for the characteristics of a vehicle driving. Although a clothoid curve passing through a target point is necessary for obstacle avoidance, such clothoid curve is often obtained by trial and error. Therefore, the numerical analyses were executed to obtain the characteristics of the clothoid curve, then, the method was investigated to generate the clothoid curve to pass through the target point. Furthermore, a method to generate a target avoidance trajectory was also investigated expanding the generated clothoid curve based on the traveling characteristics of a vehicle. For driving on the target trajectory satisfactory, both the position and turning angle of the vehicle are controlled by means of a steering manuplation. The controller was constructed using a 1-input 2-output system, therefore, it is very difficult to satisfy both value at the same time. Furthermore, it is also necessary to consider a nonholonomic characteristics of the vehicle. From these point, this paper investigated the optimal control using nonlinear least square probrem sequential quadratic programming(NLSSQP) by means of the time behaviour of input and output in the evaluation value. Well expected results are obtained and shown in the simulation and the experiment.
1 0 0 0 OA 新分類法に依る拇指指紋の研究
- 著者
- 一盛 彌
- 出版者
- 日本民族衛生学会
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3-4, pp.41-52, 1947-11-30 (Released:2010-11-19)
1 0 0 0 OA 対戦型ゲームにおける戦略多様性についてのStGA法を用いた自動分析手法の提案とその評価
- 著者
- 山本 界人 水野 竣介 ターウォンマット ラック
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.11, pp.2328-2335, 2014-11-15
本稿では,対戦型ゲームにおける戦略多様性の観点からゲームバランスの分析を自動的に行う手法を提案し,その有用性を評価した.ゲーム開発におけるゲームバランスの分析,調整は面白いゲームを作成するためには不可欠な要素である.一方で,その分析,調整のプロセスには時間的コストがかかる.開発期間に限りがあるゲーム開発の現場では,十分にゲームバランスの分析,調整を行うことができない場合も少なくない.このため,ゲームバランスを自動的に分析する手法が必要とされている.既存のゲームバランスの自動分析手法は,1つの状況を分析するために大きな計算時間を必要とする,もしくは事前に人間がゲームタイトルに依存する専門的な知識を必要とするものだった.このため,人間が知識を獲得していない,かつ多くの状況が存在するゲームへと適用する場合には大きな計算時間を必要とした.そこで,本稿では,Stochastic Genetic Algorithm(StGA)を用いて,専門的な知識なしに多くの状況を持つゲームを分析する手法を提案する.国際AI大会のプラットフォームとして利用されているFightingICEを対象にした実験から,本手法の有用性を確かめた.
1 0 0 0 OA プリント配線板の無洗浄技術
- 著者
- 山口 政義
- 出版者
- The Surface Finishing Society of Japan
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.108-114, 1993-02-01 (Released:2009-10-30)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 田中 万里子
- 出版者
- FORMATH研究学会
- 雑誌
- FORMATH (ISSN:21885729)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.101-114, 2007 (Released:2020-06-05)
- 参考文献数
- 3
現在, ICタグやICカードなどのRFID技術がIT分野のキーテクノロジーになっている. この技術とネットワークを利用することで, ユーザインターフェースを容易にした使い易いシステムを実現しようとしている.流通業界では食品トレーサビリティのためのシステムが作られ, 博物館等では入場者管理やインタープリーティングでも活用されている.そこで, RFID技術の現状とこれを使ったシステムの実例やアイデアを紹介する. そして, 現在森林情報では未利用であるが, 森林や林産物の分野への応用について考察する.
1 0 0 0 OA 肺高血圧症とシルデナフィル
- 著者
- 清野 精彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.462-464, 2010-10-01 (Released:2011-04-30)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 御府内場末往還其外沿革圖書
- 巻号頁・発行日
- vol.[34]貮拾壹亨,
1 0 0 0 産業者の政治的教理問答
1 0 0 0 OA 自閉症における視線処理の非定型発達 ――発達認知神経科学的視点からの検討――
- 著者
- 千住 淳
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.13-30, 2007 (Released:2019-04-12)
1 0 0 0 OA FPGAを用いた論理回路設計実験のための遠隔実験システムの作成と評価
- 著者
- 赤池 英夫 島崎 俊介 成見 哲 Hideo Akaike Toshiyuki Shimazaki Tetsu Narumi
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 教育とコンピュータ(TCE) (ISSN:21884234)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.51-63, 2022-06-23
本研究では,本学学内における対面での利用のみを想定して作成されていた実験システムを,やむを得ない理由で遠隔対応させ使用した結果,教育にどのような影響を及ぼしたかを調査した.対象となる実験システムは,本学3年生の実験科目の中のFPGA(Field Programmable Gate Array)を用いて初歩的な論理回路を設計する課題で用いられている.作成した回路の動作確認に実機の物理的な操作をともなうため,例年,受講生は機器の設置された計算機室に一堂に介して課題に取り組んできた.2020年度は新型コロナウイルス感染症対策として入構禁止措置がとられたため,学外から機器を操作する仕組みを導入し実験を遂行した.とくに致命的なトラブルもなく実験を行うことはできたが成績の低下がみられた.遠隔対応とすることで学生の望むタイミングで課題に取り組めたことが見出されたものの,対面であれば容易に行える学生の理解度チェックがオンラインでは難しいことも分かり,ひいてはそれが成績低下の一因であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 新規植物系変圧器用電気絶縁油パームヤシ脂肪酸エステル(PFAE)の特性
- 著者
- 鈴木 貴志 狩野 孝明 小出 英延 彦坂 知行
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.8, pp.975-979, 2009-08-01 (Released:2009-08-01)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 5 8
We have developed new vegetable based insulating oil for transformers called PFAE (Palm Fatty Acid Ester). PFAE has 0.6 times less viscosity and 1.3 times higher dielectric constant compared to mineral oil. The oxidative stability, biodegradability and acute toxicity to fish of PFAE has also been determined to be superior to mineral oil. In this paper, in order to optimize the characteristics of fatty acid esters originating from palm oil, several kinds of fatty acid alkyl esters were first synthesized in the laboratory by the molecular design technique and the transesterification from fatty acid methyl esters and alkyl alcohols. Next the electro-chemical characteristics of the fatty acid alkyl esters as insulating oil were analyzed.
1 0 0 0 OA HALおよびヒュージング仕上げプリント配線板用洗浄剤および洗浄機の開発
- 著者
- 岡田 万佐夫
- 出版者
- The Japan Institute of Electronics Packaging
- 雑誌
- サーキットテクノロジ (ISSN:09148299)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.42-46, 1993-01-20 (Released:2010-03-18)
- 参考文献数
- 2
PCBの脱フロン化に伴う無洗浄実装化や高密度実装化に対応するため, 基板の表面仕上げ方法の重要性が増している。ホットエアレベリングやヒュージング仕上げは耐熱性および耐湿性において非常に良く, 優れた方法であると言える。しかし, 実装の無洗浄化や高密度化には, プリント配線板に高い清浄性が必要となる。水溶性フラックスでホットエアレベリングやヒュージング仕上げしたプリント配線板は, 普通, 水のみで洗浄されている。ところが, 小径スルーホールの密度が高いプリント配線板やある種のソルダレジストを塗布したプリント配線板は, 水のみの洗浄では十分洗浄できないケースが認められた。そこで, 洗浄剤および洗浄機を開発し, 優れた洗浄効果を確認した。また洗浄剤導入の効果は, 超低残渣ポストフラックスによるフローソルダリング後にも反映された。
1 0 0 0 OA 日本におけるヘイトスピーチの心的基盤と法規範形成の研究
本研究の目的は、現行のいわゆるヘイトスピーチ対策法(正式名称:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)を超える新しい法規範形成の可能性を視野に入れつつ、現代日本のヘイトスピーチに関する心的基盤を実証的に明らかにすることであった。より具体的には、いかなる条件のもとでこのような差別や言葉の暴力を一般の日本人が許容するのか、またその理由は何か、といったヘイトスピーチに関わる心的メカニズムについて、サーベイ実験の手法を用いつつ検討した。
1 0 0 0 OA 注入同期型発振器の注入同期能力の最適化に関する研究
1 0 0 0 OA X線式はんだ付検査装置の開発
- 著者
- 浜田 利満 仲畑 光蔵 伏見 智 森岡 喜史 西田 武彦
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.65-71, 1993-01-05 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 5 8
This paper describes an automatic solder joint inspection system by X-ray imaging. The following were developed for highly reliable inspection of J-lead and gull-wing lead solder joints : (1) An automatic inspection method for double side-mounted PCBs (Printed Circuit Boards) by micro-focus X-ray imaging and board tilting, (2) Enhancement of X-ray image of solder joints by logarithmic transformation of a detected image, (3) Fillet judgement by comparison between a detected image and a number of typical nondefective images selected by a clustering procedure, (4) Bridge determination by multi-step thresholding and comparison between pattern frequency distribution of a detected image and that of a nondefective image. The inspection system developed with these technologies had a defect detection rate of 100% with the smallest detectable defect being 50 μm.
1 0 0 0 OA Bálint症候群を呈した急性期脳出血患者1例のADLの代償方法
- 著者
- 宮内 貴之 佐々木 祥太郎 佐々木 洋子 最上谷 拓磨 榊原 陽太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.487-493, 2022-08-15 (Released:2022-08-15)
- 参考文献数
- 21
本研究の目的は,Bálint症候群を呈した患者1名を対象に日常生活活動(ADL)で用いられる代償手段を明らかにすることとした.事例は左後頭葉出血で急性期病院に入院中の80歳代女性とした.急性期病院入院中に事例のBálint症候群の重症度に変化はなかったが,ADLは向上し,セルフケアが発症から4週間で自立した.向上したADLでは非利き手を用いた視覚的な手がかりと体性感覚による代償手段を用いていた.このことから,Bálint症候群を呈した患者のADLの再獲得には非利き手を用いた視覚的な手がかりと体性感覚を活用した代償手段の練習が有効であると示唆された.