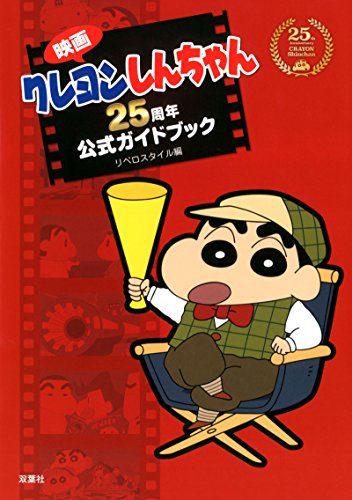1 0 0 0 OA 批判と歴史 ――アドルノとベンヤミンのマルクス理解にそくして――
- 著者
- 麻生 博之
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.61, pp.85-104_L7, 2010 (Released:2011-01-18)
- 参考文献数
- 26
If one were to reread Marx's writings today, which would be the phase of Marx's thought that would merit special attention? In this paper, I find that one core of Marx's thoughts lies in “critique.” I would therefore like to explore the significance that this critique can have as a form of fundamental thought. With this in mind, I want to consider Adorno's and Benjamin's interpretation of Marx's thought, with particular reference to their emphasis on “history”. Adorno characterizes Marx's thought as “a critical theory of society” and thinks that it is only understandable as “a historical theory”. Adorno's view is remarkable in that it characterizes Marx's thought as a form of “interpretation (Deutung)” of “natural history (Naturgeschichte)”. This can be seen as an attempt, on the one hand, to show that various societal realities that should have historical reality appear as something inevitable or as things which obey “the coercion of nature”, but on the other hand, to perceive such realities in the form of something natural or eternal which have become historically, therefore as things which are fundamentally contingent. Benjamin, in contrast, thinks that one core of Marx's thoughts consists in the recognition of history as a “critique” to uncover “the memory of the anonymous (das Gedächtnis der Namenlosen)”. In Benjamin's view, when history up to the present is grasped as something continuous, it is just a “continuum of the oppressors”. Benjamin defines the form of history description that liquidates “the epic element” of this continuous history as “construction”, and tries to understand an essential part of the Marx's thought as such an attempt to explode “the continuum of history” and to rescue “the tradition of the oppressed”.In this paper, through my clarification of Adorno's and Benjamin's understanding of Marx's thought, I attempt to examine the significance of Marx's “critique” of “history” and, through it, offer a worthy topic for further discussion.
1 0 0 0 OA Comma の研究
- 著者
- 岡部 佑人
- 出版者
- 東洋大学大学院
- 雑誌
- 東洋大学大学院紀要 = Bulletin of the Graduate School, Toyo University (ISSN:02890445)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.287-303, 2016
1 0 0 0 OA ザトウムシの形態的特徴と脚の自切
- 著者
- 中尾 栞奈 加藤 元海
- 出版者
- 高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科
- 雑誌
- 黒潮圏科学 = Kuroshio Science (ISSN:1882823X)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.86-93, 2020-03
1 0 0 0 コミックにおける読者依存性の高い地雷表現回避手法の実現
- 著者
- 伊藤 理紗 中村 聡史
- 雑誌
- 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) (ISSN:21888760)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022-HCI-199, no.39, pp.1-7, 2022-08-15
コミックは多種多様であるため,読者にとって好みの描写もあれば,苦手な描写もある.作品のメインではない一部分に苦手な描写が出現する場合,そこだけを飛ばすことができればその先も読み続けることができるが,その表現を読んで読書を止めてしまう可能性もある.そこで我々は,読者が苦手な描写を気にすることなくコミックを鑑賞するための手法を提案する.また,本研究ではその手法を実現するため,コミックを読みながら手軽に読者が任意の苦手な表現についてフラグを付与することができるシステムを開発し,データ収集実験を行った.実験の結果,実験協力者によってフラグの内容に個人差はあるもののある程度フラグが重複することが明らかになった.さらに,知見をもとにしたプロトタイプシステムを実装し,簡易的な利用実験を行うことで利用可能性を検討した.利用実験の結果,読書への没入感をなるべく損なわない予告方法にするといったシステムの改善点が明らかになった.
1 0 0 0 OA 千葉成政先生夜話聞書
- 著者
- 柳本 祐加子
- 雑誌
- 中京ロイヤー = CHUKYO LAWYER
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.43-60, 2011-09
- 著者
- Katsumi Fujii
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE Communications Express (ISSN:21870136)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022XBL0127, (Released:2022-09-05)
Before performing electromagnetic interference (EMI) measurement tests in the frequency range below 30 MHz, the test site must be evaluated by normalized site insertion loss (NSIL) using a pair of loop antennas. The site insertion loss measurements are performed with three arrangements of loop antennas to measure three-axis components of magnetic fields in the near-field regions. In this paper, it is shown that the locations of the feed gaps on the loop antenna elements change the values of the SIL. The preferable locations of the feed gaps are proposed to perform the NSIL measurements with the measurement results in a semi-anechoic chamber.
1 0 0 0 OA 農山村青少年の居住環境評価と転出・帰還志向 滋賀県朽木村を事例として
- 著者
- 森川 稔
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.163-168, 1982-10-25 (Released:2020-09-01)
- 参考文献数
- 4
- 著者
- Yutaro Hyodo Takumi Jiroumaru Noriyuki Kida Michio Wachi Shun Nomura Minoru Kuroda Hikaru Kitagawa Shinichi Noguchi Yasumasa Oka Teruo Nomura
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.242-246, 2022 (Released:2022-03-14)
- 参考文献数
- 14
[Purpose] This study aimed to compare the muscle activity around the foot and ankle joints, notably of the abductor digiti minimi, between affected and unaffected sides of individuals with chronic ankle instability. [Participants and Methods] Twelve adult males with chronic ankle instability in one ankle (age, 27.7 ± 5.4 years; height, 172.5 ± 8.1 cm; weight, 67.5 ± 8.1 kg) were included and underwent surface electromyography assessments in multiple positions on both affected and unaffected sides. Measurements were obtained for eight muscles including the abductor digiti minimi. Each measurement included a 5-s segment of the stable waveform, with the root mean square-processed and normalized to the resting position set to 1. [Results] Abductor digiti minimi activity on the affected side was significantly reduced during maximal toe extension/abduction with both ankle dorsiflexion and plantarflexion. Peroneus longus activity on the affected side was significantly greater during maximal toe extension/abduction with ankle plantarflexion; peroneus longus and tibialis anterior muscle activities were significantly greater on the affected side during maximal toe extension/abduction with ankle dorsiflexion. [Conclusion] In the absence of load, muscle imbalance in the intrinsic and extrinsic muscles of the foot was suggested. However, no significant differences were observed under loading conditions.
1 0 0 0 OA リハビリテーション医療におけるアパシーとその対策
- 著者
- 蜂須賀 研二
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.184-192, 2014-06-30 (Released:2015-07-02)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
Marin はアパシーを意識障害,認知障害,感情障害によらない動機付けの減弱と定義し,Levy & Dubois は1)情動感情処理障害によるもの,2)認知処理障害によるもの,3)自己賦活障害によるものの3 タイプに分類した。アパシーは臨床症状にもとづき診断され,やる気スコア,Neuropsychiatric Inventory,必要に応じて標準意欲評価法を用いて評価されるが,MRI や脳受容体シンチグラフィーで客観的に責任病巣を確認する必要がある。薬物療法としてドパミン系薬剤,ノルアドレナリン系薬剤,アセチルコリン系薬剤が用いられる。非薬物療法としては,促し,チェックリスト,面接と外的代償,行動の構造化,音楽療法等の報告はあるが十分なエビデンスはない。今後,原因疾患,責任病巣とアパシーのタイプ,重症度とその経過に配慮して,訓練方法の研究が必要である。
1 0 0 0 OA パルクールの新たな課題 : ルーツとイノベーションの狭間を読み解く
- 著者
- 石沢 憲哉
- 出版者
- 立命館大学人文科学研究所
- 雑誌
- 立命館大学人文科学研究所紀要 (ISSN:02873303)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, pp.49-74, 2022-01
1 0 0 0 OA 諸外国の水質管理制度(Ⅸ) ―カナダ―
- 著者
- 内藤 勲 徳田 博保
- 出版者
- 一般社団法人 日本治山治水協会
- 雑誌
- 水利科学 (ISSN:00394858)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.44-55, 1981-08-01 (Released:2020-03-15)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 哺乳類のレック繁殖における自律分散機構
筆者が1987年から1989年にかけて、英国サセックス州のペットワ-ス公園に生息するダマジカのレック繁殖行動を調査した資料を分析し、レック繁殖における雄どうしの闘争の機能の解明と、レックにおける雄間の繁殖成功度の偏りを表わすシミュレ-ション・モデルの開発に関して研究をおこなった。ダマジカは、レック内において頻繁に雄どうしが闘争を行なうが、その闘争にどのような意味があるのかは不明であった。分析の結果、レック内での闘争のほとんどは勝敗の結着があいまいな、60秒以下の闘いであること、闘争のほとんどは、闘争をしかけた個体もしかけられた個体も、なわばり内から雌のほとんどすべてを失う結果に終わること、闘争に勝つことと繁殖成功度との間には相関がないこと、なわばり内の雌の数が少ない雄が、なわばり内に多くの雌を持つ雄に対して闘いをしかけることが明らかとなった。なわばり内にいる雌の数と各雄の繁殖成功度との関係を分析すると、レック内にいる雌の、各雄のなわばりへの分布の分散が大きいほど(つまり分布に偏りがあるほど)、各雄の繁殖成切度間の分散も大きくなることがわかった。これよりダマジカのレックで行なわている闘争は、配偶の確率の低い雄が、レック内の雌の分布の偏りを平均化し、特定の雄の配偶のチャンスを低める機能を持っていることが推測される。上記のようなレック内の闘争による、雌の移動、雌が他の雌のいるところへ行きたがる傾向などを組み込み、実際のデ-タから得られた値を導入して、レック内の各雄をそれぞれ一つのセルとみなし、セル・オ-トマトンの考えでレック繁殖のモデルを開発した。これについては、いくつかの点について改良をほどこしている段階である。
1 0 0 0 OA 京都における造園用石材の地域性の研究
- 著者
- 小林 章 金井 格
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.154-170, 1983-02-28 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 77
- 被引用文献数
- 1 2
京都の造園用石材の地域性を明らかにするため地域性を石材の高目の構成 (特徴: 多くの京都産の品目。京都産・他地域産の品目の併存。数百年にわたり記載のある品目。多様な形質の品目) により記述した。その域因の解析に地域の自然要素として地形・地質を, 人文要素として庭石商の性格を採り上げた。多様な石材が京都の多くの河川・山地・丘陵地から採取きれてきた。庭石商は近世水運または資源により立地し, 石材を供給してきた。