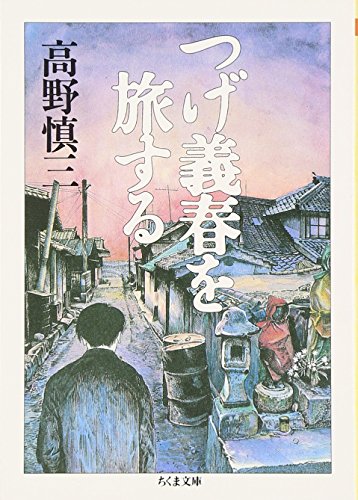1 0 0 0 文法を考慮したソースコード差分解析ツールDiff/AST
- 著者
- 橋本 政朋
- 雑誌
- ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2022論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, pp.153-154, 2022-08-29
ソースコードがどのように変更されたのかを調べる際には,テキストとしての差分を計算するツールを用いることが一般的である.しかしながらそのようなツールは基本的に記述言語の文法を考慮せず変更を行単位で示すのみであるため,ソースコードの最適化や不具合修正などの変更パターンを抽出するといった用途には不向きである.本稿では,テキストを行単位で比較するのではなく抽象構文木をノード単位で比較するツールDiff/ASTを紹介する.
1 0 0 0 OA 情動ストループ課題とプローブ検出課題で測定される注意バイアスの収束的妥当性の検討(資料)
- 著者
- 松本 圭 塩谷 亨 伊丸岡 俊秀 沢田 晴彦 近江 政雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.83-95, 2009-01-31 (Released:2019-04-06)
本研究の目的は、情動ストループ課題とプローブ検出課題のそれぞれによって測定される注意バイアス指標の収束的妥当性を検討することであった。健常な実験参加者(n=39)に、情動ストループ課題、プローブ検出課題、状態-特性不安検査を実施した。本研究では、情動ストループ課題においては単語タイプをブロック化して呈示する手続きを、プローブ検出課題においては中性語ペアが呈示される試行のプローブへの反応時間を基準として、脅威語に注意が向けられる傾向と、脅威語からの注意の解放が困難となる傾向を切り分ける手続きをそれぞれ用いた。相関分析の結果、情動ストループ課題にみられる脅威語への色命名の遅延が、プローブ検出課題においてみられる脅威語からの注意の解放の困難さと関連していることが示された。ただし、それらと不安との関連はみられなかった。これらの結果から、両課題で測定される注意バイアスの解釈について議論した。
- 著者
- 井垣 宏 堀口 諒人 福安 直樹
- 雑誌
- ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2022論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, pp.36-44, 2022-08-29
プログラミング教育へのコードレビューの導入は学生のプログラミングスキルの向上だけでなく,授業満足度の向上やレビュー後の自発的なプログラミング行動の促進といった効果があることが知られている.著者らの所属する大学では,コロナ禍の影響により一部のプログラミング演習をオンライン環境で実施している.そのため,学生間交流の機会の増加やプログラミングスキルの向上等を目的として,チームでのコードレビュー(以降チームレビューと呼ぶ)を同一のプログラミング演習を実施している一部のクラスに導入した.その結果,チームレビューを導入したクラスと導入していないクラスの間で,プログラミング課題提出締め切り後に行った自発的なコードの編集という観点において,量,質ともに一定の差があること,特にリファクタリングや未完成の課題に取り組む学生がチームでのコードレビュー実施クラスにおいて増加したことが確認された.
1 0 0 0 つげ義春ワールドゲンセンカン主人
- 著者
- つげ義春 石井輝男著
- 出版者
- ワイズ出版
- 巻号頁・発行日
- 1993
1 0 0 0 OA 小学校におけるはだし教育と安全に関する意識・態度,および健康習慣との関連性
- 著者
- 青柳 直子 内山 有子 小林 正子 柴若 光昭 衞藤 隆
- 出版者
- The Japanese Society of Health and Human Ecology
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.173-181, 1999-07-31 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 2
Based on a questionnaire survey carried out in July 1996, this study aims to evaluate the effects of barefoot education of schoolchildren in elementary schools, with respect to behaviourmodification concerning safety and healthy lifestyle. The subjects were 571 schoolchildren, 420from a school which conducted barefoot education for seven months from April to October and151 from a school which did not. The 420 children in the former were divided into one group(N=289, 76.1%) who were always barefooted and another (N=91, 23.9%) who were not. The major findings were as follows. 1. The comparison between the two schoolchildren groups revealed that the barefoot educationgroup developed more safety and health behaviour such as avoidance against hazardous objects on the schoolyard and in the classroom, hand-washing, and cleaning of gymnastic wear. 2. Within the schoolchildren in the barefoot education school, the?galways berefooted" grouppaid more attention to hazardous objects and did hand-washing more frequently, though significantly different items between the two groups were fewer than those in the between-schoolcomparison. This study suggests advantageous effects of barefoot education on development of safety and healty behaviour in schoolchildren.
1 0 0 0 OA ゴキブリを中心とした昆虫のアンテナ指示行動
- 著者
- 馬場 欣哉 塚田 章
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.142-153, 2004-09-30 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 サブワードフレーズ抽出を併用した文書分類
- 著者
- 木村 優介 駒水 孝裕 波多野 賢治
- 雑誌
- 研究報告情報基礎とアクセス技術(IFAT) (ISSN:21888884)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022-IFAT-148, no.24, pp.1-6, 2022-09-02
深層学習を用いた文書分類は従来の手法と比べて高精度を達成してきた.文書分類は固有表現抽出とのマルチタスク学習によりその精度を向上させることが可能であると報告されている.単語に基づいた特徴量を基本とする手法において,意味のまとまりとしてのフレーズは文書分類の精度に寄与することが知られている.一方で,深層学習においてサブワードは一般的に使われているが,単語とは異なり,意味のまとまりを表すとは限らない.そのため,サブワードで構成されるフレーズを文書分類に応用する研究はされてこなかった.そこで,本研究では文書分類の精度向上を目的に,サブワードフレーズ抽出と文書分類のマルチタスク学習を行う文書分類フレームワークを提案する.従来の単語に基づくフレーズ抽出手法が出現頻度を用いてきた点に倣い,本稿では高頻度なサブワードのフレーズをサブワードフレーズとして定義し抽出する.
1 0 0 0 非会話文を用いたデータ拡張による雑談対話システムの多様性向上
- 著者
- 田中 陸斗 高木 友博
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会研究会資料 言語・音声理解と対話処理研究会 95回 (2022/09) (ISSN:09185682)
- 巻号頁・発行日
- pp.47-52, 2022 (Released:2022-09-01)
深層学習を利用した対話システム構築において対話データの質と量は重要である.しかし,日本語の対話コーパスは大規模なものが公開されておらず,限られたデータしかないといった問題がある.また,コーパスを用いてend-to-endに学習したモデルはありきたりで短い応答をすることが多く,生成文の多様性が少ないといった問題もある.これらの問題を克服するために,本研究では非会話文を活用して対話データを増やすことで対話モデルの多様性の向上を試みる.ここで言う非会話文とは,web上の文章や小説の台詞などの対話の形式として整えられていない文のことであり,対話データと比較して収集が容易である.逆翻訳とサンプリング生成を用いて非会話文から対話データを増やし,不適切な対話を除去するためのフィルタを通すことでより質の高いデータを獲得する.増やしたデータを加えて対話モデルを学習させた結果,生成文の多様性の向上が見られた.
1 0 0 0 OA 地域包括ケア病床における自宅転帰困難者の検討
- 著者
- 小嶋 佑亮 鶴井 慎也 風晴 俊之 美原 盤
- 出版者
- 社団法人 日本理学療法士協会関東甲信越ブロック協議会
- 雑誌
- 関東甲信越ブロック理学療法士学会 第38回関東甲信越ブロック理学療法士学会 (ISSN:09169946)
- 巻号頁・発行日
- pp.O-109, 2020 (Released:2020-01-01)
【はじめに】地域包括ケア病棟にはポストアキュートとサブアキュートの役割があるが、これからのわが国の診療提供体制から鑑みるとサブアキュートとしての役割が強く求められる。自宅から入院するサブアキュート患者は、何らかの原疾患および障害を抱えていることが多い。 これらの患者に対し入院中理学療法が介入し入院前のADL状況と変わらない状態になったにもかかわらず、自宅復帰できない場合は少なくない。そこで今回、非自宅復帰者の特性について比較・検討した。【方法】2017年6月から2018年12月に地域包括ケア病床に入院し、理学療法士が介入した275名のうち、自宅から直接入院した患者103名を対象とした。対象を自宅復帰と非自宅復帰の2群に分類し、入棟時・退棟時FIM、入院前のADL状況、入院前主な移動手段(歩行・車椅子)、入院目的疾患を調査、比較した。また自宅転帰できなかった患者の要因を調査した。【結果】入棟時・退棟時FIMにおいて運動項目および総点数は非自宅復帰群で有意に低かったが、両群ともFIM の有意な改善を認めた。入院前のADLにおいて非自宅復帰群は、なんらかの介助を要する患者が84.6%と自宅復帰群の50.0%に比較し有意に多く、入院前の移動手段が介助歩行、車椅子であった患者の割合も非自宅復帰群が53.8%で、自宅復帰群34.4%に比較し有意に多かった。 なお、非自宅復帰群は内科系疾患がほとんどで、新規に麻痺などの機能障害を呈した患者はいなかった。自宅転帰できなかった患者のうち、76.9%は家族の受け入れの問題があった。【考察】当該病棟に自宅から直接入院してくるサブアキュート患者のうち、入院前からADL動作能力が低い患者は、在宅転帰しにくいことが示された。理学療法士の努力によりADL能力の改善が図られても、家族の受け入れにより自宅転帰が阻害される。自宅復帰を促進するには家族への働きかけが重要である。
1 0 0 0 OA 地域包括ケア病棟におけるポストアキュート・サブアキュートの傾向
- 著者
- 村田 尚寛
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.G-88_1, 2019 (Released:2019-08-20)
【はじめに・目的】 地域包括ケア病棟における機能としてポストアキュート、サブアキュートがある。現在、ポストアキュート、サブアキュートそれぞれの身体機能や在宅復帰における傾向を述べた文献は少ない。そこで当院の地域包括ケア病棟におけるポストアキュート、サブアキュートそれぞれの身体機能、在宅復帰についての傾向を明らかにする。【方法】 対象は平成29年10月から平成30年3月に当院入院した疾患別リハビリテーションの処方があった死亡退院を除くポストアキュート群121名、サブアキュート群64名とした。処方率は85.9%であった。今回この2群それぞれの入院時と退院時のFunction Independence Measure(FIM)の比較、そしてポストアキュート群、サブアキュート群2群間の年齢、入院時退院時それぞれのFIMとFIM利得、FIM効率、在院日数を比較した。統計はT検定、X2検定を用いて有意水準を5%未満とした。【結果】 まずポストアキュート、サブアキュートのそれぞれの入院時退院時のFIMの比較ではどちらも入院時より退院時の方がFIMは高い値を示しており有意差が認められた。 次にポストアキュートとサブアキュート2群間の比較では入院時FIMがポストアキュート群67.7±30.8、サブアキュート群58.4±30.4とポストアキュート群が高い値であり有意差が認められた。一方で在院日数、在宅復帰率はポストアキュート群38.8±30.7日、63.6%、サブアキュート群29.1±15.9日、78.1%とサブアキュート群の方が在院日数は短く、在宅復帰率は高く有意差が認められた。その他の項目では有意差は認められなかった。 また在宅復帰患者に限定したFIMにおいても退院時FIMがポストアキュート87.7±32.8、サブアキュート73.6±35.7と有意差が見られた。【結論】 地域包括ケア病棟の入院患者に関しては一様にリハビリテーションの介入により身体機能の向上が図れることが示唆された。ポストアキュートの方が入院時退院時ともにFIMは高い一方で在院日数や在宅復帰率はサブアキュートより低値であり在宅復帰が困難となる事例が多い事がわかった。これは他医療機関で身体機能の向上が図れているものの全身状態とは別の要因が大きく影響していることが考えられ、家屋環境や社会的背景にて在宅復帰困難となる事例が多い。一方でサブアキュートでは元々介護保険サービスの利用といった社会的資源を活用されている事例が多くFIMが低値であっても一定の身体機能に達することにより在宅への意志が強く早期在宅復帰となる事例が多いと思われる。 ポストアキュートの患者は早期に自宅環境、社会的要因の確認を行い在宅復帰に向けた多職種、地域との連携がサブアキュートより必要である可能性が示唆された。【倫理的配慮,説明と同意】 本研究は当院倫理委員会の承認を得て実施した。
1 0 0 0 OA ナスの2本仕立て栽培における育苗期の摘心処理が苗および定植後の生育に及ぼす影響
- 著者
- 堤 淑貴 陣在 ゆかり 岩崎 泰永 元木 悟
- 出版者
- 日本生物環境工学会
- 雑誌
- 植物環境工学 (ISSN:18802028)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.136-145, 2022 (Released:2022-09-01)
- 参考文献数
- 32
ナスの新たな仕立て法に関する基礎的な知見を得るため,ナスの2本仕立て栽培における育苗期の摘心処理が苗および定植後の生育に及ぼす影響を検討した.その結果,育苗期の摘心処理により育苗日数は慣行区に比べて長かった.本葉節摘心区が子葉節摘心区に比べて9~10日短かった.成苗率は本葉節摘心区が慣行区と同じ100 %,子葉節摘心区が慣行区および本葉節摘心区の70~80 %であった.本葉節摘心区では,主枝開花段数および一次側枝数は慣行区と同等であったものの,側枝乾物重,側枝着果数,可販果数,可販果収量ともに,慣行区と同等か有意に多かった.また,本葉節摘心区では,第1花までの葉数は慣行区に比べて有意に少なく,主茎長および草丈は栽培期間を通して慣行区に比べて有意に短かった.以上から,育苗期の摘心処理は,主茎長および草丈を抑制できる仕立て法の1つになると考えられ,摘心は主枝となる側枝の生育が揃い,子葉節に比べ育苗期間の短縮が見込まれる本葉節で行うことが望ましいと考える.また,摘心を行うことで着果開始節位が低下し,初期収量が慣行と同等か有意に多くなることが明らかとなった.
1 0 0 0 OA 身体計測を活用した高齢者の健康スクリーニング—肥満から骨粗しょう症まで—
- 著者
- 香川 雅春
- 出版者
- 日本生理人類学会
- 雑誌
- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.59-75, 2022-08-25 (Released:2022-08-25)
- 参考文献数
- 112
Prolongation of healthy life expectancy has been an important global issue to be achieved where the world population is continuously growing, and acceleration of ageing society in many countries and regions. Ageing causes a number of physiological changes including loss of skeletal muscle tissues and fat distribution pattern, which may increase risk of health problems such as metabolic syndrome, underweight, and sarcopenia. An early screening and diagnosis of health problems among the elderly are therefore essential to maintain health and well-being of this population. Anthropometry is a simple, portable, cost-effective, and non-invasive technique that commonly applied to screen health problems. This review describes common anthropometric variables and their cut-off points that have been utilized in health screening for the elderly and also considerations and its future prospects.
1 0 0 0 OA 薬物治療のupdate
- 著者
- 田辺 晶代 内原 正樹 成瀬 光栄
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.105-109, 2022 (Released:2022-08-29)
- 参考文献数
- 14
PPGLに対する治療の第一選択は腫瘍摘出であり,薬物治療は術前治療あるいは切除不能性に対する慢性治療として施行される。PPGLの診断が確定したら速やかにα受容体遮断薬を開始し,頻脈に対してβ受容体遮断薬を併用する。交感神経受容体遮断薬で十分な治療効果が得られない症例にはメチロシンを併用する。PPGLの根治治療は未だ存在せず,治療目標はカテコールアミン過剰症状のコントロール,無増悪生存期間(progression-free survival:PFS)の延長である。手術困難例では抗腫瘍治療として化学療法,対症療法としてαβ受容体遮断薬やメチロシンの内服が行われる。海外ではチロシンキナーゼ阻害薬,Mammalian target of rapamycin(mTOR)阻害薬,免疫チェックポイント阻害薬が試みられている。
1 0 0 0 OA 足関節底屈筋筋力調節能力と姿勢制御機能との関連
- 著者
- 廣野 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本基礎理学療法学会
- 雑誌
- 基礎理学療法学 (ISSN:24366382)
- 巻号頁・発行日
- pp.JJPTF_2022-R3, (Released:2022-08-29)
- 参考文献数
- 21
筋力を評価する際,その多くは最大随意筋力が用いられる。しかしながら日常生活動作では最大随意筋力を必要とする場面は少なく,弱い運動強度の筋力をいかに制御しながら発揮するかが重要である。その評価方法として一定の筋力を保持している最中の力変動を評価する筋力調節能力(Force Steadiness:以下,FS)がある。FS は加齢や中枢神経疾患によって,変動が大きくなる。FS は目標値を低強度から高強度まで設定可能であり,さまざまな運動強度での能力を評価することができる。今回,足関節底屈筋のFS と姿勢動揺との関連に着目した。健常若年者を対象とした場合,安定面上での姿勢動揺には最大筋力の5% のFS のみが関連し,不安定面上での姿勢動揺には20%のFS のみが関連した。一方で高齢者を対象とした場合,安定面上での姿勢動揺にはいずれのFS も関連を示さず,不安定面上での姿勢動揺に20%のFS のみが関連を示し,強度ごとに関係する運動課題が異なることを示唆した。
1 0 0 0 OA 簡便な振動板浸漬式とろみ評価法
- 著者
- 西桶 雅輝 鈴木 郁
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.Supplement, pp.2G1-01, 2022-07-30 (Released:2022-09-01)
1 0 0 0 OA 嚥下障害への対応 ―評価と手術―
- 著者
- 津田 豪太
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会報 (ISSN:24365793)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.8, pp.1309-1310, 2022-08-20 (Released:2022-09-01)
1 0 0 0 OA 軟骨細胞, 間葉系幹細胞, iPS 細胞を用いた気管喉頭軟骨再生研究の現状
- 著者
- 吉松 誠芳 大西 弘恵 岸本 曜 大森 孝一
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会報 (ISSN:24365793)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.8, pp.1281-1287, 2022-08-20 (Released:2022-09-01)
- 参考文献数
- 43
気管喉頭は硝子軟骨により枠組みを保持されており, 呼吸, 発声, 嚥下機能を担う重要な臓器である. しかし, 外傷や炎症性疾患・悪性腫瘍に対する手術などで軟骨が欠損した場合, 枠組みが維持できなくなり, その機能は大きく損なわれる. 硝子軟骨はそれ自体に再生能が乏しいため, 気管喉頭軟骨欠損に対して, これまで組織工学を応用したさまざまな軟骨再生方法の開発, 研究が行われてきた. 足場としては非吸収性足場素材や脱細胞組織が臨床応用されたが, 前者は枠組みの安定性は得られるものの, 大きさが不変であるため小児への適応が困難であり, 後者はドナーの確保や長期的な内腔保持困難が課題であった. 一方, 細胞移植 (+足場素材) による軟骨組織再生では, 軟骨細胞や間葉系幹細胞 (MSC) を用いた移植法が, 治験の段階ではあるが, 一部で臨床応用されている. しかし, 初代培養の軟骨細胞や MSC では培養時に生じる細胞の脱分化や増殖能の低下が課題として残っている. また, 近年, 無限増殖能・多分化能を有する iPS 細胞から軟骨細胞や MSC への分化誘導法が開発され, 特に膝関節領域においては臨床研究も実施されている. しかし, 気管喉頭領域における iPS 細胞由来細胞を用いた軟骨再生研究はいまだ少なく, 確立された方法はない. 今後, 細胞移植が確立されるためには, 必要な細胞を効率よく誘導したり, 必要な数だけ確保したりする, 細胞の動態をコントロールする技術が必要となる. 医工学分野の新しい技術を適切に応用し, 気管喉頭の安全かつ確実な軟骨再生方法が確立されることが期待される.
1 0 0 0 OA 歩行時の足底圧分布と足部形状および歩容の関係
- 著者
- 河村 隼太 齋藤 誠二
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.Supplement, pp.1F3-03, 2022-07-30 (Released:2022-09-01)