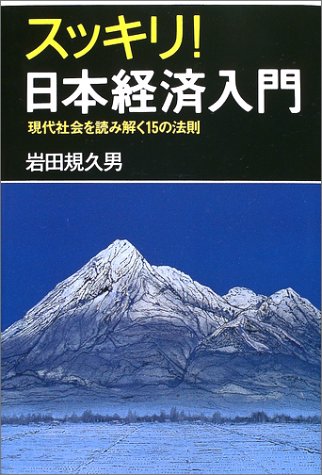- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1870, pp.54-60, 2016-12-12
オランダのアムステルダム。ここにスマートスタジアムの先進事例がある。同国の強豪サッカーチーム、アヤックスが本拠とする「アムステルダム・アレナ」がそれだ。ICT(情報通信技術)を駆使して様々な機能を競技場に付加している。
- 著者
- 荒木 孝子
- 出版者
- 天理大学言語教育研究センター
- 雑誌
- 外国語教育 : 理論と実践 (ISSN:02881942)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.49-62, 2013
ジェイムズ・クラレンス・マンガン(James Clarence Mangan, 1803-1849)がアイルランド語から英語に翻訳した優れた詩のひとつに「マグワイアに寄せるオハッシーのオード(O'Hussey's Ode to the Maguire)」がある。原詩は,詩人オハッシーが,エリザベス1世との9年戦争で命を落とした主君ヒュー・マグワイアを詠った音節詩(syllabic poetry)である。原詩の背景として,オハッシーとヒュー・マグワイアとの繋がりや原詩の音節詩としての形を明らかにした後で,マンガンの翻訳した英詩を原詩と比較検討する。この翻訳詩の特徴とその詩が,当時のアイルランドの英詩に新しい詩形を生み出した詩であることを検証する。
- 著者
- 生野 照子
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, 2010
1 0 0 0 スッキリ!日本経済入門 : 現代社会を読み解く15の法則
1 0 0 0 OA ロマンティックスタイルのドレスの構造 レプリカ製作
- 著者
- 加々美 真由
- 出版者
- 服飾文化学会
- 雑誌
- 服飾学研究 (ISSN:24344443)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.37-46, 2021 (Released:2022-03-08)
1 0 0 0 IR 帝政ロシアの移住農民家族とアジアロシア植民事業
- 著者
- 青木 恭子
- 出版者
- 富山大学人文学部
- 雑誌
- 富山大学人文学部紀要 (ISSN:03865975)
- 巻号頁・発行日
- no.65, pp.59-82, 2016
帝政ロシアでは,ウラルの東に広がるアジア部分の帝国領(以下,本稿ではアジアロシアと呼ぶ)の植民および開発は,経済的にも政治的にも,そして安全保障上も重要な意味を持つ,国家的事業として推進されていた。その国家的事業の直接の担い手となるのは,ヨーロッパロシアから移住する農民である。彼らに期待されていたのは辺境地域の開拓だけにとどまらない。「ロシア」をウラル以東へ拡大し,「統一された不可分のロシア」を創り上げること,一言で言えば帝国の「ロシア化」の担い手となることもまた期待されていた。しかし,移住農民には帝国の一体化も「ロシア化」も全く関係のないことだった。彼らは政府の移住奨励策を利用しようとしていたが,だからといって政府の意向に従うわけでもなく,彼らなりの論理に基づいて行動していた。帝国統治の文脈でアジアロシア植民が持つ意味と,個々の移住農民の人生にとって移住という経験が持つ意味は,同じではなかった。本稿は,アジアロシア移住を農村社会および農民家族の伝統や慣習と関連づけて分析する試みである。移住前と移住後では農民家族のあり方に何か変化が生じているのか,生じたとすれば何がそれをもたらしたのか考察する。そして,国家的事業としてのアジアロシア入植という大きな枠組みに,移住農民家族の経験がどのように位置づけられるのか,考えていきたい。
- 著者
- 竹中 浩
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 日本政治學會年報政治學 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.61-77, 1994
1 0 0 0 OA 漢・韓史籍に顕はれたる日韓古代史資料
- 著者
- 邵 象清
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 人類学雑誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.3, pp.p313-326, 1989-07
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 酸化チタン系誘電体
- 著者
- 日野 博夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本セラミックス協会
- 雑誌
- 窯業協會誌 (ISSN:00090255)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.693, pp.163-178, 1954-03-01 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 平塚らいてう 戦争と俳句(続)
- 著者
- 度会 さち子
- 出版者
- 追伸舎 ; 2018-
- 雑誌
- 追伸
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.127-136, 2021-10
1 0 0 0 平塚らいてう 戦争と俳句
- 著者
- 度会 さち子
- 出版者
- 追伸舎 ; 2018-
- 雑誌
- 追伸
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.50-66, 2021-06
- 著者
- おおしろ 健
- 出版者
- 現代の理論・社会フォーラム
- 雑誌
- 現代の理論
- 巻号頁・発行日
- pp.72-75, 2022
1 0 0 0 中級日本語の語法例集 : いくつかの日本語教科書から
- 著者
- 下瀬川 慧子 若松 久恵 川幡 愛恵美 宮城 幸枝
- 出版者
- 東海大学
- 雑誌
- 東海大学紀要. 留学生別科 (ISSN:03892255)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.55-131, 1978
1 0 0 0 OA 熱硬化性樹脂コンポジットにおけるフィラーの効果
- 著者
- 永田 員也 真田 和昭
- 出版者
- 合成樹脂工業協会
- 雑誌
- ネットワークポリマー (ISSN:13420577)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.6, pp.299-308, 2015-11-10 (Released:2016-01-07)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
フィラーの利用分野は多岐わたり,技術体系も複雑であることから,本稿ではトリックスポリマーをゴムや熱硬化性樹脂などの架ポリマーに焦点を当て,コンポジットの材料設計にいてフィラーの視点から詳しく紹介したい。
1 0 0 0 IR 第74回東邦医学会総会 パネルディスカッション:The Work Shift─働き方改革やCOVID-19感染症における各診療科の現状と取り組み─ 医師の働き方改革と当科における現状
- 著者
- 原 真範
- 出版者
- 東邦大学医学会
- 雑誌
- 東邦医学会雑誌 (ISSN:00408670)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.105-107, 2021-09-01
総説日本が直面する少子高齢化に伴う労働人口減少を背景に,「働き方改革関連法」が2019年4月から施行され,2024年4月からは医師の時間外労働規制が開始予定となっている.医師の働き方改革に関する政府検討会は,基本となる勤務医の時間外労働の上限水準「(A)水準」を設け,臨時的な必要がある場合は月100時間,年960時間と定めた.外科系診療科,産婦人科,救急科,臨床研修医においては,現状で約半数の医師がこの水準をオーバーしており,規制により医療の質の維持と労働時間短縮という相反するミッションが課せられることになり,十分な医師の確保が必要になる.大学病院の勤務医は,診療・教育・研究・地域医療支援と多くの任務を抱えており,当院においても医師の働き方改革を実現するためには,ワーキンググループを構築し,業務の見直しと効率化を図り,多様性,柔軟性のある働き方を取り入れ労働力を確保することが必要である.
1 0 0 0 IR 俳誌「風花」同人・須田英子(=伊澤みゆき・濱野雪・伊東英子)と世田谷 (特集 世田谷)
- 著者
- 福田 委千代 Ichiyo Fukuda
- 出版者
- 昭和女子大学近代文化研究所
- 雑誌
- 学苑 (ISSN:13480103)
- 巻号頁・発行日
- no.959, pp.41-52, 2020-09
Kazahana (discontinued), first published in May 1947, was a haiku magazine initially presided over by Teijo Nakamura (1900-1988). The issuing office was located in the residence of Teijo Nakamura in Daita, and the haiku meetings were held at the 9th branch of the Setagaya ward office near Shimokitazawa Station, hence the journals activities were closely connected to Setagaya. Hideko Suda was affiliated with Kazahana as a haiku poet in her later years. But in her early days she had contributed to various literary magazines as a minor writer: short novels for girls in Shojogaho, short novels in Seito, and short novels and essays in Shojochi, etc. under the pseudonyms "Miyuki Izawa," "Yuki Hamano," and "Hideko Ito." Focusing on her work for Kazahana, this article looks at her life and describes how she was involved in haiku as a self-sufficient resident of Setagaya ward.
- 著者
- 久米 依子
- 出版者
- 明治書院
- 雑誌
- 国語と国文学 (ISSN:03873110)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.5, pp.18-33, 2017-05