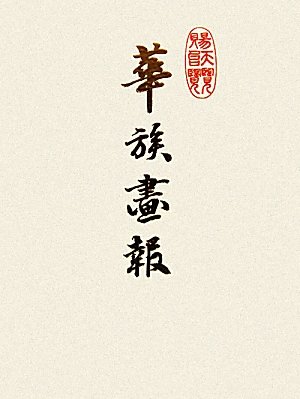1 0 0 0 OA 『官話指南』の多様性―中国語教材から国語教材
- 著者
- 氷野 善寛
- 出版者
- 関西大学文化交渉学教育研究拠点(ICIS)
- 雑誌
- 東アジア文化交渉研究 = Journal of East Asian Cultural Interaction Studies (ISSN:18827748)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.237-259, 2010-03-31
A Chinese textbook titled the Kuan Hua Chih Nan has been used by many Japanese and Western learners of Chinese since its publication in 1882. The textbook was also translated into various Chinese dialects including Shanghai dialect and Cantonese. Furthermore, the Chinese textbook, originally designed for foreigners, was revised and published in around 1918 as a textbook for Chinese people under different titles. In other words, the Kuan Hua Chih Nan also served as a textbook for Chinese people in the early 1900s to learn Mandarin Chinese or the common speech. This paper focuses on the Kuan Hua Chih Nan as a Chinese textbook published for Chinese people and examines the Kuan Hua Chih Nan and textbooks derived from the Kuan Hua Chih Nan.
1 0 0 0 OA 日本のウラン資源
- 著者
- 片山 信夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本セラミックス協会
- 雑誌
- 窯業協會誌 (ISSN:00090255)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.741, pp.C285-C288, 1957-09-01 (Released:2010-04-30)
1 0 0 0 OA ゴリラの大量虐殺とその背景 : コンゴ民主共和国の内戦が脅かす野生動物と人間との共存
- 著者
- 山極寿一
- 出版者
- 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アフリカレポート
- 巻号頁・発行日
- no.31, 2000-09
- 著者
- Ai Ebisui Ryo Inose Yoshiki Kusama Ryuji Koizumi Ayako Kawabe Saki Ishii Ryota Goto Masahiro Ishikane Tetsuya Yagi Norio Ohmagari Yuichi Muraki
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.816-821, 2021-06-01 (Released:2021-06-01)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
Pseudomonas aeruginosa resistance is a major issue worldwide. Drug resistance is related to inappropriate antibiotic use. Because antipseudomonal agents have a wide spectrum, they must be used appropriately. The purpose of this study was to clarify the trends in antipseudomonal agent use in Japan based on sales data from 2006 to 2015. The total antipseudomonal agent use was increased significantly (r = 0.10, Pfor trend = 0.00040). The proportion of fluoroquinolones use was the highest throughout the year, accounting for 88.6–91.4%. The use of piperacillin/tazobactam significantly increased. The increased use of these drugs may be due to the launch of higher doses and additional indications. On the other hand, for antipseudomonal agents, parenteral carbapenems use was 2.7–3.7%, but it has remained unchanged over the years. In Japan, permit and notification systems have been introduced to prevent the inappropriate use of parenteral carbapenems in medical institutions. It was speculated that these efforts suppressed the inappropriate use of parenteral carbapenems. This study clarified the trend of antipseudomonal agent use in Japan from 2006 to 2015. It is important to continue monitoring antipseudomonal agents use to conduct appropriate antimicrobial resistance measures.
- 著者
- 宇佐美 しおり
- 出版者
- 一般社団法人 日本専門看護師協議会
- 雑誌
- 日本CNS看護学会誌 (ISSN:21895090)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.5-12, 2016-11-18 (Released:2019-03-30)
- 参考文献数
- 18
今回、セルフケアケアモデルにPAS理論を導入し、行動化を有する患者に焦点を当て、介入技法、治療的要因を事例研究で明らかにした。2015年(平成27年)から2016年の間、精神看護CNSが関わった事例で、行動化を有する患者9名への精神看護CNSの介入技法は、「怒りのベクトル(対象)の明確化」「怒りのエネルギーをCNSがコンテインする」「怒りの対象との心理的距離の保持」「行動化のストレッサーの回避」「行動化のストレッサーの認知」「エネルギー運用のポジテイブフィードバック」「愛情対象の焦点化」「パフォーマンスの強化」「情緒的エネルギーの交換」「行動化以外の対処方法の検討」「対処行動の獲得」「現実吟味力の検討」「傷つきのある内的世界の保護」「母とのバウンダリーの明確化」「内的世界と外的世界のバウンダリーの確保」「患者の欲求、願望、意思の明確化」が、治療的要因としては、〈怒りの安全空間供与〉〈安全空間保持〉〈運用エネルギーの増幅〉〈エネルギー使用の転換〉〈共感〉〈コーピング〉〈自我機能の拡大〉〈自他バウンダリーの強化〉〈リビドーベクトルの明確化〉が抽出された。
- 著者
- 浦添市立図書館 [編]
- 出版者
- 浦添市立図書館
- 巻号頁・発行日
- 1989
1 0 0 0 三重県立図書館紀要
- 著者
- 三重県立図書館 [編]
- 出版者
- 三重県立図書館
- 巻号頁・発行日
- 1995
1 0 0 0 沖縄県立図書館紀要
- 著者
- 沖縄県立図書館 [編集]
- 出版者
- 沖縄県立図書館
- 巻号頁・発行日
- 2006
- 著者
- 山本 正彦 吉岡 さおり 岩脇 陽子
- 出版者
- 一般社団法人 日本専門看護師協議会
- 雑誌
- 日本CNS看護学会誌 (ISSN:21895090)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.1-9, 2021-11-10 (Released:2021-11-10)
- 参考文献数
- 17
本研究は,がん看護専門看護師の役割行動の実態と役割行動能力に関連する要因を明らかにすることを目的とした.全国の病院に勤務するがん看護専門看護師636名を対象に質問紙調査を実施した.質問紙は,専門看護師における自律性測定尺度におけるCNS役割行動,ENDCOREsコミュニケーションスキルスケール,育成環境に対する認識項目,属性で構成した.CNS役割行動を従属変数とする重回帰分析を行った.調査の結果,266名(有効回答率42.5%)の有効回答が得られた.重回帰分析の結果,コミュニケーションスキルを示す「他者受容」「自己主張」「自己統制」,育成環境を示す「活動支援の程度」「職務規程の有無」などの要因との関連が示された.看護管理部の役割開発における育成環境の支援整備とともに,がん看護専門看護師自らも組織に所属する管理職や専門職と協働できる高度なコミュニケーションスキルの獲得が重要であることが示唆された.
1 0 0 0 IR アダム・スミスにおける本能の概念化と経済学の生物学的基礎
- 著者
- 高 哲男
- 出版者
- 神奈川大学経済学会
- 雑誌
- 商経論叢 (ISSN:02868342)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.113-153, 2007-05
論説
1 0 0 0 IR 教職課程「総合演習」における「ジェンダーと教育」
- 著者
- 冨安 玲子
- 出版者
- 愛知淑徳大学文学部
- 雑誌
- 愛知淑徳大学論集 文学部・文学研究科篇 (ISSN:13495496)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.1-14, 2011
1 0 0 0 明治・大正期における名古屋旧有力商人の企業者活動
- 著者
- 村上 はつ
- 出版者
- 経営史学会
- 雑誌
- 経営史学 (ISSN:03869113)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.71-86, 1979
1 0 0 0 IR 愛国婦人会と社会事業 : 大正後期の山口支部の活動に焦点をあてて
- 著者
- 今井 小の実 Konomi Imai
- 出版者
- 関西学院大学人間福祉学部研究会
- 雑誌
- Human welfare : HW (ISSN:18832733)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.71-86, 2020-03
1 0 0 0 IR 学習指導要領とその解説及び教科書から見る中学校数学指導におけるICT 活用の方向性
- 著者
- 中村 好則
- 出版者
- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター
- 雑誌
- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 = The journal of Clinical Research Center for Child Development and Educational Practices (ISSN:13472216)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.69-78, 2016-03-31
平成26年6月24日に閣議決定した世界最先端IT国家創造宣言において「学校の高速ブロードバンド接続,1人1台の情報端末配備,電子黒板や無線LAN環境の整備,デジタル教科書・教材の活用等,初等教育段階から教育環境自体のIT化を進め,児童生徒等の学力の向上と情報の利活用の向上を図る」ことが,さらに「これらの取組により,2010年代中には,全ての小学校,中学校,高等学校,特別支援学校で教育環境のIT化を実現するとともに,学校と家庭がシームレスでつながる教育・学習環境を構築し,家庭での事前学習と連携した授業など指導方法の充実を図る」ことが述べられ,政府主導で教育の情報化が進められている。また,文部科学省では,平成26年度にICTを効果的に活用した教育の推進を図ることを目的に,教育効果の明確化,効果的な指導方法の開発,教員のICT活用指導力の向上方法の確立を図るためにICTを活用した教育の推進に資する実証事業を行い,成果報告書や手引き書を公表している(ICTを活用した教育の推進に資する検証事業,2015)。さらに,総務省でも,平成26年6月から「ICTドリームスクール懇談会」を開催し,教育分野におけるICT活用の推進に取り組み,平成27年4月に中間取りまとめを公表している。これらのことからも,教育の情報化は着実に進展している。しかし,学校現場ではどうだろうか。文部科学省や総務省,県や市などの研究指定校や先進的に研究に取り組んでいる学校だけがICTを活用した実践に取り組み,それ以外は従来からの指導とあまり変わらない現状があるのではないだろうか。特に,数学指導においては,ICT活用よりも,紙と鉛筆による指導こそが重要だという教師の思い込み(固定観念あるいは素朴な考え方)がある(例えば,中村2015a)。中学校においても,電子黒板やパソコン,タブレット等のICT 環境が徐々に整備され(平成26年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果,文部科学省2015),それらを数学指導においても有効に活用することが求められている。しかし,数学指導において「なぜICTを活用するのか(ICT活用の目的)」,そのために「どのようにICTを活用するのか(ICT活用の方法)」が,学校現場において十分に理解されていない。そこで,本研究では,中学校学習指導要領とその解説及び教科書を基に,数学指導におけるICT活用について検討し,中学校の数学指導におけるICT活用の方向性(目的と方法)を明らかにすることを目的とする。そのために,平成20年版の中学校学習指導要領とその解説におけるICT活用に関する記述内容を調査する(第2章)とともに,中学校数学の平成27年検定済みの教科書におけるICT活用の取り扱いを分析(第3章)し,それらを基に中学校の数学指導におけるICT活用の方向性を考察する(第4章)。最後に,本研究のまとめと課題を述べる(第5章)。
1 0 0 0 「固定観念から外れる一歩」
- 著者
- 雑村 史高
- 出版者
- Japan Thermosetting Plastics Industry Association
- 雑誌
- ネットワークポリマー
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.56, 2004
1 0 0 0 IR 自由の発露としての英語学習
- 著者
- 上松 一
- 出版者
- 弘前大学21世紀教育センター
- 雑誌
- 21世紀教育フォーラム
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.17-33, 2006-03-31
実践的英語運用能力の重要性が強調され、授業も改良され始めてはいるが、日本の英語教育現場では未だに「正確に読んで訳す」ことが主流である。教師も学習者も、多くがこの固定観念の呪縛から解放されず、このことが往々にして学習者を萎縮させ、彼らをして「英語はつまらない。」と言わしめ、英語で意思疎通ができない学習者を量産し続けている結果に繋がっている。この否定的状況を打破するためには、教師は知識の伝達者として英語を「教える」ことを止め、学習者が自立して学習に取り組めるよう支援し、手助けするfacilitator となる必要がある。その際、教師のみならず、学習者共々、英語をその本来の機能である意思疎通のための言語として尊重し、使用する必要がある。そうすることにより、学習者のみならず、教師自身も、英語の授業に喜びを見出し、自由を感じ、教師は自立した学習者の能力を信頼し、学習者は教師を信頼し、自らの能力を信頼する。これは教師にとっても、学習者にとっても、英語学習の喜びと自由の獲得へのチャレンジである。