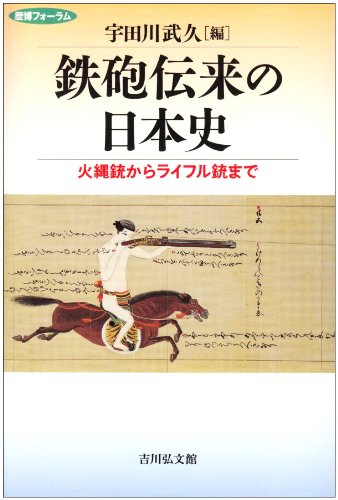- 著者
- 須田 紀子 大平 通泰
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.148-152, 1979
ドレープ形態を最も単純化した形のモデルすなわちゴムの円環一本を糸で吊り下げた円環モデルのドレープ形成機構についてはすでに検討を行った.<BR>本報では, この円環モデルの実際の応用例の一つとして, 裾回り (試料長) およびウエスト回り (支持盤の周) を一定とし, 垂下長を5段階に変化させたフレヤースカート状モデルを作り, 各垂下長の時に生ずるひだ (挫屈波形) の形態および数等について考察した.<BR>垂下長が短いときの方が挫屈波形の形態が明確であり, 長くなるに従って乱れが出てくる.また, 薄地のものより厚地のものの方がより波形が明確である.<BR>ノード数は円環モデルの結果と同様に, 垂下長の短い方が多く, 長さが増すにつれて減少する傾向が認められた.<BR>さらに, 円環モデルのノード数の計算式を適用し, ノード数の理論値を求め実験値と比較してみると, ほぼ類似した傾向がみられ, 本報のモデルにも式の適用は可能と考えられる.
(目的)睡眠は、家畜の疲労回復およびエネルギー蓄積に必要なものであるとされている。したがって、1日の睡眠時間の長さや睡眠の質(N-REM睡眠、REM睡眠)を検討することは飼養管理技術の改善につながる。(方法)脳波の導出で鼻梁に基準電極、頭部に探査電極を装着する単極導出法を用いた。24時間の脳波測定のために無束縛携帯型生体アンプとコンパクトカセットデータレコーダを専用のベルトで牛体に固定した。さらに、脳波測定と同時に暗視カメラによる行動観察を行い、休息行動(横臥時間)の成長に伴う変化を脳波測定による睡眠計測から検討した。(結果)幼齢子牛での24時間連続の睡眠脳波測定では、脳波測定用の電極を前頭部中央3箇所とし、記録紙送り速度を秒速1mm、電池交換時刻を飼料給与直後および23時の1日3回交換することが適切であると結論した。1日当りの睡眠時間(=N-REM+REM)は1週齢で493分、7週齢で267分と発育に伴い減少した。N-REM睡眠およびREM睡眠についても同様の結果となった。睡眠時間の日内パターンは週齢に伴う変化は認められなかった。1日当りの横臥時間は1週齢で1120分、15週齢で594分となった。また、1日当りの睡眠時間は1週齢で505分、15週齢で146分となった。N-REM睡眠は睡眠時間と同様の結果となったが、REM睡眠については一定の傾向が見られなかった。1日当り反芻時間は、給与飼料の種類によらず1週齢時ではほとんど認められず、7週齢時では6〜8時間の範囲まで延長した。1日当りの横臥時間は給与飼料の種類によらず1週齢で約18時間から、7週齢での約14時間へ短縮した。さらに、睡眠時間は1週齢での9時間程度から7週齢での4時間程度まで短縮した。成長に伴うN-REM睡眠の変化は、睡眠と同様の傾向であった。一方、REM睡眠には週齢に伴う一定の傾向が見られなかった。このことから、幼齢子牛における週齢に伴う睡眠時間の減少には反芻時間の延焼が大きく関わるものと考えた。
1 0 0 0 摩擦堅牢度に及ぼす添付白布の摩擦係数の影響
- 著者
- 菅沼 恵子
- 出版者
- The Society of Fiber Science and Technology, Japan
- 雑誌
- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.8, pp.194-198, 2010-08-10
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2
Rub-fastness of dyed fabrics is a matter of importance for practical use. Generally speaking, vat and naphthol dyes tend to suffer from poor rub fastness. However poor it is, it depends on the friction coefficient between dyed fabric and rubbed cloth. That is, smooth one should have good rub-fastness. In this paper rubbing-off behavior of denims using various white cloths is investigated from the kinetic viewpoint so that the interesting results are obtained. That is, the values of the rate constant k<sub>1</sub> of transfer of dye from dyed fabric to white cloth and the equilibrium constant K (k<sub>1</sub>/k<sub>-1</sub>) are ranged about ten times by various white cloths. These values depend on friction coefficient of white cloth, with having nothing to do with variety of fibers, fabrics and so on. Natural logarithm of each constant is linearly related to the reciprocal of friction coefficient. It suggests that the measurement of friction coefficient should be effective for standard of rub-test in addition to a designation of cloth or adjustment of moisture regain.
1 0 0 0 IR リチャード三世 : ヨークの白いばら
- 著者
- 横山 徳爾
- 雑誌
- 人文研究 (ISSN:04913329)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.5-54, 2001-12
ヨーク朝最後の国王であるリチャード三世(Richard III, 1452-85, 在1483-85)は, 在位わずか2年2か月弱ののちに, 1485年8月22日にレスターシャーのボズワース・フィールドにおいて, リッチモンド伯ヘンリー・チューダー(Henry Tudor, Earl of Richmond)に敗れ, 32歳にして落命した。リチャードの死によってヨーク朝は滅亡し, 28歳のヘンリー・チューダーがヘンリー七世(Henry VII, 1457-1509, 在1485-1509)として即位し, チューダー朝が成立した。……
- 著者
- 福長 秀彦
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.7, pp.2-24, 2020
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、トイレットペーパーをめぐる流言と買いだめが如何にして発生したのか、また、両者がどのように関わり合っているのかを検証した。そのうえで、流言と買いだめを的確に抑制する報道のあり方を考察した。検証と考察の結果は以下の通り。■「トイレットペーパーが不足する」という流言の発生には、マスク不足、オイルショック、海外の買い占め騒動が心理的要因として作用していた。日本とシンガポールなどで拡散した流言はほぼ同じ内容であり、感染症の流行による国際社会の不安から、流言は国境を越えて拡がった。■買いだめの動きは、流言がきっかけとなって各地で散発的に始まり、2月28日に急加速した。急加速を主に促したのは、品切れの様子を伝えたテレビだった。■流言を信じて買いだめをした人は少なかった。多くの人は流言を信じていなかったが、「他人は流言を信じて買いだめをしているので、このままでは品物が手に入らなくなる」と思い、買いだめをしていた。そうした心理は品切れとなる店舗が増えるにつれて増幅し、買いだめに拍車をかけた。■流言を否定する情報は、店頭から現実にモノが消えているので、説得力を欠いた。買いだめが加速すればするほど、品不足への不安が高じて、流言の打ち消しは効果が逓減した。■流言が社会に悪影響を及ぼす群衆行動へとエスカレートする前に、流言の拡散を抑え込まなければならない。
1 0 0 0 OA プロテインコロナの制御による新規ナノワクチンの安全設計
- 著者
- 宇髙 麻子 吉岡 靖雄 吉田 徳幸 宇治 美由紀 三里 一貴 森 宣瑛 平井 敏郎 長野 一也 阿部 康弘 鎌田 春彦 角田 慎一 鍋師 裕美 吉川 友章 堤 康央
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第39回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.O-39, 2012 (Released:2012-11-24)
抗原を粘膜面から接種する粘膜ワクチンは、全身面と初発感染部位である粘膜面に二段構えの防御を誘導できる優れたワクチンとなり得る可能性を秘めている。しかし抗原蛋白質は体内安定性に乏しく、単独接種ではワクチン効果が期待できない。そのため、免疫賦活剤(アジュバント)の併用が有効とされており、既に我々はTNF-αやIL-1α等のサイトカインが優れたアジュバント活性を有することを先駆けて見出してきた(J.Virology, 2010)。しかしサイトカインは吸収性にも乏しく、アジュバントの標的である免疫担当細胞への到達効率が極めて低い。そのため十分なワクチン効果を得るには大量投与を避け得ず、予期せぬ副作用が懸念される。言うまでも無く、現代のワクチン開発研究においては、有効性のみを追求するのではなく、安全性を加味して剤型を設計せねばならない。そこで本発表では、ナノ粒子と蛋白質の相互作用により形成されるプロテインコロナ(PC)を利用することで、サイトカイン投与量の低減に成功したので報告する。PCとは、ナノ粒子表面に蛋白質が吸着して形成する層のことを指す。近年、PC化した蛋白質は体内安定性や細胞内移行効率が向上することが報告されている。まず粒子径30 nmの非晶質ナノシリカ(nSP30)を用いてPC化したTNF-α(TNF-α/nSP30)を、ニワトリ卵白アルブミン(OVA)と共にBALB/cマウスに経鼻免疫し、OVA特異的抗体誘導能を評価した。その結果、有害事象を観察することなく、0.1 µgのTNF-αを単独で投与した群と比べ、TNF-α/nSP30投与群においてOVA特異的IgG・IgAの産生が顕著に上昇していた。以上、PCがTNF-αアジュバントの有効性と安全性を向上できる基盤技術となる可能性を見出した。現在、体内吸収性の観点からPC化サイトカインのワクチン効果増強機構やナノ安全性を解析すると共に、最適なPC創製法の確立を推進している。
1 0 0 0 訪問地域,旅行形態,年令別にみた日本人海外旅行者の観光動機
- 著者
- 林 幸史 藤原 武弘
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.17-31, 2008
- 被引用文献数
- 2
本研究の目的は,日本人海外旅行者の観光動機の構造を明らかにし,訪問地域・旅行形態・年令層による観光動機の違いを比較することである。出国前の日本人旅行者1014名(男性371名,女性643名)を対象に観光動機を調査した。主な結果は以下の通りである。(1)観光動機は「刺激性」「文化見聞」「現地交流」「健康回復」「自然体感」「意外性」「自己拡大」の7因子構造であった。(2)観光動機は,年令を重ねるにつれて新奇性への欲求から本物性への欲求へと変化することが明らかになった。(3)アジアやアフリカ地域への旅行者は,今までにない新しい経験や,訪問国の文化に対する理解を求めて旅行をする。一方,欧米地域への旅行者は,自然に触れる機会を求めて旅行をすることが明らかになった。(4)個人手配旅行者は,見知らぬ土地という不確実性の高い状況を経験することや,現地の人々との交流を求めて旅行をする。一方,主催旅行者は,安全性や快適性を保持したままの旅行で,外国の文化や自然に触れることを求めて旅行をすることが明らかになった。これらの結果を踏まえ,観光行動の心理的機能について考察した。<br>
1 0 0 0 OA 「食べること」を文化として教育する試み 「おいしさ」を分析する
- 著者
- 青木 三恵子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成14年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.56, 2002 (Released:2003-04-02)
昨今では食生活の外部化や個食化·簡便化などにより、味の認識が平坦になり、食行動も「食べる」ことは単に「食品や栄養を摂取する」ことであり、摂取栄養により人体そのものをも操作できるかのような感覚さえ見受けられる。こうした状況においては、味·味わい·おいしさは、教育の対象としていかなければならないのではないかと、教育法について試行した。「食べること」「おいしさ」を広い視野で捉えるために、「食べている情景」を細かく、かつ広い視野で画用紙に描写させ、同時に言葉による描写を行った。また、情景を描く時、学生同士で質問をして見落としている部分に気づくようにした。絵に描く作業により、食べる·おいしさを味わうことには多くのファクターが関与していることに気づいた。
1 0 0 0 鉄砲伝来の日本史 : 火縄銃からライフル銃まで
1 0 0 0 IR 医療防災プロダクトのデザイン開発に関する基礎調査
- 著者
- 竹田 周平 西尾 浩一 三浦 英夫 Nishio Kouichi 三浦 英夫 Miura Hideo 川島 洋一 Kawashima Yoichi 谷内 眞之助 Taniuchi Shinnosuke 山内 勉 Yamauchi Tsutomu 吉野 剛 Yoshino Tsuyoshi
- 出版者
- 福井工業大学
- 雑誌
- 福井工業大学研究紀要 Memoirs of Fukui University of Technology (ISSN:18844456)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.130-134, 2014
At 14:46 local time on March 11, 2011, a magnitude 9.0 earthquake occurred off the coast of northeast Japan. It was one of the most powerful earthquakes to have hit Japan. The many hospitals which are located at Fukushima, Miyagi and Iwate prefecture suffered damage from this Mega-earthquake. Forever, little is known about the damaged of hospital have not generally decreased in the last 20 years. In this paper, we used the following questionnaire to clarify the damage factor of a hospital. It was found that Medical disaster prevention product was a top priority.
1 0 0 0 IR 人文情報学とは何か (文化交流茶話会トーク)
- 著者
- 大向 一輝
- 出版者
- 東京大学文学部次世代人文学開発センター
- 雑誌
- 文化交流研究 : 東京大学文学部次世代人文学開発センター研究紀要 = Study of cultural exchange : annual report of Center for Evolving Humanities (ISSN:13478931)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.83-91, 2020
文化交流茶話会トーク
1 0 0 0 渦虫および両生類幼生の尾の再生軸についての実験的観察
- 著者
- 手代木 渉 志田 孝夫
- 出版者
- 日本動物学会
- 雑誌
- 動物学雑誌 (ISSN:00445118)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.11, pp.350-358, 1968-11
It is well known that in the amphibian tail the main axis of regeneration blastema is at the right angle with the cut-surface (Barfurth, 1923). The same view has been held by many investigators who worked with various animals. For supporting this view, the cellular materials concerned in regeneration must be produced uniformly from the cut-surface, as stated by E. Korschelt (1927) and Yo. K. Okada (1950). However, this did not hold in planarians, since the rate of production of new tissue at the cut-surfaces differs along the longitudinal or the lateral axes of the body. The rate of regeneration in the amphibian tail was exactly the same to that of planarians. When the planarian or amphibian tail was sectioned obliquely, the axis of blastema was not always at the right angle with the cut-surface. It has been conclusively shown in the planarian and amphibian tail that as the acute angle between cut-surface and the main axis of the body (section angle) approaches the right angle, the acute angle of blastema-axis to the main axis of the body (regeneration angle) falls to zero, while, the regeneration angle becomes at the right angle as the section angle approaches zero. This can be mainly explained by differences in the rate of regeneration of new tissue along the cut-surface of the oblique section.
1 0 0 0 OA 津軽半島の淡水産プラナリアの生態調査報告
- 著者
- 川勝 正治 手代木 渉 八木橋 元一
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.43-47, 1969-04-01
The vertical distribution of freshwater planarians in the Tsugaru Peninsula in Aomori Prefecture (Lat. 40°40′N. to lat. 41°20′N. and Long, 140°10′E. to Long. 140°45′E.), the northernmost part of Honshu, was surveyed in 1966 and 1967. The Peninsula faces both the Tsugaru Straits and Mutsu Bay. The larger part of the Peninsula is covered with low mountains, of which the highest peak is 827 metres in height. The south-western part of the Peninsula is characterized by a level plain of cultivation. The main river system in the area surveyed is the Iwaki, which discharges into Juni-ko Lake and the Sea of Japan. In the area surveyed, six species of freshwater planarians, Dugesia japonica ICHIKAWA et KAWAKATSU, Phagocata vivida (IJIMA et KABURAKI), Phagocata teshirogii ICHIKAWA et KAWAKATSU, Polycelis auriculata IJIMA et KABURAKI, Polycelis sapporo (IJIMA et KABURAKI) and Dendrocoelopsis lacteus ICHIKAWA et OKUGAWA, were found. D. japonica was found to be common at the stations below the altitude of about 160 metres (inhabitable water temperature range, 8.0〜22.2℃). Ph. vivida was common at the stations below the altitude of about 380 metres (5.0〜21.8.C). Pol. auriculata was found in both the cold-water mountain streams and in some cold-water springs in the seaward district (0.5〜480m, 9.0〜14.0℃). Pol. sapporo, one of the common species in Hokkaido, was found at the stations below the altitude of about 120 metres (9.0〜21.8℃). It is an interesting fact that this species was rather common at the stations in the Tappizaki Cape district in the Tsugaru Peninsula. Small populations of Ph. teshirogii and Den. lacteus were found in the Tsugaru Peninsula. The type of the vertical distribution of the planarians in the area surveyed is (JSV)-JSVA-SVA-VA-A (J : D. japonica ; V : Ph. vivida ; S : Pol. sapporo ; A : Pol. auriculata). The geographical distribution of Pol. sapporo and Den. lacteus in Honshu were discussed. According to the best of our knowledge, Pol. sapporo has been recorded only from the northern side of the demarcation line drawn between the base of the Shimokita Peninsula and of the Tsugaru Peninsula (cf. KAWAKATSU 1965,p. 356,Fig. 5,1967,p. 125,Fig. 5). Den. lacteus has been recorded both from the Tsugaru Peninsula and in a little south of the southern demarcation line of distribution of Pol. sapporo (cf. KAWAKATSU, TESHIROGI, ISHIOKA & KASAHARA 1968).
- 著者
- Luis A. González-Ortega Andrés A. Acosta-Osorio Peter Grube-Pagola Carolina Palmeros-Exsome Cynthia Cano-Sarmiento Rebeca García-Varela Hugo S. García
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.123-131, 2020 (Released:2020-02-05)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1 12
Curcumin is a bioactive compound with proven antioxidant and anti-inflammatory activities, but has low water solubility and dermal absorption. The inflammatory process is considered as the biological response to damage induced by various stimuli. If this process fails to self-regulate, it becomes a potential risk of cancer. The objective of this work was to evaluate the anti-inflammatory activity of curcumin administered to mice with induced atrial edema using two topical vehicles: organogels and O/W-type nanogels at pH 7, Organogels and O/W-type nanogels at pH 7 were prepared, characterized and the anti-inflammatory activity was assessed. A histopathological analysis of mouse ears was performed and two gel formulations were selected. Thermograms of organogels indicated that increasing the gelling agent improved the stability of the system. Deformation sweeps confirmed a viscoelastic behavior characteristic of gels in both systems. During the anti-inflammatory activity evaluations, the nanogels demonstrated greater activity (61.8 %) than organogels; Diclofenac® (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid), used as a control medication achieved the highest inhibition (85.4%); however, the drug produced the death of 2 (40%) of the study subjects caused by secondary adverse events. Histopathological analysis confirmed the data.
1 0 0 0 荳科植物の種皮の構造と吸水との関係〔英文〕
- 著者
- 堀 武義 平光 重
- 出版者
- 岐阜大学学芸学部
- 雑誌
- 岐阜大学学芸学部研究報告 自然科学 (ISSN:04340078)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.47-54, 1953-03
1 0 0 0 OA 入院期間の違いが筋組織に及ぼす影響(第2報) 高齢者献体標本からの組織学的検討
- 著者
- 浅井 友詞 田中 千陽 馬渕 良生 佐久間 英輔 曽爾 彊
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A0502, 2007 (Released:2007-05-09)
【はじめに】長期臥床による筋萎縮の研究は古くから行われ、筋力に関する研究では、1週間の臥床により10から15%、3~5週間では50%低下するといわれている。また、立野らはマウスの後肢懸垂モデルにて2週間で筋の湿重量が20%減少したと報告している。こうした量的な研究から最近では質的な検討がなされてきたが多くは動物実験である。我々は第41回本学会で献体された2症例より、入院期間の違いによる筋萎縮の変化を肉眼的観察および筋組織の横断面より検討し報告した。そこで今回は筋組織の縦断面からの情報を加え検討したので報告する。【第1報の要旨】短期(4日)および長期入院(4ヵ月半)中、肺炎にて死亡した2症例の肉眼的観察にて長期入院例の下腿三頭筋に高度の筋萎縮がみられ、扁平化していた。組織学的にも細胞間の結合組織が増加すると共に筋細胞は減少し、細胞の形態は極度に萎縮していた。【症例】症例1: 死亡時年齢90歳・女性・身長約145cm・死因;急性胆のう炎にて4日間入院中、誤嚥性肺炎にて急死。症例2: 死亡時年齢92歳・女性・身長約145cm・死因;4ヶ月半入院中、肺炎にて死亡。【肉眼的観察】症例2は、下肢筋の強度な筋萎縮と共に、大体外側の腸脛靭帯から膝関節下部外側の付着部までの軟部組織に緊張がみられ、柔軟性の低下から膝関節に屈曲拘縮が推測できる。このことより歩行困難となり、臥床を強いられていたことが予測できる。岡崎によると安静臥床後6週間で、下腿三頭筋の筋力低下は他筋と比較して特に大きいと報告され、今回の症例2の筋萎縮と同様の症状である。【組織学的観察】本献体はホルマリン固定にて保存され、肉眼解剖時に上腕二頭筋・大腿四頭筋・腓腹筋・ヒラメ筋を採取した。標本はホルマリン固定後、定法にてパラフィン包埋をした。その後、5μmで薄切片を作成し、ヘマトキシリン・エオジン染色した縦断面を光学顕微鏡にて観察した。症例1では、各筋において筋線維の形状が保たれ、線維間は、結合組織で隔壁され、密集した縦方向への筋線維が観察された。一方、症例2では不規則な筋線維の配列間に多量の結合組織を観察した。また、筋線維数の著明な減少がみられ、結合組織中には多くの核が点在していた。今回観察された症例2の廃用性の変化は、筋線維数の減少のみならず、結合組織の増加など退行性変化が強く認められ、筋の伸縮性低下より理学療法の阻害因子となり得ると思われる。【まとめ】今回献体より入院期間の違いによる筋の変化について検討し、長期入院者では筋細胞間に結合組織が増加し、筋機能の低下が示唆された。
1 0 0 0 あせもの語源と方言分布
- 著者
- 鏡味 明克
- 出版者
- 岡山大学教育学部
- 雑誌
- 岡山大学教育学部研究集録 (ISSN:04714008)
- 巻号頁・発行日
- no.64, pp.p123-130, 1983-10
1 0 0 0 警察による性犯罪対策 (特集 性犯罪)
- 著者
- 青山 彩子
- 出版者
- 日立みらい財団
- 雑誌
- 犯罪と非行 (ISSN:03856518)
- 巻号頁・発行日
- no.149, pp.17-33, 2006-09
1 0 0 0 花に暮れる (特集 桜秀歌・考)
- 著者
- 畑 彩子
- 出版者
- 角川書店
- 雑誌
- 短歌 (ISSN:13425625)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.74-75, 1998-04