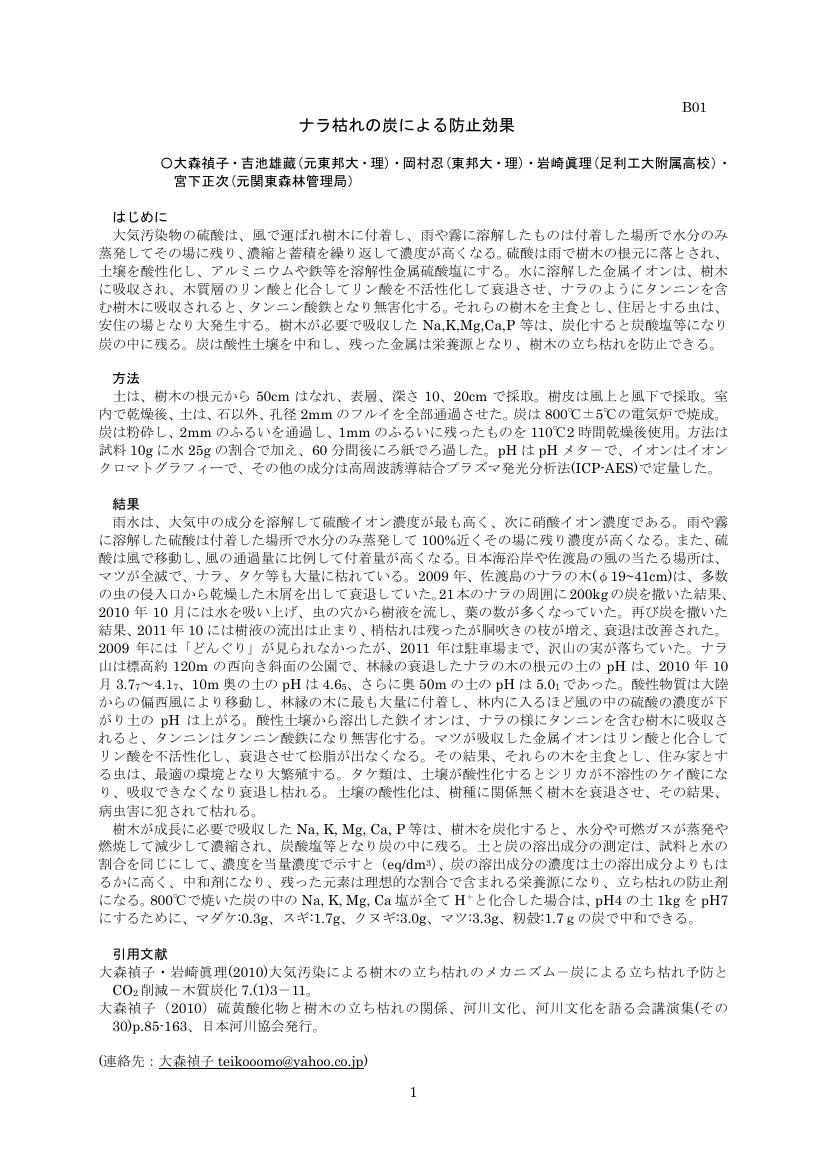- 著者
- Kotaro Mochizuki editor
- 出版者
- Liberal News Agency
- 巻号頁・発行日
- 1909
1 0 0 0 OA 乳牛における子宮捻転整復後の産科処置が生存率及び繁殖成績に及ぼす影響
1 0 0 0 OA 勝川春亭考(続) 落款譜・武者絵作品目録
- 著者
- 岩切 友里子
- 出版者
- 国際浮世絵学会
- 雑誌
- 浮世絵芸術 (ISSN:00415979)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, pp.24-28, 1996 (Released:2021-02-19)
1 0 0 0 OA 監査人に求められる役割と倫理 企業不正を巡る諸問題
- 著者
- 加藤 正浩
- 出版者
- 日本監査研究学会
- 雑誌
- 現代監査 (ISSN:18832377)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.14, pp.40-46, 2004 (Released:2009-11-16)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA 内分泌異常と腎疾患
- 著者
- 向山 政志
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.7, pp.1486-1494, 2015-07-10 (Released:2016-07-10)
- 参考文献数
- 15
腎臓は内分泌臓器の1つであり,また種々のホルモンの標的臓器として極めて重要であると同時に,多くの内分泌機能調節の鍵を握っている.したがって,腎臓の内分泌機能の異常,あるいはホルモン受容・情報伝達機構の異常に伴い,様々な疾患が生じる.一方,慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)に代表される腎障害の際には,他臓器におけるホルモンの産生・分泌・代謝・情報伝達のあらゆる面においてしばしば異常がもたらされる.これらの病態を理解することは,内分泌代謝学の面からも腎臓病学の面からもともに重要である.本稿では,腎疾患と内分泌異常について,代表的な疾患を中心に概説する.
1 0 0 0 OA ナラ枯れの炭による防止効果
- 著者
- 菊川 信吾 磯村 悟 岩田 聡 塩見 繁 内山 晋
- 出版者
- The Magnetics Society of Japan
- 雑誌
- 日本応用磁気学会誌 (ISSN:02850192)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.83-86, 1983
New bubble garnet films with orthorhombic anisotropy, (YTmGdBi)<sub>3</sub>(FeGa)<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, (YTmEuBi)<sub>3</sub>(FeGa)<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, (YTmSmBi)<sub>3</sub>(FeGa)<sub>5</sub>O<sub>12</sub> and (YTmLaBi)<sub>3</sub>(FeGa)<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, have been epitaxially grown on (110) GGG substrates. Although a large in-plane anisotropy <i>K</i><sub>p</sub> of 2∼4×10<sup>4</sup> erg/cm<sup>3</sup> is induced in YTmEu and YTmSm films, the uniaxial anisotropy <i>K</i><sub>u</sub> obtained is not large enough to be used for bubble materials. In YTmGd and YTmLa films, <i>K</i><sub>u</sub> is of almost the same magnitude as <i>K</i><sub>p</sub> with a value of 1.0∼1.5×10<sup>4</sup> erg/cm<sup>3</sup>. The wall dynamics has been investigated by stripe domain transport method. For YTmLa films, the wall mobility μ is ∼22 m/sOe, the peak velocity <i>V</i><sub>p</sub> is ∼120 m/s and the coercive force <i>H</i><sub>c</sub> is ∼0.7Oe. These characteristics may be useful for current access devices.
1 0 0 0 ゼロから始めるECビジネス(11)電子メール・マガジン本日創刊!
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ネットビジネス (ISSN:13450328)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.164-167, 1999-12
あるインターネット・プロバイダのショッピング・モール運営の仕事を手がけている。仕事がら、コンピュータやECについて非常に詳しい。前回、小林さんたちのマルチメディア推進室に配属された新スタッフの三村さん。実はEC(電子商取引)を目玉に来年度のシステム予算の大幅アップを狙う情報システム部の"工作員"でした。
- 著者
- 井原 涼子 岩坪 威
- 出版者
- アークメディア
- 雑誌
- 臨床精神医学 = Japanese journal of clinical psychiatry (ISSN:0300032X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.283-289, 2018-03
1 0 0 0 OA 進行相の副次的機能再考 POLITENESS の視点から
- 著者
- 黒滝 真理子
- 出版者
- 日本実用英語学会
- 雑誌
- 日本実用英語学会論叢 (ISSN:1883230X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.7, pp.39-52, 1999-09-25 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 18
The purpose of this paper is to examine some features of “will” in the progressive form. This form of “will” has been the most difficult of all future meanings to characterise, from the standpoint of functional politeness. It can be summed up as “future-as-a-matter-of-course”. The progressive form of “will” is used tactfully in daily conversation. When used in this form, “will” not only expresses polite interest, but relieves the burden of a response from the listener. It can depict an activity as if it were independent of the speaker's volition. This form of “will” can also be used to reconfirm previous plans, by implying “in addition to...”.These observations suggest that “will” in the progressive form is basically an expression in which the speaker is aware of the listener, resulting in the appearance of polite discourse.
1 0 0 0 プレセニリンによる蛋白輸送制御機構
- 著者
- シュウ ワッシ
- 出版者
- 日本生理学会
- 雑誌
- 日本生理学会大会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.35, 2006
Alzheimer's disease (AD), the most common form of senile dementia, is characterized by excessive production and accumulation of neurotoxic β-amyloid (Aβ) peptides which are proteolytically derived from β-amyloid precursor protein (APP) via β- and γ-secretase cleavages. Experimental evidence from several groups including our own has demonstrated that the production of Aβ occurs largely in the trans-Golgi network (TGN) where APP molecules predominantly reside. Mutations in presenilins genes are associated with the majority of familial AD likely through a mechanism of increase Aβ42 production. Presenilins (PS, PS1 and PS2) along with their associated proteins including nicastrin (Nct), PEN2 and APH1 are essential for the γ-secretase activity. The precise functions of Nct, APH-1 and PEN-2 have not been fully elucidated. Recent studies including ours suggest that PEN-2 mediates endoproteolysis of PS1, while APH-1 and Nct play regulatory roles in maintaining the stability of PS1 and the complex. PS1 knockout mice exhibit pre-neonatal lethality and PS1 has also been shown to affect numerous physiological functions including calcium homeostasis, skeletal development, neurite outgrowth, apoptosis, synaptic plasticity, tumorigenesis. These data strongly indicate critical physiological roles of PS1 addition to its essential role in γ-secretase activity. We and others have reported that PS1 plays an important role in intracellular trafficking (especially from the TGN to the plasma membrane) of select membrane proteins including APP, PEN2 and nicastrin. The detailed cell biological mechanism for PS-mediated protein trafficking will be discussed. <b>[J Physiol Sci. 2006;56 Suppl:S35]</b>
- 著者
- Rauzah Hashim N. Idayu Zahid T. S. Velayutham Nurul Fadhilah Kamalul Aripin Shigesaburo Ogawa Akihiko Sugimura
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.6, pp.651-668, 2018 (Released:2018-06-01)
- 参考文献数
- 99
- 被引用文献数
- 2 26
Also recognized as carbohydrate liquid crystals, glycolipids are amphiphiles whose basic unit comprises of a sugar group attached to an alkyl chain. Glycolipids are amphitropic, which means these materials form liquid crystal self-assemblies when dry (thermotropic) as well as when dissolved in solvents (lyotropic/surfactants) such as water. Many glycolipids are also naturally derived since these can be found in cell membranes. Their membrane and surfactant functions are largely understood through their lyotropic properties. While glycolipids are expected to play major roles as eco-friendly surfactants in the global surfactant market, their usefulness as thermotropic liquid crystal material is, to date, unknown, due to relatively lack of research performed and data reported in the literature. Understandably since glycolipids are hygroscopic with many hydroxy groups, removing the last trace water is very challenging. In recent time, with careful lyophilization and more consistent characterization technique, some researchers have attempted serious studies into “dry” or anhydrous glycolipids. Motivated by possible developments of novel thermotropic applications, some results from these studies also provide surprising new understanding to support conventional wisdom of the lyotropic systems. Here we review the dry state of glycosides, a family of glycolipids whose sugar headgroup is linked to the lipid chain via a glycosidic oxygen linker. The structure property relationship of both linear and anhydrous Guerbet glycosides will be examined. In particular, how the variation of sugar stereochemistry (e.g. anomer vs. epimer), the chain length and chain branching affect the formation of thermotropic liquid crystals phases, which not only located under equilibrium but also far from equilibrium conditions (glassy phase) are scrutinized. The dry glycolipid assembly has been subjected to electric and magnetic fields and the results show interesting behaviors including a possible transient current generation.
1 0 0 0 IR 原因・理由表現をめぐる日タイ対照研究 : 「のだから」を中心に
- 著者
- ケウワッタナ ピヤトーン
- 出版者
- 大東文化大学語学教育研究所
- 雑誌
- 語学教育研究論叢 (ISSN:09118128)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.19-35, 2016
本稿では、「のだから」の意味・用法を中心に考察し、タイ語における表現と比較する。「のだから」は、文末表現「のだ」と原因・理由表現「から」から構成されている表現であるが、「のだから」の意味・用法は通常の原因・理由を表す「から」や「ので」とは異なっている。「のだから」は、判断系の原因・理由表現の中でも代表的なもので、原因・理由を表すほかに、判断・根拠も表す。タイ語では、このタイプの原因・理由表現に類似している表現は対応していないため、一般的にどのような表現に近いかは不明である。タイ語における因果関係を表す表現の中に、「のだから」に近い働きをするものがあるかどうかを検討する。
1 0 0 0 ARを利用した複数視点からの物体指示手法の実装と評価
- 著者
- 井上 綺泉 阪田 大輔 佐藤 健哉
- 雑誌
- マルチメディア,分散協調とモバイルシンポジウム2018論文集
- 巻号頁・発行日
- no.2018, pp.1447-1452, 2018-06-27
1 0 0 0 アルツハイマー病に対する免疫療法:ヒト脳内アミロイドβ除去の成功
- 著者
- 郷 すずな
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.471, 2017
アルツハイマー病(AD)は,アミロイドβ(Aβ)を主要成分とした老人斑とよばれる細胞外沈着物の脳内蓄積とリン酸化タウタンパク質を主要成分とした神経原線維変化を特徴とする.ADの発症機序は不明であるが,代表的な発症仮説にアミロイド・カスケード仮説がある.この仮説は,Aβの蓄積が,ADの病態進行に特徴的なシナプス障害とそれにつづく神経変性に関与すると仮定している. これまでに,この仮説に基づいてADの根本治療薬の開発が進められてきたが,有効性が検出されず治験の中止が相次ぎ,アミロイド・カスケード仮説の妥当性についての懸念が生じていた. 本稿では,この現状の中で行われた抗Aβ抗体アデュカヌマブ(aducanumab)の第1b相臨床試験の中間解析結果を報告したSevignyらの論文を紹介する.<br>なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.<br>1) Selkoe D. J., Hardy J., <i>EMBO</i> <i>Mol</i>. <i>Med</i>., <b>8</b>, 595-608(2016).<br>2) Herrup K., <i>Nat</i>. <i>Neurosci</i>., <b>18</b>, 794-799 (2015).<br>3) Sevigny J. <i>et</i> <i>al</i>., <i>Nature</i>, <b>537</b>, 50-56 (2016).
- 著者
- 伊藤 朝輝
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経パソコン = Nikkei personal computing (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.835, pp.69-74, 2020-02-10
iPadは以前から物理キーボードに対応していたが、iPadOSではキーボードを接続して使わないのはもったいないと感じるぐらいに進化した。 iPadに物理キーボードを接続すれば、パソコンのようにテキストを入力できることは、今や多くの人がご存じだろう。しかし…
1 0 0 0 OA 体育実技科目における授業の再設計過程 〜新型コロナウイルス感染症への対応〜
- 著者
- 中澤 謙 沖 和砂
- 出版者
- 会津大学
- 雑誌
- 会津大学文化研究センター研究年報 = The University of Aizu Center for Cultural Research and Studies annual review (ISSN:21899290)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.93-100, 2020
1 0 0 0 非同期並列プログラミング言語の意味論と実装
- 著者
- 諏訪 重貴
- 雑誌
- 第79回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.1, pp.305-306, 2017-03-16
近年,様々なソフトウェア開発において「非同期処理」を扱う状況が増加している.非同期処理や並列処理を記述するための既存技術として,「Thread」「Promise」「Channel」「Async/Await」 などが存在する.これらはすべて,特別な予約語や構文を用いたり,非同期処理を意識しながらコードを記述する必要がある.本研究では,このような非同期処理の複雑さを排除することを目的とし,非同期処理に特化したプログラミング言語の処理系を提案する.そして,言語の意味論を定式化し,提案言語で記述されたプログラムを解釈できるインタプリタの実装を行う.
1 0 0 0 OA 食品包装ラップフィルムからのノニルフェノールおよびビスフェノールAの溶出
- 著者
- 川中 洋平 鳥貝 真 尹 順子 橋場 常雄 岩島 清
- 出版者
- Japan Society for Environmental Chemistry
- 雑誌
- 環境化学 (ISSN:09172408)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.73-78, 2000-03-24 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2 2
食品包装用ラップフィルム (7材質, 22試料) からのノニルフェノール (NPs) 及びビスフェノールA (BPA) の溶出試験を行った。蒸留水を溶出溶媒として試験を行った結果, ポリ塩化ビニル製のラップフィルム6試料中5試料からNPsが, さらに, そのうち1試料からBPAが溶出することが確認された。ラップフィルム表面積当たりの溶出量はNPsで98~120ng/cm2, BPAでり30ng/cm2であった。なお, 他の材質のラップフィルムからはNPs, BPAとも溶出は認められなかった。さらに, ポリ塩化ビニル製のラップフィルムを用いて4%酢酸及びn-ヘプタンによる溶出試験を行ったところ, BPAの溶出量に変化は認められなかったが, NPsの溶出量はn-ヘプタンによる試験で, 不検出である1試料を除き480~610ng/cm2となり, 蒸留水や4%酢酸の場合と比較して高くなる結果が得られた。
1 0 0 0 Liquid - 非同期一階関数による並行計算体系
- 著者
- 諏訪 重貴 福田 浩章 篠埜 功
- 雑誌
- 第80回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.1, pp.255-256, 2018-03-13
ウェブアプリケーションのようなソフトウェア開発においては,非同期プログラミングを用いた並列実行が必須である.callback,thread,promise,future,async/awaitなどのモデルを用いたコードは,同期処理よりも複雑であり,その性質の差異を考慮してコードを記述する必要がある.この差異を考慮することなく,非同期処理を同期処理と同様に記述できるようにすることで,保守性や可読性を向上させ,致命的なバグを抑制できると考えられる.これを実現するため,本研究ではLiquidという計算体系を提案し,操作的意味論を定義した.