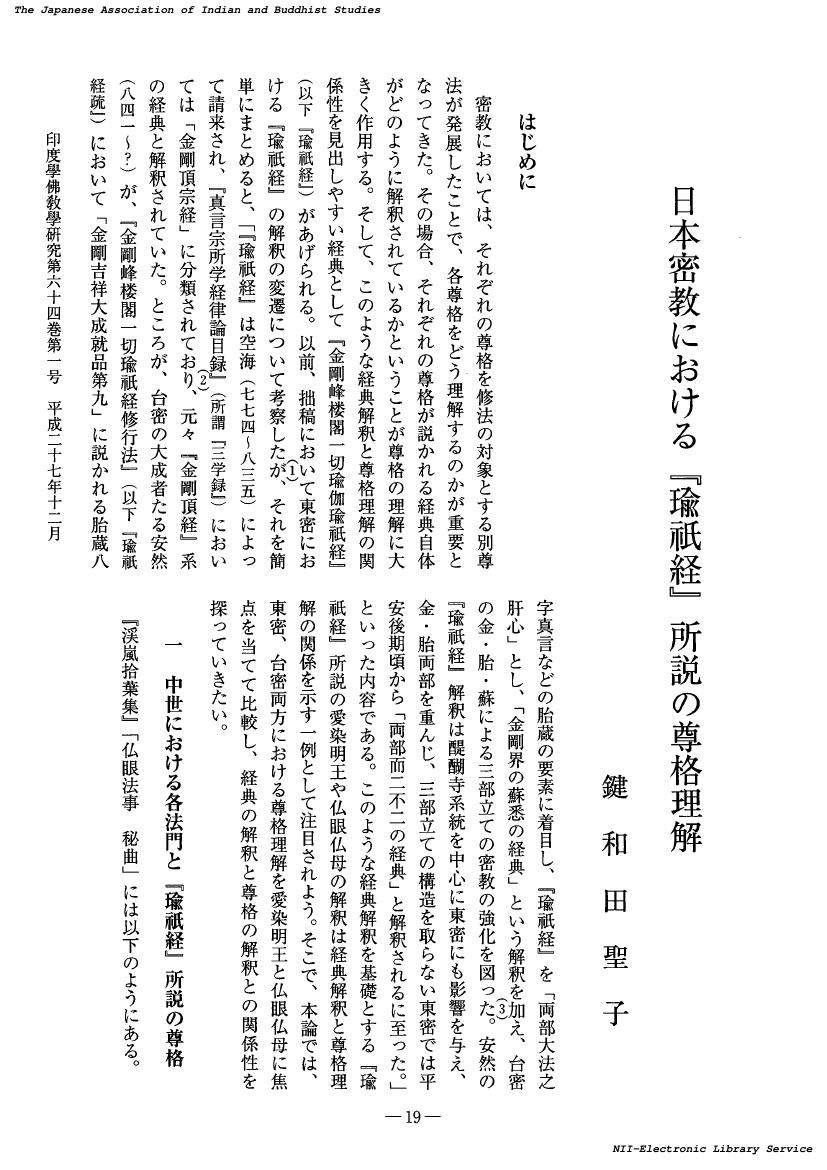- 著者
- 河野 俊丈
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.29-43, 1992-02-14 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 58
1 0 0 0 IR ろくでなし子事件に関する意見書
- 著者
- 牧 陽一
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.145-153, 2015
- 著者
- 森 勇斗
- 出版者
- 一橋研究編集委員会
- 雑誌
- 一橋研究 (ISSN:0286861X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.1-21, 2020-04
1 0 0 0 IR 「市民派」選挙と女性 : 東久留米市長選挙運動を担った女性たち
- 著者
- 古田 睦美
- 出版者
- 一橋研究編集委員会
- 雑誌
- 一橋研究 (ISSN:0286861X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.97-116, 1993-07-31
論文タイプ||論説
- 著者
- 高橋 準
- 出版者
- 一橋研究編集委員会
- 雑誌
- 一橋研究 (ISSN:0286861X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.21-40, 1993-04-30
論文タイプ||論説
1 0 0 0 OA マーケティングとメタファー
- 著者
- 武井 寿
- 出版者
- 早稲田商学同攻会
- 雑誌
- 早稲田商学 (ISSN:03873404)
- 巻号頁・発行日
- vol.413・414, pp.147-181, 2007-12
論文
1 0 0 0 OA 境界性パーソナリティ障害患者への看護をとおした精神科看護師の自己形成
1 0 0 0 OA ハイビジョンに於ける映像表現
- 著者
- 皆川 慶助
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.49, pp.7-11, 1995-10-06 (Released:2017-10-13)
- 著者
- 黒岩 宙司
- 出版者
- 日本国際保健医療学会
- 雑誌
- 国際保健医療 (ISSN:09176543)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.83-92, 2006
グローバリゼーションにともない国際保健医療の分野でもパートナーシップの重要性が言われている。1992年から2001年まで行われたラオスにおける「公衆衛生プロジェクト」と「小児感染症予防プロジェクト」は国際機関とのパートナーシップのもとに成功した。最大の成功要因はWHO総会で世界プログラムが決議され政治的なコミットメントが得られたことで、そこから共通の目的、共有された単一の政策的枠組み、パートナーシップが生まれ、資金的な裏づけが可能になった。しかしながら次々と国際機関から発信される保健政策には途上国の現場での検証が乏しい。現場で起こる問題点を科学的に分析することが重要で、援助と各省庁の利権を断ち切ることが求められる。外交の一環としてパートナーシップがあることを認識した上で、日本はアジアの一員として環境と文化とニーズを尊重し、国際社会と成熟したパートナーシップを構築する必要がある。そのために国際機関へのモニタリング・評価は重要である。
- 著者
- 三科 仁伸
- 出版者
- 三田史学会
- 雑誌
- 史學 = The historical science (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.3, pp.291-316, 2020-05
- 著者
- ヨハネス・ キーナー
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, pp.108-109, 2015
1 0 0 0 IR 「市民派」選挙と報道 : 東久留米市長選挙運動の研究
- 著者
- 井川 充雄
- 出版者
- 一橋研究編集委員会
- 雑誌
- 一橋研究 (ISSN:0286861X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.1-19, 1993-04-30
論文タイプ||論説
1 0 0 0 OA 日本密教における『瑜祇経』所説の尊格理解
- 著者
- 鍵和田 聖子
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.19-24, 2015-12-20 (Released:2017-09-01)
1 0 0 0 OA 中国高等職業教育分野における1+X証書制度の位置づけ
- 著者
- 張 潔麗
- 出版者
- 京都大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 京都大学大学院教育学研究科紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.57-70, 2021-03-25
本稿では中国高等職業教育分野における1+X制度の位置づけを明らかにするため、従来ある各種証書を制度枠組みと高等職業教育分野における取得方法を整理した。その結果、高等職業教育分野と企業・産業界との緊密なつながりを図る方向性は2000年以降継続してみられ、その具体的な方法は、既存の職業資格証書自体の高等職業教育分野への導入から、各種職業基準が反映される職業技能水準証書の新設までに転換したことが明らかになった。現在、高等職業教育分野では学歴証書、職業資格証書、職業技能水準証書が同時に存在し、これらの組み合わせからなる双証書制度および1+X制度が異なる位置づけを有している。後者の1+X制度は、労働者の学歴教育および職業の間の流動可能性を向上させて、高等職業教育分野と産業界の境界線を不明確にするものとして、高等職業教育分野と企業・産業界の双方の需要が反映される架け橋として位置づけられているといえよう。
1 0 0 0 IR 「市民派選挙運動」の組織論--東久留米市長選を中心に
- 著者
- 市川 虎彦
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 一橋論叢 (ISSN:00182818)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.2, pp.p250-266, 1993-02
- 被引用文献数
- 1
論文タイプ||論説
1 0 0 0 OA 大正・昭和戦前期の九州における自動車の普及過程
- 著者
- 奥井 正俊
- 出版者
- THE TOHOKU GEOGRAPHICAL ASSOCIATION
- 雑誌
- 東北地理 (ISSN:03872777)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.4, pp.230-244, 1990-12-01 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
大正初期から昭和戦前期にかけての九州において, 自動車が諸地域の中へ導入され, その普及が進展した過程を, 拡散理論の文脈に沿いながら考察した。おおむね旧郡を集計単位とする統計地区別に自動車普及率を求め, それらの分布の経年変化と, 自動車普及率の時間的経過の地区による相違について分析を加えた。九州全体の自動車普及率は, 研究対象期間を通してロジスティック曲線を近似できるようなS字状に上昇をつづけたが, 大正中期以降においては各地で乗合バスの導入が図られたことから急速な上昇を示し, さらに昭和5年頃からは停滞気味となり一定の上限値 (11台/万人) に収束する, という経過をたどった。地区別自動車普及率の分布がどのように経年変化したかをみると, 大正初期における普及率の高水準地区は, 福岡県から佐賀県にかけての地域と, 中・南九州の一部地域に分布し全体の3割程度を占めたが, その後普及率の平準化に伴って拡大していった。中・南九州と島嶼は, 自動車普及の後進地域と位置づけられる。次に自動車普及率の推移をロジスティック曲線でモデル化し,それらの地区による相違を考察した。自動車の導入時期は大正元年から, 最も遅いところで昭和元年までと大きな差がみられ, この差異の要因として階層効果と近接効果が作用しているが, これらに並び商工業のような自動車交通の需要因子も関与している。さらに自動車の普及の浸透速度も地区による差がみられるが, これは導入時期の遅速と密接に関係している。
1 0 0 0 IR 「笑い」の図像学的試論--16,17世紀のフランドル,オランダ絵画を中心として
- 著者
- 森 洋子
- 出版者
- 明治大学人文科学研究所
- 雑誌
- 明治大学人文科学研究所紀要 (ISSN:05433894)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.321-354[含 英語文要旨], 2008-03
1 0 0 0 OA 乳腺粘液癌における予後因子について
- 著者
- 常山 聡 日下 起理子 田村 裕恵 小松 良一 久保田 芳正 櫻井 宏治 赤羽 弘充 高橋 昌宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第55回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.268, 2006 (Released:2006-11-06)
<緒言>乳腺粘液癌は、腫瘍性上皮細胞から細胞外へ分泌された粘液巣を特徴とする特殊型の浸潤性乳癌である。発生頻度は全乳癌の1_から_4%であり、比較的まれな腫瘍である。また、予後については他の組織型に比して良好である。今回我々は、17症例の粘液癌における予後因子について、他の組織型との比較を行なった。<対象と方法>1995年から2004年に当院外科にて手術が施行され組織学的に乳腺粘液癌と確認された17症例を対象とした。また、比較対象として2002年_から_2004年の期間に当院で手術施行され、組織学的診断において粘液癌を含む特殊型を除いた166症例を使用した。これらの症例について、予後因子としてのエストロゲンレセプター(ER)、プロゲステロンレセプター(PgR)、p53、Her2/nueとの比較を行なった。<結果>ERにおける陽性率は、粘液癌では17症例中16件が陽性であり94%であった。また他の組織型では、120症例中84件で陽性率は70%であった。 ERは乳癌における予後因子として有用とされており、悪性度と負の相関を示すとされている。今回の結果における粘液癌のER陽性率は、他の組織型に比して高く、予後が良好であることを示していると考えられる。また、粘液癌でER陰性の症例1例は、肺転移をおこしていた。 PgRについては、粘液癌で13例が陽性で陽性率76%、他の組織型では120症例中陽性68例で陽性率51%であった。 PgRも乳癌における予後因子として有用であり、ER同様に悪性度と負の相関を示している。今回の結果における粘液癌のPgR陽性率も、他の組織型に比して高く、予後が良好であることを示していると考えられる。また、肺転移をおこした粘液癌については、PgRも陰性であった。 p53については、粘液癌で1例が陽性で陽性率6%、他の組織型では126症例中45件が陽性で陽性率36%であった。 p53については、ER・PgRとは反対に悪性度と正の相関を示すとされている。今回の粘液癌のp53陽性率は、他の組織型に比し低く、予後が良好であることを示していると考えられる。 Her2/nueについては、粘液癌で1例が陽性で陽性率6%、他の組織型では146症例中30例が陽性で陽性率21%であった。 Her2/nueは、p53同様にER・PgRとは反対に正の相関を示すとされている。今回の粘液癌のHer2/nue陽性率は、他の組織型に比し低く、予後が良好であることを示していると考えられる。また、粘液癌でHer2/nue陽性の症例1例は、ER・PgRともに陰性で肺転移をおこしていた症例であった。<考察>乳腺粘液癌は他の組織型に比較して、予後は良好であるとされている。また今回検討した予後因子からも良好であることが示されている。また、粘液癌17症例中現在までに転移が確認されている1例については、ER・PgRともに陰性、Her2/nue陽性と今回検討した3つの予後因子が、悪性度の高い可能性を示している。乳腺粘液癌においては、予後因子で悪性度が高い可能性を示している場合、将来の転移の可能性も考慮し、経過を観察していく必要があると考えられる。今後、再発の有無を含めた術後経過と予後因子の関係についても更なる検討をしていく必要があると考えられる。
- 著者
- 山田 政寛 北村 智
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.353-362, 2010-01-20 (Released:2016-08-06)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 3
教育学習研究において社会的存在感が着目されてきている.社会的存在感は学習意欲の向上や学習満足度の向上に対して有効であるとされているが,これらの知見は1つの社会的存在感の概念で説明されたものではない.社会的存在感の考え方が複数存在し,その違いによって研究知見も異なる.システムデザインや協調学習の評価のためには,「社会的存在感」に関する考え方や知見が整理されていることが望ましい.本稿では「社会的存在感」概念に関する考え方をSHORTらの考え方,GUNAWARDENA,TUらの考え方,GARRISONらの考え方に大別し,それぞれの考え方ごとにどのような研究が行なわれているのかを整理する.またその3つの考え方にもとづく測定法を整理することで「社会的存在感」概念が何の評価に関わるのかを議論する.
- 著者
- 池田 信太朗
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1376, pp.114-119, 2007-01-29
「お母さんも、何か趣味でも持ってよ」。大阪府岸和田市の主婦、辻イト子さん(57歳)は高校生になる娘がいつもの親子喧嘩のさなかに口にした一言に一瞬、たじろいだ。「何を生意気な!」と、すぐに気を取り直していつもの調子で返したが、娘が寝静まった後、1人で考え込んでしまった。 人生の全エネルギーを2人の娘の教育に注いできたと言っても過言ではない。