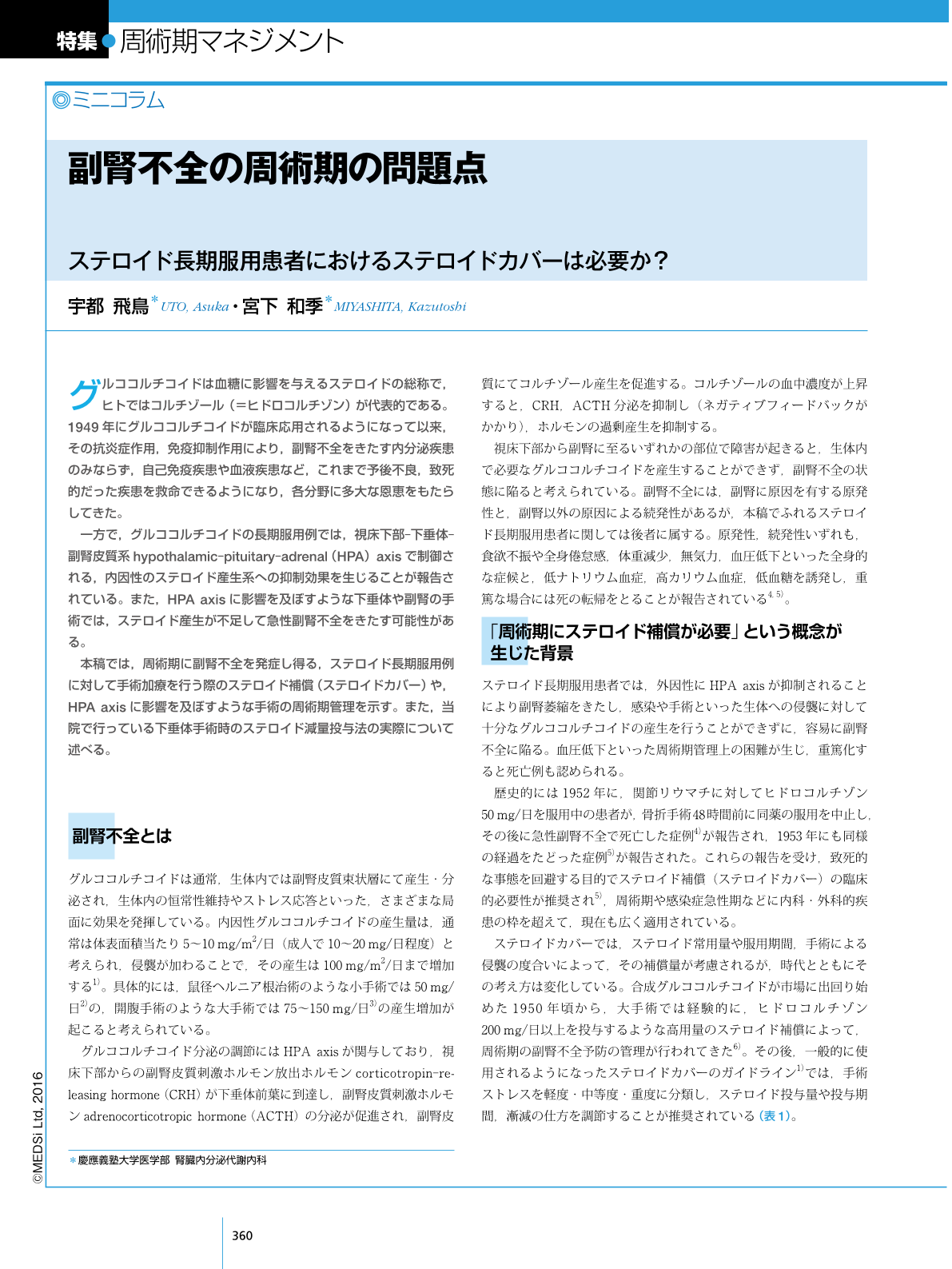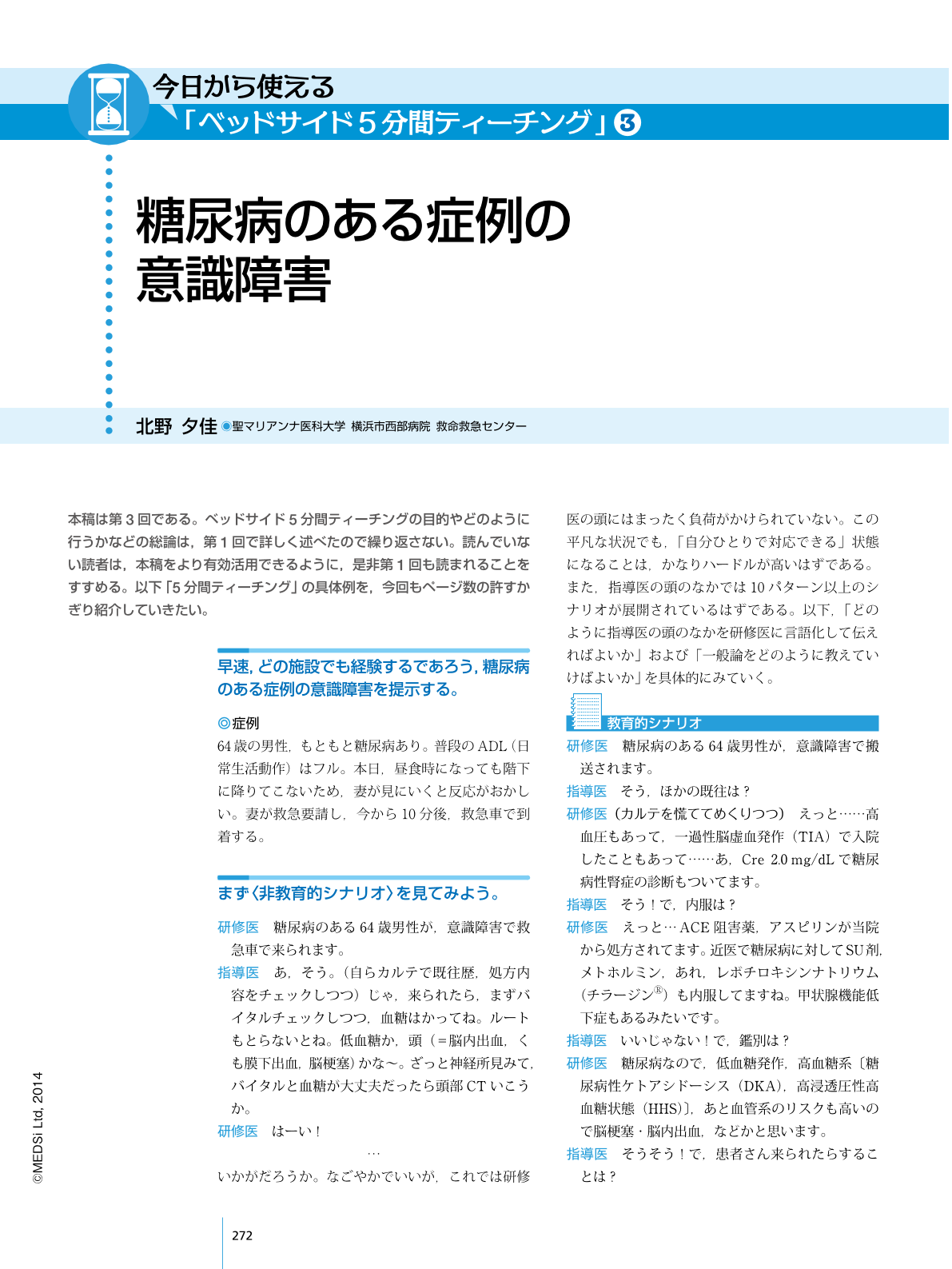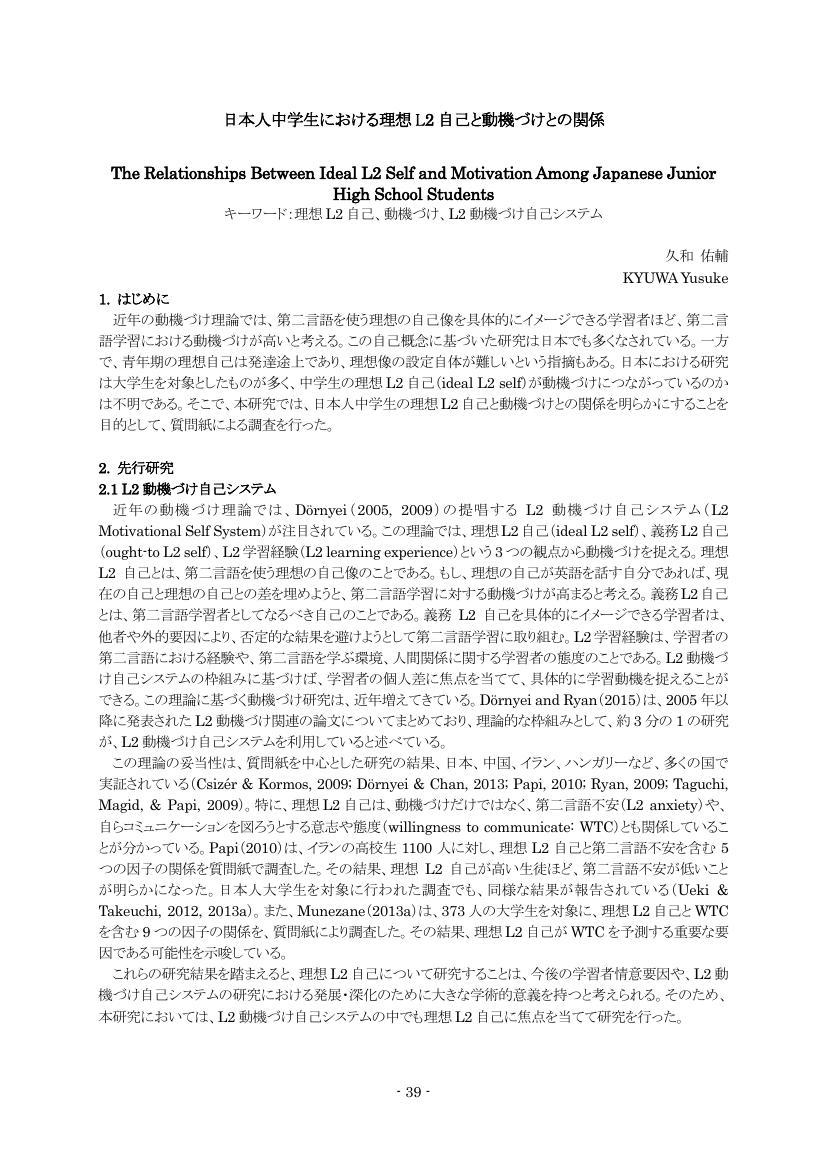1 0 0 0 OA 物理授業の作業化の方法とその事例
- 著者
- 赤堀 侃司
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 科学教育研究 (ISSN:03864553)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.152-159, 1983-12-10 (Released:2017-06-30)
- 著者
- 加藤 崇 佐々木 健介 Diego Fernandez Laborda Daniel Fernández Alonso David Díaz Reigosa
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, no.4, pp.265-271, 2020-04-01 (Released:2020-04-01)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 6
This paper presents a novel methodology of magnet temperature estimation using a magnet flux linkage observer for a Variable Leakage Flux Interior Permanent Magnet Synchronous M (VLF-IPMSM), whose parameters vary depending on load current conditions. The magnet temperature estimation algorithm consists of a Gopinath-Style flux observer, magnet flux linkage observer, and magnet temperature estimator based on the look-up table. The estimation accuracy is evaluated on d-q current plane by using both a behavior model of JMAG-RT and a control model of MATLAB Simulink. Then it is shown that the proposed methodology can be applied to a VLF-IPMSM for magnet temperature estimation.
1 0 0 0 OA 情報技術科,情報処理科の教育について
- 著者
- 佐々木 享 Sasaki Susumu
- 出版者
- 名古屋大学教育学部技術教育学研究室
- 雑誌
- 技術教育学研究 (ISSN:02870711)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.129-159, 1986-09-30
1 0 0 0 OA 日本産カワウにおけるダイオキシン類汚染の現状
- 著者
- 井関 直政 長谷川 淳 羽山 伸一 益永 茂樹
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.37-55, 2002 (Released:2007-09-28)
- 参考文献数
- 66
- 被引用文献数
- 4 4
化学物質による野生鳥類の研究史についてわが国の取り組みを紹介した.ダイオキシン類の汚染が大きな注目を浴びた近年,それらの問題に向けた対策や技術は大きな社会現象にもなった.わが国における化学物質による野生動物への影響に関する研究は,未だ少ないのが現状である.著者らは,魚食性鳥類であるカワウに着目し,ダイオキシン類の体内残留レベルを明らかにすると共に,既報の日本産鳥類のデータと比較した.その結果,カワウは最も高濃度に蓄積する鳥種であった.またPCDD/Fs の残留パターンは, 2,3,7,8-置換体PCDD/Fsが優占し,WHO-TEF (birds) を用いた毒性値への寄与には,1,2,3,7,8-PeCDDや2,3,4,7,8-PeCDF,CB126が大きな寄与を示した.肝臓におけるこれらのコンジェナーは,筋肉や卵よりも特異に蓄積していた.カワウにおけるダイオキシン類の半減期を算出し,環境濃度から卵への濃度を予測した結果,孵化率への影響は1970 年代をピークに減少傾向であることが推察された.現在のダイオキシン類の曝露による未孵化率は27%と見積もられ,個体群の減少には影響しないことが結論づけられた.しかしながら,別のエンドポイントや免疫などの調査の必要性が考えられ,これらを遂行するための非捕殺的モニタリング手法など,カワウ個体群をリスク管理するための新たな取り組みが期待された.
- 著者
- 石庭 寛子 十川 和博 安元 研一 星 信彦 関島 恒夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.69-79, 2016 (Released:2016-06-01)
- 参考文献数
- 66
- 被引用文献数
- 1
本稿では、化学物質汚染による野生個体群への影響を明らかにする1 つのアプローチとして、生物で普遍的に起きている「適応」に焦点をあてた評価例を紹介する。ダイオキシン類による汚染によってアカネズミ個体群内に、ダイオキシン抵抗性個体が増加するような集団構造の変化が起きているか否かを明らかにするため、ダイオキシン感受性の違いを識別する遺伝子マーカーを開発し、野外集団への適用を試みた。遺伝子マーカーとしてダイオキシン類の作用機序に深く関わるダイオキシン受容体(AhR)に着目し、野生集団におけるAhR 遺伝子の配列解析を行ったところ、アカネズミのAhR にはタンパク質の機能に差をもたらす変異、グルタミン(Q)、アルギニン(R)が799 番目のアミノ酸に存在していた。さらに生体での機能を調べるため、各遺伝子型を持つアカネズミへダイオキシン投与を行ったところ、Q を持つ個体はダイオキシンに対する反応が高く、R を持つ個体は低かった。このことから、このAhR のアミノ酸変異は、アカネズミ個体群においてダイオキシンに対する抵抗性保持個体を検出する遺伝子マーカーとして有用であると示唆された。ダイオキシン汚染地域のアカネズミ個体群において、確立された遺伝子マーカーのアリル頻度を調べたところ、非汚染地域と比較してアリル頻度に差は見られなかった。ダイオキシン類の暴露下で、Q タイプは有利性が低下し、R タイプは有利性が相対的に増加するが、その選択係数は非常に低く、世代数の経過も少ないためにアリル頻度の変化は見られなかったと考えられる。
- 著者
- 宇都 飛鳥 宮下 和季
- 出版者
- メディカル・サイエンス・インターナショナル
- 巻号頁・発行日
- pp.360-362, 2016-06-01
グルココルチコイドは血糖に影響を与えるステロイドの総称で,ヒトではコルチゾール(=ヒドロコルチゾン)が代表的である。1949年にグルココルチコイドが臨床応用されるようになって以来,その抗炎症作用,免疫抑制作用により,副腎不全をきたす内分泌疾患のみならず,自己免疫疾患や血液疾患など,これまで予後不良,致死的だった疾患を救命できるようになり,各分野に多大な恩恵をもたらしてきた。 一方で,グルココルチコイドの長期服用例では,視床下部-下垂体-副腎皮質系hypothalamic-pituitary-adrenal(HPA)axisで制御される,内因性のステロイド産生系への抑制効果を生じることが報告されている。また,HPA axisに影響を及ぼすような下垂体や副腎の手術では,ステロイド産生が不足して急性副腎不全をきたす可能性がある。 本稿では,周術期に副腎不全を発症し得る,ステロイド長期服用例に対して手術加療を行う際のステロイド補償(ステロイドカバー)や,HPA axisに影響を及ぼすような手術の周術期管理を示す。また,当院で行っている下垂体手術時のステロイド減量投与法の実際について述べる。
- 著者
- Yosuke Inoue Shuhei Nomura Chihiro Nishiura Ai Hori Kenya Yamamoto Tohru Nakagawa Toru Honda Shuichiro Yamamoto Masafumi Eguchi Takeshi Kochi Toshiaki Miyamoto Hiroko Okazaki Teppei Imai Akiko Nishihara Takayuki Ogasawara Naoko Sasaki Akihiko Uehara Makoto Yamamoto Makiko Shimizu Maki Konishi Isamu Kabe Tetsuya Mizoue Seitaro Dohi
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20190332, (Released:2020-07-25)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 6
Background: While much effort has focused on quantifying disease burden in occupational health, no study has simultaneously assessed disease burden in terms of mortality and morbidity. We aimed to propose a new comprehensive method of quantifying the disease burden in the workplace.Method: The data were obtained from the Japan Epidemiology Collaboration on Occupational Health (J-ECOH) Study, a large-scale prospective study of approximately 80,000 workers. We defined disease burden in the workplace as the number of working years lost among the working population during a 6-year period (April 2012 to March 2018). We calculated the disease burden according to consequences of health problems (i.e., mortality, sickness absence [SA], and ill-health retirement) and disease category. We also calculated the age-group- (20–39 and 40–59 years old) and sex-specific disease burden.Results: The largest contributors to disease burden in the workplace were mental and behavioural disorders (47.0 person-years lost per 10,000 person-years of working years, i.e., per myriad [proportion]), followed by neoplasms (10.8 per myriad) and diseases of the circulatory system (7.1 per myriad). While mental and behavioural disorders made a greater contribution to SA and ill-health retirement compared to mortality, the latter two disorders were the largest contributors to the disease burden in the workplace due to mortality. The number of working years lost was greater among younger vs. older female participants, whereas the opposite trend was observed in males.Conclusions: Our approach is in contrast to those in previous studies that focused exclusively on mortality or morbidity.
- 著者
- 片山 富美代 大北 全俊 工藤 成史
- 出版者
- 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部・スポーツ科学研究科
- 雑誌
- 桐蔭スポーツ科学 = Toin sport sciences (ISSN:24335177)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1-9, 2020
- 著者
- 辰野 勇
- 出版者
- 日本共産党中央委員会 ; 1979-
- 雑誌
- 女性のひろば (ISSN:03879429)
- 巻号頁・発行日
- no.458, pp.98-101, 2017-04
1 0 0 0 OA 凍結防止剤の種類および低温下における降温と昇温がソルトスケーリングに及ぼす影響
- 著者
- 田中舘 悠登 羽原 俊祐
- 出版者
- 一般社団法人 セメント協会
- 雑誌
- セメント・コンクリート論文集 (ISSN:09163182)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.244-250, 2020-03-31 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 12
凍結防止剤溶液の凍結と融解過程がスケーリングに及ぼす影響を明らかにするため、種々の凍結防止剤溶液の凝固点以下-30~-5℃において、様々な温度範囲で降温と昇温を繰り返し行った。凍結防止剤の種類によってスケーリングが起こる温度域が異なる結果となった。全ての凍結防止剤溶液において、スケーリングが起こる温度域は凝固点と共晶点の間であり、純氷と高濃度の凍結防止剤溶液が混在する状態である。一方、凍結防止剤の結晶と純氷の2成分の固体状態である共晶点以下では、スケーリングは起こらなかった。温度変化に伴い凍結防止剤溶液の一部分において凍結と融解が起こることにより、スケーリングが起こると考えられる。
1 0 0 0 糖尿病のある症例の意識障害
- 著者
- 北野 夕佳
- 出版者
- メディカル・サイエンス・インターナショナル
- 巻号頁・発行日
- pp.272-280, 2014-03-01
本稿は第3回である。ベッドサイド5分間ティーチングの目的やどのように行うかなどの総論は,第1回で詳しく述べたので繰り返さない。読んでいない読者は,本稿をより有効活用できるように,是非第1回も読まれることをすすめる。以下「5分間ティーチング」の具体例を,今回もページ数の許すかぎり紹介していきたい。
1 0 0 0 OA 1997年 (平成9年) の日本の天候の特徴
- 著者
- 植田 亨
- 出版者
- The Society of Agricultural Meteorology of Japan
- 雑誌
- 農業気象 (ISSN:00218588)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.171-177, 1998-06-15 (Released:2010-02-25)
1 0 0 0 OA 良書の読書と情報系大学生との関係性の研究
- 著者
- 柴田,雅雄
- 出版者
- 日本社会情報学会
- 雑誌
- 日本社会情報学会学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, 2010-09-30
近年,情報化の急激な進展とともに読書離れも懸念されつつある。このような状況の中で,良書を日頃からよく読むことが,情報化社会を生き抜くうえでどのような重要な意味を持つのかがこの研究の問いである。我々は,良書の読書が情報化社会の影の側面の予防と光の側面の促進に寄与していると考え,情報化社会の影響が著しい情報系大学生をケーススタディとして検証した。具体的には,良書の読書がテクノ依存症を抑制しQOLを向上させるだけでなく,プログラミングの学習意欲向上にも影響があると仮説を設定してアンケート調査を実施し,共分散構造分析で分析と検証を行った。その結果,良書の読書傾向が強い人は,テクノ依存症の予防的効果が示されるとともに,論理的思考愛好度が高くそれが結果としてプログラミング愛好度を高めるという因果関係が検証された。そのため,情報系大学生の教育現場において,良書の読書を推進することの重要性が示唆された。
1 0 0 0 OA 虚構制作の根源性 : ケンダル・ウォルトンの虚構論
- 著者
- 田村 均 Tamura Hitoshi
- 出版者
- 名古屋大学文学部
- 雑誌
- 名古屋大学文学部研究論集. 哲学 (ISSN:04694716)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.1-34, 2013-03-31
This paper has two purposes. One is to introduce Kendall Walton's theory of representational arts to the Japanese philosophical community. His theory is highly original in that it reveals the fact that the representational works of arts, such as paintings, sculptures, films, plays and novels, are to be regarded as being functionally the same as playthings, such as dolls, hobbyhorses, toy trucks and teddy bears. The theory depends on distinctive use of such concepts as games of make-believe, props, and representations. I try to make it clear what these concepts are meant to serve for. In doing this, I also try to give an overview of the role of imaginative activities as the foundation for our intellectual and emotional understanding of the world. This is the other purpose of this paper. According to Walton's view, dolls, toy trucks and works of arts, which serve for props of our games of make-believe, prompt us to imagine a fictional world where we have them as real things. An object in the real world can be turned into an item in an imaginary world that is different from itself-in-the-real-world. It should be real, however, in this fictional world. So we can take ourselves living with multiple realities in view of a Waltonian theory of make-believe. We would have an unexpected revelation of reality by artistic appreciation regarded as a kind of children's games of make-believe. In this sense, fiction-making capacity emerges as something very important and essential to human beings.
1 0 0 0 OA <文壇作家>時代の松本清張(Ⅰ) : 「多芸は無芸」の危うさのなかで
- 著者
- 藤井 淑禎 フジイ ヒデタダ
- 雑誌
- 大衆文化 = Popular culture
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.2-15, 2013-09-30
1 0 0 0 OA 二代目団十郎と江戸の開帳興行 : 不動明王を中心に
- 著者
- ビュールク トーヴェ
- 雑誌
- 大衆文化 = Popular culture
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.30-48, 2013-09-30
1 0 0 0 OA 亀井勝一郎「読書の態度と実際」(一九四二年) : 翻刻と解題
- 著者
- 赤堀 杏奈
- 雑誌
- 大衆文化 = Popular culture
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.49-61, 2013-09-30
1 0 0 0 OA 皮膚筋炎において嚥下障害に関連する自己抗体
- 著者
- 室野 重之
- 出版者
- 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科免疫アレルギー (ISSN:09130691)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.25-27, 2020 (Released:2020-03-26)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 IR ブレンターノの調査と優生学
- 著者
- 山崎 聡
- 出版者
- 高知大学教育学部
- 雑誌
- 高知大学教育学部研究報告 = Bulletin of the Faculty of Education, Kochi University (ISSN:1346938X)
- 巻号頁・発行日
- no.74, pp.123-129, 2014-03
1 0 0 0 OA 日本人中学生における理想L2自己と動機づけとの関係
- 著者
- 久和 佑輔
- 出版者
- 中部地区英語教育学会
- 雑誌
- 中部地区英語教育学会紀要 (ISSN:03866548)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.39-46, 2017-01-31 (Released:2018-01-31)