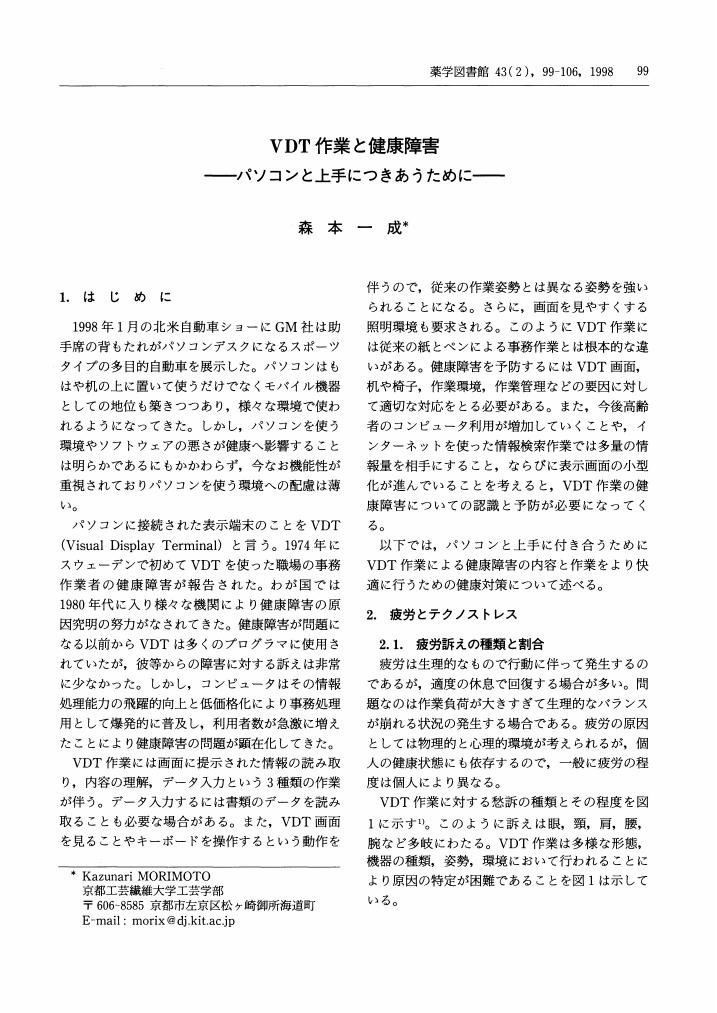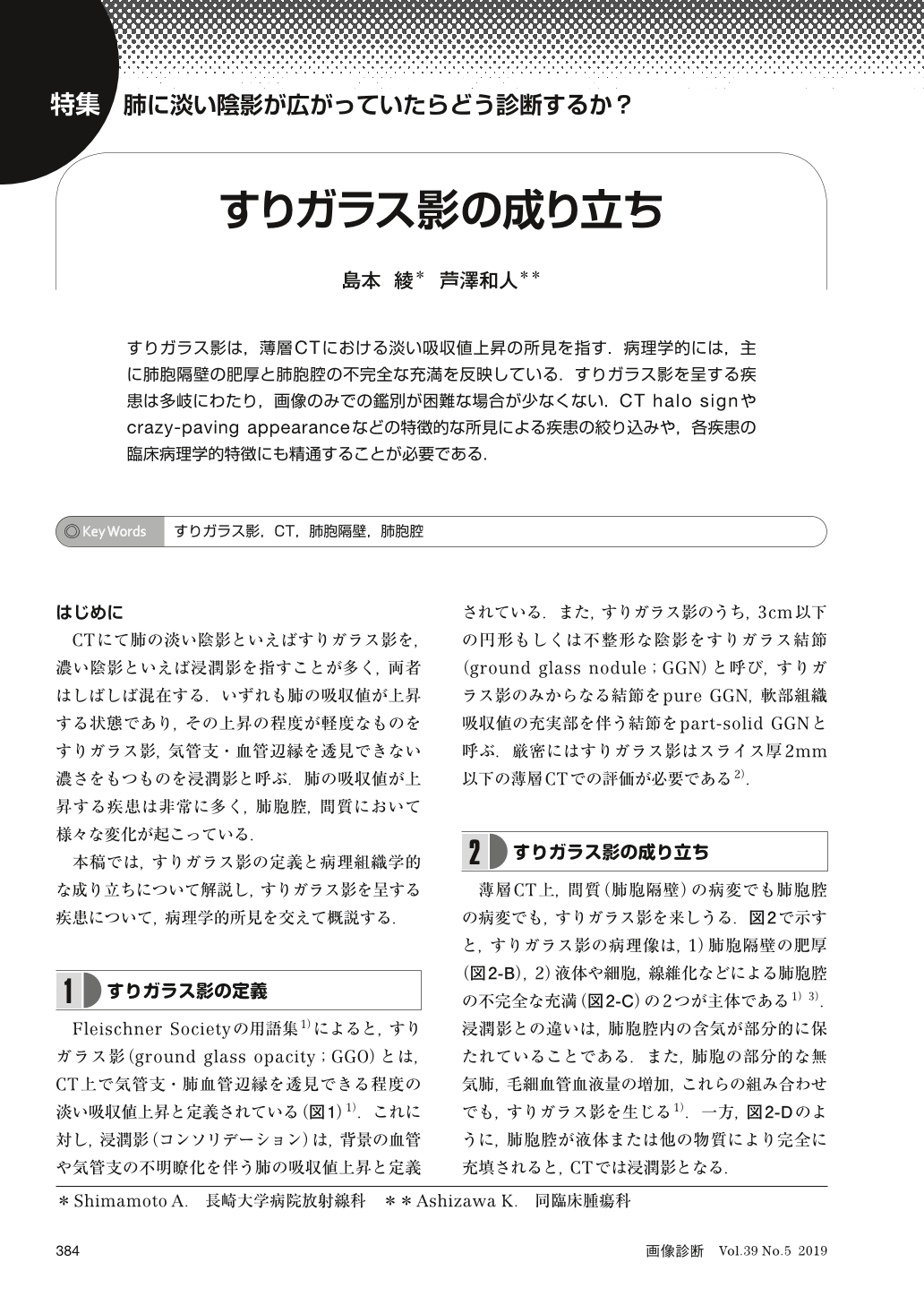1 0 0 0 OA VDT作業と健康障害
- 著者
- 森本 一成
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.99-106, 1998-04-30 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 澤地 實 山本 攻
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会誌 (ISSN:18835864)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.6, pp.422-426, 2016
1 0 0 0 OA AIの進化は故障解析に何をもたらすのか ~その期待とリスク~
- 著者
- 斎藤 彰
- 出版者
- 日本信頼性学会
- 雑誌
- 日本信頼性学会誌 信頼性 (ISSN:09192697)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.64-71, 2018 (Released:2019-10-07)
ディープラーニング技術の発明以来,様々な分野で業務の AI 化が進み,社会の構造が大きく変化しつつ ある.一方,品質という社会的責任を支える品質管理部門の人材不足は深刻であり,また電子機器の複雑 化・精密化に対応できる高い故障解析力を有する故障解析技術者の育成は至難の業である.本報文では, AI 自体の進歩や社会への浸透ではなく,AI 化がもたらす故障解析業務への影響を主に示した.加えて,故 障解析技術者の育成や技術の伝承をサポートするための方向性も示した.なお,本報文は,日本信頼性学 会故障物性研究会での調査結果と議論した内容に筆者の私見を加えたものである.
1 0 0 0 OA バイアスの種類とその対策 (2)
- 著者
- 若井 建志 大野 良之
- 出版者
- 社団法人 日本循環器管理研究協議会
- 雑誌
- 日本循環器管理研究協議会雑誌 (ISSN:09147284)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.188-190, 1999-04-30 (Released:2009-10-16)
- 参考文献数
- 1
前回はバイアスとは何か, およびバイアスの種類について述べた。今回はバイアスに対する対策を考えてみたい。
1 0 0 0 OA ノルウェーにおける土砂災害
- 著者
- 岡本 隆
- 出版者
- 公益社団法人 砂防学会
- 雑誌
- 砂防学会誌 (ISSN:02868385)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.56-60_2, 2006-05-15 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- DiogenesLaertius 武井 英明
- 出版者
- 立正大学教養部
- 雑誌
- 立正大学教養部紀要 (ISSN:02868946)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.p99-109, 1982
1 0 0 0 OA 非水溶液滴定法
- 著者
- 桝井 雅一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.8, pp.511-523, 1957-08-05 (Released:2009-06-30)
- 参考文献数
- 157
滴定分析法は分析法のなかでも簡易迅速な方法として最も広く用いられるものである.これには溶媒として水が重要な役割を果して来たが,水を用いないで種類の豊富な有機溶媒や,水以外の無機溶媒をその代りに用いることによって,滴定法の範囲が著しく拡大され,従来不可能か困難かまたは繁雑であった多くの滴定が容易に実施できるようになって来た.用いる器具類は大概の場合従来の水溶液滴定法と全く変りなく,往々電位差測定用に入力抵抗の高い装置,また大気と遮断された滴定系を必要とするが,前者は今日では大抵の研究室に常備されるガラス電極pHメーターなどで充分用が足りる.このような理由で急速にその応用が広まって来て,文献数も1940年代以後,特に1950年代になって急に増して来た.また著書や総説類も多数出てをり紹介は比較的よく行なわれている.このうち,わが国では木本氏の総説が1952年に出た後1954年に基礎分析化学講習会にて高橋氏の講座(テキスト)があり,1955年本誌に大内氏の文献紹介が出された.筆者は先に"最新の分析化学"第8集にイオノトロピーを紹介し試薬の解説を行い,1957年度薬学会年会総説講演要旨に主として薬学上の応用について紹介した.ここでは与えられた紙数がはなはだ少ないので,もっぱら日常分析法に関連したものについて,主として溶媒と終末点検知法の面からまとめてみた.従って基礎化学研究上行なわれた滴定,たとえば液体アンモニア中金属化合物の滴定などのごときは原則として含めないことにし,またそれぞれの物質については本総説によって応用は容易になると思われるし,"Analytical Chemistry"に出るReviewその他個々の文献から比較的索引しやすいので省くことにした.なお引用文献は"Chem.Listy"その他若干のものはChem.Abstr.によった.
1 0 0 0 IR 青蓮院蔵表制集及び灌頂阿闍梨宣旨官牒の紙背文書について
- 著者
- 伊東 卓治
- 雑誌
- 美術研究 = The bijutsu kenkiu : the journal of art studies
- 巻号頁・発行日
- no.184, pp.39-65, 1956-03-25
The Hyōsei-shū written in four horizontal scrolls and the Kanjō Ajari Senji Kanchō in one scroll, recently discovered in the Shōren-in Monastery in Kyoto by Prof. AKAMATSU Toshihide of the Kyoto University and Mr. ŌTA Kizō of the Kyoto Municipality, attract out attention as they have valuable writings inscribed on the back sides of their paper base. The Hyōsei-shū in Chinese : Piao-chih-chi) is a record concerning the T'ang priest Pu-K'ung San-tsang, its original being in six scrolls; the latter is a collection of Imperial documents investing kanjō ajari (ācārya or masterpriests qualified to baptize others) in the Enryaku-ji Monastery, and documents from the Prime Minister investing ajari (ācārya) in the Gangyō-ji and Hosshō-ji Monasteries, its original probably consisting of two scrolls. Both are manuscripts associated with the Esoteric Buddhism, and are imagined to have been possessed by Ryōyū, the head priest of the Shōren-in in its second generation from the eleventh to twelfth centuries. Both the documents were inscribed on the blank reverse sides of used sheets of paper. The obverse sides are chiefly manuscripts and letters addressed to a priest, presumably the above-mentioned Ryōyū, and some other letters and discarded documents. (Translator's note: In early times when paper was precious, back sides of already used paper sheets were frequently utilized for writing. Very often the second writings are more important historically, so that the original obverse sides with the first writings are treated as if they were the reverse sides. In these cases the original writings are called "paper-back writings".) The Hyōsei-shū was inscribed by priest Shunchō in 1087. The Kanjō Ajar i Senji Kanchō was inscribed about the same time by an unknown calligraphist, probably on the model of the same documents originally owned by the priest Jikaku Daishi. The present study is devoted to researches on the contents, characteristics and the significance in the history of Japanese calligraphy, of the manuscripts and letters on the original obverse sides of the scrolls. They comprise sixty--five items altogether, consisting of eight documents, seven letters in Chinese characters, and fifty letters in kana (Japanese syllabaries). Most of the letters are by members of the family of the courtier FUJIWARA Tamefusa (1049-1115): eleven Chinese-character letters by Tamefusa, forty-two kana letters by Tamefusa's wife, and two Chinese-character letters supposedly by Tamefusa's son. Their dates are mostly in the Ōtoku era (1084-1086). Other items include documents with dates of Eiho 3 to 4 (1082-1084) and Ōtoku 2 (1085), and kana letters whose writers and dates are unknown. It is interesting to find in one of them a statement about smallpox, for it is recorded in history that the Crown Prince Sanehito died of smallpox on the eighth day of the eleventh month of Ōtoku 2 (1085). The kana letters by Tamefusa's wife are the only examples of the sort known to date. They are very important materials in the history of calligraphy, for they enable us to date the surviving portions of the anthology Reika shu (known as "Kōshi-gire", calligraphed by Ko-ōgimi) and of the Collected Poems by Lady Saigū (known as "Kōjima-gire", calligraphed by Ono-no-Tōfū) showing marked resemblance in style to them, in approximately the same period as these letters. Furthermore, some of the kana letters by unknown writers contain early specimens of calligraphic style akin to those of the "Indigo Paper Version" of the anthology Man-yo-shu ascribed by some scholars to the hand of FUJIWARA Koremochi, and of the record of a poetry contest known as "Jūgo-ban Uta-awase"; the kana letters by Tamefusa written to his children also are unique examples. To summarize, the discovery of the writings on the back of these scrolls supplies us valuable materials of kana writing which help us in chronological editing of other specimens in the second half of the eleventh century. It is significant also that they include kana letters with dates and the names of writers.
1 0 0 0 OA 九段坂病院(東京都内)における最近 20 年間のケムシ皮膚炎患者について
- 著者
- 大滝 倫子 滝野 長平
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.65-68, 1998-03-15 (Released:2016-08-18)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1 2
Two hundred and fifty-four patients with caterpillar dermatitis treated in the Department of Dermatology, Kudanzaka Hospital, from 1977 to 1996,were studied. Of the 254 patients, 163 were male, so the male-female ratio was 1.8 : 1. The ages of patients ranged from 2 to 79. The predominant age was 40 to 59 for male (52% of all males) and 26 to 29 for females. About half of the male patients in the predominant age group came in contact with caterpillars during gardening on weekends. Seasonal prevalence showed two peaks, the maximum was in July and the next highest in September. The causative insect was predominantly thought to be Euproctis pseudoconspersa. During twenty-year period, the highest number of patients visited our clinic in 1996,followed by 1989 and 1984. The relationship between the number of patients and climate conditions, which may affect the population of these insects, was investigated. However, no clear relationship between the two was observed.
1 0 0 0 OA 4.毛虫皮膚炎はなぜ生じるか
- 著者
- 夏秋 優
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.230, 2003-06-15 (Released:2016-08-07)
- 著者
- 鈴木 邦雄
- 出版者
- ニュ-・サイエンス社
- 雑誌
- 昆虫と自然 (ISSN:00233218)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.14-21, 2004-03
1 0 0 0 すりガラス影の成り立ち
- 著者
- 島本 綾 芦澤 和人
- 出版者
- 学研メディカル秀潤社
- 巻号頁・発行日
- pp.384-392, 2019-03-25
すりガラス影は,薄層CTにおける淡い吸収値上昇の所見を指す.病理学的には,主に肺胞隔壁の肥厚と肺胞腔の不完全な充満を反映している.すりガラス影を呈する疾患は多岐にわたり,画像のみでの鑑別が困難な場合が少なくない.CT halo signやcrazy-paving appearanceなどの特徴的な所見による疾患の絞り込みや,各疾患の臨床病理学的特徴にも精通することが必要である.
1 0 0 0 OA 児童の遊び場としてのUR団地屋外空間の設計指針と利用実態に関する研究
- 著者
- 松浦 きらら 藤井 さやか 有田 智一
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.285-290, 2013-10-25 (Released:2013-10-25)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
本研究では都区部におけるUR賃貸住宅団地が有する団地屋外空間を取り上げ、URによる団地屋外空間設計手法が持ちうる課題を抽出することと、団地屋外空間が地域内で活用される実態の把握を通じて今後の団地屋外空間への設計指針への示唆を得ることを目的としている。団地屋外空間の設計内容と活用実態について、地区内の複数の遊び場と対象地を比較すること、対象団地における設計内容と活用実態の比較検討をする際に団地敷地内における配置計画に着目することによって、団地屋外空間が団地居住の児童のみならず周辺地域児童にとっても活用できる遊び場である可能性を検討する。調査結果からは、都区部におけるUR賃貸住宅団地には公的機能・配置を有する屋外空間が豊富に存在し、地域資源として貢献できる可能性があることを把握した。活用実態としては、UR所有の屋外空間であったとしても団地全体の配置計画上団地外居住児童による利用が活発となる場合があり、そのために設計時の利用構想内容と活用実態に齟齬が生じうることが明らかになった。
1 0 0 0 OA 日本北アルプス登山案内
1 0 0 0 中古語におけるナドの引用助詞用法について
- 著者
- 辻本 桜介
- 出版者
- 明治書院
- 雑誌
- 国語と国文学 (ISSN:03873110)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.7, pp.53-68, 2018-07
1 0 0 0 OA 市販魚醤の品質調査ならびに味質評価
- 著者
- 石川 匡子 内田 詩乃 佐藤 春香 伊藤 俊彦 渡辺 隆幸
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.5, pp.308-316, 2016 (Released:2017-09-27)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
市販魚醤を用い,品質ならびに呈味評価を行った.魚介類と食塩のみで製造する場合は,魚介類自体のタンパク質の自己消化のみで分解するため,長期熟成が必要であり,微生物繁殖抑制のため塩分濃度が高めに設定されていたが,遊離アミノ酸総量やグルタミン酸量も多いという特徴があった.魚介類に食塩と麹を添加する方法では,短期熟成が可能であり,塩分濃度が低く,麹により甘くクセが抑えられた香りという特徴があった.魚種や製法の違いは,アミノ酸量や有機酸量にも反映された.特に,グルタミン酸,アラニン,乳酸量は魚醤のうま味や甘味,酸味の強さとなって現れた.これらの味質は,お吸い物に用いた際に,まろやかさや好ましさに影響しており,魚醤の味質に合わせた最適添加量を求める必要性が示唆された.
- 著者
- 福嶋 開人 湯村 翼 リム 勇仁 丹 康雄
- 雑誌
- 研究報告ユビキタスコンピューティングシステム(UBI) (ISSN:21888698)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020-UBI-66, no.1, pp.1-8, 2020-05-18
少子高齢化の進展により,少ない働く世代で多くの高齢者を支えることから働く世代,高齢者ともに負担が高まっており,少ない介護者で効率的に高齢者を見守る方法が注目されている.そこで,無線電波によるデバイスフリーで呼吸数および心拍数を推定する研究がされており,種々の電波方式が検討されている.例えば,専用無線機器を用いた FMCW や汎用無線の Wi-Fi を用いる方法が挙げられる.しかし,これらの方法には機器が社会に広く普及していない点や消費電力が大きい点で,家庭内での利用に不向きという問題がある.本稿では,汎用無線標準である Bluetooth Low Energy のアドバタイズ機能を用いて家庭内にいる居住者の呼吸数および心拍数の取得の可能性について検討する.実験では,人の呼吸数および心拍数に相当する振動をアルミバルーンを用いて再現し,送信電波がフレネルゾーンにより干渉することで生じる受信強度の変化から振動が取得できるかを確認した.呼吸数の 10bpm,15bpm,20bpm において,想定した周波数に反応が出ている結果を得た.このことから,BLE 電波を用いて生体情報の実現が取得が可能であると結論付けた.今後の展望として,本実験では利用しなかった送信パケットのデータ部に送信機の位置を格納し,マルチアンテナ構成を実現することでより高精度な測定の実現を見込む.また,家庭内での位置情報を利用する研究と組み合わせることで居住者一人ひとりを識別し,個人に合わせた提案を行う社会的に影響の大きな技術となり得る.
1 0 0 0 OA 〈論文〉事業収益におけるテールリスクの定量化:モンテカルロシミュレーションを用いた簡便法
- 著者
- 中岡 孝剛
- 出版者
- 近畿大学商経学会
- 雑誌
- 商経学叢 = Shokei-gakuso: Journal of Business Studies (ISSN:04502825)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.5, pp.279-297, 2019-03-31
[要旨]金融危機などのテールイベントに対するリスクエクスポージャーを評価することは事業継続の観点から重要である。しかし,事業活動において,企業が直面するテールリスクを定量的に把握することは難しく,モデルの開発が進んでいない。本稿では,アーニングス・アット・リスク(EaR)の概念を用いて,企業が事業収益において直面するテールリスクの簡便的な定量化方法を紹介する。この方法は複数のリスクドライバーの導入などモデル精緻化あるいは拡張が可能であり,実務的にも応用が可能なものである。 [Abstract]Measuring the risk exposure to tail-events like the global financial crisis that was happened in 2008 has become a vital role for the principle of business continuity. However, it is not easy to quantitatively perceive the tail risk that firms may face in their businesses. In this paper, I provide a simple model which allows us to measure the tail risk by applying the concept of“ Earnings at Risk(EaR)”. This model can be ameliorated or expanded to include multiple risk-drivers, and applicable to the practical analysis.
- 著者
- 久木原 賢治 入江 智和
- 出版者
- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会
- 雑誌
- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集 平成22年度電気関係学会九州支部連合大会(第63回連合大会)講演論文集
- 巻号頁・発行日
- pp.47-48, 2010 (Released:2012-02-24)
現在Internetが直面している非常に切実な問題はIPアドレスの枯渇と経路表増大である。 これらの問題に対する短期的解決法としてNATが挙げられる。 NATは主にローカルなネットワークではプライベートIPアドレスを設定し、インターネットへ接続するときにグローバルIPアドレスに変換する用途で用いられる。 しかし現在の一般的なNAT実装にはローカルブロードキャストを転送しないなど、NATの透過的利用の側面での課題がある。 その解決のために本研究ではNAT拡張を提案している。 今回は提案拡張の有効性と実現性の検証を行う。提案拡張によりNATの透過性が向上が実現する。