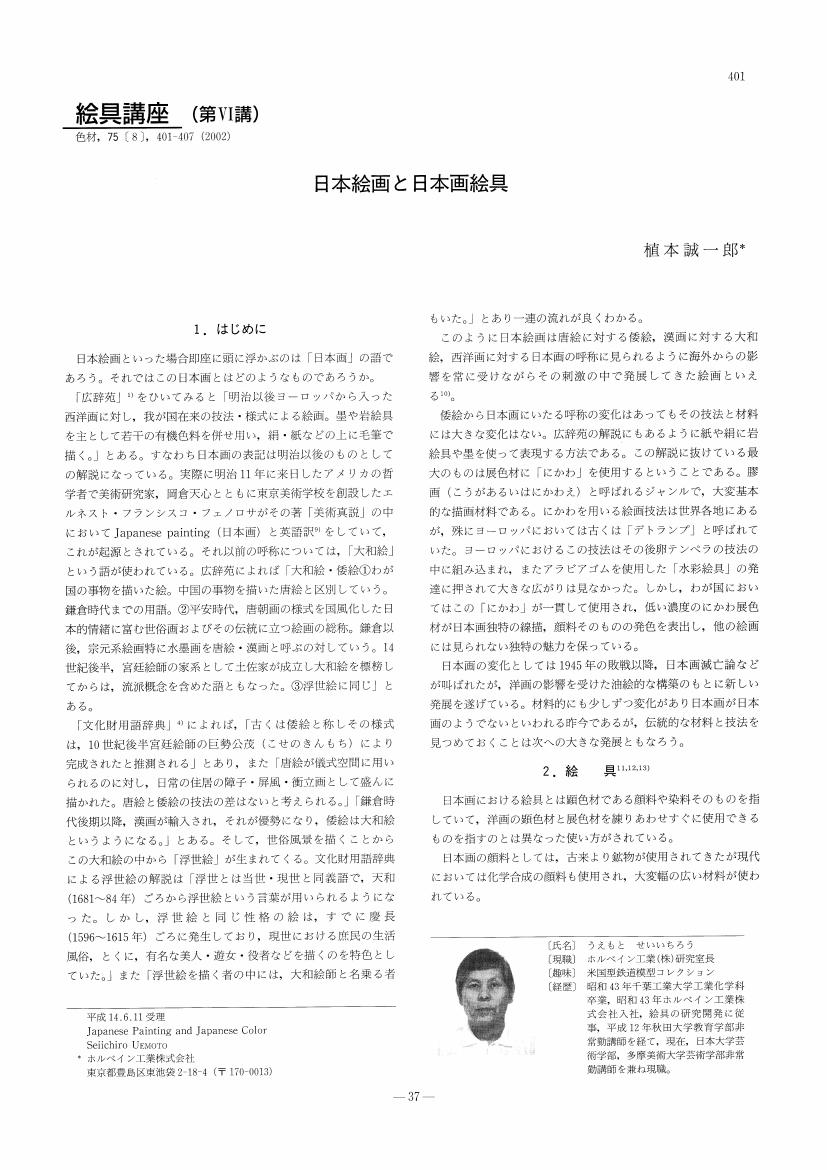3 0 0 0 OA ビッグデータ時代における特許情報調査への人工知能の活用
- 著者
- 田辺 千夏
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.7, pp.372-376, 2017-07-01 (Released:2017-07-01)
現在の第3次人工知能ブームは,情報の蓄積が爆発的に進んだことと情報処理能力が向上したことがきっかけとなっている。特許情報も例外ではなく,特許調査・解析分野への人工知能の応用は既に始まっている。筆者の所属企業である昭和電工(株)でも数年前から人工知能の特許調査分野への応用に着目しており,Patent Explorer,XLPATといった人工知能を用いた商用ツールの導入により特許調査の効率化,自動化を推進している。本稿ではシステムユーザーとしてこれらのツール導入にあたっての期待効果,使用感ならびに今後の展望を紹介する。
3 0 0 0 OA ビッグデータの解析ツールとしての機械学習
- 著者
- 池田 和司
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.26-30, 2014-06-01 (Released:2014-09-01)
- 参考文献数
- 12
3 0 0 0 OA 結び目のエネルギー
- 著者
- 今井 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.365-378, 1997-10-30 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 47
3 0 0 0 OA 鍼灸の有害事象トピックスと B 型肝炎対策の最新情報
3 0 0 0 OA 夏季に発生したアカウニの細菌感染症
- 著者
- 浜口 昌巳 川原 逸朗 薄 浩則
- 出版者
- Japanese Society for Aquaculture Science
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.189-193, 1993-06-20 (Released:2010-12-10)
- 参考文献数
- 24
佐賀県栽培漁業センターで1992年の4月に採卵・孵化したのち, 種苗生産を行っていた稚アカウニに8月後半から9月初旬にかけて大量斃死が発生した。発生時の水温は23~25℃で, 斃死個体は黒斑や脱棘が顕著ではなく, 囲口部の変色や付着力の低下などの症状を呈していた。また, 管足表面には多数の糸状とも思える長かん菌の蝟集が認められた。この菌はFlex-ibactey maritimus2408株に対する抗血清とよく反応した。海水で調製した改変サイトファガ培地上で分離したところ, 無色で周辺が樹根状のコロニーを形成した。この細菌による人為感染試験を菌液塗布法 (2.3×106cells/ml) と浸漬法 (3.8×106, 3.8×105cells/ml) によって行ったところ, いずれも発症・斃死にいたった。このことから, 今回の大量斃死は細菌感染症であることが明らかとなった。
3 0 0 0 OA 水道水の微生物汚染
- 著者
- 金子 光美
- 出版者
- 公益社団法人 日本水環境学会
- 雑誌
- 水質汚濁研究 (ISSN:03872025)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.8, pp.478-483, 1986-08-10 (Released:2009-09-10)
- 参考文献数
- 35
3 0 0 0 OA 戦後都区制度改革の歴史と論点
- 著者
- 小原 隆治
- 出版者
- 日本行政学会
- 雑誌
- 年報行政研究 (ISSN:05481570)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.2-23, 2014 (Released:2020-03-24)
- 著者
- Kazushi Matsumura
- 出版者
- Chem-Bio Informatics Society
- 雑誌
- Chem-Bio Informatics Journal (ISSN:13476297)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.54-57, 2020-09-11 (Released:2020-09-11)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2
Skin sensitization is an important aspect of occupational and consumer safety. Because of the ban on animal testing for skin sensitization in Europe, in silico approaches to predict skin sensitizers are needed. Recently, several machine learning approaches, such as the gradient boosting decision tree (GBDT) and deep neural networks (DNNs), have been applied to chemical reactivity prediction, showing remarkable accuracy. Herein, we performed a study on DNN- and GBDT-based modeling to investigate their potential for use in predicting skin sensitizers. We separately input two types of chemical properties (physical and structural properties) in the form of one-hot labeled vectors into single- and dual-input models. All the trained dual-input models achieved higher accuracy than single-input models, suggesting that a multi-input machine learning model with different types of chemical properties has excellent potential for skin sensitizer classification.
3 0 0 0 OA 若年女性冷え症者における心電図と身体状況の特徴
- 著者
- 青峰 正裕 大和 孝子
- 出版者
- Japanese Heart Rhythm Society
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.10-15, 2002-01-25 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 4 4
女子大学生 (252名) を対象として, 身体の各部に冷えを訴える冷え症者 (冷え症群) と, 冷えを自覚しない正常者 (正常群) の身体的特徴と標準肢誘導心電図を比較した.冷え症群では体脂肪量, 皮下脂肪厚, 体脂肪率は正常群と比べて, いずれも有意に低下しており, 体脂肪が低い傾向にあった.また, 除脂肪体重も正常群に比し有意に低く, このことは身体を構成する筋肉量も少ないことを示唆しており, したがって体重, BMIも低く, 冷え症群は痩せ型の傾向があった.心電図波形を正常群と冷え症群で比較した場合, QT時間とR-R間隔を除いて他の心電図波形には有意な差は観察されなかったが, 両ファクターはともに冷え症者で延長していた.また, 脈拍数は冷え症群では有意に低下しており, R-R間隔の延長がQT時間の延長を招き, それが冷え症群における心拍数の減少を引き起こしていることが考えられ, QT時間を先行するR-R間隔で補正したQTcを両群間で比較すると, 有意差は消失した.このように冷え症者は一般に痩せ型であり, 徐脈傾向で, 心電図ではQT時間とR-R間隔の延長が観察される傾向があることが明らかになった.最後に冷え症と自律神経障害との関係を論じた.
3 0 0 0 OA 高等植物におけるテロメア長の解析とテロメア結合タンパク質のクローニング
- 著者
- 森口 亮 金浜 耕基 金山 喜則
- 出版者
- 日本植物生理学会
- 雑誌
- 日本植物生理学会年会およびシンポジウム 講演要旨集 第45回日本植物生理学会年会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.589, 2004-03-27 (Released:2005-03-15)
テロメアは染色体末端領域のことであり、染色体の安定的な維持に必須である。本研究ではテロメア長の制御機構を明らかにすることを目的として、まず永年生植物であるリンゴ・サクラを用い、植物個体内の齢に沿ったテロメア長の測定を行った。その結果、テロメア長は各部位間で一定の範囲内に保たれ、少なくとも20年間に渡る細胞分裂を経てもテロメア長は変化しないことが示された。このことより、細胞分裂に伴ってテロメア長が減少する動物と異なり、植物では厳密なテロメア長制御機構の存在が考えられた。 続いて、モデル園芸作物であるトマトを用い、テロメア長の制御に関わると考えられるテロメア結合タンパク質(TBP)のクローニングを行った。まず、トマトESTにおいてアラビドプシス、イネのTBPと相同性の高い配列を参考にして全翻訳領域を含むcDNAの単離を行った。この推定トマトTBP(LeTBP)は689アミノ酸から成り、C末端領域にMyb型DNA結合モチーフが確認できた。またLeTBP遺伝子はシングルコピーで存在し、解析に用いた全ての器官において発現がみられた。次に、Myb型DNA結合モチーフを含む部分タンパク質を大腸菌で発現させ、ゲルシフト解析に用い結果、LeTBPは2本鎖テロメア配列に特異的に結合するTBPであることが示された。
3 0 0 0 OA 化粧品の種類と使い方—スキンケア化粧品—
- 著者
- 南野 美紀
- 出版者
- 日本香粧品学会
- 雑誌
- 日本香粧品学会誌 (ISSN:18802532)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.109-124, 2018-06-30 (Released:2019-06-30)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 2
Cosmetics that are used daily to keep our skin healthy and to make it look attractive, are available in many types where ingredients comprising them vary depending on the formulation in which they are contained. The infant stage of modern Japanese cosmetic history just after the Meiji Restoration (1868) saw many novel products appearing on the market one after another due to demands and changes in consumer perceptions, new findings in dermatology and the birth of new ingredients and development of formulation technologies, where up until then, only limited items e.g., facial cleansers and skin lotions for skincare and face powders, rouge and eyebrow pencils for makeup were commercially available. The myriad of cosmetic formulations available today are the fruits of the technology development history to meet consumer demands. With the recent advent of consumers demanding both efficacy and safety concurrently, cosmetic research and development too has entered a new era, and changes are envisaged in marketing strategies as well. Hence, to safely make full use of the products that flood the market today, their proper usage should be understood and executed correctly. This article will attempt to outline the types and usage of skincare cosmetic products that flourish the market through tracing the history of cosmetic technologies and marketing strategies.
3 0 0 0 OA 日本絵画と日本画絵具
- 著者
- 植本 誠一郎
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.8, pp.401-407, 2002-08-20 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- Erik J.G. Sewalt Fuweng Zhang Volkert van Steijn J. Ruud van Ommen Gabrie M.H. Meesters
- 出版者
- Hosokawa Powder Technology Foundation
- 雑誌
- KONA Powder and Particle Journal (ISSN:02884534)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021017, (Released:2020-09-19)
- 参考文献数
- 79
- 被引用文献数
- 5
Sticking of particles has a tremendous impact on powder-processing industries, especially for hygroscopic amorphous powders. A wide variety of experimental methods has been developed to measure at what combinations of temperature and moisture content material becomes sticky. This review describes, for each method, how so-called stickiness curves are determined. As particle velocity also plays a key role, we classify the methods into static and dynamic stickiness tests. Static stickiness tests have limited particle motion during the conditioning step prior to the measurement. Thus, the obtained information is particularly useful in predicting the long-term behavior of powder during storage or in packaging. Dynamic stickiness tests involve significant particle motion during conditioning and measurement. Stickiness curves strongly depend on particle velocity, and the obtained information is highly relevant to the design and operation of powder production and processing equipment. Virtually all methods determine the onset of stickiness using powder as a starting point. Given the many industrial processes like spray drying that start from a liquid that may become sticky upon drying, future effort should focus on developing test methods that determine the onset of stickiness using a liquid droplet as a starting point.
3 0 0 0 OA 高坂正顕における超越と人間の問題-「生命の根源に対する畏敬の念」についての考察-
- 著者
- 山田 真由美
- 出版者
- 日本道徳教育学会
- 雑誌
- 道徳と教育 (ISSN:02887797)
- 巻号頁・発行日
- no.333, pp.43, 2015 (Released:2019-09-02)
本論文は、中教審答申・別記「期待される人間像」に明記される「生命の根源」がいかなる概念であるかということを念頭に、主査として同文書をまとめた京都学派の哲学者・高坂正顕の歴史哲学を再検討する。教育行政に積極的に関与したことから高坂は、国家や天皇に従属する「人間像」を主張する国家主義者であると解されることが一般的であった。しかしながら彼の思索を吟味してみると、その根柢には西田哲学を継承した「絶対無」の思想が横たわり、一貫して絶対の不在が説かれている。特に本稿でみた『歴史の意味とその行方』1950では、人間性の超越的否定性なる性格ゆえに、歴史的世界に存するすべては絶対的相対性をその本質とする旨が強調される。そして高坂のいう「無」の概念を引き受けたとき、道徳教育は「無限の探究」という新たな可能性をひらくのである。
3 0 0 0 OA 家庭犬におけるシカ副産物に対する嗜好評価
- 著者
- 福澤 めぐみ 中島 彩香 若山 遥
- 出版者
- 日本家畜管理学会
- 雑誌
- 日本家畜管理学会誌・応用動物行動学会誌 (ISSN:18802133)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.151-157, 2018-12-25 (Released:2019-03-03)
- 参考文献数
- 15
シカ副産物(「大腿骨」、「肋骨」、「角」)に対するイヌの嗜好性を評価した。健康な成犬8頭(47.38 ± 36.80ヶ月齢、21.4 ± 9.78kg)に対して、3種類のシカ副産物を3分間提示した。嗜好テスト中の各副産物はケースに封入され、イヌは各副産物の特徴を視覚と嗅覚から入手することは可能だったが、直接の接触はできなかった。各副産物摂食経験による嗜好変化を検討するため、嗜好テストは摂食経験前および後、それぞれ3反復実施した。嗜好テスト中の行動(6項目)、副産物を封入したケース破壊の有無、副産物到達時間をそれぞれ連続記録した。探査行動の発現時間から、摂食経験前は「肋骨」や「角」よりも「大腿骨」に興味を示した。また、「角」への興味は反復に伴い低下した。摂食経験後もイヌは「肋骨」と「角」よりも「大腿骨」に興味を示し、到達時間は有意に短縮した。ケース破壊行動からは、「大腿骨」よりも「肋骨」への嗜好が高まったと考えられた。これらのことより、イヌのシカ副産物の外観に対する嗜好は摂食経験によって変化することが明らかとなった。
- 著者
- 早川 貴子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第48回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.37, 2006-08-21 (Released:2017-03-30)
3 0 0 0 OA 磁束線ピン止め・非局在転移・非エルミート量子力学
- 著者
- 羽田野 直道
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.11, pp.826-833, 1998-11-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 18
非Hermiteなハミルトニアンを持つ量子力学の新しい模型が提案され, その興味深い性質が明らかにされつつあります. この解説ではその模型を研究する物理的動機を説明し, 性質の一端を紹介します. この非Hermite系の示すAnderson局在という現象と, 高温超伝導体中の磁束線ピン止めという物理現象が, Feynman経路積分を通してつながっていることを示します. そして, 非Hermite系の複素エネルギー・スペクトルが磁束線のピン止め破壊転移をどのように記述するかを議論します. 非Hermite系は従来「物理的でない」と考えられがちでしたが, 様々な分野で物理現象を有効的に記述する模型として, ここ数年で急速に研究が進み始めました.
3 0 0 0 OA 補体レクチン経路と凝固系の協調作用 ―補体系研究の新展開―
- 著者
- 遠藤 雄一
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.164-170, 2011-08-01 (Released:2011-09-13)
- 参考文献数
- 27
3 0 0 0 OA 関節リウマチ患者のフットケアの戦略,靴と装具の実践法の紹介
- 著者
- 矢部 裕一朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本フットケア学会
- 雑誌
- 日本フットケア学会雑誌 (ISSN:21877505)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.7-12, 2019-03-30 (Released:2019-03-30)
- 参考文献数
- 5
【要旨】関節リウマチ足部疾患は見逃されやすいため,患者の足,靴,歩き方を見ること,患者の訴えを生活に合わせて伺うことが大切と考える.「爪が切れるか」の動作を確認して,下肢だけでなく上肢機能体幹機能も確認する.「下肢浮腫は,両側 or 片側?」,「レイノー現象,血管炎はあるか」,「皮膚潰瘍の確認」,「胼胝の確認」,「皮膚乾燥」,「靴の履き方,擦れ,靴紐が締解可能か」,「服薬,外用剤が使用できるか確認」等が観察ポイントと考える.フットケアチーム(患者,介護ケアする家族,地域医療関係者,医師,看護師,理学作業療法士,義肢装具士,靴小売業,ケアマネージャー等)で問題点の共通化をして,双方向性のコミュニケーションを持って合意を形成して,問題点の改善を図る.具体的に例示すると,MTP 関節周囲の足底胼胝では,メタタルザルバー,メタタルザルパッドを胼胝のやや踵よりに設置し,必要に応じ足底挿板を処方し,義肢装具士,靴業者に依頼している.足趾関節で PIP 関節炎や外反母趾的 MTP 関節炎では,靴アッパーヴァンプの靴革を鞣してあたる部位の靴革を伸ばす.関節リウマチフットケアでは,足部疾患の問題点を総括,ケアを継続していくことが必要と考える.
3 0 0 0 OA 地上デジタル放送日本方式の規格と国際展開
- 著者
- 古川 易史
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.15, pp.15_49-15_53, 2010-11-25 (Released:2011-06-01)