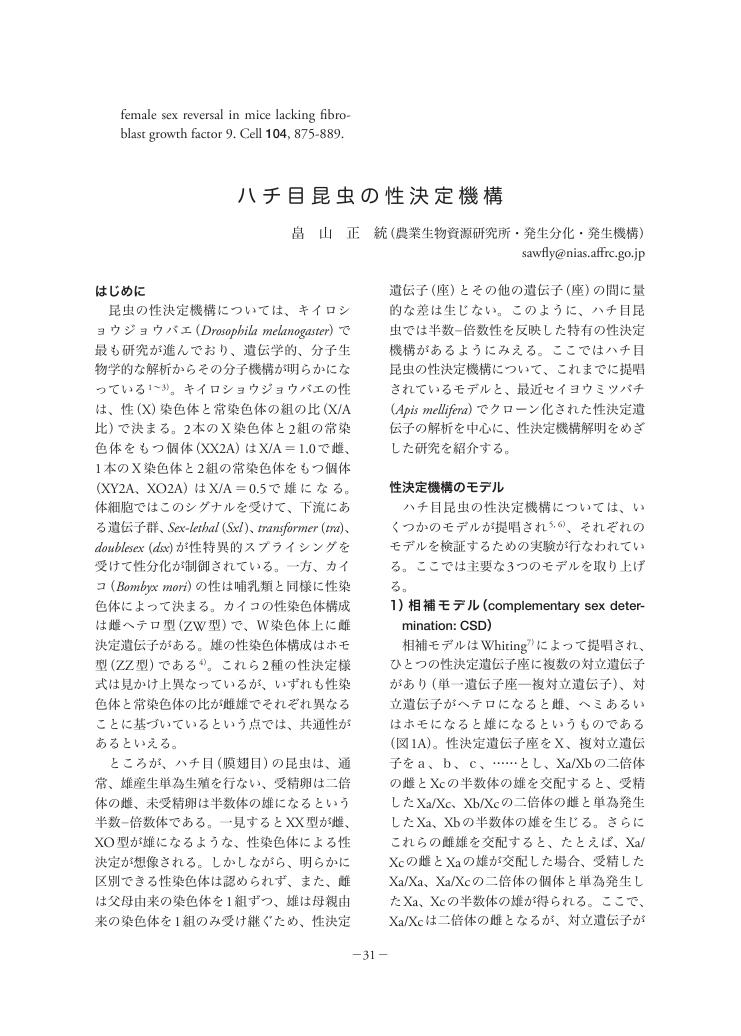6 0 0 0 IR 性同一性障害の概念について
- 著者
- 康 純
- 出版者
- 近畿大学臨床心理センター
- 雑誌
- 近畿大学臨床心理センター紀要 = Bulletin of Center for Clinical Psychology, Kinki University (ISSN:21868921)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.3-10, 2012
KOH, Jun[要旨] ギリシャ神話の「変身物語」や平安時代の「とりかえばや物語」に描かれているように、異なる性別で生きることを求める人は昔から存在していたと考えられる。 19世紀中頃から、解剖学的性やその性の役割に対し違和感を表現する人々に対し、医学的な枠組みの中で報告され始めた。しかし、1950年頃までは同性愛やフェティシズム、性同一性障害などが混同されていた。ハリー・ベンジャミンは身体的性とは反対の性であると確信している人々に対して性転換症(transsexualism)という用語を用い、ジョン・マネーらは性分化疾患の性意識を研究して、ジェンダー(gender)概念を提唱した。ここから解剖学的な性とジェンダー・アイデンティティとの不一致を性同一性障害という精神病理学的状態と位置づけるようになった。一方、自分の性に対する表現は自分の生き方の問題であるとして脱病理化を表現するトランスジェンダーという言葉で自らを表現する立場もある。このような状況の中、アメリカ精神神経学会や世界保健機関も診断基準の見直しを進めており、性同一性障害の概念は変遷していく課程にあると考えられる。
6 0 0 0 OA ハチ目昆虫の性決定機構
- 著者
- 畠山 正統
- 出版者
- 日本比較内分泌学会
- 雑誌
- 日本比較内分泌学会ニュース (ISSN:09139044)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.111, pp.111_31-111_38, 2003 (Released:2003-12-23)
- 参考文献数
- 42
6 0 0 0 平成28年熊本地震に伴う阿蘇地域の牧野被害と牧野組合の復旧対応
- 著者
- 冨田 大智
- 出版者
- 地理科学学会
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.4, pp.211-228, 2021-07-28 (Released:2021-07-28)
- 参考文献数
- 13
本稿では,平成28年熊本地震の発生に伴い,肉牛生産に利用される牧野においてどのような被害が発生し,それらの牧野を利用し維持・管理する牧野組合においてどのように復旧対応がなされたかということを,熊本県阿蘇郡旧長陽村及び旧白水村の11牧野組合を事例として明らかにした。牧野組合での被害内容は,肉牛生産に直結する牛の死亡等よりも,牧野における土砂崩壊や道路被害が大きく,各牧野組合で受け入れられた外部組織による補助事業費もそれらに関するものが主であった。土砂崩壊や道路被害が大きくなると,補助事業費も大きくなる牧野組合がみられる一方で,被害が小さいにもかかわらず補助事業費が大きい牧野組合や,被害が大きいにもかかわらず補助事業費が小さい牧野組合もみられた。背景には,各牧野組合の牧野の維持・管理作業の在り方の違いがあると考えられる。前者の牧野組合では,近隣地区での野焼き事故の発生により,地震発生以前から野焼きが実施されていなかった。ただし,条件が整い次第野焼きを再開する意向が示されており,行政による復旧支援も充実したと考えられる。後者の牧野組合では,地震以前から牧野の維持・管理作業が実施しやすいように独自に恒久防火帯を整備していた場合と,放牧地に対して牛の放牧頭数が多いことから野焼きによる牧野の維持・管理を必要としないと考えられていた場合とがあり,復旧支援も抑えられたと考えられる。
6 0 0 0 OA 中学校・高等学校の制服に関する研究 (第2報)
- 著者
- 三井 紀子 酒井 豊子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.6, pp.391-398, 1984-06-20 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 2
Through the questionnaire survey reported in Part 1, followings have become clear about boys' uniforms.1. School uniforms of close buttoned jacket type are very popular for boys, and blazer or business suit type come second.2. Most of the close buttoned jackets are black, and blazers or business suits are dark blue.3. The proportion of blazers or business suits to close buttoned jackets has increased with the years.4. Various wool/polyester blended fabrics are used for boys' uniforms more than for girls' uniforms, especially in summer.5. Regulations of private and national boys' schools are less rigid than those of private and national girls' schools.For 83 % of the schools which prescribe their uniforms, teachers affirm the prescription of uniforms. For 30 % of the schools which have no uniform, teachers feel the necessity of uniforms. These suggest that most teachers expect some educational effects of school uniforms.
6 0 0 0 OA 韓国のギャンブル依存症対策
- 著者
- 藤原夏人
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- no.269, 2016-09
- 著者
- Hayato Tada Hirofumi Okada Atsushi Nohara Masakazu Yamagishi Masayuki Takamura Masa-aki Kawashiri
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.11, pp.2073-2078, 2021-10-25 (Released:2021-10-25)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1 24
Background:Recent studies suggest that cumulative exposure to low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) leads to the development of atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD). However, few studies have investigated whether this link extends to individuals with familial hypercholesterolemia (FH), a relevant patient population.Methods and Results:We retrospectively investigated the health records of 1,050 patients with clinical FH diagnosis between April 1990 and March 2019. We used Cox proportional hazards models adjusted for established ASCVD risk factors to assess the association between cholesterol-year-score and major adverse cardiovascular events (MACEs), including death from any cause or hospitalization due to ASCVD events. Cholesterol-year-score was calculated as LDL-C max × [age at diagnosis/statin initiation] + LDL-C at inclusion × [age at inclusion − age at diagnosis/statin initiation]. The median follow-up period for MACE evaluation was 12.3 (interquartile range, 9.1–17.5) years, and 177 patients experienced MACEs during the observation period. Cholesterol-year-score was significantly associated with MACEs (hazard ratio, 1.35; 95% confidence interval, 1.07–1.53; P=0.0034, per 1,000 mg-year/dL), independent of other traditional risk factors including age and LDL-C, based on cross-sectional assessment. Cholesterol-year-score improved the discrimination ability of other traditional risk factors for ASCVD events (C-index, 0.901 vs. 0.889; P=0.00473).Conclusions:Cumulative LDL-C exposure was strongly associated with MACEs in Japanese patients with FH, warranting early diagnosis and treatment initiation in these patients.
6 0 0 0 OA 短信
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 291-1), 2022-03
6 0 0 0 IR <基地文化>とポピュラー音楽 : 横浜・横須賀をフィールドとして
- 著者
- 塚田 修一
- 出版者
- 三田社会学会
- 雑誌
- 三田社会学 (ISSN:13491458)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.80-93, 2014-07
1. 目的と方法2. <基地文化>の形成3. <基地文化>の逆用 : 宇崎竜童と山口百恵4. <基地文化>の希薄化と陳腐化5. <基地文化>の再帰的利用 : クレイジーケンバンド6. 結語論文
- 著者
- 酒井 元樹
- 出版者
- 東京国立博物館
- 雑誌
- 東京国立博物館紀要 = Proceedings of the Tokyo National Museum (ISSN:05638259)
- 巻号頁・発行日
- no.56, pp.139,141-381,383, 2020
6 0 0 0 OA 特異摂動理論から見た量子開放系の摂動的手法
6 0 0 0 OA 取り戻すこと:フェミニスト・スピリチュアリティにおける癒し
- 著者
- 小松 加代子
- 出版者
- 多摩大学グローバルスタディーズ学部グローバルスタディーズ学科
- 雑誌
- 紀要 = Bulletin (ISSN:18838480)
- 巻号頁・発行日
- vol.No.5, pp.43-54, 2013-03-01
フェミニスト・スピリチュアリティとは1960 年代に始まった女性たちの宗教を求める運動である。このフェミニスト・スピリチュアリティの運動の核心にあるReclaim(取り戻す)という言葉に注目し、神学者で哲学者のメアリ・デイリー(Mary Daly)と、魔女として幅広い活動をしているスターホーク(Starhawk)を取り上げる。フェミニスト・スピリチュアリティは歪められた物語の中から力を「取り戻し」、不完全な宗教的伝統を創りなおし、完全なものへと近づけることを目指しており、それは聖なるものを癒すことにもなるだろう。“Feminist Spirituality” is part of the women’s movement that aims to create a religion based on feminist values. In this paper, the meaning of this movement’s the core-term “to reclaim” will be discussed with reference to Mary Daly, a theologian and philosopher, and Starhawk, a witch and activist. “Feminist Spirituality” has been trying to reclaim power from distorted religious myths and recreate incomplete religious traditions and heal the divine.
6 0 0 0 IR ドゥルーズと法/『マゾッホ紹介』を読む
- 著者
- 志紀島 啓 Kei SHIKISHIMA
- 雑誌
- 芸術工学2017
- 巻号頁・発行日
- 2017-11-25
哲学者ジル・ドゥルーズは『アンチ・オイディプス』において、自身の思想を体現する形象として「スキゾ」の概念を打ち出した。それに先立つ『マゾッホ紹介』(以下ではPSMと略す)ではサディズムと対比しながら、マゾヒズムの論理が語られている。 PSMにおいてサディズムとマゾヒズムは、単に加虐・被虐を好む性的倒錯を指しているのではなく、法規範に対する異った二つの脱構築的態度として記述されているのである。そこでマゾヒズムという概念はのちの「スキゾ」の原形であると考えられる。PSMではドゥルーズの法規範に対する基本的な考え方が述べられている。ならばPSMを読解することによってドゥルーズの(反)法哲学を明らかにすることができるだろう。 本論ではドゥルーズが「マゾヒズム」と呼ぶ概念が(スキゾフレニーではなく)自閉症に近く、「サディズム」と呼ぶ概念がスキゾフレニーに近いことを示す。さらに法哲学の書としてPSMを読解する以上当然であるが、マゾヒズムの政治について批判的に考察する。 Gilles Deleuze, a philosopher proposed the concept of "Schizo" as a figure that embodies his own thought in "Anti-Oedipus". On the other hand, he explained his theory of Masochism in contrast to Sadism in "Presentation of Sacher-Masoch " (hereinafter referred to as "PSM") that had been published prior to "Anti-Oedipus". In PSM, Deleuze described Sadism and Masochism not only as perverted sexuality seeking for behaviors to hurt someone or be hurt by someone else, but also as two deconstructive attitudes to the rule of law, i.e. the concept of Masochism is considered to be the prototype of "Schizo" that was introduced later. Also, Deleuze described his basic idea on the rule of law in PSM. Therefore, if we read PSM, we will be able to clarify Deleuze's (anti-) philosophy of law. In this manuscript, I will explain that the concept that is called "Masochism" by Deleuze is (not Schizophrenia, but) close to autism, while the concept called "Sadism" is close to Schizophrenia. Furthermore, I will critically comment on politics of Masochism since we read PSM as one of the books on philosophy of law.
6 0 0 0 OA 辞闘戦新根 : 2巻
6 0 0 0 OA ヤマノカミ:厳しい生息現状とその保全
- 著者
- 竹下 直彦 鬼倉 徳雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本魚類学会
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.202-205, 2011 (Released:2014-03-07)
- 参考文献数
- 26
6 0 0 0 OA 古代東アジアにおける政治的流動性と人流
- 著者
- 河内 春人
- 出版者
- 専修大学社会知性開発研究センター
- 雑誌
- 専修大学社会知性開発研究センター古代東ユーラシア研究センター年報
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.103-121, 2017-03
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
6 0 0 0 OA 天城勲 (元文部事務次官) オーラルヒストリー
- 雑誌
- C.0.E.オーラル・政策研究プロジェクト
- 巻号頁・発行日
- 2002-10
インタビュー対象者 : 天城 勲 (アマギ イサオ)
6 0 0 0 OA ニホンジカの誘引に適した餌の検討
- 著者
- 飯島 勇人 大地 純平
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.145-149, 2016 (Released:2017-02-07)
- 参考文献数
- 13
野生ニホンジカ(Cervus nippon)の誘引に適した餌を明らかにするために,山梨県森林総合研究所実験林内にアルファルファ(乾燥牧草),チモシー(乾燥牧草),ヘイキューブ(アルファルファを粉砕圧縮したもの),配合飼料を設置し,自動撮影カメラによって最初に摂食される餌の回数を,季節ごとに調査した.多項ロジットモデルによる解析の結果,季節を問わずアルファルファの摂食回数が最も多く,次いで配合飼料,ヘイキューブ,チモシーの順であった.チモシーは,摂食される回数が特に少なかった.また,配合飼料は他の動物が摂食することがあった.以上の結果から,野生ニホンジカの誘引にはアルファルファが適していると考えられた.
6 0 0 0 OA ダイヤの接続性を考慮した地域公共交通網の性能評価手法に関する研究
- 著者
- 長谷川 大輔 嚴 先鏞
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.532-538, 2021-10-25 (Released:2021-10-25)
- 参考文献数
- 13
少子高齢化やインフラ維持管理費用の増加に伴い,「コンパクト・プラス・ネットワーク」の構築が求められている.このような都市構造を支えるためには,住民の移動の利便性を考慮した効率的な公共交通ネットワーク形成が必要であり,現在の公共交通ネットワークの性能を住民の利便性の観点から評価することが不可欠である.しかし,多くの自治体で人口カバー率を中心にした公共交通利便性の評価や拠点計画が行われており,カバー率が同じであっても移動需要に対応した路線網とダイヤの接続性によって住民の利便性は大きく異なる.そこで本研究では,公共交通のダイヤの接続を考慮できる時空間ネットワークを構築し,住民の日常的な移動に対した自治体の公共交通ネットワークの性能を平均移動速度と移動時間割合から評価し,利便性向上のための改善方策を検討することを目的とする.第一に,平均移動速度は,路線形状が移動需要とどの程度マッチしているかを評価する.第二に,移動時間割合は,運行頻度と接続性によって発生する待ち時間による時間ロスを定量化する指標である.最後に,これらの二つの指標の組み合わせにより,住民の利便性向上のための改善方策を検討する.
6 0 0 0 IR 慶応二年政局における薩摩藩の動向―藩政改革と薩英関係の伸展
- 著者
- 町田 明広
- 雑誌
- 神田外語大学日本研究所 紀要 = The Bulletin of the Research Institute for Japanese Studies (ISSN:13403699)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.1-29, 2021-03-30