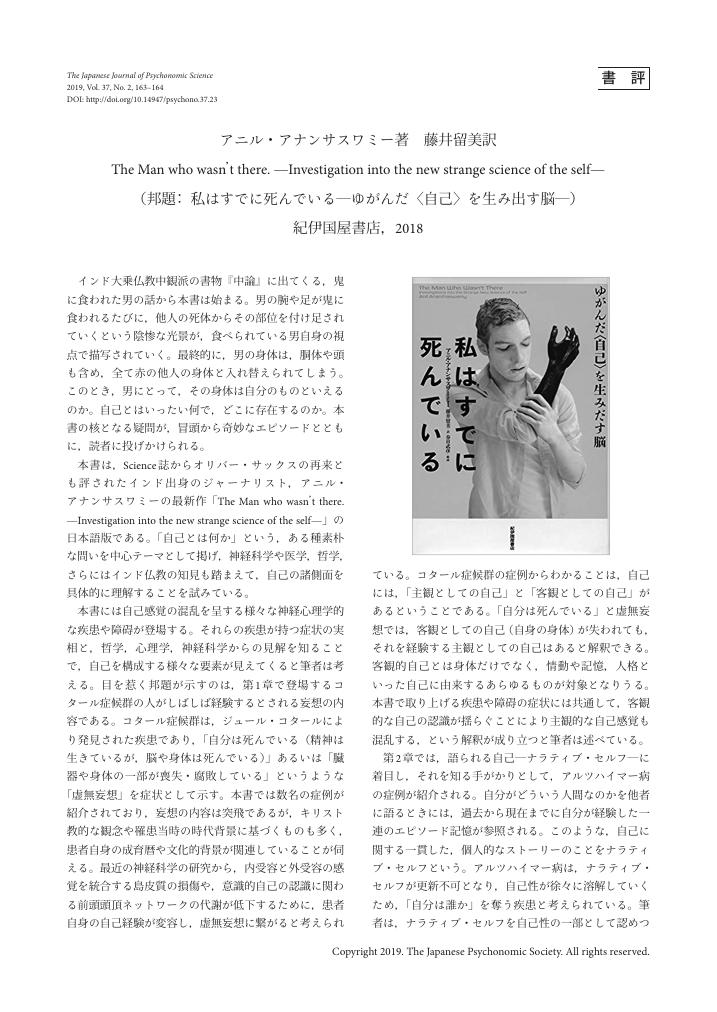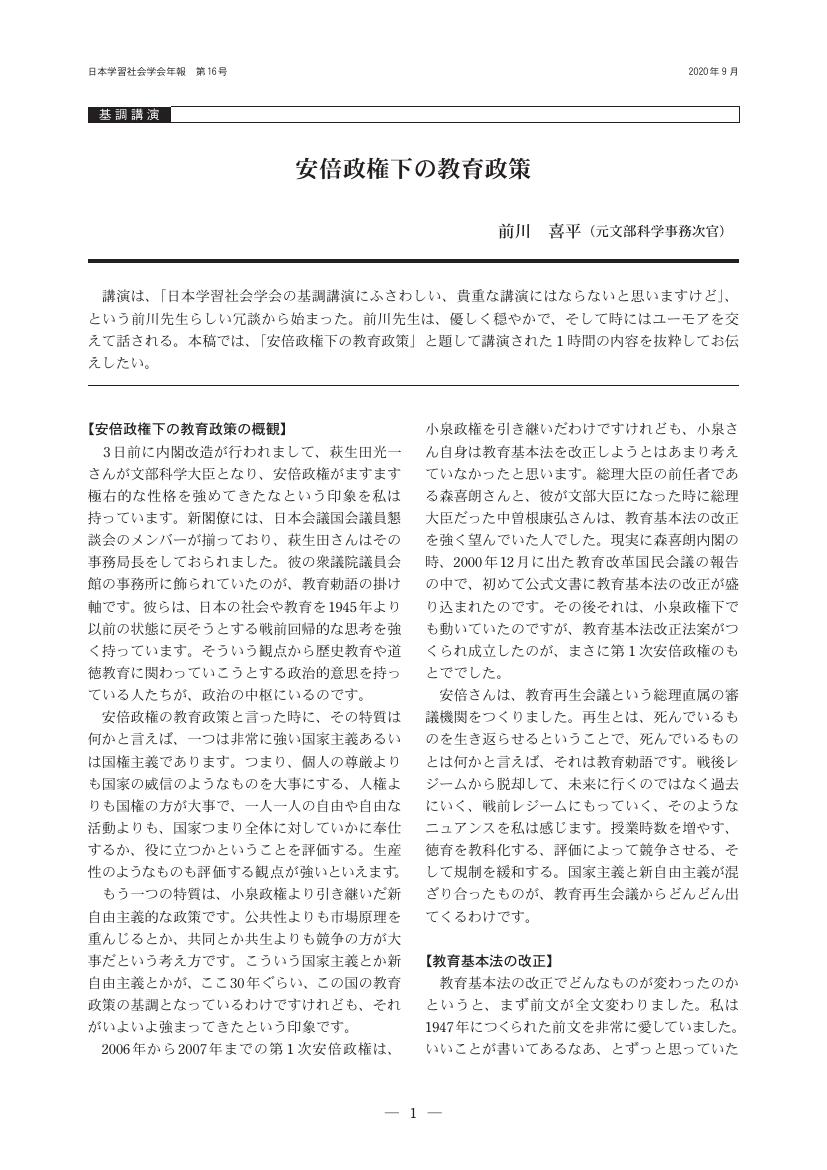- 著者
- 山本 佳生
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会関東支部
- 雑誌
- 日本フランス語フランス文学会関東支部論集 31 (ISSN:09194770)
- 巻号頁・発行日
- pp.53-68, 2022 (Released:2023-12-24)
2 0 0 0 OA 琉球国の「対欧米発給文書」の基礎的考察 残存形態、作成・発給、様式、発給主体に着目して
- 著者
- 小禄 隆司
- 出版者
- 琉球沖縄歴史学会
- 雑誌
- 琉球沖縄歴史 (ISSN:24351377)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1-18, 2021-08-31 (Released:2023-12-23)
- 著者
- 堤 香津雄 藍 譲二郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.1216, pp.10-12, 2020-03-05 (Released:2020-04-01)
2 0 0 0 OA 日本語と日本社会をめぐる言語政策・言語計画―言語政策から日本語教育を問う―
- 著者
- 伊東 祐郎
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.4-16, 2019-09-30 (Released:2019-09-30)
- 参考文献数
- 23
本稿は,日本の社会が外国人の受け入れに際して常に問題となる日本語教育についてこれまでにとってきた政策を概観し,日本語教育の捉え方,在り方等を考察するものである.最初に留学生の受け入れに関わる政策と日本語教育の発展に言及し,その後,入管法改正後に増加した生活者としての外国人に対する日本語教育の需要の拡大とその多様化を紹介する.グローバル化社会で求められる日本語とその教育は言語政策の視点からどのように位置づけられるべきか,また実現のためのビジョンはどのように描かれるべきかについて論じる.
- 著者
- Takanori Ohata Nozomi Niimi Yasuyuki Shiraishi Fumiko Nakatsu Ichiro Umemura Takashi Kohno Yuji Nagatomo Makoto Takei Tomohiko Ono Munehisa Sakamoto Shintaro Nakano Keiichi Fukuda Shun Kohsaka Tsutomu Yoshikawa
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-23-0356, (Released:2023-10-31)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1
Background: Despite recommendations from clinical practice guidelines to initiate and titrate guideline-directed medical therapy (GDMT) during their hospitalization, patients with acute heart failure (AHF) are frequently undertreated. In this study we aimed to clarify GDMT implementation and titration rates, as well as the long-term outcomes, in hospitalized AHF patients.Methods and Results: Among 3,164 consecutive hospitalized AHF patients included in a Japanese multicenter registry, 1,400 (44.2%) with ejection fraction ≤40% were analyzed. We assessed GDMT dosage (β-blockers, renin-angiotensin inhibitors, and mineralocorticoid-receptor antagonists) at admission and discharge, examined the contributing factors for up-titration, and evaluated associations between drug initiation/up-titration and 1-year post-discharge all-cause death and rehospitalization for HF via propensity score matching. The mean age of the patients was 71.5 years and 30.7% were female. Overall, 1,051 patients (75.0%) were deemed eligible for GDMT, based on their baseline vital signs, renal function, and electrolyte values. At discharge, only 180 patients (17.1%) received GDMT agents up-titrated to >50% of the maximum titrated dose. Up-titration was associated with a lower risk of 1-year clinical outcomes (adjusted hazard ratio: 0.58, 95% confidence interval: 0.35–0.96). Younger age and higher body mass index were significant predictors of drug up-titration.Conclusions: Significant evidence-practice gaps in the use and dose of GDMT remain. Considering the associated favorable outcomes, further efforts to improve its implementation seem crucial.
2 0 0 0 OA 進行性核上性麻痺患者の病棟内歩行自立に関連する因子の検討
- 著者
- 佐藤 佑太郎 太田 経介 松田 涼 濵田 恭子 髙松 泰行
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.76-83, 2023-06-20 (Released:2023-06-20)
- 参考文献数
- 46
【目的】進行性核上性麻痺患者の病棟内歩行の自立度と歩行機能,バランス機能,全般的な認知機能および前頭葉機能との関連性を検討し,抽出された項目のカットオフ値を算出することを目的とした。【方法】進行性核上性麻痺患者86名を対象とした。歩行機能,バランス機能,全般的な認知機能および前頭葉機能が病棟内歩行自立と関連するかを多重ロジスティック回帰分析で検討し,抽出された項目をreceiver operating characteristic curve(ROC)にてカットオフ値を算出した。【結果】歩行自立に対してバランス機能評価である,姿勢安定性テストとBerg Balance Scale(以下,BBS)が関連し(p<0.01),カットオフ値は姿勢安定性テストで2点,BBSで45点であった。【結論】進行性核上性麻痺患者における病棟内歩行自立可否には姿勢安定性テストやBBSの包括的なバランス機能が関連することが示唆された。
2 0 0 0 OA 領域展開の合成生物学
- 著者
- 橋本 講司
- 出版者
- 公益社団法人 日本生物工学会
- 雑誌
- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.8, pp.450, 2023-08-25 (Released:2023-08-25)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- 氏家 悠太
- 出版者
- 日本基礎心理学会
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.163-164, 2019-03-31 (Released:2019-05-18)
2 0 0 0 OA 大正期から昭和戦後期の大衆向け着物「銘仙」に関する考察
- 著者
- 柴 静子
- 出版者
- 日本家庭科教育学会
- 雑誌
- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集 第61回大会/2018年例会
- 巻号頁・発行日
- pp.10, 2018 (Released:2018-09-07)
【研究の背景および目的と方法】本年3月末に公示された新高等学校学習指導要領では、「政治や経済,社会の変化との関係に着目した我が国の文化の特色、我が国の先人の取組や知恵、武道に関する内容の充実、和食、和服及び和室など、日本の伝統的な生活文化の継承・創造に関する内容を充実したこと」が改訂の眼目とされている。発表者が平成26年度に行った広島県と山口県の高等学校の家庭科教師を対象とした調査では、その時点で既に95%の教師が、「家庭基礎」や「家庭総合」において,「衣食住の文化や様式について授業をしたことがある」と答えていた。それらは,浴衣の着装やたたみ方・帯の結び方の実習、外部講師による着付け講習、刺し子のコースターやランチョンマットの製作、日本の伝統文化である着物や風呂敷についての解説、備後絣や柳井縞についての解説、着物解き布のはぎれを使用した小物製作などであった。これらは生徒の興味を喚起する実践であるが、上記の指導要領改訂の際に考慮された、「先人の取組と知恵を知り、社会的・歴史的視点から衣生活文化を継承・発展させる」という視角から見ると、再考の余地があるように思われる。全国を見廻すと、かつて生糸や絹織物の名産地であった埼玉県秩父市や群馬県伊勢崎市においては、総合的な学習として「銘仙」を取り上げている小・中学校がいくつかある。伊勢崎市立境北中学校においては、「伊勢崎銘仙によるふるさと学習」が中学2年生の衣服分野と絡めて実践されている。平成 26年度は、家庭科の授業で、伊勢崎銘仙について専門的知識を有する外部講師を招き講話をしてもらったこと、および数多くの銘仙を準備し、実際に着用してよさを実感させたこと、さらには他地域のものと比較ができるように、多様な伊勢崎銘仙を展示するといった環境づくりをしたこと、その結果、生徒は感動し、興味関心は高まった、という報告がなされている。このように「銘仙」に焦点を合わせて、衣生活の伝統と文化に関する学習が実践されていることは、この着物への国内外からの注目が高まっている今日、意義深いことと考える。銘仙は、大正期から昭和戦後期にかけて、長期にわたり大衆向け着物として衣生活を支配した、歴史的・社会的に見て特別な意味をもつ着物である。そのように考えると、銘仙についての学習は、特定の地域に限定されるものではなく、着物の文化に関する学習として広く全国の学校に普及させる価値があると思われる。そこで本研究においては、銘仙の実物収集と考察、国内外の関連文献の検討およびはぎれ布を使用した教材見本の製作を通して、銘仙に焦点を当てた衣生活の伝統・文化の学習の創造に向けての基礎的資料を提供することを目的とした。【結果】1.銘仙の五大産地として、伊勢崎、秩父、足利、桐生、八王子が認められているが、これらに限定されず日本全国で生産されており、中には品質に相当問題があるようなものまで流通していた。2.1932年までの銘仙生産量は、伊勢崎が他の地域を圧倒していた。伊勢崎銘仙の特徴は「併用絣」にあり、他地域の銘仙に比べて色の鮮やかさで抜き出ている。伊勢崎銘仙には「馬首印(マーク)」や「正絹マーク」が付けられており、収集した着物や羽織、反物や洗い張りの中にも、このようなマークが見られるものがある。3.銘仙の大きな特徴は、アール・ヌーボーやアール・デコの影響を受けた、まるで絵画といってもよいデザインにある。ボストン美術館、ミネアポリス美術館などの海外の美術館には、相当数の銘仙が収蔵されているが、それらのデザインの多くはこの範疇に入る。4.近年、海外のコレクターが銘仙を収集し、写真・図を中心とした大型本を出版するなど、活発化している。色鮮やかで大胆な模様の伊勢崎銘仙(併用絣)が数多く取り上げられているが、収集した銘仙の中にも類似のデザインのものがある。5.本研究から、銘仙は、国際的、歴史的、社会的、文化的要素を入れて教材化することが可能であることが示唆された。
2 0 0 0 OA 放射性同位体標識化合物の合成
- 著者
- 長谷川 賢
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.116-126, 1967-02-01 (Released:2011-03-01)
- 参考文献数
- 74
2 0 0 0 OA 動いている庭と共生の技法
- 著者
- 山内 朋樹
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会関東支部
- 雑誌
- 日本フランス語フランス文学会関東支部論集 31 (ISSN:09194770)
- 巻号頁・発行日
- pp.3-12, 2022 (Released:2023-12-24)
2 0 0 0 OA 顔面神経麻痺の治療と後遺症への対応
- 著者
- 司会:村上 信五 欠畑 誠治 シンポジスト:萩森 伸一 濱田 昌史 羽藤 直人 東 貴弘 朝戸 裕貴
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.4, pp.416-421, 2019-04-20 (Released:2019-05-22)
2 0 0 0 OA 高電圧高周波環境における極小玉軸受の電食に関する研究
- 著者
- 野口 昭治 赤松 洋孝 福地 孝啓
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会学術講演会講演論文集 2006年度精密工学会秋季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.275-276, 2006 (Released:2007-03-04)
近年ではエアコン,無停電電源装置(UPS)等で電流制御のためにインバータ(可変電圧・可変周波数制御装置)が多く使われている.インバータの近くで使用されている冷却用ファン内の軸受に電食が発生する現象が多発している.インバータによる高周波ノイズによって微弱電流が発生してしまい,長期間に渡って軸受内に電流が流れることが原因とされている.電食に関する研究は、鉄道車両用軸受を対象に多く行われてきたが、小型玉軸受を対象とした研究はほとんどない。そこで本研究では、高周波電食が起こる原因を究明することを最終的な目的とし,高周波環境で軸受を回転させた場合の軸受特性を調べ、小型玉軸受693を対象に無通電高周波電食の基礎実験を行った。
2 0 0 0 OA アンプル入りかぜ薬事故の経過と措置(官公庁だより,交信)
- 著者
- 豊田 勤治
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.7, pp.273-275, 1965-07-15 (Released:2018-08-26)
2 0 0 0 OA 屠蘇酒の起源に関する考察
- 著者
- 毛利 千香 御影 雅幸
- 出版者
- 日本薬史学会
- 雑誌
- 薬史学雑誌 (ISSN:02852314)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.78-83, 2015 (Released:2020-12-03)
The original formulation for Tusujiu, which Japanese people still consume on the morning of January 1st, was created by Hua Tuo, but has not been studied in detail. The book Huatuo Shenyi Bizhuan, found in 1918, describes a concoction, Biyijiu, that shows great similarity to the current Tusujiu; the ingredients for Biyijiu being rhubarb, atractylodes rhizome, cinnamon bark, platycodon root, zanthoxylum fruit, processed aconite root and smilax rhizome. The procedures for preparing and drinking it are to pound the ingredients and then put them into a silk bag dyed with madder. During the daytime of the last day of the year, hang the bag in a well to soften the powder. Take the bag out early in the morning of the next day, the first day of the year. Heat the bag in fermented liquor until simmering. Drink the liquid with all family members, doing so while facing east. If one person drinks it, there will be no disease in the family. If the whole family drinks it, there will be no disease in their neighborhood in an area of one square li. In this study, to determine the original formulation for Tusujiu, we examined a number of ancient medical texts from the 3rd to the 13th century that discuss Biyijiu and Tusujiu. As a result, we concluded that Biyijiu is likely to be the original formulation developed by Hua Tuo. PMID: 26427101 [Indexed for MEDLINE]
2 0 0 0 OA The history and future of KAATSU Training
- 著者
- Y. Sato
- 出版者
- Japan Kaatsu Training Society
- 雑誌
- International Journal of KAATSU Training Research (ISSN:13494562)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.1-5, 2005 (Released:2008-07-18)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 72 85
KAATSU training involves the restriction of blood flow to exercising muscle and is the culmination of nearly 40 years of experimentation with the singular purpose of increasing muscle mass. KAATSU Training consists of performing low-intensity resistance training while a relatively light and flexible cuff is placed on the proximal part of one's lower or upper limbs, which provides appropriate superficial pressure. KAATSU Training should not be confused with training under ischemic conditions which has previously been reported (Sundberg, 1994). KAATSU Training does not induce ischemia within skeletal muscle, but rather promotes a state of blood pooling in the capillaries within the limb musculature. Applied basic and clinical research conducted over the past 10 years has demonstrated that KAATSU Training not only improves muscle mass and strength in healthy volunteers, but also benefits patients with cardiovascular and orthopedic conditions.
2 0 0 0 OA 糖尿病ラットにおける白内障の発症・進行過程とレスベラトロールの白内障予防効果
2 0 0 0 OA 安倍政権下の教育政策
- 著者
- 前川 喜平
- 出版者
- 日本学習社会学会
- 雑誌
- 日本学習社会学会年報 (ISSN:18820301)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.4-7, 2020 (Released:2023-04-01)
2 0 0 0 OA 運動の形成と資源動員論
- 著者
- 牟田 和恵
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.57-76,168, 1986-01-31 (Released:2017-02-15)
- 被引用文献数
- 1
First, I will make a brief survey of resource mobilization theory as it relates to the formation of social movements. Second I will discuss its main problematic point: because it tends to portray social movements as rational and non-emotional, resource mobilization theory reduces social movements to a form of collective action in which people act together organically in pursuit of their common interests. In my mind there is little doubt that social movements encompass larger and more dynamic concepts than those contained in collective action. Based on the work of the Italian sociologist, F. Alberoni, I introduce another theory of social movements. He defines a movement as a historical process which starts with the nacent state and ends with the re-establishment of the everyday institutionalized order within which social movements exist as the opposite of institutions. For Alberoni, movements can exist only as a temporary state. As a theory of social movements his opinion might be regaded as almost heretical. But I believe that his theory offers useful suggestions to supplement the theoretical weaknesses of the resource mobilization theory I described above. In short, by incorporating some parts of Alberoni's theory, this paper tries to develop resource mobilization theory and the theory of social movements in a wider perspective.
2 0 0 0 OA 内生的貨幣供給説への到達とその深化:吉田金融論の形成過程
- 著者
- 斉藤 美彦
- 出版者
- 大阪経大学会
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.1-20, 2023-07-15 (Released:2023-08-03)