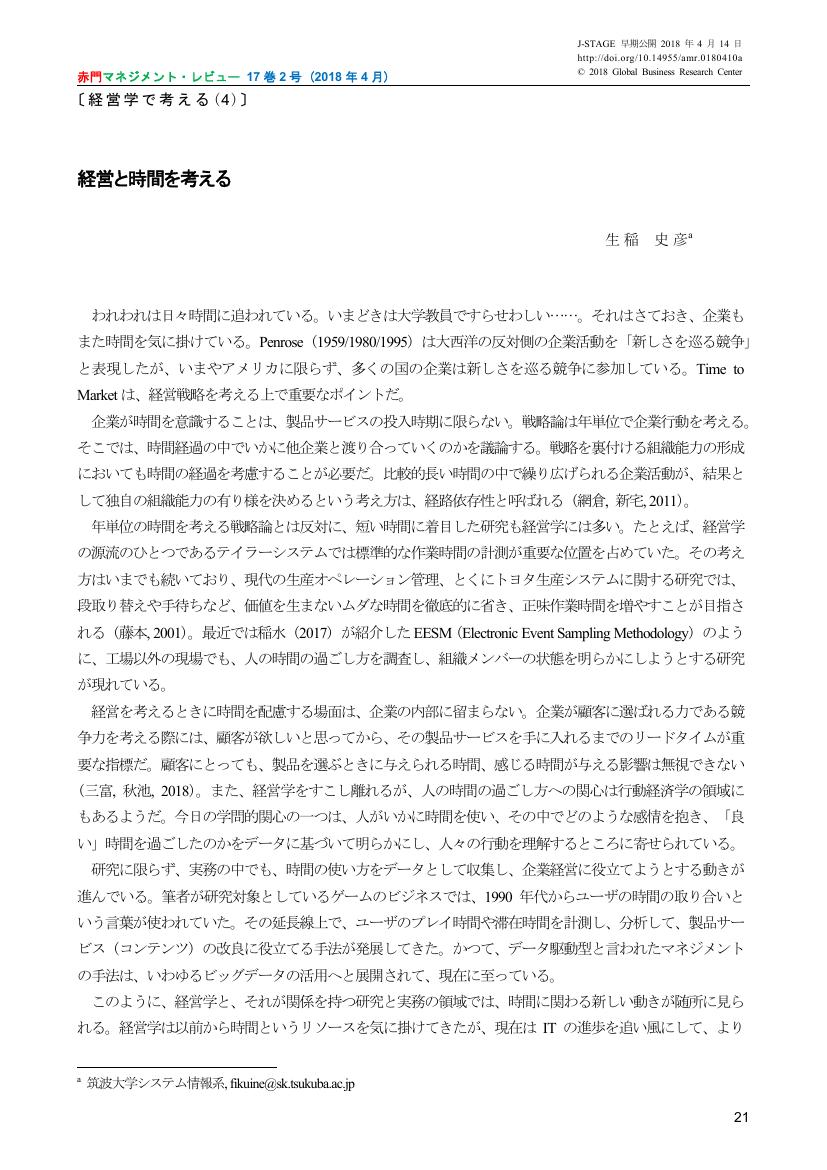1 0 0 0 OA タイヤ騒音の減少と対策
- 著者
- 上野 一海
- 出版者
- The Institute of Noise Control Engineering of Japan
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.82-86, 1982-04-01 (Released:2009-10-06)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 最大・最小位相分離によるディジタルフィルタの振幅・位相同時近似
- 著者
- 徳田 恵一 小林 隆夫 徳田 篤洋 今井 聖
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 A (ISSN:03736091)
- 巻号頁・発行日
- vol.J71-A, no.2, pp.260-267, 1988-02-25
任意の対数振幅・位相をもつ希望特性は,複素ケプストラムの性質を用いることにより,最大・最小位相成分に分離することができる.このとき,最大位相あるいは最小位相の対数振幅と位相は,ヒルベルト変換により一意に関係づけられるので,振幅と位相の同時近似問題は,最大および最小位相成分の振幅近似問題に置き換えられる.本論文では,最大位相成分を逆線形予測法により,最小位相成分を極零分離法により,それぞれ近似する方法について述べ,更に振幅あるいは位相のいずれかに着目して,最大・最小位相成分の近似を交互に繰り返すことにより,特性を改善する方法を提案している.本方法は,振幅あるいは位相のどちらかに厳しい近似特性が要求されたとき,特に有効となる.フィルタ係数の決定は,FFTおよび線形予測法に基づいているため,非線形最適化法に比べ高速である.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経アーキテクチュア (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.1087, pp.44-47, 2017-01-12
5カ年で改修を進める計画では、塗装や仕上げ材、防水処理の更新、各種設備の点検・整備を中心に、実施項目や実施スケジュールを明示。さらに、実施項目ごとの概算工事費も算出した。既に施工中の項目は、市が自ら設計している。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経アーキテクチュア (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.1052, pp.34-37, 2015-07-25
豊田スタジアムは01年に故黒川紀章氏の設計で完成した。鳥瞰すると固定屋根の上端にある2本のキールアーチを足場に、蛇腹状の開閉屋根が閉じる構造だと分かる。しかし、このキールアーチの形状がくせものだった。
1 0 0 0 平安末・鎌倉前期における唐宋画論の波及
- 著者
- 辻 惟雄
- 出版者
- 美術史學會
- 雑誌
- 美術史 (ISSN:0021907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.p57-67, 1986-01
- 著者
- 戸田 禎佑
- 出版者
- 東京国立博物館
- 雑誌
- 東京国立博物館研究誌 (ISSN:00274003)
- 巻号頁・発行日
- no.511, pp.p15-19, 1993-10
1 0 0 0 OA 経営と時間を考える
- 著者
- 生稲 史彦
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.21-24, 2018-04-25 (Released:2018-04-25)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 知識移転研究はどこまで来たか
- 著者
- 横澤 公道
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.25-46, 2018-04-25 (Released:2018-04-25)
- 参考文献数
- 69
本稿の目的は、 知識移転に関する論文の系譜を読み解くことにより、現在ある理論の空白を明らかにしたうえで今後の研究課題を提示することである。まずは知識移転としての経営システム移転論の発展経路を分析し、その後、特に戦略論をベースとする知識移転論に焦点を当て、その中でどのような課題が残されているのか調査した。その結果、知識移転論の大きな課題のひとつとして単一組織対単一組織の知識移転ではなく組織のコミュニティに対する研究とその優位性に関する研究が少ないことを明らかになった。コミュニティへの知識移転は、組織同士の境界線が比較的顕著になることからメンバー同士の制度、文化、力関係などの相互作用が顕著になり、知識移転の複雑化が見込まれる。しかし、移転の過程において、メンバー間において自主的に学習する制度を作ることで、独立した企業へ行うよりも、財閥、系列企業から作ったコミュニティを利用して移転したほうが知識の移転度が高い可能性があることを議論する。
1 0 0 0 OA デザインは市場成果をもたらすのか?
- 著者
- 原 寛和 立本 博文
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.47-106, 2018-04-25 (Released:2018-04-25)
- 参考文献数
- 85
製品デザインが市場成果に与える影響について、(i)企業レベル(ii)製品レベル(iii)デザイン組織レベルに分類して実証研究のレビューを行なった。いずれの研究も、製品デザインが市場成果にプラスの影響を与えることを支持している。ただし、そのメカニズムは単純ではなく、変数間の媒介効果や交互作用効果を多く含んでいる。これら既存研究のレビューを踏まえ、今後の研究として、(1)戦略的文脈の影響を考慮した研究 (2)消費者の反応を取り込んだデザインプロセスの研究 (3)デザインマネジメントの組織メカニズムの研究が必要であることを報告する。
1 0 0 0 OA [豊田天功書簡]
- 著者
- [豊田天功] [著]
- 巻号頁・発行日
- vol.[32], 1800
1 0 0 0 OA 神奈川県警察における写真測量の活用について
- 著者
- 魚谷 増男 山口 正博 後藤 保雄 宮坂 俊雄 矢野 和良
- 出版者
- Japan Society of Photogrammetry and Remote Sensing
- 雑誌
- 写真測量とリモートセンシング (ISSN:02855844)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.24-32, 1978-08-15 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 3
A diagram has been annexed to the spot inspection record of the traffic accident or incident were drawn up with measuring-tape heretofore. We introduced the method applied with photogrammetry partially into the police since 1969. Sixteen (16) of the stereo-camera (base length-120 centimeter) were provided and came into use for the investigation of traffic accident and incident at present. These methods have produced some good effects on speedy spot investigation, quick settlement of traffic stagnation along with specialization and efficient investigation and prevention of traffic policemen from traffic accident. These stereo-cameras are utilized in another field actively in order to use them efficiently.Take some sample of our practical use of them, these instrument are utilized for investigation of the road structure at the intersection of traffic accident frequency or scheme of road improvement in order to root out of traffic accident. Furthermore, they are employed in the inspection of the ultimate causes of accidents due to the road administration. Inspect the desruction of the“motorcar to motorcar”accident and make out the identification materials to study the cause of accident. Write out the study documents of the cause of“roll-up”accident by the large-sized vehicles to study of the prevention measures of such accident. These instruments produced much good effects on calculation of area and volume required by the nature of the criminal cases. In recent years, the stereo-camera (base length-20 centimeter) had been developed. It is expected that it will be utilized to make correct dianognosis a part of casualty (sufferer) .A system with stereo-cameras as axis (main-instrument) produced low cost, simple operation, almost unnecessary for control point surveying and less influence of the weather as compared with the aerial photogrammetry. As the stereo-camera has like this advantages, it is presumed that there is enough room to be utilized widely in the public.It is ten (10) years since the police had introduced the photogrammetry, we believed that we should make every efforts to extend practical use of the instrument.
- 著者
- 松本 直也 出村 慎一 松浦 義昌 内田 雄 長澤 吉則
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.192_1-192_1, 2017
<p> サッカー選手は、相手選手の巧みな動きに対する反応が遅れると、すぐに攻守が入れ替わるため、優れた敏捷能力が不可欠である。本研究は連続選択反応テスト(Tsubouchi et al. 2016)を利用し、大学サッカー選手の敏捷性のポジション間差を検討する。連続選択反応テストは連続的且つランダムに提示される方向指示に従って8方向の移動を繰り返すテストである。方向指示刺激は5パターン用意されており、被験者は全てのパターンを実施する。最大最小を除いた3パターンの動作時間の平均を評価変数とした。本研究では、関西学生サッカーリーグ1部校のM大学サッカー部員116名を被験者とし、連続選択反応テストを2試行(計10パターン分)実施した。試行間信頼性を検証するために級内相関係数(ICC)を算出した。また、対応のない1要因分散分により動作時間を4ポジション(ゴールキーパー13名、ディフェダー40名、ミッドフィールダー43名、フォワード20名)間で比較した。解析の結果、高いICC(0.815)が認められ、ポジション間の比較ではいずれも有意差は認められなかった。以上より、サッカー選手はポジション違いに関係なく敏捷性に差はない。</p>
1 0 0 0 OA 近畿地方の新期新生代層の研究 I.
- 著者
- 深草団体研究会
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科学 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.1962, no.63, pp.1-9, 1962-11-30 (Released:2017-07-24)
The loose sediments at Fukakusa, southeast Kyoto, are recognized to be the Osaka Group by discovering the Azuki-Tuff and the Pink-Tuff. The Osaka Group at this area consists of gravels, sands, silts and clays. In this group 8 cycles exist and the upper four cycles have four marine clays and the lower four cycles have non-marine clays. It is 130 m in thickness and is marginal sediments in the Kyoto Basin. The marine molluscan fossils occur mainly from the seventh cycle and the plant fossils from the first and the fourth cycles. The Kuragatani Formation and the Momoyama Gravel, unconformably overlie the Osaka Group and they may correspond to the Manchidani Formation and the Meimi Gravel (the higher terrace deposits) respectively.
- 著者
- 杉岡 良彦
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.4, pp.1220-1221, 2010-03-30 (Released:2017-07-14)
- 著者
- 清水 裕子 川崎 圭造 伊藤 精晤
- 出版者
- 社団法人日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.5, pp.517-520, 2003-03-31
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2 2
Expectations have been placed on scenic thinning in recent years in recovering the environmental conservation function and promoting recreational purposes of the increasing uncontrolled artificial forest stands. Although there have been recent reports on scenic thinning, there are very few examples of implementation. This study was conducted for the purpose of examining the possibilities of scenic thinning by investigating its impact on the place where Ito et al practiced it within the Shinshu University in 1992. We conducted the study by complete enumeration and vegetation survey of the tree and bush layers against the forest where scenic and ordinary thinning were carried out stand (scenic and ordinary thinning areas) and made a comparative review. As a result, there were no significant disparities of tree layers between both areas and no difference were found in the growth, which was expected in the scenic thinning area. However, with the bush layer, the average height of bush layer of arboreal vegetations was significantly taller with the scenic thinning and the differences in the distribution of tree height were great as well. This suggests that woodlands managed by scenic thinning can be lead effectively to multiple layered forest stands in comparison to ordinary thinning and indicates the forest's stability and the possibility of natural scenic cultivation.
1 0 0 0 OA 物理分析としての質量分析とガスクロマトグラフィ
- 著者
- 佐々木 申二
- 出版者
- The Mass Spectrometry Society of Japan
- 雑誌
- Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan (ISSN:13408097)
- 巻号頁・発行日
- vol.1959, no.12, pp.3-3, 1959-03-31 (Released:2010-06-28)
- 著者
- 和田 雄次
- 出版者
- 社団法人日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- no.56, 2005-11-01