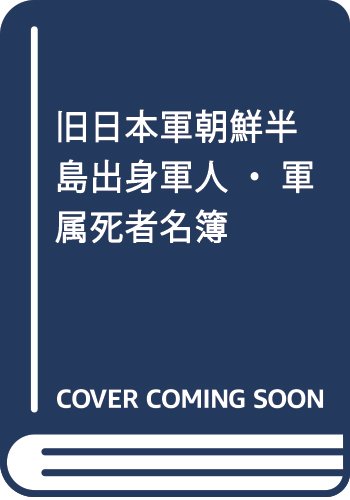1 0 0 0 OA KS-10 AIに関わる安全保障技術をめぐる世界の潮流
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 2018年度人工知能学会全国大会(第32回)
- 巻号頁・発行日
- 2018-04-12
AIと安全保障技術を巡り,世界中で議論が注目されています.国連ではLAWS(自律型致死兵器)の開発・使用の規制に向けた議論が昨年から本格的に始まりました.安全保障技術をめぐる世界の潮流を理解するため,拓殖大学国際学部教授・海外事情研究所副所長佐藤丙午氏とLAWSの規制に関する国連の会議を担当されている外務省軍縮不拡散・科学部通常兵器室上席専門官の南健太郎氏をお招きして,お話を伺います.http://ai-elsi.org/archives/707
1 0 0 0 OA IEEE「倫理的に調和した設計」を用いた議論の場とコミュニティの設計
- 著者
- 江間 有沙 長倉 克枝 工藤 郁子
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 2018年度人工知能学会全国大会(第32回)
- 巻号頁・発行日
- 2018-04-12
技術の設計段階からその倫理的,法的,社会的な観点について考えていくためには,技術者にとっても倫理や価値の議論が自分事として考えられるような場や環境づくりが重要となる.そのため,技術に関する倫理や価値の「中身」の議論だけではなく,多様な人々を巻き込むという「プロセス」や,コミュニティ形成の方法についても実践と記録を残していくことが,重要である.筆者らは,これまでも「人工知能と社会について考える場作り」として,様々な分野・業種の専門家を対象とした企画を行ってきた.本稿では,IEEEが公開している報告書に関するワークショップを事例として,どのように異分野・異業種の専門家による企画を組織,運営しているかを紹介する.
1 0 0 0 IR EPMAによる火山ガラス組成分析 : Na損失の検証と分析条件の提案
- 著者
- 松本 亜希子 宮坂 瑞穂 中川 光弘
- 出版者
- 北海道大学大学院理学研究院
- 雑誌
- 北海道大学地球物理学研究報告 (ISSN:04393503)
- 巻号頁・発行日
- no.78, pp.1-9, 2015-03
We examined the analysis method of the compositions of volcanic glass using WDS-EPMA, focusing on Na migration caused by electron-beam bombardment. As a result of the comparison among the beam current in 10 μm square area, it is concluded that Na migration occurs in any cases at 15 kV. During the first 30 seconds, Na decay is not observed, and therefore, the detection of Na must be finished within the first 30 seconds. Considering the variations of other elements, the 15 kV accelerating voltage and 7 nA beam current with raster scanning of 10 μm square area is the best condition for the determination of volcanic glass compositions. This can prevent "grow-in" of Si and Al, as well as can make smaller the deviations of the minor elements. Using this condition, we can discuss the variations of volcanic glass compositions (except for Na) without any corrections.
1 0 0 0 OA 国立公文書館長業務引継帳余録
- 著者
- 高山 正也
- 出版者
- 記録管理学会
- 雑誌
- レコード・マネジメント (ISSN:09154787)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.4-11, 2014-03-15 (Released:2017-03-24)
著者は2006年4月から理事として、2009年7月から館長として勤めていた(独)国立公文書館を2013年5月で、退職した。国立公文書館在職中に課せられた主な使命は、主要諸外国に比較し、異常に小規模で低水準の国立公文書館の水準を向上させるべく、関連法令の制定、施行に始まり、末端行政組織と化した国立公文書館の活性化とそれを公文書館本来のアーカイブズ専門業務担当組織に変質させることにあった。しかし、長い伝統の下で硬直化した公文書館のような公的な組織の変革は著者のごとき理屈だけを、公文書館同様日陰の存在になっている図書館を対象とした経験しかない者の手には余るものであった。その様子が法律の制定、公文書館業務の実態等を経営の要素としての、ヒト、カネ、資料等の扱いといった具体例に触れて記述される。結局、日本における国際標準から外れた公文書類の扱いは公的組織の奥深くまで浸透しており、今後息の長い取り組みが必要との結論が述べられる。
1 0 0 0 IR 1989年ロマ・プリータ地震の震度分布
- 著者
- Abeki Norio Enomoto Takahisa Murakami Hitomi Mochizuki Toshio
- 出版者
- 東京都立大学都市研究センター
- 雑誌
- 総合都市研究 (ISSN:03863506)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.5-24, 1991-12
1989年10月17日午後5時4分(現地時間)に発生したロマ・プリータ地震(M7.1)は、サンフランシスコの南東約110kmのサンアンドレアス断層上を震度として発生した。断層の長さは約40kmで、震度の深さ約18kmとされ、断層上で右横ずれ1.7m, 縦ずれ1.3mの断層運動が確認された。震度近傍地域の市街地の建築構造物の被害はもとより、震源より約100km程度離れた近代的な都市であるサンフランシスコ市やオークランド市において海岸部の埋立地を中心に大きな被害が発生し、特にベイブリッジや高架橋構造の高速道路の崩壊による多くの死傷者やライフライン系の被害など典型的な都市型の被害が生じた市民生活に大きな影響を及ぼした。この地震による人的被害は死者62人、負傷者約3800人であった。また、倒壊建物を含む被災建物数は約3万棟で被害総額は約59億ドルと報告されている。本地震の震度分布は震源近傍の地域において修正メルカリ震度階で震度8(気象庁震度階6程度)、サンフランスコ市やオークランド市においては同震度7(同5程度)であるが、同地域内において局所的に同震度9(同7程度)の大きな震度分布を示す地域があり、大被害地域となっている。一方、地震動の強震計観測記録はUSGS(米国地質調査所)とCDMG(カリフォルニア鉱山局)が設置した観測網により多数の地点で貴重な記録が観測されている。震源近傍の地域では、地盤上の水平動成分の最大加速度値が0.64g(Corralitos)、0.54g(Capitola) と大きな値を示し、上下動成分も0.5~0.6g の値を記録している。またオークランド市周辺地域で0.26g(Emeryville)、サンフランシスコ市周辺で0.24g(Golden Gate Bridge)、0.33g(San Francisco Intl. Airport) と報告されている。しかしながら、これらの資料だけからではサンフランシスコ市やオークランド市の市内における地域的に細かな震度分布を評価することは難しい。米国では、USGSが中心となって、地震の多発するカリフォルニア州のサンフンドレアズ断層に沿う地域、特にサンフランスシコ湾岸地域を対象として、同断層および平行して走るヘイワード断層上に発生する大地震を想定した震度分布予測のためのゾーニングマップが作成されている。これは、地震断層・地質地形・地盤などを考慮して作成されたものであり、特に今回のロマ・プリータ地震でのサンフランシスコ市やオークランド市における被害発生地域は、上記のゾーニングマップにおいて、震度が相対的に高いと予測されていた地域と符合しているように思われる。本報告では、特に大都市であるサンフランシスコ市においてサイスミックマイクロゾーニングの観点から、アンケートによるミクロな震度分布調査を行い、すでにUSGSにおいて作成されている既往の地盤分類に基づいたマイクロゾーニングマップとの対応について検討を行った。その結果、サンフランシスコ市におけるUSGS による震度分布は、一部の大被害発生地域の震度を除いてMM 震度で7~6 程度であったのに対して、地域的に詳しい震度分布のコンターが得られ、表層地盤の性質に対応していることが明かとなった。
1 0 0 0 旧日本軍朝鮮半島出身軍人・軍属死者名簿
- 著者
- Makoto T Hayashi
- 出版者
- The Genetics Society of Japan
- 雑誌
- Genes & Genetic Systems (ISSN:13417568)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.3, pp.107-118, 2017-06-01 (Released:2018-01-20)
- 参考文献数
- 132
- 被引用文献数
- 15
The ends of eukaryotic linear chromosomes are protected from undesired enzymatic activities by a nucleoprotein complex called the telomere. Expanding evidence indicates that telomeres have central functions in human aging and tumorigenesis. While it is undoubtedly important to follow current advances in telomere biology, it is also fruitful to be well informed in seminal historical studies for a comprehensive understanding of telomere biology, and for the anticipation of future directions. With this in mind, I here summarize the early history of telomere biology and current advances in the field, mostly focusing on mammalian studies relevant to aging and cancer.
- 著者
- 井上 裕嗣 岸本 喜久雄 中西 智明 渋谷 壽一
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 A編 (ISSN:03875008)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.581, pp.153-160, 1995-01-25 (Released:2008-02-21)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 5 6
The wavelet transform is applied to time-frequency analysis of dispersive stress waves. The Gabor function is adopted as the analyzing wavelet. The magnitude of the wavelet transform of wave data takes its maximum value at the time when the stress wave reaches the observation point with its group velocity at each frequency. An experiment on the flexural wave in a beam shows that the dispersion relation for the group velocity can be accurately identified by the wavelet transform of measured data. In addition, the application of the wavelet transform to ultrasonic testing of a polymer alloy shows that changes in velocity and attenuation coefficient due to mechanical damaging can be evaluated at each frequency. These results suggests that the wavelet transform has potential ability to present more detailed evaluation of material damages.
1 0 0 0 OA ニクソン・キッシンジャー外交の研究動向 ──対中和解、三角外交の解釈を中心に──
- 著者
- 佐橋 亮 Ryo Sahashi
- 雑誌
- 国際基督教大学学報. II-B, 社会科学ジャーナル = The Journal of Social Science
- 巻号頁・発行日
- no.59, pp.71-101, 2006-09-30
- 著者
- 中崎 隆司
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経アーキテクチュア (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.849, pp.76-81, 2007-05-28
熊本空港に近い丘陵地に建つ新本社である。熊本市内の旧本社が手狭になったため、今年1月に移転した。 1997年から再春館製薬所の施設をプロデュースしてきた北山創造研究所(東京都港区)が総合プロデュースを担当した。
- 著者
- 岡野 雄一 宇佐 康江 安部 修明
- 出版者
- 日本航空医療学会
- 雑誌
- 日本航空医療学会雑誌 = Journal of Japanese Society for Aeromedical Services (ISSN:1346129X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.28-31, 2015-08
1 0 0 0 Characteristics of Uptake of Cefroxadine by Rabbit Small Intestinal Brush Border Membrane Vesicles
- 著者
- KITAGAWA Shuji SUGAYA Yoshio
- 出版者
- 公益社団法人日本薬学会
- 雑誌
- Biological & pharmaceutical bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.268-273, 1996-02-15
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 4 1
Characteristics of transport of an oral aminocephalosporin, cefroxadine, in rabbit small intestinal brush border membrane vesicles were examined. Uptake rate of cefroxadine was saturable in the presence of an inward H<SUP>+</SUP> gradient, and kinetic parameters were similar to those of cephradine. However, the uptake rate was almost linear with the concentration in the absence of an inward H<SUP>+</SUP> gradient up to 5mM. Overshoot phenomenon was observed in the presence of an inward H<SUP>+</SUP> gradient at 37°C, but it disappeared with decrease of temperature. The Arrhenius plot of uptake rate constant showed a break point at approximately 30°C. Cefroxadine uptake was optimum in the vicinity of pH 5.5 at 37°C, but the dependence on extravesicular pH disappeared at 15°C. The uptake of cefroxadine in the presence of an inward H<SUP>+</SUP> gradient was markedly inhibited by other aminocephalosporins such as cephalexin, but the inhibition was only slight in the absence of an inward H<SUP>+</SUP> gradient. Alkyl alcohols such as n-hexyl alcohol also inhibited H<SUP>+</SUP>-coupled uptake of cefroxadine at the concentration range at which the alcohols increased the membrane fluidity, and overshoot phenomenon diminished, suggesting that H<SUP>+</SUP>-coupled transport of cefroxadine is sensitive to the alcohol-induced increase in membrane fluidity. On the other hand, the alcohols rather stimulated its uptake in the absence of an H<SUP>+</SUP> gradient.
1 0 0 0 脳海馬で合成される男性・女性ホルモンは記憶力を増強する
- 著者
- 川戸 佳
- 出版者
- 日本生化学会
- 雑誌
- 生化学 (ISSN:00371017)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.3, pp.342-353, 2016-06
- 著者
- 鳥羽 三佳代 森脇 睦子 尾林 聡 伏見 清秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療・病院管理学会
- 雑誌
- 日本医療・病院管理学会誌 (ISSN:1882594X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.215-222, 2017 (Released:2018-04-13)
- 参考文献数
- 25
【緒言】パクリタキセル・カルボプラチン療法(TC療法)薬剤を後発医薬品に変更したところ,婦人科外来化学療法症例において血管外漏出事例が増加し,先発薬への再変更により有害事象が減少した事例を経験したので報告する。【方法】2013年1月~2016年12月に外来TC療法を実施した婦人科症例を対象として診療録の後方視的調査を実施した(第1次先発医薬期:238件,後発薬期:141件,第2次先発薬期:158件)。【結果】血管外漏出発生率は第1次先発薬期:1.3%,後発薬期:9.3%,第2次先発薬期:1.6%と後発薬期に有意に増加していた(P<0.01)。年齢,TC療法回数,BMI,後発薬の有無を調整した多変量解析での後発薬の血管関連合併症のオッズ比は6.8(95%CI:4.1-11.3)であった。【結論】TC療法における後発医薬品使用は血管外漏出,静脈炎などの血管関連合併症を増加させた。
1 0 0 0 OA 標本をめぐる採集人と貿易商と収集家
- 著者
- 川田 伸一郎 安田 雅俊
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.257-264, 2012 (Released:2013-02-06)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
The Hainan mole, Mogera hainana Thomas, 1910, was recorded to be collected by “a native employed by Mr. Alan Owston” in the original description of the species. We noticed the specimen tag of the holotype was printed and handwritten in Japanese characters. The same tag was attached to another specimen of this species deposited at the Forestory and Forest Products Research Institute (Tsukuba, Ibaraki, Japan). Those specimens were both collected in November, 1906; therefore, the Hainan mole was collected by a Japanese person who visited Hainan Island in this period. We searched for the same form of specimen tags, and found many among bird specimens from Hainan Island at the Yamashina Ornithological Institute (Abiko, Chiba, Japan). In this period, Zensaku Katsumata collected the birds in Hainan Isl. and sent them to the Lord of Lionel Walter Rothschild in England. We estimated the type series of the Hainan mole was also collected by Z. Katsumata, who was a collector employed by a merchant A. Owston, and he sent it to L. W. Rothschild in UK. L. W. Rothschild communicated with the Natural History Museum and his name was dedicated to 18 mammalian species by researchers of this museum. It is possible to consider that Rothschild’s mammalian collection was presented to the Natural History Museum and examined by mammal researchers. Although Zensaku Katsumata was an obscure person in mammalogy, we discuss his contribution to the dawn of natural history in Japan.
1 0 0 0 情報記録技術研究のすすめ
- 著者
- 栗原 義武
- 出版者
- 香川高等専門学校
- 雑誌
- 香川高等専門学校研究紀要 (ISSN:21852391)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.69-73, 2015-06
You can study cutting-edge worldwide technologies in a certain area such as signal processing of digital recording systems while sitting in the comfort of your home, Shikoku section of Japan. Magnetic recording technology has a long history in Japan. Japan has lead magnetic recording technologies for a long time. Hard disk drive (HDD) has played a key role in the area of storage technologies. In 1977 perpendicular magnetic recording was invented by a Japanese scientist who won the Japan Prize in 2010. Signal processing technology such as PRML (partial response maximum likelihood) has studied in Ehime University since 1980's.
1 0 0 0 沖縄トラフにおける熱水スモ-カ-・生物・鉱床の調査と解析
1986年に世界の背弧海盆に先駆けて中央地溝の一つである伊平屋海凹内で研究者らにより、低温で非晶質の熱水性マウンドが発見された。そこで、本研究においては、大洋中央海嶺で発見されたような硫化鉱床や大型生物コロニ-が認められるような高温の熱水性ベント・システムが背弧海盆にも認められるのかということを世界に先駆けて検証することを目標の一つとした。そして、それによって背弧海盆が大洋中央海嶺と同じ様な拡大メカニズムにより形成されたのかどうかということを明らかにしようと努めた。その結果、研究者らが参加・協力した調査・研究において以下に述べるような成果があげられた。昭和63(1988)年度:4ー6月、伊平屋海凹と伊是名海穴で熱水性生ベント・システム発見。ドレッジにより大型生物や硫化鉱床採取(ゾンネ号:「かいよう」)。9月には、前記熱水域に潜航し、熱水性鉱床・生物コロニ-等のサンプル採取に成功(「しんかい2000」)。平成元(1989)年度:4ー5月、伊是名海穴で高温熱水を噴出するブラックスモ-カ-が発見され、さらに新熱水域を発見する(「しんかい2000」)、1990ー91年の調査により、さらに北方の奄西海丘でも熱水性鉱床が発見された。1991年6月、沖縄トラフ南部北縁の潜水調査。トラフ縁の沈水時期を明らかにする(「スコ-ピオン」)。平成4年1月、南西諸島南方海域の海底地形精密調査。海溝運動と島弧・背弧海盆形成メカニズムを探る(「よこすか」)。以上、本研究により、発見された鉱床は、わが国経済水域内にあり、いわゆる黒鉱型鉱床に酷似し、金・銀を多量に含む珍しいものである。そして、シロウリ貝やバクテリア等も発見採取され、生命の起源解明にも寄与した。更に今後熱水域が新たに発見される可能性も指摘することができた。一方、構造探査の方では、沖縄トラフは典型的な大陸性地殻構造を持っていることが明らかになったが、鉱床の性質はそれと予盾しない。