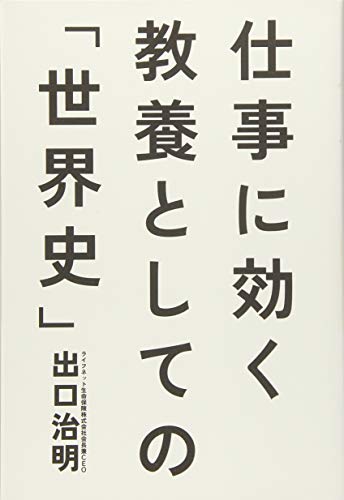1 0 0 0 OA メタヒューリスティックスによる都市街路網におけるサブエリア構成最適化
- 著者
- 織田 利彦 音喜多 亨 津久家 智光 橋場 加奈
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム制御情報学会論文誌 (ISSN:13425668)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.8, pp.466-476, 1998-08-15 (Released:2011-10-13)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 2
For the purpose of implementing the coordinated traffic signal control, urban road networks in Japan are divided into several sub-areas. Each sub-area consists of a series of signal intersections. The traffic signal timing is optimized within each sub-area and reflects the local traffic situation. Since there is no well-established method of decomposing a traffic network into sub-areas, the decomposition is determined by skillful engineers based on their experience. This paper proposes a new method of decomposition, which is based on an effectiveness index reflecting the traffic delay and the topological structure of the sub-area network. To evaluate the performance of our approach, simulation experiments are carried out for an actual road network. The results show that the decomposition obtained by our method outperforms the conventional decomposition in terms of the employed performance index.
- 著者
- 酒井 一人 仲村渠 将 吉永 安俊 長野 敏英 大澤 和俊 石田 朋康
- 出版者
- 土壌物理学会
- 雑誌
- 土壌の物理性 = Journal of the Japanese Society of Soil Physics (ISSN:03876012)
- 巻号頁・発行日
- no.122, pp.23-31, 2012-12
本研究では,冬季に沖縄県北部亜熱帯広葉樹林地の沢沿い複数地点でのCO2フラックス,地温測定および土壌水分測定により,CO2フラックスの地点間および観測日による変動実態を把握し,既往研究と比較した。さらに,対象地点の土壌の粒度分布,有機物含有量,根量とCO2フラックスの関係について解析した。また,温度制御した円筒管土壌呼吸実験により対象土壌のCO2フラックスの温度依存性について確認した。その結果,次の(1)~(5)が認められた。(1)CO2フラックスはばらつきがあり,南尾根で最大,谷に向かって小さくなる傾向にあった。同じ観測日での地温の測定地点間差は小さく,各地点の観測時の温度差がCO2フラックスの差に与えた影響は小さいと判断された。(2)既往の研究との比較では,本調査での値はA0層除去の影響により小さかったと判断できた。(3)観測日の温度の違いによるCO2フラックスの違いは明確ではなかった。それに対して,土壌水分の増加によりCO2フラックスが減少するという土壌呼吸特性が見られた。(4)本研究での観測では,粒度組成,有機物量,根量などとCO2フラックスの関連性は明確ではなかった。(5)土層実験により温度依存性を調べた結果,既往研究で示されたQ10値の範囲内の結果を得た。
1 0 0 0 OA 職域における抑うつと完全主義との関係について
- 著者
- 清水 光栄 古井 景
- 出版者
- 公益社団法人日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.173-180, 2004-09-20
- 被引用文献数
- 1 1
職域における抑うつと完全主義との関係について調査を行った. 対象は大手建設関連会社に勤務する380名で, ベック抑うつ尺度, 桜井, 大谷による新完全主義尺度などの質問紙調査を行った. 新完全主義尺度のうち「ミスを過度に気にする傾向(CM)」は年代を問わず抑うつと正の相関関係にあった. しかし「自分に高い目標を課する傾向(PS)」については若年群では抑うつと負の相関関係にあったが中高年群においては抑うつとの間に有意な相関関係が見られなかった. 抑うつに至る背景にはこのように年代間で差異があると考えられた. バブル経済崩壊以後, わが国の経済はいわゆる冬の時代, 平成不況が続いた. 雇用情勢が悪化する中で, 企業における「心の病」は増加傾向を示し, 心の病による長期休業の多くが「抑うつ」であると報告されている1). 抑うつに陥る要因は何であろうか.
1 0 0 0 星恋
- 著者
- 野尻抱影, 山口誓子 著
- 出版者
- 中央公論社
- 巻号頁・発行日
- 1954
- 著者
- 美細津 茜 池上 雄星 沓掛 登志子 辻 俊一 吉田 聡 生嶋 茂仁
- 出版者
- 公益社団法人日本生物工学会
- 雑誌
- 日本生物工学会大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.64, 2012-09-25
1 0 0 0 OA Prospective Memory in Nonhuman Primates
- 著者
- MICHAEL J. BERAN BONNIE M. PERDUE THEODORE A. EVANS
- 出版者
- 日本動物心理学会
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- pp.65.1.2, (Released:2015-04-22)
- 参考文献数
- 56
- 被引用文献数
- 2
Prospective memory requires forming an intention that cannot be completed at the present time, remembering that intention, and then recognizing the appropriate time to execute it. We review recent work in our laboratory that has revealed prospective memory-like patterns of performance in nonhuman primates. Rhesus monkeys and capuchin monkeys were given computerized tasks in which the monkeys either had to remember a future response they could not make immediately, or they sometimes saw a particular stimulus during an ongoing task they had to remember to later indicate seeing or not seeing. Most monkeys succeeded on these tasks and even anticipated the necessary responses. Chimpanzees also showed evidence of prospective memory. They appeared to form intentions about less valuable food items that they did not want immediately but would want later, and they responded at a later time when it was possible to obtain those items. Even when the response option was embedded within an ongoing task, the chimpanzees still showed some success in remembering to carry out the prospective intention. This research indicates that nonhuman primates form intentions for future responses, maintain those intentions during a delay, and execute them at an appropriate time.
1 0 0 0 高度衛星デジタル放送方式のARIB実証実験
- 著者
- 橋本 明記 井上 康夫 松本 英之 方田 勲 上田 和也 市川 鋼一 佐藤 彰 柴田 豊 石原 友和 太田 陽介 野崎 秀人 北之園 展 斉藤 知弘 筋誡 久 小島 政明 鈴木 陽一 田中 祥次
- 出版者
- The Institute of Image Information and Television Engineers
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 : 映像情報メディア = The journal of the Institute of Image Information and Television Engineers (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.7, pp.957-966, 2009-07-01
- 被引用文献数
- 9 1
Three channels, which will cease to be used for analog satellite broadcasting in July 2011 and 4 channels of the BS-17 19, 21, and 23ch, which were assigned to Japan at the WRC-2000, will be used for new digital broadcasting services after 2011. In these channels, a new broadcasting system called "Advanced Digital Satellite Broadcasting System" will be available as well as the current ISDB-S one. The new system can increase transmission bit rate by 30%compared with the current ISDB-S system by using LDPC codes and a roll-off factor of 0.1. The Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) conducted evaluation tests to acquire its C/N-BER and synchronous performance as well as confirm how well the TMCC signal functions. Demonstrative tests to transmit Super Hi-Vision were also performed. The tests were done using a satellite simulator and a real satellite transponder. The tests showed that the system performed very well, and the details are reported here.
1 0 0 0 OA 養殖経営に関するアンケート調査
- 著者
- 山本 淳 高橋 一孝
- 出版者
- [山梨県魚苗センター]
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.35-40, 1993 (Released:2015-04-17)
1 0 0 0 教育行政
- 著者
- 高田休廣 小笠原豐光著
- 出版者
- 私製
- 巻号頁・発行日
- 1934
1 0 0 0 OA Samaññaphalasutta (沙門果経) と Veda 祭式
- 著者
- 阪本(後藤) 純子
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.958-953, 2001-03-20 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 IR 書評と紹介 佐藤幹夫著『ルポ 高齢者ケア : 都市の戦略,地方の再生』
- 著者
- 橋本 美由紀 Hashimoto Miyuki
- 出版者
- 法政大学大原社会問題研究所
- 雑誌
- 大原社会問題研究所雑誌 (ISSN:09129421)
- 巻号頁・発行日
- no.679, pp.96-98, 2015-05
- 著者
- 藤井 守男
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.161-164, 2001-09-30 (Released:2010-03-12)
- 著者
- 筒井 泉
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理學會誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.12, pp.836-844, 2014-12-05
ベル不等式とベル定理の物理的な意義について,その歴史的背景と今日における影響を含めて解説する.EPR論文で提示されたアインシュタインの量子論に対する懐疑的立場は,ベルによって局所実在性を持つ隠れた変数の理論として体現されて,実験的にその可否が検証可能な形となった.それが2者間の相関に関するベル不等式であり,これまで数多くの検証実験が行われてきたが,本稿ではこれらの実験に共通する問題点と近年の展開を概観し,その物理的意味を吟味する.実験的に明らかとなったベル不等式の破れは,物理量の実在性がアインシュタインが想定したような局所的なものではなく,非局所的にも測定の状況(文脈)に依存するものであることを示唆している.
1 0 0 0 OA 野幌国有林野生植物調査報告書
1 0 0 0 仕事に効く教養としての「世界史」
1 0 0 0 健康保険制度の改正が受診行動に与えた影響
1 0 0 0 国際的に見た企業の知的戦略
- 著者
- 内田 盛也
- 出版者
- JAPAN TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY
- 雑誌
- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.6, pp.685-701, 1993
ご紹介にあずかりました内田でございます。本日は紙パルプ技術協会のこういう大会にお招きを頂き, 大変光栄に存じております。今日お話ししたいと思いますのは「国際的にみた企業の知的戦略」という題目でございますが, ご承知の通り, ただ今は大変な世界の変動期にあります。戦後懸命に日本の産業を大きくされてきた皆さん方は, 何となく今後の将来について戸惑いがおありになるのではないか。いったい今後どういうことになるのであろうか。私どもが大学を出て産業界に入りました時は, アメリカの国力の 1/30 でありました。現在, アメリカに匹敵するような大国になっております。ということは, 戦後我々がやってきたような方法で懸命に働いてこのままいきますと, 世界全体が日本になってしまうという事で, ご承知の通りいろんな摩擦問題等が出て来ております。<BR>それから, もう一つは小国日本が世界的な観点から色々な期待をされております。所が日本人の意識構造には全くそのような観点がありません。歴史的に見てヨーロッパなどでは学問が出きて, 宗教の中に育てられて, そういう形の中で伝統的に国際社会の自分達という意識構造, 社会構造というシステムが出来上がっておりますが, 日本はたった 30, 40 年の間にそうなったという事でこれからという所であります。こういう問題と同時に, 経営環境をどうしたら良いかといろんな意味の戸惑いがあると思いますので, 今後の大きな戦略的なものの中から少しでも皆様方の参考になればと思って, このような題目でお話をしてみたいと思うわけであります。
- 著者
- 陶山 恭博 岡田 正人
- 出版者
- 南山堂
- 雑誌
- 治療 (ISSN:00225207)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.11, pp.1936-1941, 2012-11
1 0 0 0 OA 成層状態の内湾に風が起こす現象(シンポジウム:気象擾乱に対する沿岸海洋の応答)
- 著者
- 藤原 建紀 高杉 由夫 肥後 竹彦
- 出版者
- 日本海洋学会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究ノート (ISSN:09143882)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.38-46, 1989-08-31
- 被引用文献数
- 1
成層状態の内湾に風が吹くと躍層の深化・成層の崩壊・風が止んだ後の再成層化などの現象が起きる.水温・塩分・溶存酸素の自動観測装置を瀬戸内海の周防灘・播磨灘・大阪湾・江田島湾に長期間設置し,これらの現象を観測した.湾の長さが約60kmであり,上層と下層の密度差が5kg/m^3であった周防灘では,8〜12m/sの風によって,1日のうちに完全に成層が崩壊した.また風が止んだ後は,水平的な密度勾配による密度流が起き,約1日で再び成層状態にもどった.底層に及ぶ上下混合が強風によって起こされる頻度は,周防灘・播磨灘・大阪湾・江田島湾において,それぞれ4回/2月,3回/1月,0回/1月,0回/2.2月であった.
- 著者
- 鮎川 正雄
- 出版者
- 建設コンサルタンツ協会
- 雑誌
- Civil engineering consultant : 建設コンサルタンツ協会会誌
- 巻号頁・発行日
- no.267, pp.26-29, 2015-04