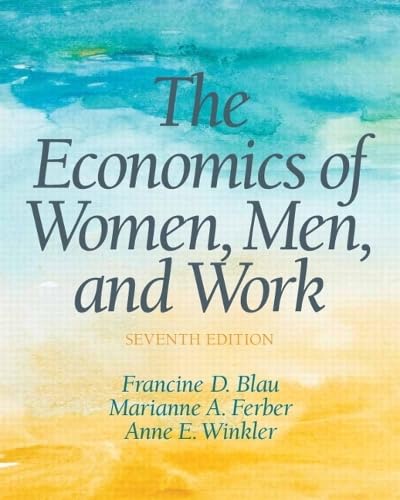- 著者
- 浅利 満継
- 出版者
- ぎょうせい
- 雑誌
- 税 (ISSN:09134824)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.10, pp.111-120, 2014-10
- 著者
- 板倉 聖哲
- 出版者
- 青月社 ; 2011-
- 雑誌
- 聚美
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.10-23, 2014
- 著者
- Francine D. Blau Marianne A. Ferber Anne E. Winkler
- 出版者
- Pearson
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 OA P230 室温下におけるCO_2 15μm帯の吸収線パラメータの測定
1 0 0 0 OA P224 低温下におけるCO_2 2.7μm帯の吸収線パラメータの測定
- 著者
- 深堀 正志 青木 忠生 渡邉 猛
- 出版者
- 社団法人日本気象学会
- 雑誌
- 大会講演予講集
- 巻号頁・発行日
- vol.85, 2004-05
1 0 0 0 OA 医療、精神保健、および家族に対する精神科的危機対応法の習得を目的とした介入研究
- 著者
- 大塚 耕太郎 鈴木 友理子 藤澤 大介 米本 直裕 加藤 隆弘 橋本 直樹 岩戸 清香 青山 久美 佐藤 玲子 鈴木 志麻子 黒澤 美枝 神先 真
- 出版者
- 岩手医科大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2010
医療、精神保健、および家族、社会的支援制度に該当する領域(法律、生活相談)、教育など幅広い領域におけるゲートキーパー養成プログラムを内閣府と協力して作成した。また、内閣府との共同で全国へ研修会やITを通じた普及を図り、ファシリテーター養成のためのプログラムを提供した。うつ病、統合失調症、不安障害、物質依存という4つの精神疾患の危機対応法プログラムとファシリテーター養成プログラムの開発を地域の精神保健に関する関係機関と共同で行い、有効性や妥当性を検証した。
- 著者
- 高橋 哲郎 元田 幸代
- 出版者
- 精華女子短期大学
- 雑誌
- 精華女子短期大学研究紀要 (ISSN:13495453)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.37-42, 2005-03
- 被引用文献数
- 1
卒業後, 現場での保育活動に適応してもらうためのプログラムの一つとして「実習指導IV」において, 卒業生へのアンケート調査結果を活用した試みを実施した。その内容から学生が「実習指導IV」で学びたいと思った10項目を選び出した。これらの項目について, 学外講師 (幼稚園園長先生), 教員, 実習助手, 学生の代表委員 (実習連絡協議会担当者) に担当を割り振り, 授業で実施した。アンケート結果を用いることにより, 就職後生じるであろう問題を身近に具体的に捉えさせることができた。さらに, 学生自身が現在の自分の状況を客観的に捉えて就職までに行っておくべき課題を見つけ, 課題を解決していこうとする意欲, そして, 就職後に問題が生じたとしても解決していこうとする意欲を喚起することができた。また, 学生の考察からこのプログラムの実施時期や内容のさらなる検討も必要であることがわかった。全国保育士養成協議会における専門委員会の研究報告との比較により, 卒業生が課題としてあげている内容は, 保育現場で時間をかけて行われている職務内容と保育者として専門性が要求される職務内容とがあることがわかった。今後は, プログラムの実施時期や内容をさらに検討していきたい。
1 0 0 0 エクアドルが電子マネーを通貨に 独立した金融政策の復活狙う
- 著者
- 木下 直俊 林 康史
- 出版者
- 毎日新聞社
- 雑誌
- エコノミスト (ISSN:00130621)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.46, pp.48-49, 2014-10-28
1 0 0 0 OA 歯科臨床 基礎のそを学ぶ
- 著者
- 加藤 泰二
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会
- 雑誌
- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.242-243, 2013-11-25 (Released:2014-11-15)
1 0 0 0 OA こどもの外遊びを活性化させる空間としての縁側の可能性
こどもの外遊びを回復させるために、日本の伝統的空間である縁側に着目した。そして、縁側のある保育施設で観察調査し分析することにより、「外遊びに展開しやすい縁側」について提案した。縁側が活発に使われている保育園では、幅が広く(約2m以上)、通行しやすく、室内と広くつなげられていた。また、保育室面積の大小に関わらず、こどもたちは自ら縁側に出て遊んでいた。滞留が多い縁側ほど保育室や園庭との出入りも多くなる。また、縁側の回遊性や園庭と積極的につなげるような形状も、縁側における滞留や通行を促すので外遊びへの展開に寄与するといえる。
- 著者
- 斎藤 環
- 出版者
- スタジオジブリ
- 雑誌
- 熱風 : スタジオジブリの好奇心
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.10, pp.24-28, 2014-10
- 著者
- 水谷 良亮
- 出版者
- ナショナルピーアール
- 雑誌
- Energy for the future
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.25-29, 2014
- 著者
- 江本 哲朗
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ヘルスケア : 医療・介護の経営情報 (ISSN:18815707)
- 巻号頁・発行日
- no.300, pp.42-50, 2014-10
- 著者
- 桑畑 洋一郎
- 出版者
- 日本保健医療社会学会
- 雑誌
- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.91-103, 2011
本論文の目的は、罹患経験を理由とした特有の医療利用実践を現在も行わざるを得ないハンセン病療養所退所者の状況を記述し、そうした実践の社会的背景と帰結を考察することにある。考察の結果、退所者は、ハンセン病療養所等特定の医療機関を選び利用するという実践を現在も行っていることが明らかとなった。また、それらの実践の背景には、<病いのスティグマ性>と<知識の配置の偏り>という退所生活における困難が存在する。退所者の医療利用実践は退所生活を続けていくために必要なものである。しかしながらこうした実践によって、退所生活における困難が維持されてしまうというジレンマも存在すると考えられる。退所生活における困難は、隔離政策をはじめとしたハンセン病者への社会的な排除が導いたものと考えられる。ハンセン病者のみに困難の解消を求めるのではなく、社会の側がこうした困難を解消する必要がある。
1 0 0 0 OA McMaster大学での臨床実習
1 0 0 0 OA 税負担削減行動の指標に関する理論的・実証的研究
1 0 0 0 OA タグした二光子過程ハドロン生成断面積の高統計測定による量子色力学の詳細検証
まず,一方の光子をタグしたπ0中間子の遷移形状因子の測定を行い,BaBarの結果と異なり,よりQCD極限値に近い結果を得て,この問題を落着させた。次にノータグ二光子過程によるK0S中間子対生成反応を閾値付近からの断面積を測定解析し,f2(1270)とa2(1320)の負の干渉,f2’(1525)の二光子幅×分岐比等の高精度の測定が可能となった。現在,一方の光子をタグしたπ0中間子対の微分断面積をQ2=30 GeV2まで測定解析して,論文として投稿準備中である。f2(1270)(ヘリシティ=2,1,0別々)とf0(980)中間子の遷移形状因子をQ2の関数として測定し,理論の予言と比較した。