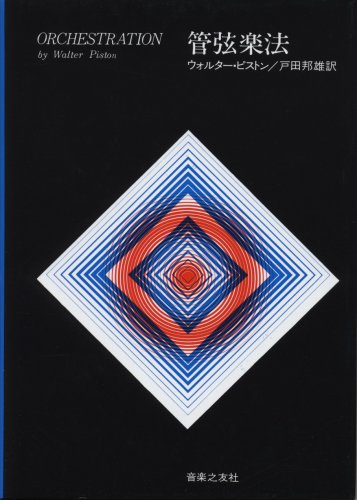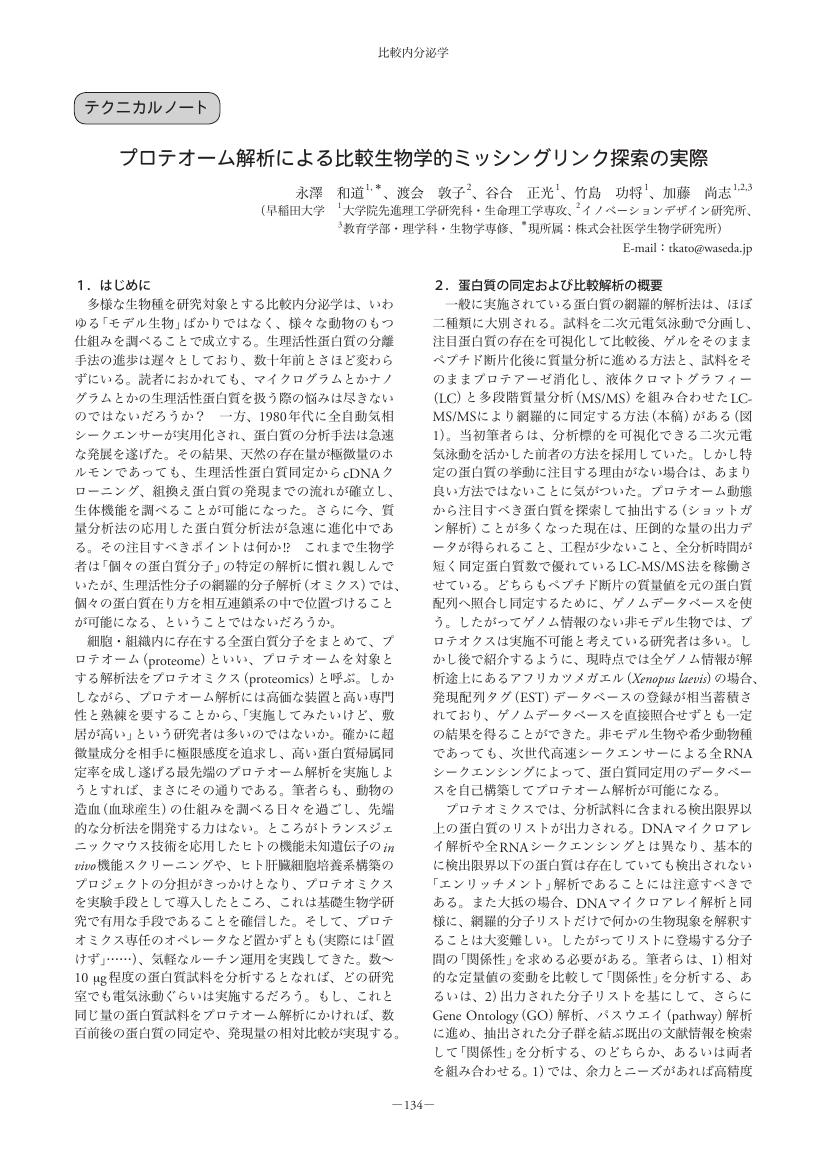1 0 0 0 OA 作問学習のモデル化
- 著者
- 平嶋 宗
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, 2009
「問題を作ること」の学習上の意義は様々に論じられている.本稿では,作問学習を知的に支援するシステムの設計・開発・評価の基盤として,問題を作る過程およびその意義を議論するための参照モデルを提案する.
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1941年07月30日, 1941-07-30
1 0 0 0 飢餓を生きる人々 : ガンジー翁の運動とは何か
1 0 0 0 OA 民芸ブームの一側面 : 都市で消費された地方文化
- 著者
- 濱田 琢司 Takuji Hamada
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2/3, pp.111-124, 2000-12-10
1 0 0 0 管弦楽法
- 著者
- ウォルター・ピストン[著] 戸田邦雄訳
- 出版者
- 音楽之友社
- 巻号頁・発行日
- 1967
1 0 0 0 OA T-RFLP法による腸内細菌叢の解析
- 著者
- 長島 浩二 久田 貴義 望月 淳
- 出版者
- 公益財団法人 日本ビフィズス菌センター
- 雑誌
- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.155-164, 2014 (Released:2014-10-29)
- 参考文献数
- 67
- 被引用文献数
- 1
近年,16SリボソームRNA遺伝子をターゲットとした分子生物学的手法は複雑な微生物群集の構造と機能を解明するための強力なツールとなっている.ここでは,同手法の一つであるT-RFLPとその関連技術ならびにT-RFLPを使って得られている研究成果について,著者らの考案した方法を中心に概説した.また,近年急速に普及してきた次世代シーケンサーによる網羅的解析とT-RFLPで得られた結果とが良く一致する幾つかの研究結果を紹介しながら,T-RFLPの今後の在り方について簡単に言及した.
- 著者
- 北村 晃寿
- 出版者
- 日本古生物学会
- 雑誌
- 化石 (ISSN:00229202)
- 巻号頁・発行日
- no.88, pp.59-60, 2010-09-30
- 著者
- 安原 由美子
- 出版者
- つくば国際大学東風小学校
- 雑誌
- 奨励研究
- 巻号頁・発行日
- 2012
「研究の目的」4年生の説明文の読解学習に、学習者が自らの学びをメタ認知し、<鉛筆対話>を取り入れ学習者同士が学び合う授業を行った。そのことにより、学習者は教材に向き合い筆者とかたり合うことで批判的な読みを行い読解力が育成されることがわかった。そこで、低学年においても読解活動に<鉛筆対話>を取り入れることの有効性について実践研究を行う。「研究の方法」「書く」ことに抵抗がなくなってきたと思われる2年生を対象に研究を行った。5月の初期段階と2月に自身の担当学級と大阪とで行い比較検討を行った。その間も説明文学習においては、<鉛筆対話>を取り入れた実践を継続する。また、<鉛筆対話>を取り入れない指導も行い比較検討する。「研究の成果」2学年においても、「思い」を交流し合うことはできる。単に(わかったこと)を交流し合うのではなく、(わからないこと)も出し合うようにした。友だちとの考えの違いに気付かせるための方法としては有効である。また、説明文の読み取りの手順を意識化させることにより「説明文の書き方」に目が向くようになってきた。学年末には、「筆者の書き方の上手なところ」を発見し、自分の書き方に取り入れようとする様子も見られた。(こんなことも書いてほしいなあ・なんで書いていないのかなあ)などという教材文に対して積極的に関わるようになってきた。しかし、低学年の場合は「思考」が拡散する傾向があるため時間を制限し、指導者として学習者同士が話し合う論点を明確に示す必要がある。私立と公立の児童に大きな違いはないが、「書きなれている」という点では、私立の児童の方が量的に多く書ける傾向がある。今回茨城の指導者に説明文指導についてのアンケートを行った。前回の大阪・秋国と比較しても「説明文の指導法」に変化がなく、指導者として「力のつく」指導法を模索する姿が見えた。学年の発達段階にそった<鉛筆対話>を取り入れた実践を開発していきたい。
1 0 0 0 IR ヴァルター・フォン・デァ・フォーゲルヴァイデの「冬の歌」
- 著者
- 松村 國隆
- 出版者
- 大阪市立大学
- 雑誌
- 人文研究 (ISSN:04913329)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.8, pp.573-596, 1997
1 0 0 0 OA プロテオーム解析による比較生物学的ミッシングリンク探索の実際
1 0 0 0 カット青果物の生理・化学的特性と流通技術に関する研究
- 著者
- 阿部 一博
- 出版者
- 日本食品保蔵科学会
- 雑誌
- 日本食品保蔵科学会誌 = Food preservation science (ISSN:13441213)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.283-290, 2006-11-30
- 被引用文献数
- 3 5
近年の社会情勢や食環境の変化とともに食習慣や食素材の形態も移り変わり、特に簡便性を有するカット青果物の流通・消費量が急激に増加し、日本では最近10年程の間に2,000億円を超える市場規模となっている。カット青果物の先進国であるアメリカ合衆国では、2005年のフレッシュカット青果物の売上総額は前年比10%増の60億ドル(6,900億円/1ドル=115円換算)に達し、全国青果物小売総売上額の16%を占めることが、国際フレッシュカット青果物協会の市場調査で明らかになっており、日本におけるカット青果物の消費量のさらなる増加が予想される。一方、栄養士志望の若い女性を対象として、2005年に筆者が実施したアンケート調査においても、カット青果物の利用頻度が今後も高まることが明らかになっている。筆者は、1987年ごろから十数年間にわたってさまざまなカット青果物を研究の対象としており、また、基礎的な研究から応用研究まで幅広い分野の研究結果を報告しているので、それらを11項目に分けて記載する。
- 著者
- 内山 郁夫
- 出版者
- 一般社団法人日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.6, pp.266-269, 2002-11-25
MBGD is a database system for making use of rapidly accumulating microbial genome sequences through comparative analysis. The basic function of MBGD is to create an orthologous gene classification table, which comprises sets of "equivalent" genes among multiple genomes. In MBGD, classification tables can be created on demand with specified set of organisms and parameters. This feature becomes important to understand diversity of genomes using almost a hundred genome sequences now available.
1 0 0 0 OA 先端記憶デバイスを利用する記憶階層の再構築に関する研究
依然として上昇している要求性能に答えることが可能な,プロセッサ性能の向上が達成されている.しかしシステム全体を眺めると,十分な性能を提供できているとは言い難い.メモリが足枷となっている.加えて,メモリはエネルギー消費量が大きい点でも問題である.このような問題意識から,本課題を実施した.近い将来に磁気抵抗メモリ等の次世代メモリが利用可能になるという仮定の下で,アーキテクチャ上の工夫により高性能・低電力・高信頼なメモリシステムを実現するために,従来の記憶階層を解体して新たに構築することを目標とした.提案する記憶階層を用いると最良の場合で,エネルギー遅延積を49%改善できることが確認できた.
- 著者
- 川本 直義 清水 裕之 大月 淳
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.580, pp.41-48, 2004
- 被引用文献数
- 1 1
I investigated the situation of the practice fields use of city bands and satisfactory degree for practice fields and analyzed it. Now city bands used a social educational institution most. Users of social educational institution have dissatisfaction toward that the practice field is not for music, but it is thought that they endure it because the fee for use is cheap. Local governments should consider the use of a cultural organization in public facilities and should keep the multi-purpose use.
1 0 0 0 我が国労働者の労働=生活時間構造の変化に関する実証的研究
- 著者
- 鷲谷 徹 藤本 武 木下 武男 FUJIMOTO Takeshi
- 出版者
- (財)労働科学研究所
- 雑誌
- 一般研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 1987
初年度においては、労働=勤務時間と生活時間の内的連関構造を明らかにすることを目的として、電機産業の既婚男子労働者を対象とした生活時間調査データの解析を行ない、そこから、1.職業関連行動時間(勤務時間、通勤時間等)の延長が他の諸生活行動時間をいかに圧迫しているかを構造的に分析し、能動的「余暇」活動を行なうためには、まとまったある程度長い時間(「最小必要連続時間」)が必要であり、長時間労働による生活時間の圧迫は量的のみならず、生活の質に大きな影響を及ぼすこと、2.家庭生活の「良好度」、労働者の健康状態等の指標を労働=生活時間の状態と関連づけて分析すると、帰宅時刻との強い連関が認められ、帰宅時刻が21時を超えると、家族関係や労働者自身の健康状態に様々な障害が発生する可能性があることを明らかにした。さらに、第2年度には、異なる2種類の生活時間調査データの分析を行い、初年度の分析結果との比較検討を行なった。そこでは、3.地域や勤務先業種、職種等の違いにも拘らず、帰宅時刻をひとつの基準として、家庭生活の良好さを確保するという視点からの、労働時間の上限の一般的目安を見いだし得ることが明らかとなり、また、4.労働時間短縮の実現に関わる労使関係上の問題解明のための実態調査結果の分析を通じて、所定外労働を行なう理由として、労働者自身は「自己の仕事を消化するため」を挙げるものがとくに多く、見かけ上は、「自発的に」時間外労働を行なっていること。この限りで、時間外労働の削減の方向は、いったん、労働時間制度の枠組みを外部化し、それ自体の遵守を労使関係の基盤と化すべく論理の倒置が要求されていることが明らかとなった。
- 著者
- 範 麗雅
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部アジア地域文化研究会
- 雑誌
- アジア地域文化研究 (ISSN:18800602)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.82-101, 2010
論文/Articles
1 0 0 0 OA 個票データを用いた病院倒産分析に関する予備的考察
- 著者
- 山本 克也
- 出版者
- 公益財団法人 医療科学研究所
- 雑誌
- 医療と社会 (ISSN:09169202)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.3_81-3_96, 2004 (Released:2010-02-02)
- 参考文献数
- 23
本稿では「医療施設調査」の個票データを利用し,病院の倒産確率の測定を行なった。「医療施設調査」は非財務データであるが収支の代理変数を抽出しプロビット分析を施して,病院の倒産事由の代表である放漫経営と販売不振を検討した。収入項目である病床に関しては,現在のところ,慢性期患者向けの病床を保有することは固定収入の確保につながり,倒産確率は下がる。一方,外来患者については倒産確率を引き下げる効果を持たない。入院の赤字を外来で埋める式の経営は成立しないので病床管理は重要である。一方,診療機器については,その需要予測はもちろん,普及期をすぎれば診療報酬は下がるということも勘案して導入しなくてはならない。販売不振については,医療需要の飽和ということも考えられるが,患者のニーズと病院の設備事態,有り様がミスマッチになっている可能性もある。すべての病院(医師)が最新の医療,高度医療を行なう必要がないことを病院経営者は銘記すべきであろう。