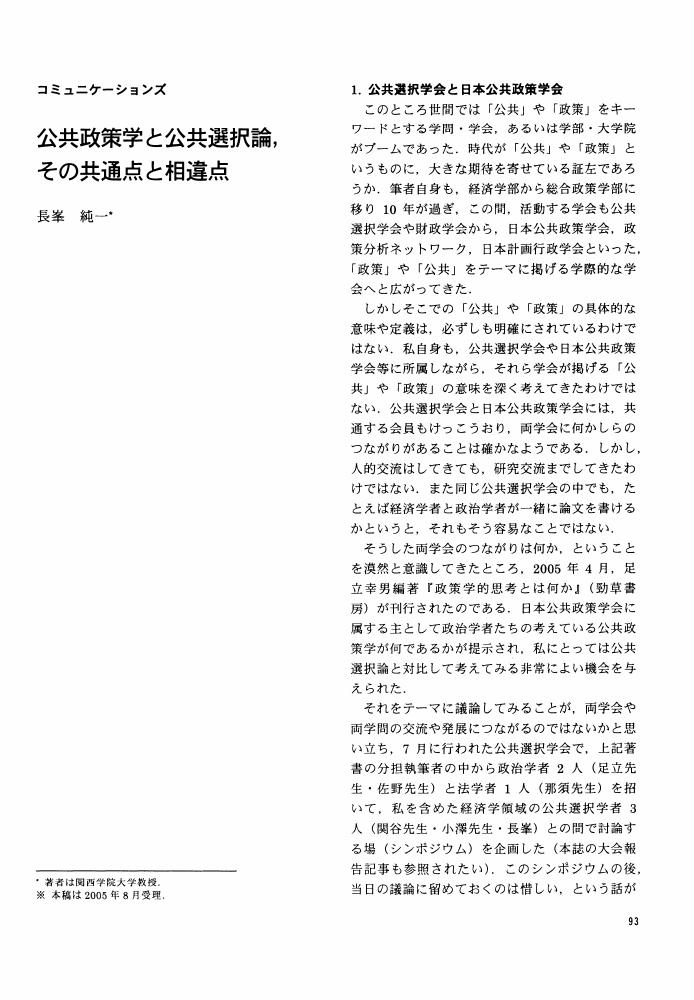- 著者
- 戸田 均
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 年次大会 2013 (ISSN:24242667)
- 巻号頁・発行日
- pp._S113024-1-_S113024-3, 2013-09-08 (Released:2017-06-19)
To prevent the wheel separation accidents, clarifying the influence of running condition on load of wheel bolts. In this paper, I investigated the stress of wheel bolts while the vehicle is moving. In the results, I confirmed that stress amplitude on left rear wheel bolts increased in the car trun to the right. Then the load of wheel bolts changed the pulsating bending load from the reversed bending load with loosing the wheel bolt.
2 0 0 0 OA 身体運動の大きさが拡散的アイデア産出に与える効果
- 著者
- 永井 聖剛 山田 陽平 仲嶺 真
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.3, pp.294-300, 2019 (Released:2019-08-25)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 2
Previous studies have shown that the physical movements of participants influence creativity thinking. We examined whether another type of movements (bigger or smaller arm movements) modulates creative idea productions. In Experiment 1 participants were required to generate new names for rice after performing bigger or smaller arm movements. Bigger arm movements were associated with more divergent idea productions (e.g., non-typical ideas) compared to smaller arm movements. In Experiment 2, another task was used to generate as many ideas as possible for creative gifts the participants might give to an acquaintance, and the results showed the possibility that bigger arm movements led to more flexible idea generation than did smaller one. Taken together, the current study suggested the size of movements modulated creative thinking: bigger ones increased divergent creative thinking, possibly because bigger physical movements facilitate the divergent cognitive processing mode.
2 0 0 0 OA 院内感染とバイオフィルム
- 著者
- 水之江 義充
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.199-203, 2013-08-15 (Released:2014-08-15)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA メラミン樹脂製食器の酵素的及び非酵素的分解
- 著者
- 石綿 肇 杉田 たき子 武田 明治
- 出版者
- Japanese Society of Food Chemistry
- 雑誌
- 日本食品化学学会誌 (ISSN:13412094)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.145-150, 1997-02-24 (Released:2017-12-01)
- 参考文献数
- 15
プラスチック製品は、生態系において分解しにくいことから環境問題として大きく取り上げられている。生分解プラスチックの開発、製品化も図られているが、現在、市販されている製品は大部分が既存プラスチックである。分解促進のために、ポリエチレンのような熱可塑性プラスチックへのデンプンの添加なども試みられている。メラミン樹脂をはじめとする熱硬化性プラスチックは、物理的強度を保つために、通常、製造原料として17%から50%のセルロースが加えられている。そこで、環境保全の観点から、メラミン食器の酵素的及び非酵素的分解について検討を試みた。食器用の未硬化メラミン樹脂コンパウンド及び2種類のメラミン樹脂製コップを粉砕したものを試料として用いた。コンパウンド及びコップ粉末に0.1Mリン酸緩衝液(pH4.5)中40℃でセルラーゼを48時間作用させたところ、コンパウンドではグルコースとして603ppm、コップ粉末では88ppmの糖が遊離した。セルラーゼ無添加では遊離糖は検出されなかった(Fig. 1及び2)。遊離糖のHPLC分析を行ったところ、主成分はグルコースで、セロビオースは見られなかった(Fig. 3)。この時、ホルムアルデヒドとメラミンモノマーの増加がみられたが、セルラーゼの添加による促進は認められなかった。従って、ホルムアルデヒドとメラミンモノマーの増加は、樹脂の非酵素的分解によるものである。コップ粉末での48時間後におけるこれら3種類のモノマーの合計は、原料の約3%であった。メラミン樹脂の非酵素的分解は、温度が高いほど促進され、また、酸性あるいはアルカリ性で促進された(Fig. 5)。これらの結果は、メラミン樹脂は自然環境下で酵素的、非酵素的に徐々に分解されることを示している。遊離したメラミンモノマーはある種の微生物により資化されることが知られており、モノマーによる二次汚染の可能性は低いと考えられる。
2 0 0 0 OA D21S11型におけるトリアレルピークに関する研究
- 著者
- 轡田 行信
- 出版者
- 日本法科学技術学会
- 雑誌
- 日本法科学技術学会誌 (ISSN:18801323)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.211-222, 2020 (Released:2020-07-31)
- 参考文献数
- 29
Tri-allelic peaks are rarely detected from single-source DNA in the case of testing with commercial STR kits, while homozygous or heterozygous peaks are frequently observed at each locus. Tri-allelic patterns can possibly occur in healthy people, and the peak balance of various tri-alleles from different origins can cause some problems that discern from artifact peaks affecting the result of STR typing, or difficulties in the evaluation of kinship. In this study, different samples from a volunteer with D21S11 tri-alleles (alleles 26, 29, and 30) were tested using routine STR analysis methods. The peak balances of the tri-allele varied significantly between samples, therefore a type 1 tri-allelic pattern caused by somatic mutation in the early stages of differentiation was possible because the sum of the lower two peak heights was roughly equal to the highest peak height in every case. Direct sequence analysis of the individual's family members revealed that the tri-allelic pattern was not inherited from the mother, nor was it passed down to the daughter. In addition, a mutated form of one of the tri-alleles and its mutated repeat unit and numbers were identified. When tri-allelic peaks are suspected, it is essential to analyze not only intra-locus peak balance but also the whole electropherogram profile. This means that STR typing is necessary considering the fact that pull-up peaks or stutter peaks could resemble tri-allelic peaks.
2 0 0 0 OA 音楽が柔軟性に及ぼす影響
- 著者
- 山下 優希
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)
- 巻号頁・発行日
- pp.220, 2016 (Released:2016-11-22)
【目的】音楽にはリラクセーション効果があり,最近では様々な分野に治療の一貫として注目を集めている.スタティックストレッチング(以下ストレッチ)は運動後に行うことにより傷害予防や疲労回復の促進,疼痛の軽減の効果があるとされている.そこで運動後,ストレッチを実施している最中に音楽のリラクセーション効果を同時に取り入れることによりさらなる効果が得られるのではないかと考えた.【対象と研究方法】被験者は運動疾患のない健常な29名(男性13名 女性16名 年齢32±22歳 身長164±15cm 体重60±40kg),測定場所は静寂空間で実施した.曲はモーツァルトの「2台のピアノのためのソナタ二長調(ケッヘル四四八番) 第一楽章」を選定.ストレッチはハムストリングスに対して実施し,痛みを感じない最大伸展位を至適強度とした.運動機器はコンパス コンパクト レッグプレス(以下レッグプレス)を使用した.立位体前屈指床間距離(以下FFD)の測定は距離が遠い方とした.測定の順序は, 膝伸展位股関節屈曲角度(以下SLR),FFDを測定後,レッグプレス 負荷30㎏ 10分を実施.運動後SLR・FFDを測定.運動後に①音楽聴取(2分間)群(以下A) ②ストレッチ(30秒間)群(以下B) ③音楽聴取とストレッチの同時群(以下C)の実施後にSLR・FFDを再測定.効果の影響を考慮して各群の間隔は1週間とした.検定方法は一元配置分散分析と多重比較を使用し,有位水準は5%未満とした.【結果】SLR右下肢はAとC間のSLRが優位に上昇した.(P=0.037263)SLR左下肢はAとC間,BとC間のSLRが優位に上昇した.(P=0.000102)FFDは,各群の平均値は上昇したが,優位な差はみられなかった.【考察】今回の研究においてSLRがAとC間において左右の下肢ともに優位な上昇がみられた.左下肢ではBとC間においてSLRの優位な上昇がみられたが,右下肢ではBとC間においてSLRの優位な上昇はみられなかったものの数値的にはSLRが向上している.このことから音楽聴取とストレッチを同時に実施することで,それらを単独で行った場合に比べてハムストリングスの柔軟性が向上することが示唆された.これは音楽聴取により交感神経の活動が抑制され,副交感神経の活動が活発になりα波が優位になったことで筋緊張の緩和がみられたことが要因と考える.またトマティス理論により周波数が延髄に作用し,副交感神経優位となったことも柔軟性の向上に繋がった要因の一つと考える.FFDにおいて今回優位な差はみられなかった.これは松永らによるストレッチングの長期介入による腰椎骨盤リズムへの作用が今回の即時的な効果では結果に反映されなかった事が原因の一つと考える.しかし,平均値でみるとCが他のA,Bよりも改善はみられており,音楽の効果も影響していると考える.【まとめ】今回の研究では音楽を聴きながらストレッチを実施することで,音楽聴取とストレッチを単独で行った場合に比べて柔軟性が向上することが示唆された.今後もリハビリテーションの中に運動後の疲労回復,障害予防としてストレッチを取り入れていくことは重要であり,そこに音楽を同時に取り入れることでさらなる効果の増大に繋がることが示唆される.本研究の制約としては聴取音楽の統一や,健常者への実施が挙げられる.今後,音楽の種類や疾患等を考慮した更なる研究が必要である.【倫理的配慮,説明と同意】実施に関しては当該施設の倫理委員会に承認を得るとともに,対象者へ目的の説明を行い協力の同意を得た.
2 0 0 0 OA 8年制医師養成教育―GHQサムス准将の提案
- 著者
- 二至村 菁
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.421-428, 2013-12-25 (Released:2015-07-06)
- 参考文献数
- 32
《学士課程修了者のみを医学部に入学させる》という8年制医師養成教育計画は,1945年末に連合軍総司令部(GHQ)内の日本医科学審査委員会によって提案され,1946年からGHQ公衆衛生福祉局のクロフォード・F・サムス局長によって推進された.この計画は厚生省の医学教育審議会の賛成を得たが,文部省の教育刷新委員会の安倍能成座長が敗戦国日本の困窮を理由に強硬に反対し,GHQ民間教育情報局も協力せず,廃案となった. 日野原重明氏は学士課程修了者を対象とする大学院医学校を計画しておられるが,もし実現すれば戦後先進国となった日本が初めて18歳ではなく22歳の成熟した学生を医師として養成するという興味深い試みとなろう.
2 0 0 0 OA 中国医学古典にもとつく鍼灸治療の基礎的体系
- 著者
- 柴崎 保三
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.396-404, 1973-12-10 (Released:2010-10-21)
2 0 0 0 OA 古代アステカ人の供犠 : 「食べる」と「建てる」
- 著者
- 岩崎 賢
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.3, pp.679-702, 2003-12-30 (Released:2017-07-14)
本稿の目的は古代アステカ人の宗教伝統の中心的要素である人身供犠に関して、宗教学的視点から新たな解釈を行い、従来と異なるより適当なアステカ宗教像を提示することにある。メキシコの歴史家アルフォンソ・カソの議論以来、研究者はアステカ人の供犠の説明として、アステカ人の神話に基づいて、彼らは人間の体を食料として捧げることで守護神である太陽神に活力を与え養おうとした、という説を採用してきた。しかし近年のいくつかの考古学的発見により、このような「太陽神の食事」式の説明はもはや支持し得ないものとなってきている。実際、この儀礼はいわゆる原初巨人解体神話という神話的主題、および建築儀礼との関連において理解されるべきである。筆者はここで「食べる」と「建てる」という二つの概念を鍵として、アステカ宗教と供犠の新たな理解のあり方を探りたいと考えている。
2 0 0 0 OA ガリエヌス帝の「騎兵軍改革」について
- 著者
- 井上 文則
- 出版者
- 日本西洋古典学会
- 雑誌
- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.84-94, 2004-03-05 (Released:2017-05-23)
In 1903 E Ritterling put forward a new theory the emperor Gallienus created four independent cavalry corps, all under the control of one commander Aureolus This theory was developed by A Alfoldi who used coins as a historical source to argue that these four independent cavalry corps were converted into the central cavalry corps stationed at Milan Alfoldi's argument was generally accepted However, H G Simon recently rebutted it and denied the existence of such corps on the grounds that the main Greek sources concerning Gallienus' reform of cavalry are unreliable In this paper, I examine Gallienus' supposed reform of cavalry to clarify the military system of the Roman Empire in the mid-third century First, I attempt to reconstruct the career of Aureolus who is key to understanding cavalry reform According to the Greek sources, Aureolus was commander of the central cavalry corps at the time of his rebellion against Gallienus But there are many inconsistencies in the Greek sources and further the Latin historian Aurelius Victor said that Aureolus was commanding the army in Raetia when he revolted In Simon's view, the Latin source is more reliable and he reinterprets the Greek sources to reconcile them with the Latin source Since his interpretation seems unconvincing, I here propose another solution to this problem I argue that Aureolus was the commander of the central cavalry corps at the time of Gallienus' war against Postumus in 265, not in 268 and that after concluding the war Aureolus remained in Raetia to defend the invasion of Postumus into Italy I observe that there is no evidence for the existence of the central cavalry corps except the title of Aureolus Rather it is recognized that independent cavalry corps, such as the Dalmatian cavalry corps, played a prominent part in many battles Moreover there were some independent cavalry corps not included into the central cavalry corps, though it is commonly said that they are all created to form it Form these observations, I suggest that Gallienus originally intended to create the independent cavalry corps and the central cavalry corps was temporarily formed from the independent cavalry corps which happened to be under the direct command of the emperor To understand the real significance of the independent cavalry corps, it is necessary to consider to the phenomenon that prior to the cavalry reform, Roman legion, which mainly consisted of infantry, divided into the vexillatio for independent use By creating a new cavalry unit corresponding with vexillatio, Gallienus probably intended to form mobile field forces, containing both cavalry and infantry I can find it not only under the direct command of the emperor but also deployed by other military commanders elsewhere It seems probable that such military condition in the mid-third century shaped Diocletian's later policy to divide the Roman Empire into four parts
2 0 0 0 OA 「社会心理学の危機」を巡る論争について
- 著者
- 三井 宏隆
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.171-176, 1986-02-20 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 36
2 0 0 0 OA オスグッド-シュラッター病発症後のサッカー選手における 膝伸展に関与する身体因子の特徴
- 著者
- 古後 晴基 満丸 望 岸川 由紀
- 出版者
- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会
- 雑誌
- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.51-56, 2018-07-31 (Released:2018-10-05)
- 参考文献数
- 24
[目的]本研究の目的は,Osgood-Schlatter disease(OSD)発症後の膝伸展に関与する身体因子の特徴を明らかにすることであった。[対象と方法]高等学校男子サッカー選手でOSD 発症者41名(54膝),非発症者160名(320膝)を対象とし,膝伸展に関与する身体因子5項目を測定した。OSD の発症膝と非発症者の両膝の2群間で,身体因子を比較した。[結果]OSD の発症膝は非発症膝と比較して,大腿直筋筋厚が有意に高値を示し,中間広筋筋厚が有意に低値を示した。また,大腿四頭筋筋力が有意に低値を示し,ハムストリングスの筋伸長性が有意に高値を示した。[結語]OSD 発症後の膝伸展に関与する身体因子の特徴は,大腿直筋筋厚が厚く,中間広筋筋厚は薄いことが示され,大腿四頭筋筋力が低く,ハムストリングスの筋伸長性は高いことが示唆された。
2 0 0 0 OA シカ生息地におけるオオバアサガラ林の成立と剥皮による枯死
- 著者
- 石原 正恵
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース 第129回日本森林学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.679, 2018-05-28 (Released:2018-05-28)
ニホンジカの個体数の増加による採食植物の減少と不嗜好性植物の優占、そして生態系への影響が日本各地で問題となっている。生態系を管理していく上で、不嗜好性植物が優占した状態で生態系が安定するのか、それとも不嗜好性とされていた植物種も新たに採食されるようになり植物群落が変化しつづけるのか、を明らかにすることが重要である。 本研究は不嗜好性植物とされてきたオオバアサガラを対象に、京都大学芦生研究林において樹皮はぎ(剥皮)の被害状況と今後の動態を検討した。芦生研究林では2000年ころから採食植物の減少する中、オオバアサガラは分布を拡大してきたと考えられているが、2016年ころから樹皮はぎが見られるようになった。2017年にオオバアサガラ純林2ヶ所(各10m✕15m)で毎木調査を行った。剥皮は調査幹の7割でみられた。剥皮された幹の9割は枯れており、その割合は剥皮されていない幹の約3倍高かった。剥皮された幹では剥皮されなかった幹に比べ多数の萌芽が地際から伸びていた。シカによる樹皮はぎはオオバアサガラ幹を枯死させるが、しばらくは萌芽による再生と樹皮はぎが繰り返され、オオバアサガラが優占した状態が続くと考えらる。
2 0 0 0 OA 高速量子アルゴリズムの開発
- 著者
- 谷 誠一郎 高橋 康博
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.15-27, 2020-07-01 (Released:2020-07-01)
- 参考文献数
- 62
量子コンピュータは現在のコンピュータにおける不可能を可能にする高速コンピュータとして大きな期待を集めている.この期待の実現には,新しいハードウェア技術とともに,ハードウェアの能力を引き出す新しいアルゴリズム技術が不可欠である.本稿では,このような高速量子アルゴリズムの開発に焦点を当て,量子コンピュータ単体による計算や通信が可能な複数の量子コンピュータを利用する計算のために開発されてきた高速量子アルゴリズムの歴史を振り返るとともに,我々の成果について,その原点となる発想を中心に紹介する.
2 0 0 0 OA Different Future Changes between Early and Late Summer Monsoon Precipitation in East Asia
- 著者
- ENDO Hirokazu KITOH Akio MIZUTA Ryo OSE Tomoaki
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-073, (Released:2021-09-01)
- 被引用文献数
- 10
Future changes in East Asian summer monsoon (EASM) precipitation and the associated atmospheric circulation changes are investigated based on ensemble projections with the 60-km mesh Meteorological Research Institute atmospheric general circulation model (MRI-AGCM60). The projections at the end of the twenty-first century under the Representative Concentration Pathway 8.5 (RCP8.5) scenario indicate an overall increase in EASM precipitation, but with large sub-seasonal and regional variations. In June, the Meiyu–Baiu rainband is projected to strengthen, with its eastern part (i.e., the Baiu rainband) shifted southward relative to its present-day position. This result is robust within the ensemble simulations. In July and August, the simulations consistently project a significant increase in precipitation over the northern East Asian continent and neighboring seas; however, there is a lack of consensus on the projection of the Meiyu–Baiu rainband in July. A small change in precipitation over the Pacific is another feature in August. Sensitivity experiments with the MRI-AGCM60 reveal that the precipitation changes in early summer are dominated by the effects of sea surface temperature (SST) warming (i.e., uniform warming and the tropical pattern change), which induce an increase in atmospheric moisture and a strengthening and southward shift of the upper-level East Asian westerly jet (EAJ), especially over the Pacific. On the other hand, the influence of land warming and successive large SST warming in the extratropics is evident in the precipitation changes in late summer. These late summer effects oppose and exceed the early summer effects through changes in the EAJ and low-level monsoon winds. These results suggest that the competition between the opposing factors makes the signal of the Meiyu–Baiu rainband response smaller in July than in June, and thus there tends to be a larger spread among simulations regarding the future tendency of the rainband in July.
- 著者
- BAO Jiawei STEVENS Bjorn
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-072, (Released:2021-09-06)
- 被引用文献数
- 5
Understanding of the tropical atmosphere is elaborated around two elementary ideas, one being that density is homogenized on isobars, which is referred to as the weak temperature gradient (WTG), the other being that the vertical structure follows a moist-adiabatic lapse rate. This study uses simulations from global storm-resolving models to investigate the accuracy of these ideas. Our results show that horizontally the density temperature appears to be homogeneous, but only in the mid- and lower troposphere (between 400 hPa and 800 hPa). To achieve a homogeneous density temperature, the horizontal absolute temperature structure adjusts to balance the horizontal moisture difference. Thus, water vapor plays an important role in the horizontal temperature distribution. Density temperature patterns in the mid- and lower troposphere vary by about 0.3 K on the scale of individual ocean basins, but differ by 1 K among basins. We use equivalent potential temperature to explore the vertical structure of the tropical atmosphere and we compare the results assuming pseudo-adiabat and the reversible-adiabat (isentropic) with the effect of condensate loading. Our results suggest that the tropical atmosphere in saturated convective regions tends to adopt a thermal structure that is isentropic below the zero-degree isotherm and pseudo-adiabatic above. However, the tropical mean temperature is substantially colder, and is set by the bulk of convection which is affected by entrainment in the lower troposphere.
2 0 0 0 OA 公共政策学と公共選択論, その共通点と相違点
- 著者
- 長峯 純一
- 出版者
- 公共選択学会
- 雑誌
- 公共選択の研究 (ISSN:02869624)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.45, pp.93-97, 2005-12-05 (Released:2010-10-14)
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 OA 麻酔科診療報酬の変遷からの俯瞰─麻酔科医の社会的地位は?─
- 著者
- 横田 美幸 平島 潤子 大里 彰二郎 見市 光寿 風戸 拓也
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.5, pp.573-585, 2019-09-15 (Released:2019-10-29)
- 参考文献数
- 8
麻酔科の診療報酬の変遷を俯瞰し,麻酔科医の立ち位置を考察した.麻酔科医は,その活躍や国民からの期待に沿って評価されている.麻酔料の基本,全身麻酔料(L008)の1986年を1として,2002年では1.74と大きく増加している.最近の麻酔科への逆風は,一部の麻酔科医師の不適切な行動にあるのかもしれない.この逆風の結果,麻酔料の基本部分は1.74から1.71に下げられ,それは他の部分に配分された.麻酔科の領域は広く,麻酔科医の責任は重い.この期待に応えるためには,安全性を確保した上での効率化,すなわち麻酔科医の行うべき範囲と他に任せることを明確にすることであり,そのことが調和のとれたチーム医療へと帰結していく.それを成し得たチームが,今後の変革に対応することができるであろう.
2 0 0 0 OA 河川から考える海洋プラスチックごみ・マイクロプラスチック対策
- 著者
- 二瓶 泰雄 片岡 智哉
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会誌 (ISSN:18835864)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.309-316, 2018-07-31 (Released:2019-07-31)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
本報では,海洋プラスチックごみやマイクロプラスチックの発生源と考えられる陸域・河川ごみの動態を示すために,多くの現地調査事例に基づいて,河川におけるごみ (川ごみ) の輸送状況やごみ組成を示すとともに,日本の河川におけるマイクロプラスチック汚染状況の実態を取りまとめた。その結果,川ごみは出水時に大量に輸送され,川ごみ全体の 6 %がプラスチック等の人工系ごみであった。マイクロプラスチックに関しては,全 23 河川で発見されたこと,流域の市街化が進んでいる河川のほうがマイクロプラスチック汚染が進んでいることも示された。さらに,海洋プラスチックごみおよびマイクロプラスチック対策としての河川におけるごみ捕捉技術の可能性について言及した。
2 0 0 0 OA 耳疾患に対する漢方治療
- 著者
- 小川 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.1, pp.78-79, 2015-01-20 (Released:2015-02-05)
- 参考文献数
- 6