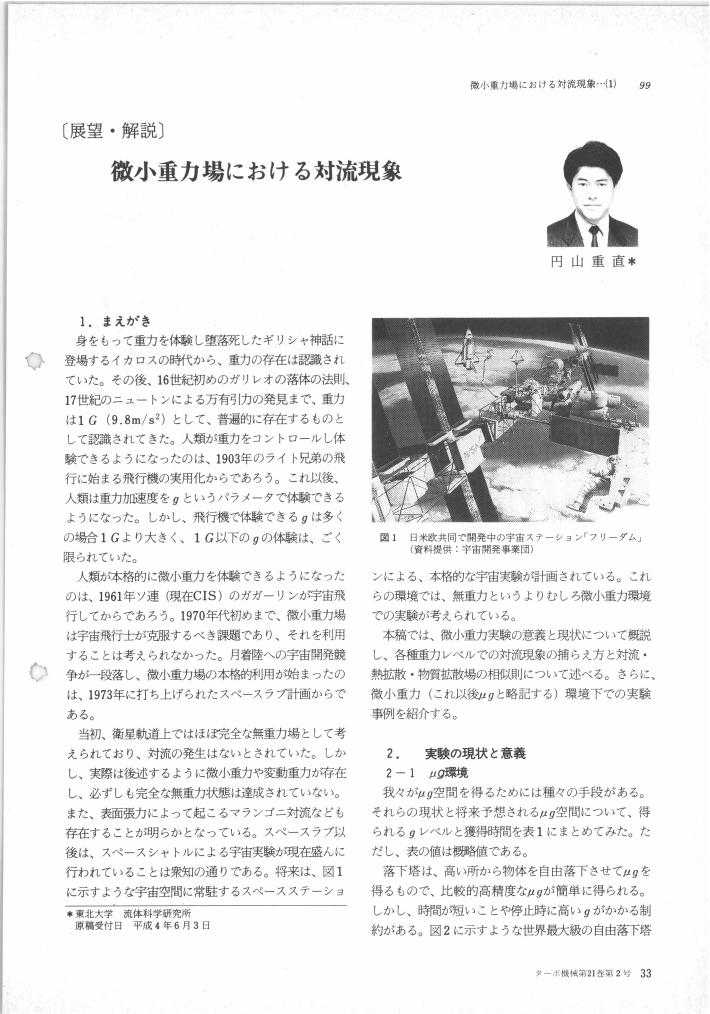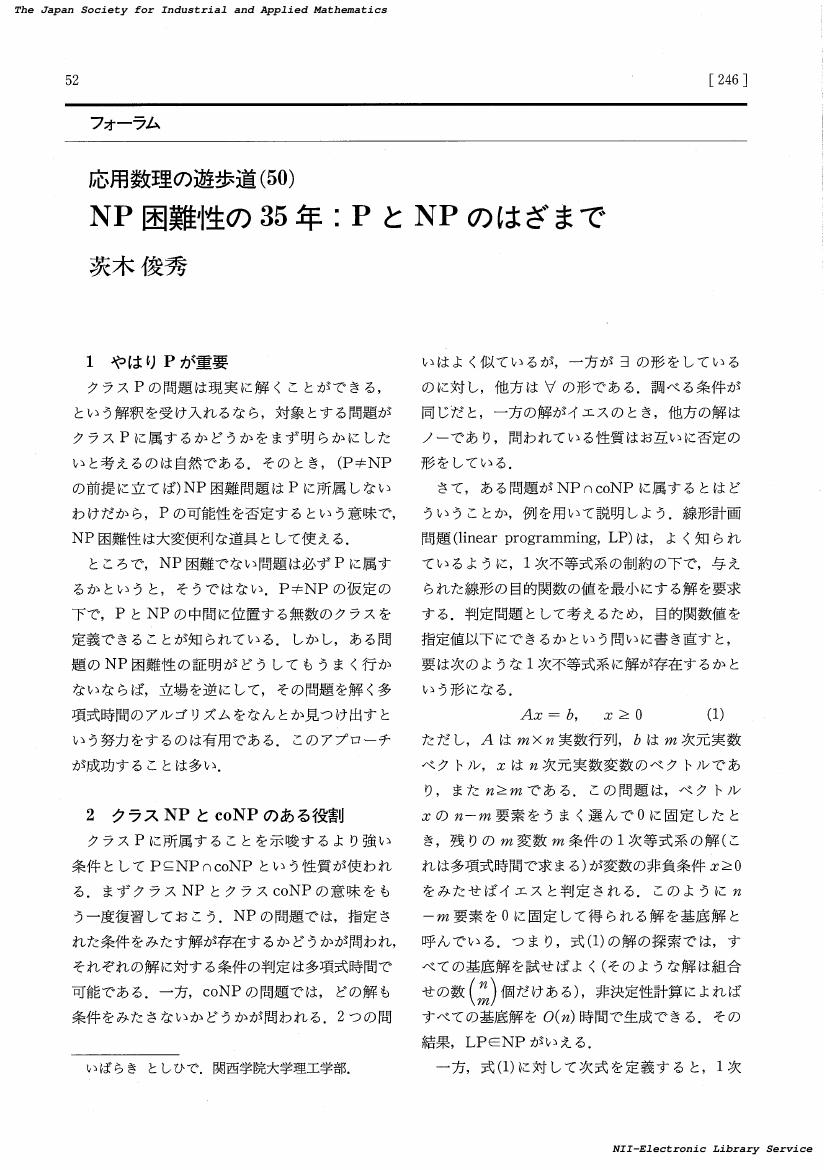- 著者
- 小川 束 田中 正明
- 出版者
- 四日市大学
- 雑誌
- 四日市大学論集 (ISSN:13405543)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.289-300, 2019 (Released:2019-05-20)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
Cymbella janischii (A. W. F. Schmidt) De Toni and Gomphoneis minuta (Stone) Kociolek & Stoermer collected from the upper Tama River in Oume City, Tokyo, were examined with a scanning electron microscope (SEM). We present 56 pictures here which were taken from various directions as a basis for future research in taxonomy or morphology.
2 0 0 0 OA モンゴル帝国=元朝の軍隊組織 : とくに指揮系統と編成方式について
- 著者
- 大葉 昇一
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.7, pp.1135-1172,1286-, 1986-07-20 (Released:2017-11-29)
Chinghis khan reorganized his troops in accordance with the decimal system in 1204 before he attacked the Naiman tribe. This formation was a military unit, but on the other hand, it was also an administrative unit. This system is called the Ch'ien-hu-zhi 千戸制, which has remained the standard system in the Mongol Empire since then. The features of this formation are a simple chain of command, a simple style of organization and ease of mobilization. It functioned very effectively. But this formation had irregular characteristics and various ploblems. For example, the chief of the Ch'ien-hu 千戸 (chiliarchs) posessed a Po-hu 百戸 (centurions) which was under his direct control. He held the post of the chief of the Po-hu concurrently. And the chief of the Po-hu posessed a Shi-hu 十戸 (decurions), which was under his direct control. He held the post of the chief of the Shi-hu concurrently. In these cases, we find the traces remaining of the body guard formation of clan faction organization. These cases do not describe the usual military formation of the Mongol empire. At least in the period of the Yuan dynasty, the hierarchy of officers was systematized bureaucratically and the officer's compentence was restricted reasonably. However, in the cace of the Shih-wei-ch'in-chun 侍衛親軍 (the imperial personal army), there was not a solitary commander who could lead the whole army in the bureaucratic system, in order to prevent an army clique from appearing. On the contrary, high officers of the central government were able to occupy the post of the solitary commander. It was too difficult to prevent men from concentrating power. They were the Mongolian and the Se-mu-ren 色目人 who stood on the basis of the Shih-wei-ch'in-chun. There are various explanations about the Ch'ien-hu. The correct explanation is that it was organized with one thousand hu 戸 (households), which were able to offer one thousand soldiers. In Mongol, the general idea of hu was that it was a kinship group, each such group with one manhood was counted as one hu, whose man was destined to be a soldier. A group with two soldiers was counted as too hu, and so on. Therefore, every hu had only one male member who should be a soldier. In Mongol it was the social custom that they counted the number of hu this way. The Ch'ien-hu was the military and administrative unit organized with one thousand hu each of which offered one soldier. However the number of members or hu was not mathematically strict. The Yuan dynasty used the system of Ch'ien-hu when it organized the Chinese into the Han-chun 漢軍. But the households of Han-chun could not stand the military economic burden. Therefore, the Yuan dynasty had to allow military households, which could not offer a soldier, to mainly bear military expenses. Consequently, the capacity for mobilization did not correspond to the fixed numbers in accordance with the decimal system. This difference resulted from the fact that the military formation of the nomadic society was applied without revision to the farming society. However, after the middle of the Yuan period, the formations of Han-chun were completed relatively, resulting in the military of the Mongols and the Se-mu-ren severely lacking in soldiers. This paper aims at describing the general idea of the military formation of the Mongol empire and the Yuan dynasty and how to solve it's structural deficiencies from the viewpoint of both the chain of command system and the style of organization.
2 0 0 0 OA 2022年 電気学会産業応用部門大会 大会開催案内と論文募集
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, no.9, pp.NL9_2, 2021-09-01 (Released:2021-09-01)
- 著者
- Kota Murai Satoshi Honda Yasuhide Asaumi Teruo Noguchi
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-21-0522, (Released:2021-07-17)
- 参考文献数
- 2
2 0 0 0 OA 有翼回収型ロケットの研究課題
- 著者
- 長友 信人
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.152-156, 1984-01-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 2
2 0 0 0 OA 微小重力場における対流現象
- 著者
- 円山 重直
- 出版者
- 一般社団法人 ターボ機械協会
- 雑誌
- ターボ機械 (ISSN:03858839)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.99-105, 1993-02-10 (Released:2011-07-11)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA NP困難性の35年 : PとNPのはざまで(応用数理の遊歩道(50),フォーラム)
- 著者
- 茨木 俊秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.246-249, 2007-09-26 (Released:2017-04-08)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 OA 中小企業雇用者におけるワーク・ファミリー・コンフリクトに関連する要因
- 著者
- 熊谷 麻紀 五十嵐 久人
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.12, pp.850-859, 2020-12-15 (Released:2020-12-31)
- 参考文献数
- 48
目的 本研究は,国内の中小企業雇用者のWFCは生活習慣や就労状況とどのような関係があるのか明らかにすることとした。方法 研究協力の得られた中小企業4社294人の従業員を対象に,自記式質問紙調査を実施した。調査項目は基本属性,就労状況,生活習慣,多次元的ワーク・ファミリー・コンフリクト尺度日本語版(WFCS),主観的健康感,主観的ストレス度とした。WFCの下位尺度であるWork Interference with Family(仕事から家庭への葛藤:WIF)とFamily Interference with Work(家庭から仕事への葛藤:FIW)スコアを高低で2群化し,これらを従属変数にロジスティック回帰分析を行い,関連する要因を検討した。結果 227人から回答を得て,欠損のない185人を分析対象とした。男性146人(78.9%),女性39人(21.1%),平均年齢43.6±11.2歳,配偶者および子がいる者の割合は6割弱で,WIF・FIWそれぞれの中央値は3.0,2.3であった。 WIFの2群間では平均労働時間(h/日),休暇取得のしやすさ,欠食の有無等に有意差があり,FIWの2群間では休暇取得のしやすさ,主観的健康感,主観的ストレス度に有意差が認められた。 ロジスティック回帰分析の結果,WIFには「欠食の有無」,「主観的ストレス度」,「平均労働時間(h/日)」,「年齢」,「主観的健康感」,「休暇取得のしやすさ」との関連が認められ,FIWには「主観的健康感」のみ関連がみられ,異なる要因が抽出された。結論 中小企業雇用者のWFCに関連する要因を検討した結果,仕事から家庭への葛藤(WIF)を低下させるためには,適切な生活習慣を送ること,長時間労働の短縮や雇用者が休暇を取得しやすい職場環境の改善を要し,家庭から仕事への葛藤(FIW)を低下させるためには,ストレスとうまく向き合い,精神的安定を図り,主観的健康感を高めていくことが必要となる可能性が示された。
2 0 0 0 OA パネルディスカッション
- 出版者
- 日本鼻科学会
- 雑誌
- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.425-438, 1992-02-01 (Released:2010-03-11)
2 0 0 0 OA ナラティヴ研究と「日常的な民俗誌実践」 日本の旧産炭地筑豊における遺産と記憶
- 著者
- 川松 あかり
- 出版者
- 日常と文化研究会
- 雑誌
- 日常と文化 (ISSN:21893489)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.19-33, 2020 (Released:2021-08-31)
2 0 0 0 OA 締約国会議における国際法定立活動
- 著者
- 柴田 明穂
- 出版者
- 世界法学会
- 雑誌
- 世界法年報 (ISSN:09170421)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.25, pp.43-67, 2006-03-31 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 77
- 著者
- Yoshifumi Mochinaga Hirofumi Fujie Masateru Mito
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- IEEJ Transactions on Industry Applications (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.3, pp.336-343, 1987-03-20 (Released:2008-12-19)
- 参考文献数
- 9
2 0 0 0 OA 持続的関係を創る相互行為としての物乞い ――タンザニア・ダルエスサラームの事例――
- 著者
- 仲尾 友貴恵
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.23-40, 2019-02-01 (Released:2021-07-10)
- 参考文献数
- 24
自らの労働で生計を立てられない人々による経済活動である「物乞い」は、「自分がいかに悲惨な境遇にあるかを、金を恵んでくれる側にアピールすること」と同視されてきた。それを行う人々である「物乞」については、対面する人々とはほどんど会話もせず、困窮性の訴えに徹する存在というイメージが共有されてきた。しかし、こうしたイメージに反し、タンザニアのダルエスサラームという都市の路上では、彼らが朗らかに通行人と挨拶を交わし、談笑に興じる姿が見られる。 物乞いという営みの理論的説明を試みた先行研究は、それを匿名的関係性においてなされると前提して議論を蓄積してきた。しかし、この前提は人類学的研究をはじめとする経験的知見と矛盾する。先行研究は物乞いを「匿名的関係性において困窮性をアピールする営み」と「顔馴染みから支援を受けられる営み」とする二つの見解を提示したが、これらの接続作業は十分になされていない。 本稿はダルエスサラームの住民が一年以上に亘り同じ場所で行う物乞いに着目し、ここでみられる物乞―非物乞のやり取りを相互行為論的知見に照らして解釈することで、先行研究の溝を埋める作業に貢献する。本稿の分析から、常に相手を適切に尊重した所作を返すことで出会った相手との関係性をより友好的なもの、つまり、より継続可能なものへと維持または変化させる営みとしての物乞いの側面が明らかとなった。住民が継続的に行う物乞いとは、匿名的関係性を個別的なものに変化させ、その個別性の獲得によって、贈与が含まれる物乞いという営みの継続可能性を高めていくような、具体的文脈に即した個別的な相互行為の集積である。
2 0 0 0 OA 急傾斜ヒノキ人工林における伐採方法の違いによる細土, 土砂, リター移動量の変化
- 著者
- 中森 由美子 瀧井 忠人 三浦 覚
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.3, pp.120-126, 2012-06-01 (Released:2012-07-05)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 5 5
急傾斜地の若齢ヒノキ人工林において, 処理の違い (皆伐, 強度間伐, 通常間伐) による表土移動量 (細土, 土砂, リター) の変化を明らかにするため, 土砂受け箱法によって, 処理前後4年間にわたる表土移動量を測定し, 処理ごとの細土, 土砂, リター移動レート (g m−1 mm−1) を比較した。細土, 土砂, リター移動レートは, 皆伐処理後に著しく増加した。一方, 強度間伐区, 通常間伐区では, 処理前後で細土, 土砂移動レートの変化は認められなかった。林内の相対照度および林床植生は, 通常間伐, 強度間伐, 皆伐の順に伐採強度が高いほど増大した。強度間伐や通常間伐が表土移動量に与える影響は, 皆伐区に比べて小さいことが明らかとなった。皆伐区や強度間伐区では, 植生回復の増加による土砂移動抑制効果が, 伐倒木処理などの人為的な地表撹乱によって相殺された可能性が考えられた。以上から, 急傾斜ヒノキ人工林で森林管理を行う場合, 作業時の地表撹乱を最小限にすることと, 速やかな植生回復を促すことを調和させることが林地の土壌を保全する上で重要であると考えられた。
- 著者
- Yoshimi KISHIMOTO Emi SAITA Chie TAGUCHI Masayuki AOYAMA Yukinori IKEGAMI Reiko OHMORI Kazuo KONDO Yukihiko MOMIYAMA
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.237-245, 2020-06-30 (Released:2020-06-30)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 2 15
Green tea and coffee contain various bioactive compounds (e.g., polyphenols), and their consumption has been proposed to decrease the risk of cardiovascular diseases. Here, we investigated the associations between the consumption of green tea and that of coffee and the prevalence of coronary artery disease (CAD) in Japanese patients. The study group was 612 patients who underwent coronary angiography at Tokyo Medical Center between July 2008 and February 2017. CAD was confirmed in 388 of the patients: one-vessel disease (1-VD, n=166); two-vessel disease (2-VD, n=112); three-vessel disease (3-VD, n=110). Myocardial infarction (MI) was found in 138 patients. After adjustment for well-known atherosclerotic risk factors and other dietary habits, greater green tea consumption was significantly inversely associated with CAD prevalence (p for trend=0.044), and the patients who drank >3 cups/d had a lower prevalence of CAD compared to those who drank <1 cup/d (odds ratio [OR]: 0.54, 95% CI: 0.30-0.98). Greater green tea consumption (>3 cups/d) was also associated with a decreased prevalence of 3-VD (OR: 0.49, 95% CI: 0.24-0.98, p-trend=0.047) and MI (OR: 0.51, 95% CI: 0.27-0.97, p-trend=0.037). In contrast, coffee consumption was not associated with CAD or MI. In subgroup analyses, the inverse association between green tea consumption and CAD or MI was found in the high intake groups of vegetables or fruits but not in the low intake groups of vegetables or fruits. These results suggest a beneficial effect of green tea consumption, especially with a diet rich in vegetables and fruits, against coronary atherosclerosis in Japanese.
2 0 0 0 OA 橋爪大三郎編『小室直樹の世界――社会科学の復興をめざして』
- 著者
- 友枝 敏雄
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.301-303, 2014 (Released:2015-09-30)
2 0 0 0 OA 消費者のきのこに対する意識調査と新規利用法の開発
- 著者
- 関根 加納子 鷲見 亮 森 伸夫 吉本 博明 江口 文陽
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.3-11, 2011-01-15 (Released:2013-07-16)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
Developing new markets and uses for mushrooms are important to the mushroom growers and industry. We conducted an attitude and awareness survey among consumers towards mushrooms in order to identify their possible new uses. The initial results suggested that many consumers had high interest in using medicated cosmetics made from mushrooms. We therefore studied the effects of mushrooms on platelet aggregation and chemokine gene expression which are both indicators of the state of lifestyle diseases and rough skin. The results indicated that several species of mushroom had high inhibition effects on these indicators, and suggested that these species would have strong potential as raw materials in such medicated cosmetics products as those for whitening, and for treating skin against rough surfaces and wrinkles.
- 著者
- 井上 太貴 岡本 透 田中 健太
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- pp.2041, (Released:2021-08-31)
- 参考文献数
- 48
半自然草原は陸上植物の多様性が高い生態系であるが、世界でも日本でも減少している。草原減少の要因を把握するには、各地域の草原の分布・面積の変遷を明らかにする必要があるが、これまでの研究の多くは戦後の草原減少が扱われ、また、高標高地域での研究は少ない。本研究は、標高 1000 m以上の長野県菅平高原で、 1722年頃-2010年までの約 288年間について、1881-2010年の 130年間については地形図と航空写真を用いて定量的に草原の面積と分布の変遷を明らかにし、 1722年頃-1881年の約 159年間については古地図等を用いて定性的に草原面積の変遷を推定した。 1881年には菅平高原の全面積の 98.5%に当たる 44.5 km2が一つの連続した草原によって占められていた。1722-1881年の古地図の記録も、菅平高原の大部分が草原であったことを示している。しかし、2010年には合計 5.3 km2の断片化した草原が残るのみとなり、 1881年に存在した草原の 88%が失われていた。草原の年あたり減少率は、植林が盛んだった 1912-1937年に速く、 1937-1947年には緩やかになり、菅平高原が上信越高原国立公園に指定された 1947年以降に再び速くなった。全国の他地域との比較によって、菅平高原の草原減少は特に急速であることが分かった。自然公園に指定された地域の草原減少が、全国平均と比べて抑えられている傾向はなかった。草原の生物多様性や景観保全のためには、自然公園内の草原の保全・管理を支援する必要がある。
- 著者
- Koji Ueda Takashi Nagai
- 出版者
- Pesticide Science Society of Japan
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.267-273, 2021-08-20 (Released:2021-08-31)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2
We investigated the relative sensitivity of duckweed Lemna minor and six species of algae to seven herbicides, using an efficient high-throughput microplate-based toxicity assay. First, we assessed the sensitivity of L. minor to the seven herbicides, and then we compared its sensitivity to that of previously published data for six algal species based on EC50 values. For five herbicides, the most sensitive species differed: L. minor was most sensitive to cyclosulfamuron: Raphidocelis subcapitata was most sensitive to pretilachlor and esprocarb: Desmodesmus subspicatus was most sensitive to pyraclonil; and Navicula pelliculosa was most sensitive to pyrazoxyfen. Simetryn was evenly toxic to all species, whereas 2,4-D was evenly less toxic, with only small differences in species sensitivity. These results suggested that a single algal species cannot represent the sensitivity of the primary producer assemblage to a given herbicide. Therefore, to assess the ecological effects of herbicides, aquatic plant and multispecies algal toxicity data sets are essential.
2 0 0 0 OA マクロデータから読み解くAMLO政権下のメキシコ経済の実情
- 著者
- 内山 直子
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.32-50, 2020 (Released:2020-01-31)
- 参考文献数
- 12
2018年12月に就任した左派のアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領は、それまでの新自由主義を否定する言説を繰り返すとともに自らの政権奪取を「第4の変革(Cuarta Transformación)」と位置づけ、就任直後から矢継ぎ早に公約を実行に移し、2019年10月まで70%近い支持率を維持し続けてきた。同大統領は就任から10カ月となる2019年9月に発表された政府年次報告書(Primer Informe de Gobierno)において、100項目の政権公約のうち、79項目をすでに「実現した」とその成果をアピールした。一方で国内経済に関しては、政権発足当初は2.7%と予想されていた2019年の経済成長率は11月の最新予想で0%まで引き下げられる事態となっているほか、治安状況にも改善がみられず、殺人件数は2018年を上回り、過去最多となることが確実視されている。AMLO政権の言説とメキシコ経済の実態の乖離はなぜ起きているのか、本稿では月次マクロデータを用いてその実情を明らかにするとともに、対外要因に加え、財政規律重視の行き過ぎた緊縮財政(公務員改革)が経済停滞の要因となっていることを指摘する。