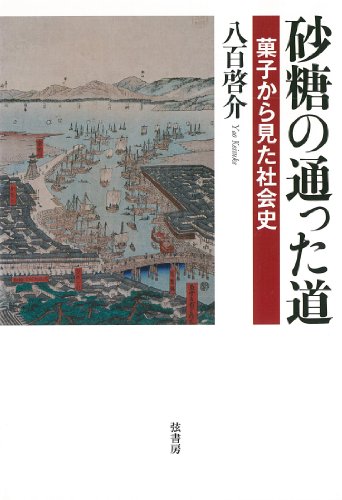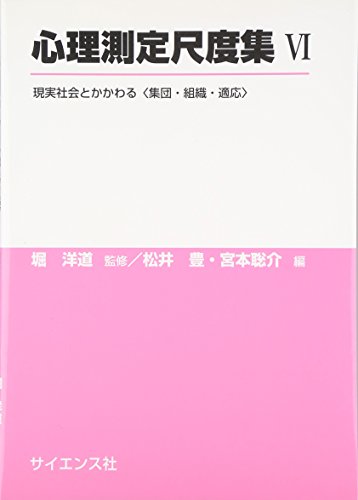- 著者
- 鈴木 哲 秋場 真人 齊藤 正克
- 出版者
- 社団法人プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌 (ISSN:09187928)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.10, pp.699-706, 2006-10-25
- 被引用文献数
- 2
核融合装置炉内機器の中で最も高い熱負荷を受けるダイバータについて,必要となる機能やその機能を満たすために要求される条件および構造上の特徴や設計の考え方などを,主として国際熱核融合実験炉ITERを例にとって熱・構造工学的な視点から解説するとともに,核融合原型炉ダイバータへの展望についても述べる.
1 0 0 0 カール一二世の自己戴冠 : 儀礼のなかのスウェーデン絶対主義
- 著者
- 入江 幸二
- 出版者
- 関西大学
- 雑誌
- 史泉 (ISSN:03869407)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.1-19, 2002-07
- 著者
- 田中 享英
- 出版者
- 北海道大学文学研究科= The Faculty of Letters, Hokkaido University
- 雑誌
- 北海道大学文学研究科紀要 (ISSN:13460277)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, pp.1-40, 2001-03-01
1 0 0 0 OA 苦痛の薬理学
- 著者
- 佐藤 公道
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.1, pp.13-18, 2007 (Released:2007-01-12)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
痛み(痛覚)に関する研究は,複雑であるが故に,他の感覚(視・聴・触・味・嗅)に比べて遅れている.生理的に重要な生体警告系の痛み以外の痛み(感覚と情動両面)はヒトのQOLを低下させる要因である.痛みを完全にコントロールする術を手に入れるために,動物実験は不可欠である.本稿では,痛みの定義,動物における神経因性疼痛を含む痛みの評価法と動物モデル,感覚としての痛みの成立機序について,筆者の独断と偏見を交えて概説し,さらに,研究が緒についたばかりである痛みに伴う負の情動と扁桃体の関連についての筆者らのデータを紹介する.
1 0 0 0 ヘリコバクター・ピロリ除菌による胃がん予防の基礎的研究
(研究目的)ヒト胃粘膜におけるヘリコバクター・ピロリ(Hp)感染は、慢性胃炎、消化性潰瘍のみならず胃発がんとも関連すると考えられている。本研究ではHp除菌前後の胃粘膜における発がんと関連した諸因子の変化について検討することを目的としており、今年度はその予備的検討を行った。(方法と結果)Hp除菌判定法に関する検討:除菌治療後の判定にHpのureAをターゲットとしたPCR法を併用し、治療1カ月後の時点で通常の方法でHp陰性と判断された症例の中にもPCR法ではHp陽性と判断される症例が少なくないことが明かとなった。これらの症例の少なくとも一部が臨床的にHp感染の再燃を来すものと考えられた。医原性Hp感染に関する検討:内視鏡を介する医原的なHp感染の可能性を検討するため内視鏡検査前にHp陰性であった症例を経過観察し、内視鏡検査後自覚症状的にも、また血清学的にもHp感染が起こっていないことを確認した。Hpサイトトキシン遺伝子の解析:Hpの菌体側の病原因子として重要なサイトトキシン遺伝子vacAの多型性についてPCR-RFLP法で解析し、各臨床分離株の間で著しい多様性があることが明かとなった。胃粘膜におけるケモカイン発現の解析:Hp感染胃粘膜における炎症反応の解析のため、胃粘膜でのケモカインの発現をRT-PCR法などで検討した。IL-8などのCXC型ケモカインだけでなく、MCP-1、RANTESなどのCC型ケモカインも高頻度に発現していることが明かとなった。(考案)本研究によってHp除菌治療評価に関する有用な情報が得られ、また胃内視鏡検査に伴うHp感染の危険性はほとんどないことが確認された。また、Hpの菌体側因子、Hp感染胃粘膜における慢性炎症病態の解析も進んできたので、これらの情報をもとに、実際に慢性胃炎でHp除菌を希望する患者の胃粘膜における諸因子の治療前後における変化についての検討に着手している。
1 0 0 0 クリスティーヌ=ド=ピザンと「ばら物語論争」 : Christine de Pisan et "le querelle du Roman de la Rose" (聖心会渡来五十周年記念)
- 著者
- 木間瀬 精三
- 出版者
- 聖心女子大学
- 雑誌
- 聖心女子大学論叢 (ISSN:00371084)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.36-71, 1958-02-01
1 0 0 0 OA 準結晶の数理
- 著者
- 藤原 毅夫
- 出版者
- 一般社団法人日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:09172270)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.117-134, 1991-06-14
Quasicrystals are newly discovered equiliblate systems, showing diffraction patterns of the sharp and densely distributed spots with the crystallographically disallowed symmetry. These materials open a new field of condensed matter physics. Mathematical aspects of quasicrystals are briefly reviewed, including several general methods constructing quasiperiodic systems, generalized crystallography and fractal character of electronic structures.
1 0 0 0 OA Comparison of Gastrointestinal Adverse Effects of Ketoprofen between Adult and Young Cats
- 著者
- Kenji TAKATA Yoshiaki HIKASA Hiroshi SATOH
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.11-0563, (Released:2012-07-10)
- 被引用文献数
- 2
This study elucidated differences in predisposition to the gastrointestinal adverse effects of ketoprofen between young and adult cats. Ketoprofen was administered subcutaneously (2.0 mg/kg, s.c.) once a day for 3 days. The animals were sacrificed 24 hr after final injection to allow examination of gastrointestinal mucosal lesions. Ketoprofen caused gastric lesions in adult cats (>6 months) but not in young cats (<3 months). Ketoprofen caused more severe small intestinal lesions in adult cats than in young cats. In the study of prevention of lipopolysaccharide (LPS)-induced hyperthermia using ketoprofen, young and adult cats of both sexes were administered LPS (0.3 μg/kg, intravenously), and body temperature was measured 24 hr later. Ketoprofen was administered subcutaneously 30 min before LPS injection. LPS-induced hyperthermia was almost completely inhibited by pretreatment with ketoprofen in both adult and young cats. In the pharmacokinetics of ketoprofen, plasma concentrations were analyzed by high-performance liquid chromatography. No significant differences were observed in plasma concentrations of two mirror-image R(−) and S(+) ketoprofen between young and adult cats from 0.5–4 hr after injection. As observed in a previous study using flunixin, the degree of gastrointestinal damage was unrelated to plasma concentrations of ketoprofen. The results of this study demonstrated that ketoprofen is safer for use in young cats than in adult cats from the viewpoint of gastrointestinal adverse effects.
- 著者
- Mari VAINIONPÄÄ Marja RAEKALLIO Elina TUHKALAINEN Hannele HÄNNINEN Noora ALHOPURO Maija SAVOLAINEN Jouni JUNNILA Anna HIELM-BJÖRKMAN Marjatta SNELLMAN Outi VAINIO
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.12-0180, (Released:2012-07-09)
- 被引用文献数
- 1 15
The objective of this study was to compare the method of thermography by using three different resolution thermal cameras and basic software for thermographic images, separating the two persons taking the thermographic images (thermographers) from the three persons interpreting the thermographic images (interpreters). This was accomplished by studying the repeatability between thermographers and interpreters. Forty-nine client-owned dogs of 26 breeds were enrolled in the study. The thermal cameras used were of different resolutions—80 × 80, 180 × 180 and 320 × 240 pixels. Two trained thermographers took thermographic images of the hip area in all dogs using all three cameras. A total of six thermographic images per dog were taken. The thermographic images were analysed using appropriate computer software, the FLIR QuickReport 2.1. Three trained interpreters independently evaluated the mean temperatures of hip joint areas of the six thermographic images of each dog. The repeatability between thermographers was >0.975 with the two higher-resolution cameras and 0.927 with the lowest resolution camera. The repeatability between interpreters was >0.97 with each camera. Thus the between-interpreter variation was small. The repeatability between thermographers and interpreters was considered high enough to encourage further studies with thermographic imaging in dogs.
1 0 0 0 カルツァ・クライン理論
- 著者
- 加藤 正昭
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.119-126, 1985
強い相互作用から重力までのすべての相互作用を統一する理論をつくることは, 素粒子論の夢である. この夢の実現を目指す有力な指導原理がカルツァ・クライン理論である. この理論では, 時空は4より大きな次元をもつという一見現実ばなれした仮定をおき, 素粒子の内部対称性を, 拡張された時空の幾何学的な対称性に帰着させる. この理論の基本的な考え方と, 現在ぶつかっているいくつかの問題点を紹介する.
1 0 0 0 当用漢字体表についての林大氏の弁明を読む
- 著者
- 大岩 正仲
- 出版者
- 至文堂
- 雑誌
- 国語と国文学 (ISSN:03873110)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.12, pp.47-54, 1949-12
- 著者
- 白井 祐浩
- 出版者
- 九州産業大学大学院附属臨床心理センター
- 雑誌
- 心理臨床研究 (ISSN:18800599)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.23-26, 2006
1 0 0 0 砂糖の通った道 : 菓子から見た社会史
1 0 0 0 OA ナンシー・K・ストーカー著『出口王仁三郎 帝国の時代のカリスマ』
- 著者
- 川口 典成
- 出版者
- 東京大学文学部宗教学研究室
- 雑誌
- 東京大学宗教学年報 (ISSN:02896400)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.171-178, 2010-03-31
書評/Book Reviews
1 0 0 0 OA ビデオ・フィードバックを用いた自閉症圏障害児と母親に対するコミュニケーション支援
- 著者
- 財部 盛久
- 出版者
- 琉球大学
- 雑誌
- 琉球大学教育学部障害児教育実践センター紀要 (ISSN:13450476)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.51-68, 2001-03-31
The present study examined the effectiveness of videotape feedback procedure in the development process of affective communication between an infant with autistic spectrum disorder and a mother who has an infant with autistic spectrum disorder, and mother's change in the manner of talking and behavior towards her infant with affective communication developed. Videotape observations at her home and videotape feedback interviews were conducted. As a result, the manner of talking and behavior towards her infant and the point of view understanding to her infant were changed. At the same time, mother-infant interactions were activated and affective communication between mother and infant was developed. Using PAC analysis, it could be confirmed that the mother had positive image for her infant. Based on these results, the effectiveness of videotape feedback procedure and PAC analysis were discussed.
私共は、平成16年度〜19年度にかけて、音声コミュニケーション障害者、高齢者、聴覚障害者、言語聴覚障害児者に対する支援システム、評価法の開発およびコミュニケーション援助の開発や臨床への応用を目的として、以下の3グループに分かれて研究を行ってきた。研究分担者や研究協力者は、文系と理系からなる学際的なメンバーで構成され、それぞれの専門性を活かした研究に取組み、成果を上げてきたことが特記される。3グループの研究は次の通りである。1.音声コミュニケーション障害者への支援システムの開発とコミュニケーション援助:神経筋病患者の自声による日英両言語のコミュニケーション支援システムの構築を行い、臨床への応用が可能であることを示した。コーパスベース方式でシステム構築を行った後、より少ないデータで構築可能なHMM音声合成方式でも試作を行い実用レベルに達するという評価結果を得た。2.聴覚障害者に対する支援システムの開発とコミュニケーション援助:聴覚障害児者や老人性難聴者のための残響環境下における聞きやすい拡声処理と補聴器のための音声処理方式の開発と実用化への適用を推進した。3.言語聴覚障害児者に対する支援システムの開発とコミュニケーション援助:高次脳機能に障害を持つ、後天性小児失語症児や中枢性聴覚障害児のコミュニケーション能力向上のための評価、指導法を開発し、発達性構音障害の鑑別診断となる基礎的研究と臨床への応用を行い、発達性読み書き障害児への基礎的、臨床的検討を行った。また、言語習得過程の不備からコミュニケーション障害が形成される可能性について問題提起した。
1 0 0 0 いにしへに恋ふらむ鳥はほととぎす--額田王の弓削皇子との贈答歌
- 著者
- 身崎 寿
- 出版者
- 万葉学会
- 雑誌
- 万葉 (ISSN:03873188)
- 巻号頁・発行日
- no.133, pp.p1-20, 1989-09
1 0 0 0 弓削皇子
- 著者
- 吉井 巌
- 出版者
- 帝塚山学院大学研究論集編集委員会
- 雑誌
- 帝塚山学院大学研究論集 (ISSN:02862956)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.1-15, 1968-12
1 0 0 0 現実社会とかかわる「集団・組織・適応」
- 著者
- 山岸 剛 柴原 聡子
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 建築雑誌 (ISSN:00038555)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.1606, 2010-07-20