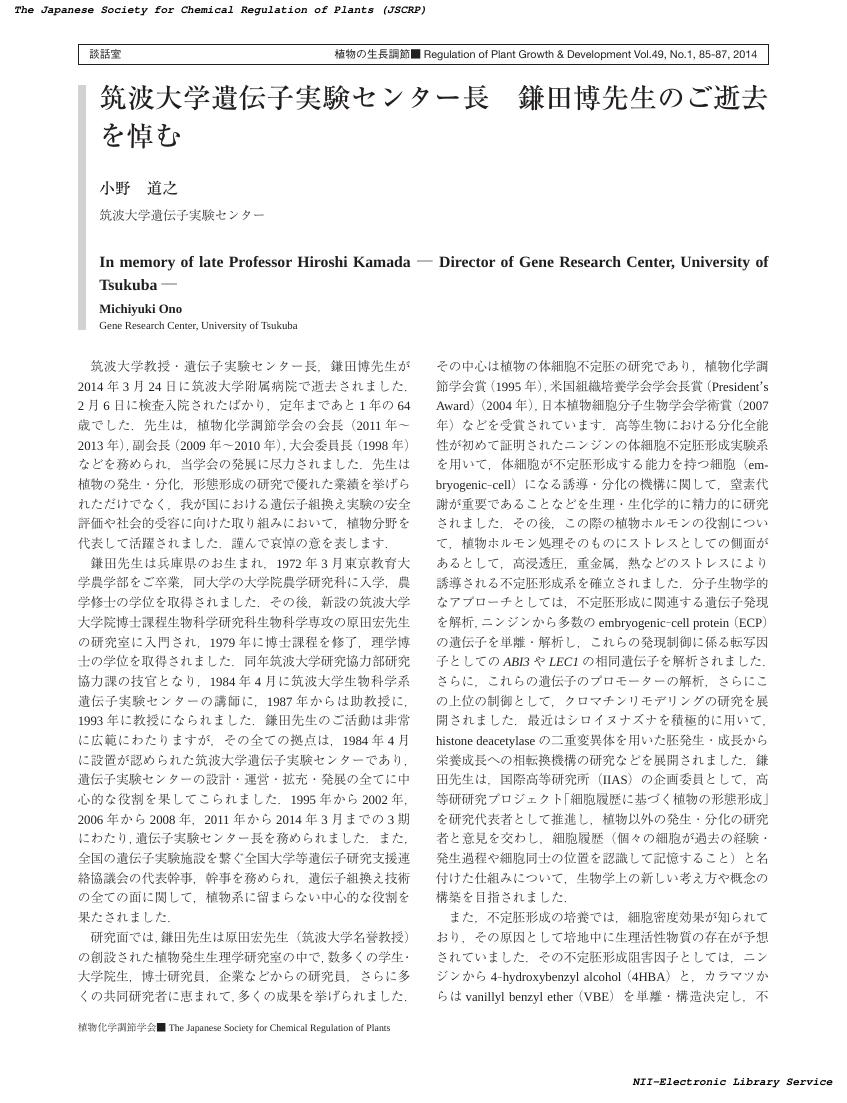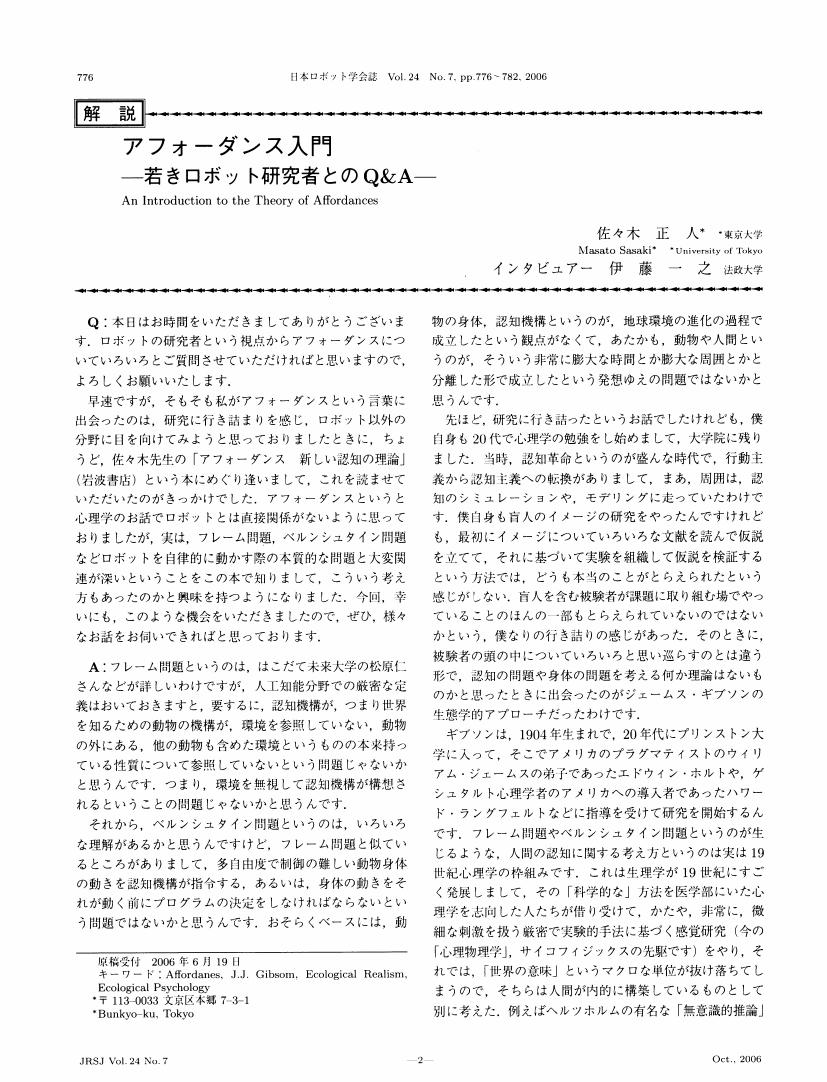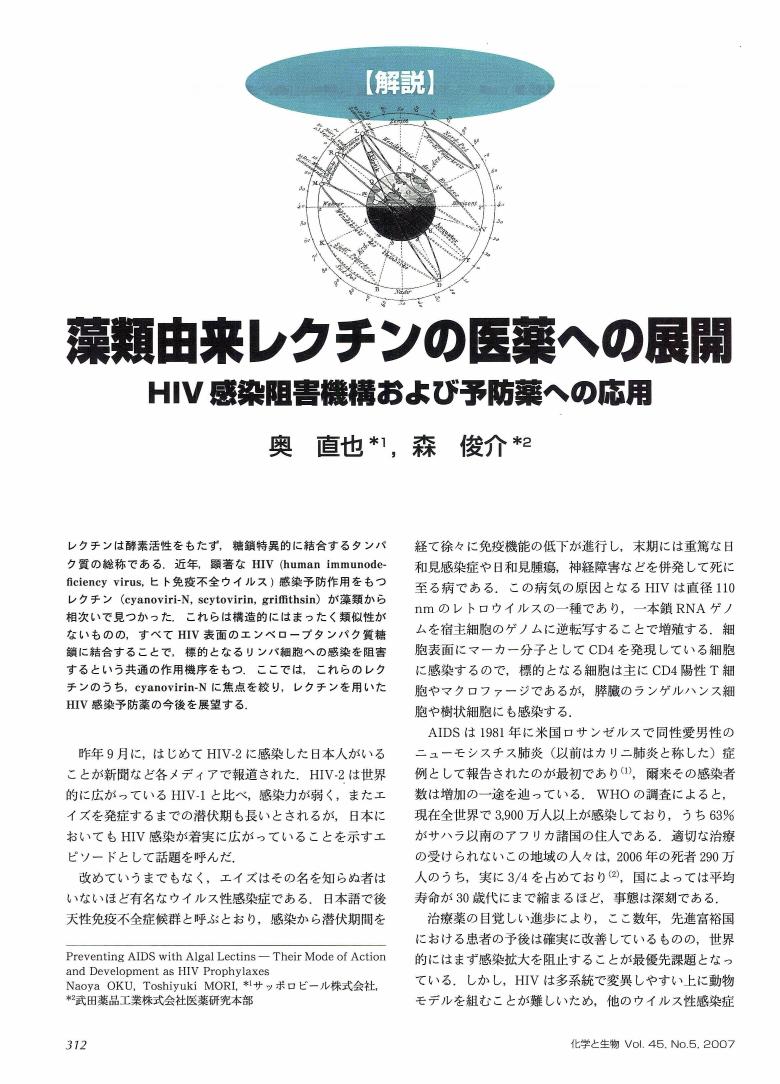- 著者
- 大島 希巳江
- 出版者
- 日本笑い学会
- 雑誌
- 笑い学研究 (ISSN:21894132)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.14-24, 2011-07-23 (Released:2017-07-21)
欧米などの低コンテキストな多民族社会と、日本のような高コンテキスト社会では人々の間で語られるジョークや笑い話の種類およびスタイルが異なる。コミュニケーションにおいて必要とされる要素がそこにはあらわれると思われる。そこで2010年4月から2011年3月の1年間で「日本一おもしろい話」プロジェクトを運営し、サイト上で日本各地からおもしろい話を募集した。毎週、投稿された話をサイトに掲載し、おもしろいと思う話に投票してもらうというシステムをとり、日本人がおもしろいと感じる話を分析することを試みた。その結果、560の有効な投稿があり、1949票の投票がされた。投票により、毎月のトップ10までを決定し、それらの話の分類と分析を行ったところ、多くが投稿者の体験談であることがわかった。全体としては言い間違いや同音異義語を使った、言葉に関する話が最も多かった。また、年代でみるとおもしろい話の多くは40代、50代、30代からの投稿であった。性別でみると、女性は突発的な偶然から起きる言い間違い・聞き間違いなどに関する話が最も多く、男性からの投稿は作り込まれた言葉遊び、文化・社会を反映した笑い話などが多いことがわかった。今回のプロジェクトで日本人のユーモアの傾向が一部明確になり、また今後の研究の貴重な資料になると考えている。
2 0 0 0 OA 体重を一定に保つ分子機構と肥満
- 著者
- 新谷 隆史
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.11, pp.725-731, 2018-10-20 (Released:2019-10-20)
- 参考文献数
- 28
脂肪細胞から分泌されるレプチンは,脳の視床下部に働いて摂食を強力に抑制する.肥満により脂肪組織が肥大するに従ってレプチンの分泌量が増加するため,レプチンによる食欲制御機構は動物の体重を一定に保つシステムとして機能していると考えられる.しかしながら肥満が続くと,レプチンが視床下部に作用しにくくなるレプチン抵抗性が生じることで肥満が解消しにくくなる.本稿では,レプチンの情報伝達制御機構ならびにレプチン抵抗性の形成機構について解説するとともに,われわれが最近明らかにしたチロシンホスファターゼであるPTPRJによるレプチンシグナルの制御機構について解説する.
- 著者
- Kazuki Nagata Katsuaki Oyama Atsushi Ota Chihiro Azai Kazuki Terauchi
- 出版者
- Applied Microbiology, Molecular and Cellular Biosciences Research Foundation
- 雑誌
- The Journal of General and Applied Microbiology (ISSN:00221260)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020.01.008, (Released:2020-03-30)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 3
The cyanobacterial circadian oscillator can be reconstituted by mixing the purified clock proteins KaiA, KaiB, and KaiC with ATP in vitro, leading to a 24-h oscillation of KaiC phosphorylation. The cyanobacterial mutant pr1 carrying valine instead of alanine at position 422 of KaiC (KaiC-A422V) lost the ability to shift the phase of the circadian rhythm. In this study, we analyzed KaiC-A422V to investigate the effect of this single-residue substitution on the in vitro reconstitution of KaiC oscillation. KaiC-A422V exhibited low amplitude oscillations of phosphorylation with a smaller amount of Kai complex than wild-type KaiC (KaiC-WT). Although KaiA can stimulate KaiC phosphorylation, the phosphorylation level of KaiC-A422V is much lower than that of KaiC-WT even at higher KaiA concentrations. It has been suggested that monomer shuffling of KaiC is involved in entraining the in vitro rhythm. To examine whether KaiC-A422V has the capacity for monomer shuffling, we used the difference in the amplitude of the phosphorylation rhythms between KaiC-WT and KaiC-A422V as the indicator of monomer shuffling. When KaiC-A422V and KaiC-WT were mixed, the amplitude of the phosphorylation rhythm changed according to the mixing ratio. This suggests that KaiC-A422V has a reduced ability to shuffle monomers in hexameric KaiC. In addition, the A422V mutation resulted in a change of the stability of the KaiC protein.
2 0 0 0 OA Boytchev法における筋皮神経の解剖学的検討
- 著者
- 森澤 豊 野口 政隆 川上 照彦 山本 博司 貞廣 哲郎
- 出版者
- 日本肩関節学会
- 雑誌
- 肩関節 (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.267-269, 1998-06-25 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
We studied the mechanism of musculocutaneous neuropathy associated with the Boytchev procedure in cadavers.(Materials and methods)The subjects we re 21 adult cadavers (42 shoulders) for anatomical study. The distance from the anterior end of the coracoid process to the site of the entry of the musculocutaneous nerve trunk into the coracobrachialis muscle was determined as A, the distance to the insertion of the short head of the biceps among the nerve branches as B, and the distance to the coracobrachialis insertion site as C. Then, the coracoid process (served to measure the insertion of the short head of the biceps and that of the coracobrachialis) was returned to its original position beneath the full-thickness of the subscapularis muscle by the original Boytchev method, and the distance from the anterior end of the coracoid process to the lower margin of the subscapularis was determined as D.(Results)A was 47.5±13.2mm, B was 30.1±6.2mm, C was 33.9±7.5mm and D was 33.3±5.3mm. A was below D, i. e., the entry site of the musculocutaneous nerve trunk was above the lower margin of the subscapularis muscle, and entrapment of the musculocutaneous nerve trunk by the subscapularis muscle was present in nine shoulders (21.4%).(Discussion)In patients where the site of the entry of the musculocutaneous nerve trunk into the coracobrachialis muscle is at a higer position than the lower margin of the subscapularis, it appears necessary to take technical precautions such as passing the severed coracoid process through the lower one third of the belly of the subscapularis.
2 0 0 0 OA 緑膿菌感染症とQuorum-Sensing機構
- 著者
- 舘田 一博
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.5, pp.999-1004, 2005-05-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 11
細菌の産生するホルモン様物質(autoinducer)を介した情報伝達機構,すなわちクオラムセンシング(Quorum-sensing)が微生物学・感染症学・化学療法学の分野で注目されている.これはビブリオ属細菌における菌数依存的な蛍光物質産生という現象から見つかってきたシステムであるが,その後,緑膿菌をはじめとする多くの病原細菌が本機構を用いて病原因子発現をコントロールしていることが明らかとなっている.また最近では,このautoinducer分子が生体細胞に対しても多彩な影響を及ぼしていることが報告され,菌側と生体側の両面から感染症の発症に関与する因子として注目されている.ここでは緑膿菌のクオラムセンシング機溝に焦点を当て,その基本構造と特徴を概説するとともに,本機構の感染病態形成における役割,クオラムセンシングをターゲットとした新しい感染症治療の可能性について述べてみたい.
- 著者
- 前薗 葉月 野杁 由一郎 上田 未央 野口 展生 藪根 敏晃 恵比須 繁之
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会学術大会 プログラムおよび講演抄録集 日本歯周病学会50周年記念大会プログラムおよび講演抄録集
- 巻号頁・発行日
- pp.75, 2007 (Released:2007-08-31)
2 0 0 0 OA 慶良間諸島渡嘉敷島渡嘉志久湾の魚類相:144 種の追加記録
- 著者
- 田中 翔大 下光 利明 瀬能 宏 宮崎 佑介
- 出版者
- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)
- 雑誌
- 神奈川県立博物館研究報告(自然科学) (ISSN:04531906)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.49, pp.107-118, 2020 (Released:2020-03-31)
2 0 0 0 OA 筑波大学遺伝子実験センター長 鎌田博先生のご逝去を悼む(談話室)
- 著者
- 小野 道之
- 出版者
- 一般社団法人 植物化学調節学会
- 雑誌
- 植物の生長調節 (ISSN:13465406)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.85-87, 2014-05-30 (Released:2017-09-29)
- 著者
- Masahiro Hayashi Moe Kawamura Yuki Kawashima Takeshi Uemura Takashi Maoka
- 出版者
- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN
- 雑誌
- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.92-102, 2020-03-01 (Released:2020-03-01)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 9
This study investigated the effect of a dietary supplement containing astaxanthin-rich extract derived from Paracoccus carotinifaciens (astaxanthin supplement) on the status of stress and sleep in individuals aged 20–64 years. Twenty-five subjects orally administered 12 mg astaxanthin/day of astaxanthin supplement for 8 weeks (astaxanthin group) and 29 subjects given a placebo (placebo group) were evaluated with Profile of Mood States 2nd Edition for stress and Oguri–Shirakawa–Azumi Sleep Inventory for Middle-aged and Aged version for sleep. We did not observe any significant intergroup differences in the stress and sleep. A subgroup analysis was performed after dividing the subjects into two groups: those who scored >65 and those who scored ≤65 in the “Depression–Dejection” dimension of Profile of Mood States 2nd Edition. The sleep of subjects who scored >65 (”Depression–Dejection”) showed significant improvement in the astaxanthin group compared with the placebo group, whereas no significant improvement was observed in stress and the other subjects. Our results indicate that people who tend to be strongly depressed may experience improved sleep after ingesting astaxanthin supplement. On the basis of the parameters tested, administration of astaxanthin supplement was not associated with any problems related to safety. Clinical registration: This study has been registered at the University Hospital Medical Information Network (https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000038619) on August 24, 2018 as “A study to evaluate the effect of intake of astaxanthin on the status of stress and sleep in adults,” Identification No. UMIN000033863.
- 著者
- Limei Hua Min Lei Sujuan Xue Xiaoling Li Shaojian Li Qi Xie
- 出版者
- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN
- 雑誌
- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.146-151, 2020-03-01 (Released:2020-03-01)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 9
The additive effect of high-intensity interval training to fish oil supplementation on newly diagnosed type 2 diabetes is unknown. 173 newly diagnosed type 2 diabetes patients were randomly assigned into the control group (received corn oil), fish oil group (eicosapentaenoic acid, EPA:docosahexaenoic acid, DHA = 3:2, total 2.0 g/day), and the fish oil + high-intensity interval training group. Three instructed high-intensity interval training sessions (Monday, Wednesday, and Friday; 10 × 60-s cycling bouts) were performed for 3 months. Glycaemic control was assayed by serum haemoglobin A1c, fast glucose, fast insulin, and adiponectin. Homeostatic model assessment of insulin resistance was utilized to determine the homeostasis of pancreatic function. Fat mass, triglycerides, total cholesterol, low-density lipoproteins, and high-density lipoproteins were measured to indicate cardiovascular risk. Within and between groups analysis were performed with linear mixed-effects modeling (95% CIs and p values). When compared with fish oil, fish oil + high-intensity interval training intervention has significant additive beneficial effects on haemoglobin A1c (p<0.01), fast glucose (p<0.001), homeostatic model assessment of insulin resistance (p<0.05), adiponectin (p<0.05), fat mass (p<0.01), and total cholesterol (p<0.01), but not on fast insulin level to newly diagnosed non-obese type 2 diabetes. High-intensity interval training has an additive effect on fish oil supplementation on glycaemic control, insulin resistance, cardiovascular risk, and fat mass, which indicates the potential necessity of combining high-intensity interval training with fish oil.
2 0 0 0 OA アフォーダンス入門―若きロボット研究者のQ&A―
- 著者
- 佐々木 正人
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.7, pp.776-782, 2006-10-15 (Released:2010-08-25)
- 被引用文献数
- 3 2
2 0 0 0 OA ツイッターデータと気象データから熱中症救急搬送者数を予測する
- 著者
- 布施 明 坂 慎弥 布施 理美 萩原 純 宮内 雅人 横田 裕行
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.573-579, 2019-08-31 (Released:2019-08-31)
- 参考文献数
- 10
目的:気象データに熱中症関連ツイートの要素を加えることで熱中症救急搬送者数を予測できるかを検討すること。対象・方法:2015〜2017年を対象とした。2015年東京データを用いて,平均気温と熱中症ツイート数から,熱中症救急搬送者数の予測式を作成した。次に,作成した予測式が他年次や他地域へも適応可能であるかを評価するため,他年次の東京都および,大阪府と神奈川県に関するデータでの検証を行った。結果:予測値と実数の相関係数は0.9726であった。ツイート数を用いたことで予測精度が向上した。他地域でも熱中症ツイート数の補足を加えた予測式は平均気温から算出した予測式よりも有用であった。考察・結論:熱中症の“リアルタイムでの”予防対策として,気象データ(平均気温)に熱中症関連ツイートデータを加えた予測式による熱中症救急搬送者数の予測は有用であると考えられた。
2 0 0 0 OA 防災無線で流されている放送内容と市町村勢の関係について
- 著者
- 永幡 幸司 大門 信也
- 出版者
- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.128-136, 2003-04-01 (Released:2009-10-06)
- 参考文献数
- 13
福島県下の全自治体を対象としたアンケート調査より, 各自治体における防災無線の設置状況, 及び, その運用状況を明らかにし, それらと, 各自治体の特徴を表す指標である市町村勢との関係について検討した。その結果, 防災無線の有無と市町村勢の間には直接的な関係がないこと, 防災無線を用いて放送される内容の間には, 防災情報, 行政情報, 農林水産情報, 学校情報, 選挙結果の順に社会的に容認されやすいという構造関係があり, 都市化の進んだ自治体であるほど, 社会的に容認される放送内容が少ないことが明らかとなった。
2 0 0 0 OA Factors Affecting Flood Evacuation Decision and Its Implication to Transportation Planning
- 著者
- Ma. Bernadeth LIM Hector LIM Jr. Mongkut PIANTANAKULCHAI
- 出版者
- Eastern Asia Society for Transportation Studies
- 雑誌
- Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies (ISSN:18811124)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.163-177, 2013 (Released:2013-12-21)
- 参考文献数
- 52
Evacuation decision during flood disasters indicates the choice of households to evacuate or stay from area at risk. This may be viewed as simple decision but involves complex behavioral and other external factors. Evacuation decision serves as key input to transportation planning in the event of flood, hence, careful consideration of the factors that determine this decision should be done. Such factors include broadly the characteristics of households and their capacity as well as risk-related factors. This review identifies the factors by bringing together findings from viewpoint of evacuation managers and social scientists as well as transportation planners. Further research is needed to identify the interrelationships of these factors for consideration in evacuation transportation planning and modeling.
2 0 0 0 OA メタ認知と自己注目がコーピングの柔軟性および抑うつに及ぼす影響
- 著者
- 中村 志津香 大塚 泰正
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.77-84, 2014 (Released:2014-11-20)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
ストレスフルな状況において、数あるコーピングの中のどのコーピングが有効であるのかは状況に依存する。そのため、状況に応じてコーピングを柔軟に使い分ける能力であるコーピングの柔軟性の重要性が指摘され、研究が進められてきている。これまでの研究では、コーピングの柔軟性における認知機能の役割を理解することが重要であるといわれ、認知機能の中でも1つの認知活動に固執することを避けたり、認知活動を柔軟に切り替えたりする能力が重要であると指摘されている。さらに、個人が実行することのできるコーピング方略が多様であることだけでは不十分であり、ストレッサーの変化に応じてコーピング方略の有効性をモニタリングする能力としてのメタ認知能力が必要であることが指摘されている。また、コーピングの柔軟性を規定するもう一つの要因として自己注目が挙げられ、自己注目の高い人はストレスフルな状況におかれた場合でも、自己へ注意が向かいやすく、柔軟なコーピングを行うことができない可能性が考えられる。こうした先行研究を踏まえ、本研究では、5つのメタ認知(認知能力への自信のなさ、心配に対するポジティブな信念、認知的自己意識、思考統制の必要性に関する信念、思考の統制不能と危機に関するネガティブな信念)と自己注目が抑うつに与える影響について、大学生396名(男性230名、女性166名)を対象に調査を行った。メタ認知と自己注目がコーピングの柔軟性と抑うつに影響を与えるモデルを作成した。共分散構造分析の結果、思考統制の必要性に関する信念からコーピングの柔軟性に正の関連が認められ、思考の統制不能と危機に関するネガティブな信念からコーピングの柔軟性に負の関連が認められた。さらに、コーピングの柔軟性は抑うつと負の関連があること、認知能力の自信のなさ、思考の統制不能と危機に関するネガティブな信念、自己注目は抑うつと正の関連があることが認められた。これらの結果から、非適応的な思考やコーピングを止める必要があると考えることができる人は、コーピングの柔軟性が高いことが明らかになった。一方、非適応的な思考やコーピングを止めることができないと考える人は、それを適応的な思考やコーピングに切り替えることができないことも明らかになった。また、自己注目とコーピングの柔軟性には関連が認められなかった。さらに、コーピングの柔軟性に富む人は抑うつが低いことが明らかになった。
2 0 0 0 OA 係留ビネット法による反応スタイルの分類
- 著者
- 北條 大樹 岡田 謙介
- 出版者
- 日本行動計量学会
- 雑誌
- 行動計量学 (ISSN:03855481)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.13-25, 2018 (Released:2018-11-03)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1
This study conducts a data-driven classification of the response styles for the 2,131 respondents of the SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) survey. In the standard Likert scale measurement, item responses reflect not only the latent traits of respondents but also their response style biases which are irrelevant for the purpose of the original measurement. The anchoring vignettes is an effective method to measure and correct for such biases. In this study, we first modeled the anchoring vignettes variables in the SHARE dataset using the Bayesian multidimensional item response model. Then, we classified the estimated individual response style parameters using the divisive analysis clustering. As a result, seven different clusters of response styles were obtained. While some of them correspond to the well-documented response styles, many of the clusters of respondents exhibit unique response styles which are both interpretable and relevant. Thus, bottom-up classification approach of response styles would undertake a key role in revealing the empirical analysis of item response behavior.
2 0 0 0 OA 『出張フットケア』と『靴を考える会』の活動について
- 著者
- 藤井 恵 西山 睦子 小林 茂 阪田 茂宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本フットケア学会
- 雑誌
- 日本フットケア学会雑誌 (ISSN:21877505)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.131-136, 2018-09-30 (Released:2018-09-30)
【要旨】2008 年よりフットケアサロンを持たずに関西地域の靴店,クリニック,自宅訪問の『出張フットケア』と,その他「靴と足」に関連する啓発活動を行ってきた.『出張フットケア』の特徴は,フットケアが必要とされる人のところへ直接行きサービスができることや靴店,クリニックとの連携でさらにトラブルの改善ができることにある.一方,1987 年に設立された「プロフェッショナルシューフィッティングを読む会」が現在大阪,東京,名古屋,広島,北海道,北陸など各地域で,「靴と足」に関係する集まりの中で勉強会を開催している.この専門知識や横のつながりを深める『靴を考える会』の活動と,『出張フットケア』と関連する啓発活動の,2 つの活動を紹介し,今後の課題を報告する.
2 0 0 0 OA 藻類由来レクチンの医薬への展開
- 著者
- 奥 直也 森 俊介
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.5, pp.312-319, 2007-05-01 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 52
2 0 0 0 OA 日本初の洋式公園 日比谷公園
- 著者
- 武智 ゆり
- 出版者
- 特定非営利活動法人 近代日本の創造史懇話会
- 雑誌
- 近代日本の創造史 (ISSN:18822134)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.26-27, 2009 (Released:2009-10-25)
2 0 0 0 OA 関東平野の地下に分布する先新第三系基盤岩類
- 著者
- 林 広樹 笠原 敬司 木村 尚紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.1, pp.2-13, 2006 (Released:2006-05-01)
- 参考文献数
- 78
- 被引用文献数
- 15 12
関東平野の地下に分布する先新第三系の地体構造に制約を与えるため,新第三系を貫通した深層ボーリング,および反射法地震探査のデータを収集した.収集したデータはボーリング49坑井,反射法地震探査31測線である.坑井ではコアまたはカッティングス試料により岩相を観察し,地体構造区分上の帰属を足尾帯,筑波花崗岩・変成岩類,領家帯,三波川帯,秩父帯,四万十帯およびこれらを覆う中生界の堆積岩類に区分した.また,坑井におけるVSP法またはPS検層データによって基盤岩の物性を調べたところ,より年代の古い地質体ほど大きなP波速度を示すことが明らかになった.この性質を用いて,反射法地震探査による地下構造断面を地体構造の観点から解釈し,関東平野地下における地体構造区分分布図を作成した.