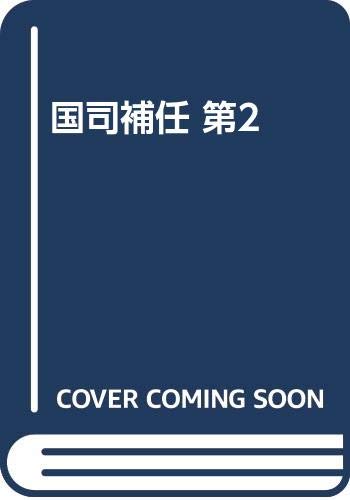- 著者
- 福石 信之 吉岡 美乃 赤木 正明
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.5, pp.259-264, 2005 (Released:2005-07-01)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 1
肥満細胞は抗原抗体反応によりヒスタミンや脂質メディエーターのみならず,サイトカインやケモカインなどを放出することで,アレルギー・炎症を形成する主な細胞の一つである.近年,肥満細胞の持つ貪食機能がクローズアップされ,それに伴い自然免疫系の細胞としての一面に脚光が集まりつつある.我々は現在ヒト肥満細胞株を用いて,菌体成分暴露におけるToll-like receptorの発現変化,細菌貪食のメカニズム,菌体成分暴露による他の免疫系細胞との関わりの変化,および抗菌ペプチドの発現と肥満細胞への作用を検討している.これらの知見を通じて,肥満細胞は獲得免疫系がIgEを産生した後,そのIgEを表面に捕捉してアレルギー・炎症を引き起こす細胞であるという概念から,IgEなど獲得免疫系の関与なしに外界からの異物の侵入に対して,直接的に防御·排除を行う結果として炎症を惹起しているという別の姿が見えてきた.
4 0 0 0 OA JAXAにおけるヘリコプタ全機落下試験
- 著者
- 少路 宏和
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.617, pp.182-187, 2005-06-05 (Released:2019-04-17)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 IR 現代ロシアの歴史認識問題 : 共産党によるスターリン再評価
- 著者
- 西山 美久
- 出版者
- 九州大学法学部政治研究室
- 雑誌
- 政治研究 (ISSN:02898357)
- 巻号頁・発行日
- no.67, pp.35-69, 2020-03
- 著者
- 鎌田 さゆり
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1283, pp.172-175, 2005-03-14
2003年11月の衆院選で民主党候補として宮城2区から2度目の当選を果たしたのですが、その年の12月9日に共に選挙を戦った連合宮城会長代理(当時)の恵美須(浩司)さんらが公職選挙法違反容疑で逮捕されました。 選挙期間中に有権者に電話をかけて支持をお願いするのに、電話かけを請け負った会社に対して報酬を支払っていました。
4 0 0 0 IR 『日本書紀』の素戔嗚尊 (特集 『日本書紀』研究の現在と未来)
- 著者
- 谷口 雅博
- 出版者
- 國學院大學
- 雑誌
- 國學院雜誌 = The Journal of Kokugakuin University (ISSN:02882051)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.11, pp.186-201, 2020-11
- 著者
- 金子 順一 堀尾 健一郎
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会学術講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, pp.586, 2005
5軸制御加工における工具姿勢の決定に際しては,工具軸と被削物·把持具との干渉の回避が必須となる.従来,この対策として,切削工具が取りうる工具姿勢の範囲を幾何演算によって求めるC—Space法が提案されている.本研究では,この幾何演算を,近年高速化·多機能化が著しいグラフィックスハードウェアの機能を用いて行う手法を提案する.これにより,高速な工具姿勢の決定が可能になると期待される.
- 著者
- 梁 小煒
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.223-273, 2021-11-29
- 著者
- 毛利 康秀
- 出版者
- 日本観光研究学会 = Japan Institute of Tourism Research
- 雑誌
- 日本観光研究学会全国大会学術論文集 = Proceedings of JITR annual conference (ISSN:2436617X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.145-148, 2021-12
4 0 0 0 IR キキはなぜ黒いワンピースを着るのか : スタジオジブリとファッション
- 著者
- 菊田 琢也
- 出版者
- 昭和女子大学近代文化研究所
- 雑誌
- 学苑 (ISSN:13480103)
- 巻号頁・発行日
- no.965, pp.84-87, 2021-03
4 0 0 0 OA びぶろす
- 著者
- 国立国会図書館総務部
- 出版者
- 国立国会図書館
- 巻号頁・発行日
- no.(92), 2021-12
4 0 0 0 OA 銅欠乏症による種々の血球減少症を併発した透析患者の5例
- 著者
- 池田 弘 櫻間 教文 黒住 順子 大森 一慶 荒木 俊江 真鍋 康二 福島 正樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.115-122, 2019 (Released:2019-02-28)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
銅欠乏症による種々の血球減少症を併発した透析患者5例を経験した. 男女比は1 : 4, 平均年齢は76歳, 平均透析歴は5.2年, 原疾患は糖尿病2例, 多発性囊胞腎1例, 腎硬化症1例, 不明1例, 併存症は誤嚥性肺炎3例, 脳神経障害2例, アクセス感染2例, 大腸癌術後の低栄養状態1例, 化膿性脊椎炎1例であった. 1例で経腸栄養, 4例で亜鉛製剤投与が行われていた. 診断時の血中銅, セルロプラスミンの平均濃度は26.6μg/dL, 12.6mg/dLで, 汎血球減少症2例, 貧血+血小板減少2例, 貧血のみ1例であった. 3例に硫酸銅, 1例に純ココア, 1例に銅サプリ投与を行い, 全例, 血球減少が改善した. 透析患者ではリン制限に伴う銅摂取量減少, 亜鉛補充による腸管での銅吸収抑制から健常人より銅欠乏をきたしやすいと考えられる. ESA抵抗性の貧血や複数系統にわたる血球減少症をみたときは, 銅欠乏も念頭において診療を行う必要があると考えられた.
4 0 0 0 OA 清水澄の憲法学と昭和戦前期の宮中
- 著者
- 菅谷 幸浩
- 出版者
- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.1_162-1_182, 2009 (Released:2013-02-07)
Toru Shimizu was a scholar of constitutional and administrative laws in Modern Japan. He lectured the Taisho Emperor as an employee of the Imperial Household Ministry, and young Showa Emperor as an employee at the educational section of the prince's palace. The objective of this study is to elucidate the political processes in the pre-war Showa Era, in which the Meiji constitutional system unsettled and collapsed, by reviewing the doctrine of Shimizu and its political position. In this study, the doctrine of Shimizu is compared with the constitutional theory of Tatsukichi Minobe from the viewpoint of constitutionalism and liberalism. In detail, the author discussed the commonalities and differences regarding the Emperor's political power, the state minister's consulting responsibility, the Imperial Diet's position and roles, party cabinet system theory, and electoral system theory, etc. In addition, the author attempts to conduct a comprehensive analysis, discussing how the doctrine of Shimizu was evaluated by the emperor's entourages including Nobuaki Makino and Kouichi Kido, middle-class army personnel, and right-wing constitutional scholars, and to position his presence in the Japanese political history in the 1930s.
4 0 0 0 OA 東京「遷都」の政治過程
- 著者
- 佐々木 克
- 出版者
- 京都大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.41-64, 1990-03
4 0 0 0 OA 善光寺案内
- 著者
- 村松今朝太郎 (清陰) 編
- 出版者
- 朝陽館
- 巻号頁・発行日
- 1912
4 0 0 0 日本三景「安芸の宮島」工事機材を自衛隊ヘリコプターで輸送
- 著者
- 村井 仁
- 出版者
- 公益社団法人 砂防学会
- 雑誌
- 砂防学会誌 (ISSN:02868385)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.52-57, 2008
4 0 0 0 IR 「笑う写真」の誕生 : 雑誌『ニコニコ』の役割
- 著者
- 岩井 茂樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.45-67, 2020-11
本稿は、明治末期から大正時代にかけて増加した笑った写真(本稿では「笑う写真」とした)の誕生と定着過程を明確にすることを目的としたものであり、そこで重要な役割を担った雑誌『ニコニコ』の特徴について論じたものである。 従来、「笑う写真」の定着過程については、石黒敬章などによって、おおよそ大正時代のことであったということが指摘されてきたが、その原因についてはほとんど考察されることがなかった。 しかしながら、本稿では1911(明治44)年に、ニコニコ倶楽部によって創刊された雑誌『ニコニコ』が「笑う写真」の定着過程に大きな役割を担ったことを証明した。この雑誌には、従来なかったような特徴があった。その一つが「笑う写真」の多用である。口絵はもとより、本文中にも「笑う写真」を多数配していたのである。また1916(大正5)年時点での発行部数は当時もっとも多く発行されていた『婦人世界』に次ぐものであり、また図書館における閲覧回数も上位10 位内に入るほど広く読まれた雑誌であった。 この雑誌の発刊に尽力した中心人物は当時、不動貯金銀行頭取をしていた牧野元次郎という人物であったが、彼は大黒天の笑顔にヒントを得て「ニコニコ主義」という主義を提唱し、それを形象化するために雑誌『ニコニコ』に「笑う写真」を多数掲載したのである。大黒天の笑顔を手本にし、皆が大黒様のような笑顔になることを、牧野は望んだ。国民全員がニコニコ主義を信奉し、実践することによって、国際的な平和と、身体の健康、事業の成功(商売繁盛)を実現しようとしたのである。『ニコニコ』は好評を博し、大衆に広く受け入れられた。その結果、「笑う写真」が誕生し、急増した結果、大正時代になって「笑う写真」が普及したのである。 本稿によって、雑誌『ニコニコ』の特徴が示され、その普及程度が具体的な数値や言説を用いて推定されたとともに、この雑誌が「笑う写真」に及ぼした影響が明確になった。
4 0 0 0 胎児のコギト アンリとラカンの情動論的交点をめぐって
- 著者
- 上尾 真道
- 出版者
- 日本ミシェル・アンリ哲学会
- 雑誌
- ミシェル・アンリ研究 (ISSN:21857873)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.1-12, 2021 (Released:2021-12-10)
- 参考文献数
- 23
Michel Henry, dans son livre Généalogie de la psychanalyse, distingue deux courants de la philosophie moderne depuis Kant — la conscience représentative et la vie affective — pour interroger l’invention de la psychanalyse par Freud en tant que charnière entre les deux. Cet article se propose de jeter la lumière sur la réflexion henrienne mise en relation à la pensée de Jacques Lacan, dont le nom est absent de l’œuvre d’Henry. Dans un premier temps, l’interprétation du Cogito cartésien d’Henry est comparée avec celle de Lacan. Tous les deux s’accordent à tenir compte du clivage entre la dimension représentative et l’irreprésentabilité du Cogito, et mettent l’accent sur le manque à naître dans l’ordre représentatif. Ensuite le concept de l’affectivité est examiné, comme le domaine de ce qui ne se réalise pas dans le représentatif. Tandis qu’Henry traite l’affectivité comme pré-représentative de l’immanence de la vie, Lacan élabore le concept de l’angoisse comme affect qui surgit en relation avec la langue maternelle et non-représentative, ce qui entraine l’insistance de l’altérité à l’intérieur de l’affection vitale. On trouve ici ce qui diffère entre les deux auteurs. Finalement, à partir d’une citation implicite d’un séminaire de Lacan à propos d’Henry, nous considérons ce qu’impliquent leurs différences pour ce qui est la relation avec la divinité, ainsi que la problématique de la puissance d’agir.