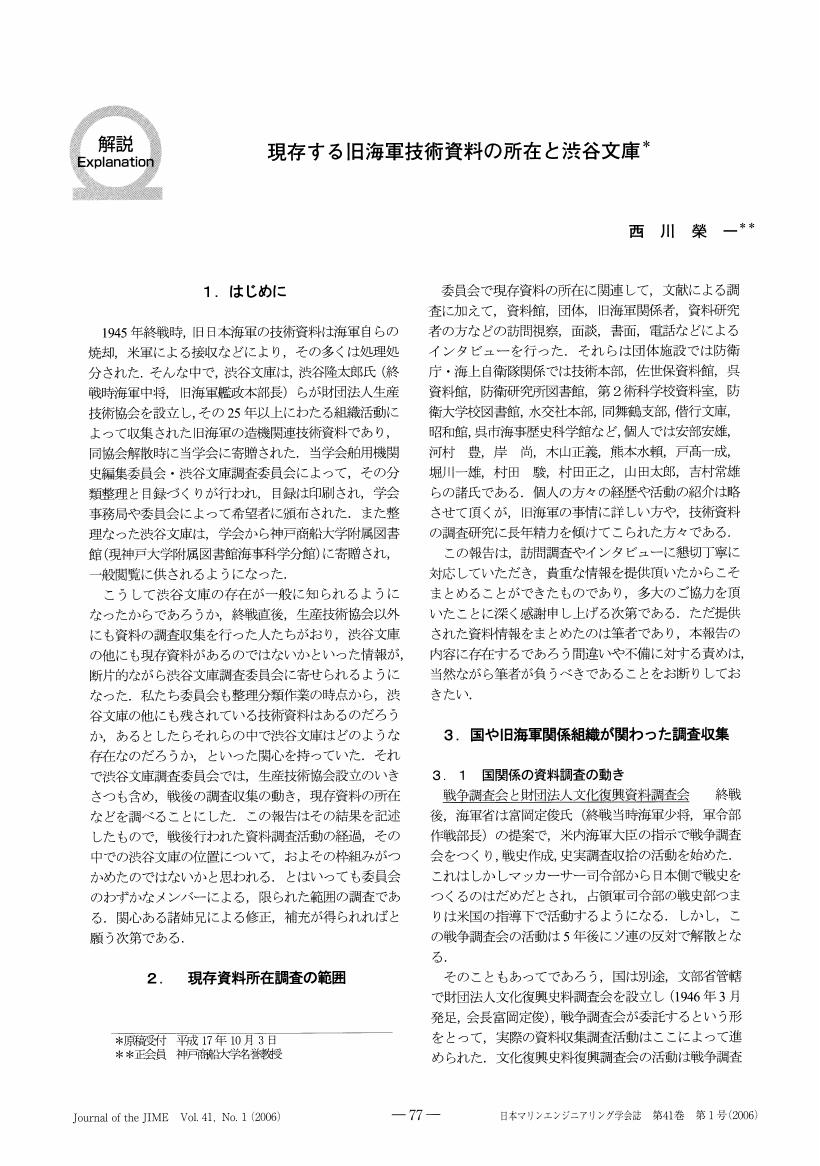4 0 0 0 OA 猥りに外國より鳥獸を輸入するは危險なり
4 0 0 0 OA 猥りに外國より鳥獸を輸入するは危險なり(續き)
4 0 0 0 OA サルコペニアは自宅退院した脳卒中患者の手段的日常生活動作の実施状況を低下させる
- 著者
- 田中 龍太郎 吉村 芳弘 嶋津 さゆり 北原 浩生
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.730-737, 2021-12-15 (Released:2021-12-15)
- 参考文献数
- 30
本研究は,回復期から自宅退院した脳卒中患者の退院後のIADLとサルコペニアとの関連性を検証した後ろ向きコホート研究である.対象は2015~2019年に当院を退院した脳卒中患者69名で,方法は退院1~1.5ヵ月後に自宅訪問による追跡調査を行った.IADLの評価はFAIを,サルコペニアの評価はAWGSを用いた.退院時のサルコペニア有群は無群と比較し退院後FAIが有意に低かった. 交絡因子を調整した多変量解析の結果,自宅退院した脳卒中患者のFAIにはサルコペニアが独立して関連していた.脳卒中患者のFAIの改善のために,サルコペニアの予防や改善を念頭に入れた作業療法が必要であると考えられた.
4 0 0 0 OA PTA 活動に対する母親たちの態度の多様性
- 著者
- 有馬 明恵 下島 裕美 竹下 美穂
- 出版者
- 東京女子大学論集編集委員会
- 雑誌
- 東京女子大学紀要論集 (ISSN:04934350)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.209-230, 2017-03-15
This article reveals mothers’ attitudes toward PTA activities through internet survey. Four hundred and fifty mothers who had participated in PTA activities answered a questionnaire. Hierarchical cluster analysis found five types: “mothers engaging in PTA activities for their children,” “mothers criticizing PTA,” “traditional and moderate mothers,” “mothers participating in social activities,” and “rational mothers”. The results showed the following; “mothers participating in social activities” think that parents and teachers should be equal partners and parents should work hard in PTA activities. These mothers however became more negative and suffered stress through engaging in the activities. On the other hand, “mothers criticizing the PTA” and “rational mothers” were reluctant to participate in PTA activities but, through the activities, they became more positive. There is a prevailing norm that tells mothers that they should help teachers as if they were servants and engage in PTA activities with modesty.
- 著者
- 米地 文夫 今泉 芳邦
- 出版者
- 岩手大学教育学部
- 雑誌
- 岩手大学教育学部研究年報 = The annual report of the Faculty of Education, Iwate University (ISSN:03677370)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.p131-144, 1994
4 0 0 0 IR 日本語教育文法からみた「やさしい日本語」の構想--初級シラバスの再検討
- 著者
- 庵 功雄
- 出版者
- 大東文化大学語学教育研究所
- 雑誌
- 語学教育研究論叢 (ISSN:09118128)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.255-271, 2011
4 0 0 0 OA COVID-19流行が黒色衛生マスク着用者への顕在的・潜在的態度に及ぼす影響
- 著者
- 鎌谷 美希 伊藤 資浩 宮崎 由樹 河原 純一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.92.20046, (Released:2021-07-31)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 4
Pre-COVID-19 epidemic studies found that wearing a sanitary mask negatively impacted perceived facial attractiveness. In particular, people demonstrated more negative explicit or implicit attitudes toward wearers of sanitary masks when the masks were black rather than white. The present study examined whether changes in social behavior in response to the COVID-19 epidemic, including the prevalent use of sanitary masks, might alter explicit and/or implicit attitudes toward wearers of black sanitary masks. We measured explicit (Study 1) and implicit attitudes (Study 3) and facial attractiveness (Study 2) of males wearing black or white sanitary masks. The results revealed that attitudes toward wearers of black sanitary masks were more positive than those measured pre-epidemic. Regardless of mask color, explicit attractiveness rating scores for low-attractiveness faces tended to increase after the epidemic. However, no such improvement was observed for high- and middle-attractiveness faces. There was also no change in implicit attitudes measured by the implicit association test. These results suggest that the COVID-19 epidemic has reduced explicit negative attitudes toward wearers of black sanitary masks.
4 0 0 0 OA 愛媛県松山平野における湧水性水域へのマツカサガイの試験的導入
- 著者
- 吉見 翔太郎 井上 幹生 畑 啓生
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.99-114, 2018 (Released:2018-07-23)
- 参考文献数
- 45
愛媛県松山平野では、1990 年からの約25 年間に、淡水二枚貝のイシガイとマツカサガイが減少し、2017 年現在イシガイはほぼ地域絶滅し、マツカサガイも絶滅の危機にある。また、松山平野では、これらの二枚貝を産卵床とするヤリタナゴが生息するが、その分布域も急減し、かつ国内外来種のアブラボテと産卵床を巡って競合し、二種の間の交雑が生じている。そのため、ヤリタナゴ-マツカサガイ共生系の保全が急務である。本研究では、人為的な管理が容易な自然再生地の保全区としての有用性を検討するため、二つの自然再生地(広瀬霞と松原泉)の、それぞれ1 地点と、上、中、下流の3 地点に加え、農業灌漑用湧水地である柳原泉の1 地点の、計5 放流区にマツカサガイを放流し、マツカサガイの生残率を追跡した。同時に、餌となる珪藻量や溶存酸素量などの環境条件の計測を行った。 その結果、広瀬霞で一年間の生残率が37%、松原泉下流で半年間の生残率が75%であった。他の3 放流区では一年の間に全ての放流個体が斃死した。これらの放流区が不適な要因として、珪藻類の密度の低さが挙げられた。生残が確認された広瀬霞や松原泉下流における珪藻類の密度は他の放流区と比べると高いが、国近川や神寄川のマツカサガイが自然分布する地点に比べると低い時期があった。また、広瀬霞と松原泉上流で、2015 年10 ~ 11 月に低酸素状態(3 ~ 5 mg/l)が発生した。追跡調査中、放流したマツカサガイ個体が底質から脱出することが確認された。この行動は、その後二週間以内に死亡する個体で頻繁に見られ、不適な環境からの逃避と考えられた。柳原泉では、アブラボテの侵入と放流したマツカサガイへの産卵が確認された。これらの結果から、マツカサガイとヤリタナゴの共生保全区を策定するには、珪藻類の密度が高く、一年を通して貧酸素条件が発生しない、アブラボテの侵入を管理できる場所とすべきであることが示唆された。放流後のモニタリングにおいては、冬季にマツカサガイの底質からの脱出がないこと、アブラボテの侵入がないことに留意する必要がある。本研究で用いた自然再生地では、珪酸の添加や、水を滞留させる構造を付加するなど、珪藻類を増加させる対策と、外来性の浮葉性植物を駆除し貧酸素状態を生じさせない対策をとり、保全地として再評価することが必要である。
4 0 0 0 IR 『大日本帝国憲法』第28条「信仰自由」規定の成立過程
- 著者
- 中島 三千男
- 出版者
- 奈良大学
- 雑誌
- 奈良大学紀要 (ISSN:03892204)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.p127-140, 1977-12
『大日本帝国憲法』(以下帝国憲法と略す)第28条「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務二背カサル限二於テ信教ノ自由ヲ有ス」(「信仰自由」規定)は戦前の国家と宗教の関係(政教関係)を規定したものであり,明治国家のイデオロギー政策の重要な構成要素である宗教政策の基本的枠組を表現したものである.この38文字によって表現された「信仰自由」規定は極めて漠然としたものであるが,戦前日本がファシズム化していく過程にあって,とりわけ1935年の大本教第二次大弾圧を契機に多くの宗教団体・宗教者がこの規定を具体化した諸法規によって激しい弾圧を受けたのであり,そういった意味では私たちにとって忘れることのできない規定であった.しかしながら,このような重い意味を持った規定でありながら,この規定に関する研究は皆無といってよい程少い.筆者はかつて,この規定の成立過程をあきらかにする前提作業として1885(明治18)年以前に・すなわち,帝国憲法の起草が本格的に始まる以前の段階で作成された政府官僚層の手になる憲法草案(「私擬憲法」)の「信仰自由」規定を分析し,以下の三点にわたる結論を導き出しておいた.
4 0 0 0 台北の歴史を歩く(その8)台北駅前と北門、忠孝西路を歩く
- 著者
- 片倉 佳史
- 出版者
- 交流協会
- 雑誌
- 交流 (ISSN:02899191)
- 巻号頁・発行日
- no.844, pp.19-27, 2011-07
4 0 0 0 OA 国語科教育における多様な性への対応と言語感覚の育成
- 著者
- 永田 麻詠
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 国語科教育 (ISSN:02870479)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.39-47, 2020-09-30 (Released:2020-10-23)
- 参考文献数
- 42
性的にマイノリティとされる子どもが「言葉の暴力」にさらされているという問題から、国語科教育としてどのように「言語環境の整備」に取り組むことが多様な性への対応となりうるのか、「言語感覚」と社会言語学の知見を手がかりに検討を行った。その結果、(1)多様な性に対する意識変容を目標として、言語感覚の育成をめざす(2)多様な性への対応として言語感覚を育てることにより、すべての子どものエンパワメントをめざす(3)アウティングやカミングアウトの強制を避けるために、文学的教材を用いて実践を構想する(4)性をめぐることばに対する具体的な違和感を検出することで、多様な性に対する社会的な価値観を批判的に検討できるような学習展開を具体化するの4点を、多様な性への対応としての言語感覚を育成する手がかりとした。
4 0 0 0 OA 薬学生を対象としたチーム基盤型学習によるEBM教育 ~兵庫医療大学における取り組み~
- 著者
- 上田 昌宏 清水 忠
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬学教育学会
- 雑誌
- 薬学教育 (ISSN:24324124)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.2019-033, 2020 (Released:2020-04-24)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
本研究では,受講生が主体的に論文を評価し,論文データの活用を学習できるチーム基盤型学習(team-based learning: TBL)を取り入れた授業コースにより受講生の論文評価能力が向上するかについて検証を行った.TBL 1回目と2回目の個人準備確認試験(iRAT)を比較した結果,2回目のiRATの平均点が(1回目:4.60 ± 2.11,2回目:6.49 ± 2.11,平均点の差:1.88[95%CI, 1.45–2.31])向上した.アンケートの単純集計から,受講生はチーム議論よりも試験解説で論文内容を理解できたと評価し,EBMの理解においては応用課題演習が重要であると評価していることが示された.さらに,因子分析とiRATの結果から,論文を理解できたと自己評価した受講者はiRATの得点が高い傾向にあった.以上のことから,TBLを取り入れた論文評価学習コースは,EBM実践に必要な論文評価能力の向上に寄与することが明らかとなった.
4 0 0 0 OA 公共事業政策に対する公共評価の心理学的構造:政府に対する一般的信頼と社会的公正感
- 著者
- 大渕 憲一
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.65-76, 2005 (Released:2006-04-29)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 8 8
全国15地域の一般市民772名に対する社会調査によって,社会的公正感,政府に対する信頼,公共事業政策に対する評価などを測定し,それらの間の関係を分析した。公正感,政府に対する信頼,公共事業政策などに対する評価は全体として厳しいものであった。公共事業政策評価は事業そのものの評価と事業主体である行政の評価に分かれること,前者に関しては肯定的評価と否定的評価が独立性の高い別次元となることなどが見いだされた。また,政府に対して一般的信頼を持たない回答者が公共事業政策をあらゆる面で否定的に評価する傾向が見られ,このことは,人々がヒューリステックな政策評価を行っていることを示唆している。また,政府に対する一般的信頼は,ミクロ,マクロ,地域,職業の4水準における社会的公正感によって強められることも確認された。このことは,社会集団内において自分が公正に扱われていると感じるかどうかが集団の権威者(例えば,政府)に対する態度を規定するとする公正の絆仮説を再確認するものであった。
- 著者
- Thomas Birner John R. Albers
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- vol.13A, no.Special_Edition, pp.8-12, 2017 (Released:2017-07-25)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 64
Abrupt breakdowns of the polar winter stratospheric circulation such as sudden stratospheric warmings (SSWs) are a manifestation of strong two-way interactions between upward propagating planetary waves and the mean flow. The importance of sufficient upward wave activity fluxes from the troposphere and the preceding state of the stratospheric circulation in forcing SSW-like events have long been recognized. Past research based on idealized numerical simulations has suggested that the state of the stratosphere may be more important in generating extreme stratospheric events than anomalous upward wave fluxes from the troposphere. Other studies have emphasized the role of tropospheric precursor events. Here reanalysis data are used to define events of extreme stratospheric mean flow deceleration (SSWs being a subset) and events of extreme lower tropospheric upward planetary wave activity flux. While the wave fluxes leading to SSW-like events ultimately originate near the surface, the anomalous upward wave activity fluxes associated with these events primarily occur within the stratosphere. The crucial dynamics for forcing SSW-like events appear to take place in the communication layer just above the tropopause. Anomalous upward wave fluxes from the lower troposphere may play a role for some events, but seem less important for the majority of them.
- 著者
- 美添 泰人
- 出版者
- 日本統計協会
- 雑誌
- 統計 (ISSN:02857677)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.10, pp.2-6, 2019-10
4 0 0 0 IR 古事記の言象学的構造(その2)―「 時」の源泉と歴史的世界 ―
- 著者
- 清水 茂雄
- 出版者
- 飯田女子短期大学
- 雑誌
- 飯田女子短期大学紀要 = Bulletin of Iida Women's Junior College (ISSN:09128573)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.1-121, 2021-05-27
本論文(「その2」)において,『古事記の言象学的構造』と題される論文の第2章の全体が展開される.「第2章」では,『古事記』の「火の神(ヒノヤギハヤヲノ神)」誕生から三貴子と言われる「アマテラス大御神」・「ツクヨミノ命」・「スサノオノ命(タケハヤスサノヲノ命)」誕生までの言象学的文法論的解明を行う.これらの神々の系譜の底辺には,述語が「主語の述語」に「成る」ことを開始してから,動詞に至るまでの言象学的文法論的プロセスが横たわっている.述語は自身の生まれ故郷の村(「始原の言葉」の領域)から出て行き,そこからの呼びかけの声(イザナミ)を振り切って(イザナキのイザナミからの離別)都会へと去る.述語が至った都会が,言象学的文法論的には,「論理的領域(「有るものが有る」の世界)」と言われるところ,いわゆる「この世」である.ここに,述語の生まれ故郷の村は,秘密に閉ざされて「無」となってしまい,有と無の論理的対立と「生と死」からなる生命の世界が生起する.
4 0 0 0 OA 忠臣瀬戸物蔵 : 3巻
4 0 0 0 OA 現存する旧海軍技術資料の所在と渋谷文庫
- 著者
- 西川 榮一
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.77-81, 2006-01-01 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 2 1