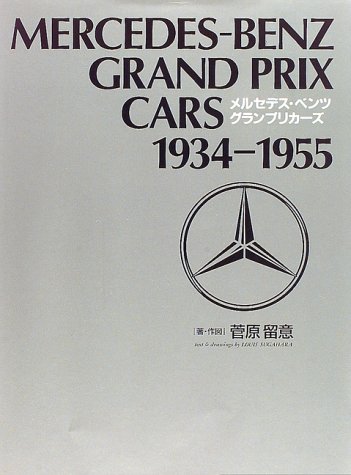4 0 0 0 メルセデス・ベンツグランプリカーズ : 1934-1955
4 0 0 0 骨格筋損傷に対する鍼治療の効果と研究の現状
- 著者
- 吉田 成仁 大岡 茂 鈴木 茂久 宮本 俊和
- 出版者
- 日本臨床スポーツ医学会
- 雑誌
- 日本臨床スポーツ医学会誌 = The journal of Japanese Society of Clinical Sports Medicine (ISSN:13464159)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.234-236, 2011-04-30
- 参考文献数
- 8
4 0 0 0 OA 近代蚕糸業地域における都市形成過程 : 本庄町における近代化に伴う富裕層の活動と空間変容
- 著者
- 佐藤 宏亮 後藤 春彦
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.547, pp.201-208, 2001-09-30 (Released:2017-02-04)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1 4
The purpose of this paper is to clarify the urban forming process in the modern silk raising area from the two aspect. The first is the action of wealthy people and second is the urban space, through the analysis of the modernizing process in Honjo-machi. The results are the followings 1) In Honjo-machi, it mordernized rapidly with the change of silk raising system 2) The action of wealthy people kept pace with flow of modernization, and contributed to form the social system 3) And thier action largely affected to industrialization, Finally, the space structure was affected by the silk mill.
4 0 0 0 OA 一次元, 二次元準結晶の電子状態
- 著者
- 甲元 真人
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.433-442, 1987-05-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 40
Shechtmanらの5回対称性を持つ新しい秩序相 (準結晶) を示唆する実験以来, 準周期を持つ系の物性に大きな関心が寄せられています. これは周期性を持つ結晶とアモルファス物質の中間と考えられるもので, これらと異なる新しい性質を持つことが予想されます. 特に一次元準結晶の電子状態はエネルギーバンドが無限に存在するカントール集合となること, 自己同型でフラクタル性を持つ波動関数が存在することなど奇妙な性質を持つことが知られています. これらは繰り込み群の考え方, カオスを出し得る非線形力学系などと深い理論的つながりがあります.
- 著者
- 永田 憲史
- 出版者
- 関西大学法学会
- 雑誌
- 關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.5, pp.1438-1461, 2021-01-27
- 著者
- 永田 憲史
- 出版者
- 関西大学法学研究所
- 雑誌
- ノモス = Nomos (ISSN:09172599)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.65-90, 2020-12-31
4 0 0 0 OA 選挙における音声アーカイヴ : 2014年衆院選における候補者音声周波数分析を事例として
- 著者
- 岡田 陽介 オカダ ヨウスケ Yosuke Okada
- 雑誌
- 応用社会学研究 = The journal of applied sociology
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.89-102, 2017-03-24
4 0 0 0 戦国末期の岩船山 : 新出「下野国岩船地蔵誓願参日記」とその周辺
- 著者
- 林 京子
- 出版者
- 日本宗教民俗学会
- 雑誌
- 宗教民俗研究 = Studies of religious folklore (ISSN:09179143)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.1-25, 2021
4 0 0 0 OA 『ハリー・ポッター』シリーズに見る英国ファンタジーの伝統
- 著者
- 安藤 聡
- 出版者
- 大妻女子大学
- 雑誌
- 大妻比較文化 : 大妻女子大学比較文化学部紀要 (ISSN:13454307)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.127-115, 2012
4 0 0 0 OA イノシシの生態から考える豚コレラ防疫
- 著者
- 小寺 祐二
- 出版者
- 獣医疫学会
- 雑誌
- 獣医疫学雑誌 (ISSN:13432583)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.4-8, 2019-07-20 (Released:2020-01-10)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 4
After wild boar arrived at the Japanese Islands during the Middle-Late Pleistocene, its distribution had spread nationwide, except Hokkaido. Afterwards in the latter half of 19th century, it had shrunk to western part of Japan by the change of the socio-economic structure of Japan. However, the energy revolution and the economic growth of Japan in 1960’s have led to the distribution recovery of wild boar and to increase in agricultural damage by the species. Now the damage by wild boar amounts over 5 billion yen per year in recent years. To solve agricultural problem by wild boar 43 prefectural governments, as of 2019, have planned the Specified Wildlife Management Plan involving feedback system. But few plans adopt ecological investigations and fulfill its feedback system function. As a result, agricultural damage by wild boar have not been decreasing.In addition to the agricultural problem, in September 2019, an outbreak of the C.S.F. in wild boar population is confirmed. The Japanese government is concerned about expansion of its infection and the immediate enforcement of the C.S.F. is required. However, the general public does not understand the ecological characteristic of the wild boar correctly. As a result, when people carry out various wild boar measures, inappropriate technique tends to be used.Therefore, in this paper, I will comment on the ecological characteristic of the wild boar and show the C.S.F. prevention of epidemics from a point of view of the ecology of wild boar.
4 0 0 0 OA ジョロウグモの成長速度と体サイズの餌による制約の直接証拠
- 著者
- 宮下 直
- 出版者
- Arachnological Society of Japan
- 雑誌
- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.17-21, 1991 (Released:2007-03-29)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 14 16
ジョロウグモを野外網室内で3つの異なる条件下で飼育し, 成長経過を調べた. 餌供給量の違いは, 成長速度やサイズに強い影響を与えた. 野外における3つの個体群の平均サイズの変異は大きかったが, いずれも飼育下におけるサイズの範囲内にあった. これらの結果は, 野外個体群における餌資源の制約とともに, 成長過程の可塑性を示すものである.
- 著者
- Tronbacke Bror Ingemar
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 国際子ども図書館の窓 = The window : the journal of the International Library of Children's Literature (ISSN:1346261X)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.5-12, 2006-03
4 0 0 0 OA 国勢調査における「従業上の地位」を踏まえた林業労働者数の分析(論文)
- 著者
- 林 宇一 永田 信
- 出版者
- 一般財団法人 林業経済研究所
- 雑誌
- 林業経済 (ISSN:03888614)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.8, pp.1-13, 2016 (Released:2017-04-27)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
日本林業は、森林組合等の法人林業事業体の労働者と林家及び非法人林業事業体の労働者により担われている。国勢調査の「従業上の地位」分類では、それぞれ役員を含む【雇用者】とそれ以外の非【雇用者】に対応すると考えられる。それらについて、産業分類上の「林業」就業者と職業分類上の「林業作業者」の動向を1980年から2010年について明らかにすることを目的とした。非【雇用者】・「林業」就業者では、「農林漁業作業者」が95%以上で、【雇用者】・「林業」就業者では「林業作業者」が60~65%、「事務従事者」が20%強であった。いずれでも「林業作業者」が増加傾向にあった。「林業作業者」 の産業構成を見ると、「協同組合」の定義変更の影響は【雇用者】において顕著で、非【雇用者】においてはそもそも「協同組合」就業者はいなかった。また「従業上の地位」を踏まえて林業労働者総数の推計を行なったところ、2010年については7万4千人となった。
4 0 0 0 OA MATEタンパク質の構造生物学
- 著者
- 草木迫 司
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.183-185, 2021 (Released:2021-05-28)
- 参考文献数
- 10
4 0 0 0 OA 「株主の株主による株主のための」会社でよいのか。日本型企業統治にもっと目を向けよう。
- 著者
- 峰内 謙一
- 出版者
- 日本経営倫理学会
- 雑誌
- 日本経営倫理学会誌 (ISSN:13436627)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.303-316, 2015-01-31 (Released:2017-08-08)
As Japanese stock prices recover from global financial meltdown, more investors - notably institutional investors returning to stock markets after the Lehman Shock - are demanding to improve the governance of Japanese corporations and call for adopting the Anglo-American model of shareholder primacy. Apparently motivated by their outcries, the Abe administration seems to have expressed support for Anglo-American style of governance without substantive discussion of the merits and deficiencies of Japanese corporate governance. Unlike Anglo-American model with its short-termism, Japan's governance model is founded on the principle of long-term corporate sustainability. This paper discusses both governance models and suggest that Japan's type can even be future world model. It argues that Anglo-American type governance is unnecessary and detrimental to Japanese corporations. It advocates the need to establish a new governance model based on Japan's "Audit & Supervisory Board" system. The paper concludes by offering recommendations that seem feasible in the author's experience as a member of the above board.
4 0 0 0 OA 加熱調理に伴うジャガイモのビタミンC含量の変化
- 著者
- 土屋 律子
- 出版者
- 北翔大学
- 雑誌
- 北海道浅井学園大学生涯学習システム学部研究紀要 = Bulletin of Hokkaido Asaigakuen University School of Continuing Education Studies (ISSN:13466178)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.35-41, 2004-03-20
4 0 0 0 OA 姉家督相続についての一考察
- 著者
- 森 謙二
- 出版者
- 日本法社会学会/有斐閣
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, no.31, pp.117-140,234, 1979-03-30 (Released:2009-01-15)
- 参考文献数
- 34
Inheritance of the first-born child ("Ane-Katoku Sozoku" in Japanese) refers to a system which stipulates that if a female happens to be the first-born child, then she (saying exactly, her adopted husband "Muko-Yoshi" in Japan) inherils the family's entire holdings. This system is different from primogeniture, in the strict sense of which the eldest son inherits the family's holdings.The custom of the first-born child inheriting was found in the North-East Regions of Japan, and exsisted until the early days of the Meiji-period. But after that, it began to break down.My report explains the following.1) The actual state of this custom in Satomi-Village in Ibaragi.2) The reason why this custom efisted.3) The process by which this custom broke down under the influence of the Act of Conscription and the Meiji Civil Code.
- 著者
- 蔡 珮菁
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.17-32, 2007-07-01
「長期的な観点」に対する「長期的観点」のように,「連語」と交替可能な「臨時的な複合語」について,その語構成レベルの成立条件を解明すべく,"接尾辞「的」による派生形容動詞(「A的」)と名詞(「B」)との結びつき"に注目して,要素「A」「B」がその語種・品詞性においてどのようなくみあわせのとき,臨時的な複合語「A的B」になりやすいかを検討した。新聞の社説本文3年分における(交替可能な)「A的なB」「A的B」の使用状況を計量的に調査した結果,「A的B」が最も活発に成立するのは,「A」「B」がともに2字漢語の(非用言的な)体言類というくみあわせであること,また,このくみあわせは,4字漢語複合名詞や和語複合名詞の構成において最も優勢なくみあわせに一致・対応することが明らかとなった。このことから,連語と交替可能な臨時的複合語の成立にも,既存の(固定的な)複合語の構成のあり方が影響を与えていること,すなわち,要素のくみあわせが,既存の語構成において安定的・生産的なタイプに一致・対応するものほど,臨時的な複合語として成立しやすいのではないかとの見通しを得た。
- 著者
- 加納 友香 石橋 知幸 土居 礼佳 藤井 沙紀 野口 佳美 森本 美智子
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.4_1-4_10, 2014-09-01 (Released:2016-03-05)
- 参考文献数
- 37
目的:大学生を対象に生活上のストレスや神経症傾向,不眠へのこだわりが睡眠の質にどのように関係しているのか,精神的健康までのモデルを構築し,その関連性について検討した。方法:A大学に在学する253名を分析対象者とした。睡眠の質にはピッツバーグ睡眠質問票日本語版(PSQI-J)等を用いた。探索的なモデルの検討を行い,採用したモデルに対して共分散構造分析を行った。結果:PSQI-J総合得点には生活上のストレス体験,不眠へのこだわりが直接的に関連し,不眠へのこだわりは中程度の関連性(β = .411,p< .001)を示していた。PSQI-J総合得点は,神経症傾向,不眠へのこだわり,生活上のストレス体験の3つの変数で30.5%説明されていた。睡眠の質は,弱いものの精神的健康に直接的に影響を与えていた。結論:睡眠の質を高めるためには,ストレスによる覚醒度や不眠へのこだわりに対する方策を検討する必要性があり,そうすることで精神的健康も高まることが示唆された。