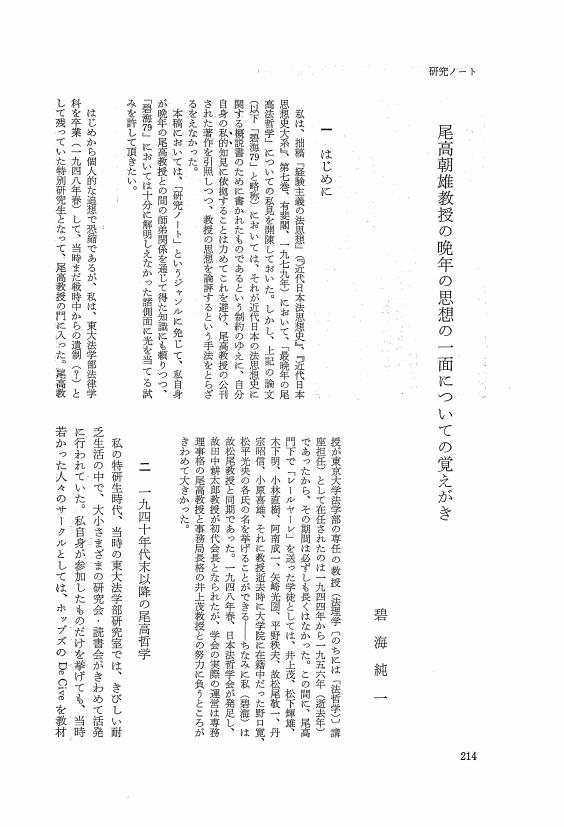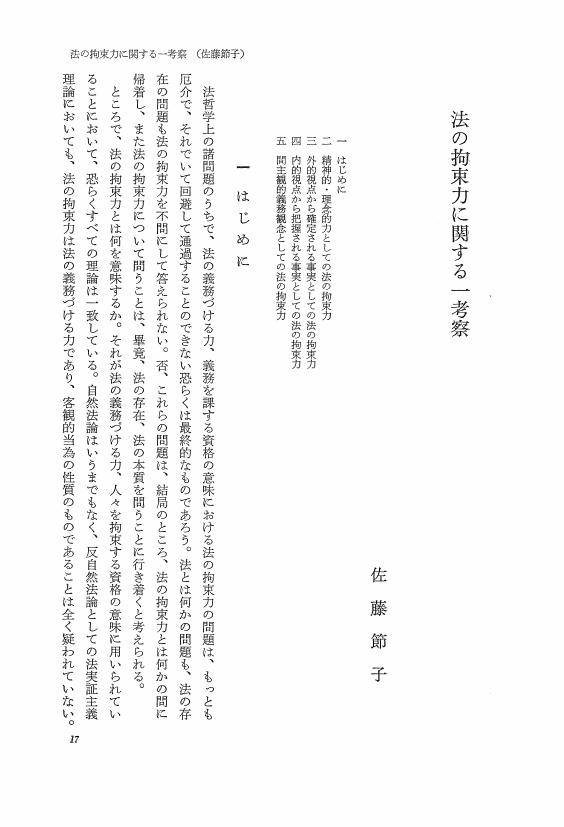4 0 0 0 OA 万延元年第一遣米使節日記
4 0 0 0 OA 鳥類に寄生するダニ類
- 著者
- 長堀 正行
- 出版者
- The Acarological Society of Japan
- 雑誌
- 日本ダニ学会誌 (ISSN:09181067)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.1-11, 1998-05-25 (Released:2011-02-23)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 1 3
A brief review of mite and tick groups of birds and their acariasis is presented. Birds are hosts to diverse groups of mites and ticks that inhabit the feathers, quills, skin, intracutaneous tissue, subcutaneous tissue, nasal cavity, trachea, lung, air sac and serous membranes of the viscera. Fifty-one families of acarina, 1of which is phoretic, that are parasitic on or in birds have been recognized. Many of them are minimally pathogenic for wild birds. However, they can lead to various health problems and death in parasitized caged and aviary birds, and some groups may bite humans. Birds are also an important animal not only as a host for vector species of acari-borne diseases but also as a healthy carrier of acari-borne pathogens.
4 0 0 0 OA 1.95GHz帯電磁波全身ばく露の雄性生殖器(精子形成)への影響
- 著者
- 今井 則夫 難波江 恭子 河部 真弓 安藤 好佑 戸田 庸介 玉野 静光 野島 俊雄 白井 智之
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本トキシコロジー学会学術年会 第35回日本トキシコロジー学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.123, 2008 (Released:2008-06-25)
【目的】携帯電話の利用者数は年々増加しており、精巣も携帯電話の長時間使用によって電磁波にばく露される対象臓器であり、精巣毒性が懸念される。そこで、携帯電話で用いられている1.95GHz電磁波の精巣毒性の有無について、ラットを用いて検討した。【方法】ばく露箱内の照射用ケージにSD系雄ラットを入れ、ばく露箱内上部に直交させたダイポールアンテナで、周波数1.95GHz、W-CDMA方式の電磁波を全身に照射した。電磁波ばく露は、性成熟過程である5週齢から10週齢に至る5週間、1日5時間行った。照射レベルは全身平均SAR(Specific absorption rate)が0 W/kg(対照群)、0.08 W/kg(低ばく露群)および0.4 W/kg(高ばく露群)の3段階を設定した。なお、実験は各群24匹を2回(1回に各群12匹)に分けて行った。ばく露終了後、剖検を実施して全身の諸器官・組織の肉眼的病理学検査を実施し、雄性生殖器の器官重量の測定を行うとともに、精子検査(精子の運動率、精巣および精巣上体の精子の数、精子の形態異常率)を行った。また、雄性生殖器の組織について病理組織学的に評価するとともに、精巣のステージング(精子形成サイクルの検査)についても評価した。【結果】ばく露期間中に死亡例はみられず、一般状態においても著変は認められなかった。体重、摂餌量、雄性生殖器系器官・組織の重量、精子の運動率、精巣上体の精子数、精子の形態異常率、精巣のステージ分析において、ばく露群と対照群との間に有意な差は認められなかった。また、肉眼的病理学検査および病理組織学的検査においても電磁波ばく露に起因すると思われる変化は認められなかった。【結論】5週齢のSD系雄ラットに1.95GHz電磁波を5週間全身ばく露した結果、電磁波ばく露の影響と考えられる変化がみられなかったことから、電磁波ばく露による精巣毒性はないと判断した。(この研究は社団法人電波産業会(ARIB)の支援によって実施した)
4 0 0 0 OA 尾高朝雄教授の晩年の思想の一面についての覚えがき
- 著者
- 碧海 純一
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, pp.214-222, 1980-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 21
4 0 0 0 OA 法の拘束力に関する一考察
- 著者
- 佐藤 節子
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1977, pp.17-51, 1978-11-20 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 58
4 0 0 0 OA 呼吸不全の病態生理
- 著者
- 一和多 俊男
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.158-162, 2016-08-31 (Released:2016-09-15)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
呼吸不全とは,呼吸器系障害により低酸素血症(PaO2≦60 Torr)をきたし,また,時に高二酸化炭素血症(PaCO2>45 Torr)をともなう状態で,生体が正常な機能を営み得ない状態である.一方,呼吸不全を広い概念でとらえると,呼吸器障害による動脈血液ガスの異常に加えて,循環障害,酸素輸送障害や末梢組織での酸素利用障害による組織低酸素も含まれる.呼吸不全は,発症形式により急性呼吸不全・慢性呼吸不全・慢性呼吸不全の急性増悪に分類される.また,病態によりⅠ型呼吸不全(低酸素性呼吸不全;PaO2≦60 Torr,PaCO2≦45 Torr)Ⅱ型呼吸不全(換気不全;PaO2≦60 Torr,PaCO2>45 Torr)に分類され,さらにⅡ型呼吸不全は,肺胞気動脈血酸素分圧較差(AaDO2)の正常な群と開大する群に分類される.一般にⅠ型呼吸不全は,Ⅱ型呼吸不全より予後不良である.
4 0 0 0 OA V.肺炎球菌ワクチン:接種法,副反応と対処
- 著者
- 嵯峨 知生 廣川 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.11, pp.2336-2342, 2015-11-10 (Released:2016-11-10)
- 参考文献数
- 9
予防接種の安全性は高いが,副反応はゼロではない.成人に安全に肺炎球菌ワクチンを接種するにあたり,定期接種・任意接種の接種要件を理解し,不適当者・要注意者を見極めることが重要である.歴史的経緯から接種経路についても注意が必要である.副反応・有害事象の考え方と対処法,および予防接種後副反応報告の義務化とその概要,健康被害救済制度についても理解しておく必要がある.
4 0 0 0 OA ドイツの都市内社会的空間的分極化は激化したか? ――ドル卜ムン卜市の事例――
- 著者
- 山本 健兒
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.1-25, 2009-01-01 (Released:2011-05-12)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 2
ドイツでは,グローバリゼーションの進展に伴って都市内の社会的空間的分極化が激化してきたといわれている.本稿は,その実態をドイツのドルトムント市を事例に検証することを目的とする.この都市は分極化を克服するための政策が積極的に実施されてきたところである.分極化は社会的排除という概念と密接に関わっている.これは移民・貧困・失業などの具体的に計測し得る指標の特定地区への集中的出現として把握できる.分析の結果,ドルトムント市内には社会的排除の現象が如実に現れている場所としてノルトシュタットをはじめ,いくつか確認できる.しかし,グローバリゼーションの進展とともにそれが激化してきたと簡単に言えるわけではない.むしろ,激化の側面と緩和の側面が同時進行してきた.ガストアルバイターだけというよりもむしろ,東欧・ロシアからの移民が多いところや,これも含めて移民の多様性が顕著な地区で激化の側面がみられる.
4 0 0 0 OA 農協連携による野菜生産の拡大とその要因 ——群馬県東毛地域のニガウリ生産を事例に——
- 著者
- 岡田 登
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.1, pp.58-71, 2012-01-01 (Released:2016-12-01)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
本研究では群馬県東毛地域を事例として,農協連携によりニガウリ生産が拡大した要因を,農協間の協力関係の構築とニガウリ栽培を導入した農家の経営内容に注目して明らかにした.2002年から東毛地域で全農群馬が主導し,東毛3農協が連携してニガウリの共同販売を開始できたのは群馬板倉農協と館林農協の販売担当者に農協連携による共同販売以前から協力関係が存在していたことがある.これによって,全農群馬は各農協への指示系統を確立させ,規格と販売先を指示し,栽培技術を共有させることができた.また東毛3農協管内の60歳未満男性専業者のいる農家がニガウリ栽培を導入したことが生産拡大の契機となった.これらの農家がニガウリの生産に成功したことで,その後キュウリやナス以外の作物を主体に生産している農家や,女性農業者,兼業農家,および60歳以上の農業者がその栽培を導入するようになり,その生産は拡大した.
4 0 0 0 OA 塩類風化による岩屑生産の定量評価 ——史跡・吉見百穴の凝灰岩の事例——
- 著者
- 高屋 康彦 小口 千明
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.4, pp.369-376, 2011-07-01 (Released:2015-09-28)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 3 5
史跡・吉見百穴の坑道壁面における凝灰岩の塩類風化による岩屑生産の速度を把握し, 塩類と岩屑の量的関係を求めるため, 崩落物質を回収する現地調査を1年間にわたって実施した.温度・湿度がともに低い冬から春先には粒状の風化による岩屑生産が著しく, それ以外の時期には岩屑量は非常に少なかった.壁面で観察された析出鉱物としては, 冬から春先にかけてはナトリウムミョウバンおよびハロトリカイトが顕著であり, 石膏とジャロサイトは年間を通して認められた.岩屑量および析出する鉱物種の季節性から, 塩類の析出に伴う岩屑生産に最も寄与している鉱物はナトリウムミョウバンおよびハロトリカイトであると考えられる.崩落した岩屑量と塩類量との間には一次の相関があることが明らかになった.
4 0 0 0 OA 東京都利島村におけるツバキ実生産による高齢者の生計維持
- 著者
- 植村 円香
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.3, pp.242-257, 2011-05-01 (Released:2015-09-28)
- 参考文献数
- 12
本稿では,生産者の高齢化が進んでいる東京都利島村のツバキ実生産を事例に,世代による経営形態の違いと,高齢者の生計維持における意義を検討した.ツバキ実生産は,粗放的で長期収穫が可能なので,高齢者でも生産しやすく,年間100万円程度の販売収入を得ることができる.しかし,若年者にとっては,ツバキ実生産のみで生計を維持することは難しく,ツバキ実生産への参入はみられない.このように経営形態が,世代によって異なることに注目し,農業者をコーホートに分けて比較分析を行った.その結果,ツバキ実生産は,高齢者によって長期的に維持されていること,高齢者の中でも上の世代ほど経営規模が大きく,より多くの収入を得て,安定した生計維持ができていることが判明した.しかし,世代間での農業資源の偏在を前提にすると,利島におけるツバキ実生産の維持には,世代間でどのようにツバキ林を受け継ぎ,ツバキ実の生産を調整していくかが課題となる.
4 0 0 0 OA 花崗岩の化学的風化における変質特性に関する実験的研究
- 著者
- 高屋 康彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.131-144, 2011-03-01 (Released:2015-09-28)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 3
花崗岩地形の形成過程を理解するためには, 酸性条件下の化学的風化で生成される二次生成物の特徴をとらえる必要がある.そのため本研究では, 風化変質実験を実施した.実験では同一形状に整形した花崗岩および鉱物4種(黒雲母, 斜長石, アルカリ長石および石英)と酸溶液とを56日間反応させ, 試料表面の化学組成をXPSで求めた.低pH条件下の花崗岩の変質では, 黒雲母が顕著に溶解してケイ素酸化物(水酸化物)が形成された.中性から弱酸性条件下では, 斜長石の溶解によるpH増が黒雲母からの鉄酸化物(水酸化物)の沈殿を促進した.同時に, 黒雲母の溶解による水溶液中のMgなどの陽イオンの存在が斜長石の変質におけるアルミニウム酸化物(水酸化物)の沈殿を遅らせた可能性がある.このような構成鉱物間の相互関係は, 黒雲母の反応性を高めている.野外での花崗岩風化の特徴の一つである鉄錆の生成は, 斜長石の溶解によって促されることが明らかになった.
4 0 0 0 OA 気温・地温観測結果からみた飛騨山脈槍・穂高連峰における山岳永久凍土の分布状況
- 著者
- 青山 雅史
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.1, pp.44-60, 2011-01-01 (Released:2015-01-16)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1 1
飛騨山脈南部槍・穂高連峰における山岳永久凍土の有無およびその分布状況を明らかにするため,小型自記温度計を用いて,気温および地温の観測をおこなった.気温観測の結果,槍・穂高連峰主稜線上は不連続永久凍土帯の気温条件下にあることが判明した.また,地表面温度観測の結果,本山域のカール内に存在する岩石氷河や崖錐斜面上の多数の地点における晩冬季の積雪底地表面温度(BTS)の値は,それらの地点に永久凍土が存在する可能性があることを示した.特に,大キレットカール内の岩石氷河上では,永久凍土が存在している可能性が高いことを示すBTSや年平均地表面温度などの値が複数年にわたって得られた.地表面が特に粗大な礫から成る地点では,冬季の地表面温度の低下が他地点よりも顕著であった.これは,冬季に粗大礫の上部が積雪面上に露出し,その露出部が寒冷な外気により冷却され,礫自体の冷却が進行していくことによりもたらされたものと考えられる.
4 0 0 0 OA 空間的連坦かつ最大限均質な部分地域への地域区分となるための必要条件
- 著者
- 増山 篤
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.6, pp.585-599, 2010-11-01 (Released:2012-01-31)
- 参考文献数
- 23
本稿の主目的は,一つの地域が空間的に連坦し,最大限均質な部分地域へ区分される必要条件を導くことである.地理学では,部分地域が連坦し,最大限均質になるという2条件を満たす地域区分がしばしば試みられる.こうした区分のために,さまざまな方法が提案されてきたが,先の2条件を厳密に満たすものはない.2条件を満たそうとする地域区分は,最適化問題としてとらえられる.一般に,最適化問題の解法は最適解が満たす必要条件に基づく.地域区分に関しても最適性の必要条件があれば,期待するような部分地域を見出すのに有用と考えられる.そこで,2条件を満たす地域区分となる必要条件を理論的に導出し,その必要条件に基づく地域区分方法について検討した.その結果,まず,等値線に従う区分が,必要条件を満たすことが分かった.また,等値線の組合せによって,二つの条件を厳密に満たすのは困難だが,従来の方法を上回る区分が期待できることが示された.
4 0 0 0 OA 日本企業によるグローバルなネットワーク形成と知識結合
- 著者
- 與倉 豊
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.6, pp.600-617, 2010-11-01 (Released:2012-01-31)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1 2
本稿は,グローバル企業の知識結合に着目し,日本企業による外資導入の実績に関する資料を基に,社会ネットワーク分析を用いて組織間の関係構造を考察した.さらに共分散構造分析を用いて,知識結合に基づく企業間ネットワークの特性と,企業のパフォーマンス(経済的成果)との関連性について検討した.分析の結果,製造業18業種がコンポーネント数や平均次数といったネットワーク統計量の差異によって六つのグループに類型化された.ノード数が多く複雑なネットワークを,ブロックモデルを用いて縮約化することによって,知識結合において重要な役割を果たすグローバル・ハブが抽出された.また,多母集団同時分析によって,ネットワークの関係構造において優位な位置にあるノードほど,財務諸表で測られる企業のパフォーマンスに対して正の影響を与えることが示された.さらに,医薬品や電気機器,自動車等,精密機械など科学的・分析的知識を必要とする業種ほど,ネットワーク優位性の影響が強く働くことが明らかになった.
4 0 0 0 OA 奥羽山脈の低標高山地(福島県御霊櫃峠)にみられる「植被階状礫縞」
- 著者
- 瀬戸 真之 須江 彬人 石田 武 栗下 正臣 田村 俊和
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.3, pp.314-323, 2010-05-01 (Released:2012-01-31)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 5 2
福島県の御霊櫃峠(約900 m)には,西北西の強風にさらされることが多い斜面に構造土が存在する.この構造土は,扁平礫が露出した帯と植生が密生した帯とが,数十cm~2 mほどの間隔で交互に配列している.両方の帯とも傾斜方向にかかわらず,ほぼ西北西–東南東の卓越風向に伸びる.伸びの方向が最大傾斜方向と直交する所では階状土,一致する所や傾斜が緩い所では縞状土の形状を示し,本稿では「植被階状礫縞」と呼ぶ.本研究では,低標高山地斜面に構造土が発達する点に注目し,その詳細を記載した.階状土部分の断面では,階段状を示すのは堆積物上面のみで,堆積物と基岩との境界面はほぼ一様の傾斜で,地表の礫は植被に乗り上げている.植被階状礫縞は,強風により積雪を欠く裸地で植被が卓越風向に平行な縞状に発達し,凍結・融解で傾斜方向に礫が移動し,卓越風向にほぼ直交する向きの斜面では植被に堰き止められ,ほぼ一致する向きの斜面ではそのまま移動して形成されたもので,現在も発達中と考えた.
4 0 0 0 OA カナダにおける日本人向け旅行業の展開過程
- 著者
- 小島 大輔
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.6, pp.604-617, 2009-11-01 (Released:2011-08-25)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 3 3
本稿では,日本人のカナダ旅行の発展に伴う日本人向け現地旅行業者の活動の展開に着目し,旅行目的地とその供給体系との関係について分析を行った.1970年代まで,日本人のカナダ旅行の供給体系はアメリカ旅行の供給体系のサブシステムだった.カナダでは主に現地の日系人が設立した旅行業者が媒介部門の役割を担い,日本人の旅行目的地においてカナダ西部と東部は,それぞれアメリカ西部と東部のそれに統合されていた.1980年代になると,東西両地域を含んだ旅行商品の大量供給や夏季以外の旅行商品の開発が行われた.また,日本人カナダ旅行者の急増に伴い,柔軟な催行体制を用いた日本系旅行業者の進出によって,アメリカ旅行の供給体系から独立したカナダ旅行の供給体系が構築された.1990年代後半の日本人カナダ旅行者数のピーク以降,日本から進出した日本系旅行業者は,季節変動に対し労働力の数量的・機能的柔軟さを高め,その存続を図っている.
4 0 0 0 OA 資源論の再検討 ――1950年代から1970年代の地理学の貢献を中心に──
- 著者
- 佐藤 仁
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.6, pp.571-587, 2009-11-01 (Released:2011-08-25)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1 2
本稿の目的は戦前から戦後にかけての日本の資源論をレビューした上で,そこに通底する考え方を明らかにし,資源論の独自性を確認することである.資源論のサーベイは過去20年以上行われておらず,地理学においても資源論という分野名称は 1990年代にはほぼ消滅した.しかし,かつての資源論には,今なお評価すべき貢献が多く残っている.本稿では,特に資源論が盛んであった1950年代から1970年代にかけての議論,特に石井素介,石光 亨,黒岩俊郎,黒澤一清といった資源調査会と関わりの深かった論者の総論部分を中心に取り上げ,そこに共通する考え方や志向性を紡ぎだす.筆者が同定した共通項は,1)資源問題を社会問題として位置づける努力,2)現場の特殊性を重視する方法論,3)国家よりも人間を中心におき,国民に語りかける民衆重視の思想,である.経済開発と環境保護の調和がますます切実になっている今日,かつての資源論に体現された総合的な視点を新たな文脈の中で学び直すべきときが来ている.
4 0 0 0 OA 鉛直構造に着目した空っ風の気候学的研究
- 著者
- 宮 由可子 日下 博幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.4, pp.346-355, 2009-07-01 (Released:2011-08-25)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1 2
関東平野で冬季に吹く局地風「空っ風」について気候学的な解析を行い,日変化や鉛直構造を明らかにした.結果は以下の通りである.①空っ風日の地上風は明瞭な日変化を示す.関東平野の北西~西北西風の卓越する地域では,日中の風速は冬期平均の2倍近くに達する.②空っ風日の境界層上部の風速は昼前に小さく,夕方に大きくなる.③空っ風日の大気の安定度は冬期平均のそれに比べて弱い.これらの特性は,空っ風日には多くの運動量が地上まで輸送されていること,空っ風が熱対流混合風の性格を持っていることを示唆している.④空っ風日の相対湿度・日降水量は日本海側で高く関東平野で低い.1日当たりの日射量は日本海側で少なく関東平野で多い.これらの傾向は冬期平均に比べてより顕著である.以上の結果は,空っ風がフェーン現象を伴っており,この現象がもたらす晴天が混合層の発達をより助け,熱対流混合層の性格をより強めていることを示唆している.