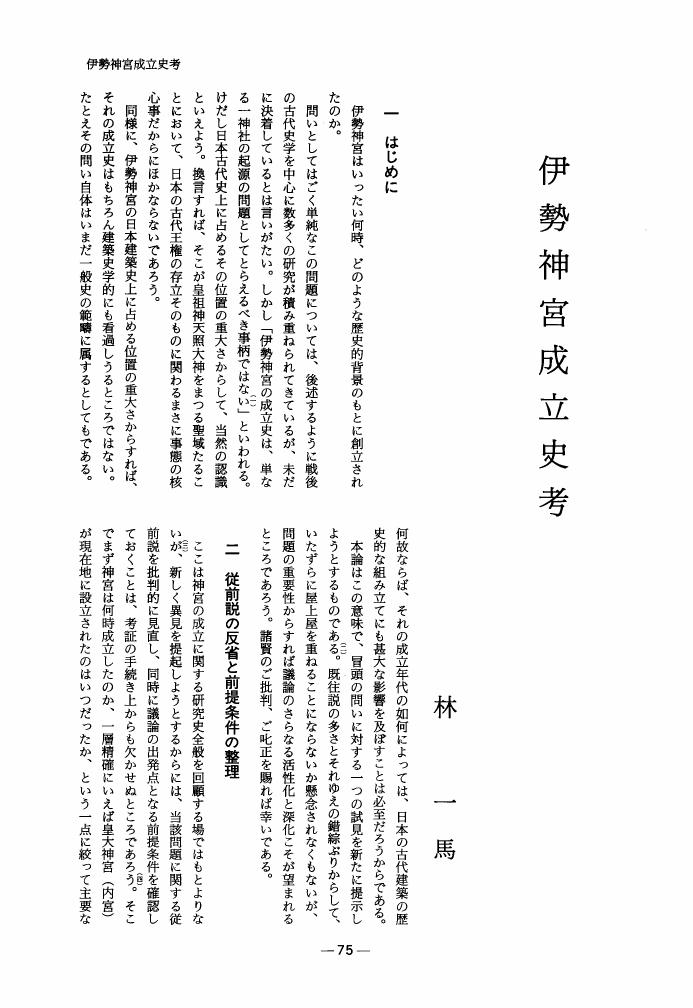3 0 0 0 公報査読の将来像とAI技術による効率化
- 著者
- 酒井 美里
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.7, pp.274-280, 2023-07-01 (Released:2023-07-01)
特許情報データベースにおいては,2000年代の概念検索ブームから沈静化の時代を経て,近年は再びAI技術応用の検討が盛んになっている。現在は特に特許分類や化合物インデックスの自動付与といった分類付与の領域で実用化が進み,各国特許庁での導入例も増えている。また,データベース検索における類似文書検索や,検索結果表示における可視化・クラスタリング等も一般的なものとなりつつある。その一方,公報査読を効率化する技術は模索されているとみられるものの,分類付与や類似文書検索と比べると,実用化は端緒についたばかり,と言えよう。本項では,特許調査業務における「調査の目的と公報の読み方の関係」や「現在表面化している公報査読上の問題点」に着目した。また,公報査読上の問題点はAI技術を応用する事で改善される可能性があるのか,といった点について考察を行った。
- 著者
- 村松 洋
- 出版者
- 日本産業技術史学会
- 雑誌
- 技術と文明 (ISSN:09113525)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.e1, pp.1-14, 2017-04-23 (Released:2023-07-10)
3 0 0 0 OA コミュニティサイトにおける共感を求める質問の認識
- 著者
- 島田 達朗 櫻井 彰人
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 知能と情報 (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.611-618, 2017-08-15 (Released:2017-08-15)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
オンラインコミュニティサイトには多くの質問が投稿されるが,その中には疑問等に対する答えを求めるのではなく質問の具体的な答えそのものよりも,自分の思いへの共感を求める質問がある.共感を求める質問に対して回答する人は,そうでない質問に対して回答する人より有意に少ない.そこで,共感を求める質問に対しても適切な回答を与えることができれば,ユーザのサイトに対する満足度が向上する.共感を求める質問に対して高い回答率を持つユーザー層に回答してもらえるよう,質問を振り分けることにより,共感を求める質問であっても回答される可能性を上げるという方法をとることとした.なお本論文では共感を求める質問とそうでない質問に対して機械学習を用いて分類を行った.
- 著者
- Yasuhiro Nakano Tetsuya Matoba Mitsutaka Yamamoto Shunsuke Katsuki Yasuaki Koga Yasushi Mukai Shujiro Inoue Nobuhiro Suematsu Taiki Higo Masao Takemoto Kenji Miyata Makoto Usui Toshiaki Kadokami Hideki Tashiro Kunio Morishige Kiyoshi Hironaga Hiroyuki Tsutsui for the QcVIC Investigators
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- pp.CR-23-0047, (Released:2023-06-06)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
Background: Recent revisions of clinical guidelines by the Japanese Circulation Society, American Heart Association/American College of Cardiology, and European Society of Cardiology updated the management of antithrombotic strategies for patients with atrial fibrillation (AF) undergoing percutaneous coronary intervention (PCI). However, the extent to which these guidelines have been implemented in real-world daily clinical practice is unclear.Methods and Results: We conducted surveys on the status of antithrombotic therapy for patients with AF undergoing PCI every 2 years from 2014 to 2022 in 14 cardiovascular centers in Japan. The primary use of drug-eluting stents increased from 10% in 2014 to 95–100% in 2018, and the use of direct oral anticoagulants increased from 15% in 2014 to 100% in 2018, in accordance with the revised practice guidelines. In patients with acute coronary syndrome, the duration of triple therapy within 1 month was approximately 10% until 2018, and increased to >70% from 2020. In patients with chronic coronary syndrome, the duration of triple therapy within 1 month was approximately 10% until 2016, and >75% from 2018. Since 2020, the most common timing of discontinuation of dual antiplatelet therapy to transition to anticoagulation monotherapy during the chronic phase of PCI has been 1 year after PCI.Conclusions: Japanese interventional cardiologists have updated their treatment strategies for patients with AF undergoing PCI according to revisions of clinical practice guidelines.
3 0 0 0 IR モスクワの大学生は学習者主導型の日本語授業から何を学ぶか
- 著者
- 小熊 利江
- 出版者
- Centre for Global Communication Strategies, College of Arts & Sciences, The University of Tokyo
- 雑誌
- Eruditi : The CGCS Journal of Language Research and Education
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.1-16, 2017-06
Section 1: Original ResearchThis study investigates a student-led Japanese language class at a university in Moscow. It was an experimental class for Russian students who were accustomed to a traditional passive-learning style. It aims to foster the students' autonomy in Japanese language learning. The purposes of the study are (1) describing the student-led class in detail to share the practice, (2) investigating what the students thought of the class which was their first experience with an active-learning style as opposed to a passive-learning style, and (3) analyzing what they had learned from the student-led class. For these purposes, students' reflection notes and a year-end survey are used for analysis. The design of the class is one in which each student has to search what the entire class should learn and conduct the class on his or her own. It has been revealed that the students took a long time to prepare the materials before leading the class, which made them learn on their own. The types of learning materials that they chose for the class are discussed in the paper. Some students used the same resources or topics as other students. It indicates that they had learned about the new learning resources from each other, in addition to where they should look for the materials. The study also examines how the student-led class was perceived by Russian students. It was apparent that the students highly evaluated the new style of the class. It was observed that the students understood other students' thoughts and opinions through discussion, which in turn led to them better understanding their own. The students were stimulated by one another. Lastly, their reflections showed some clear assessments of what they have learned. However, it seemed difficult for them to put their learning into words; students might need further support from the teacher in this area.
3 0 0 0 OA 近代利根川改修
- 著者
- 松浦 茂樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本治山治水協会
- 雑誌
- 水利科学 (ISSN:00394858)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.1-36, 2021-10-01 (Released:2023-01-11)
明治から今日までに治水を目的とする利根川改修計画は,7回策定された。 1886(明治19)年着工の計画,1900(明治33)年着工,1910(明治43)年着工,1938(昭和13)年着工,1949(昭和24)年着工の計画である。さらに1980 (昭和55)年着工,2005(平成17)年改訂の計画である。 これらを基準点である中田(栗橋)の計画対象流量でみると,1886(明治19)年の計画では定められず,1900(明治33)年計画では3,750m3/s,1938(昭和13)年計画では9,200m3/s,1949(昭和24)年計画では14,000m3/s(ただし上流山地部ダム群で3,000m3/sを調節)となった。1949(昭和24)年計画で,ダム群による調節が登場したのである。 1980(昭和55)年計画,2005(平成17)年計画でもダム群による調節が行わ れ,前者の計画では,6,000m3/sをダム群で調節し17,000m3/sであり,後者の計画では,5,500m3/s調節し17,500m3/sとなっている。 なぜこのように変遷していったのか。1949(昭和24)年計画までは計画直前に生じた洪水(既往洪水)を参考にしたのに対し,1980(昭和55)年と2005 (平成17)年の計画では,年超過確率によって机上計算をもとに定めていった。 計画手法が異なったのである。また,1949(昭和24)年計画までは既往洪水を参考にしたといっても,1938(昭和13)年・1949(昭和24)年計画ではピーク流量の最大値に基づいて定めていったのに対し,それ以前の計画では異なっていた。1886(明治19)年計画では,対象とする洪水がそもそも小さかった。 1900(明治33)年計画では,最大流量ではなく,それより小さい流量を対象と したのである。
- 著者
- Koichiro Suemori Yumi Taniguchi Ai Okamoto Akiko Murakami Fumihiro Ochi Harutaka Aono Naohito Hato Haruhiko Osawa Hitoshi Miyamoto Takashi Sugiyama Masakatsu Yamashita Hisamichi Tauchi Katsuto Takenaka
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.5, pp.523-526, 2022-09-30 (Released:2022-09-22)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2
We conducted two-year seroprevalence surveys of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) antibodies among outpatients and healthcare workers (HCWs) at Ehime University Hospital. Data were collected for outpatients and HCWs in June 2020 (1st survey), December 2020 (2nd survey), July 2021 (3rd survey), and December 2021 (4th survey), focusing on demographics, occupation, and the seroprevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies. Blood samples were obtained from randomly selected outpatients who visited our hospital for medical care and HCWs undergoing regular medical checks with opt-out informed consent. SARS-CoV-2 antibody positivity was evaluated using two laboratory-based quantitative tests. The total number of participants enrolled was 6,369 (1st survey: 1,000 outpatients and 743 HCWs, 2nd survey: 1,000 outpatients and 407 HCWs, 3rd survey: 1,000 outpatients and 804 HCWs, 4th survey: 1,000 outpatients and 415 HCWs). The prevalence of SARS-CoV-2 antibodies among outpatients and HCWs was 0–0.1% and 0–0.124% during the research period, respectively, and changed little over time. These findings suggest that the magnitude of COVID-19 infection during the pandemic among outpatients and HCWs in this rural hospital might have been small.
3 0 0 0 OA 伊勢神宮成立史考
- 著者
- 林 一馬
- 出版者
- 建築史学会
- 雑誌
- 建築史学 (ISSN:02892839)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.75-110, 1997 (Released:2018-08-19)
3 0 0 0 OA 歴代首相の憲法観 -せめぎ合う改憲派・護憲派・現実派-
- 著者
- 井芹 浩文
- 出版者
- 崇城大学
- 雑誌
- 崇城大学紀要 = Bulletin of Sojo University (ISSN:21857903)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.1-9, 2014
明治憲法は全面改正されるまで56年間存続した。これに対し現行の日本国憲法は改正せずにすでに66年が経過した。これだけ長期に改正されなかったのはなぜか。その大きな理由の一つが、歴代の自民党首相が現実主義的なアプローチを取ったためではないかとの仮説を立てた。これを立証するため、吉田茂以来の歴代首相の憲法観を振り返ってみた。歴代首相はカテゴリーとしては「改憲派」「護憲派」「現実派」および自らの見解を示す機会のなかった「回避派」に分けることができよう。まず現実主義者のプロトタイプとして吉田を取り上げる。ただ吉田自身は自衛力を禁じた現行憲法には違和感を持ちつつ、さりとて急激な再軍備は国力が見合っていないというアンビバレントな悩みを抱えていた。続く鳩山一郎、岸信介は改憲を掲げたが挫折し、その後の高度成長期に政権を担ったい池田勇人、佐藤栄作らは改憲論から距離を置き、保守政権の現実主義は定着していく。この後のいわゆる「三角大福中」世代の最後に政権を担当した中曽根康弘はもともと改憲論を唱導していたが、政権に就くや改憲を否定し、現実主義に身をおいた。改憲論者である中曽根にしてこうした行動をとったところに現実主義の岩盤の大きさがうかがえる。そういう背景の中で、新たな改憲派として登場した安倍晋三の出方が注目される。
3 0 0 0 OA 仙台湾における水質環境の推移とその変動要因
- 著者
- 石川 哲郎 三浦 瑠菜 田邉 徹 増田 義男 矢倉 浅黄 阿部 修久 髙津戸 啓介 奥村 裕
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- pp.22-00044, (Released:2023-07-07)
- 参考文献数
- 36
長期モニタリングデータを用いて,震災前後で仙台湾の水質環境(水温,塩分,DO,栄養塩類)に変化が生じているか検討した。震災後,震災前と比べ,栄養塩類とDOは低下し,水温と塩分は上昇する傾向が認められた。震災後の栄養塩類(DINとDIP)の減少は底層で大きく,春季に栄養塩に富む親潮系水の波及が減少した一方で栄養塩が少ない黒潮系水が波及するようになった影響や,震災で生じた底質の変化による夏季から秋季の底質からの栄養塩類の溶出の減少が要因として考えられた。
- 著者
- 牧迫 飛雄馬 赤井田 将真 立石 麻奈 松野 孝也 鈴木 真吾 平塚 達也 竹中 俊宏 窪薗 琢郎 大石 充
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年療法学会
- 雑誌
- 日本老年療法学会誌 (ISSN:2436908X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.1-7, 2022-03-01 (Released:2022-03-30)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 2
【目的】地域在住高齢者における軽度認知障害(mild cognitive impairment: MCI)に関連する可変因子を探索し,それらの組み合わせによるMCIとの関連性を検討することを目的とした。【方法】地域コホート研究(垂水研究2018および2019)に参加した高齢者のうち,MCI群289名と非MCI群289名(プロペンシティ傾向スコアによる1:1のマッチング)の計578名(平均年齢76.15歳,女性63.7%)のデータを横断的に分析した。決定木分析によりMCIの有無に関連する項目を抽出してグループ化した。【結果】決定木分析の結果,握力低下(男性 28 kg未満,女性 18 kg未満),睡眠の質の低下,社会参加の有無の組み合わせによりグループが形成され,MCIの割合は握力低下なし+睡眠の質の低下なしの群で最も低く(37.7%),握力低下あり+地域行事の参加なしの群で最も高かった(82.0%)。【結論】筋力が維持され,睡眠の質が良好な高齢者では認知機能低下が抑制されている可能性が高く,一方で筋力が低下し,社会参加(地域行事などへの参加)が乏しい高齢者では認知機能の低下が疑われ,MCIを有する割合が高くなることが示唆された。筋力,睡眠,社会参加を良好な状態に維持すること,またはいずれかに低下が認められてもそれ以外の因子を良好な状態を保つことが認知機能低下の抑制に寄与するかもしれない。
3 0 0 0 OA 二重織技法の応用による作品制作―台湾の民話―
- 著者
- 許 尚廉 松本 美保子
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維機械学会
- 雑誌
- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.9, pp.610-613, 2008-09-25 (Released:2021-07-25)
- 参考文献数
- 5
3 0 0 0 OA 日本陸軍の戦時動員計画と補給・兵站体制構築の研究
3 0 0 0 OA 米国における合理的配慮 ―産業保健専門職による支援の実務と役割―
- 著者
- 辻 洋志
- 出版者
- 一般社団法人 日本産業精神保健学会
- 雑誌
- 産業精神保健 (ISSN:13402862)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.99-104, 2023-06-20 (Released:2023-06-20)
- 参考文献数
- 11
障害を持つアメリカ人法(ADA)は合理的配慮規定を有する世界初の包括的な差別禁止法として1990年に米国で制定され,病気や障害を持つ労働者の職場復帰支援や両立支援に大きな影響を与えた.2008年に改正され権利保護の対象は広く,また明確化された.機能障害と能力障害を明確に分けつつ,適格者,本質的な職務,主要な生活活動,主要な身体機能,相当制限,機能障害軽減手段,合理的配慮,話し合いによる合意プロセス,過重な負担をキーワードに構成される.合理的配慮に関する事例対応は健康診断/医学的評価と提供可能な職務の身体精神負荷の評価を行い,話し合いによる合意プロセスを経て,必要な合理的配慮を同定,提供と共に目標を設定し,その後は観察しつつ配慮内容を適宜修正する.医師は医学的職務適性評価を軸に支援を行っている.本来行われるべき合理的配慮の不提供は事業主に罰則があり,HR部門や,産業看護職,産業医,外部機関が支援に当たる.
3 0 0 0 OA 食品ハザードの評価次元の検討 ──人工性の評価に着目して──
- 著者
- 長谷 和久
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.94.21063, (Released:2023-02-01)
- 参考文献数
- 44
Studies on various hazards have shown that such hazards are characterized by two dimensions, namely being “dreaded” and “unknown.” Conversely, when evaluating food-related hazards, the degree to which the food is perceived as artificial (i.e., the evaluation of artificiality) has been shown to affect risk perception and willingness to accept food. Accordingly, this study (N = 923) investigated the factors that influence risk perception for various food hazards (e.g., genetically modified foods) by adding items related to artificiality to the conventional items related to the two dimensions (dreaded, unknown). The results showed that items related to artificiality constituted the same principal component as those related to the dimension of “dreaded.” Additionally, foods that were evaluated as artificial were also evaluated as having lower benefits. Based on the findings, specific characteristics of foods that are likely to be avoided (or accepted) were mentioned, and future directions for studies related to food risk perception were discussed.
- 著者
- Hiroyuki Yamamoto Takahiro Sawada Hirohisa Murakami Tomofumi Takaya
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- pp.CR-23-0018, (Released:2023-05-31)
- 参考文献数
- 1
3 0 0 0 OA クラスター弾に「烙印」は押せるか ―オスロ・プロセスをめぐる言説の分析―
- 著者
- 福田 毅
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.67-87, 2010-03-31 (Released:2022-04-14)
3 0 0 0 OA 小動物整形外科用骨プレートを用いて外科的矯正術を行った漏斗胸の猫5例
- 著者
- 草場 祥雄 平川 篤 草場 晴奈 草場 治雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.11, pp.695-699, 2019-11-20 (Released:2019-12-20)
- 参考文献数
- 9
漏斗胸は幼齢猫にまれに発生し,胸骨及び肋軟骨の先天的奇形により胸郭形態が異常なため,呼吸困難,発咳,発育不良などの症状を呈する.その症状改善には,外科的矯正術が必要とされる.今回われわれは,本疾患の7~22週齢の幼猫5症例において,小動物整形外科用骨プレートを用いて胸郭の矯正術を行った.すなわち,全例において,半楕円形に湾曲させた骨プレートを最陥没部の胸骨とその左右肋軟骨に非吸収糸で結紮固定した.結果,全例において,手術直後から胸郭形態の正常化と症状の消失が得られ,その後の追跡期間(8~48カ月,中央値15カ月)においても再発は認められなかった.また,術前術後の解剖学的重症度と臨床重症度スコアによる評価結果からも,本術式は猫の漏斗胸の矯正に有用であると思われた.