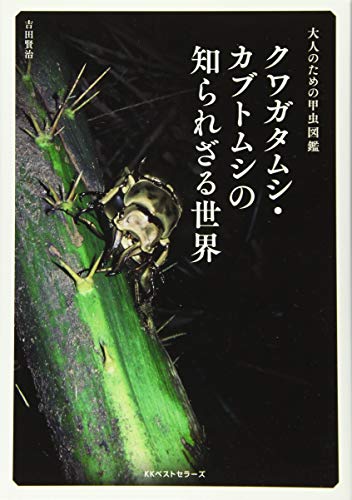3 0 0 0 OA ショパール関節と後足部の機能解剖から理解する足の変形
- 著者
- 橋本 健史
- 出版者
- 一般社団法人 日本フットケア・足病医学会
- 雑誌
- 日本フットケア・足病医学会誌 (ISSN:24354775)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.22-27, 2023-01-31 (Released:2023-01-31)
- 参考文献数
- 15
直立二足歩行を支える足関節,特に後足部の距腿関節, 距骨下関節およびショパール関節に焦点をあて, 機能解剖を検討した. 距腿関節は脛骨天蓋と腓骨がつくる溝に距骨がはまり込む蝶番関節である. 骨性に安定した関節である反面, 内果傾斜角の増大など, その構造に変形が生じると変形性関節症を生じる. 距骨下関節は距骨底面の楕円凹面と踵骨上面の楕円凸面がつくる顆状関節である. 荷重時には, 距腿関節では底屈, 内がえしが生じ, 距骨下関節では背屈, 外がえしが生じるというまったく逆の動きをする. ショパール関節は距骨と舟状骨がつくる距舟関節と踵骨と立方骨がつくる踵立方関節からなる. 後脛骨筋が収縮して内がえしとなると, 距舟関節と踵立方関節の運動軸が交叉して足の剛性が高まり, 安定した足となる. 逆に長腓骨筋が収縮して外がえしとなると, 2つの運動軸は平行となって, 足の剛性が低下して柔軟な足となる. 後足部の腱には, 後脛骨筋腱の内果後方部とアキレス腱の停止部付近に血管の少ない阻血領域が存在する. 加齢や使い過ぎによって, この部位に血流障害が生じやすく, 後脛骨筋腱に障害が生じたときは, 後脛骨筋腱機能不全となり, 扁平足変形となる.
3 0 0 0 OA 日本における犯罪鑑識科学の現状
- 著者
- 鈴木 隆雄
- 出版者
- 社団法人 日本写真学会
- 雑誌
- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.339-344, 2004-08-25 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 12
犯罪捜査において, 犯罪を立証するためには物的証拠が不可欠であるが, 裁判において, その物件が犯罪の証拠であることを科学的に証明する学問を法科学と呼んでいる. 法科学は大きく2つの範疇に分けられる. 1つは, 犯罪現場で採取される物件の分析鑑定を法科学者が行うための学問である犯罪鑑識科学と, 他の1つは死体を医学者が医学的に検証する法医学である. 犯罪鑑識科学は, 狭義の法科学とも呼ばれ, 生物学, 化学, 工学, 心理学, 文書, 指紋・足痕跡・写真などの分野を包含し, あらゆる犯罪捜査の鑑識活動を支えている. 鑑識画像科学は工学分野に属するが, その技術は様々な犯罪鑑識科学の分野で利用されている.
- 著者
- 中西 襄 阿部 光雄
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.A3-A5, 1989-04-20 (Released:2017-10-02)
3 0 0 0 OA 日本の主要都市における直線距離と道路距離との比に関する実証的研究
- 著者
- 森田 匡俊 鈴木 克哉 奥貫 圭一
- 出版者
- 一般社団法人 地理情報システム学会
- 雑誌
- GIS-理論と応用 (ISSN:13405381)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.1-7, 2014-06-30 (Released:2019-02-28)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 23 7
Using the empirical road network data and regression analysis, we investigated the ratio of the road distance to the straight line distance in major cities in Japan. The ratios are relatively different by cities. Therefore, in order to replace the road distance by the straight line distance, we do not use the known ratio that is revealed in different city without careful consideration. If we replace the road distance by the straight line distance, we have to consider the road network of the target city. In addition, we found that the cities which have small ratio of the road distance to the straight line distance generally tend to have high coefficient of determination. In other hands, the cities that have high ratio of the road distance to the straight line distance generally tend to have small coefficient of determination. Therefore, when we replace the road distance by the straight line distance in the cities which have small ratio of the road distance to the straight line distance, there is a certain degree of reliability.
3 0 0 0 OA 全国人口の再生産に関する主要指標:2020年
- 著者
- 別府 志海 Motomi BEPPU
- 出版者
- 国立社会保障・人口問題研究所
- 雑誌
- 人口問題研究 = Journal of Population Problems (ISSN:03872793)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.1, pp.212-227, 2022-03
統計
3 0 0 0 OA ベイトソンの戦時研究 NARA および UCSC 資料の分析から
- 著者
- 飯嶋 秀治
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第57回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.B02, 2023 (Released:2023-06-19)
本研究ではグレゴリー・ベイトソンの戦時活動をアーカイブス研究から明らかにする。特にNARAⅡの文献カードの定量調査とUCSCの個別フォルダ調査を用い、OSS前史としての反ナチ運動とモラル研究、サイバネティクス研究前史としての精神医学者ミルトン・エリクソンとの関係を重視する。そこからベイトソンのインテリジェンス活動を位置づけ、戦後理論への文脈を見る。
- 著者
- Arito Yozu Junji Katsuhira Hiroyuki Oka Ko Matsudaira
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.7, pp.502-506, 2023 (Released:2023-07-01)
- 参考文献数
- 16
[Purpose] Humans keep their trunks vertical while walking. This defining characteristic is known as upright bipedalism. Research on the neural control of locomotion indicates that not only subcortical structures, but also the cerebral cortex, especially the supplementary motor area (SMA), is involved in locomotion. A previous study suggested that SMA may contribute to truncal upright posture-control during walking. Trunk Solution® (TS) is a trunk orthosis designed to support the trunk in decreasing the low back load. We hypothesized that the trunk orthosis might reduce the burden of truncal control on the SMA. The objective of this study was, therefore, to determine the effect of trunk orthosis on the SMA during walking. [Participants and Methods] Thirteen healthy participants were enrolled in the study. We measured the hemodynamics of the SMA during walking with functional near-infrared spectroscopy (fNIRS). The participants performed two gait tasks on a treadmill: (A) independent gait (usual gait) and (B) supported gait while wearing the TS. [Results] During (A) independent gait, the hemodynamics of the SMA exhibited no significant changes. During (B) gait with truncal support, the SMA hemodynamics decreased significantly. [Conclusion] TS may reduce the burden of truncal control on the SMA during walking.
3 0 0 0 OA 海産生物に含まれるヒ素の化学形・毒性・代謝
- 著者
- 塩見 一雄
- 出版者
- Japanese Society for Food Hygiene and Safety
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.1-10, 1992-02-05 (Released:2009-12-11)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 11 8
3 0 0 0 OA ワシントン会議開催と日米関係
- 著者
- 大畑 篤四郎
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.17, pp.91-106, 1961-12-15 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 48
3 0 0 0 OA 同位体分離の最近の進歩 化学交換法およびプラズマ分離法によるウラン濃縮とトリチウム分離
- 著者
- 中根 良平
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.8, pp.754-767, 1980-08-10 (Released:2009-02-09)
- 参考文献数
- 43
Isotope separation effect for uranium by chemical exchange had been found to be too small for practical applications. However, Japan developed recently a promising uranium en-richment process based on chemical exchange, which is an ion exchange reaction between uranous ion in an anion resin bed and uranyl ion in solution. Developement of a water-hydrogen exchange process has been eagerly anticipated as tech-nology for large scale separation of tritium. This paper reviews recent studies which have resulted in the developement of highly active hydrophobic platinum catalysts. The research concerning isotope separation in plasma has been in progress. In this area two schemes-plasma rotation and ion cyclotron resonance-show the most promissing results. However, one cannot presently be sure that these methods will lead to an economical large scale separation, because the physics is more complex than that involved in other separ-ation techniques.
- 著者
- 坂本 祐太 甘利 貴志 寄持 貴代 山田 徹 小野 美奈
- 出版者
- 日本ヘルスサポート学会
- 雑誌
- 日本ヘルスサポート学会年報 (ISSN:21882924)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.25-32, 2019 (Released:2020-01-11)
- 参考文献数
- 25
目的:地域在住高齢者の5 回立ち上がりテスト(Sit to Stand-5、以下、SS-5)におけるQuality Of Life (以下、QOL)低下のカットオフ値を算出する。方法:一次介護予防事業に参加した65 歳以上の参加者155 名を対象に、SS-5 とEuro QOL 5 dimension の項目で主観的にQOL を評価した。Euro QOL 5 dimension は項目を正常と低下の2 群とした。カットオフ値はReceiver Operating Characteristic曲線のAria under curve (以下、AUC)により算出した。結果:SS-5 のカットオフ値は、それぞれ「移動の程度」で10.0 秒(AUC=0.72)、「普段の活動」で10.0 秒(AUC=0.77)、「痛み/不快感」で8.3秒(AUC=0.77)であった。結論:この研究ではSS-5 のカットオフ値を検証した。SS-5 におけるQOL 低下のカットオフ値は下肢とQOL の関連を示し、運動の動機づけするための具体的な目標値となる可能性が有る。
- 著者
- 田中 雄大
- 出版者
- 日本現代中国学会
- 雑誌
- 現代中国 (ISSN:04352114)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.95, pp.94-98, 2021 (Released:2023-07-01)
3 0 0 0 OA 超音波エラストグラフィによる肝線維化診断
- 著者
- 飯島 尋子 西村 貴士
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.1, pp.30-42, 2020-01-10 (Released:2020-01-15)
- 参考文献数
- 122
この約20年間に,超音波エラストグラフィが利用可能になったことで,非侵襲的な方法で肝線維症の診断と病期判定が可能になり,肝臓学の臨床診療が変わりつつある.しかし慢性肝疾患には複数の成因があり,それにより測定値が異なる.また肝線維化の評価だけでなく,予後予測,および経過観察も重要である.超音波エラストグラフィには,strain(ひずみ)イメージング,transient elastography,p-SWE,2D-SWEがあり,すべてにおいて肝線維化診断は可能である.それぞれの方法,臨床的有用性などについて述べる.
- 巻号頁・発行日
- 1945-07
3 0 0 0 OA 明治期のデザイン技法書
- 著者
- 日野 永一
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.23-30, 1994-09-20 (Released:2017-07-25)
明治末から大正の初期(1909-1913)にかけて,5冊のデザイン技法書が相次いで刊行された。これらの書は専門教育を対象としているが,当時普通教育の中へデザインが導入されたことが,大きな出版の契機となっている。これら技法書は,欧米の研究に基づきながらも,日本独自のデザインを生み出すことに意を用い,それぞれが独自の特色を示している。現在と比較するならば,時代の差と,体系的な未整備が残るが,その基本的な考え方は現在にまで続くものがあり,現在そのまま使用されている用語も少なくない。これらの書で確立されたデザインの創作方法は,その後の日本のデザイン教育に大きな影響を与えることになり,特に「便化」という自然物のスケッチから始まって模様を構成する方法は,長く中心的な指導法の位置を占めるようになった。
3 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1889年03月23日, 1889-03-23
3 0 0 0 OA 人工膝関節全置換術後の個別理学療法と個別集団併用型理学療法の比較
- 著者
- 杉木 竣介 田中 正二 山崎 俊明 後藤 伸介 東 利紀 黒田 一成
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.50-55, 2023 (Released:2023-02-15)
- 参考文献数
- 18
〔目的〕本研究は,人工膝関節全置換術(TKA)後の個別理学療法(個別療法)と個別集団併用型理学療法(併用型療法)を比較し,併用型療法の効果を明らかにすることを目的とした.〔対象と方法〕個別療法を行った者を個別療法群,併用型療法を行った者を併用型療法群とした.研究形式は後ろ向きコホート研究とした.〔結果〕膝関節屈曲可動域(ROM)は,術後3週と術後4週で個別療法群よりも併用型療法群で有意に大きかった.併用型療法群は,個別療法群よりも膝伸展筋力体重比が有意に高く,杖歩行獲得日数および在院日数が有意に短かった.〔結語〕TKA後の併用型療法は,個別療法よりも膝ROMや膝伸展筋力,杖歩行獲得日数や在院日数に正の効果を与える可能性が示唆された.
3 0 0 0 OA 教団法(戒律)と心掛け(戒) : 日本人の気づかなかった区別
- 著者
- 小林 信彦 Nobuhiko KOBAYASHI
- 雑誌
- 桃山学院大学総合研究所紀要 = ST.ANDREW'S UNIVERSITY BULLETIN OF THE RESEARCH INSTITUTE (ISSN:1346048X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.35-50, 2000-01-24
In ancient India, the Buddhist samgha as a self-governing community maintained order by means of its own law called "vinaya." Violators were punished according to vinaya. On the other hand, all Buddhists, whether monks or laymen, were expected to follow particular customs called "sila." Unlike vinaya, this was not compulsory and did not carry penalties. In Japan far away from the original land of Buddhism, no one paid attention to the distinction between vinaya and sila, because temples were the apparatus of government and there was no samgha to be governed by vinaya. Under such circumstances, Saicho (766-822) openly repudiated vinaya and replaced it with sila. From that time down to this day, the Japanese have been convinced that the essence of true Buddhism consists in the repudiation of vinaya.