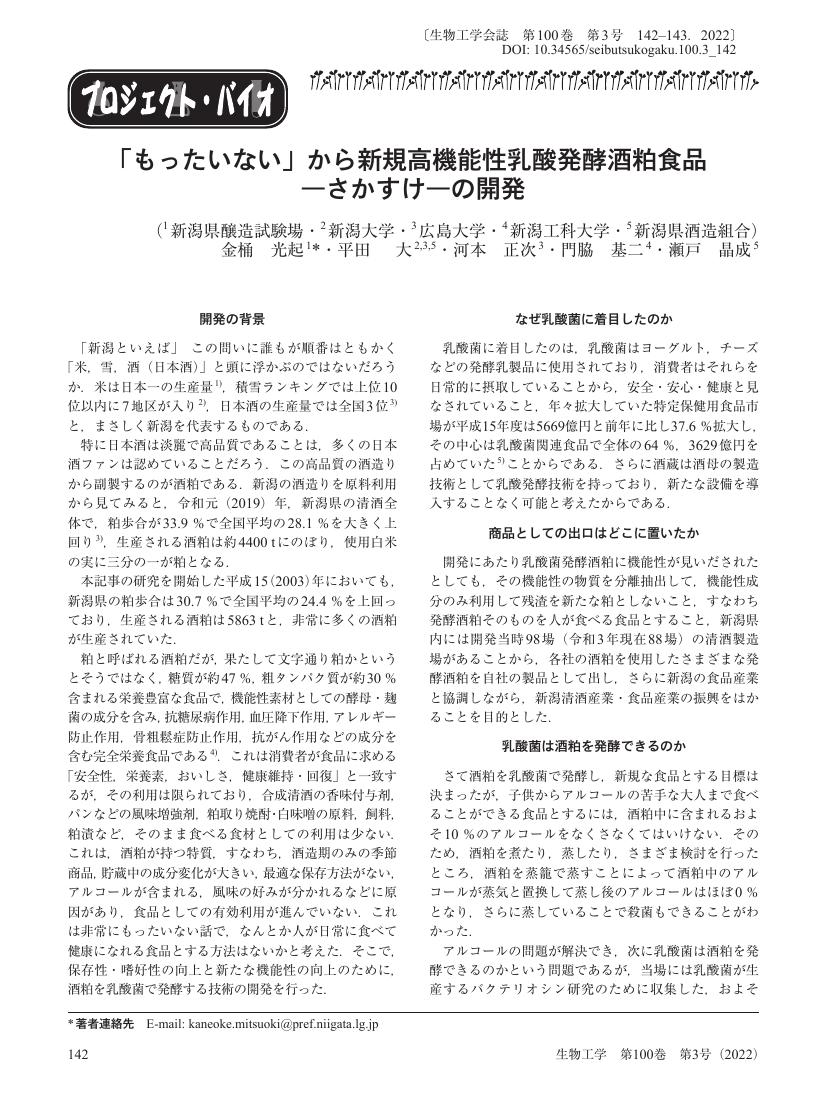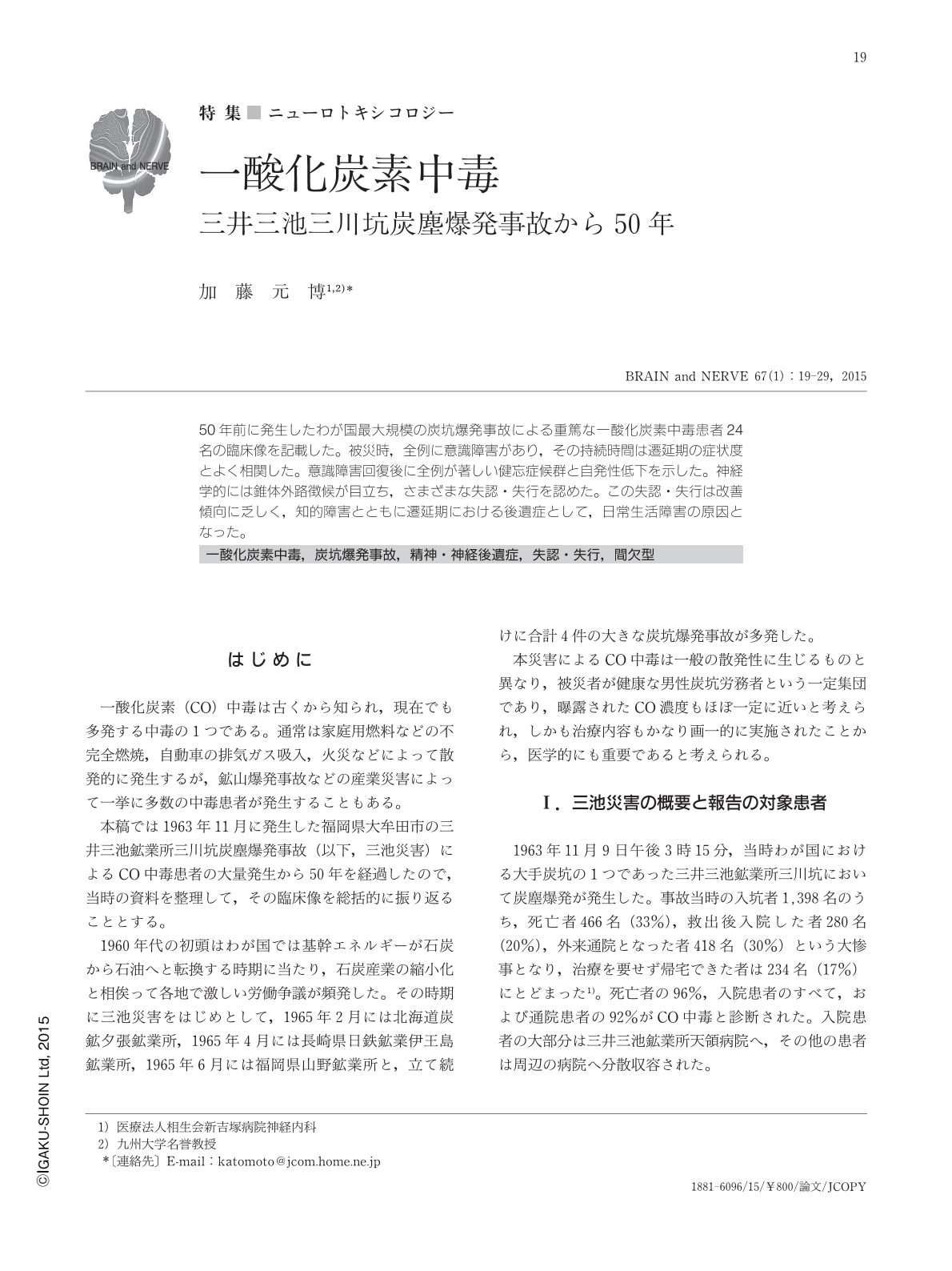3 0 0 0 OA 巻頭言
- 著者
- 舘 暲 藤正 巌 釜江 尚彦
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会誌 (ISSN:13426680)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.4-6, 1996-12-25 (Released:2022-10-30)
3 0 0 0 北極海氷下観測ドローンの開発
- 著者
- 石橋 正二郎 田中 聖隆 前田 洋作 吉田 弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会関東支部総会講演会講演論文集 2021.26 (ISSN:24242691)
- 巻号頁・発行日
- pp.17C09, 2020-03-13 (Released:2021-03-02)
There are lots of knowledge gaps concerning the sea ice of the Arctic Ocean, such as sea ice thickness, sea ice dynamics and sea ice – ocean interactions. Therefore JAMSTEC is now developing a special platform that will be able to move under ice and measure various kinds of data continuously and automatically. It is an intelligence underwater drone for the Arctic Ocean named as COMAI-Drone (COMAI-Drone:Challenge of Observation and Measurement under Arctic Ice - Drone). Now its proto-type have been already designed and initiated to build. Additionally, some aid systems, which can detect its position, can detect the relative direction to a support ship and can communicate between the drone and the support ship, are now developing. At the same time, watertank-tests and field-tests have been conducted gradually. In near future, COMAI-Drone will collect invaluable data under the sea ice in the Arctic Ocean. In this paper, its outline including its mechanism, functions and operation system are described.
3 0 0 0 OA アルミニウム合金の溶接とその歩み
- 著者
- 小林 藤次郎
- 出版者
- 一般社団法人 軽金属学会
- 雑誌
- 軽金属 (ISSN:04515994)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.10, pp.597-607, 1985-10-30 (Released:2008-07-23)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2
3 0 0 0 OA エンドトキシンを引き金としたIgE非依存性鼻炎症状の誘導
- 著者
- 岩﨑 成仁 善本 知広
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.7, pp.936-944, 2017 (Released:2017-08-18)
- 参考文献数
- 38
3 0 0 0 OA 家族と新型コロナ感染拡大におけるジェンダー問題
- 著者
- 筒井 淳也
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.5, pp.5_24-5_28, 2022-05-01 (Released:2022-09-22)
新型コロナウイルスのパンデミックが家族生活に及ぼす影響を整理するために、まずは日本の家族および世帯の50年間の推移を概観すると、男性稼ぎ手型の「標準家族」が一部で持続しているのと並行して、単身世帯の増加などの多様化が生じていることが確認できる。新型コロナの影響のあり方はこうした多様な家族・世帯に応じて異なっており、行政等の対応もこの多様性に配慮すべきである。また新型コロナは、家族の健康管理といったみえにくい家庭内無償労働の女性への偏りを顕在化させ、家族外の人との接触を制限することで女性へのDVリスクを高めたり、メンタルな満足を低減させている可能性がある。新型コロナの問題は、同居人以外との接触制限というこれまで目立ってこなかった措置の結果であり、その影響は通常の経済不況とは違って見渡しにくく、十分な現状把握のもとでの問題の整理が必要である。
3 0 0 0 OA 山口県下の法医解剖における死因究明の実際と将来構想
- 著者
- 姫宮 彩子 中川 碧 酒井 大樹 重本 亜純 髙瀬 泉
- 出版者
- 山口大学医学会
- 雑誌
- 山口医学 (ISSN:05131731)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2+3, pp.75-81, 2022-08-31 (Released:2022-11-02)
- 参考文献数
- 19
法医学講座では,主な業務の一つとして遺体の解剖・検案を実施し,死因等の鑑定を行っている.法医解剖が実施される事例は,医学的に死因が不明であるだけでなく,多くがその背景に社会的課題をもつため,死因究明に加えて死亡状況を検証することは,生きている者に重要な示唆を与える.よって,法医解剖によって得られた情報を関係各所と共有し,現場に携わる関係者同士が再発予防策について検討することの意義は高い.本稿では,山口大学医学系研究科法医学講座の法医解剖における死因究明の現状について2021年実施例の報告というかたちで示し,今後の法医解剖情報の活用について考察する.解剖数は157件で,男性が女性の2倍強を占めた.年齢階級別では10代が最も少なく,成人以降では年齢が上がるとともに漸増し,70代以上が約4割を占めた.死因の種類では内因死が3割,外因死が6割,不詳の死が1割で,内因死の約7割は循環器系疾患,外因死は外傷および溺没で約7割を占めた.全体の約2割が救急搬送され,その一部で臨床科医師による死因の言及がみられた.また,全体の約3割で画像検査データが死因判断に活用された.その他,世代別の外因死,自殺(疑い),医療関連死の事例の特徴を報告する.今後は個々の事例・課題について,関連する臨床科や医療,保健,福祉,行政,さらには医学系研究者の勉強会あるいは検討会等に参加しながら,近い将来の『死因究明により得られた情報を相互に共有・活用できる体制の構築』の実現をめざし,試行していきたい.
3 0 0 0 OA 「もったいない」から新規高機能性乳酸発酵酒粕食品―さかすけ―の開発
- 著者
- 金桶 光起 平田 大 河本 正次 門脇 基二 瀬戸 晶成
- 出版者
- 公益社団法人 日本生物工学会
- 雑誌
- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.3, pp.142-143, 2022-03-25 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 8
3 0 0 0 OA ヨガ : 文化のグローバル化をめぐって
- 著者
- 河原 和枝
- 出版者
- 甲南女子大学
- 雑誌
- 甲南女子大学研究紀要. 人間科学編 = Konan Women's University Studies in Human Sciences (ISSN:13471228)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.89-97, 2015-03-18
3 0 0 0 IR オンライン・フォーラム : コロナ時代の労働・福祉・共生社会
- 著者
- 今野 晴貴 岩橋 誠 藤田 孝典
- 出版者
- 北海道大学公共政策大学院
- 雑誌
- 年報 公共政策学 (ISSN:18819818)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.19-47, 2021-03-31
3 0 0 0 OA 接客対応者におけるカスタマーハラスメント被害経験の分析
- 著者
- 桐生 正幸 島田 恭子
- 出版者
- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所
- 雑誌
- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.19, pp.47-53, 2021 (Released:2022-05-18)
3 0 0 0 OA 癌性腹膜炎で発見された乳癌の1例
- 著者
- 渡部 英 佐藤 雅彦 根上 直樹 石戸 保典 齋藤 徹也 山田 正樹 佐藤 英章 伴 慎一
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.4, pp.890-895, 2013 (Released:2013-10-25)
- 参考文献数
- 16
症例は47歳の女性,急性腹症で来院.腹部全体の筋性防御と圧痛の所見があり,CTで多量の腹水を認めた.汎発性腹膜炎を疑い,緊急開腹手術を施行した.開腹の結果,消化管穿孔の部位はなく,黄色清の腹水を認め,腹腔内全体に白色の硬い小結節が散在していた.手術は試験開腹術に終わった.手術時に摘出した結節と腹水から低分化型腺癌を認め,原発部位不明の癌性腹膜炎と診断した.腹膜播種結節を免疫染色した結果,病理学的に乳癌由来の組織像と診断した.両側乳房に腫瘤は触知しなかったが,CTで左乳腺に淡い陰影像があり,同部位を穿刺した結果,病理学的に腹膜播種と同様の低分化型腺癌を認め,原発部位は乳癌であることが判明した.
3 0 0 0 OA 鹿児島県下大隅国大島郡惨状実記
3 0 0 0 OA 創傷治癒における物理的刺激の役割とその分子メカニズム
- 著者
- 小川 令 黄 晨昱 赤石 諭史 佐野 仁美 百束 比古
- 出版者
- 一般社団法人 日本創傷外科学会
- 雑誌
- 創傷 (ISSN:1884880X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.102-107, 2014 (Released:2014-07-01)
- 参考文献数
- 33
地球上の生命は重力を常に感受し,三次元形態を保っており,皮膚および軟部組織には自然の状態で張力が生じている。これら物理的刺激が,創傷治癒に大きな役割を担っていることが最近分かってきた。メカノバイオロジーは,物理的刺激が,細胞や組織,臓器にどのような影響を与えるかを研究する学問である。皮膚や軟部組織は体内と体外それぞれから常に物理的刺激を受けている組織であり,創傷治癒や組織再建,再生医療を実践する創傷外科医・形成外科医はメカノバイオロジーを理解しておく必要がある。物理的刺激は,細胞のメカノセンサーによって感受され,機械刺激シグナル伝達系路を通じて核内に情報が伝達される。その結果,細胞がタンパク質を産生し,種々の機能が発現される。これら物理的刺激をコントロールする医療をメカノセラピーと定義し,今後創傷外科領域において発展させるべきと考えられた。
3 0 0 0 一酸化炭素中毒—三井三池三川坑炭塵爆発事故から50年
3 0 0 0 OA Nerve Growth Factor-Inducing Activity of Hericium erinaceus in 1321N1 Human Astrocytoma Cells
- 著者
- Koichiro Mori Yutaro Obara Mitsuru Hirota Yoshihito Azumi Satomi Kinugasa Satoshi Inatomi Norimichi Nakahata
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.9, pp.1727-1732, 2008-09-01 (Released:2008-09-01)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 78 105
Neurotrophic factors are essential to maintain and organize neurons functionally; thereby neurotrophic factor-like substances or their inducers are expected to be applied to the treatment of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease. In the present study, we firstly examined the effects of ethanol extracts of four edible mushrooms, Hericium erinaceus (Yamabushitake), Pleurotus eryngii (Eringi), Grifola frondosa (Maitake), and Agaricus blazei (Himematsutake), on nerve growth factor (NGF) gene expression in 1321N1 human astrocytoma cells. Among the four mushroom extracts, only H. erinaceus extract promoted NGF mRNA expression in a concentration-dependent manner. In addition, secretion of NGF protein from 1321N1 cells was enhanced by H. erinaceus extracts, and the conditioned medium of 1321N1 cells incubated with H. erinaceus extract enhanced the neurite outgrowth of PC12 cells. However, hericenones C, D and E, constituents of H. erinaceus, failed to promote NGF gene expression in 1321N1 cells. The enhancement of NGF gene expression by H. erinaceus extracts was inhibited by the c-jun N-terminal kinase (JNK) inhibitor SP600125. In addition, H. erinaceus extracts induced phosphorylation of JNK and its downstream substrate c-Jun, and increased c-fos expression, suggesting that H. erinaceus promotes NGF gene expression via JNK signaling. Furthermore we examined the efficacy of H. erinaceus in vivo. ddY mice given feed containing 5% H. erinaceus dry powder for 7 d showed an increase in the level of NGF mRNA expression in the hippocampus. In conclusion, H. erinaceus contains active compounds that stimulate NGF synthesis via activation of the JNK pathway; these compounds are not hericenones.
3 0 0 0 OA 資金の時間価値を考慮したJコスト論の検討
- 著者
- 井岡 大度
- 出版者
- 日本原価計算研究学会
- 雑誌
- 原価計算研究 (ISSN:13496530)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.113-123, 2014 (Released:2017-04-17)
トヨタ生産方式におけるジャスト・イン・タイムの重要な側面としてリードタイム短縮があげられるが,その改善活動の効果を財務数値と結びつけものとして,田中正知氏により提唱された理論が「Jコスト論」である。本稿では,この「Jコスト論」が資金の時間価値の考慮について,その評価が単利計算によるものであることを計算構造の観点から明らかにし,その展開として,連続複利による複利計算を前提とし,リードタイム等の短縮による効果の分析のための評価方法について提案・検討するものである。