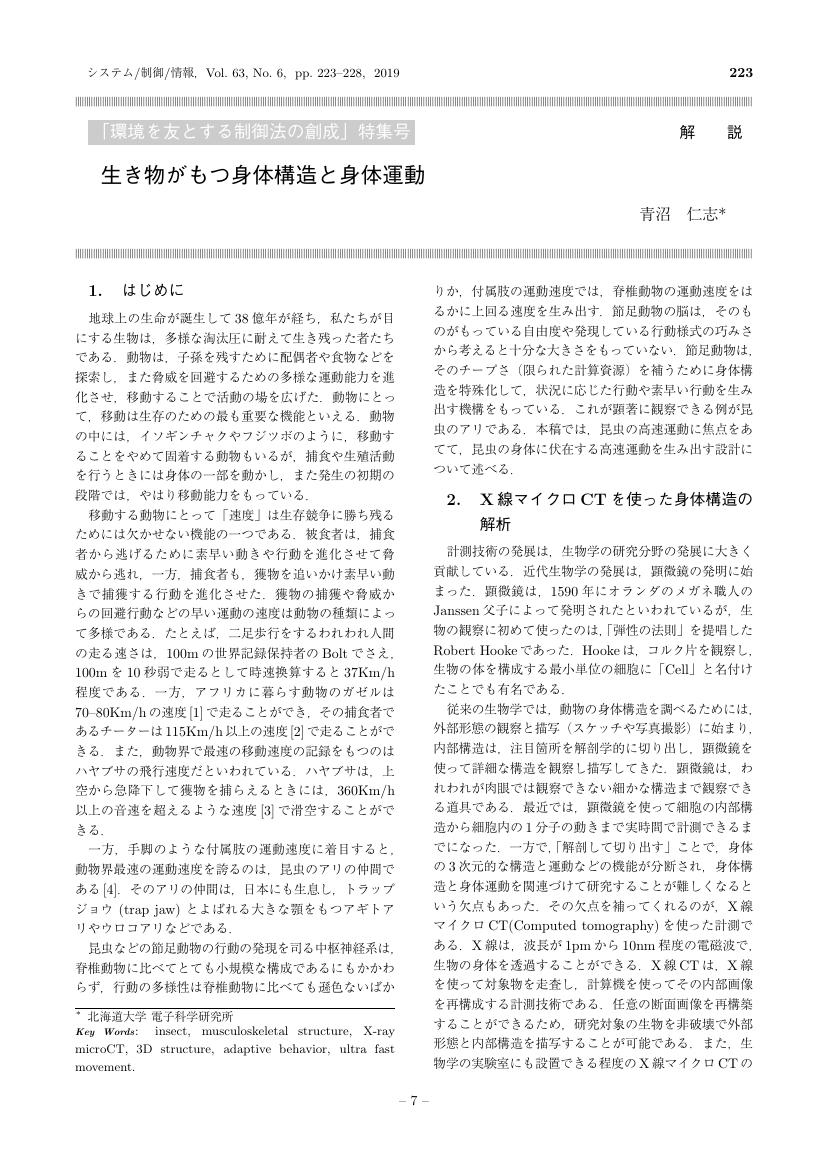- 著者
- 岡本 拓 杉島 夏子
- 出版者
- 海外日本語教育学会
- 雑誌
- 海外日本語教育研究 (ISSN:24323179)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.1-16, 2020-12
- 著者
- 川口 純 江幡 知佳 KAWAGUCHI Jun EBATA Chika
- 出版者
- Division of Education, Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba
- 雑誌
- 筑波大学教育学系論集 = Bulletin of Institute of Education University of Tsukuba (ISSN:03858979)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.35-48, 2017-03
3 0 0 0 OA 児童・青年期の非自殺性自傷 ─嗜癖と自殺との関係から─
- 著者
- 松本 俊彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.158-168, 2019-04-01 (Released:2020-02-28)
- 参考文献数
- 28
非自殺性自傷とは,感情的苦痛の緩和や他者に対する意思伝達や操作などの,自殺以外の意図からなされる,故意の身体表層に対する直接的損傷行為を指す。この行動は,DSM-Ⅳ-TRの時代までは,境界性パーソナリティ障害の一症候としてのみ認識されてきたが,DSM-5では,この行動は境界性パーソナリティ障害とは独立した診断カテゴリーとなった。このことは,従来の,自傷を限界設定の対象と見なす考え方から,自傷それ自体を治療の対象とする考え方と,治療理念の変化が生じたことを意味する。本稿では,まず非自殺性自傷に関する臨床概念の歴史的変遷を振り返り,今日における非自殺性自傷の捉え方へと至る過程を確認したうえで,物質使用障害などの嗜癖,ならびに自殺との異同を論じ,最後に,DSM-5における非自殺性自傷の診断カテゴリーの意義と課題について筆者の私見を述べた。
3 0 0 0 OA 富士山測候所における大気環境観測
- 著者
- 大河内 博
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.10, pp.639-643, 2021-10-05 (Released:2021-10-05)
3 0 0 0 OA 鳥取県立博物館に寄贈された石坂元貝類コレクション : 非海産腹足類
- 著者
- 黒住耐二
- 出版者
- 鳥取県
- 雑誌
- 鳥取県立博物館研究報告
- 巻号頁・発行日
- no.48, 2011-03-30
- 著者
- アスラン アドナン
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究. 別冊 (ISSN:21883858)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.61-62, 2015-03-30
3 0 0 0 OA 福祉実践の方法論としての行動分析学 : 社会福祉と心理学の新しい関係
- 著者
- 望月 昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.64-84, 1989-11-01 (Released:2018-07-20)
- 被引用文献数
- 2
This article is a proposal for the full cooperation of the profession of "psychology" and "social welfare" for the handicapped person through the mediation of philosophy and methodology of "behavior analysis. " From the standpoint of "radical behaviorism," which is the philosophy of "behavior analysis" founded by B.F. Skinner, every term or concept on handicapped person is a description of the interaction between individual and environment. Any behavioral service for those people, therefore, is a "adjustment" between individuals and their environments. In this context, if necessary, we must change their environments including the social systems. Behavioral approach, however, has been regarded as a procedure which changes only the client in the field of social casework. The reason of the misconception might be derived both from outside and inside of the framework of behavioral approach itself. For the full cooperation of behavior analyst and social caseworker, some new directions of method of "behavioral social casework" were discussed.
3 0 0 0 「二層の広域圏」の「生活圏域」構想に関する考察と提言
- 著者
- 森川 洋
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.111-125, 2009
<p>In May 2004 the National Land Council introduced the concept of 'service areas of central cities (living areas)' in the 'regional structure of two tiers'. It consists of two parts: 9 regional blocks with 6 to 10 million inhabitants, and 82 living areas principally with more than 300,000 inhabitants in areas delimited by a one-hour-distance (by family car) from central cities with over approximately 100,000 inhabitants. However, in actually considering their distribution as uniform as possible throughout the whole country, there are smaller areas such as the living area of Imabari City with only 190,000 inhabitants in 82 living areas which are distributed similarly to the 85 commuting and schooling areas prepared by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Within these 82 living areas about 90 percent of total population of the country can enjoy fundamental urban services and maintain their high living condition. Accordingly, the concept of living areas is intended to prevent population decreases in non-metropolitan areas.</p><p>Although this concept that intends to maintain a uniform living standard for the inhabitants of non-metropolitan areas seems to be mostly effective in the period of population decrease forecast for the future, it tends to overestimate the service areas of central cities as compared to the actual commuting area of each central city as shown in Table 3. Commuting areas of smaller cities located on the peripheries of designated living areas, such as the commuting area of Kashiwazaki City near by Nagaoka City and the commuting area of Mihara City near Fukuyama City, are fearful of extraordinary decline under decreasing population brought about by the measures for the promotion of these 82 central cities. In order to prevent the rapid population decrease of central cities and their surrounding areas in non-metropolitan areas, and to keep a population balance between them and metropolitan areas, it is necessary to designate smaller central cities with living areas of 100,000 to 300,000 inhabitants as the second tier, adding to the living areas of over 300,000 inhabitants. In addition, the author will propose the promotion of central places with living areas of more than 10,000 inhabitants as the third order. The promotion measures of larger cities strikes a severe blow to smaller cities, so it is necessary to promote not only large cities but also small cities. Since some of these small central places have under-populated areas within their living areas, these measures will contribute to relieving the population decrease in under-populated areas and areas rich in natural surroundings.</p>
3 0 0 0 IR 日本モンゴル共同調査"ビチェースⅢ"成果報告:突厥ならびにウイグルの石造物 [英文]
- 著者
- ルンデフ ゴーニー 大澤 孝 鈴木 宏節 齊藤 茂雄 ツォグトバータル バトムンフ LKHÜNDEV Göönii OSAWA Takashi SUZUKI Kosetsu SAITO Sigeo TSOGTBAATAR Batmönkh
- 出版者
- 金沢大学人文学類考古学研究室
- 雑誌
- 金大考古 = The Archaeological Journal of Kanazawa University
- 巻号頁・発行日
- no.79, pp.16-41, 2021-03-31
特集:モンゴル国で実施された考古調査報告集Special issue: Reports of archaeological research in Mongolia
3 0 0 0 OA 生き物がもつ身体構造と身体運動
- 著者
- 青沼 仁志
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.223-228, 2019-06-15 (Released:2019-12-15)
- 参考文献数
- 23
3 0 0 0 地震観測記録に基づく応答スペクトル比の評価
- 著者
- 北野 哲司 小島 清嗣 永田 茂 大保 直人 石田 寛
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 地震工学研究発表会講演論文集 (ISSN:18848435)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.393-396, 2001
名古屋市及びその周辺地域には, 都市ガス供給設備の地震安全性確保を目的として103台の地震計が設置されており, 1997年愛知県東部地震 (M5.8), 1998年岐阜県美濃中西部地震 (M5.4) 及び2000年三重県中部地震 (M5.5) の地震動が観測されている.本論文では, これら高密度地震観測網で得られた地表観測記録と対象地域内の数箇所で実施した地質調査データを用いてせん断波速度Vsが500m/s程度の工学的基盤における広域の地震動予測を行った. さらに, 地表の観測記録及び工学的基盤における推定地震動から, 中小地震時の表層地盤を対象とした加速度応答スペクトル (5%減衰) の増幅倍率 (以下では応答スペクトル比と呼ぶ) の広域評価を行った.
3 0 0 0 OA 講義ノート:容貌の障害 : 障害福祉の視点から
- 著者
- 杉野 昭博
- 出版者
- 首都大学東京社会福祉学研究科
- 雑誌
- 人文学報, 社会福祉学 (ISSN:03868729)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.149-163, 2019-03
資料
3 0 0 0 IR 青年期における恋愛と性行動に関する研究(3)- 大学生の浮気経験と浮気行動 -
- 著者
- "牧 野幸志" Koshi" "MAKINO
- 雑誌
- 経営情報研究 : 摂南大学経営情報学部論集
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.19-36, 2012-02
"本研究は,青年期における恋愛と性行動に関する調査研究である。本研究では,まず,現代青年の浮気経験,性経験を明らかにする。その後,浮気経験者への調査により,浮気関係,浮気行動の内容を明らかにする。被験者は,大学生・短大生400 名(男性195 名,女性205 名,平均年齢19.09歳)であった。そのうち,浮気経験者は52 名(男性22 名,女性30 名)であった。調査の結果,現代青年において浮気経験率は全体の13.0%,恋愛経験者における浮気経験率は17.4%であった。性差はみられなかった。また,性経験率は全体で40.5%であった。浮気行動を分析したところ,浮気関係では性的な関係を持つものが多く,浮気相手は同年齢が多かった。浮気の主な理由は,男性では「性的欲求を満たすため」が多く,女性では「相手の魅力」が多かった。浮気回数は,男女ともに1,2 回が多く,浮気が終わった理由は,女性では「恋人への罪悪感」が最も多かった。"
3 0 0 0 OA モータ代数とグラフ理論による機構の記述と解析(第1報) 自由度の定義と速度解析
- 著者
- 城 道介 鳥原 冬輝
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.7, pp.1272-1278, 1988-07-05 (Released:2009-10-08)
- 参考文献数
- 6
A new definition of degrees of freedom of mechanisms is presented in terms of pair-loop matrices derived from pair-axis-motors and circuit matrices. A motor or a set of screw coordinates is an extended form of a vector by which instantaneous motion of a rigid body can be represented completely and uniquely. Superpositions of velocities correspond to summations of motors. The definition is valid for mechanisms with multiple closed loops and with critical forms such as pantograph. Pair-loop matrices have enough information of constraints of mechanisms to set up loop equations which determine magnitude ratios of relative velocities on all pairs. An algorithm based on pair loop equations is presented in order to simulate motion of mechanisms. Output examples of simulation program coded in APL show the effectiveness and conciseness of this algorithm.
- 著者
- 後藤 早智 茂木 瑞穂 薮下 綾子 三輪 全三 髙木 裕三
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.193-201, 2012-06-25 (Released:2015-03-17)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
歯科用局所麻酔剤スキャンドネストⓇ(3%メピバカイン塩酸塩製剤)は,血管収縮薬,防腐剤や酸化防止剤等の添加物が無配合,短時間作用型という特徴を持つことから小児歯科治療において有用であると考えられるが,小児に対しての国内での使用成績の報告は少ない。そこで,本研究では,小児歯科治療における本剤の臨床的有用性を検討した。対象は東京医科歯科大学歯学部附属病院小児歯科外来で局所麻酔下にて窩洞形成や抜髄等の歯科治療を行った148 症例で,術者および患児にアンケート調査を行った。局所麻酔剤はスキャンドネストⓇ,シタネストⓇ,シタネスト-オクタプレシンⓇ,キシロカインⓇ,オーラⓇ注の5 種類から,術者の判断で選択し,使用した。その調査結果では,麻酔効果および処置中の痛みにおいて,薬剤間による有意差は認められなかった。また,薬剤の種類と術後違和感において有意な差が認められ,スキャンドネストⓇは,他剤と比較して術後違和感が少ない傾向が認められた。以上より,スキャンドネストⓇの麻酔効果は他剤と同等で,持続的観血処置や長時間(30 分以上)の処置を除けば,術後の咬傷などを防ぐ意味でも小児歯科において有用性の高い局所麻酔剤と考えられ,他剤を含めた局所麻酔剤の選択肢が拡大したといえる。
- 著者
- 芳賀 恵 玄 武岩
- 出版者
- 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院 = Graduate School of International Media, Communication, and Tourism Studies, Hokkaido University
- 雑誌
- 国際広報メディア・観光学ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.3-19, 2018-03-20
This article examines the narrow path to de-nationalisation in South Korean films dealing with the Japanese colonial period since the 2000s that we call 'colonial pieces'. Based on Ryu Seung-wan's "Battleship Island" (Gunhamdo, 2017) situated during Korean mobilization under colonial rule, we argue that it is possible to clarify the style and strategy of visual representation used to replace the dichotomy of victimizers (Japan) and victims (Korea) in recent 'colonial piece' films. By focusing on the representation and its stylistic aspects of "Battleship Island" in relation to the empire of Japan through the periodical transition of political, social and cultural meaning, this article explores the way in which these films act on the process of reproducing colonial memories in Korean society and the historical issue between Japan and Korea, as a postcolonial problem of cultural and social politics.
- 著者
- 斎藤 祥平
- 巻号頁・発行日
- 2015-03-25
Hokkaido University(北海道大学). 博士(学術)
- 著者
- 武山 絵美 九鬼 康彰 松村 広太 三宅 康成
- 出版者
- 社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業土木学会論文集 (ISSN:03872335)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.241, pp.59-65, 2006-02-25 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 9
和歌山県龍神村の山間農業集落を対象に, 獣害を引き起こすイノシシに注目し, 生息痕跡を調査することにより山林から水田団地までのイノシシの侵入経路を把握した.また, 水田利用・管理状況を水田一筆単位で調査し, 水田団地へのイノシシの侵入経路形成との関連性を分析した.その結果,(1) 谷沿いの永年性作物転作水田の管理不足により谷沿いにバソファが形成されてイノシシの移動経路 (コリドー) が拡大し, これらの水田が水田団地への侵入経路として利用されていること,(2) 石積み畦畔に比べ土畦畔が圃場から圃場への移動ポイントとして利用される傾向にあり, 約2mの土畦畔でも乗り越えが可能であること, また乗り越えられるポイントは同じ地点が継続的に利用される傾向にあること, を示した.
3 0 0 0 OA 大気・海洋・陸面結合モデルによる温暖化予測
- 著者
- 真鍋 淑郎
- 出版者
- The Remote Sensing Society of Japan
- 雑誌
- 日本リモートセンシング学会誌 (ISSN:02897911)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.366-372, 2001-09-28 (Released:2009-05-22)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
大気・海洋結合モデルの数値実験によると,21世紀末ころには地表の全球平均気温は現在より2~3℃程度上がる。昇温は,陸面で更に大きくなると予測される。また,半乾燥地帯の土壌水分が減少し,砂漠が拡張しそうである。二酸化炭素などを規制せずに放出し続ければ,数百年先に大気の二酸化炭素濃度が,今の4倍位になり,非常に大きな気候の変化がおこる可能性が大きい。これからは,温暖化に伴う全球的変化の検出,放射強制力を持っ温室効果ガス,エアロゾル等の分布決定,モデルに組み込まれた色々な素過程の検証等にRemote Sensingが増々重要になるであろう。