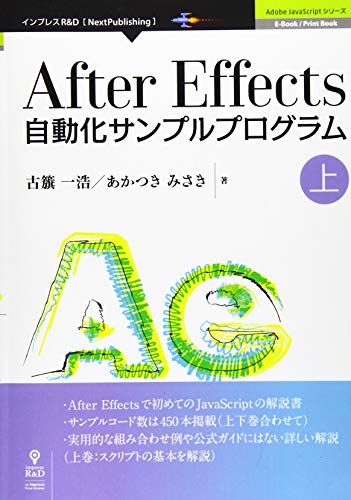3 0 0 0 OA 「正常性の構築」としての排除
- 著者
- 山口 毅
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.19, pp.13-24, 2006-07-31 (Released:2010-04-21)
- 参考文献数
- 23
Previous works concerning the form of exclusive interaction have focused on practices in which the excluded persons are deprived of positions as the “subject”. From this perspective, it is difficult to criticize ambiguous exclusion. Focusing on the fact that the normality of the excluded people is constructed through mutual interaction, I describe the methods of exclusion that are used even when the position as the “subject” is maintained. In order to criticize such ambiguous exclusion, we should be aware that there are alternative methods by which participants can construct mutual normality without exclusion and advocate an interactional culture where ambiguous exclusion is considered to be improper.
3 0 0 0 OA 御船層群から産出した日本で最初の肉食恐竜
- 著者
- 長谷川 善和 村田 正文 早田 幸作 真鍋 真
- 出版者
- 横浜国立大学
- 雑誌
- 横浜国立大学理科紀要. 第二類, 生物学・地学 (ISSN:05135613)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.41-49, 1992-10-30
- 被引用文献数
- 1
A tooth described herein represents the first discovery of an indisputable theropod, in Japan in 1979, which has been followed by late discoveries of dinosaurs in Kyushu and other parts of Japan. The tooth is uniquely characterised by an elongated but very thin crown, which suggests an as yet unrecognized group of theropods.
3 0 0 0 OA ニコチン性アセチルコリン受容体に作用する殺虫剤の無脊椎動物における薬理学
- 著者
- Andrew J. Crossthwaite Aurelien Bigot Philippe Camblin Jim Goodchild Robert J. Lind Russell Slater Peter Maienfisch
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- pp.D17-019, (Released:2017-07-29)
- 参考文献数
- 158
- 被引用文献数
- 53
ニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)は,カチオン選択性細孔の周囲に配置された5つのタンパク質サブユニットからなるリガンド作動性イオンチャネルである.いくつかの天然および合成殺虫剤は,nAChRと相互作用することによってその効果を表す.ここでは,ネオニコチノイドとその関連化合物の標的害虫に対する薬理作用についてまとめた.無脊椎動物に内在するnAChRを構成するサブユニットの量比は不明であるが,昆虫の受容体調製物において,ネオニコチノイド結合部位の存在が明らかにされ,これら殺虫剤は広範囲のnAChRに対して異なる薬理作用を表すことが示された.スピノシンは,主に鱗翅目のような咀嚼害虫を防除するために使用されるに対して,ネライストキシン類縁体は接触および浸透作用を介してイネおよび蔬菜害虫に使用されるが,これら殺虫剤の薬理作用は特有で,ネオニコチノイドの薬理作用とは異なる.
3 0 0 0 IR 『広日本文典』に見られる音声分析
- 著者
- 内田 智子 Tomoko UCHIDA
- 出版者
- 長崎国際大学
- 雑誌
- 長崎国際大学論叢 = Nagasaki International University Review (ISSN:13464094)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.1-11, 2017-03
大槻文彦(1897)『広日本文典』『広日本文典別記』「文字篇」に見られる用語、概念(「母韻」「発声」「単純音」「成熟音」)について考察した。大槻の「母韻」の語は、現在の「母音」に該当し、悉曇学に由来することが明らかとなった。大槻の「発声」は、現代の「子音」に対応する概念である。一方で、幕末の音義派は、「父音」「母音」「子音」の3つの用語を使用し、明治時代には、音義派に由来する「子音」と、洋学に由来する「子音」の2種が使用されていた。大槻の「単純音」の語は、「母韻」と同じ意味で使われており、「ア行音」を意味している。大槻がいわゆる母音に2種の語を当てた理由は、悉曇学にある。「成熟音」の概念は、伝統的音韻学の「仮名反切」に原型があり、音義派の手法を用い、それをオランダ語に適用した「蘭学」の影響の下に生まれた。伝統的音韻学の手法を蘭学に適用した結果が、大槻の記述に流れ込んでいる。This paper examines the features of the terms and the concepts of the "Boin" ,the "Hassei" ,the "Tanjun-on" and the "Seijuku-on" referred to in "Konihonbunten" and the "Konihonbunten Bekki" of OTSUKI Fumihiko published in 1897. It has become obvious that the "Boin" corresponds to today's "vowel" and derived from the "Shittan-gaku", whereas the "Hassei" corresponds to today's "consonant". On the other hand, the Edo period, the "Ongi" school used three words of the "Huon", "Boin" and "Shion". In the next Meiji period, two types of the "Shion(子音)", derived from the "Ongi" school and the Western studies, were used. The "Tanjun-on" is equivalent with the "Boin(母韻)" and both indicate the "Agyo-on". The course for this phenomena is to be able to trace back to the "Shittan-gaku". As for the "Seijuku-on", its original concept is to be found in the "Kanahansetsu" of the traditional phonology. It was created as a result of the application of the "Kanahansetsu" for Dutch under influence of the Western studies with the methods of the "Ongi" school. This application eventually led to OTSUKI's description in "Konihonbunten" and "Konihonbunten Bekki".
3 0 0 0 精神疾患をもつ人におけるベネフィット・ファインディングの特性
- 著者
- 千葉 理恵 宮本 有紀 船越 明子
- 出版者
- Japan Academy of Nursing Science
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.32-40, 2010
- 被引用文献数
- 6
目的:わが国で地域生活または入院している精神疾患をもつ人の,疾患の経験によるベネフィット・ファインディングの特性を,質的に明らかにすること.<br>方法:2008年6~9月に,精神疾患をもつ20歳以上の者を対象として,ベネフィット・ファインディングに関する質的項目を含む,調査票を用いた横断調査を行った.調査の同意を得られた193名のうち,有効回答者107名の回答を,ベレルソンの内容分析の手法により分析した.<br>結果:分析の結果,『人間関係の深まり・人間関係での気づき』『内面の成長・人生の価値観の変化』『健康関連の行動変容・自己管理』『精神の障害に関する関心や理解の深まり』『社会の中で新たな役割を見出すこと』『宗教を信じること』および『その他』の7カテゴリーが抽出された.<br>結論:精神疾患をもつ人のベネフィット・ファインディングには多彩な内容があり,さまざまな慢性身体疾患をもつ人のベネフィット・ファインディングと共通点をもつことが明らかになった.
3 0 0 0 OA 表情が印象判断に及ぼす影響における性差
- 著者
- 上田 彩子 廼島 和彦 村門 千恵
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.103-112, 2010-02-28 (Released:2010-11-25)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 3
主に顔の形態特徴の情報処理を基に行われる顔認知過程において,表情情報が影響を及ぼすことは,多くの研究で示されている.また,表情認知に性差があることも示唆されている.表情認知における性差が,顔認知過程で表情が及ぼす影響に関与する可能性がある.そこで,本研究では,顔の印象決定において表情が及ぼす影響に性差が認められるかどうか実験的に検討した.刺激の顔の形態変化にはメイク手法を用いた.被験者は,刺激の相貌印象と表情表出強度について評価を行った.その結果,表情認知能力に性差は認められなかったが,相貌印象判断に表情が与える影響は女性のほうが大きいことが示された.
3 0 0 0 OA 脅威アピールでの被害の記述と受け手の脆弱性が犯罪予防行動に与える影響
- 著者
- 島田 貴仁 荒井 崇史
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.88.16032, (Released:2017-07-10)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 7
A field experiment was conducted to examine the factors in threat appeal responsible for maintenance of crime-prevention behavior. At four public bicycle parking lots, 256 riders with variable receiver vulnerability characteristics were encouraged to use an extra bicycle lock. They were randomly presented with one of three threat messages featuring victims of bicycle theft (identifiable victim, statistical victim, or control), followed by either high- or low-efficacy preventative-messages. After extra locks were installed on their bicycles, participants’ use of the lock was observed five times within 28 days after the intervention. A mixed-effect generalized linear model revealed that vulnerability of the participants increased the use of the lock immediately after the intervention. Meanwhile, highly vulnerable participants who were presented with an identifiable victim and high-efficacy messages decreased their use of the lock significantly compared to low-vulnerability participants and those who were presented with the low-efficacy message. The result implies that threat appeal strategies differ depending on receiver vulnerability and the type of preventative behavior.
3 0 0 0 OA 災害救援者支援のための会話集等作成について
- 著者
- 山根 聡 Yamane So
- 出版者
- 大阪大学世界言語研究センター
- 雑誌
- 大阪大学世界言語研究センター論集 (ISSN:18835139)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.217-225, 2009-03-11
- 著者
- 悪原 至
- 出版者
- 国立音楽大学大学院
- 雑誌
- 音楽研究 : 大学院研究年報 (ISSN:02894807)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.51-64, 2017-03
3 0 0 0 OA 2014年の国家公務員制度改革関連法について(上)
- 著者
- 稲葉 馨
- 出版者
- 地方自治総合研究所
- 雑誌
- 自治総研 (ISSN:09102744)
- 巻号頁・発行日
- no.439, pp.14-29, 2015-05
3 0 0 0 OA 災害救援者の二次受傷とメンタルヘルス対策に関する検討
- 著者
- 大塚 映美 松本 じゅん子
- 出版者
- 長野県看護大学紀要
- 雑誌
- 長野県看護大学紀要 (ISSN:13451782)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.19-27, 2007-03-31
3 0 0 0 打ち上げ花火のシミュレーション
日本の伝統であり、世界的にも評価の高い芸術である打ち上げ花火は、そのデザインの創作が容易でない。この原因として、試作・試し打ちに時間と費用がかかることと、その完成イメージが花火師の頭の中にしかないことがあげられる。これまで花火のコンピュータ処理としては、点火の制御とアミューズメント用途がほとんどで、花火のデザイン支援のためのシステムはなかった。試作・試し打ちがCADで行なえれば、時間と費用が大幅に節約できると考えられる。また、完成イメージがCRT上で動画として見られれば熟練していない人でも容易に花火のデザインが可能になる。本稿では打ち上げ花火を計算機の画面上に表現することのできるシステムについて報告する。
3 0 0 0 After Effects自動化サンプルプログラム
- 著者
- 古籏一浩 あかつきみさき著
- 出版者
- インプレスコミュニケーションズ (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2017
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1104, pp.28-31, 2001-08-20
日本の読者はあなたがどんなに重要な人物か、ほとんどだれも知りません。だからお願いです。オフレコにはせず「正体」を明かさせてくれませんか。 ——ペンタゴン(米国防総省)のとある一室で、取材の最後そう必死に頼み込んでみた。しかしこの9月で80歳を迎える老人は、好々爺然とした笑みを浮かべたままこちらの言い分を一通り聞いたうえ、それでもゆっくりかぶりを振った。
3 0 0 0 アイヌ語の衰退と復興に関する一考察
- 著者
- 上野 昌之
- 出版者
- 埼玉学園大学
- 雑誌
- 埼玉学園大学紀要. 人間学部篇 (ISSN:13470515)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.211-224, 2011-12
アイヌ語は、アイヌ民族の独自言語である。かつて樺太、千島、北海道の三方言があったと言われるが、現在母語話者が残っているのは北海道方言のみとなっており、その母語話者も人数としては極めて少ない。こうした状況は言語学的には危機言語、つまり消滅の危機に瀕した言語として考えられている。アイヌ語の母語話者が減少した背景には、歴史的な要因が大きく関わっている。幕末から明治期の対アイヌ政策がもとらした帰結といえる。アイヌ語の衰退は、アイヌ民族の日本語への転換、日本化が進行してたことを意味する。言語を媒体とした相互の意志・思想・感情の世代間の継承行動の喪失が生じ、民族共同体に統一性が失われ、これまでの日常性が崩壊し、伝統的共同体の解体へと至ることになる。民族的アイデンティティが揺らぎ民族の存在が危ぶまれる状況になっていった。しかし、今日アイヌ民族は民族の権利回復をめざす活動を行っている。その中でアイヌ語の復興活動の持つ意味は大きいものになっている。本稿では、アイヌ語の衰退を歴史的な事実からたどり、アイヌ民族への教化により彼らの習慣、生活様式が変質を強いられていく過程を概観し、その際学校教育がアイヌ語の衰退に大きく関与していたことを明らかにする。次にアイヌ語のように危機言語と位置づけられる言語が衰退に導かれるプロセスを追い、その意味を考察する。そして、民族集団の持つ言語の権利を踏まえ、言語保護のための国際的潮流を参照する。そして最後に、アイヌ語の復興活動の一つとして地域的に繰り広げられているアイヌ語教室について、平取二風谷アイヌ語を例にその活動を概観し、行われている活動の中からアイヌ語復興にとって必要な事柄、復興の意義を考えることにする。