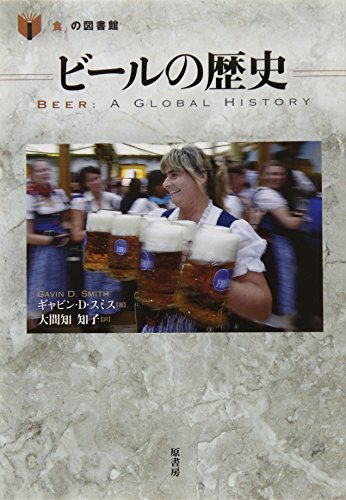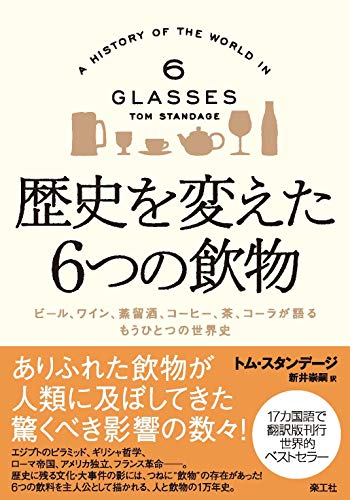3 0 0 0 OA 加齢によりなぜ味覚は変化してしまうのか?
3 0 0 0 ビールの歴史
- 著者
- ギャビン・D・スミス著 大間知知子訳
- 出版者
- 原書房
- 巻号頁・発行日
- 2014
- 著者
- トム・スタンデージ著 新井崇嗣訳
- 出版者
- 楽工社
- 巻号頁・発行日
- 2017
3 0 0 0 OA 心因性視力障害の視野
- 著者
- 須田 和代 森 由美子 調 広子 大池 正勝 山本 節
- 出版者
- 公益社団法人 日本視能訓練士協会
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.151-158, 1992-11-20 (Released:2009-10-29)
- 参考文献数
- 24
従来,心因性視力障害患者の視野には管状視野・螺旋状視野・求心性狭窄等の特有なものが検出されることがあるとの報告がされているが,視野とは視覚感度の分布であるという定義に基づくと,その視野には矛盾する点がみられる。我々は心因性視力障害疑いの患者に対しても,本来の概念に基づいて視野検査を行ってきた。その結果,他院から異常視野として紹介された症例も含め,全例正常視野を得,他の器質的疾患を否定する一助に充分なり得た。特有な視野が心因性に限るものではないことから,心因性視力障害疑いの患者に対しては,その心因的要素を取り除くよう配慮し,可能な限り正確に診断できる検査結果を得るべく努力すべきであると考える。
3 0 0 0 OA 日本基督教の精神的伝統
- 著者
- 魚木忠一 著
- 出版者
- 基督教思想叢書刊行会
- 巻号頁・発行日
- 1941
3 0 0 0 OA 愛媛県会社並ニ工場通覧
- 著者
- 愛媛県総務部統計課 編
- 出版者
- 愛媛県総務部統計課
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和10年12月末日現在, 1936
3 0 0 0 OA 沖縄の砂浜に生息する食用二枚貝資源量の変遷 -貝塚出土貝類と現生貝類の比較-
- 著者
- 矢敷 彩子 山口 正士
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会大会講演要旨集 第52回日本生態学会大会 大阪大会
- 巻号頁・発行日
- pp.122, 2005 (Released:2005-03-17)
沖縄本島沿岸の砂浜には潮干狩りの対象となる主な二枚貝として、イソハマグリ(Atactodea striata)、リュウキュウナミノコ(Donax faba)、ナミノコガイ(D. cuneatus) の3種が分布している。1980年代までは、貝を掘る潮干狩りの人々で砂浜にぎわっていたが、それ以降その姿をほとんどみかけなくなった。本研究では砂浜に生息する食用二枚貝について、全島的に貝塚から出土した貝類のデータを基本情報とし、それを現生貝類の分布量と比較して資源量の変遷を考察した。貝塚データと比較するために貝塚に近い砂浜を40箇所選出し、1998年から1999年に現生貝類調査を行った。現生貝類の砂浜における「単位掘り出し時間当たりの個体数」を種類ごとに求め、「多」、「普通」、「少」、「無」にランクわけした。貝塚出土の貝類データについても現生貝類と同様、相対的にランクわけした。その結果、沖縄本島では貝塚の出土状況から資源量が大きかったとみなされた砂浜の多くで、現生の貝類分布では潮干狩り可能な状態の生息密度に及ばず、明らかに資源量は減少したと考えられた。また金武湾沿岸部などの貝塚から出土し、沖縄において食用資源として過去に生息が推測されたハマグリ類 (Meretrix spp.) は、今回の調査では確認されなかった。砂浜貝類集団の生息分布には時空間的な変動が激しく、自然変動で増減することがよく知られており、貝塚時代に比べ現在の資源量が少ないことを単に環境変化の影響と言い切ることはできない。しかし埋立や護岸整備などによる砂浜の消失が各地に見られ、ハマグリ類 (Meretrix spp.) の地域絶滅の可能性もあることから、砂浜における食用貝類資源が乏しくなっている現状が推察された。
- 著者
- Koji Sugie Akira Taniguchi
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉄鋼協会
- 雑誌
- ISIJ International (ISSN:09151559)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.513-520, 2011-03-15 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 56
- 被引用文献数
- 4 11
The bioavailability and durability of Fe released from decarburization steelmaking slag was examined for two marine diatom species. The bioavailability of Fe released from the slag was compared with that from the reagent FeCl3·6H2O in the presence or absence of the synthetic chelator ethylenediaminetetraacetic acid, which affects Fe speciation in seawater. The duration of bioavailability was determined by the recovery of the growth rate on intermittent additions of macro-nutrients other than Fe. Abiotic reduction of bioavailable Fe from the slag in seawater was also investigated for 5 or 15 d. Thus, the bioavailability of Fe released from the slag was observed to be sufficiently high to promote the maximum growth rate; this was similar to that observed with the reagent inorganic Fe. This implies that the iron released from the slag is a dissolved ferric and/or ferrous ion/hydroxide species. In the culture media, to which the slag was added at the concentration of 20 mg L−1, the slag supplied bioavailable Fe to two diatoms for 50 d. The probable duration for which the slag was available as an Fe source was approximately 10 times longer than the reported duration in in situ iron fertilization experiments. These results indicate that continuous Fe fertilization can be achieved by a single addition of the slag, and hence, we can reduce the energy and cost of ocean fertilization and also create a resource of microalgae biofuels.
3 0 0 0 IR 江戸時代の日独交渉に関する一考察
- 著者
- 黄 逸
- 出版者
- 関西大学大学院東アジア文化研究科
- 雑誌
- 文化交渉 東アジア文化研究科院生論集 (ISSN:21874395)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.85-98, 2016-11-30
東アジアの思想と構造It is generally considered that the eastward expansion of German influence in Japan began in the Edo period. The Japanese first became aware of Germany through the introduction of Rangaku studies ("Dutch Learning"). At that time, German doctors, through their exchange with their Japanese counterparts,popularized the accomplishments of western medicine that had been developing since the European Renaissance. The Japanese who studied Dutch learning in order to learn western medicine, may have also been exposed to the German language through Dutch language texts. Dutch Learning in the Edo Period notonly promoted the development of modern western medicine in Japan at the time, but also laid the foundations for the introduction of German science during the Bakumatsu and early Meiji periods. This paper discusses the early process of cultural interaction between Japan and Germany in the Edo Period based on Dutch Learning, in order to demonstrate the influence of German scholarship on the modernization of Japan.
3 0 0 0 IR 旅の痕跡 和田忠彦著『タブッキをめぐる九つの断章』
- 著者
- 前田 和泉 マエダ イズミ MAEDA Izumi
- 出版者
- 東京外国語大学総合文化研究所
- 雑誌
- 総合文化研究 (Trans-Cultural Studies) (ISSN:18831109)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.149-151, 2017-03-22
3 0 0 0 OA オリンピックのための情報処理:9.オリンピック招致のためのVR/AR・MR
本章では,東京オリンピック招致の際に利用されたVR/AR・MR技術について概説する.前回,2016年招致の際には,晴海ふ頭に建設予定のスタジアムをVR/MR技術によって再現し,未来の競技を体験できるシステムによって国際オリンピック 委員会(IOC)委員へのプレゼンテーションが行われた.また今回2020年の招致 活動においてもAR技術によって競技をより魅力的に観戦できるアイディアが紹介映像の中で用いられ,日本の技術力をアピールするとともに招致に大きく貢献した.本章ではこれらの技術について紹介し,さらに2020年東京オリンピックにおける映像処理技術への期待について述べる.
- 著者
- 小川 真生 道渕 路子 我妻 孝則 西川 美香子 川﨑 康弘 土田 英昭 寺口 奏子
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.501-505, 2017 (Released:2017-03-24)
- 参考文献数
- 18
【緒言】終末期の難治性せん妄が数日間の持続的な深い鎮静後に改善した事例を経験した.【症例】脳実質浸潤を伴った57歳女性の頭頸部がん患者の異常行動を伴ったせん妄が,急激に悪化した.オピオイドスイッチや薬物治療などを行ったが,異常行動は改善しなかった.難治性の終末期せん妄と診断され,家族は鎮静を希望した.ミダゾラムによる間欠的鎮静を開始し,さらに持続的鎮静へと移行した.その数日後,家族の鎮静継続への葛藤を認め,10日後に鎮静を中止した.覚醒後,患者の異常行動は消失し,軽度の意識障害はあったが,家族とのコミュニケーションを保ちながら2カ月後に死亡した.【考察】鎮静に伴う多種類の薬剤の中止はせん妄改善の原因の一つと考えられる.緩和医療学会のガイドラインにおいて家族の気持ちの確認以外の持続鎮静中止の基準は明確ではなく,よりエビデンスレベルの高い鎮静中止の基準が必要であると考えられる.
3 0 0 0 OA 鹿児島県の離島,徳之島における,悪性貧血14例の臨床的および疫学的検討
- 著者
- 小林 晃 畑 泰司 山本 浩文 鈴木 真紀 竹元 慎吾 宮上 寛之 太良 光利
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.86-90, 2017-06-20 (Released:2017-06-21)
- 参考文献数
- 10
目的:徳之島の医療施設で経験した14例の悪性貧血について臨床的および疫学的検討を行った.方法:平成21年3月より平成26年5月までに当院で悪性貧血と診断した14例を対象として,後方視的に検討した.結果:全例50歳以上で,高齢女性に多かった.14例のうち6例は特に症状はなかったが,定期検査で大球性貧血を認めたことが契機で,悪性貧血の診断に至った.この期間における当院の年間発症数は中央値3(95%confidence interval[CI]:1.25-3.42)であった.結論:徳之島での今回の我々の成績では,悪性貧血の10万人当たりの年間発症率が,本邦の従来の報告例に比し,大幅に高い可能性があることが判明した.その理由として,高い高齢化率,看過されやすい疾患であること,民族的ないし地域的特異性が関与している可能性を指摘した.悪性貧血の罹患率は従来の報告より高い可能性があり,貧血の鑑別診断として,悪性貧血を念頭に入れて診療を行う必要がある.
- 著者
- 小谷 博泰 安井 寿枝
- 出版者
- 甲南大学
- 雑誌
- 甲南大学紀要. 文学編 (ISSN:04542878)
- 巻号頁・発行日
- vol.160, pp.3-14, 2010-03
3 0 0 0 OA 21世紀の「軍事革命」と社会について
- 著者
- 岡本智博
- 出版者
- 国際交通安全学会
- 雑誌
- IATSS review
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, 2007-07
3 0 0 0 OA ため池決壊に伴う洪水流出過程に関する研究
- 著者
- 原田 紹臣 赤澤 史顕 速見 智 里深 好文
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B1(水工学) (ISSN:2185467X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.I_1213-I_1218, 2013 (Released:2014-03-31)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
Recently, many hazardous flooding cases caused by an irrigation tank overflow under concentrated downpour have been reported. Using a hydrograph to predict the overflow is an important countermeasure against hazardous flooding in the downstream area. Many preceding studies have considered only peak flow discharge without timescale for the hydrograph in the prediction of runoff characteristics due to irrigation tank flow. The present paper deals with the importance of the runoff characteristics and proposes a new index for the hydrograph to evaluate flooding risks in the downstream area, using numerical simulation. The proposed index includes both peak flow discharge and timescale for the hydrograph. Next, the applicability of the two-dimensional numerical simulation model is examined comparing the examples of damage with the in situ experimental results, which were carried out in a narrow channel located in a mountainous site.
3 0 0 0 OA EBウイルスの感染様式とがん
- 著者
- 村田 貴之
- 出版者
- 日本ウイルス学会
- 雑誌
- ウイルス (ISSN:00426857)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.95-104, 2014-06-25 (Released:2015-03-10)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 1 2
Epstein-Barr (EB)ウイルスはガンマヘルペスウイルスに分類されるヒト腫瘍ウイルスである.進化学的観点からみても長期にわたって宿主と共存してきた,高度な生存戦略を備えたウイルスであり,複雑,巧妙な感染様式をとることで自身の維持,拡大を図っている.その感染様式は,潜伏感染と溶解感染のふたつに分けられ,潜伏感染から溶解感染への移行を再活性化と呼ぶ.さらに潜伏感染は主に0-IIIの4つに分類される.このような感染様式の相違や変遷は,ウイルスの維持拡大のみならずがん化のプロセスや臨床病態とも深く関わっており,その理解は重要である.本稿では,EBウイルスによる増殖性疾患の発生,維持,進展の機序について,我々の感染様式に関する研究成果を交えながら紹介したい.
3 0 0 0 OA 学会の抄録を見て思うこと
- 著者
- 西山 友貴
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.4, pp.229a-229a, 1995-10-01 (Released:2009-03-27)
3 0 0 0 近世前期の島津氏系譜と武家相続・女子名跡
- 著者
- 林 匡
- 出版者
- 九州史学研究会
- 雑誌
- 九州史学 (ISSN:04511638)
- 巻号頁・発行日
- no.152, pp.1-26, 2009-01