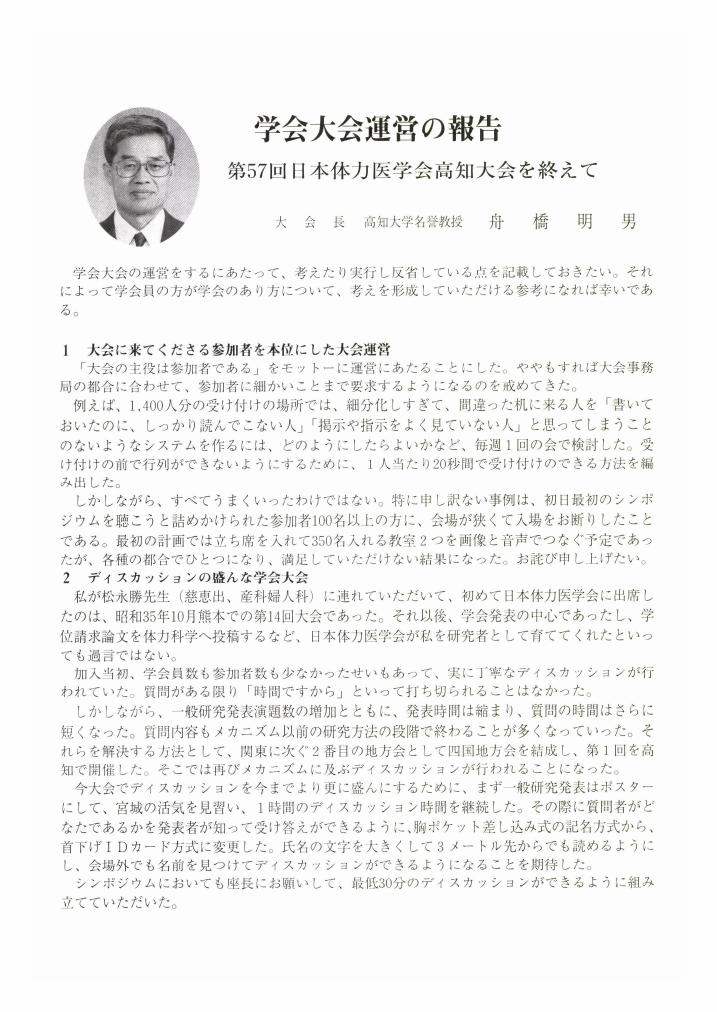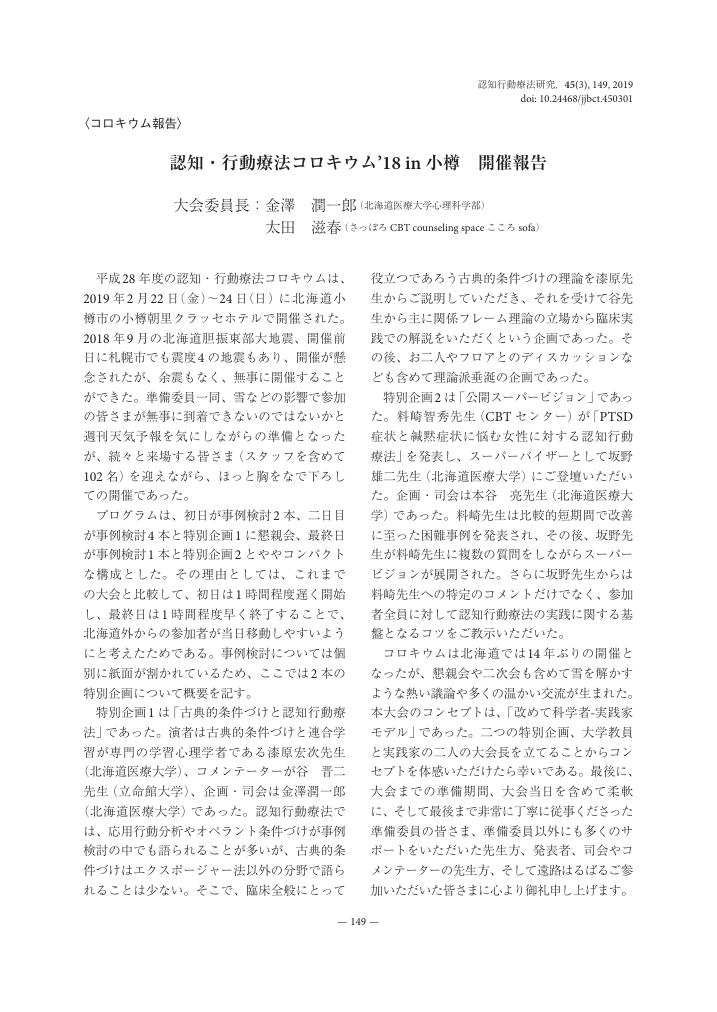2 0 0 0 OA MAISアプローチによる東海村JCO臨界事故の分析 : 臨界に至るまで
- 著者
- 原 拓志
- 出版者
- 關西大學商學會
- 雑誌
- 關西大學商學論集 (ISSN:04513401)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.59-80, 2023-03-10
本研究はJSPS科研費助成金(基盤研究(C))20K01880の助成を受けている。
2 0 0 0 OA ソクラテス教説「徳は知である」考 プラトン初期対話篇を手がかりとして
- 著者
- 岩間 秀幸
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1990, no.62, pp.1-15, 1990-11-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 24
Socrates' theory of the 'Unity of Virtue and Knowledge' implies that in order to lead a virtuous (good) life, all that is needed is to know what a virtuous (good) life means. But Socrates was firmly convinced that the knowledge of living virtuously (hereafter called 'kowledge') can never be fully attained by man. Hence, the 'knowledge' in the context of 'Unity of Virtue and Knowledge' is a human knowledge (anthropinê sophia) which possesses the following double meaning : One is the realization of the fact that man cannot attain the 'knowledge' concerning virtue (the Good); the other meaning implies that nevertheless and keeping in mind the above-mentioned realization, one should continue to strive after that 'knowledge'.By the question, 'what is virtue' Socrates makes his partner in the dialogue stand in a non-daily, contemplative, critical-existential, spiritual situation quite different from the daily routine situation governed by opinion (doxa) and there makes him discover the 'human knowledge' (anthropinê sophia).Because how to live the good life (virtue) cannot be known by man, the answer remains forever a question. In other words, the 'knowledge' how to live the good life (virtue) remains always connected with a question. In that sense, searching for the good life (virtue) and the intellectual inquiry into its content remains always one and the same thing. That, in my opinion, is what is meant by Socrates' 'Unity of Virtue and Knowledge'.
2 0 0 0 OA 第57回日本体力医学会大会
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.489-810, 2002-12-01 (Released:2010-09-30)
- 著者
- 山口 祥義
- 出版者
- 日経産業消費研究所
- 雑誌
- 日経グローカル (ISSN:13494880)
- 巻号頁・発行日
- no.276, pp.32-34, 2015-09-21
2 0 0 0 IR 中国語音声の記述と音韻論的分析
2 0 0 0 OA 7.人工知能(AI)の臨床医学・ゲノム医学への応用
- 著者
- 井元 清哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.3, pp.492-498, 2021-03-10 (Released:2022-03-10)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 IR ナチス権力と中央党員の行動
- 著者
- 中井 晶夫
- 出版者
- 上智大学史学会
- 雑誌
- 上智史学 (ISSN:03869075)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.p11-39, 1984-11
2 0 0 0 OA アニミズム発生論理再考 ―「霊魂」の人類学的思想史(1)タイラー ―
- 著者
- 久保田 力
- 巻号頁・発行日
- 2008-03
2 0 0 0 OA アメリカ建国200年の意義
- 著者
- 鵜飼 信成
- 出版者
- アメリカ学会
- 雑誌
- アメリカ研究 (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- vol.1976, no.10, pp.1-8, 1976-03-25 (Released:2010-06-11)
- 参考文献数
- 18
- 著者
- 大滝 一登
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 国語科教育 (ISSN:02870479)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, pp.17-25, 2021-09-30 (Released:2021-10-20)
- 参考文献数
- 36
本稿は、高等学校「現代国語」新設において「作文の能力」が重視された高等学校独自の背景や改革の経緯を考察し、その到達点を明らかにするものである。特に、当時国が有していた情報と問題意識、改訂に関わった研究者の見解に着目し検討を行った。そこで明らかとなったのは、科学技術立国を目指す社会情勢の中、高等学校の作文教育の低調さを示す調査資料の存在、作文を重視しアメリカで注目されていた「コナント・レポート」への傾倒、コンポジション理論の導入を積極的に進めた森岡健二の作文教育観と、言語過程説に基づき独自の作文教育理論を構築しようとした時枝誠記のそれとが混在した形で指導事項として示されたと考えられる我が国独自の「作文の能力」観であった。
2 0 0 0 OA ワッ,静か!快適な流線形 ~電気自動車に試乗して~
- 著者
- 阿部 賢二
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.4, pp.255, 1994-04-20 (Released:2008-04-17)
2 0 0 0 著作権台帳 : 文化人名録
- 著者
- 日本著作権協議会編集・監修
- 出版者
- 著作権協議会編集局
- 巻号頁・発行日
- 1999
2 0 0 0 OA 認知・行動療法コロキウム’18 in小樽 開催報告
- 著者
- 金澤 潤一郎 太田 滋春
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.149, 2019-09-30 (Released:2020-06-25)
2 0 0 0 OA 超伝導加速空洞の物理と課題、そして性能向上への理論的示唆 ―新規参入の誘い―
- 著者
- 久保 毅幸
- 出版者
- 公益社団法人 低温工学・超電導学会 (旧 社団法人 低温工学協会)
- 雑誌
- 低温工学 (ISSN:03892441)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.275-282, 2019-07-20 (Released:2019-08-01)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 3 2
We discuss the physics of superconducting resonant cavities for particle accelerators, including the basics of a superconducting cavity, Meissner state stability, and surface resistance together with related scientific and technological challenges. Ongoing research and some proposals for solving the challenges are also discussed.
2 0 0 0 OA 超伝導空洞の物理と窒素インフュージョン:国際リニアコライダー計画の実現に向けて
- 著者
- 久保 毅幸
- 出版者
- 日本加速器学会
- 雑誌
- 加速器 (ISSN:13493833)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.40-51, 2018-07-31 (Released:2021-10-05)
- 参考文献数
- 36
The nitrogen infusion, the recently discovered surface processing method for high-gradient and high-quality factor superconducting cavities, attracts much attention in the particle accelerator community in particular in the context of the International Linear Collider project. In this paper, we briefly review the basics of superconducting cavity, the causes of performance limitation, and the three modern surface processing methods including the nitrogen infusion and resultant cavity performances. The present understanding on physics behind these surface treatments are also discussed.
2 0 0 0 OA マイクロ波帯・ミリ波帯の電波伝搬
- 著者
- 福地 一
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.9, pp.770-775, 2016 (Released:2018-09-01)
- 参考文献数
- 23
2 0 0 0 OA はじめに ―政治理論と実証研究の対話―
- 著者
- 小川 有美
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.1_3-1_8, 2015 (Released:2018-06-10)
- 参考文献数
- 14
2 0 0 0 OA 異性装をとおして見る近世ヨーロッパの社会史
- 著者
- 大木 昌 OKI Akira
- 出版者
- 明治学院大学国際学研究
- 雑誌
- 明治学院大学国際学研究 = Meiji Gakuin review International & regional studies (ISSN:0918984X)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.55-68, 2007-12
2 0 0 0 OA 東北の河原町の特色
- 著者
- 森栗 茂一
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.245-265, 1996-03-29
東北の河原町の特色一般に、日本のマチ場は河原や坂に位置するという。ここでは、東北のさまざまな城下町の河原に位置する町について検討した。日本の川は、勾配が急なため、また局地的な降水のため、広い河原が存在する。近世の都市においては、これを河川改修することで、城下町を建設してきた歴史がある。そうした河原町には、次の三つの歴史展開のケースがある。 ① 下級武士の住宅地としての歴史をたどったもの。現在も住宅地。 ② 城下町の武士の町と町人の町の境界の川にそった所にあり、現在も盛り場になっている。 ③ 城下町から出た街道が、城下町の端の川を渡頭のターミナルとして展開したもの。現在でも、職人町・在郷商人町となっている。弘前、盛岡、会津若松、仙台など、ある程度以上の規模の城下町では、こうした、町外れの河原の町が存在していた。なかでも、仙台の河原町周辺は、飢饉のときの餓死者を処理し、供養する場であった。また、被差別の人々、流浪芸人・障害者が集まっていた。河原である限り、差別された「河原者」と関わる歴史がある。仙台では、その差別をストレートに記述している資料があることに問題を感じる。一方で、仙台ではそうした差別の歴史を隠したり排除するのではなく、彼らの存在も、地域の特色の一つとして肯定的に受け止める姿勢がある。これは、差別の現実が眼前にあり、かつそうした差別記述を隠そうとする西日本の伝承の状況と異なっている。