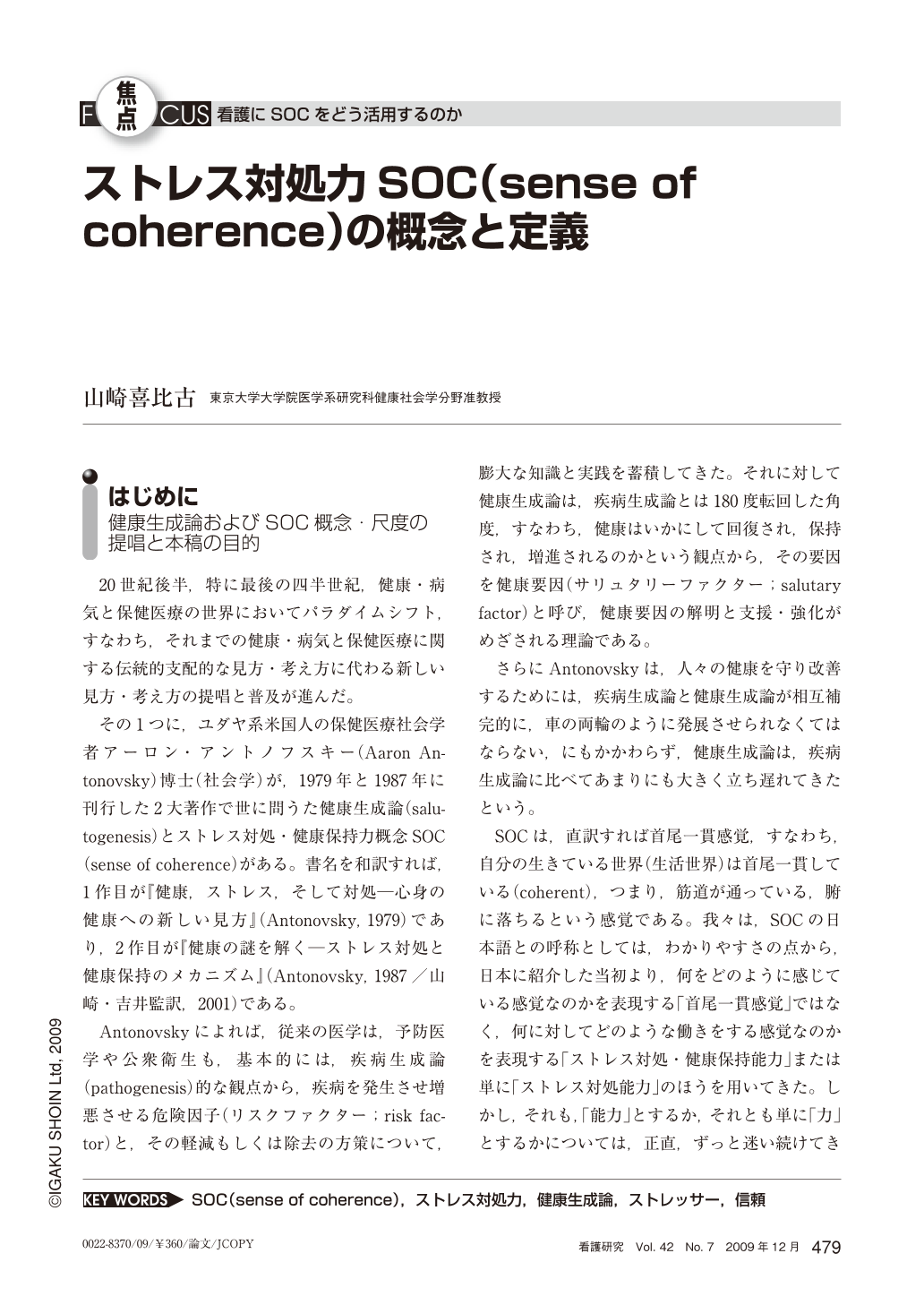2 0 0 0 OA 腸管バリア機能における亜鉛の重要性
- 著者
- 東村 泰希 内藤 裕二
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.7, pp.437-440, 2017 (Released:2018-07-31)
- 著者
- Wonsuk Lee
- 出版者
- Japan Society of Mixed Methods Research
- 雑誌
- 混合研究法 (ISSN:24368407)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.53-58, 2022 (Released:2022-04-20)
- 参考文献数
- 5
This paper is about my story of learning and exploring mixed methods in abroad. So, the purpose of this paper is to provide readers with a catalyst and a guide necessary to participate in the journey of mixed methods. My story is mainly composed of two parts, that is, one is my doctoral program period at University of Illinois at Urbana-Champaign and the other is my senior visiting scholar program period at University of Michigan. Finally, this paper emphasizes that we should endeavor to find out diverse paths how we can reach to the potential of mixed methods in practice.
- 著者
- Ken PARSONS
- 出版者
- National Institute of Occupational Safety and Health
- 雑誌
- Industrial Health (ISSN:00198366)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.368-379, 2006 (Released:2006-08-28)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 152 211
This paper presents heat stress Standard ISO 7243, which is based upon the wet bulb globe temperature index (WBGT), and considers its suitability for use worldwide. The origins of the WBGT index are considered and how it is used in ISO 7243 and across the world as a simple index for monitoring and assessing hot environments. The standard (and index) has validity, reliability and usability. It is limited in application by consideration of estimating metabolic heat and the effects of clothing. Use of the standard also requires interpretation in terms of how it is used. Management systems, involving risk assessments, that take account of context and culture, are required to ensure successful use of the standard and global applicability. For use outdoors, a WBGT equation that includes solar absorptivity is recommended. A `clothed WBGT' is proposed to account for the effects of clothing. It is concluded that as a simple assessment method, ISO 7243 has face validity and within limits is applicable worldwide.
2 0 0 0 OA 渡辺雅子著「納得の構造-日米初等教育に見る思考表現のスタイル-」
- 著者
- 恒吉 僚子
- 出版者
- 日本比較教育学会
- 雑誌
- 比較教育学研究 (ISSN:09166785)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.31, pp.281-283, 2005-06-25 (Released:2011-01-27)
2 0 0 0 OA 集団間状況における複数リーダー存在の効果に関する検討
- 著者
- 高口 央 坂田 桐子 黒川 正流
- 出版者
- The Japanese Group Dynamics Association
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.40-54, 2002-09-30 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2 1
本研究では, 集団間葛藤・協力の文脈からなる仮想世界ゲームを用いて, 複数のリーダーによるリーダーシップが, 集団にどのような影響を及ぼすのかを検討した。各集団における公的役割を持ったリーダーを公式リーダーとし, 集団内の1/3以上の成員から影響力があると評価された人物を非公式リーダーとした。両リーダーのリーダーシップ発揮形態に基づき, 全集団を次に挙げる2つの基準で5つに分類した。分類の基準は, a非公式リーダーの有無, bリーダーシップ行動 (P機能と集団内M機能, 及び集団間M機能が統合された形 (PMM) で発揮されているか) であった。この分担形態を用いて, 集団へのアイデンティティ, 個人資産について検討を行った。さらに, 本研究では, 集団間文脈において検討を行ったため, 特にリーダーシップの効果性指標として, 他集団からの評価, 集団間関係の認知を採用し, それらについても検討を行った。その結果, 複数のリーダーによってリーダーシップが完全な形で発揮された分担統合型の集団が, もっとも望ましい状態にあることが示された。よって, 集団間状況においては, 複数リーダーによるリーダーシップの発揮がより効果的であることが示唆された。
2 0 0 0 OA 読みやすさを決める文字の空間配置
文字を読みやすくする空間配置を調べるために2つの問題を設定した。一番目は、文字認知に縦と横の配置はどのように影響するかであった。日本語は縦書きも横書きもでき、多くの印刷物にもそのどちらかが使われている。実験により、文字を読む視野の大きさを推定したところ、縦書きより横書きのほうが視野は大きかった。この傾向は、米国人でも日本人でも同様であった。二番目に、縦書きと横書きの読みやすさを、読みの速さを指標として調べた。縦書きと横書きに、読みの速さに違いはなかった。さらに「書の文字の美しさ」を研究課題に加えた。書の点画構成による美的効果を測定する尺度を開発し、実際の書の評価を実施した。
2 0 0 0 IR イタリア理想主義の葛藤
- 著者
- 中川 政樹
- 出版者
- 島根大学
- 雑誌
- 島根大学社会福祉論集 (ISSN:18819419)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.57-69, 2008-03
イタリア理想主義の代表的思想家として広くその名を知られているベネデット・クローチェ(Benedetto Croce, 1866-1952)とジョヴァンニ・ジェンティーレ(Giovanni Gentile, 1975-1943)は、相互協力によって新しい観念論哲学の体系を構築して当時の思想的諸潮流に論戦を挑み、イタリア思想史上他に例をみない影響力を獲得したのであった。しかし、両者がそれぞれの思想体系を確立していく過程で、さまざまな理論的相違が顕現することになった。そして、相対立する二つの理想主義理論が展開されることになったのである。しかし、両者の友愛と知的協力関係は、理論的対立の深化にもかかわらず、ファシズム台頭期まで続いた。そこには何があったのか。本稿は両者の連帯が辿った1910 年代の複雑な過程の詳細を明らかにし、その理論的意味を考察する。
- 著者
- 山崎 喜比古
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護研究 (ISSN:00228370)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.7, pp.479-490, 2009-12-15
はじめに 健康生成論およびSOC概念・尺度の提唱と本稿の目的 20世紀後半,特に最後の四半世紀,健康・病気と保健医療の世界においてパラダイムシフト,すなわち,それまでの健康・病気と保健医療に関する伝統的支配的な見方・考え方に代わる新しい見方・考え方の提唱と普及が進んだ。 その1つに,ユダヤ系米国人の保健医療社会学者アーロン・アントノフスキー(Aaron Antonovsky)博士(社会学)が,1979年と1987年に刊行した2大著作で世に問うた健康生成論(salutogenesis)とストレス対処・健康保持力概念SOC(sense of coherence)がある。書名を和訳すれば,1作目が『健康,ストレス,そして対処─心身の健康への新しい見方』(Antonovsky, 1979)であり,2作目が『健康の謎を解く─ストレス対処と健康保持のメカニズム』(Antonovsky, 1987/山崎・吉井監訳,2001)である。 Antonovskyによれば,従来の医学は,予防医学や公衆衛生も,基本的には,疾病生成論(pathogenesis)的な観点から,疾病を発生させ増悪させる危険因子(リスクファクター;risk factor)と,その軽減もしくは除去の方策について,膨大な知識と実践を蓄積してきた。それに対して健康生成論は,疾病生成論とは180度転回した角度,すなわち,健康はいかにして回復され,保持され,増進されるのかという観点から,その要因を健康要因(サリュタリーファクター;salutary factor)と呼び,健康要因の解明と支援・強化がめざされる理論である。 さらにAntonovskyは,人々の健康を守り改善するためには,疾病生成論と健康生成論が相互補完的に,車の両輪のように発展させられなくてはならない,にもかかわらず,健康生成論は,疾病生成論に比べてあまりにも大きく立ち遅れてきたという。 SOCは,直訳すれば首尾一貫感覚,すなわち,自分の生きている世界(生活世界)は首尾一貫している(coherent),つまり,筋道が通っている,腑に落ちるという感覚である。我々は,SOCの日本語との呼称としては,わかりやすさの点から,日本に紹介した当初より,何をどのように感じている感覚なのかを表現する「首尾一貫感覚」ではなく,何に対してどのような働きをする感覚なのかを表現する「ストレス対処・健康保持能力」または単に「ストレス対処能力」のほうを用いてきた。しかし,それも,「能力」とするか,それとも単に「力」とするかについては,正直,ずっと迷い続けてきた。本号焦点でも,基本的には従来通り,「能力」を用いているが,本稿では,あえて「能力」の代わりに,包括性のより高い「力」のほうを使わせていただくこととした。両者のニュアンスの違いについては,簡単にではあるが後述する。 SOCは,Antonovskyが,上述した健康生成論的な観点から,極めてストレスフルな出来事や状況に直面させられながらも,それらに成功裏に対処し,心身の健康を害さず守れているばかりか,それらを成長や発達の糧にさえ変えて,明るく元気に生きている人々のなかに見いだした,人生における究極の健康要因であり,健康生成論の要の概念である。 Antonovskyの健康生成論的な発想と見方・考え方は,その後,世界の保健,医療,看護や心理などヒューマンサービスに関わる広範な分野の学問と実践にパラダイムシフト的なインパクトをもたらした。また,SOC概念がAntonovskyの2作目の著作(Antonovsky, 1987/山崎・吉井監訳,2001)において尺度化され,SOC尺度が提案されることによって,この20年あまりの間に,SOCと健康生成モデルの実証研究が大いに促進され,年々,幾何級数的な増加を示し,世界の学術雑誌に掲載されたSOC実証研究論文だけでも,今日までに千数百本にものぼっている。健康生成モデルとは,SOCはどのような働きをするのか,SOCは何によって育まれるのかということについての理論モデルのことである(図1)。 本稿では,以下,こうしたSOCとその着想のもとになった健康生成論とはどういう概念であり理論なのか,特に,SOCはどういう感覚なのか,人生における究極の健康要因として,ストレスフルな出来事や状況に直面して,どのような働きをする,どういう力なのかということについて,Antonovskyの提唱した理論をベースに,その後の実証研究の成果も踏まえて,概説してみたい。筆者らが2008年に出版した『ストレス対処能力SOC』(山崎・戸ヶ里・坂野編,2008)の第1章「ストレス対処能力SOCとは」とも重なるところが少なくはないが,本稿では,さらに整理と深化を随所で図ったつもりである。
2 0 0 0 OA 中程度LEDブルーライト照射によるマウス網膜の変性について
- 著者
- 川手 美穂 木下 明美 品川 英朗 山野 眞利子
- 出版者
- 大阪府立大学総合リハビリテーション学研究科
- 雑誌
- Journal of Life Science Research (ISSN:21865809)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.15-19, 2014-12-27
2 0 0 0 OA 経済的中枢管理機能からみたフランスの主要都市と都市システム
- 著者
- 阿部 和俊
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告, 人文・社会科学編 (ISSN:13414615)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.133-140, 2009-03-01
2 0 0 0 OA 二本の指 : 社会部記者の手帖から
2 0 0 0 OA ズヴェーヴォと「書くこと」
- 著者
- 芝田 高太郎
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.199-218, 1993-10-20
Le opere di Svevo sono caratterizzate dalla quotidianita della vita dell'eroe, dal suo mondo interiore esplorato e messo in chiaro dettagliatamente. E questi caratteri sono comuni fra i grandi romanzieri primonovecenteschi come Proust, Joyce, Kafka, Musil, ecc. Ele opere di Svevo sono fortemente autobiografiche. Cioe, Svevo racconta di se stesso in tutte le sue opere. Naturalmente i suoi eroi non sono fotocopie dell'autore stesso. Ma, i lettoriricevono l'impressione che essi ci mostrino inconfondibilmente l'essenza della personalita dell'uomo Italo Svevo. Incuriositi dal raporto fra l'uomo e le opere, si cominciano a leggere le sue lettere e i diari. Ma si incontra la stessa faccia anche in questi scritti <privati>. Si crede che Svevo abbia <smesso> di scrivere dopo l'insuccesso dei suoi primi due romanzi. Ma in realta Svevo, sotto la maschera dell'impiegato Ettore Schmitz, continuava a scrivere. In un diario, Svevo confessa che non puo sentirsi vivere senza scribacchiare giornalmente per conoscere meglio se stesso. L'impiegato Ettore Schmitz, prima del matrimonio, scriveva Diario per la fidanzata. In questo diario Ettore Schmitz tenta di far conoscere la propria personalita alla fidanzata Livia Veneziani. Ma in questo diario, stranamente, Ettore Schmitz esibisce le proprie debolezze piuttosto volutamente, esagerandole. Anche nelle sue opere, per esempio in Una Vita e in Senilita, Svevo espone troppo le debolezze dei protagonisti. Cosi, Italo Svevo=Ettore Schmitz, in tutti i suoi scritti, privati o <pubblici>, tratta i personaggi ugualmente. Quando scriveva, comunque voleva scrivere sinceramente. Anche quando scriveva romanzi o novelle, cioe finzioni, voleva scrivere solo la verita. Cosi risulta l'omogeneita degli scritti privati e pubblici. Ma Ettore Schmitz ha adottato lo pseudonimo Italo Svevo. Aveva bisogno di una maschera. Dopo il successo de La coscienza di Zeno, Svevo=Schmitz prepara un'altra maschera. Nei suoi ultimi anni, Svevo ha scritto piccole autobiografie nelle lettere ad alcuni scrittori come Montale, o Prezzolini. E nel 1928 ha scritto Profilo autobiografico. In queste autobiografie, Svevo, dopo l'insuccesso dei primi due romanzi, ha escluso la letteratura dalla sua vita perche la letteratura danneggia la vita dell'impiegato Ettore Schmitz. Ma in realta Svevo non poteva fare a meno della penna. Cosi, Italo Svevo era una maschera gia mascherata. Un Romanziere deve vivificare le sue pagine nelle opere. Dunque deve <vivere> il mondo delle sue opere. Da qui nasce il rischio che il romanziere confonda la propria vita con le vite finte nelle sue opere. Anche Svevo soffriva di questa malattia. Nel diario per la fidanzata confessa la sua indifferenza per la vita. Ogni avvenimento reale gli sembrava tutto finto. Dopo La coscienza di Zeno, Svevo non voleva la soluzione del proprio problema, cioe la conoscenza completa della propria personalita, la guarigione assoluta della sua malattia che era l'indifferenza alla vita. L'unica via rimasta era lo studio di se stesso che non finisce mai. La verita si puo cogliere solo proseguendo questo studio.
2 0 0 0 OA オートラジオグラフィの現状
- 著者
- 若林 康夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.9, pp.469-478, 1967-09-15 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 9
2 0 0 0 OA 神経伝達物質と神経疾患
- 著者
- 金澤 一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.97-103, 1989-03-01 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 12
ニューロン同士の情報伝達にかかわる化学物質である神経伝達物質の概念そのものが近年大きな変革をせまられている.かつてのように局在, 作用, 放出といった性質の他に最近では特異的レセプターの存在も重視されてきている.さらに, 同一ニューロンに二種類あるいはそれ以上の神経伝達物質が局在していることも明らかになっていることなどを概説した.さらに, このような神経伝達物質の基礎的知識の臨床応用として, ヒト神経疾患脳で測定されているが, その変動のパタンが単にニューロン変性の二次的現象としての減少, 形態変化を伴わない機能低下を反映した減少の他, 代償的増加など三つの基本的パタンがあることを述べた.
- 著者
- 多田 智
- 出版者
- 大阪南医療センター
- 雑誌
- 産学が連携した研究開発成果の展開 研究成果展開事業 大学発新産業創出プログラム(START) プロジェクト推進型 SBIRフェーズ1支援
- 巻号頁・発行日
- 2021
予備群含めると国内4700万人が罹患していると推計されるロコモティブシンドロームは、 放置すると要介護状態に至るが早期の診断で治療や予防が可能である。本支援により、患者歩行動画からロコモティブシンドロームを診断する非侵襲的高精度AI診断機器開発のための概念実証を取得し、将来的に疾病診断補助サービスを行うベンチャー企業の設立を目指す。
2 0 0 0 OA 若者は公民館でなにを学ぶのか —国立市公民館「コーヒーハウス」の実践から—
- 著者
- 井口 啓太郎
- 出版者
- 日本公民館学会
- 雑誌
- 日本公民館学会年報 (ISSN:1880439X)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.81-90, 2017-11-30 (Released:2019-04-04)
In recent years, efforts of youth education in Kominkan have declined, while measures to support youth independence centering on welfare and public health fields are expanding. Amid these current circumstances, vigorous activities are continuing at Kunitachi City Kominkan (Tokyo) in the “Coffee House” of youths who have been working with disabled people since the 1980s. This paper is a practical report aimed at considering the meaning of learning by youths based on the descriptions of the youths themselves; the author has been involved as a staff member in this program.In order to clarify the background of the practice of the current “Coffee House” Chapter 2 reviews the history of this practice. It is confirmed that the youth room and coffee corner in the Kominkan became the “place of residence” of the youths who were learning alongside the disabled people, and have influenced the community-making symbiosis.While providing an overview of the participation of youths of the present “Coffee House,” chapter 3 includes a concrete description of the diverse background of the youths, their process of learning, and the transformation of their cognition. At that time, referring to the recent “Practice Record Magazine” issued by Kunitachi City Kominkan, we discuss the words that the youths have used to describe and consider the meaning of that learning.Participating youths are caught up in the practice of “Coffee House” by some chance, gradually making relationships with others. Through this, the values of the “Coffee House” are internalized, and some youths draw on how they became involved in the operation of the course.The future task is to reexamine “independence” from the practices of the youths reported in this paper, and to reexamine the existing value of Kominkan practices and the social education staff.
2 0 0 0 OA ケニヤのマサイ族の生産する伝統的発酵乳:マジワララの微生物学的特性
- 著者
- 中村 正 菅井 理子 男澤 綾 有賀 秀子 小疇 浩 キュラ キーユキア 荒井 威吉 浦島 匡
- 出版者
- 日本酪農科学会
- 雑誌
- ミルクサイエンス (ISSN:13430289)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.9-14, 1999 (Released:2015-10-31)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
ケニアの一般家庭より伝統的発酵乳であるMaziwa lalaを採取し, その菌叢および流動特性について検討した。生菌数はMaziwa lala (A) で5.2×107 c.f.u/ml, (B)で1.3×109 c.f.u/mlであった. また, Maziwa lala (A), (B) からそれぞれ分離した45菌株, 54菌株を同定試験に供した結果, 主要菌種はLact. lactis subsp. lactisとLeuc. mesenteroides subsp. mesenteroides dextranicumであり, これらが全菌株の90%以上を占めていた。 スキムミルク培地で, これら主要菌種であるLact. lactis subsp. lactis, Leuc. mesenteroides subsp. mesenteroides dextranicumおよびこれら2種を混合 (1:1) したものを培養し, 粘性試験を行った。その結果, 混合培養したものが最も粘性が高く, また, 風味が良かったことから, これら2菌種がMaziwa lalaの製品特性を形成するものであることが示唆された。