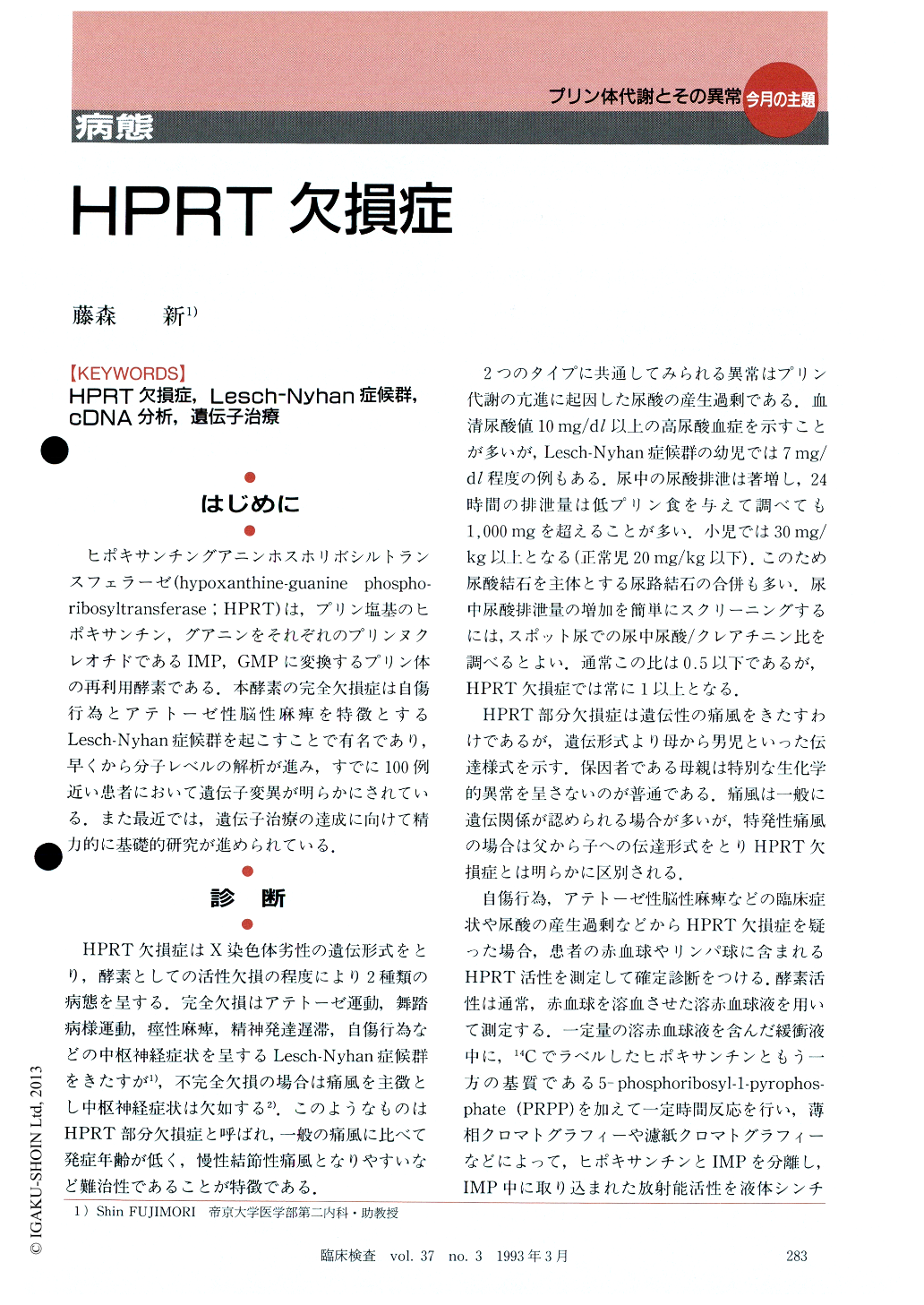2 0 0 0 OA アッシャー症候群
- 著者
- 石川 浩太郎 吉村 豪兼 西尾 信哉 宇佐美 真一
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳科学会
- 雑誌
- Otology Japan (ISSN:09172025)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.142-147, 2021 (Released:2021-11-25)
- 参考文献数
- 8
アッシャー症候群は聴覚・視覚の重複障害のため,コミュニケーション障害を生じる疾患である.アッシャー症候群について,これまで厚生労働科学研究補助金(難治性疾患研究事業)において研究が進められており,現在は難治性聴覚障害に関する調査研究班が担当して研究が行われている.アッシャー症候群は感音難聴と網膜色素変性症のそれぞれの症状の程度とその発症時期によって3つのタイプに分類されている.しかし臨床的な診断には限界があり,遺伝学的検査が確定診断の手助けとなっている.2020年3月31日現在で,204例が全国から登録され,先天性難聴を有し,網膜色素変性症の発症年齢は,10歳未満および10歳代の発症が多く見られた.原因遺伝子はタイプ1ではMYO7A遺伝子とCDH23遺伝子が,タイプ2ではUSH2A遺伝子が多数を占めた.同じ原因遺伝子でも,聴力型にバリエーションが見られることが確認され,原因遺伝子検索の重要性が示唆された.
- 著者
- 宮坂 清
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.3, pp.95-101, 2021-12-30 (Released:2022-03-30)
2 0 0 0 IR イタリア・ミラノにおける社会センターという自律空間の創造 : 社会的包摂と自律性の間で
- 著者
- 北川 眞也
- 出版者
- 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター
- 雑誌
- 都市文化研究 (ISSN:13483293)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.12-25, 2012-03
2 0 0 0 HPRT欠損症
- 著者
- 藤森 新
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床検査 (ISSN:04851420)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.283-286, 1993-03-15
はじめに ヒポキサンチングアニンホスホリボシルトランスフェラーゼ(hypoxanthine-guanine phospho-ribosyltransferase;HPRT)は,プリン塩基のヒポキサンチン,グアニンをそれぞれのプリンヌクレオチドであるIMP,GMPに変換するプリン体の再利用酵素である.本酵素の完全欠損症は自傷行為とアテトーゼ性脳性麻痺を特徴とするLesch-Nyhan症候群を起こすことで有名であり,早くから分子レベルの解析が進み,すでに100例近い患者において遺伝子変異が明らかにされている.また最近では,遺伝子治療の達成に向けて精力的に基礎的研究が進められている.
2 0 0 0 OA 学士課程における大規模データに基づく学修状態のモデル化
- 著者
- 近藤 伸彦 畠中 利治
- 出版者
- 教育システム情報学会
- 雑誌
- 教育システム情報学会誌 (ISSN:13414135)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.94-103, 2016-04-01 (Released:2016-05-07)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 5
Institutional Research (IR) has been receiving much attention in Japanese higher education. In order to guarantee the educational quality of university, it has been discussed how to utilize the educational big data. In this paper, it is considered to construct models of students’ learning states using large-scale students’ learning data collected through the baccalaureate degree program based on some machine learning methods. In this research, data in 5 years are utilized in order to investigate the generalization ability of the models, and the performances of some machine learning methods are compared. From the experimental results, it is indicated that the models of students’ learning states with high generalization ability can be constructed. Its capability of application to enrollment management is also discussed from experimental results.
2 0 0 0 OA 古今集の成立と藤原時平
- 著者
- 山口 博
- 出版者
- 中古文学会
- 雑誌
- 中古文学 (ISSN:02874636)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.1-9, 1971-09-30 (Released:2019-03-10)
- 著者
- 工藤 遥 田村 俊明
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.61, 2014
架空の存在でありながら世界中の神話に登場し、現代においてもファンタジーには欠かせない存在であり続けている竜・龍・ドラゴン。人間は彼らに対してなぜこれほどにまで興味を抱いてきたのか。そして、人間は彼らに何を投影しているのか。ここでは歴史を通して様々な姿に描かれてきた竜を追い、現代における竜のキャラクター性に目を向けることで、人間と竜との関わり、またその背後に潜む人間の自然に対する意識の変化を考察する。
2 0 0 0 OA 対立ロジックの協調による消費実践の脱スティグマ化
- 著者
- 織田 由美子
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングレビュー (ISSN:24350443)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.85-93, 2020-03-04 (Released:2020-03-04)
- 参考文献数
- 32
本稿の目的は,負のイメージを付与された消費様式が人々に受け入れられるようになるプロセスを脱スティグマ化として捉え,その際に創発される多様な意味間の関係性について明らかにすることである。理論枠組みとして,制度論における制度ロジックという概念を用いる。具体的には,2008年以降ブームとなった「婚活」の事例研究に基づき,多様なロジックの発展プロセスと,ロジック間の関係性について,過去29年間の新聞記事のテキストマイニングにより明確化する。市場創造に関するこれまでの研究において,企業のマーケティングは多様なロジックが創造される中で棲み分けを行ったり,差別化を行ったりすることが明らかにされた。これに対し,本研究は多様なロジックが補完し合うことで,大規模な普及につながる可能性について示唆する。
2 0 0 0 OA 二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)
- 著者
- 下田昭郎
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 脱炭素社会の技術と諸課題 : 科学技術に関する調査プロジェクト報告書
- 巻号頁・発行日
- 2022-03
2 0 0 0 OA 水素の関連技術と普及拡大のための諸課題
- 著者
- 萩原真由美
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 脱炭素社会の技術と諸課題 : 科学技術に関する調査プロジェクト報告書
- 巻号頁・発行日
- 2022-03
2 0 0 0 IR 英語差別用語の基礎的研究(1) : 性差別語
- 著者
- 苅部 恒徳
- 出版者
- 新潟国際情報大学情報文化学部
- 雑誌
- 新潟国際情報大学情報文化学部紀要 (ISSN:1343490X)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.1-17, 2001-03-19
- 著者
- 大川 裕子
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.11, pp.2019-2020, 2009-11-20 (Released:2017-12-01)
2 0 0 0 Igスーパーファミリーに属す膜糖蛋白、ベイシジンの作用機構の解明
免疫グログリン(Ig)スーパーファミリーに属する膜糖蛋白ベイシジン(Bsg)は細胞外に2つのIgドメインを有する。そのノックアウトマウスを作製して解析すると1)着床期での多数の死亡2)生後1ヶ月以内の間質性肺炎による死亡3)精子形成不全、卵成熟不全、着床不全による両性の不妊4)記憶学習能力の著しい低下が明らかになった。そこで本研究では1)精子形成におけるBsgの役割の解明2)Bsgのホモオリゴマーの形成機序とその生理的意義の解明3)Bsgと相同性を持つエンビジンとのクロストークの可能性の3点に目的を絞って解析を進めた。Bsgノックアウトマウスでは第1減数分裂のメタフエーズで精子形成が止まる結果無精子症になることが判明した。セルトリ細胞と精娘細胞間で通常見られない型のectoplasmic specializationが見られBsgがこの形成に関与する可能性が示唆された。Bsgのホモオリゴマー形成はシス型の(つまり同一細胞表面上の)ものであり、それにはN末側のIgドメインが重要であることが判明した。Bsgとエンビジンとのオリゴマー形成は見ることができなかった。Bsgノックアウトマウスの解析は網膜まで及びelectroretinogramと組織学的解析の結果、桿体細胞、錐体細胞両者の機能ともBsgノックアウトマウスではほとんど消失し、加齢に伴って廃用性萎縮がおこった。色素上皮にBsgの発現が強いことからこの部位でのBsgの機能が視細胞の生存あるいは維持に必要であると考えられた。以上をまとめると本研究はBsgの機能発現に関わる二とが予想されるホモオリゴマー形成機構の一部を解明し、また新たな機能発現の場として網膜をクローズアップしたといえる。今後その作用機構のさらなる解明のためにはBsg細胞内ドメインの結合蛋白の同定、Bsg受容体の同定が急務となると考える。
2 0 0 0 OA 脱炭素技術を実装するために必要な社会技術の諸課題
- 著者
- 岸本充生
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 脱炭素社会の技術と諸課題 : 科学技術に関する調査プロジェクト報告書
- 巻号頁・発行日
- 2022-03
2 0 0 0 OA 脱炭素技術のライフサイクルアセスメント
- 著者
- 玄地裕
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 脱炭素社会の技術と諸課題 : 科学技術に関する調査プロジェクト報告書
- 巻号頁・発行日
- 2022-03
2 0 0 0 OA なぜ脱炭素化が必要なのか? : 気候変動の現状と将来見通し
- 著者
- 江守正多
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 脱炭素社会の技術と諸課題 : 科学技術に関する調査プロジェクト報告書
- 巻号頁・発行日
- 2022-03
2 0 0 0 OA 久保田新 他著, 『臨床行動心理学の基礎 医と心を考える : 人はなぜ心を求めるか』
- 著者
- 坂上 貴之
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.131-137, 2004-06-30 (Released:2017-06-28)
久保田新ら(2003)による魅力的でずっしりとした教科書は、感覚と知覚から人間の発達にわたる心理学的現象を考察するための、様々な視点を私たちに与えてくれる。この本は、この理由から臨床及び医療分野の学部学生、心理学専攻の大学院生に強く推薦できるが、特に行動分析家へは、自らの徹底的行動主義の哲学的基盤を著者のそれとつきあわせるために推薦できる。随伴性の概念と有名な誤信課題であるサリーとアンの課題の問題が著者の用法に基づいて詳細に議論された。
2 0 0 0 男性養護教諭の仕事に対する意識と体験に関する質的研究
- 著者
- 鈴木 春花 朝倉 隆司
- 出版者
- 日本健康相談活動学会
- 雑誌
- 日本健康相談活動学会誌 (ISSN:18823807)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.29-40, 2018
<p> 本研究は、性別意識に着目して、男性養護教諭の仕事の意識と体験の特徴を明らかにした。</p><p> 男性養護教諭4名を対象とし、約1時間程度の半構造化インタビューを実施した。分析は、テーマ分析の方法を参考に、共著者間で協議して進め、基本的問題意識とデータの読み込みから、5つのテーマを設定してカテゴリーを生成した。</p><p> 性別意識が現れたカテゴリーは、《養護教諭を目指した理由・動機》《養護教諭としての職業観》では、【男性でもなれるという思い】【専門性と性別は無関係】であるという認識のカテゴリーであった。男性の《養護教諭としての仕事上の体験》では【男性養護教諭に対するバリアへの挑戦】【少数派男性ゆえの孤独感と存在価値】【中年期の男性養護教諭イメージの不確定さからくる不安と期待】【子供が持つ羞恥心への理解】【セクハラの危険性の認知と予防策】【性別を超えた対人職の倫理】と特徴的なカテゴリーを見出した。《うまく働ける要因》では、【学校のニーズ】【男女の複数配置】【普通と思う受け入れ姿勢】という職場の条件、【本人のポジティブな性格】という本人の要因を見出した。《男性養護教諭の存在意義》に関しても、【子供に養護教諭の選択肢を与えることができる】【キャリア教育の一翼を担う】【これまでの当たり前を問い直すことができる】【多様なニーズへの対応ができる】のように、男性養護教諭の立場から養護教諭のあり方を問い直すカテゴリーを見出した。</p>
- 著者
- 渋谷 真樹
- 出版者
- お茶の水女子大学ジェンダー研究センター
- 雑誌
- ジェンダ-研究 (ISSN:13450638)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.149-162, 2000-03