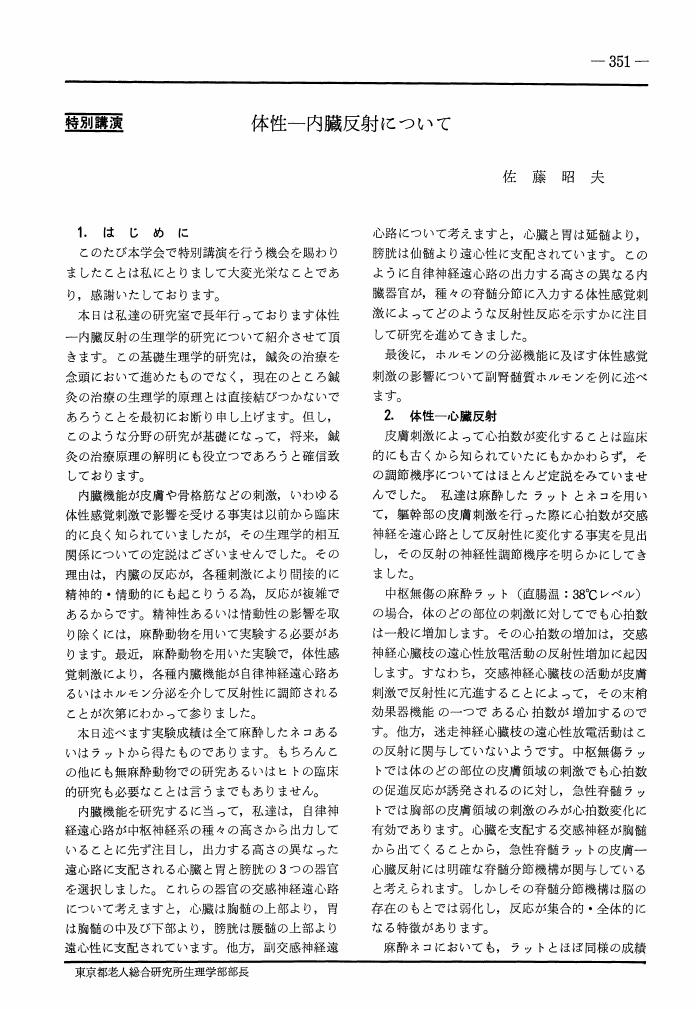2 0 0 0 網目像(fine network pattern)
定義 大腸の正常粘膜表面には腸管短軸方向にほぼ平行して走る無数の微細な溝があり,無名溝と呼ばれる.無名溝には時に交叉し,これによって囲まれるやや細長い“小区”があり,微細網目構造となっている.これは網目像(fine network pattern ; FNP)と呼ばれる.病変部分ではこの構造が消失し,組織学的な病変部分と一致している. FNPは1965年にWilliams1)により“innominate grooves”として報告された.その後,1971年に狩谷,西澤ら2)は“innominate grooves”から形成される大腸粘膜の微細な模様を“網目像(FNP)”と名付けた.このFNPはX線造影像で再現可能な最小単位であり,大腸二重造影像の基本像となる(Fig. 1).
2 0 0 0 OA 独唱:歌に生き恋に生き 「トスカ」より
- 著者
- 伊庭 孝(訳詩)[作詞]
- 出版者
- コロムビア(戦前)
- 巻号頁・発行日
- 1934-06
2 0 0 0 OA 鞘翅目昆蟲の染色体研究 Ⅳ. : コガネムシ科5種の染色体比較
2 0 0 0 OA オキシトシンと加齢
- 著者
- 大野 重雄 丸山 崇 吉村 充弘 梅津 祐一 浜村 明徳 佐伯 覚 上田 陽一
- 出版者
- 日本自律神経学会
- 雑誌
- 自律神経 (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.119-129, 2020 (Released:2020-07-15)
- 参考文献数
- 50
オキシトシン(OXT)は,分娩や射乳反射だけではなく,様々な調節(鎮痛,不安,信頼,絆,社会的認知,向社会的行動,骨・骨格筋)に関わることが報告されている.我々は加齢とOXTの関係を明らかにするために,OXT-monomeric red fluorescent protein 1(mRFP1)トランスジェニックラットを用いて下垂体後葉(PP),視索上核(SON),室傍核(PVN)におけるOXT-mRFP1蛍光強度の加齢変化を調べた.その結果,加齢群でPP,SON,PVNでのmRFP1の集積増加と視床下部でのウロコルチン増加を認めた.また増化したウロコルチンはOXTニューロンにほぼ共発現していた.今後,加齢とOXT発現の機序が解明されることにより,高齢者のサルコペニアや孤独/社会的孤立の予防にも役立つ可能性がある.OXTの加齢との関係を含めて文献をもとにこれまでの知見をまとめ概説した.
- 著者
- 宮崎 里司
- 出版者
- 早稲田大学大学院日本語教育研究科
- 雑誌
- 早稲田大学日本語教育研究 (ISSN:13471147)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.1-25, 2005-09-15
- 著者
- 千葉 直樹 永谷 稔
- 出版者
- Japan Society of Sports Industry
- 雑誌
- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.2_327-2_336, 2015
The purpose of this study was to examine the changes in characteristics of spectators of professional basketball teams, and the relationship between frequency of attendance and participant motives in Sapporo. The name of the professional basketball team and its company changed from "Rera Kamuy Hokkaido" to "Levanga Hokkaido" in 2011. Questionnaire surveys conducted in 2010 and 2012 were analyzed. Findings indicated that between the two research periods there was no change in spectators′ characteristics according to sex and age groups. Previous studies had indicated that 70% of spectators were women and half of these female spectators were between the ages of 20-40. About 80% of spectators surveyed participated in both research periods. The 2012 results indicated that the percent of spectators who had belonged to basketball club in their junior and high school days was higher compared to that in 2010.
2 0 0 0 プラーグの妖術師 : ウォーハンマーRPGリプレイ2
- 著者
- 友野詳グループSNE著
- 出版者
- 社会思想社
- 巻号頁・発行日
- 1993
2 0 0 0 IR シュガーデコレーションの技法研究
- 著者
- 冨田 靖子
- 出版者
- 文化学園大学
- 雑誌
- 文化女子大学紀要. 服装学・生活造形学研究 (ISSN:0919780X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.37-44, 2000-01
ケーキデコレーションにおける表現技法の一つに装飾砂糖菓子と言われているシュガーデコレーションがある。ケーキの上にシュガーペーストでカバーリングを施し,シュガーペーストで製作したシュガーフラワーやアイシングなどでデコレーションした技法である。本報では,シュガーデコレーションを製作する上で必要な技法に関しての調査を行い,専門書に掲載されている128種を技法別,モチーフ別,用途別に分類した。技法別では「アイシングワーク」「ペーストワーク」「ペインテイング」「その他」と4区分に分類でき,その中に14技法があることが判明した。モチーフ別では,「花」「建物」「人形」「その他」と4区分に分類され,「花」が大半を占めた。用途別にみると「ウェディング」「アニバーサリー」「特別な日」の3区分に分類でき「ウェディング」が半数近くあった。シュガーペーストの扱いについても実験をした結果,調整後3~5分が最も扱い易く,伸展性,形状の観察結果ともに良好であった。この条件を用いて,ウェデイングケーキを製作した。
2 0 0 0 OA 文献にみる牛鍋とスキ焼きの歴史について
- 著者
- 山口 和彦
- 出版者
- 一般財団法人 日本英文学会
- 雑誌
- 英文学研究 支部統合号 (ISSN:18837115)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.67-76, 2016-01-20 (Released:2017-06-16)
Cormac McCarthy's Blood Meridian, or the Evening Redness in the West has been highly evaluated as a counter-history of the borderland, or as an epic novel. A number of critics, however, have pointed out its lack of ethical substance due to its abundant descriptions of violence, blood, and death. This essay examines the thematics of violence, and reinterprets BM as a work of fiction that explores the whereabouts and possibility of ethics in the postmodern and in the posthuman. The kid's characterization as a mother-killer is associated with the violence of American historiography, reflecting the rhetoric of America's expansion as biological development. It, in turn, defies the conventions of the Western-Bildungsroman genre: the building of American character through frontier experiences. Thus, BM foregrounds ontological problems of human existence and free will in the apocalyptic borderland. The desert in BM functions as a topos in which the judge practices his hyper-rational, hyper-nihilistic violence, which relativizes every system of values to the single purpose of life: "war," that is, "the truest form of divination." The kid, the judge's biggest rival, rejects being a subject of the "war," and, as a result, is cannibalized by the judge himself (not as a sacrifice for the common good or belief). His death, however, is presented as the unrepresentable, which demonstrates that this death itself is not usurped by the judge, who attempts to be the suzerain of the earth. The biggest dilemma the story presents is the kid's rejection of opportunities to kill the judge by exercising his own violent nature. This, paradoxically, leads to the possibility of a counter-ethics that continues to reject the judge's philosophy of violence. The counter-ethics (in the posthuman), in this sense, might be represented as one always already in a germinal stage, as shown in the epilogue.
2 0 0 0 OA 体性-内臓反射について
- 著者
- 佐藤 昭夫
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 自律神経雑誌 (ISSN:03870952)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.351-354, 1981-03-01 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 22
- 著者
- 王 才林 宇田津 徹朗 湯 陵華 鄒 江石 鄭 雲飛 佐々木 章 柳沢 一男 藤原 宏志
- 出版者
- 日本育種学会
- 雑誌
- Breeding science (ISSN:13447610)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.387-394, 1998-12-01
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
1992年から,プラント・オパール分析による中国長江中・下流域における稲作の起源およびその伝播に関する日中共同研究が開始され,太湖流域に所在する草鞋全山遺跡における古代水田趾の発掘調査が行われた。調査の結果,遺跡の堆積土層が10層確認され,5層からlO層までは馬家浜中期(B.P.5900〜6200年)の文化層であることが判った。また,プラント・オパールの分析により,春秋,綾沢,馬家浜時期の水田土層が確認された。さらに,馬家浜中期の土層から40面余りの水田遺構が検出された。本論文では,検出された水田遺構の一部および各土層から採取した土壌試料について行ったプラント・オパールの定量分析および形状分析の結果を報告し,当該遺跡における古代イネの品種群およびその歴史的変遷について検討を加えたものである。プラント・オパールの定量分析より,各遺構および各土層からイネのプラント・オパールが多量に検出された。この結果から,草革全山遺跡周辺では,B.P.6000年の馬家浜中期からイネが継続して栽培されてきたと推測される。
2 0 0 0 IR 保育要求権と行政責任--真理子ちゃん訴訟を素材に
- 著者
- 倉岡 小夜
- 出版者
- 日本女子大学社会福祉学科
- 雑誌
- 社会福祉 (ISSN:02883058)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.p62-73, 1988
2 0 0 0 OA 内リンパ水腫と内耳液性恒常性
- 著者
- 北原 糺
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.64-74, 2015-04-15 (Released:2016-04-15)
- 参考文献数
- 48
2 0 0 0 IR 社会的現実と虚構論 (故 畝部俊也准教授 追悼 田中重好教授 退職記念)
- 著者
- 成瀬 翔 NARUSE Sho
- 出版者
- 名古屋大学文学部
- 雑誌
- 名古屋大学文学部研究論集 (ISSN:04694716)
- 巻号頁・発行日
- no.63, pp.61-74, 2017
John Seale claims that human society are based a special rules: constitutive rules. Constitutive rules have form of ʻX counts as Y in context Cʼ, and are characterized as constituting social facts. For example, bills in the wallet are physically only pieces of paper. However, certain type of paper counts as bills in our society. Seale asserts constitutive rules are foundation to create such a social fact. But, the problem is acts of ʻcounts asʼ. Searle is assumed this act as a primitive concept. In order to explain this act, I will compare the Kendall Walton and Searle, and try to clarify the constitutive rules. The contents of this paper are as follows. In Section 1, I will survey Searleʼs discussion and consider concepts of constitutive rules and social facts. In Section 2, I will introduce Waltonʼs theory of make-believe. In Section 3, I will compare the Searle and Walton, and point out the differences between them.
2 0 0 0 OA <論説>マルクスの両親
- 著者
- 岩淵 慶一
- 出版者
- 立正大学文学部
- 雑誌
- 立正大学文学部論叢 (ISSN:0485215X)
- 巻号頁・発行日
- no.114, pp.1A-20A, 2001-09-20
- 著者
- 鮎貝 崇広 金川 哲也
- 出版者
- 日本工業出版
- 雑誌
- 超音波techno (ISSN:09162410)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.50-53, 2020-09
2 0 0 0 OA ネットワークを通して情報を高速で効率的・安全に伝送するための研究
- 著者
- 岡本 栄司
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.275-280, 2016-04-01 (Released:2016-04-01)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA ジフェンヒドラミン含有軟膏の大量誤飲で急性薬物中毒に至った症例の血中濃度モニタリング
- 著者
- 竹増 まゆみ 梶谷 真也 徳本 和哉 要田 芳代 川上 恵子 只佐 宣子 堀川 俊二 福原 和秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.6, pp.904-908, 2013 (Released:2013-07-23)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
急性薬物中毒患者が搬入された際には,薬剤師が中毒原因物質に関する情報を迅速に収集し,個々の症例にあった適切な情報と治療方法を医師,看護師に提案する必要がある。 今回,ジフェンヒドラミン(以下,DPH)含有軟膏を大量に誤飲した99歳女性の救命治療に対して,胃洗浄を含めた治療方法と,患者の血中DPH濃度を経時的に測定することを提案した。その結果,血中DPH濃度の低下とともに臨床症状の改善が認められ,DPH含有軟膏誤飲例に対して胃洗浄を施行したこと,および血中濃度測定の臨床における有用性が示唆された。
2 0 0 0 IR 主題と係り結びから見る日本語の体言文と用言文
- 著者
- 谷守 正寛 Masahiro TANIMORI
- 出版者
- 甲南大学国際言語文化センター
- 雑誌
- 言語と文化 = The Journal of the Institute for Language and Culture (ISSN:13476610)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.169-209, 2021-03-24
In this paper, the latent and essential pattern of Japanese sentence will be established that might be able to be discovered through the consideration of the relation between the topic and kakarimusubi (the rule of linked forms that is said to had spread before the Muromachi Period), based on the observation of the linguistic phenomenon of sentence structure terminating not with the dictionary end-form of a declinable word (yo−gen1) like a verb or an adjective but with the adnominal form (rentaikei ) that ought to be followed by a noun (taigen) or nominal that is attributively modified by it.The author considers the similarity or something common between the verbal or adjectival sentence structure with kakarimusubi and the nominal sentence structure, pointing out that the Japanese sentence structure with kakarimusubi has something in common with English cleft sentence structure and referring to the behavior of the adnominal form of yo−gen that terminates a sentence as that of taigen that also terminates a sentence as the prototype of nominal sentence like 'Haru wa akebono.', and constructs, based on his previous studies on the topic marker wa and Japanese nominal sentences, a hypothesis that the topic of a sentence tends to demand or aim at the adnominal form of a declinable as a nominal at the end of a verbal or adjectival sentence.本稿では,日本語の係り結び文について,本居宣長以来様々に問われてきた係り結び構文の構造が都合よく説明できるように考察すべく,従来の捉え方とは異なる新たな提案として,英語の分裂文との間にその表現上の意図から生じる構造的及び意味機能上の特徴に共通点があることを指摘しつつ,また,用言の連体形は修飾機能を持つものの体言的な性格も有しながら,その被修飾句+係助詞ゾが,分裂文と同様に,強調のために前置されて残された修飾部の連体形のまま文終止を担うようになったと言えようことを指摘し,先行する係り結びの研究を援用しつつ,係り結び文において強調される文要素が文中で確固たる地位を与えられ安定的に常置されるようになると,その必要性の希薄化による役割の弱体化とともに係助詞の衰退を招き,そこにガが古来属格であったことからも,また文中の都合の良い位置関係から見ても,体言的性格を持つ用言の連体形に属格的に機能する格好で前接するポジションを取り,或いは,文末述語句に対する補助的(格)要素として係助詞特にゾに代わる格好で入り込み,その句内の位置からみてもやがて主格として強く意識されるようになった,と合理的にみられようことを例示し考察した。 主題については,紙上の文内で線上的に単に要素移動として取り扱うものとしてではなく,独自の視点からクオリアトピック(Quale Topic)とメモリートピック(Memory Topic)という2 つのカテゴリーに大別し,しかし共通して,文末述語句である連体句とは,文頭の主題から格関係に関わりなく抽出される様々な情報を含む要素でありながら,話者にとってもっとも表出したいものが単純に(論理性に係わらず)接続されて文末に配置されるものとし,そこに係り結びに係る従前から唱えられた倒置理論を修正しつつ融合させて,文成立全体としての整合性を独自に考察した。その上で改めて,「象は鼻が長い」といった現代文を吟味すべく,古文の係り結び文と対照させながら,上述したように,係助詞の前接部分が前置されてのち係助詞の衰退・消滅後も係留される中で,助詞の穴を補うかのように格助詞ガの入り込むに適した余地がそこに与えられ,結果的に「〜ハ〜ガ〜」という構成上の主要要素が基本文型の原型に組み込まれてきたことについても少しく考察した。今後も残る日本語の基本文型に係る課題について独自の手法で吟味したいと考えている。