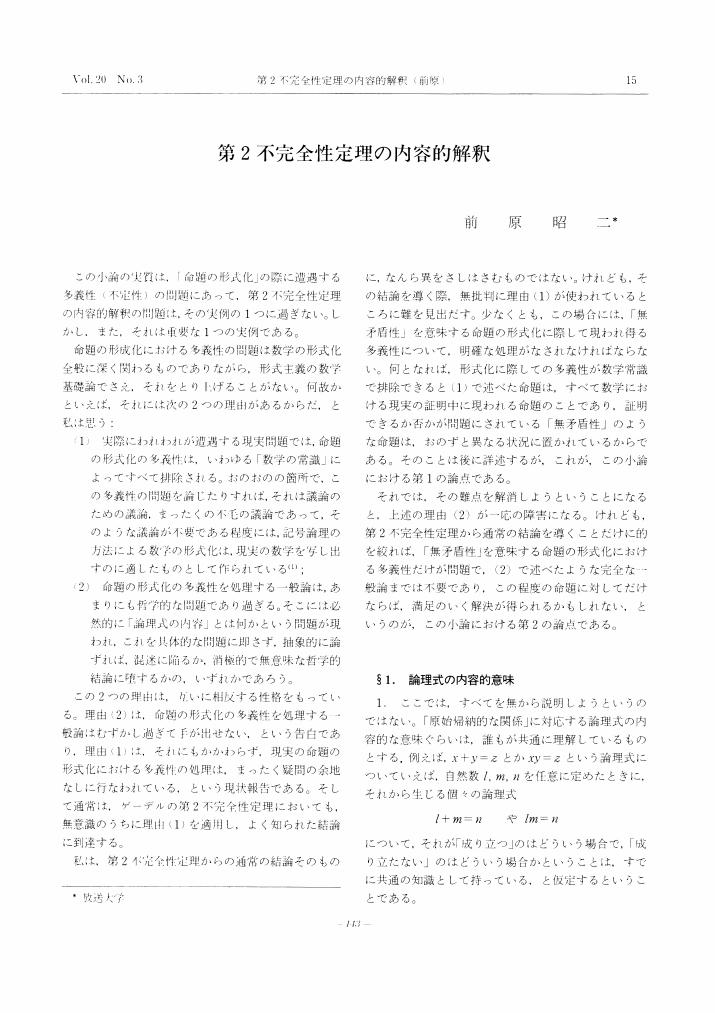2 0 0 0 OA 初回切除後19年目に肺・胃の再切除を行った不完全型Carney's triadの1例
- 著者
- 常塚 啓彰 加藤 大志朗 下村 雅律 寺内 邦彦 島田 順一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会
- 雑誌
- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.748-753, 2014-09-15 (Released:2014-10-03)
- 参考文献数
- 11
Carney's triadは胃平滑筋肉腫,肺軟骨腫,副腎外傍神経節腫の3病変を伴う稀な疾患で,この内の2病変を発症したものを不完全型とされている.我々は初回手術後19年目に肺・胃の再切除を行った不完全型Carney's triadの1例を経験した.症例は30歳女性で11歳時に胃平滑筋肉腫の核出術を受け,21歳時に肺軟骨腫に対する肺部分切除術を施行され不完全型Carney's triadと診断された.今回PET-CTで左肺S1+2bの結節とFDGの異常集積を伴う胃腫瘤性病変を指摘された.胃病変はgastrointestinal stromal tumorと診断され幽門側胃切除術を施行された.肺病変に対し胸腔鏡下に左肺部分切除術を行い,病理学的に軟骨腫と診断した.再切除後5年経過しているが更なる新病変の出現は認めていない.Carney's triadでは異時性に腫瘍発生するため長期的に経過を観察する必要がある.
2 0 0 0 デカルト哲学における観念と存在:物質的事物の存在証明に即して
- 著者
- 小泉 義之
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, no.36, pp.118-128, 1986
2 0 0 0 社会構築主義における批判と臨床
- 著者
- 小泉 義之
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.209-222, 2004
健康と病気の社会構築主義は, 生物医学モデルを批判し, 社会モデルを採用した.そして, 健康と病気を生命現象ではなく社会現象と見なした.そのためもあって, 社会構築主義において批判と臨床は乖離することになった.そこで, 健康と病気の社会構築主義は心身モデルを採用した.心身モデルとゲノム医学モデルは連携して, 心理・社会・身体の細部に介入する生政治を開いてきた.<BR>これに対して, 生権力と生命力がダイレクトに関係する場面を, 別の仕方で政治化する道が探求されるべきである.
2 0 0 0 OA 第2不完全性定理の内容的解釈
- 著者
- 前原 昭二
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.143-147, 1991-12-25 (Released:2009-09-04)
2 0 0 0 豚肉と日本人
- 著者
- 吉田 宗弘
- 出版者
- 食生活研究会
- 雑誌
- 食生活研究 (ISSN:02880806)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.261-272, 2018
- 著者
- 北原 斗紀彦
- 出版者
- 尚美学園大学総合政策学部総合政策学会
- 雑誌
- 尚美学園大学総合政策論集 (ISSN:13497049)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.35-53, 2011-12
戦後日本における原子力発電を中心とする原子力「平和利用」に関する朝日新聞と読売新聞の社説を時期を区分して分析し、両紙の論調の推移の考察と比較を行った。6 つの時期に区分される戦後日本の原子力開発利用史のうち、原子力研究が禁止・休眠していた1945 ~ 53 年の時期(第期)において、両紙の関心はまだ低調であり、「平和利用」への漠然とした期待と夢を表明するにとどまっていた。日本の原子力利用推進体制が整備された1954~65 年の時期(第期)において、読売新聞は1954~57年の4年間にわたり「平和利用」促進の大キャンペーンを行い、原子力が将来のエネルギー源として重要であり、原子炉導入を急ピッチで図らなければならないと主張した。これに対し、朝日新聞は「平和利用」を肯定する立場に立ちつつ、原子力利用推進行政の拙速さを批判する論調を掲げた。
- 著者
- Naohisa Nosaka Yoshie Suzuki Hiromi Suemitsu Michio Kasai Kazuhiko Kato Motoko Taguchi
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.11, pp.1455-1462, 2018 (Released:2018-11-07)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 3 10
Medium-chain triglycerides (MCT) are useful for increasing fat utilization during exercise. The highest rate of fat oxidation during submaximal exercise tends to precede the lactate threshold in untrained adults. In our previous study, blood lactate concentration was more than 4 mmol/L (onset of blood lactate) in recreational athletes during exercise at a workload corresponding to 60% peak O2 uptake (V・o2), which was below ventilation threshold. In the present study, we investigated the effect of 2 week of ingestion of food containing 6 g MCT on substrate oxidation during moderate-intensity (50% peak V・o2) exercise and high-intensity (70% peak V・o2) exercise in recreational athletes. For comparison, two experimental trials were conducted after participants had been administered isoenergic test foods (MCT-supplemented food with mainly maltodextrin-containing carbohydrate (MCT + CHO) or CHO) for 2 weeks, with a washout period between trials. Participants were instructed to perform cycle ergometer exercise at a workload corresponding to 50% peak V・o2 for 40 min followed by a workload corresponding to 70% peak V・o2 until exhaustion. Fat oxidation was significantly increased in the MCT + CHO trial (13.3 ± 2.7 g/40 min, mean ± SD, p < 0.05) during moderate-intensity exercise and the duration was extended significantly (23.5 ± 19.4 min, p < 0.05) during subsequent high-intensity exercise, compared with that observed in the CHO trial (fat oxidation; 11.7 ± 2.8 g/40 min, duration; 17.6 ± 16.1 min). In conclusion, continuous ingestion of 6 g MCT with maltodextrin could increase fat oxidation during moderate-intensity exercise and extend the duration of subsequent high-intensity exercise in recreational athletes, compared with the ingestion of isoenergic maltodextrin alone.
2 0 0 0 OA 『紫式部集』研究の現在
2 0 0 0 放送法・受信料関連規定の成立過程 : 占領期の資料分析から
- 著者
- 村上 聖一
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.5, pp.32-47, 2014-05
- 著者
- 安陪 等思 淡河 喜雄 上野 隆登 堀田 まり子 林 明宏 吉田 一郎 早渕 尚文 佐田 通夫
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.193-199, 2002-06-25 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
【目的】医師となる過程に医療人としての自覚を認識するための明確な通過儀式がなかったので, これを白衣授与式として行った. 学生に対するアンケート調査を元に評価したので報告する.【方法】臨床研修として患者に初めて直に接する直前の2001年1月11日に第4学年112人を対象に白衣授与式を行った. 白衣授与式は学長, 医学部長, 病院長の出席を得て, 臨床の場にこれから第一歩を踏み出す学生に白衣と顔写真付きの名札を授与し, 医師を目指す医学生としての心構えを新らたにする目的で行われた. 式の翌日にアンケート調査を行い, 学生の意識調査を行った. 調査項目は医療に携わる責任感, 患者さんへの優しさ, 愛校心, 白衣に対する愛着, プロフェッショナルとしての意識, 医師としての使命感, 勉学する意欲, 厳粛な気持ち, 倫理的・道徳的生活を実行する意欲の9項目である. また, 教職員, 学生の聞き取り調査を加えた.【結果】アンケート調査のすべての項目において意識の向上が認められた (P<.0001). 約8割の学生が来年も引き続き行うことに賛意を示した. 確立した儀式の様式がないことに多少の問題もあったが, 意義深い試みであったとの評価を得た. 一方, 進級の決定と異なった時期であったので違和感をもった学生が多かった.【結論】不慣れな点もあったが教職員, 医学生ともに意義深い通過儀式としておおむね肯定的な意見が得られた. 医師としての専門職意識を育成するひとつの方法として有効な手段であると思われた. 今後は効果の継続性の有無, 意義, 利点や欠点について教職員と学生を含めた検討, 考察を行い, バランス感覚の取れた通過儀式として修正を加えたい.
- 著者
- 大嶋 光昭
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- ドクメンテーション研究 (ISSN:00125180)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.230-242, 1984
- 著者
- 山辺 恵理子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.146-147, 2009
2 0 0 0 OA 人口・労働・学歴 ――大学は,決して過剰ではない――
- 著者
- 矢野 眞和
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, pp.109-123, 2008-06-15 (Released:2017-06-01)
- 参考文献数
- 8
In 1985, an interesting report that helps understand the relation between the population and the labor market was published. This report, 21 Seiki no Sarari-man Shakai, made forecasts on changes in the Japanese employment system toward the year 2000 by forecasting the manpower requirements in various occupations and analyzing the impact of the baby boomers on the labor market.Looking back over this past forecast and learning from its experience, this paper makes projections in the following two areas.The first is a forecast of the manpower requirements by industry and occupation in 2015. The report, based on a consideration of both the change of population by age and structural changes in industry, makes clear that there will be a large mismatch of supply and demand in the labor force. In particular, the service industry sector will experience a shortage of 2.34 million workers and the there will be a shortage of 1.67 million professionals. Conversely there will be too many manufacturing and technical workers. These dramatic changes will accelerate mobility in employment, it projects, to a level above the figure projected in the report in 1985.The second is an analysis of the relation between the number of workers and wages, an indicator of the quality of labor, during three decades of 1976-2006. The main results are as follows.1) Based on an analysis of relative wages by age group, the ratio of wages of the group in their fifties divided by that of those in their twenties, and of the number of workers in same age groups, it is possible to conclude that the shock of increasing numbers of seniors has been absorbed and that the seniority management system has been maintained through a decline in the wages of seniors relative to the young.2) Based on the same approach, looking at the relative wages and number of workers by educational background, the relative wage of university graduates to high school graduates has been rising among workers in their thirties and forties even as the number of university educated graduates has increased. This suggests the important policy implication that university is never an over-investment in education because the labor demand for university graduates is rising compared to that for high school graduates within the changing labor market.
- 著者
- 山本 未來 深田 武志
- 出版者
- 日経BP社 ; 1985-
- 雑誌
- 日経マネー (ISSN:09119361)
- 巻号頁・発行日
- no.408, pp.84-86, 2016-06
──最近のお仕事では「Nのために」(TBS系)での榮倉奈々さんの、精神的に不安定なお母さん役の印象が強いですが。 もう1年半くらい経つんですよね(笑)。いまだにみなさん、よく言ってくださるんですけど。──怪演、みたいな言われ方をされていましたね。
2 0 0 0 OA アスリートの心理的健康を促進するマインドフルネスと心理的競技能力
- 著者
- 雨宮 怜 金 ウンビ 稲垣 和希 坂入 洋右
- 出版者
- 日本スポーツ心理学会
- 雑誌
- スポーツ心理学研究 (ISSN:03887014)
- 巻号頁・発行日
- pp.2019-1802, (Released:2019-07-04)
- 参考文献数
- 49
The relationship between mindfulness, psychological competitive abilities and mood states were investigated among Japanese university athletes.Athletes (N=233, 169 men and 64 women, mean age 18.51 years, SD=1.16) responded to a questionnaire package comprising the Athletes Mindfulness Questionnaire, the Diagnostic Inventory of Psychological Competitive Ability for Athletes 3 (DIPCA. 3), and the Japanese version of the Profile of Moods States short version (POMS).Results indicated that athletes with high compared to low mindfulness scores had higher scores for self-control, ability to relax, concentration, confidence, decision, judgment, as well as higher total DIPCA. 3, and lower score for total POMS scores. Furthermore, mediation analyses indicated direct and indirect associations between mindfulness and total mood disturbance through self-control and ability to relax skills of the DIPCA. 3.These results suggest that mindfulness is one predictor of psychological aspects of performance and mental health of athletes.
- 著者
- 川崎 直樹 小玉 正博
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.59-61, 2010-08-31 (Released:2010-08-18)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3 1
Researchers have hypothesized that narcissists mask their implicit sense of self-dislike by constructing a grandiose self-representation. Several studies have tested this “mask model” using measures of implicit self-esteem, but no study has been done with a Japanese sample. In this study, the Implicit Association Test (Study 1; n=62) and a name letter task (Study 2; n=102) were administrated to measure the implicit self-esteem of Japanese undergraduates. The relationship between implicit self-esteem and narcissism was examined, and the results did not support the mask model. This result is similar to recent findings from a meta-analysis of the mask model of narcissism.
2 0 0 0 IR 所謂人乳中毒症及ビ乳兒脚氣ノ異同問題ニ就テ
- 著者
- 池田 嘉一郎
- 出版者
- 岡山医学会
- 雑誌
- 岡山醫學會雜誌 (ISSN:00301558)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.371, pp.646-666, 1920
(一)所謂人乳中毒症ニ於ケル精紳症状ハ、輕症ナルモノニ於テハ、一過性ノ興奮性充進竝ニ嗜眠状態ヲ呈スルニ過ギザルモ、重症ナルモノニ於テハ、更ニ進ミテ意識溷濁乃至無慾状顔貌ヲ呈シ、周圍ノ事情ニ對スル識別力ヲ失ヒ笑ハズ泣カズ、眼付曇ヨリシ、時トシテ舞踏病樣不隨意運動乃至不明ノ言ラ發ス、カク特異ナル精紳症状ヲ呈スルハ神經申樞ニ何等カノ病變ノ存スルモノト考ヘザルベカラズ、余ハカカル患者ニ遭遇スル毎ニ勉メテ腰椎穿刺ヲ行ヒ腦脊髓液ノ性状ヲ檢シタルニ、ソノ外觀、比重、糖反應、蛋白量、蜘蛛網状物形成ノ有無等ノ關係ハ、多クハ健康者ノモノト差異ヲ認ムルコト能ハザリシモ、「グロブリン」反應及ビ細胞數ニ於テ輕微ノ變化ノ存スルヲ認メタリ、即チ「グロブリン」反應中、ノンネーアツペルト氏反應竝ニパンヂー氏反應ハ多クハ陰性(時トシテ弱陽性ナルコトアリ)ナルモ野口氏反應ハ毎常弱陽性ヲ示セリ、而シテ淋巴球ノ數ハ通常ナルカ或ハ僅ニ増加セリ、即チ輕度ノ漿液性腦膜炎ノ腦脊髓液ニ相類似ス、カカル腦脊髓液ノ變化ハ唐澤博士ノ報告セル軟腦膜ニ於ケル解剖的變化ト相符合ス。<br>(二)臨牀上ニ於ケル所謂人乳中毒症ト乳兒脚氣トノ主要ナル區別點ハ、伊東博士ニ依レバ血行器症状竝ニ精神症状ノ有無ニ存ス、然レドモ血行器症状ハ兩疾患ヲ鑑別スルニ向ツテ爾カク重要ナル資料トナスヲ得ズ、蓋シ血行器症状ハ乳兒脚氣ニ於ケル必要ナル症状ノ一ツナルモ而モ之ヲ伴ハザルモノ稀ナラズ、又所謂人乳中毒症ニ於テモ血行器症状ハ必ラズ缺如スベキモノニアラザルガ故ナリ、況ンヤ症例(三)ニ於ケルガ如ク、所謂人乳中毒症ニ於テ其ノ經渦中ニ突然衝心症状ヲ表ハシタル事實アルエ於テオヤ。<br>精神症状ノ有無ニ至リテハ、吾人ハ兩疾患ニ於ケル最モ顯著ナル差異タルヲ是認セザルベカラズ、然レドモ大人脚氣ニ於テ稀ニ精神症状ヲ伴フコトアルコト竝ニ余ノ實驗例ノ如ク幼兒脚氣ニ於テ躁暴狂状乃至昏迷ヲ呈シ、而モ軟腦膜ノ病理解剖的所見ニ於テ所謂人乳中毒症ト殆ド同樣ナル病變ヲ呈セルコトアル事實ヨリ推考スル時ハ、乳兒脚氣ニアリテモ亦精神症状ノ表ハルルコトアリテ可ナル理ナリ。<br>(三)所謂人乳中毒症ト母體脚氣トハ甚ダ密接ナル關係ヲ有スルハ余ノ統計的觀察ニ依リテ明カナリ、余ノ症例(四)及ピ(五)ハ正シクコノ事實ヲ立證セルモスト云フヲ得ベシ、即チ余ノ症例ハ哺乳ノ時期ヲ異ニスルモ、脚氣ヲ有スル同一母體ノ乳汁ヲ哺乳シタルニ依リテ、第四子ハ乳兒脚氣ヲ惹起シ、第五子ハ所謂人乳中毒症ヲ惹起セルモノトス、カカル事實ハ、所謂人乳中毒症ハ其ノ本態ニ於テ乳兒脚氣症ト同一ナルモノニアラズヤトノ疑念ヲ益々吾人ニ抱カシム。<br>(四)以上ノ事實ヲ綜合スル時ハ、所謂人乳中毒症ハ其ノ本態ニ於テ乳兒脚氣ト同一上ニ立ツベキ疾患ニシテ、詳言セバ乳兒脚氣ノ一異型ト見做スベキモノナリト信ズ、余思ヘラク、乳兒脚氣ハ脚氣毒素ガ母體ノ乳汁ヲ介シテ小兒ニ移行スルニ依リテ起ル一種ノ中毒症ニ外ナラズ、而シテ臨牀上ニ於テ一方ニハ專ラ心臓機能ヲ障碍スル衝心型アリ又他方ニ血行器症状ヲ件ハズシテ専ラ末梢神經ヲ侵ス所ノ麻痺型ナルモノアリ、コレ等ノ事實ヨリ考フル時ハ脚氣毒素ガ主トシテ心臓ヲ侵ス時ハ衝心型トナリテ表ハレ、主トシテ末梢神經ヲ侵ス時ハ麻痺型トナリテ表ハレ、專ラ腦膜ヲ侵ス時ハ所謂人乳中毒症ノ型トナリテ表ハルルモノニアラザルカ、カカル關係ハカノ麻疹ノ例ニ於テ之ヲ見ル、即チ症状ノ劇烈ナルモノニ於テハ、多クハ肺炎ヲ合併シコレト同時ニ心臓衰弱ヲ招來スルモ、時トシテハ主トシテ中樞神經系統ニ障碍ヲ及ボシ、既ニ前驅期或ハ發疹期ノ初メニ於テ意識溷濁ヲ來シ遂ニ無慾状態ニ陷ルコトアリ、又恢復期ニ於テ稀ニ腦膜ヲ侵シ漿液性腦膜炎ヲ惹起スルモノアリ、是レ麻疹毒ハ時ニ主トシテ中樞神經系統ヲ侵スコトアルヲ意味スルモノニシテ、以上述ベタル余ノ乳兒脚氣ニ於ケル説明ト相符合スル點アルヲ以テ茲ニ之ヲ引用シタルニ過ギズ、カク觀察シ來ル時ハ精神症状ノ有無ハ敢テ問題トナスニ足ラザルナリ、余ハ所謂人乳中毒症ヲ乳兒脚氣腦型トナシ乳兒脚氣中ニ包括スルニ賛スル者ナリ。
2 0 0 0 OA 福祉原理の根源としての「コンパッション」の思想と哲学
- 著者
- 木原 活信
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.3-16, 2005-11-30 (Released:2018-07-20)
本論文では,コンパッション(compassion)の思想を検討する.コンパッションは,これまで社会福祉界では,啓蒙的な意味のスローガンのように主張されることはあっても,十分に学術的に議論されることはなかった.本論では,感傷的主張を排して,その概念を語源的,哲学思想的に議論を展開する.まず語義およびルソーの自然感情としての議論,ニーチェの「同情の禁止」という批判を取り上げる.そのうえでキリスト教思想がコンパッションをどうとらえているのかについて,古典ギリシャ語のスプランクノンσπλαγχνον「腸がちぎれる想い」という概念にその語源を求め,特にヘンリ・ナウエンの「弱さ」とコンパッションの先駆的研究を吟味する.そして現代におけるアレントのコンパッション論を検討したうえで,最終的にコンパッションが閉じられた関係ではなく,開かれた公共空間という場所のなかで位置づけられる意義を主張する.以上により,コンパッションを福祉原理の根源として位置づけその意義を検討する.