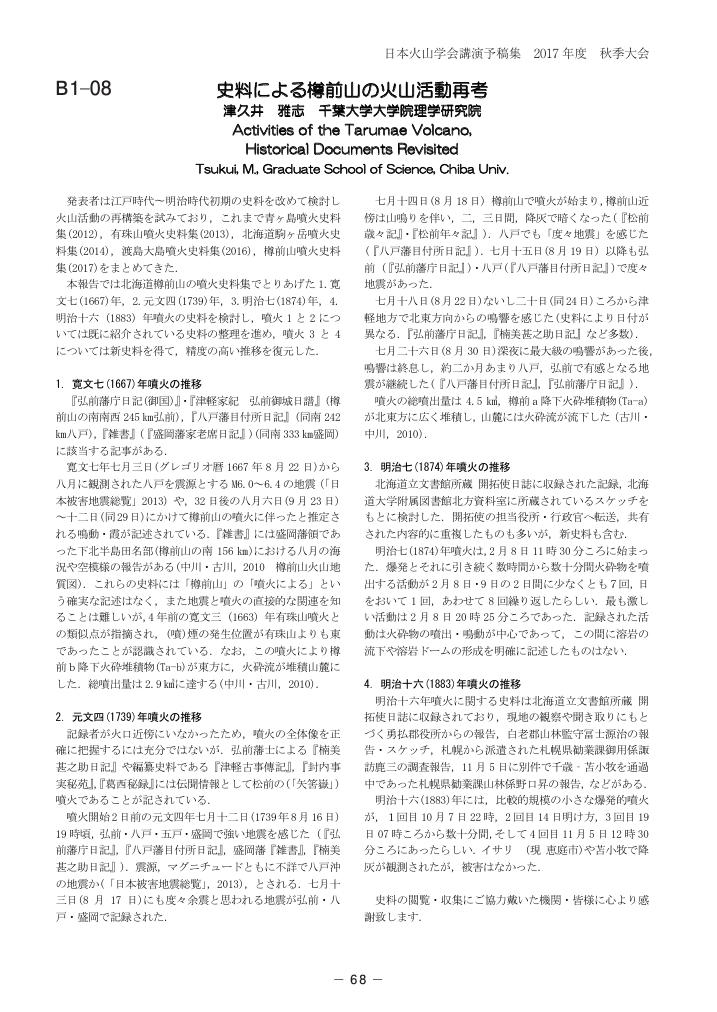2 0 0 0 OA 労働災害における休業見込期間と実休業日数の差異 -労働者死傷病報告と実休業日数との乖離-
- 著者
- 加藤 善士 太田 充彦 八谷 寛
- 出版者
- 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
- 雑誌
- 労働安全衛生研究 (ISSN:18826822)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.173-179, 2019-09-30 (Released:2019-09-30)
- 参考文献数
- 10
労働基準監督署では,労働災害の重篤度を休業見込期間により判断し,労働災害防止施策を展開している.しかし,労働災害の休業が当初の休業見込期間を超えて長期に及ぶことがある.的確な労働災害防止施策を展開するためには,休業期間を早期に正確に把握することが重要となる.そこで某労働基準監督署管内の過去3 年間に発生した労働災害1,672件(男性1,204名,女性468名)について,事業場から報告される労働者死傷病報告と労働者災害補償内容を対比し,休業見込期間と実際の実休業日数の乖離状況を調べ,業種,事業場規模,性別,年齢,業務経験期間,平均賃金との関連を検討した.休業見込期間を超えて実際に休業した者の割合は男性で71.2%,女性で63.9%であった.休業見込期間(中央値:男性30日,女性28日)と実休業日数(中央値:男性50日,女性39日)は男性の方が長かった.休業見込期間を超えて休業する者の割合は,男性において事業場業種,事業場規模,年齢で有意な差が認められた.また,実休業日数/休業見込期間比の中央値は男性1.38,女性1.20と男女間で有意な差があった.労働災害の重篤度を休業見込期間で判断することは,重篤度を過小評価する可能性が高く,実休業日数が休業見込期間を超える割合には,男女で差があった.
2 0 0 0 OA オーストラリア 1979年電気通信(傍受及びアクセス)法の改正
- 著者
- 内海和美
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 290-1), 2022-01
2 0 0 0 OA 学習院史 : 開校五十年記念
2 0 0 0 IR 地域福祉と社会的排除--ホームレス支援の課題と展望
- 著者
- 岡部 卓
- 出版者
- 東京都立大学人文学部
- 雑誌
- 人文学報 (ISSN:03868729)
- 巻号頁・発行日
- no.339, pp.69-94, 2003-03
ホームレス問題を社会的排除の典型として捉えることができる。われわれは社会福祉法における地域福祉計画を推進しながら、新しい住民概念によって支援システムを構築し、ホームレス状態にある人々を社会的に包摂していく必要がある。小稿では、2002年に実施した全国調査の結果を紹介するとともに、ホームレス支援に向けての基本的な考え方、そして地域福祉の推進役である社会福祉協議会が関わっていく上での視点・アプローチを検討し、今後の方向性を提示する。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.886, pp.10-13, 1997-04-14
「何でこんなことになってしまったのか」——。東京地検による本社強制捜査の激震に揺れた野村証券の社内には,経営陣への怨差にも似た声が渦巻いている。生まれ変わったはずの「新生野村」は,まだ「闇」を引きずっていた。リスク管理の欠如がもたらした「再犯」に対する社会の制裁は,容赦ない。野村は創業以来,最大の危機に立たされている。
2 0 0 0 IR ジョージ・ハーバートとフランシス・ベイコン : アタランタの玉をめぐる寓意的解釈
- 著者
- 山根 正弘
- 出版者
- 創価大学英文学会
- 雑誌
- 英語英文学研究 (ISSN:03882519)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.83-107, 2015-03
2 0 0 0 IR 雑誌『アタランタ』と女性たち
- 著者
- 加塩 里美 カシオ サトミ KASHIO Satomi
- 出版者
- 鹿児島大学
- 雑誌
- 地域政策科学研究 (ISSN:13490699)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.55-77, 2014-03
This paper deals with girls' education through the Victorian magazine, Atalanta, which targeted middle class unmarried women. This magazine made its first appearance in 1887 at a time when the imbalance of the population between men and women had become so serious. Women who were unable to find marriage partners had to seek other ways of life by themselves. The editors aimed to make Atalanta a guide for women who were trying to find jobs. This paper explains the magazines issued from October 1887 to September 1893, for they were edited by Meade, a famous author in those days. The paper consists of three chapters. Chapter 1 treats the social circumstances which had an influence on the policy of the editors of Atalanta. Chapter 2 concentrates on the characteristic figures of the magazine, "Atalanta Scholarship and Reading Union" and "Brown Owl", connected with "Atalanta Letter-Bag". In Chapter 3, Japanese women who appear in this magazine are focused on. Two stories about Japanese women are in the magazine, and a letter from Taki in Tokyo appears in 'Brown Owl'. Through the investigation, the lives of Japanese women in comparison with those of British are brought to light.10代から20代前半の中流階級女性層を読者のターゲットとした雑誌『アタランタ』がイギリスで創刊された1887年当時は,ヴィクトリア朝の後期にあたる。雑誌や新聞などの定期刊行物が花盛りであったこの時代に,『アタランタ』は,文芸雑誌として高い評判を得た。それは,「女余り現象」が顕著となった時代を生きるため,自立と自活を目指す女性たちを導いていこうとする編集者の意が,この雑誌の質の高い内容に表れているからである。そこで本稿では2008年から2010年にかけて復刻版として出版された6年分の雑誌『アタランタ』について検証を加え,どのような雑誌であったのかを明らかにする。 第1章「ヴィクトリア時代と『アタランタ』」では,時代背景と女子教育という側面から『アタランタ』の編集方針やその役割を探る。 第2章「『アタランタ』の中の特徴的な企画」では,この雑誌の内容から特徴的な2つの記事であるスカラーシップ・コンペティションと,ブラウン・アウルとレター・バッグを取り上げる。読者の教養を高め,意見の形成を意図したこれら2つの記事の内容を考察対象とする。第3章「『アタランタ』にみられる日本」では,雑誌の中に描かれる日本を取り上げる。ミードが編集者として携わった6年間の『アタランタ』には,日本人を物語の中心に据えた2作品が含まれている。イギリス本国に住む読者に,日本を紹介する意図があったこの2つの作品に書かれた内容からは,当時の日本人の様子やイギリス人の日本人に対する印象が浮かび上がる。また,ブラウン・アウルで採用された東京に住む1人の日本人女性「タキ」の投書からは,時代の牽引力となった中流階級の女性の生き生きとした様子がうかがえる。そこで当時の新聞や資料を基にして,タキの人となりや育ってきた家庭環境などを検証し,若き「アタランタ」の姿を明確にする。
2 0 0 0 IR 「キャリドンのアタランタ」試論
- 著者
- 上村 盛人
- 出版者
- 奈良教育大学
- 雑誌
- 奈良教育大学紀要 人文・社会科学 (ISSN:05472393)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.p41-58, 1978-11
With the publication of Atalanta in Calydon in 1865, Swinburne became famous and was welcomed "to an honourable place among younger poets of England". Aside from his juvenilia, The Queen Mother and Rosamond, issued in 1860, Atalanta was virtually his first important work, because we can find in it almost all Swinburnian traits that he was to develop further in his later works. From the legendary story of Meleager and the boar hunting which Homer, Euripides and Ovid had told, Swinburne created his own tragic version of the myth. Though Swinburne thought that Atalanta was "pure Greek", it was not necessarily so because of its Swinburnian antitheism and aestheticism. Throughout this drama, Heraclitean idea that "Παντα ρει" is repeatedly expressed. Althaea urges her son to serve the gods' law and social customs, while Meleager respects "great things done" that "endure". Chief Huntsman, Chorus and Althaea worship and implore Artemis, the goddess of moon, chastity, hunting and death, while Meleager wishes to be praised by Apollo, the god of sun and art. Artemis, Aphrodite and Atalanta are all represented as femmes fatales. Though Meleager dies a tragic death, he acquires an eternal fame for "what he did in his good time". Like Balen and Tristram, Meleager lives an everlasting life in the world of art, because his "great deeds" have been told by the artists who have immortal soul. Atalanta is a meta-poem and embodies "art for art's sake" like Swinburne's other excellent works.
2 0 0 0 IR 中近世スペインの異端審問とコンベルソ : エストレマドゥーラ都市シウダー・ロドリゴを例に
- 著者
- 関 哲行
- 出版者
- 慶應義塾大学言語文化研究所
- 雑誌
- 慶応義塾大学言語文化研究所紀要 (ISSN:03873013)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.333-346, 2019-03
1. はじめに2. ユダヤ人追放へ向けて3. 近世的異端審問制度4. シウダー・ロドリゴのコンベルソと異端審問5. 結び研究ノート
2 0 0 0 OA 大学入学共通テストがめざすもの ― 「思考力」をどう捉えるか―
- 著者
- 山地 弘起
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬学教育学会
- 雑誌
- 薬学教育 (ISSN:24324124)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.2020-031, 2020 (Released:2020-10-16)
- 参考文献数
- 14
今日の大学入試改革は,高校教育および大学教育の改革と一体となって,高大接続を円滑化することを目的としている.そのなかで,大学入試センター試験に代わって2021年度入試から実施される大学入学共通テストでは,マークシート式問題で「思考力・判断力・表現力」を評価する工夫・改善がなされる.本稿では,まず大学入学共通テストのねらいを概観したうえで,「思考力・判断力・表現力」のなかでも明確な定義が難しい思考力に焦点を当て,多肢選択式の共通試験において扱うことのできる思考力とはどのようなものかを吟味した.そして,各科目での論理的思考や批判的思考を支える関連づけの技能に着目し,それらを習得知識とともに活用する問題,あるいは思考の成果としての深い理解を問う問題を工夫することで,思考する力を間接的に評価する方向を示した.
2 0 0 0 OA 顔の魅力と認知
- 著者
- 大坊 郁夫
- 出版者
- The Society of Cosmetic Chemists of Japan
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.241-248, 2000-09-20 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
顔の魅力は, 身体的特徴にのみによって形成されるものではなく, 社会的脈絡や文化によって大きく影響される。多くの研究は, 進化によって築かれた民族的な同一性と顔の形態特徴によって顔の魅力が形成されることを示している。日本人は, 歴史的に外見的特徴自体および外見的美を表現することに抑制的であり, 包括的な平等さを重視する傾向がある。しかし, 外見美に無関心なわけではない。このような間接性を重視する文化は, 欧米, 他のアジアとも異なるものであり, 日本人の同調性, 集団主義的傾向を示唆する。外見美や化粧の効用の社会心理学的研究において, 個人の特徴や文化的影響を十分に踏まえる必要がある。さらに, 顔の形態特徴に加えてコミュニケーション性への視点も重要である。
2 0 0 0 OA 史料による樽前山の火山活動再考
- 著者
- 津久井 雅志
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 日本火山学会講演予稿集 2017 (ISSN:24335320)
- 巻号頁・発行日
- pp.68, 2017 (Released:2018-02-01)
2 0 0 0 OA 認知機能障害を呈する介護老人保健施設入所者の転倒の特徴について
- 著者
- 三谷 健 太田 恭平 小松 泰喜
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.261-266, 2009-08-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
【目的】身体機能,認知症の行動心理症候(以下BPSD:Behavioral and psychological Symptoms of Dementia)に注目し,入所者の転倒の特徴を明らかにすることを目的とした。【対象と方法】対象は介護老人保健施設2施設の入所者で,日常生活での移動手段が歩行であり,MMSE23点以下の入所者45名である。過去6ヶ月間の転倒歴,10m歩行速度,10m歩行歩数,Timed up and go test,Mini-mental State Examination,BPSDについて調査し,転倒群,非転倒群の比較検討を行った。【結果】転倒者18名,非転倒者27名であり,群間比較の結果,転倒群において10m歩行速度の低下,攻撃性の出現頻度が高い結果であった。【結論】入所者の転倒の特徴として,歩行速度の低下,BPSDの攻撃性の出現といった具体的な行動が問題となることが示唆された。身体機能,BPSD両側面からのアプローチを検討することが,今後の転倒予防につながる可能性がある。
2 0 0 0 OA 酸性雨・紫外線が農作物に及ぼす影響
- 著者
- 野内 勇
- 出版者
- 環境技術学会
- 雑誌
- 環境技術 (ISSN:03889459)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.7, pp.450-453, 1999-07-20 (Released:2010-03-18)
- 参考文献数
- 18
2 0 0 0 パーネルの亡霊ージョイスとイェイツの場合
- 著者
- 戸田 勉
- 出版者
- 山梨英和大学
- 雑誌
- 山梨英和大学紀要 (ISSN:1348575X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.A69-A83, 2010
本稿では、「無冠の帝王」と呼ばれた19世紀アイルランドの政治家で、自治運動の指導者であったチャールズ・スチュアート・パーネルの死が、アイルランドを代表する二人の作家ジェイムズ・ジョイスとW・B・イェイツにどのような影響を及ぼしたかについて、ゴシック的な観点を軸にして考察した。 ジョイスは、「パーネルの亡霊」というエッセイを発表し、パーネルを裏切ったアイルランド人を激しく糾弾したが、その後彼の作品からはパーネル主義が徐々に影を潜め始める。この変化は、アイルランドにおけるかつての共同体の崩壊をジョイスが認識したことと深く関わる。その認識から、ジョイスはパーネルを脱神格化・世俗化させる方向に向かった。 一方、イェイツは、貴族主義の模範としてパーネルを崇拝し、彼の死に気高い犠牲の精神を見た。イェイツは、パーネルの亡霊や葬儀を歌い、彼の不在を嘆き続けるが、最後には、祝祭的な詩によってパーネルを賛美する。ジョイスと同じように、共同体の崩壊を感じ取ったイェイツではあるが、彼はそこから失われたものの再構築に向かう。そのため、イェイツはパーネルの死を儀式化し、神話化する必要があった、と結論付けた。
2 0 0 0 OA [新吉原略説并元吉原町起立]
- 著者
- 仏庵 [編]
- 巻号頁・発行日
- 1800
2 0 0 0 IR 言語的思考と外国語の学習と発達 (特集 第二言語習得の問題)
- 著者
- 西口 光一 ニシグチ コウイチ Nishiguchi Koichi
- 出版者
- ヴィゴツキー学協会
- 雑誌
- ヴィゴツキー学 (ISSN:13454900)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.27-33, 2006-07
In recent years Vygotskian theory on the development of thinking and speech have been attracting attention of second language researchers and teachers. However,nobody has ever theorized second language acquisition or development in the spirit of Vygotskian theory. In this paper I first paves the ground by summarizing Vygotsky's theory on the development of verbal thinking and also his discussions on foreign language learning/acquisition. Then I propose a theory of second language development from Vygotskian perspective
2 0 0 0 OA 情報活用の実践力に見る児童および教師の問題解決過程の認識構造および評価の相違について
- 著者
- 奥木 芳明 古田 貴久
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.185-192, 2009-10-10 (Released:2016-08-06)
- 参考文献数
- 10
本研究では,情報活用能力の1つである情報活用の実践力に関連して,教師と学習者の問題解決過程に対する認識構造および評価の相違について検討した.教師と児童の実践力を測る質問紙を作成し,小学校高学年の「総合的な学習の時間」の授業において調査を行った.因子分析および共分散構造分析の結果,教師の認識では個々の問題解決活動は互いに結びついているが,児童の認識構造では活動間の関連性があまり意識されていないことが示唆された.また,児童は,内容をまとめたり考察する活動において,教師よりも高めに達成度を自己評価した.
2 0 0 0 写本テクスト学の構築に向けて-中世フランス抒情詩の諸相
本研究課題は,2005年9月に開催されるボルドー大学での「第8回国際オック語オック文学研究集会」(AEIO)で行なう発表に向けて,「写本テクスト学」の実践として,テクスト設定に問題をはらむトルバドゥールの1作品の研究を,収集したマイクロフィルムをもとに試みるものであった。具体的には,ラインバウト・ダウレンガの,Non chantで始まる作品について,とくにその27行目にひそむ問題をテクスト校訂の立場から,各写本の読みを検討し,従来提出されることのなかった私なりの読みを行なったのである。いくつかの写本によればla amorと,母音接続(イアチュス)を容認せざるをえなかった部分を,あらたにトルヴェールのコーパスをも含めた他の作品のコンテクストを徹底的に探索することによって,cel amor que…という読みを導き出したのであった。この内容を実際にボルドー大学において発表したところ,これを傍聴していたローマ大学のエンリコ・ジメイ氏より,同氏の母音接続にかんする詳細な研究の一端を知ることができた。それによると,私の例では,定冠詞laと,アクセントのない母音a-morとの母音接続であったが,この場合は,やはりイアチュスを認めるには不自然であり,写本伝承の過程でテクストが変質したものと考えることができる。ジメイ氏の調査はある程度は徹底的なものではあるが,コーパスとしてデ・リケールのアンソロジーを用いているために,各写本の読みの違いは考慮されていない。私のいう「写本テクスト学」の必要性をあらためて痛感している。この立場から,ラインバウトの同作品におけるセニャル(仮の名)の研究を,トルヴェールのクレテイアン・ド・トロワの一作品と比較し,写本間におけるテクストの異動の重要性に着目した(大学院研究紀要における日本語論文)。また,ラインバウト・ダウレンガの作品とは別に,ペイレ・カルデナルの「寓話」一篇のあたらしいテクストと解釈を提示してみた(リケッツ教授献呈記念論文集)。ここでは,従来検討されてこなかった,アルスナル写本の読みをも考慮したテクスト設定を試みた。
2 0 0 0 IR 日米安保条約の強化と朝日新聞 : 社説にみる日本防衛論(4)
- 著者
- 水野 均 ミズノ ヒトシ Hitoshi MIZUNO
- 雑誌
- 千葉商大紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.67-87, 2005-06-30
『朝日新聞』は1970年に日米安保条約が自動延長された後,「極東の範囲の明確化」や「事前協議制度の強化」等を,「日米安保条約を容認するための条件」として主張し続けた。しかし同紙は,それらを実現するための具体案を提示することはなかった。他方の日本政府は,「日本が安保条約で対米防衛義務を負わない代償としての対米便宜供与を続ける」形で日米安保条約を運用する方法を採り,同条約の自動延長が繰り返された。さらには世論のみならず,社会党等安保条約反対勢力の中からも,安保条約の「条件付き容認」論が提示されるようになった。しかし,その過程で日米両国間の防衛協力は,期限を延長したのみならず,適用範囲も日本の領域を越えて太平洋地域に拡大し,さらには部隊の共同作戦運用といった内容面でも強化されていった。それは日米安保条約が,「極東の範囲」や「事前協議」制度の対象及び拒否権に関わる曖昧さを残している以上,当然の帰結であった。