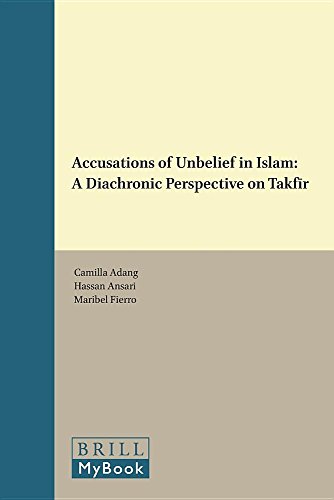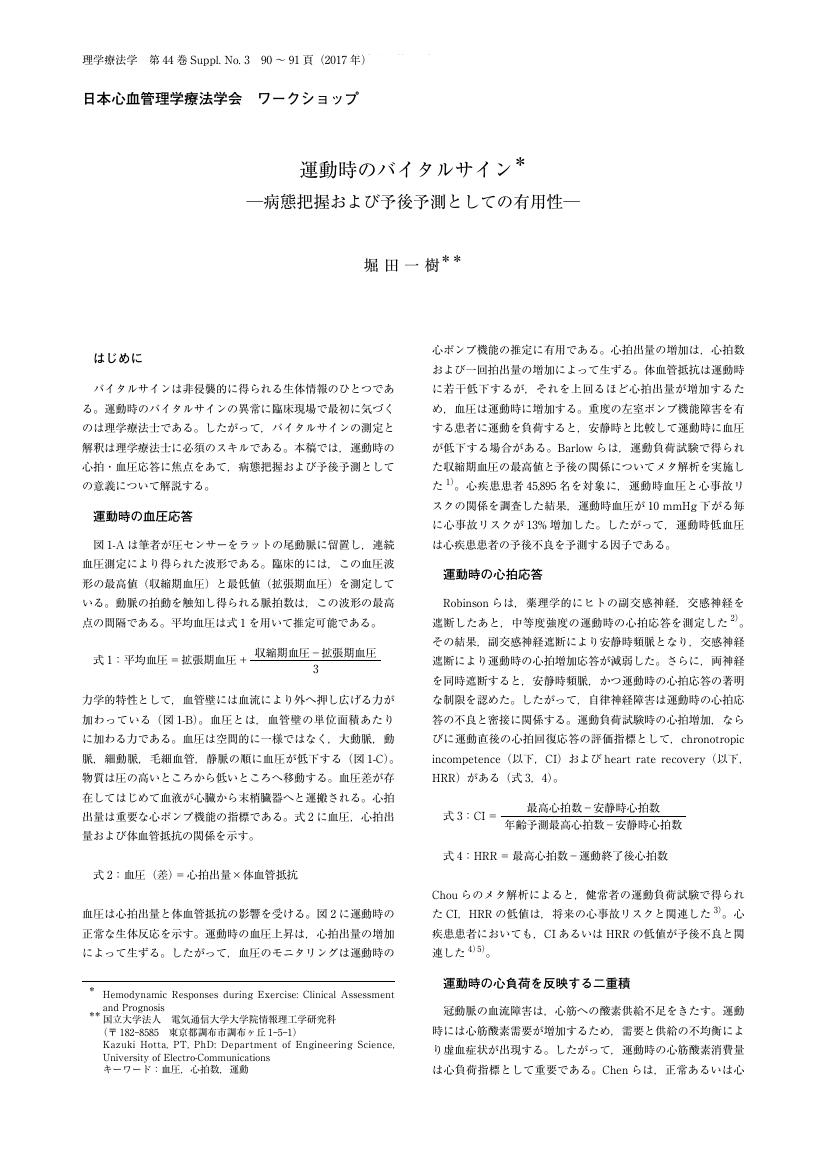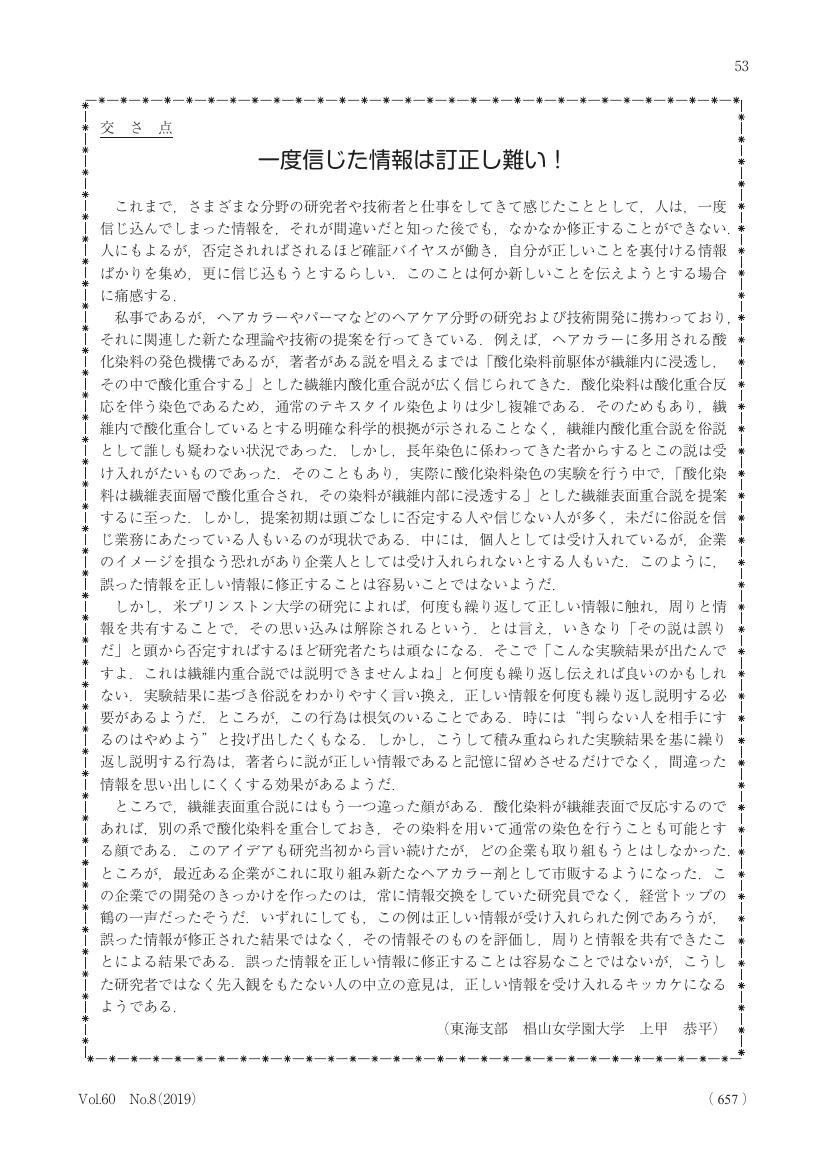- 著者
- 川口 久雄
- 出版者
- 金沢大学
- 雑誌
- 日本海域研究所報告 (ISSN:0287623X)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.117-148,図巻末6p, 1972-03
2 0 0 0 OA AI時代の医療職業務
- 著者
- 木村 通男
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.9, pp.882-886, 2018 (Released:2018-09-01)
- 参考文献数
- 4
今回のAIブームは実は3回目で、2回目の80年代の時にも、医療職はAIに取って変わられるのではと言われた。 2回目のブーム以後、生き残ったシステムは画像認識、音声認識などで、処理能力、データの細緻化により、いま、花を咲かせつつある。 今回の技術的ブレークスルーはディープラーニングであるが、それによる診断には、根拠を示すことが難しい。問題はそれを患者が受け入れるかである。 一方、病気は患者の個性そのものであり、個性に対応することはまさに創造的な行為なのである。 これを念頭に、機械にできることは機械に任せ、新しい職能を常に探せ、と、前回のブームの際、30年前に賢者はすでに記している。
- 著者
- edited by Camilla Adang ...
- 出版者
- Brill
- 巻号頁・発行日
- 2016
2 0 0 0 OA 代用電荷法と数値等角写像に関する研究
2 0 0 0 神奈川県内でのキマダラカメムシの新分布と食糞
- 著者
- 田口 正男
- 出版者
- ニューサイエンス社
- 雑誌
- 昆虫と自然 (ISSN:00233218)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.29-31, 2017-02
2 0 0 0 OA 筋腱移行部及び腱骨移行部刺激の臨床における有用性
- 著者
- 祝 広孝 大通 恵美 大城 広幸 猿渡 勇 森川 綾子 野中 昭宏 古野 信宏 近藤 真喜子 坂田 光弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.Cb0480, 2012 (Released:2012-08-10)
【はじめに、目的】 我々は第44回学術大会において骨格筋の筋腱移行部に軽い圧迫刺激を加えることにより筋緊張抑制効果が得られることを報告した.同様の効果が腱骨移行部への刺激によっても得られることが確認され,それらを組み合わせて「筋腱移行部及び腱骨移行部刺激:Muscle tendon junction and Enthesis stimulation」(以下,MES)と称し臨床に用いている.MESは速効性に優れ,評価や治療場面で広く応用できる手技である.そこで今回,MESの実施方法を紹介すると共に足関節背屈可動域と肩関節外旋可動域及び屈曲可動域に対し前者は腱骨移行部,後者は筋腱移行部を刺激部位としてMESの効果を検証し,MESの臨床における有用性について報告したい.【方法】 MESの実施方法骨格筋の筋腱移行部もしくは腱骨移行部に対し,軽い圧迫刺激(圧迫力は筋腱移行部で1kg-3kg,腱骨移行部では0.5kg程度)を加える.筋緊張抑制に必要とする刺激時間は1秒-5秒程度であるが,関節可動域練習や筋力増強練習時においては刺激を持続しながら行うと効果的である. 対象検証1:足関節背屈可動域では成人15名(男性8名,女性7名,年齢31.9±9.0歳)30肢を対象に,検証2:肩屈曲・外旋可動域では成人17名(男性10名,女性7名,年齢31.6±8.7歳)のなかで,肩屈曲制限があり尚且つ外旋可動域に制限を有した24肢(右11肢,左13肢)を対象とし,各々MESを行うMES群とMESを行わないControl群(以下C群)に分けた(検証1:MES群15肢,C群15肢/検証2: MES群12肢,C群12肢).方法検証1)足関節背屈可動域へのMES効果(腱骨移行部を刺激部位に選択):MES実施肢位は仰臥位,下肢伸展安静位にて後脛骨筋停止腱の腱骨移行部(舟状骨後縁)及び短腓骨筋停止腱の腱骨移行部(第5中足骨底後縁)に対し,触れる程度の触圧刺激を同時に5秒間加え,MES実施前後で股・膝関節90°屈曲位での自動背屈可動域を1°単位で測定.C群についてはMES実施時の肢位にて5秒間の休憩を入れ休憩前後の角度を測定した.検証2)肩屈曲及び外旋可動域へのMES効果(筋腱移行部を刺激部位に選択):MES群における刺激肢位は仰臥位.肩屈曲120°-130°位で大円筋線維が広背筋停止腱に停止する筋腱移行部(腋窩後壁前面)に対し軽い圧迫刺激を5秒間実施.MES前後で端坐位での肩屈曲可動域を,仰臥位にて肩外転90°,肘屈曲90°での肩外旋可動域を1°単位で各々測定した.C群に関しては検証1と同様.統計処理には検証1,検証2共にMES(C群:休憩)前後の角度変化の比較にはWilcoxonの符号付順位和検定を,MES群とC群の角度改善率の比較にはWilcoxonの順位和検定を用いた.【倫理的配慮、説明と同意】 全ての対象者には事前に本研究の趣旨を十分に説明し,同意を得た上で実施した.【結果】 検証1)C群においては休憩前後の背屈角度に有意な差は認められなかったが,MES群においては,MES前24.8±7.4°,MES後28.4±6.4°と有意な差を認めた(P<0.01).またC群との角度改善率の比較においてもMES群で有意な差(P<0.01)が認められた.検証2)C群においては休憩前後の肩外旋可動域及び屈曲可動域の角度に有意な差は認められなかったが,MES群においては,肩外旋可動域でMES前74.3±7.8°,MES後86.6±7.0°,肩屈曲可動域でMES前144.8±6.9°,MES後154.5±7.3°と両可動域で有意な差を認めた(P<0.01).またC群との角度改善率の比較においても外旋・屈曲可動域各々でMES群に有意な差が認められた.【考察】 ストレッチングの筋緊張抑制効果として知られるIb抑制は筋腱移行部に存在するゴルジ腱器官(以下GTO)からのインパルス発射に起因する.GTOはその発射機序より筋腱移行部の圧迫刺激による変形によってもインパルスを発射する可能性があり,大円筋の筋腱移行部への刺激による可動域改善にはIb抑制の関与が推測される.腱骨移行部刺激による効果については,多くの筋が腱骨移行部またはその間近まで筋線維を有することが知られており,それらの筋においてはGTOの働きが関与していると思われる.しかし今回刺激部位とした後脛骨筋や短腓骨筋停止腱の腱骨移行部については筋線維の存在は確認されておらず,今後その機序の解明に努めていきたい.【理学療法学研究としての意義】 MESは解剖学的知識と触察技術を用いて触れる行為そのものに目的を持たせた手技であり,本研究によって理学療法士の技術向上に寄与できればと考える.
- 著者
- 豊田 一恵 谷本 光生 松本 昌和 合田 朋仁 堀越 哲 富野 康日己
- 出版者
- 順天堂医学会
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.387-394, 2011-08-31 (Released:2014-11-11)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1 1
目的: オウギ (黄蓍;astragali radix) は, マメ科のギバナオウギ, ナイモウオウギの根から調製される生薬で, 血圧低下・利尿・肝保護・免疫増強・抗菌・強壮・鎮静作用などを有し, 種々の漢方薬に調合されている. 慢性腎不全患者において, オウギ投与により血清クレアチニン値の低下することが報告がされている. しかし, そのメカニズムは十分には解明されていない. また, 腎不全では, 酸化ストレスマーカーの一つである一酸化窒素合成酵素 (NOS) が腎組織で過剰発現しており, 腎不全の進展・増悪因子の一つとして知られている. 今回, 腎不全モデルである5/6腎摘ラットを用い, オウギ投与による腎機能ならびに腎組織におけるNOSの発現抑制効果について検討した. 方法: 8週齢で5/6腎摘出術を施行した雄性SDラットを, 12週齢から12週間 (1) オウギ10g/kg体重/日を混餌投与したオウギ投与群 (n=5), (2) 未治療群 (n=5) の2群に分け, (3) 非腎摘出群 (n=5) を対照とした. それぞれの群に対して, 尿中アルブミン/クレアチニン比 (ACR), 血清クレアチニン, 血中尿素窒素 (BUN), クレアチニンクリアランス (CCr), 尿中8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) を測定した. また, 24週齢で腎組織の糸球体硬化指数 (Sclerosis Index) をPAS染色により算出し, 血管内皮型NOS (eNOS), 誘導型NOS (iNOS) および酸化ストレスマーカーであるニトロチロシンの発現を腎免疫組織染色により検索した. 結果: CCrは, オウギ投与群で有意な改善が認められた (p<0.05). 血清クレアチニン, BUNは, オウギ投与群で未治療群と比較し低下傾向がみられた. しかし, ACRや尿中8-OHdGには有意な差はみられなかった. オウギ投与群の腎糸球体硬化指数 (Sclerosis Index) は, 未治療群に比べ有意な低下が認められた (p<0.0001). また, オウギ投与群におけるeNOS, iNOSおよびニトロチロシンの発現は, 未治療群に比べ有意な低下が認められた (p<0.0001). 結論: オウギは, 腎におけるNOS (eNOS, iNOS) およびニトロチロシンの発現抑制を伴って, 腎糸球体硬化病変の進展を抑制する可能性が示された.
- 著者
- Daisuke Nakamura Keisuke Yasumura Hitoshi Nakamura Yutaka Matsuhiro Koji Yasumoto Akihiro Tanaka Yasuharu Matsunaga-Lee Masamichi Yano Masaki Yamato Yasuyuki Egami Ryu Shutta Yasushi Sakata Jun Tanouchi Masami Nishino
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.2, pp.313-319, 2019-01-25 (Released:2019-01-25)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2 19
Background: There are few reports about the differences between drug-eluting stents (DES) and bare metal stents (BMS) in neoatherosclerosis associated with in-stent restenosis (ISR), so we compared the frequency and characteristics of neoatherosclerosis with ISR evaluated by optical coherence tomography (OCT) in the present study. Methods and Results: Between March 2009 and November 2016, 98 consecutive patients with ISR who underwent diagnostic OCT were enrolled: 34 patients had a BMS, 34 had a 1st-generation DES, and 30 had a 2nd-generation DES. Neoatherosclerosis was defined as a lipid neointima (including a thin-cap fibroatheroma [TCFA] neointima, defined as a fibroatheroma with a fibrous cap <65 µm) or calcified neointima. As a result, lipid neointima, TCFA neointima and calcified neointima were detected in 39.8%, 14.3%, and 5.1%, respectively, of all patients. The frequency of neoatherosclerosis was significantly greater with DES than BMS (48.4% vs. 23.5%, P=0.018). The minimum fibrous cap thickness was significantly thicker with DES than BMS (110.3±41.1 µm vs. 62.5±17.1 µm, P<0.001). In addition, longitudinal extension of neoatherosclerosis in the stented segment was less with DES than BMS (20.2±15.1% vs. 71.8±27.1%, respectively, P=0.001). Conclusions: OCT imaging demonstrated that neoatherosclerosis with ISR was more frequent with DES than BMS and its pattern exhibited a more focal and thick fibrous cap as compared with BMS.
2 0 0 0 IR 大和新庄藩の陣屋と桑山氏の改易に伴うその跡地利用
- 著者
- 土平 博
- 出版者
- 奈良大学
- 雑誌
- 奈良大学紀要 = Memoirs of Nara University (ISSN:03892204)
- 巻号頁・発行日
- no.47, pp.55-63, 2019-02
本報告は、桑山氏によって築かれた陣屋ならびに陣屋町の形態をみたうえで、桑山氏改易後の史料を検討しながら、永井氏の新庄について検討し、新庄陣屋と「町」の形態について明らかにしていくことが目的である。桑山氏新庄藩の陣屋および侍屋敷の配置を絵図、地籍図、空中写真等を用いて地図上で復原する作業を行い、同氏改易後の陣屋および侍屋敷の扱いについて、史料分析を通じて考察した。桑山氏は陣屋・侍屋敷・町屋敷を計画的に配置して一体化させた陣屋町をプランとして考えていたことが理解できる。しかし、桑山氏改易後に入封した永井氏は、新庄に陣屋を構えておらず、それに付帯していた侍屋敷も取り壊されていたと考えられる。その跡地は農地へと転換された。その結果、桑山氏による計画的な町屋敷のみが残り、周辺地域の在郷の町として存続していったことが明らかとなった。
- 著者
- 亘 悠哉 船越 公威
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.331-334, 2013 (Released:2014-01-31)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
リュウキュウテングコウモリMurina ryukyuanaによる日中ねぐらとしての枯葉の利用を徳之島において3例記録した.これにより,これまでにほとんど情報のなかった本種の自然条件下でのねぐら利用の一端が明らかになった.利用していた枯葉の樹種は,イイギリIdesia polycarpa,アオバノキSymplocos cochinchinensis,フカノキSchefflera heptaphyllaであり,これらに共通する特徴として,1枚1枚の葉が大きく,枯れると椀状に変形すること,また葉のつき方が放射状で,枝折れにより枝先の葉が枯れると複数の葉が合わさって群葉状になるという点が挙げられた.同属のコテングコウモリで記録されている幅広い日中ねぐら場所の利用形態を考慮すると,本種も枯葉以外の様々なタイプのねぐらを利用している可能性は十分に考えられる.今後,今回のような観察情報を蓄積することともに,行動の追跡調査などを進めることで,本種のねぐら利用の全体像の把握につながるであろう.
- 著者
- 〓谷 信三 松村 泰成 山下 晋三 松山 奉史 山岡 仁史
- 出版者
- THE SOCIRETY OF RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGYY, JAPAN
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.39-44, 1984
天然ゴム (NR) 及びイソプレンゴム (IR) の純ゴム硫黄架橋体を作製し, 溶剤抽出により精製を行った. この架橋体に空気中, 室温でγ線を照射 (0-20Mrad) して劣化した試料を引張試験, 膨潤試験, 全反射赤外吸収スペクトルなどにより検討した. その結果, (1) NR架橋体, IR架橋体ともに, 数 Mrad のγ線照射により引張強さ (<i>T<sub>B</sub></i>) は著しく低下した. (2) <i>T<sub>B</sub></i>の低下は, 応力-ひずみ曲線の変化から, 照射によって伸長結晶化が起こりにくくなったためである. (3) 20Mrad までの照射量では, 中変形領域における応力, 例えば50%伸長時の応力 (<i>M</i><sub>50</sub>) の変化は顕著ではなく, 硬さと網目鎖濃度の変化も小さかった. (4)モノスルフィドとポリスルフィドの架橋構造の違いは, <i>M</i><sub>50</sub>の照射による変化挙動に認められたが, その差は大きいとはいえない. (5)以上の結果から, シス-1, 4-ポリイソプレンは照射により, 分解と架橋反応がほぼ同程度に起こるものと考えられる, などが明らかとなった. 伸長結晶化阻害は, 照射により構造の乱れが起こったためと考えられるが, その詳細についてはいまだ結論できなかった.
- 著者
- Alejandro DATAS Daisuke HIRASHIMA Katsunori HANAMURA
- 出版者
- The Japan Society of Mechanical Engineers and The Heat Transfer Society of Japan
- 雑誌
- Journal of Thermal Science and Technology (ISSN:18805566)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.91-105, 2013 (Released:2013-03-19)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 12 21
We present the numerical simulation, using the finite difference time domain (FDTD) method, of the radiative heat transfer between two thin SiC slabs. We aim to explore the ability of the FDTD method to reproduce the analytical results for the Surface Phonon Polariton (SPhP) assisted near field radiative energy transfer between two SiC slabs separated by a nano/micro-metric vacuum gap. In this regard, we describe the key challenges that must be addressed for simulating general near-field radiative energy transfer problems using the FDTD method. FDTD is a powerful technique for simulating the near-field radiative energy transfer because it allows simulating arbitrary shaped nano-structured bodies, like photonic crystals, for which an analytical solution is not readily obtained.
2 0 0 0 OA マメタニシの解剖
- 著者
- 板垣 博
- 出版者
- The Malacological Society of Japan
- 雑誌
- 貝類学雑誌 (ISSN:00423580)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.169-_180-3_, 1965-12-30 (Released:2018-01-31)
マメタニシの殻形は雌雄によって差はないが雄のものがやや細長である.歯舌の1列は中歯(1コ), 側歯(2コ), 内縁歯(2コ), 外縁歯(2コ)からなり, それぞれの歯の小鉤には個体差がある.胃は2部からなり, 前部の方が広くて中央に胃楯があり, 後部には晶体と晶体嚢がある.陰茎には鞭状体があるが, その作用は不明である.陰茎基部の皮下には長い盲管があり, その開口は鞭状体の先端にある.この盲管内に白色粘液を含み, その中に円形と洋なし状の細胞がある.陰門は産卵門とは遠く離れ, 陰門は外套腔の奥に, 産卵門は肛門の少し後方に開く.中枢神経系は9神経節, 足神経系は2神経節からなる.血管は発達が悪いが, 血とうはよく発達している.排出孔は直接に外套腔の奥に開き, 尿管はない.
2 0 0 0 OA コレラタケによる食中毒
- 著者
- 村田 宗茂
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.414-415, 1987-10-05 (Released:2009-12-11)
2 0 0 0 OA 運動時のバイタルサイン
- 著者
- 堀田 一樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl.3(第52回日本理学療法学術大会(千葉))
- 巻号頁・発行日
- pp.90-91, 2017 (Released:2017-10-20)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 一度信じた情報は訂正し難い!
- 著者
- 上甲 恭平
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.8, pp.657, 2019-08-25 (Released:2019-08-25)
2 0 0 0 OA フランスの公文書管理行政 : 文書専門職員の派遣を中心に
- 著者
- 川西晶大
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.819, 2019-04