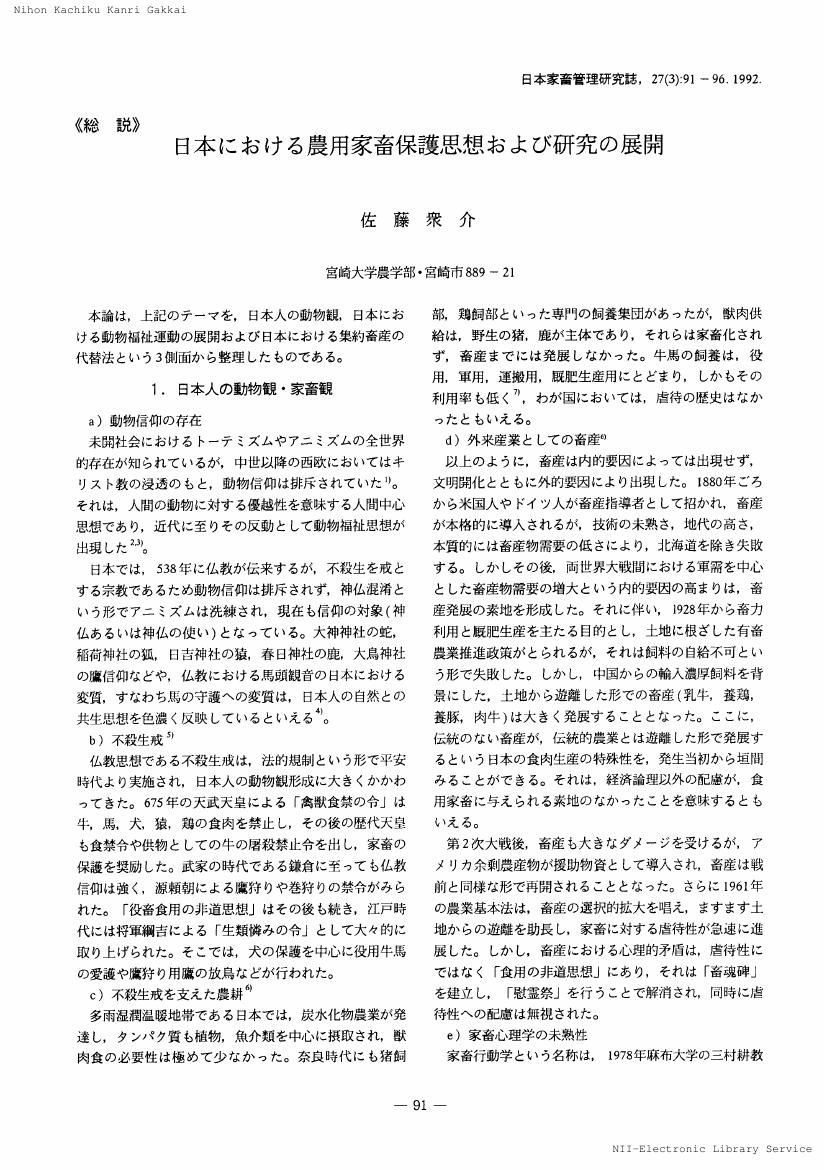2 0 0 0 OA 9097 教科体育運営のための基礎調査に関する一考察(9.体育方法,I.一般研究)
- 著者
- 佐久間 和彦 高橋 亮三 勝亦 紘一
- 出版者
- 社団法人日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号
- 巻号頁・発行日
- no.29, 1978-12-17
2 0 0 0 IR 人環フォーラム No. 17
- 出版者
- 京都大学大学院人間・環境学研究科
- 雑誌
- 人環フォーラム (ISSN:13423622)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, 2005-09-30
<巻頭言>明治文章小史 / 渡辺実<インタビュー>学問の宗教的背景 / 上山安敏, 聞き手 高橋義人<特集 : 関西三都 ― その近代化>京都 ― 中庭を忘れた西洋館 / 伊從勉<特集 : 関西三都 ― その近代化>大阪 ― 大縮尺地図にみる大阪の近代化 / 山田誠<特集 : 関西三都 ― その近代化>神戸 ― 大震災と新空港 / 松島征<リレー連載 : 環境を考える>京都議定書遵守の意味 / 阪本浩章, 西井正弘<サイエンティストの眼>生活習慣病としての糖尿病、しかし… / 林達也<知の息吹>"青"に思う地球科学 / 大西将徳<社会を斬る>法律・CSRにより環境を守る / 小畑史子<フロンティア>はねかえり係数の起源を探る / 國仲寛人<フロンティア>捕食によって進化する餌生物の色彩多型 / 繁宮悠介<奈文研の散歩道>古建築の妙 ― 見える建築、見えない建築 / 窪寺茂<文学の周辺>「書記」を学ぶということ ― 北朝文化の一側面 / 道坂昭廣<フィールド便り>映画にみる戦前の米国日系移民 / 板倉史明<フィールド便り>吉田南構内のカスミサンショウウオの生態 / 松井正文<書評>加藤幹郎著『「ブレードランナー」論序説 映画学特別講義』 / 田代真<書評>Takako SHIKAYA, Logos und Zeit / 渡邊二郎<書評>山梨正明著『ことばの認知空間』 / 鍋島弘治朗<書評>廣野由美子著『批評理論入門 ― 「フランケンシュタイン」解剖講義』 / 福岡忠雄<書評>三原弟平著『ベンヤミンと女たち』 / 徳永恂<人環図書><瓦版><コラム>人工言語の夢と挫折 / 東郷雄二
2 0 0 0 呼吸法の違いが全身反応時間に及ぼす影響 ―剣道の打突からの検討―
先行研究において,反応時間は呼吸相による影響を受けることが明らかにされており,特に呼気相に局所的反応時間および全身反応時間が高まることが報告されている。つまり,この呼吸相と反応時間の関係は,反応時間がパフォーマンスに影響する競技においては重要な役割を担うことになる。剣道は局所および全身の反応時間を高める必要がある代表的な競技の1つである。全身反応時間は呼吸相のうち,呼気相に高まることが分かっている。しかしながら,剣道の打突反応時間における呼吸相の影響はいまだ明らかではない。これを明らかにすることで,剣道の試合中や練習中に呼吸をどのようンにコトロールすればよいのかが明確になり,剣道の競技力向上の一助になると考えられる。そこで、本年度は呼吸相が剣道における打突反応時間に影響を及ぼすかどうかを検討するために,剣道有段者の大学剣道部員を対象として,自由呼吸,統制呼吸および息止め中の打突反応時間を評価する実験を実施した。その結果,自由呼吸および統制呼吸において,呼気相と吸気相の打突の反応時間に有意な差は認められなかった。一方,膝が動き出す時間と剣先が動き出す時間のピーク値については,統制呼吸時と比較して息止め時で有意に低値を示した。このことは息を止めている状態がもっとも早く反応できる可能性があることを示している。しかしながら,実際に竹刀が目標に当たる時間については,試技間に有意な差は認められなかった。一方で,自由呼吸は,吸気相および呼気相いずれにおいても,統制呼吸よりも剣先の反応時間が早かった。これは呼吸の仕方が少なからず反応時間に影響を及ぼすことを示唆している。本研究では,呼吸相が剣道の打突反応時間へ明確に影響を及ぼすことを明らかにはできなかったが,少なくとも息を止めている状態において反応時間が早くなること,また呼吸の仕方が反応時間に影響を与えることを示唆する結果が得られた。
2 0 0 0 在日朝鮮人韓国人ハンセン氏病患者同盟結成と年金問題 (らい予防法廃止20年・ハンセン病国賠訴訟勝訴15年を迎えて) -- (全体会 交流集会 全療協のたたかい : 当事者運動から学ぶ)
- 著者
- 金 貴粉
- 出版者
- ハンセン病市民学会 ; 2005-
- 雑誌
- ハンセン病市民学会年報
- 巻号頁・発行日
- pp.114-120, 2016
2 0 0 0 松平清康再考
- 著者
- 平野 明夫
- 出版者
- 愛知県総務部法務文書課県史編さん室
- 雑誌
- 愛知県史研究
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.33-43, 2014-03-31
- 著者
- 土谷 信高 西岡 芳晴 小岩 修平 大槻 奈緒子
- 出版者
- The Geological Society of Japan
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, pp.S159-S179, 2008
花崗岩質大陸地殻の形成機構を明らかにすることは,地球の進化過程の解明に通じる重要な研究課題である.本案内書では,北上山地の前期白亜紀アダカイト質累帯深成岩体と古第三紀浄土ヶ浜流紋岩類の主要な岩体について,岩石学的特徴とその成因について述べた.これらのアダカイト類の岩石化学的多様性の成因には,スラブメルトとマントルおよび下部地殻との反応の程度の差が主要な役割を果たしていたと考えられ,スラブメルトの発生から上昇・定置に至る現象の解明に重要な位置を占めると考えられる.
2 0 0 0 IR サッカーPK戦におけるゲーム理論上の最適戦略とプロの戦略との差異に関する考察
- 著者
- 小泉 昂也 折原 良平 清 雄一 田原 康之 大須賀 昭彦 Takaya KOIZUMI Ryohei ORIHARA Yuichi SEI Yasuyuki TAHARA Akihiko OHSUGA
- 出版者
- 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム (ISSN:18810225)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.9, pp.1363-1371, 2018-09-01
人や企業は様々な条件下で最適な行動を取るのだろうか.取らないのであればそれはなぜか.その原因を求めることは,実際の個人・企業等の理解を大きく助ける.また,ゲーム理論はスポーツや経済学そしてその他の社会科学の理解に大きく関わってきた.本研究は比較的データが集めやすく混合戦略を適用できるサッカーのPK戦に注目し,独自の確率を考慮した利得表を作成した.その利得表を用いてPK戦におけるキッカーの最適戦略を求め,最適戦略と実際の戦略とのズレを明らかにした.そのズレの原因を求める為にデータセット内の各データ項目についての確率分布を比較するというアプローチをした.データはインターネット動画サイトより収集した,プロ選手による2001年〜2017年の間の世界各国のPK戦150試合(計1539人分)を使用した.実験結果として,最適戦略と実際の戦略との間にズレが存在することが分かった.またそのズレには国籍・スコア差の関与が示唆された.その結果から,サッカーPK戦における最適戦略と実際の戦略との間におけるズレの原因を推定した.本手法はスポーツ分野以外への応用も期待できる.
2 0 0 0 OA 恋愛内で問題となる強い束縛に関する基礎的・応用的研究
恋愛内で生じる束縛が関係性に及ぼす影響について、束縛の強度の違いという観点から検討した。研究1では項目反応理論を用いて,「弱い束縛」因子と「強い束縛」因子からなる束縛尺度の開発を行った。束縛尺度は概ね許容できる信頼性と妥当性を示した。開発した束縛尺度を用いて,研究2では弱い束縛と強い束縛が恋愛関係に及ぼす影響について検証した。分析の結果,弱い束縛は恋愛関係にポジティブな影響を及ぼすものの,強い束縛はネガティブな影響を及ぼす可能性が示唆された。恋人に対して生じる支配的な行動の1つである束縛が支配であると捉えられにくい理由として,束縛の強さによってその影響が逆方向であるためであることが示された。
2 0 0 0 OA 日本における農用家畜保護思想および研究の展開
- 著者
- 佐藤 衆介
- 出版者
- 日本家畜管理研究会(現 日本家畜管理学会)
- 雑誌
- 日本家畜管理研究会誌 (ISSN:09166505)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.91-96, 1992-02-10 (Released:2017-10-03)
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 畜産における動物福祉思想の展開
- 著者
- 佐藤 衆介
- 出版者
- 公益社団法人 日本畜産学会
- 雑誌
- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.9, pp.978-982, 1992-09-25 (Released:2008-03-10)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 搾乳牛の行動による低投入型放牧酪農の家畜福祉性評価
- 著者
- 佐藤 衆介 西脇 亜也 大竹 秀男 篠原 久
- 出版者
- 日本家畜管理学会
- 雑誌
- 日本家畜管理学会誌 (ISSN:13421131)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.95-104, 1999-03-03 (Released:2017-10-03)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
岩手県の低投入型放牧酪農家2戸(N牧場、K牧場)の家畜福祉性を、主として乳牛の行動の調査結果に基づき、乳生産や疾病記録を加味して評価した。両牧場とも急傾斜地にあり、面積はN、K牧場とそれぞれ46ha、40haで、改良草地放牧地、野草林間放牧地および採草地からなっていた。N牧場には、加えて採草放牧兼用地があった。両牧場ともまき牛繁殖で、放牧地での自然分娩であった。N牧場では2ヵ月齢までの自然哺乳、K牧場では3ヵ月齢まで人工哺乳であった。両牧場ともに、無施肥による放牧地管理をし、フスマやビートパルプといった農産副産物の他には、濃厚飼料は無給与という低投入型で、牛乳を4,000kg/頭/年程度生産していた。N牧場の乳牛では、全行動レパートリーが出現したが、6月の食草・樹葉摂食行動は1日当たり平均11.0時間となり、それは過去の報告例の上限に近い水準であった。強制離乳子牛1頭に模擬舌遊び行動が観察された他には、異常行動は観察されなかった。K牧場では、人工哺乳のため母子行動は発現できなかった。K牧場での全摂食行動(食草、樹葉摂食、給与飼料摂食)は6月および7月には昼夜を問わず間断的にみられ、それぞれ1日当たり平均52時間および82時間であった。しかし、9月の食草・樹葉摂食時間は2.8時間と極端に短くなり、特にシバヘの依存が急激に低下した。N牧場では1994年の治療回数は2回で、捻挫と子牛の奇形による難産が理由であった。K牧場では1995年には下痢子牛3頭、後産停滞2頭、起立不能症1頭で治療を要した。両牧場とも、ウシの疾病率が低く、さらに異常行動は1頭を除き発現せず、行動レパートリーのほとんどが出現し、各行動時間配分も通常範囲内にあり、行動的にもほぼ正常であり、家畜福祉レベルは平均的な酪農家に比べて高いと判断された。しかし、N牧場では、強制離乳された子牛のストレス性の軽減が、K牧場では晩夏以降の草生の改善が、さらなる家畜福祉性改善に必要であると示唆された。日本家畜管理学会誌、34(3) : 95-104、1999 1998年4月16日受付1999年1月7日受理
2 0 0 0 OA お答えします
- 著者
- 前川 季義
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.2, pp.151, 1993-02-15 (Released:2011-09-20)
2 0 0 0 OA 疼痛疾患モデル一次性感覚ニューロンに認められるミトコンドリア異常の解析
マウスのwhisker padに10 mMカプサイシンを30分間作用させてTRPV1刺激を6日間行った。刺激と同側の三叉神経節の切片を作成して電子顕微鏡でミトコンドリアの観察を行った。なお、三叉神経節採取のタイミングは2, 4, 6日間投与完了の24時間後とした。2日投与では特に形態異常は認めなかったが、4日投与では主として小型の三叉神経ニューロンで内部構造の破壊を呈したミトコンドリアが確認された。しかし、6日間投与後にはニューロン内のミトコンドリア形態はほぼ正常であった。以上のことから、何らかの修復機構が作動するものと考えられた。細胞実験からミトファジーの機能が重要であることがわかった。
2 0 0 0 OA IIIF Curation Platformと「遊行縁起絵顔貌コレクション」
- 著者
- 鈴木 親彦
2 0 0 0 鯨蹄類(げいているい)の生物学
- 著者
- 栗原 望 曽根 啓子 子安 和弘
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.29, 2013
鯨蹄類(CETUNGULATA)は現生哺乳類の鯨偶蹄類と奇蹄類を含む単系統群である.本シンポジウムの開催により,鯨蹄類研究のさらなる発展を期待している. 演題1 キリン科における首の運動メカニズムの解明: 郡司芽久(東京大学大学院農学生命科学研究科)・遠藤秀紀(東京大学総合研究博物館) ほぼ全ての哺乳類は 7個の頸椎をもち,首が非常に長いキリンもその例外ではない.しかしキリンでは,第一胸椎が頸椎的な形態を示すことが知られている.本研究では,キリンとオカピの首の筋構造を比較し,キリン科の首の運動メカニズムの解明を試みた.調査の結果,首の根元を動かす筋の付着位置が,キリンとオカピで異なることがわかった.筋の付着位置の違いから,第一胸椎の特異的な形態の機能的意義について議論する.演題2 カズハゴンドウ(Peponocephala electra)に見られる歯の脱落 栗原 望(国立科学博物館動物研究部脊椎動物研究グループ) ハクジラ類の歯は一生歯性であり,生活史の中で必然的に脱落することはない.しかし,カズハゴンドウでは,複数の歯を失った個体が非常に多く見受けられる.歯の脱落傾向や歯の形状を調べたところ,歯の脱落が歯周病などの外的要因により引き起こされたのではなく,内的要因により引き起こされたことが示唆された.本種で見られる歯の脱落が示す系統学的意義について議論したい.演題3 偶蹄類ウシ科の歯数変異と歯冠サイズの変動性 夏目(高野)明香(NPO法人犬山里山学研究所,犬山市立犬山中学校) 哺乳類全般の歯の系統発生的退化現象から歯式進化の様々な仮説が提唱されてきているが,これらの仮説は分類群ごとの傾向を反映していない.そこで偶蹄類ウシ科カモシカ類の歯数変異と歯冠サイズの変動性を調べたところ,P 2は変異性が高い不安定な特徴や,計測学的解析から他臼歯とは異なる特徴的な形質を保有することが明らかとなった.この事から,カモシカ類において,下顎小臼歯数 2が将来の歯式として定着する可能性があると考えられる.演題4 愛知学院大学歯科資料展示室とカモシカ標本コレクション 曽根啓子(愛知学院大学歯学部歯科資料展示室) 展示室には1,300頭以上のカモシカの頭骨標本が保管されている.これらの標本は 1989年度から2011年度にかけて愛知県内で捕獲されたものであり,2001年から標本登録されている.この標本コレクションは展示室の収集物でも,研究上重要な位置を占めるものであり,カモシカの形態学・遺伝学的研究に活用されている.本発表では,カモシカの収集・保管活動を紹介するとともに,頭蓋と歯に認められた形態異常および口腔疾患 (歯周病 )について報告する.演題5 鯨蹄類における乳歯列の進化 子安和弘(愛知学院大学歯学部解剖学講座)「三結節説」と「トリボスフェニック型臼歯概念」の陰で忘れさられた「小臼歯・大臼歯相似説」に再度光をあてて,歯の形態学における乳歯と乳歯式の重要性を指摘する.最古の「真獣類」とされるジュラマイアの歯式,I5,C1,P5,M3/I4,C1,P5,M3=54から現生鯨蹄類の歯列進化過程における乳歯列の進化と咬頭配置の相同性について概観する.
- 著者
- 太田 泰弘
- 出版者
- 社団法人情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.10, 2012-10-01
- 著者
- 園部 俊晴 勝木 秀治 堤 文生
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.7, pp.245-249, 2002
- 参考文献数
- 10
今回の研究の目的は,二関節筋の多関節運動におけるメカニズムを理解することである。特に,同一筋内の部位別の筋活動比の違いに着目した。二関節筋のうち大腿直筋を用いて,健常成人10名(男性6名,女性4名)を対象とし,4つの遂行運動(大腿直筋が協同的に働く①膝関節伸展,②股関節屈曲,また協同的作用と拮抗的作用を同時に果たす複合運動として③膝関節股関節同時屈曲,(④膝関節股関節同時伸展)での大腿直筋の筋活動を調べた。大腿直筋の近位部から最遠位部までの4部位の表面筋電図を筋電計を用いて測定し,遂行運動間及び,各部位における筋活動の割合を比較した。その結果,筋断面積が最大となる中間電極位置では,遂行運動間に筋活動比の差が認められなかった。また,遂行運動①②のように大腿直筋が協同的な役割のみを果たすとき,その筋活動は同一筋内の部位による変化をほとんど認めなかった。しかし,④膝関節股関節同時伸展では股関節に近い近位電極部では筋活動は小さくなり,膝関節に近い最遠位電極部では筋活動は大きくなった。同様に,③膝関節股関節同時屈曲でもそれとは逆の現象が起こっていた。筋が,隣接する関節の協同作用と拮抗作用を同時に果たすという二関節筋の場合,その同一筋内において相反神経支配に似たメカニズムが存在することが示唆された。
2 0 0 0 IR 株式会社アダストリアの業績回復について : 2011~2016年の公開資料から
- 著者
- 三宅 敦
- 出版者
- 大阪産業大学学会
- 雑誌
- 大阪産業大学経営論集 (ISSN:13451456)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.59-70, 2017-02
Adastria Co., Ltd. is a SPA company representing Japan. Sales exceeded 200 billion yenfor the 1-year period ending February 2016. In recent years sales have grown, but operatingincome worsened for four years until 2014. However, for the two years of the most recentperiod ending February 2015 and February 2016, the company achieved a V-shaped recovery. Iconsider the causes from the standpoint of the company's public documents.