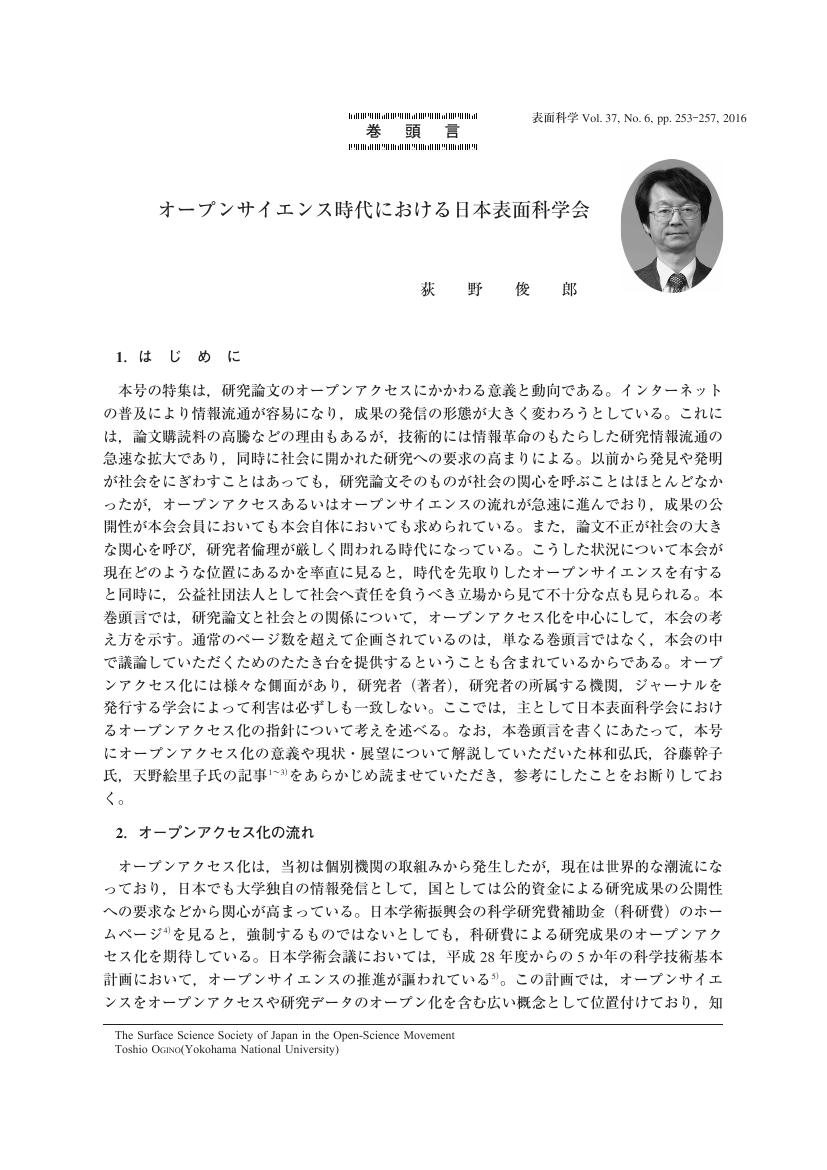1 0 0 0 OA 長期的なストレッチが筋力に及ぼす影響
- 著者
- 野末 琢馬 高橋 健太 松山 友美 飯嶋 美帆 渡邊 晶規 小島 聖
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0569, 2014 (Released:2014-05-09)
【はじめに,目的】ストレッチは可動域の拡大や組織の柔軟性向上,疲労回復効果などが報告されており,理学療法の現場においても多用されている。近年,ストレッチが柔軟性に与える影響だけでなく,筋力にも影響を及ぼすとした報告も散見される。Joke(2007)らは10週間週3回のセルフストレッチ(自動ストレッチ)を継続して実施したところ,発揮筋力が増大したと報告している。ストレッチによる筋力の増大が,他動的なストレッチにおいても得られるとすれば,身体を自由に動かすことが困難で,筋力増強運動はもちろん,自動ストレッチができない対象者の筋力の維持・向上に大変有用であると考えられた。そこで本研究では,長期的な自動および他動ストレッチが,筋力にどのような影響を及ぼすか検討することを目的とした。【方法】被験者は健常学生48名(男性24名,女性24名,平均年齢21.3±0.9歳)とし,男女8名ずつ16名をコントロール群,他動ストレッチ群,自動ストレッチ群の3群に振り分けた。他動ストレッチ群は週に3回,一日20分(各筋10分)の他動ストレッチを受け,自動ストレッチ群は同条件で自動運動によるストレッチを実施した。対象筋は両群とも大腿直筋とハムストリングスとし,介入期間は4週間とした。ストレッチ強度は被験者が強い痛みを感じる直前の心地よい痛みが伴う程度とした。測定項目は柔軟性の指標として下肢伸展拳上角度(以下SLR角度)と殿床距離を,筋力の指標として膝関節90°屈曲位の角度で膝伸展・屈曲の最大等尺性筋力を測定した。測定は4週間の介入前後の2回行った。測定結果は,それぞれの項目で変化率(%)を算出した。変化率は(4週間後測定値)/(初回測定値)×100とした。群間の比較には一元配置分散分析を実施し,多重比較検定にはTukey法を用いた。有意水準は5%とし,統計ソフトにはR2.8.1を用いた。【倫理的配慮,説明と同意】本学の医学研究倫理委員会の承認を得て行った。被験者には事前に研究内容について文書および口頭で説明し,同意が得られた場合にのみ実施した。【結果】膝伸展筋力の変化率はコントロール群で95.6±8.7%,他動ストレッチ群で115.2±21.2%,自動ストレッチ群で102.9±10.0%であった。コントロール群と他動ストレッチ群において有意な差を認めた。膝屈曲筋力,SLR角度,殿床距離に関してはいずれも各群間で有意差を認めなかった。【考察】本研究結果から,長期的な他動ストレッチにより膝伸展筋力の筋力増強効果が得られることが示唆された。筋にストレッチなどの力学的な刺激を加えることで筋肥大に関与する筋サテライト細胞や成長因子が増加し活性化され,筋力増強効果が発現するとされている(川田ら;2013)。本研究では,ストレッチによる,SLR角度や殿床距離の変化は見られなかったが,長期的なストレッチによる機械的刺激そのものが,上記に述べた効果に貢献し,筋力増強効果が得られたと推察される。膝屈曲筋力において筋力増強効果を認めなかった点について,両主動作筋の筋線維組成の相違が原因と考えられた。大腿四頭筋はTypeII線維が多いのに対し,ハムストリングスはTypeI線維が多く(Johnsonら;1973),筋肥大にはTypeII線維がより適しているとされている(幸田;1994)ことが影響したと考えられた。自動ストレッチによって筋力増強効果を得られなかったことに関しては,自己の力を用いて行うため,他動ストレッチに比べて筋を十分に伸張することができず,伸張刺激が不足したためと推察された。【理学療法学研究としての意義】他動ストレッチを長期的に行うことで筋力増強効果を得られる可能性を示唆した。他動的なストレッチが筋力にどのような影響を及ぼすのか検討した報告はこれまでになく,新規的な試みだと言える。他動的なストレッチを一定期間継続することで筋力の維持・向上に寄与することが明らかとなれば高負荷のトレーニングが適応とならない患者や,自分で身体を動かすことのできない患者にとって有用である。
- 著者
- 橋立 博幸 長田 けさ枝 森本 頼子 澤田 圭祐 柴田 未里 井上 智子 萩原 恵未 笹本 憲男
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.Ea1006, 2012 (Released:2012-08-10)
【目的】 超高齢者への運動介入により筋力増強効果が得られることが報告されてきているが,超高齢者における筋力増強効果と歩行機能向上効果との関連については十分に検証されていない.本研究では,要支援認定を受けた85歳以上の超高齢者に対して,12か月間の運動器機能向上プログラムを実施し,筋力増強効果と歩行機能改善効果との関連を検証することを目的とした.【方法】 対象は,介護保険制度下における介護予防通所介護を初めて利用した要支援高齢者17人(要支援1:7人,要支援2:10人,男性:5人,女性:12人,年齢87.2±2.5歳)であった.介護予防通所介護での運動介入は,12か月間,1~2日/週,1時間30分/日,実施し,主な介入内容として,ストレッチ,筋力増強運動,姿勢バランス練習,歩行練習,日常生活動作指導を行った.実際の介入は理学療法士,介護福祉士,看護師,等の職種が協働して行い,疼痛および疲労等の症状に応じて調整した.介護予防通所介護での運動介入実施前の初回評価時および運動介入実施後6か月ごとの生活機能について,身体機能(下肢筋力,姿勢バランス能力,歩行機能),日常生活活動(ADL)を評価した.身体機能は,脚伸展マシントレーニング機器レッグプレス1回最大挙上量(1RM),片脚立位保持時間(OLS),functional reach(FR),timed up & go test(TUG),通常歩行速度(NGS)および最大歩行速度(MGS)をそれぞれ計測した.ADLは老研式活動能力指標(TMIG-IC)を用いて調べた.初回評価時と運動介入12か月後の1RMの結果から,下肢筋力が増加した群(下肢筋力増加群,n=9)と低下した群(下肢筋力低下群,n=8)の2群に群別し,各群において初回評価時および運動介入実施後6か月ごとに評価した下肢筋力,姿勢バランス能力,歩行機能,ADLを示す各指標についてFriedman検定および有意確率をBonferroni補正した多重比較検定を用いて比較した.【倫理的配慮】 本研究はヘルシンキ宣言に基づき,概要を対象者および家族に対して事前に口頭と書面にて説明し,同意を得た後実施した.【結果】 初回評価時における両群の1RM,OLS,FR,TUG,NGS,MGS,およびTMIG-ICの各評価結果は有意差が認められなかった.介護予防通所介護における運動介入は,12か月間で合計77.9±18.8回/人,1月当たり平均6.5±1.6回/月実施され,12か月間の介入期間中,新たな疾病への罹患,症状の増悪,転倒の発生はなかった.た.初回評価時と各運動介入実施後の追跡評価時における各指標を比較した結果,下肢筋力増加群では,初回評価時に比べて1RMは介入6か月後に37.1%,介入12か月後に40.4%有意な増加を示すとともに,TUGは介入6か月後に22.1%,介入12か月後に22.9%,NGSは介入12か月後に27.3%,MGSは介入12か月後に18.3%,それぞれ有意な向上が認められた.一方,下肢筋力低下群では,1RMが介入12か月後に13.9%の有意な低下を示し,他の歩行の評価指標に有意な変化は認められなかった.また,両群ともにOLS,FR,およびTMIG-ICには有意な変化は認められなかった.【考察】 初回評価時から介入6か月ごとの各追跡評価時の指標を比較した結果,下肢筋力増加群では介入6か月後および12ヵ月後における1RMが増加するとともにTUG,NGSおよびMGSが有意に改善し,下肢筋力低下群では1RMが12か月後に有意に低下し,他の指標に変化がみられなかった.これは本研究における運動介入では,筋力増強効果と歩行練習効果が相乗的にTUGおよび歩行速度の有意な改善に反映されたと考えられた.また,これまでの先行研究では,地域に在住する健康な前期高齢者および後期高齢者においても1年後の歩行機能が低下し得ることが報告されており,超高齢者では筋力および歩行機能の低下が加速すると考えられている.本研究の対象者において,歩行機能の向上およびADLの維持が認められたことから,12か月間継続的に実施した運動器機能向上プログラムによって筋力増強効果を得ることが歩行機能の長期的な改善効果を得るために重要な要素であると考えられた.【理学療法学研究としての意義】 要支援認定を受けた85歳以上の超高齢者に対する12か月間の運動器機能向上プログラムによる筋力増強効果と歩行機能改善効果との関連を検証し,継続的な運動器機能向上プログラムによる筋力増強は超高齢者の長期的な歩行機能の維持・改善に重要であることを示唆した.
1 0 0 0 OA 耐フッ素透明材料に関する研究
- 著者
- 向坊 隆 雨宮 武男 西宮 辰明
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.497-500, 1962-04-05 (Released:2011-09-02)
- 参考文献数
- 4
フッ化水素酸に侵されにくい透明材料を得ることを目的として,新しいフッ化物ガラスを研究した。フッ化物ガラスとしてはフッ化ベリリウムを主成分とするものが知られているが,吸湿性なので他のフッ化物について調べた結果,フッ化アルミニウム- フッ化ナトリウム- メタリン酸ナトリウム系, フッ化マグネシウム- フッ化ナトリウム- メタリン酸ナトリウム系, フッ化アルミニウム- フッ化マグネシウム- メタリン酸ナトリウム系, フッ化アルミニウム- フッ化マグネシウム- メタリン酸カリウム系のガラス化組成範囲を決定した。フッ化アルミニウム-フッ化マグネシウム-メタリン酸ナトリウム系の試作ガラスに比較的よく無水フッ化水素酸に耐えるものが得られた。その一例はフッ化アルミニウム32.5mol%,フッ化マグネシウム27mol%,メタリン酸ナトリウム40.5mol%の組成のものである。この系で組成を変えたガラスについてはフッ素対酸素の原子比の大なるほど,フッ化水素酸に対する耐食性が大であり,この比が1付近でこの影響の著しいことを見出した。またフッ化水素酸中の水含有量がこの系のガラスの腐食に大きい影響を与えることが見出された。前記組成のガラスは無水フッ化水素酸による腐食は非常に少ないが,90%あるいは80%のフッ化水素酸では腐食速度は約10倍になる。ケイ酸塩ガラスではフッ化水素酸濃度の高いほど腐食速度は大きく,無水フッ化水素酸には激しく侵される。
1 0 0 0 OA オープンサイエンス時代における日本表面科学会
- 著者
- 荻野 俊郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面科学会
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.253-257, 2016-06-10 (Released:2016-06-21)
- 参考文献数
- 14
1 0 0 0 OA 会報
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.173-179, 2011-09-05 (Released:2011-10-28)
1 0 0 0 OA 日本列島における沖積層の層厚分布特性
- 著者
- 本多 啓太 須貝 俊彦
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.5, pp.924-933, 2010-10-25 (Released:2011-01-21)
- 参考文献数
- 82
- 被引用文献数
- 3 3
In warm-humid and tectonically active regions such as Japan it is important to investigate the geomorphic development of recent alluvial plains controlled by sea-level changes to prevent natural disasters. This is because human activities concentrate coastal alluvial plains composed of unconsolidated soft sediments (alluvium) including inner-bay mud, which amplify seismic intensity. However, we know little about the general shape of the alluvium quantitatively although several river basins have been investigated in detail. We selected 33 trunk rivers throughout Japan and measured the Present River long-Profile (PRP) along with the Last Glacial River long-Profile (LGRP) defined by the depositional surface of basal gravel layers formed under the influence of falling sealevels during the last glacial period. The thickness of the alluvium given by the relative altitude between PRP and LGRP was basically in proportion to the size of the river basin, and it decreased linearly upstream with the exception of several rivers such as Shinano, Kiso, Oita, and Yoshino. Along these rivers, the alluvium is markedly thicker than expected probably because of tectonic subsidence occurring repetitively after formation of basal gravel layers. This implies that the fluvial response to sea-level change is sensitive enough to distinguish the effects of the accumulation of tectonic movements after deposition of basal gravels. In stable or slightly uplifted areas, the inland distribution of inner-bay mud is basically controlled by river basin size.
1 0 0 0 OA ニシン漁の盛衰と漁民の活動
- 著者
- 服部 亜由未
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2009年度日本地理学会秋季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.182, 2009 (Released:2009-12-11)
はじめに 近世後期から近代における北海道の基幹産業は漁業であり,その中心をなしたのがニシン漁であった.ニシンの粕は北前船により,西日本を中心とした日本各地に運ばれ,魚肥として綿や菜種などの商品作物へ利用された.太平洋戦争中,及び戦後における食料難の時代には,重要な食料として求められるなど,ニシンの漁獲量が皆無になる1960年ごろまで,需要は高かった.さらに,技術の発展や漁場の拡大により,大量の労働力が求められた.近世にはアイヌ民族を使役し,アイヌ民族が減少すると,本州からの出稼ぎ者を雇うことで成り立っていた.ニシン漁を介して多くの人々が移動し,その影響力は大きかった. しかし,1960年には北海道日本海側でのニシン漁は幕を閉じ,ニシンは「幻の魚」と称されるようになった.そして,ニシン漁の担い手たちは今,姿を消しつつある.現在,ニシン漁経験者各人の中に記憶として眠っている体験をまとめることで,史料分析からは描き出せない具体的内容を付加できる最後の段階にきているといえる. 一方,北海道の日本海沿岸地域では,ニシン漁に関係する建造物の保存運動や,「ニシン」をキーワードに観光化策への連結も主張されるようになってきている. 本報告では,ニシン漁が行なわれていた時代のニシン漁と漁民とのかかわり,特にニシンの不漁から消滅にかけた漁場経営者や出稼ぎ者の対応について検討する.また,近年のニシン漁に基づく活動を紹介し,ニシン漁を考える意義について述べたい. ニシン漁と漁民 3月下旬から5月下旬の2ヵ月という短い期間に,獲れば獲るほどお金になったニシン漁には,多くの労働力が必要とされた.特に,江戸時代に行なわれていた場所請負制度が廃止されると,漁場が増加した.漁場経営者は漁業権を獲得すれば,自由に漁場を開くことができ,漁場周辺の人だけでは足らず,多くの出稼ぎ者が雇われた. ニシンは豊漁不漁を繰り返し,その漁獲地は北へ移っていった.漁の傾向が予測できない状態で,漁場経営者は多額の出資をして準備を行ない,出稼ぎ者は出稼ぎ地域を決定しなければならなかった.漁獲量が変動する中で,ニシン漁場経営者たちは,漁を行なう網数に適した出稼ぎ者を雇い,漁獲量が多い場合には,臨時の日雇い労働者を雇う形態をとっていた.また,衰退期には,ニシン漁以外の収入源や共同での漁場経営への移行,生ニシンの加工業への転換が見られた.一方,出稼ぎ者は初年度には身内とともに出稼ぎに行くが,その後は各自の判断により地域や漁場を決めた.そして,不漁期を経験した人々への聞き取り調査からは,2年続いて不漁であれば,3年目には他の漁業や他業種の出稼ぎに転換する傾向が見受けられた.報告では,史料や聞き取り調査から判明した実態を紹介・検討する. ニシン漁に基づく町おこし 北海道日本海側の市町村には,ニシンが獲れなくなった現在においても,ニシン漁にまつわる歴史や文化が存在し,ニシン漁によってその市町村が形成されたことを感じさせる.各自治体史編纂の地域史においては,この点が強調されてはいるが,自村のみの事例紹介でとどまっている.そのような中,後志沿岸地域9市町村では,「ニシン」という共通の資源を基軸にした「後志鰊街道」構築の試みがなされている.報告者はこのような興味深い取組みを後志地域だけでなく,北海道日本海側全域,東北を中心とした出稼ぎ者の出身地域,さらには北前船の寄港地を含んだ地域にまで拡大できないものかと考えている.こうしたニシンによる地域交流圏を仮称「ニシンネットワーク」として調査研究を進め,各自治体の町おこしに協力していきたい. ここではその第1報として,出稼ぎ者の出身地域である青森県野辺地町の沖揚げ音頭保存会の活動を紹介する.当会は,利尻島への出稼ぎ者を記した「鰊漁夫入稼者名簿(利尻町所蔵)」がきっかけとなり,2008年に結成された会であり,祭りや小学校での実演,指導を行なっている.2009年9月に利尻町の沖揚げ音頭保存会との交流会を行なった. ニシン漁再考 昨今,放流事業の成果もあってか,再びニシンが獲れるようになり,話題となっている.ただし,現在漁獲される石狩湾系ニシンは,かつての北海道サハリン系ニシンとは種類が異なっており,かつてほどの漁獲量にはならないと予想される.しかし,利益至上主義による乱獲をしてはならないことを過去の経験から学ぶ必要がある. また,北海道日本海側の地域形成の議論には,出稼ぎ者出身地域とのつながりからのアプローチ「ニシンネットワーク」論が有効であると考える.そのために,北海道と出稼ぎ者出身地域との両地域を対象とし,史料の発掘や経験者への聞き取りを積み重ねていきたい.
1 0 0 0 OA キノロン系薬の副作用としてのQT延長
- 著者
- 中島 光好
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学療法学会
- 雑誌
- 日本化学療法学会雑誌 (ISSN:13407007)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.229-235, 2001-04-25 (Released:2011-08-04)
- 参考文献数
- 30
多くの抗不整脈薬がQT間隔を延長しそしてときにtorsades de pointesをおこすことはよく知られている。最近, 心臓疾患を対象としない治療薬が問様にQT間隔を延長し, torsades de pointesをおこすことが数多く報告されている。向精神薬, 抗高血圧薬, 抗ヒスタミン薬, 抗真菌薬, 抗菌薬などである。近年特に, キノロン薬に注目が集まっている。Torsades de pointesは多形性心室性頻拍を起こし, 死に至ることもある重大な副作用である。キノロン薬のなかではsparfloxacin, grepafloxacinで, 少ないがlevofloxacinでも報告されている。非心臓薬によるQTc延長は通常起こり得ない現象で, 特にtorsades de pointesのような致死的なものはまれである。わずかな人しか対象としない第I~III相試験ではおこりそうもない, しかし市販後多くのさまざまな病態の患者に使用されると出現する。これを開発段階でいかに早くみつけるかその努力が求められる。そのためにはQT間隔延長をおこすメカニズムを明らかにし特殊なイオンチャネルに作用する化合物の構造活性相関の研究を行うと共に, QT間隔延長作用を持つか否かを調べる非臨床試験のin vivo研究方法の標準化, このようなQT間隔延長作用があると非臨床試験でわかった薬については臨床第I, II, III相試験のデザインを慎重に行う必要がある。
- 著者
- 高品 善 今西 茂 江頭 宏昌
- 出版者
- Japanese Society of Breeding
- 雑誌
- 育種学雑誌 (ISSN:05363683)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.33-37, 1997-03-01 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
トマトの野生種 'peruvianum-complex'に属する Lycopersicon peruvianum の5系統, L. peruvianum var. humifusum の2系統,L. chilenseの2系統を花粉親とし,栽培種2品種を種子親とするF1雑種およびF1を花粉親とするB1F1戻し交雑種を胚珠選抜法によって育成した。F1およびB1F1の獲得効率は果実あたり発芽数(GOF)により評価した。F1および1994年と1995年のB1F1についてGOFの栽培品種間の相関係数を求め,さらに,それらを組み合わせた相関係数を求めたところ,正の有意な値となった(r=0,750**,d.f.=11)。年次問においても組み合わせた相関係数は有意な正の高い値となった(r=0,907^*,d.f.=3)。F1とB1F1間の相関係数は,2栽培品種とも正であるが有意ではなく,組み合わせた相関係数も有意にはならなかった(r=0,433,d.f.=3)。しかし,供試した系統の中で1系統がF1とB1F1間で全く異なるGOFを示したので,この系統を除くと,F1とB1F1の間に正の有意な相関係数が得られた(強力大型東光:r=O.754*, d.f.=5;Early Pink:r=O.924*,d.f.=3)。相関係数に関するこれらの結果は,栽培種に対する野生種の交雑不親和性に関して野生種系統間で差があり,さらにB1F1の獲得において野生種の各系統の交雑不親和性がF1の場合と同じように現れることを示している。供試した系統の交雑不親和性を3グループに分けるとおおよそ次のようになった。最も高いグループに L. peruvianum var. humifusumの2系統が入っており,中間のグループの全てはL. peruvianumであった。最も交雑不親和性の低いグループはL. chilenseの2系統であった。一方,F1とB1F1の回帰直線は,Y(B1Fl)=O.1082X (F1)+ 0.3364:強力大型東光, Y=O.1054X + O.0366:Early Pinkとなった。この結果から,予想に反してB1F1の獲得効率がF1よりも小さいことが推察された。
1 0 0 0 OA A Program for Single-center Expansion in Laguerre-type Orbitals for the Hydrogen Molecular Ion
- 著者
- Yasuyo HATANO Shigeyoshi YAMAMOTO
- 出版者
- Society of Computer Chemistry, Japan
- 雑誌
- Journal of Computer Chemistry, Japan -International Edition (ISSN:2189048X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.2016-0003, 2016 (Released:2016-09-03)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
A Fortran program is given for calculating wave functions of the molecular hydrogen ion, expanded in terms of single-center Laguerre-type orbitals. Using this program, the radial quantum number has been extended to 203, and accuracy has been attained in energy of the order of 10−6 a.u. The electron-nucleus Coulomb integrals are evaluated numerically by applying Gaussian quadratures.
- 著者
- Umpei NAGASHIMA Junko KAMBE Toru YAGI Tomoo AOYAMA
- 出版者
- Society of Computer Chemistry, Japan
- 雑誌
- Journal of Computer Chemistry, Japan -International Edition (ISSN:2189048X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.2015-0054, 2016 (Released:2016-09-03)
- 参考文献数
- 10
An imaging tool is proposed to research marine environment in science teaching. It is for usage of digital cameras in housing underwater. Analyzed format is JPEG, in which RGB intensity is digitized in 8 bits. The intensity relates wavelength dependence in the bandwidth of RGB. We extract information from the dependence, and investigate absorption, scattering, and reflection in the water. Ratio index for wavelength dependence is discussed, which is easy for students to understand. Next, using the idea of the index, Ratio-RGB image is defined and discussed. The image is introduced for visualizing suspended solids in the sea. The environment in the sea is displayed using the Ratio-RGB images. Turbulence of scattering light layers, distribution of fishes, and small marine biology are detected clearly. The approach enables understanding of conditions in the sea visually.
- 著者
- Hiroshi SAKIYAMA
- 出版者
- Society of Computer Chemistry, Japan
- 雑誌
- Journal of Computer Chemistry, Japan -International Edition (ISSN:2189048X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.2016-0001, 2016 (Released:2016-08-31)
- 参考文献数
- 13
MagSaki(Tetra) software was developed for the purpose of analyzing the magnetic susceptibility data of tetranuclear octahedral high-spin cobalt(II) complexes. The software enables the analyses six types of tetranuclear cobalt(II) structures, including cubane and defect dicubane structures, to obtain magnetic parameters: the interaction parameters, J, J’, J”, and J”’, the spin-orbit coupling parameter, λ, the orbital reduction factor, κ, and the axial splitting parameter, Δ.
1 0 0 0 OA マイクロELISAによる患者の微量検体の分析法
- 著者
- 森 絵美 細谷 弓子 今井 靖 大橋 俊則 田澤 英克 馬渡 和真 森田 啓行 北森 武彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.6, pp.461-468, 2015-06-05 (Released:2015-07-07)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 2
マイクロフルイディクス(微小流体工学)と熱レンズ顕微鏡を応用して酵素結合免疫測定(enzyme-linked immunosorbent assay: ELISA)をシステム化した新しい機能デバイス(μELISA)を開発した.μELISAは,これまでの研究成果で,ヒト血清でも優れた性能を発揮してきた.しかしながら,様々な患者検体でマイクロリットルオーダーの微量分析を行う場合には,患者ごとに異なる検体の成分組成や粘度の違いによる影響などが課題となる可能性がある.本研究では,測定対象とするマーカーをC反対性タンパク(CRP)として,実際の患者血清に対して考慮すべき測定条件を検討した.その結果,マイクロ流体系では検体に由来する影響があることが分かり,信頼性のある測定値を得るためには,緩衝液にて希釈をする必要があることが分かった.
1 0 0 0 OA メニエール病の発症と類型
- 著者
- 北野 仁 斎藤 春雄 北嶋 和智 竹田 泰三 矢沢 代四郎 松原 秀春 北野 眞由美 北野 博也 児玉 章 水上 千佳司
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.10special, pp.2370-2378, 1981-10-25 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 7
Meniere's disease is represented by episodic vertigo (vestibular symptom), tinnitis and hearing loss (cochlear symptom). It is possible to devide patients with Meniere's disease into three groups; those with cochlear and vestibular symptoms starting at the same time, and those with the vestibular symptoms starting before or after cochlear symptoms: In this presentation, we studied the clinical differences of these three groups. The following results were obtained.1. In the case of cochlear Meniere's disease, the cochlear symptom is slight and it is easy to acquire the vestibular symptom. The cause of cochlear Meniere's disease was considered to be the existence of endolymphatic hydrops. Compared with frequency of bilateral Meniere's disease, bilateral cochlear Meniere's disease was more found.2. In the case of vestibular Meniere's disease, the vestibular symptom is slight and it is difficult to acquire the cochlear symptom. The cause of vestibular Meniere's disease, in all cases was not considered to be the existence of endolymphatic hydrops.3. In the case of Meniere's disease with vestibular symptoms starting after the cochlear symptoms, both the vestibular symptoms and cochlear symptoms are heavy. In the case of Meniere's disease with vestibular symptoms starting before the cochlear symptoms, both symptoms are slight.
1 0 0 0 OA 北海道天鹽国中川郡中川村歌内,宇土内川における蛇紋岩中の石油徴候
- 著者
- 佐々 保雄
- 出版者
- 石油技術協会
- 雑誌
- 石油技術協会誌 (ISSN:03709868)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.28-33, 1955-03-30 (Released:2008-03-27)
Two examples of oil seeps were found in 1954 in serpentine rocks of Hokkaido. These are the first occurrences discovered in such kind of rocks, although many showings had been previously found in areas of eruptive rocks in Japan. One of these seeps is located in a tributary of the Utonai river, Nakagawa village, Teshio province of northern central Hokkaido and the other is in the Mukawa river, Hobetsu village, Iburi province of the southern central Hokkaido. This paper describes its unusual type of oil seep and the related geology of the Utonai and the rare type of oil at the seep is also discussed. The crude oil is from fissure in serpentine. It is colorless, transparent and clear in appearance with a gasoline like smell and is probably natural gasoline. It is very light in specific gravity measuring 0.7707 at a temperature of 15.4°C. Its viscosity is also low which is 1.190 centipoise at a temperature of 30.0°C. and very gradually increases with increases in temperature. The behavior of the crude oil upon distillation is unusual. That is, it has a initial boiling point at 62.0°C. and is 98% of oil distilled out at a temperature of 246.0°C.The author concludes that the oil in the serpentine mass migrated from the surrounding Cretaceous oilbearing marine deposits after the serpentine intrusion into the Cretaceous. The characteristic properties of the crude oil developed by natural cracking resulting from residual heat in the igneous body. Decolorization caused by passing through clay within the serpentine as the oil moved up to the surface.The economical impotance of this field is still unknown but this occurrence suggests that more attention should be paid to the oil possibilities of the Cretaceous formations of the surounding region.
1 0 0 0 OA 内科学会NEWS
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.6, pp.News6-News6, 2015-06-10 (Released:2016-06-10)
1 0 0 0 OA 日本語母語話者における英語の音韻意識が英語学習に与える影響
- 著者
- 津田 知春 高橋 登
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.95-106, 2014 (Released:2016-03-20)
- 参考文献数
- 42
日本語を母語とする日本人中学生の英語の音韻意識と英語語彙,スペルの知識との関係が実験的に調べられた。スペルの知識は,オンセット・ライムが実在の単語と共通の偽単語を聴覚呈示し,それを書き取らせた。また,音韻意識はStahl & Murray(1994)を参考にして,英単語からの音素の抽出,音素から単語の混成,および日本語の音節構造を持つ単語・偽単語の音素削除課題が用いられた。全体で73名の中学校1年生,2年生が実験に参加した。その結果,語彙課題は学年によって成績に差が見られたが,その他の課題では学年差は見られなかった。また,音韻意識課題の誤りの多くは音素の代わりにモーラを単位として答えるものであった。語彙を基準変数とした階層的重回帰分析の結果,語彙は学年とスペル課題の成績で分散の50%以上が説明されることが確かめられた。また,スペル課題を基準変数とした階層的重回帰分析では,学年は有意な偏回帰係数が得られず,音韻意識の中では混成課題で有意な偏回帰係数が得られた。このことから語彙力を上げるためには,スペル課題で測定される英単語の語形成に関する知識が必要であり,語形成知識は,日本語の基本的な音韻の単位であるモーラではなく,音素を単位とする音韻意識を持つことによって身につくと考えられた。最後に,本研究の今後の英語教育への示唆について議論した。
1 0 0 0 OA CHL細胞の継代による品質劣化に関する研究
- 著者
- 六角 香 大中 浩貴
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第40回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.2002091, 2013 (Released:2013-08-14)
【目的】CHL/IU細胞はチャイニーズハムスター肺由来の線維芽細胞である。当細胞は,培養方法に難しい技術を必要としないこと,染色体数が少なく,染色体標本の観察が比較的容易であることから,遺伝毒性試験(特に染色体異常誘発性を評価する試験)において汎用されている。通常,培養細胞をこれらの試験に用いる際,あらかじめ継代培養を行った細胞を適宜使用するが,継代培養操作を繰り返すことによる品質の変化についての基礎データは少なく,とくに数週間から数箇月以上に及ぶ試験において,試験使用時毎にその細胞の品質の劣化の有無を確認することは容易ではない。今回,継代操作を多数回繰り返した細胞について,その特性の変化及び劣化の程度を検討した。【方法】CHL/IU細胞を,10%牛胎仔血清含有MEMアール液体培地を入れたシャーレを用いて,5%CO2,37℃の条件で継代培養した。継代回数が10回未満,20回,40回,60回の細胞を用い,各々について特性検査を行った。検査は1)細胞の倍加時間,2)染色体数,3)自然発生による異常細胞出現頻度,4)既知の染色体異常誘発物質(マイトマイシンC,ジメチルニトロサミン及びシクロフォスファミド)で処理した際の異常細胞出現頻度の各項目について実施した。【結果及び考察】細胞の倍加時間,染色体数(異数性異常細胞の増加)並びに自然発生による異常細胞出現頻度(構造異常・数的異常)は,いずれの継代回数の細胞にも差は認められなかった。一方,既知の染色体異常誘発物質で処理した際の異常細胞出現頻度は,いずれの物質においても継代回数40回以上の細胞において減少したことから,継代操作の多数回の繰り返しは染色体異常誘発性の検出精度を低下させると考えられた。
- 著者
- Jungmin SOHN Sookyung YUN Jeosoon LEE Dongwoo CHANG Mincheol CHOI Junghee YOON
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.16-0003, (Released:2016-09-05)
- 被引用文献数
- 8
Kidney size may be altered in renal diseases, and the detection of kidney size alteration has diagnostic and prognostic values. We hypothesized that radiographic kidney size, the kidney length to the second lumbar vertebra (L2) length ratio, in normal Miniature Schnauzer dogs may be overestimated due to their shorter vertebral length. This study was conducted to evaluate radiographic and ultrasonographic kidney size, L2 length and the kidney length to aorta diameter ratio in clinically normal Miniature Schnauzers and other dog breeds to evaluate the effect of vertebral length on radiographic kidney size and to reestablish radiographic kidney size in normal Miniature Schnauzers. Abdominal radiographs and ultrasonograms from 49 Miniature Schnauzers and 54 other breeds without clinical evidence of renal disease and lumbar vertebral abnormality were retrospectively evaluated. Radiographic kidney size, mean kidney length to the second lumbar vertebra ratio, in the Miniature Schnauzer (3.31 ± 0.26) was significantly larger than that in other breeds (2.94 ± 0.27). Relative L2 length, the L2 length to width ratio, in the Miniature Schnauzer (1.11 ± 0.06) was significantly shorter than that in other breeds (1.21 ± 0.09). However, ultrasonographic kidney sizes were within or very close to normal range both in the Miniature Schnauzer (6.75 ± 0.67) and other breeds (7.16 ± 1.01). Thus, Miniature Schnauzer dogs have breed-specific short vertebrae and consequently a larger radiographic kidney size, which was greater than standard reference in normal adult dogs. Care should be taken when evaluating radiographic kidney size in Miniature Schnauzers to prevent falsely diagnosed renomegaly.