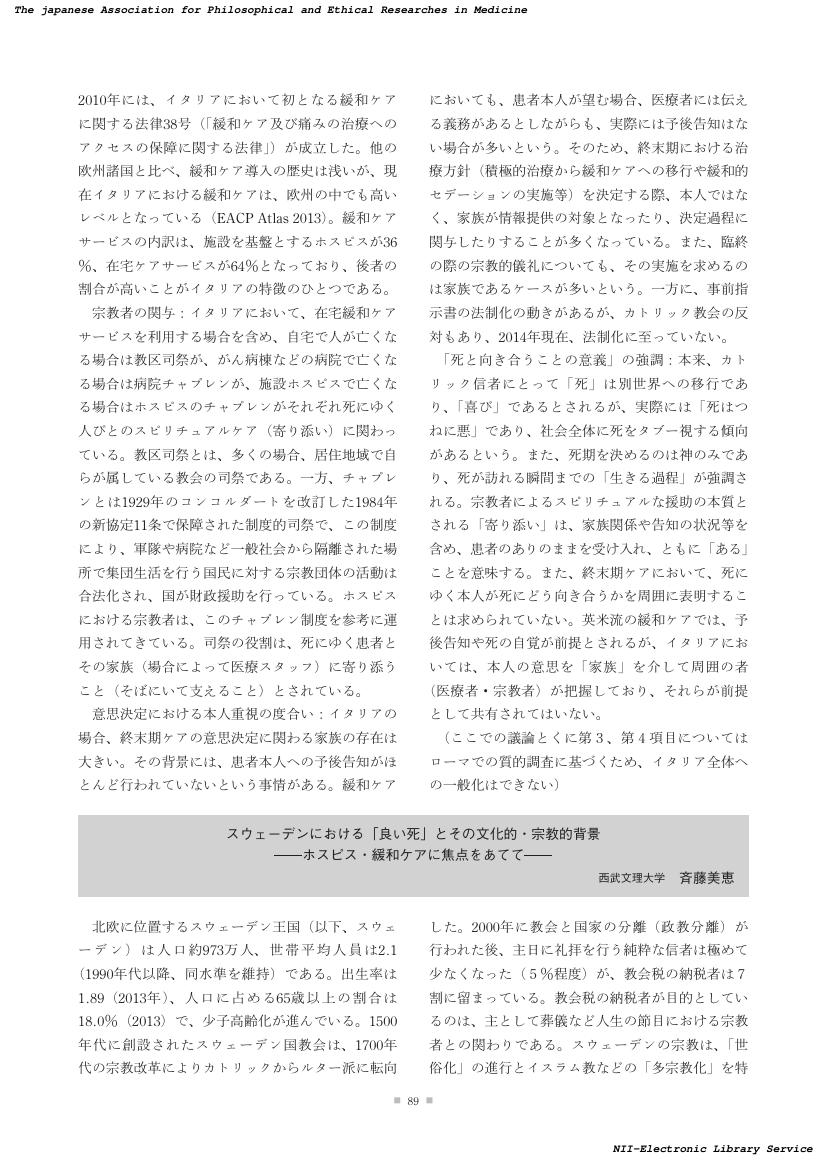2 0 0 0 OA レビュー有用性の影響要因 ― 質的・量的レビュー ―
- 著者
- 斉藤 嘉一
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.33-43, 2021-03-31 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 32
Amazon.comやTripAdvisorなど多くのクチコミサイトには,helpfulボタン(役に立ったボタン)が設置されており,読者はhelpfulボタンを押すことでレビューが役に立ったことを表明することができる。レビュー有用性,すなわち,レビューが獲得するhelpfulの数,あるいは割合がどんなレビュー特性,発信者特性,製品特性によって影響されるかは,マーケティンングと消費者行動,および情報システムの両方の領域において盛んに検討されてきた。本研究は,レビュー有用性の影響要因について,ナラティブレビュー(質的なレビュー)とメタ分析(量的なレビュー)を行った。その結果,テキストの長さと投稿者の写真の開示は,レビュー有用性とプラスの関係にあることが示された。一方,評価得点(星の数),および投稿者の名前や住所の開示と,レビュー有用性との関係については,既存研究において得られた実証結果は一貫したものではなかった。これらの一貫しない結果を整合的に説明するために,受信者のhelpful意思決定を検討することを提案した。
- 著者
- 斉藤 悦子 川谷 旺未 サイトウ エツコ カワタニ アキミ Etsuko SAITO Akimi KAWATANI
- 雑誌
- 清泉女子大学人文科学研究所紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.54-72, 2017-03-31
1860年、南北戦争開戦前夜のアメリカに幕末の日本から遣米使節団が訪れ、そのワシントン到着の様子はニューヨークの主要メディアでも大々的にとりあげられた。その中でもふんだんなイラスト付きで報じたハーパーズ・ウィークリー紙には、一般的な記事のほかにも、風刺漫画や漫談風の記事なども掲載された。本稿は1830年代からアメリカジャーナリズムの中でひとつのジャンルとして人気のあった、架空の「田舎者」的人物がなぜか歴史的瞬間に立ち会って親戚に見聞録の手紙を送る、というスタイルのコラムを訳出、注釈したものである。判読の難しいvernacularで書かれた時事放談を、まず判読して標準英語に直し、注をつけて日本語に訳出した。遣米使節団がニューヨークの庶民に向かってどのように伝えられたか、という資料として紹介したい。 On the Japanese Embassy's arrival in Washington in 1860, various media in New York responded with cover stories and feature articles. In the May 26th issue of Harper's Weekly, a vernacular parody, based on the "Major Jack Downing" letters created by Seba Smith in the 1830s, appeared as a nearly identical letter home written by Major Downing's nephew Benjamin. It is a Forrest Gump-ish account of a young lad suddenly chosen as the master of ceremony to receive the Foreign Embassy. This vernacular letter displays much of how the general public felt on their first contact with the Japanese. Since the vernacular style is difficult to encode and the text is full of political connotations specific to the eve of Civil War, it may be worthwhile to annotate and translate it into Japanese as a source for research on the Japanese Embassy of the Manei era in the late Edo period.
- 著者
- 斉藤 正美
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.3-22, 2020
本稿の目的は、「ライフプラン(ライフデザイン)教育」とはどのような内容や取組なのか、特色ある取組を行っている都道府県、特に高知県及び富山県を中心に、行政担当者や学校関係者等への聴き取り調査を行い、明らかになった現状と課題を指摘することにある。さらに取組が全国に浸透している要因の考察も行う。「ライフプラン教育」とは、国の少子化対策の交付金等により結婚を支援する「婚活政策」の一環で、地方自治体が中学・高校・大学生や市民に人生設計を考えさせ、若い時期での結婚や妊娠を増やそうとする取組である。<br> 聴き取り調査の結果、ライフプラン教育には、婚活企業の関係者や国の少子化対策等の審議会委員等、婚活や婚活政策の利害関係者が関与していること、また取組内容は、早いうちの結婚や妊娠を奨励し、LGBTや独身、子どものいない生き方、ひとり親など、多様性の確保に課題があることが判明した。共働きの家事・育児を自己責任で解決するよう、モデル家族に「三世代同居」を提示するなど、性別役割分業と自助努力が強調されていることも特徴であった。<br> こうした課題を持つライフプラン教育だが、全国の自治体に浸透し、継続され続けている。その要因としては、「優良事例の横展開」という交付金のあり方に加え、男女共同参画との連携が交付金の採択要件とされたものの、2000年代前半の右派や自民党によるバッシングにより男女共同参画が後退し、歯止めとして機能しなくなっていたことが浮き彫りになった。さらに少子化対策として整備された少子化社会対策基本法、次世代育成支援対策推進法が、妊娠・出産や家族の役割を強調する法律であったことも影響していた。<br> 本稿は、2000年代以降の男女共同参画政策の変遷を踏まえ、地方自治体におけるライフプラン教育の取組に関する現状と課題を提示するもので、少子化問題の解決策と個人の自由意志による生き方の尊重が相反しないあり方の検討に資するといえよう。
2 0 0 0 OA クロロフィルのかたちは機能にどう影響を及ぼすか : Photosystem IIを例に
- 著者
- 斉藤 圭亮 石北 央
- 出版者
- 一般社団法人 植物化学調節学会
- 雑誌
- 植物の生長調節 (ISSN:13465406)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.133-138, 2015-12-21 (Released:2017-09-29)
- 参考文献数
- 11
We investigated the degrees of chlorin ring deformations of the special pair chlorophylls P_<D1>/P_<D2> in the Photosystem II (PSII) crystal structure, using a quantum mechanical/molecular mechanical approach. We found that (i) the out-of-plane distortion of the PD1 chlorin ring can be described predominantly by a large "doming mode" arising from the axial ligand D1-His198. In contrast, (ii) the deformation of PD2 was caused by a "saddling mode" arising from the D2-Trp191 side chain and the axial ligand D2-His197. However, (iii) the redox potential difference between P_<D1> and P_<D2> was predominantly determined by the PSII electrostatic environment rather than by the degree of the chlorin-ring distortion. (iv) The chlorin ring deformation appears to simply originate from the local steric protein environment of PSII.
2 0 0 0 柔道競技における「判定」と「ゴールデンスコア」の比較に関する研究
- 著者
- 菅波 盛雄 斉藤 仁 廣瀬 伸良 中村 充 林 弘典 増地 克之
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.1-12, 2005
IJFは2001年までは「判定方式」,2002年からは「ゴールデンスコア方式」を採用している。本研究は,2000年から2003年までの4年間に国際柔道連盟が主催した4大会を対象として,試合終了時に両試合者のスコアが同一であった試合の分析を試みた。<br>2000年世界Jrナブール大会と2001年世界選手権ミュンヘン大会,全1,356試合の中で「判定」によって勝敗が決したのは73試合(5,4%)であった。2001年世界Jr済州島大会と2003年世界選手権大阪大会,全1,285試合の中で「GS」によって勝敗が決したのは42試合(3.3%)であり減少がみられた。<br>「判定」によって勝敗が決した73試合を施技ランクB,Cおよび組み手主導権の3項目で比較した結果,審判員の判定が3対0の時にプラスポイントが確認された選手が勝ちとなったのは73,8%であった。一方,2対1の時はプラスポイントでの勝ちが41.9%と減少がみられたことから,全員一致の判定の困難さが窺える。<br>同様の手法で「GS」に入る前の試合分析から,「GS」への移行が妥当と判断されたのは11試合(26.2%)であり,残りの31試合(73.8%)は項目比較によって優劣に差がみられた。「GS」導入によって試合時間は「判定方式」に比べて長くなるが,「判定」に対する「GS」の試合時間比は4分の試合で1.43倍増に対して,5分では1.28倍と減少が認められた。<br>「GS方式」の導入によって,試合終了時に同一スコアとなる試合が激減した。また,実質上の試合時間を抑制する傾向が窺え,延長時間の問題も許容範囲であると言える。「GS」による試合は,罰則よりもポイント取得によって勝敗が決する方向にあり,勝負判定の客観化を推進するためには有効な改正であった。
2 0 0 0 IR サロメの系譜 聖書の時代から現代まで
- 著者
- 斉藤 恵子
- 出版者
- 大妻女子大学
- 雑誌
- 大妻比較文化 (ISSN:13454307)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.48-71,図5〜6, 2000-03
This paper is based upon university lectures I gave in 1998 as part of a joint series on Women's Studies. The principle aim that year was to find examples of women's ways of life within each lecturer's own specialized field. Salome was taken up. The story of Salome proved popular in Christian art from an early period, and has been portrayed in other fields such as literature, music, dance and cinema. The theme permits various approaches. Salome, best known as the heroine in Oscar Wilde's one-act play and Richard Strauss's opera, is remembered as the immediate agent in the execution of John the Baptist, but she is unnamed in the Gospels, Mark and Matthew. It is her mother Herodias that is a main agent in the beheading of John. Herodias was infuriated by John's stinging rebuke of her marriage to Herod Antipas as the marriage violated Mosaic Law. Herodias has been regarded as a cruel and wicked woman who prompted her daughter to ask for the holy prophet's head, but she would have sharply protested against Mosaic Law which was extremely unfair to women. Heredias's condemnation of Judeo-Christian laws and ethics as too favorably biased toward male supremacy is a voice worth listening to. Iconographically, Salome has often been confused with Judith of Bethulia, a beautiful Jewish widow who saved her country from the evil enemy by beheading the enemy's general with his sword. Two pictures of "Judith,alias Salome" by Gustav Klimt are adequate illustrations. Judith was sometimes regarded as the female counterpart of King David of Judea, and was admired by such woman painter as Artemisia Gentileschi. But both Salome and Judith have been portrayed by the nineteenth century "fin de siecle" artists as erotic symbols. In her Tale of Salome's Nurse, contemporary historian and writer, Shiono Nanami, interprets Salome as the courageous woman, fully aware of her responsibility as a monarch, with keen insight into the political and religious disturbances within Jewish society. Completely independent of her frail mother, she requested her step-father give her the head of John the Baptist as a reward for her dance of the seven veils. In this way, Shiono has interpreted, Salome as having brought momentary peace to her country, Judea. In conclusion, Salome is an exciting example from whom we can learn both positive and negative lessons.
2 0 0 0 OA シナリオ・視覚要素・音響効果を統合的に自動生成するゲームシステムの構築
- 著者
- 斉藤 勇璃 白石 智誠 太田 和宏 根本 さくら 石川 一稀 宇田 朗子 小川 卓也 友広 純々野 中村 祥吾 山内 拓真 西川 和真 宍戸 建元 長野 恭介 蓬畑 旺周 稲垣 武 村井 源 迎山 和司 田柳 恵美子 平田 圭二 角 薫 松原 仁
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.4C2GS1303, 2020 (Released:2020-06-19)
シナリオライターの負担軽減と物語多様性の担保という観点から,ゲーム自動生成システムの開発の必要性が指摘されてきている.これまでに固有名の組みあわせによるシナリオ自動生成やダンジョン自動生成など,いくつかの挑戦は行われてきたが,ゲーム全体において一貫した世界観やストーリー展開を実現するのは困難だった.そこで本研究ではロールプレイングゲームを対象として,シナリオ自動生成,ダンジョン自動生成,BGM自動選択を統合したシステムの開発を行った.シナリオ自動生成においては,既存のゲーム作品のシナリオ分析結果に基づき,クエスト単位でのシナリオ自動生成を行った.次に生成された複数のクエストを統合してストーリーの破綻がない複合的なシナリオの自動生成を実現した.また,ダンジョンは自動生成を実現し,マップやキャラクターは生成されたシナリオに沿ったものを作成した.さらに,シナリオの各場面の機能や登場人物の感情状態に合わせたBGMの自動選択を実現した.これらのゲームの各種要素を自動的に生成して統合することで,ロールプレイングゲーム自動生成システムの構築を行った.
2 0 0 0 OA 飲酒量および酒の種類と軽度認知障害との関連:東温スタディ
- 著者
- 藤井 晶子 丸山 広達 柴 珠実 田中 久美子 小岡 亜希子 中村 五月 梶田 賢 江口 依里 友岡 清秀 谷川 武 斉藤 功 川村 良一 髙田 康徳 大澤 春彦 陶山 啓子
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.300-307, 2020-07-25 (Released:2020-09-04)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
目的:飲酒と認知症に関する海外の研究のメタ分析では,飲酒量が少量の場合には発症リスクが低く,大量の場合には高い結果が示されている.しかし,アルコール代謝や飲酒文化が異なるわが国のエビデンスは限定的である.そこで本研究では,平均飲酒量と認知症前段階の軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment,以下MCIと略)との関連について検討した.方法:2014~2017年に愛媛県東温市の地域住民に実施した疫学研究「東温スタディ」に参加した60~84歳の男性421名,女性700名を本研究の対象とした.質問調査によって飲酒頻度,酒の種類別飲酒量を把握し,1日あたりの平均飲酒量を推定した.またJapanese version of Montreal Cognitive Assessmentを実施し,26点未満をMCIと定義した.男女別に現在飲まない群に対する平均飲酒量について男性3群,女性2群に分け各群のMCIの多変量調整オッズ比(95%信頼区間)をロジスティック回帰モデルにて算出した.さらに,ビール,日本酒,焼酎(原液),ワインについては,日本酒1合相当あたりの多変量調整オッズ比(95%信頼区間)を算出した.結果:男性212名(50.4%),女性220名(31.4%)がMCIに判定された.男性では,現在飲まない群に比べて,1日平均2合以上の群のMCIの多変量調整オッズ比(95%信頼区間)は1.78(0.93~3.40,傾向性p=0.045)であったが,女性では有意な関連は認められなかった(「1合以上」群の多変量調整オッズ比:95%信頼区間=0.96:0.39~2.38,傾向性p=0.92).この関連は,高血圧者において明確に認められた.また酒の種類別の解析では,男性において焼酎(原液)については多変量調整オッズ比(95%信頼区間)が1.57(1.18~2.07)と有意に高かった.結論:男性において平均飲酒量が多いほどMCIのリスクが高い可能性が示された.この関連は高血圧者においてより明確であった.
2 0 0 0 恩顧主義と貿易自由化:コメ保護農政の日韓比較
- 著者
- 斉藤 淳 浅羽 祐樹
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.114-134, 2012
比較優位を失った農産物の保護政策を自由貿易と整合的にどのように実施するかは先進工業国に共通する重要な政策課題である。日韓はコメ保護農政において価格統制から出発し強大な農業者団体を有するなどの類似点にもかかわらず,日本は与党への支持と減反への協力と引き換えに公共事業を選択的に提供する恩顧主義から脱却しきれず,TPPに対する態度を保留している半面,韓国は裁量の余地がないプログラム型の直接支払制へと移行し,米国やEUとFTAを締結した。権限が強く,農村部が過大代表されたままの第二院を抱える両院制議院内閣制の下,衆参ねじれが常態化し,与党に対する規律が弱く,日本の首相は執政権が制約され,現状点が維持されたままである。他方,韓国の大統領は,都市部の消費者や国民経済全体の厚生により敏感で,任期半ばで迎える議会選挙の公認権を通じて与党を統制することで,政策転換が可能になった。
- 著者
- 中宮 英次郎 宮川 優一 戸田 典子 冨永 芳信 斉藤 るみ 住吉 義和 高橋 真理 徳力 剛 前澤 純也 三原 貴洋 竹村 直行
- 出版者
- 獣医循環器研究会
- 雑誌
- 動物の循環器 = Advances in animal cardiology (ISSN:09106537)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.41-47, 2011-12-01
- 参考文献数
- 12
2歳6カ月齢,去勢オスのノルウェージャン・フォレスト・キャットを各種検査に基づいて肥大型心筋症と診断し,エナラプリルの投与を開始した。第1357病日に左房の高度な拡大が見られたため,ダルテパリン療法を追加した。さらに,第1616病日に左房内に spontaneous echo contrast (SEC) が,そして第2155病日には左心耳内に血栓形成が認められた。本症例は第2229病日に死亡した。SECは拡大した左房内での血液うっ滞により生じ,ヒトでは心房内での血栓形成または血栓塞栓症の危険因子と考えられている。獣医学領域ではSECの臨床的意義に関する記載は極めて限られている。本症例はSECが確認されてから613日間生存したことから,血栓予防療法を含む心不全療法が的確に実施されれば,SECは必ずしも予後不良を示す所見ではないと考えられた。
2 0 0 0 IR 識字能力・識字率の歴史的推移 : 日本の経験
- 著者
- 斉藤 泰雄
- 出版者
- 広島大学教育開発国際協力研究センター
- 雑誌
- 国際教育協力論集 (ISSN:13442996)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.51-62, 2012-04
2 0 0 0 OA スウェーデンにおける「良い死」とその文化的・宗教的背景 : ホスピス・緩和ケアに焦点をあてて(欧州における「良い死」の多元性とその文化的・宗教的背景,国内大会ワークショップの概要)
- 著者
- 斉藤 美恵
- 出版者
- 日本医学哲学・倫理学会
- 雑誌
- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.89-90, 2015-09-30 (Released:2018-02-01)
2 0 0 0 OA 数学の哲学におけるレスニクの実在論と構造主義
- 著者
- 斉藤 健
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.149-162, 2004-12-25 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 6
The aim of this paper is to explicate and evaluate Resnik's structuralism in the philosophy of mathematics, and especially to show some difficulties in his theory. Firstly I clarify his main arguments concerning mathematical realism and structuralism. His position has some merits from the points of ontology and epistemology. Then I point out the philosophical implications of his interpretation of mathematical patterns as merely epistemological devices for philosophical explication. By using indispensability argument as a means of justification of mathematical realism, he admits the degree of our commitment to the existence of mathematical objects. Finally I will show that he fails to explain patterns and positions of mathematical structures in category theory.
2 0 0 0 OA 元荒川の生活誌(第二報・最終稿) : 元荒川の川魚料理―川魚料理の献立から
- 著者
- 斉藤 修平 佐藤 ひろみ 中林 みどり 岡本 紋弥
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 生活科学研究 = Bulletin of Living Science (ISSN:02852454)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.129-140, 2014-03-01
元荒川とその周辺の田圃、用水などはかつて川魚資源の宝庫であった。そこから捕獲された淡水魚介類は人々の食生活を彩る食材であった。その食材は伝承された加工・調理によって食卓を賑わしてきた。同時に元荒川沿いに点在する川魚料理店には、元荒川とその周辺で取られていた淡水魚介類が持ち込まれ、おなじく活用されてきた。 本稿では、元荒川沿いでいまも川魚料理店として営業をしている小島家 (岩槻区大戸) 、鮒又 (岩槻区本町) を採訪し、献立として提供している川魚料理を調理依頼し、一品ずつの味つけなどについて伺い、 「元荒川沿いの川魚料理店の現在」 を確認し、提供された川魚料理を賞味、併せて料理人から直接の解説をいただき、それを記録した。同時に淡水魚介類を県内、都内に卸している川魚卸問屋 「鯉平」 を訪ね、現在の川魚料理店への卸状況を紹介した。 川魚料理店では地元の川から種類によっては食材を得ていた時代はかつてあったが、現在は、きわめて限定されたものになっている。鰻はもとより、鯉、なまず、すっぽん、どじょうに至るまで養殖技術が進化したこと、輸入も可能になったこと、活魚の運搬範囲の拡大とスピード化が実現してきたことにより、食材が安定供給されていることがわかった。同時に、川魚料理店は、かつてのように鯉、鮒、鯰、どじょうといった川魚料理の調理機会が激減し、〈鰻一辺倒〉 に近いような献立に変更していったことが判明した。併せて、元荒川からの淡水魚供給はきわめて限定されていることが判明した。
2 0 0 0 情報リンクの基本理念(<特集>情報のリンク)
- 著者
- 斉藤 孝
- 出版者
- 社団法人情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.12, pp.670-677, 1998-12-01
情報リンクとは, 情報と情報を結び付けるもの, また必要な情報に辿り着くための結びつきのことである。情報リンクをかなり広い意味でとらえると図書目録, 索引, 参考調査, 情報検索など情報管理そのものにまで話題が拡散してしまう。そこで, 本稿では情報リンクの技術的側面に的を絞り, その集大成ともいえるハイパーテキストについて触れた。
2 0 0 0 『竹取物語』の虚構性
- 著者
- 斉藤 みか
- 出版者
- 国際基督教大学比較文化研究会
- 雑誌
- ICU比較文化 (ISSN:03895475)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.1-30, 2012-03
- 著者
- 斉藤 綾子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.274-278, 2020
2 0 0 0 OA 市販魚介類およびその加工品中のヒスタミン含有量調査
- 著者
- 観 公子 牛山 博文 新藤 哲也 斉藤 和夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.127-132, 2005-06-25 (Released:2009-01-21)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 7 10
東京都において,ヒスタミンを原因とする食中毒などは,ここ20年間においてほぼ毎年発生しており,いわし,さば,あじなどの赤身魚によることが多い.そこで,ヒスタミンをはじめ5種の不揮発性アミンについて市販の魚およびその加工品637検体について調査をした.また,ヒスタミンの生成は細菌が関与することから水分活性などを測定した.その結果,ヒスタミンが66検体から5~340 mg/100 gの範囲で検出され,その大半はいわし類の干物であった.同時にチラミンが5~51 mg/100 の範囲で43検体,プトレシンが5~42 mg/100 の範囲で26検体,カダベリンが5~180 mg/100 の範囲で64検体およびスペルミジンが5~8 mg/100 の範囲で5検体から検出された.また,ヒスタミンが検出された干物試料の水分活性は0.68~0.96であった.