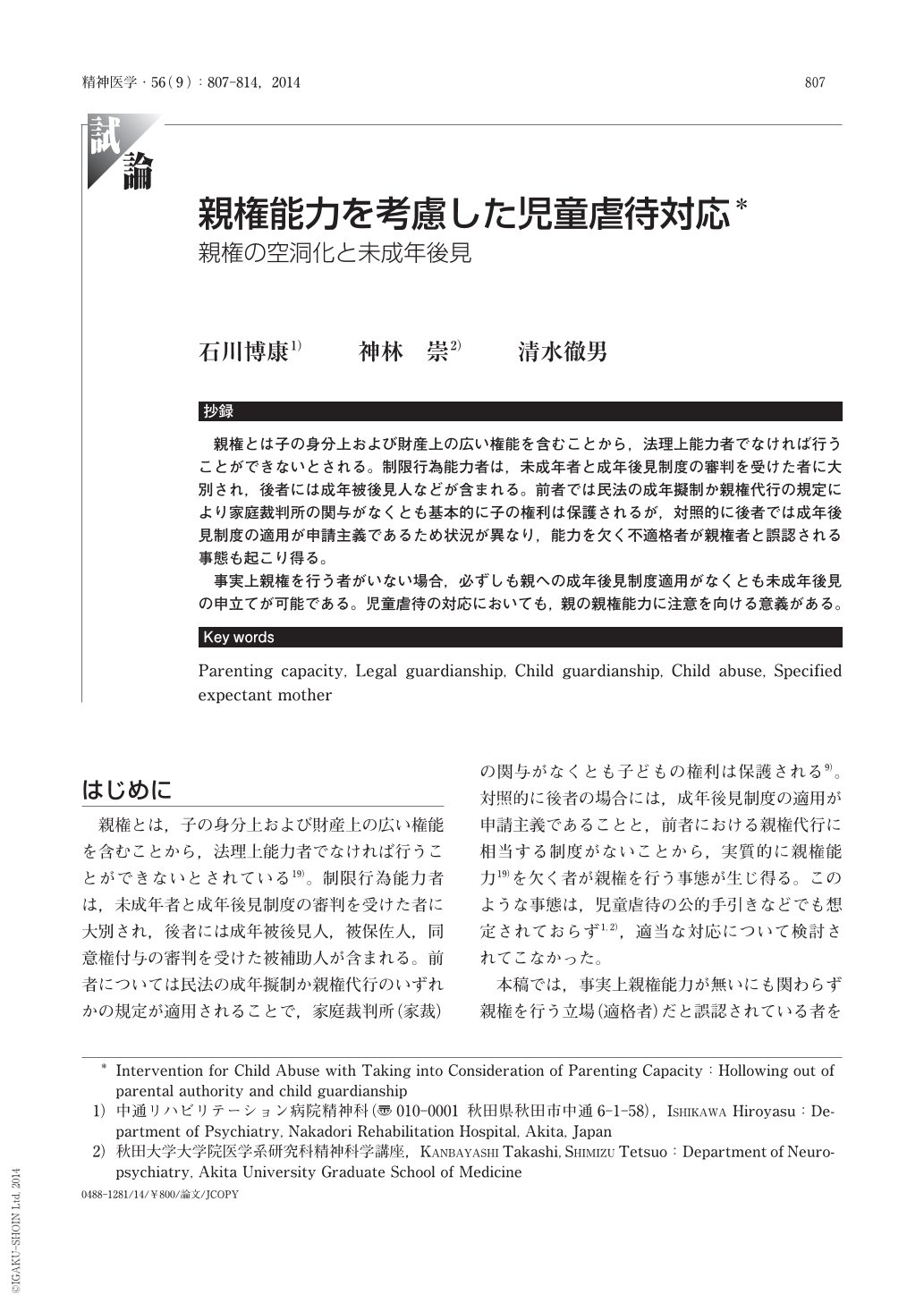1 0 0 0 高度感性情報再現を目的としてスピーカの新設計法と実例
- 著者
- 宮原 誠 石川 智治 小林 幸夫
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. EA, 応用音響 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.235, pp.9-15, 2001-07-20
- 被引用文献数
- 1
高度感性情報再現を目的としたスピーカの新設計理論を示す.高度感性情報とは人に感動を呼び起こすもの(深々さ, 凄み, 実在感など)である.コーン型のスピーカによる電気音響信号の再生(主として低温の再生)は, 制御理論の臨界制動(ζ┤0.7)の考え方を基本とする設計とは全く異なり, むしろ軽く, サスペンションの柔らかい振動板が, 複雑な電気信号に高度高く駆動されるように設計することが重要である.具体的には, 目標をQ_0<0.2, 高周波数帯域はボイスコイル近傍のみを振動板のピストン運動領域とする, などである.又, スピーカが空振りせずに空気をしっかりとらえて, 自由空間に精密な波面を放射させるようなメインアンプも含んだ新しいスピーカ駆動理論を示す.
1 0 0 0 OA 水雲徴
- 著者
- 小林幸次郎 (浅洲) 著
- 出版者
- 小林幸次郎
- 巻号頁・発行日
- 1908
1 0 0 0 OA 共和国の思想と文学-他者との出会い
- 著者
- 松林 昭
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. CAS, 回路とシステム (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.555, pp.19-24, 2005-01-12
グラフを格子に最小の辺負荷で埋め込む問題は, メッセージ交換並列計算機に並列アルゴリズムを効率的に実装する問題等に応用がある.小文では, 効率的に再帰分割可能であるグラフは同じ点数の格子に小さい辺負荷で埋め込めることを示す.特にN点平面グラフがN点格子に辺負荷O(Δ^2logN)で埋め込めること, さらに, グラフが木である場合には辺負荷O(Δ)で埋め込めることを示す.木に対する辺負荷は定数係数の範囲内で最小であり, 平面グラフに対する辺負荷は知られている下界に対してO(min{Δ^2√<logN>, Δlog N})の係数の範囲内で最適である.
1 0 0 0 9 か月間の二酸化硫黄曝露による三宅島小児住民の呼吸器影響
- 著者
- 岩澤 聡子 道川 武紘 中野 真規子 西脇 祐司 坪井 樹 田中 茂 上村 隆元 MILOJEVIC Ai 中島 宏 武林 亨 森川 昭廣 丸山 浩一 工藤 翔二 内山 巌雄 大前 和幸
- 出版者
- Japanese Society of Public Health
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.39-43, 2010
<b>目的</b> 2000年 6 月に三宅島雄山が噴火し,二酸化硫黄(SO<sub>2</sub>)を主とする火山ガス放出のため同年 9 月に全住民に島外避難命令が出された。火山ガス放出が続く中,火山ガスに関する健康リスクコミュニケーションが実施され,2005年 2 月に避難命令は解除された。本研究では,帰島後 1 年 9 か月経過した時点における,SO<sub>2</sub> 濃度と小児の呼吸器影響の関連について,2006年 2 月から11月の 9 か月間の変化を検討した。<br/><b>方法</b> 健診対象者は2006年11月時点で,三宅島に住民票登録のある19歳未満の住民を対象とした。そのうち,受診者は,141人(受診率50.4%)で,33人は高感受性者(気管支喘息などの気道過敏性のある呼吸器系疾患を持つ人あるいはその既往のあり,二酸化硫黄に対し高い感受性である人)と判定された。<br/> 健康影響は,米国胸部疾患学会の標準化質問票に準拠した日本語版の自記式質問票により,呼吸器に関する自覚症状調査,生活習慣,現病歴,既往歴等の情報を収集した。努力性肺活量検査は,練習の後,1 被験者あたり 3 回本番の測定を実施した。<br/> 環境濃度は,既存の地区名を一義的な括りとし,当該地区の固定観測点での SO<sub>2</sub> モニタリングデータをもとに,避難指示解除より健診までの22か月間のデータについて,その平均値により居住地域を低濃度地区(Area L),比較的曝露濃度の高い 3 地域(H-1, H-2, H-3)と定義し,SO<sub>2</sub> 濃度(ppm)はそれぞれ0.019, 0.026, 0.032, 0.045であった。<br/><b>結果</b> 自覚症状では,「のど」,「目」,「皮膚」の刺激や痛みの増加が,Area L と比較すると,H-3 で有意に訴え率が高かった。呼吸機能検査では,2006年 2 月と2006年11月のデータの比較において,高感受性者では%FVC,%FEV1 で有意に低下(<i>P</i>=0.047, 0.027)していたが,普通感受性者では低下は認めなかった。<br/><b>結論</b> 高感受性者では呼吸機能発達への影響の可能性も考えられ,注目して追跡観察していくべきである。
1 0 0 0 IR 握力におよぼす静的ストレッチングの効果
- 著者
- 脇田 裕久 八木 規夫 水谷 四郎 小林 寛道
- 出版者
- 三重大学
- 雑誌
- 三重大学教育学部研究紀要. 自然科学 (ISSN:03899225)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.141-148, 1985
The stretching effect on the repeated exertion of maximum hand grip strength were investigated when the wrist joint stretching was added in different muscle groups and/or different frequencies. The subjects were six healthy males aged 18-22 years. They were asked to exert their maximum hand grip strength for 6 seconds, 20 times with 1 minute intervals between each bout. Subjects performed 6 series of experiments in different interval conditions such as, Condition-A : hold resting during each enterval, B : add stretching of dorsi-flexion (7 sec×4 times), C : add stretching of palmar flexion (7 sec×4 times), D : add stretching both palmar and dorsi-flexions, alternately (7 sec×2 times each), E : hold resting until 10th trial, and then add stretching to 20th trial in the same way as in Condition-D during each interval, F : add stretching once every 5 intervals in the same way as in Condition-D. Following results were obtained. 1) No significant differences in average impulses (kg・sec) of 20 times in maximum hand grip strength were found among different conditions. 2) The greater impulses in 11-20th trials were observed in Condition-C and -D in comparison with Condition-A (p<0.05). 3) The impulses in Condition-D were greater than Condition-B in 16-20th trials (p>0.05). 4) The greater impulses were observed in 11-20th trials for Condition-D and -F in comparison with Condition-A (p<0.05). 5) The impulses in 11-15th trials were greater in Condition-F than Condition-E (p<0.05). Therefore, stretching of palmar flexion or, both palmar and dorsi-flexions are effective to prevent the decrease of hand grip strength. Stretching of every 5 trials of 20 maximum bouts is equally effective with that of every one trial.健康な男子大学生6名(18-22歳)を被検者とし、1分間の休息期をはさみながら最大努力で6秒間の握力発揮を20試行繰り返させ、手関節へのストレッチングが握力発揮にどう影響するかを、方法、時期、頻度を違えて実施した。各試行間の休息期には、毎回安静休息を保つ条件(A)、と静的ストレッチングを加える条件(B~F)があり、後者には毎回手関節の背屈方向のみ(B)、掌屈方向のみ(C)、背屈・掌屈双方(D)、第10試行まで安静休息、その後毎回背屈・掌屈双方(E)、第5、10、15試行後にのみ背屈・掌屈双方(F)の5条件とし、合計6条件を指示した。本実験結果は、次のようである。 1)各条件下における全試行の平均力積は、いずれの条件間にも有意な差が認められなかった。 2)第11-20試行では、条件C、Dが条件Aより有意に大きな力積を示した(P<0.05)。第16-20試行では、条件Dが条件Bに比較して有意に大きな力積を示した(P<0.05)。 3)第11-20試行では、条件D、Fが条件Aより有意に大きな力積を示した(P<0.05)。第11-15試行では、条件Fが条件Eに比較して有意に大きな力積を示した(P<0.05)。 以上の結果から、休息期に毎回掌屈または背屈・掌屈双方の静的ストレッチを加えることは、安静休息を保つ場合に比較して、握力低下の抑制に効果的であり、また、その効果については、5試行ごとに加えられた静的ストレッチングと毎回のそれとの間に差のないことが明らかとされた。
1 0 0 0 送変電用避雷器適用による電力供給の高信頼化
日本およびメキシコにおける避雷器適用による電力供給の高信頼化を図るために、両国の研究者が共同し、送電線用避雷器設置効果のシミュレーション、変電所用避雷器の人工汚損実験などを実施した。具体的成果を以下にまとめる。1.メキシコ首都電力電灯公社および国家電力庁を訪問し、雷事故および避雷器に関して討論・調査を行った。雷事故記録に関する資料を入手するとともに、400-kV変電所などにおいて避雷器の設置状況の実地調査を実施した。2.4回線併架送電線を対象とし、避雷器の設置個数・場所と避雷効果との関連をEMTP(過渡現象解析プログラム)を用いたシミュレーションにより評価した。避雷器の設置個数が多いほど効果的ではあるが経済性も含めた検討が必要であること、同じ設置個数の場合には効果的な設置場所があること、がわかった。また、接地抵抗や雷道インピーダンスに関する評価も実施した。3.変電所用避雷器の人工汚損試験を実験室で行い、避雷器がい管の抵抗を8つの部分に分けて抵抗の時間変化を測定した。避雷器表面は全体が時間とともに一様に乾燥して行くのではなく、ある部分のみが乾燥し、他の部分は湿潤したままであることがわかった。4.前項の試験結果を基に避雷器表面抵抗の時間変化を数式で表わし、避雷器の物理・数学モデルを構築して避雷器表面および内部素子の電位・温度分布の時間変化をシミュレーションにより求めた。表面が乾燥する部分の分担電圧がかなり大きくなるが、素子損傷に至るほどの素子温度は上昇しないことがわかった。また、がい管と内部素子との間の放電発生を想定しても、素子損傷には至らないことがわかった。5.実験室で避雷器碍管表面の電位分布を実測する方法を調査・検討し、ポッケルス効果を利用した光電界センサが適しているとの結論に達した。発・受光回路の設計・製作をして動作を確認した。
1 0 0 0 違憲な条件の法理の展開(1)
- 著者
- 中林 暁生
- 出版者
- 東北大学法学会
- 雑誌
- 法学 (ISSN:03855082)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.491-519, 2009-10
1 0 0 0 豊公能《高野参詣》制作上演の背景 (特集 十六世紀の文学)
- 著者
- 小林 健二
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 文学 (ISSN:03894029)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.5, pp.132-143, 2012-09
1 0 0 0 OA タンパク質ドメイン構成に基づくプロテオーム圧縮
- 著者
- 林田守広 阮佩穎 阿久津達也
- 雑誌
- 研究報告数理モデル化と問題解決(MPS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014-MPS-100, no.11, pp.1-2, 2014-09-18
生物は進化の過程において,突然変異や組み換えなどによって DNA の塩基配列情報を変化させながらも自らの生命を維持させてきた.生物の持つ情報を DNA の塩基配列とすると,この配列を圧縮することによって大体の情報量を知ることができる.本研究では塩基配列の代わりにタンパク質ドメイン構成に基づき,個体の持つすべてのタンパク質について圧縮する.遺伝子重複や遺伝子融合などの進化現象により同じドメイン構成を持つタンパク質が複数生成されるとすると,複製元のタンパク質を参照することでデータ量を減らすことができる.このような参照によるネットワークは有向ハイパーグラフとなり,多数の参照候補を持つグラフから最小大域木を見つけることで圧縮する.しかし現実的な時間での,ハイパーグラフからの最小大域木の抽出は困難であるので,前処理としてハイパーエッジを削減する発見的な手法を提案する.本手法を数種の生物種に適用した結果,タンパク質進化における遺伝子融合の重要性が示唆された.
1 0 0 0 OA 新規ヘテロ芳香族化合物の合成を基盤とした高性能両極性有機発光トランジスタの開発
高性能両極性有機発光トランジスタの開発を目指し、電子供与性部位であるフラン環と、電子受容性部位であるピラジン環またはキノン環を併せもつ新規ヘテロ芳香族化合物を合成し、その構造物性評価を行った。フラン環については、縮環向きの異なる二種類の構造異性体を比較した。薄膜の結晶性が低かったために、合成した試料からなる薄膜の電荷移動度は低い値しか観測されなかったが、一方で予想外に高い固体蛍光量子収率を示した。これは、凝集誘起発光とよばれ、近年おおいに注目されている。この理由は、エキシマー蛍光の効率性の向上、ならびに結晶状態における分子運動の抑制ということに起因する。
1 0 0 0 OA 電気自動車生産システムの事例研究 : 日中国際比較
- 著者
- 小林 英夫
- 出版者
- 早稲田大学日本自動車部品産業研究所出版・編集委員会
- 雑誌
- 早稲田大学日本自動車部品産業研究所紀要 (ISSN:18831494)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.3-26, 2009-11
- 著者
- 濱野 周泰 近藤 三雄 濱野 周泰 小林 達明 柴田 昌三
- 出版者
- 社団法人日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.143-150, 2001-11-09
1 0 0 0 親権能力を考慮した児童虐待対応―親権の空洞化と未成年後見
抄録 親権とは子の身分上および財産上の広い権能を含むことから,法理上能力者でなければ行うことができないとされる。制限行為能力者は,未成年者と成年後見制度の審判を受けた者に大別され,後者には成年被後見人などが含まれる。前者では民法の成年擬制か親権代行の規定により家庭裁判所の関与がなくとも基本的に子の権利は保護されるが,対照的に後者では成年後見制度の適用が申請主義であるため状況が異なり,能力を欠く不適格者が親権者と誤認される事態も起こり得る。 事実上親権を行う者がいない場合,必ずしも親への成年後見制度適用がなくとも未成年後見の申立てが可能である。児童虐待の対応においても,親の親権能力に注意を向ける意義がある。
- 著者
- 小林 公幸
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.34-37, 2014-08
1 0 0 0 日本語版IPANAT作成の試み
- 著者
- 下田 俊介 大久保 暢俊 小林 麻衣 佐藤 重隆 北村 英哉
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.3, pp.294-303, 2014
- 被引用文献数
- 7
The Implicit Positive and Negative Affect Test (IPANAT) is an instrument for the indirect assessment of positive and negative affect. A Japanese version of the IPANAT was developed and its reliability and validity were examined. In Study 1, factor analysis identified two independent factors that could be interpreted as implicit positive and negative affect, which corresponded to the original version. The Japanese IPANAT also had sufficient internal consistency and acceptable test–retest reliability. In Study 2, we demonstrated that the Japanese IPANAT was associated with explicit state affect (e.g., PANAS), extraversion, and neuroticism, which indicated its adequate construct validity. In Study 3, we examined the extent to which the Japanese IPANAT was sensitive to changes in affect by assessing a set of IPANAT items after the presentation of positive, negative, or neutral photographs. The results indicated that the Japanese IPANAT was sufficiently sensitive to changes in affect resulting from affective stimuli. Taken together, these studies suggest that the Japanese version of the IPANAT is a useful instrument for the indirect assessment of positive and negative affect.
- 著者
- 手林 佳正
- 出版者
- 日本臨床心理学会
- 雑誌
- 臨床心理学研究 (ISSN:00355496)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.56-62, 1996-03
1 0 0 0 アレルギー性気道炎症における気道温度の測定とモニタリングの開発
気管支喘息に代表されるアレルギー性疾患は,アレルギー性炎症疾患として捉えられている.古典的な炎症の定義から考察するとアレルギー性炎症として「発熱」という現象に対する検討はまだされていない.そこで,気道炎症の「発熱」を呼気温度の測定にて捉え得るのではないかと着目し,基礎的検討を行った.フローボリウム測定と瞬時に温度変化を捉えられる高感度温度計を組み合わせ,はじめに安定した測定条件の検討を行った.最大吸気から呼出までの条件,最大呼気条件による呼気測定の温度センサーの位置をマウスピースの中央,マウスピースより咽頭側,鼻マスクで検討を行った.この結果最大吸気後ゆっくりとゆっくり呼出させる方法で,温度センサーをマウスピースを咽頭側で測定した際,最も安定した測定値が得られた.次に単位面積当たりの熱エネルギー量(W/cm^2)を表す呼気熱流速と呼気温度のピーク値の体温補正値(呼気温度測定値と体温の比で表したもの)を健常者の各条件で比較した.その結果,呼気熱流速は呼気温度に比べて温度変化に敏感な値を示した.さらに呼気温度のピーク値は性別や喫煙の有無で差が認められたが,熱流速には差を認めなかった.呼気温度と呼気熱流速の両方を用いることで気道炎症の新しい指標になりうると考えられた.
1 0 0 0 解析関数空間上の作用素の構造とその不変部分空間の研究
研究代表者は(共同研究で)次の研究成果を得た。1)バイデスク上のハーデイ空間の不変部分空間において、zの掛け算作用素とwの掛け算作用素の共役作用素の交換子がランク1になる場合を調べ、ある条件の下で完全に決定することができた。同様に圧縮作用素S_zとS_wの交換子がランク1になるときの逆不変部分空間を決定した。2)有界解析関数空間の合成作用素の差の本質ノルムの上界と下界の評価式を与えた。また、加重合成作用素の差がコンパクトになるときの特徴づけを与え、位相構造を調べた。3)2次元のFock空間の中で主導項をもつ多項式の研究を行い、それに付随する準不変部分空間が相似になるときを決定した。4)1変数のハーデイ空間上で、ハンケル作用素の積がハンケル作用素のコンパクトな摂動となるときの特徴づけを与えた。5)有界解析関数環における、閉素イデアルに関するゴルキン・モルチニの問題の部分解を与えた。6)互いに特異である、単位円周上の特異測度に対して、その絶対連続測度に対応する特異内部関数の共通零点集合が互いに素であることを示した。またモルチーニ・ニコラウの特異内部関数のフロストマンシフトに関する2つの問題を解決した。中路氏は、可換持ち上げ定理はバイデスク上のハーデイ空間の2つの圧縮作用素の場合でも成立しないが、しかし多くの圧縮作用素では、可換持ち上げ定理が成立することを示した。大野氏は単位開円板上の有界調和関数空間上のハンケル型作用素のコンパクト性、完全連続性の特徴づけを行い、そのときのシンボルを決定した。また合成作用素の本質ノルムを決定した。その上ブロック空間上の2つの合成作用素の差のコンパクト性を特徴づけた。
1 0 0 0 質量,熱,運動量輸送に関する乱流制御
- 著者
- 林 農 HIGUCHI H. KLICK Heiko LAMPARD D. LICHTAROWICZ エー CLAYTON B.R. CHOI KwingーS 田辺 征一 若 良二 河村 哲也 望月 信介 大坂 英雄 LAMPARD Desmond HIGUCHI Hiroshi
- 出版者
- 鳥取大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1995
本国際共同研究は、イギリス、ドイツ、及びアメリカの研究グルプと、本年13周年を迎えた西日本乱流研究会の研究者達が協力して、それぞれが既に研究成果を挙げ十分なデータを蓄積している運動量、熱及び質量輸送に関する実験結果を相互に交換して、これらに共通する基本原理を明らかにすることを目的としたものである。本共同研究の開始に先立つ4年前、研究代表者の林は文部省在外派遣研究員として、1991年8月から4ヶ月間ドイツ・ルール大学ボフム校に滞在し、K.Gersten教授及びHeiko Klick氏と遷移境界層中に発達する温度境界層に関して共同研究を行った。引き続き、1991年12月から4ヶ月間イギリス・ノッチンガム大学に滞在して、Kwing-So Choi博士とリブレット平面上に発達する境界層内の伝熱促進に関して共同研究を行った。その際、ノッチンガム大学のB.R.Clayton教授及びルール大学のK.Gersten教授の勧めもあって、3国間での資料交換についての国際共同研究を申請することに合意し、国内外研究者の組織化を進めた。その結果、幸いにも、平成7年度文部省科学研究費補助金国際学術研究に採択いただき、国際共同研究を実施する運びとなった。国際学術研究・共同研究では、国内の研究者グループと国外の研究者グループの対等の立場での研究者交流が重要な柱となっているので、本共同研究においても、研究経費は各研究機関の負担によることとし、研究者の交流による討論及び外国研究機関での研究に主眼をおいて学術交流を推進した。本共同研究の目的である討論をより深めるためには、各々の研究者が国内外の各地に点在する大学や研究所を訪問し互いの実験結果を比較し検討するよりは、経費と時間を有効に使うためにワークショップなりセミナーの形式を採用して多くの研究者が一堂に会して、課題の本質について討議することの方が能率良く且つ実り多い結果が得られると感じられたので、共同研究の実施期間である平成7年度中に、2度の 「質量,熱,運動量輸送の乱流制御」 に関する国際会議を開催した。一つは、1995年10月6日に鳥取大学において開催した国際交流セミナー 「質量,熱,運動量輸送に関する乱流制御」 であり、B.R.CLAYTON教授、Kwing-So CHOI助教授及びHeiko KLICK博士の3名に加えて、国際的学者である東京大学・笠木伸英教授及び名古屋大学・中村育雄教授、国内の研究グループである西日本乱流研究会の多くの研究者達が討論に加われるように配慮して、検討を十分掘り下げることができた。他の一つは、1995年8月22日にイギリス・ノッチンガム大学において開催したOne-day Colloquium 「Techniques in Turbulence Management of Mass,Heat and Momentum Transfer」 であり、西日本乱流研究会からも特別講師として、研究代表者の林農教授、研究分担者の大坂英雄教授、河村哲也教授、田辺征一教授が招かれて、ノッチンガム大学のスタッフのみならず、イギリス各地の大学、研究所、企業から集まった乱流制御問題に関心のある研究者達及び別途日本から参加の岐阜大学・福島千尋助手及び日本原子力研究所の秋野詔夫主任研究員らを交えて活発な意見交換が成され,十分な成果をあげることができた。また、河村哲也教授は、短期間であるが共同研究の相手先であるノッチンガム大学工学部機械工学科に滞在して、リブレット付き平板上に発達する境界層の数値シミュレーションに関する研究を行った。研究分担者の鳥取大学・若 良二教授もノッチンガム大学短期滞在中に乱流計測技術の調査研究についての成果を得た。今回の共同研究の結果として、本研究に加わったイギリス・ノッチンガム大学及びアメリカ・シラキュース大学と鳥取大学との大学間交流協定を締結する準備が進展している。したがって、ノッチンガム大学とはリブレット付き平板上の境界層の発達と熱伝達促進に関する共同研究を、シラキュース大学とは円柱後流の干渉とウェーブレット解析に関する共同研究を、大学間協力研究として、近い将来の文部省科学研究費補助金国際学術研究に申請するよう計画しているところである。