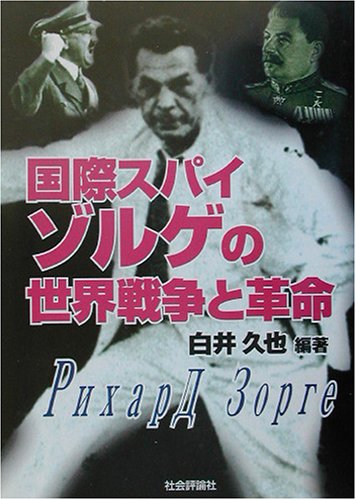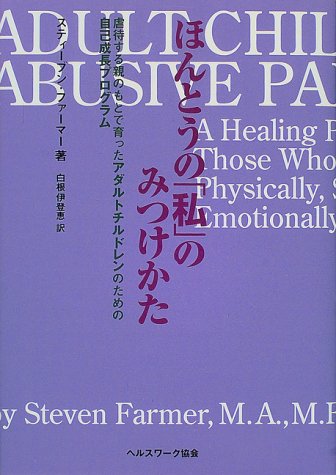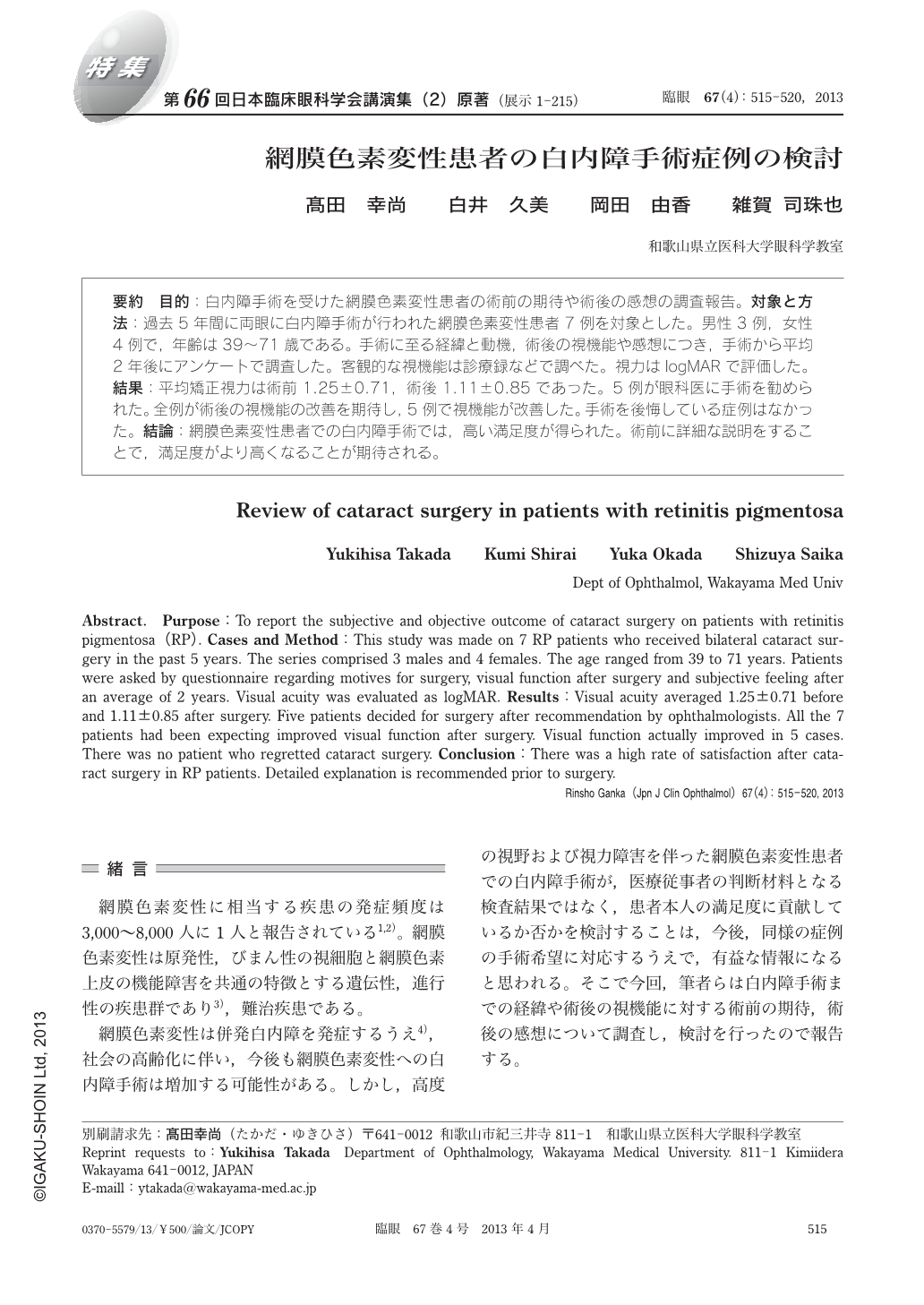1 0 0 0 OA 投球障害肩における関節窩にかかる応力分布の解析
- 著者
- 夏 恒治 望月 由 平松 武 柏木 健児 安達 長夫 菊川 和彦 白川 泰山 大前 博路 横矢 晋 奥平 信義
- 出版者
- 日本肩関節学会
- 雑誌
- 肩関節 (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.453-457, 2004-08-30 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
CT-osteoabsorptiometry gave us the information about the distribution of mineralization of subchondral bone plate (DMSB). DMSB reflected the stress distribution of joint surface. We analyzed the stress distribution of glenoid cavities in throwing injures of the shoulder by CT-osteoabsorptiometry. Twenty eight patients with throwing injuries of the shoulder,24 patients with other shoulder disorders, and 4 healthy volunteers without any shoulder disorders were evaluated in this study. Group T included 28 affected shoulders of patients with throwing injuries of the shoulder. Group C included 60 non-affected shoulders of all subjects. Three dimensionally reconstructed computed tomograms (3D-CT) and DMSB of the glenoid cavities were filmed before the series of treatment. The glenoid cavity was divided into 7 areas; anterior-superior, anterior, anteriorinferior, posterior-inferior, posterior, posterior-superior and center area. The value of each area was classified into 4 grades. In group C, the mean value of the anterior-superior areas was significantly higher than those of the other areas. Meanwhile in group T, the highest mean value was that of the anterior-superior area. However, the mean values of anterior, posterior, and posterior-inferior areas were significantly higher than those of group C. The form of glenoid cavity in group T evaluated by 3D-CT showed the posterior and posterior-inferior enlargement of the glenoid cavity, which could be interpreted as a Bennett's lesion. Our results supported the hypothesis that a Bennett's lesion would be a reactive bone growth against stress onto the glenoid cavity.
1 0 0 0 OA 若年型家族性黒内障性白痴の2例
- 著者
- 白髭 郁子
- 出版者
- Okayama Medical Association
- 雑誌
- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.2-3, pp.365-386, 1966-03-30 (Released:2009-02-13)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 1
Two cases of the juvenile form of amaurotic family idiocy were described in the present communication. 1) Case 1 was a 11-year-10-month boy. His family history had consanguinities. He was slightly deteriorated before the onset of the disease. At the age of 5 years, the ataxia of gait was initially manifested. Later there developed the progressive mental deterioration and the “Blitz-Nick- Salaam Krämpfe”. On neurological examinations the marked cerebellar syndroms (ataxia, intention-tremor and hypotonia), the involuntary movements and the narrowing of the ocular vessels could be recognised. Case 2 was 10-year-7-month girl. Her two brothers died of amaurotic family idiocy. She had been healthy until she complained of the myoclonic contractions of the tips of the fingers. The mental deterioration, the convulsive seizures and the visual disturbances were gradually appeared. The neurological examinations showed the involuntary movements, the hypotonia, the optic atrophies and the retinal degeneration. Both patients died six years after the onset of the disease. 2) The autopsy findings of the brains in both cases revealed macroscopically the generalised atrophy and the increased consistency. Microscopically the essential changes were observed in the neuronal swelling and the lipidosis. These changes were distributed ubiquitously throughout the central nerves system and were most markedly in the cerebral cortexes, decreasing by degrees caudally. Furthermore in the case 1, the severest damage was seen in the cerebellar cortex. In the cerebellum of case 1, the entire nerve cell elements except Golgi's cells and the nerve fivers were almost completely obliterated. The swelling of axons in the the cerebral cortexes was recognised in both cases. too. 3) The findings of the organs such as liver, spleen and others in case 2 revealed no lipid accumuration as seen in Niemann-Pick's disease. There were observed the degeneration of the retinal outer layer which was characteristic of the juvenile form of the disease. 4) From the results of the histochemical observations in both cases it was concluded that the intraneuronal substances consisted of the mixture of the sphingomyelin and PAS-positive substances that might be the glycolipid. A part of them and the substances in the fat granulle cells were assumed to be combined with the protein. 5) Above mentioned results, the clinical, the histological and the histochemical findings in both cases indicated the jnvenile form of the disease. In case 1 there would be the developmental anomaly of the brain beside the essential chages of amaurotic family idiocy.
1 0 0 0 国際スパイ・ゾルゲの世界戦争と革命
1 0 0 0 OA フランスにおける音楽著作権保護と管理の史的展開
- 著者
- 石井 大輔 Daisuke ISHII 目白大学社会学部メディア表現学科
- 雑誌
- 目白大学総合科学研究 = Mejiro journal of social and natural sciences (ISSN:1349709X)
- 巻号頁・発行日
- vol.(6), pp.23-34, 2010
1 0 0 0 OA 土壌中における重金属の行動
- 著者
- 白鳥 孝治
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.228-234, 1974-04-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 木材のプラスチック化
- 著者
- 白石 信夫
- 出版者
- The Society of Fiber Science and Technology, Japan
- 雑誌
- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.P95-P101, 1983-03-10 (Released:2008-11-28)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 3 4
1 0 0 0 IR 高齢者における公共トイレのニーズと方向性
- 著者
- 城 憲秀 藤丸 郁代 山口 知香枝 白石 知子 宮武 真生子 堀 文子
- 出版者
- 中部大学生命健康科学研究所
- 雑誌
- 生命健康科学研究所紀要 (ISSN:18803040)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.73-80, 2018-03
高齢者の公共トイレに対するニーズを把握し、今後の公共トイレのあり方を検討することを目的として、愛知県K市内の高齢者768名を対象とする横断調査を実施した(回収率 約74%)。高齢者全体として、散歩などの外出時にはトイレに行かない者が全体の35%程度存在し、公共トイレの普及はなお必要であることが示唆された。また、清潔さや広さなどがトイレの質的なニーズとしてあげられており、公共トイレは質、量の両者の整備が重要である。また、高齢になるほどトイレの場所がみつけにくいことが明らかとなり、トイレの場所表示もわかりやすくしていくべきである。有疾患者、女性、後期高齢者では手すりの要求が高く、身体面でハンディキャップがある場合、身体動作をスムーズにするガイドも必須である。公共トイレの充実は、高齢者の外出を促進するために重要な要件であると考えられ、今回調査したようなニーズを考慮し、質、量を充足していくことがバリアフリー社会の構築のためには必要である。
- 著者
- スティーブン・ファーマー著 白根伊登恵訳
- 出版者
- IFF出版部ヘルスワーク協会
- 巻号頁・発行日
- 2000
1 0 0 0 IR 戦場の記憶、兵士の眼差し : 浜田知明とW・D・エアハートの作品から
- 著者
- 白井 洋子
- 出版者
- 日本女子大学
- 雑誌
- 日本女子大学紀要. 文学部 (ISSN:02883031)
- 巻号頁・発行日
- no.64, pp.33-53, 2014
1 0 0 0 IR ホロコースト下のユダヤ人の子どもたち─オランダを中心に─
- 著者
- 青島 有里 Yuri AOSHIMA 目白大学短期大学部ビジネス社会学科
- 出版者
- 目白大学短期大学部
- 雑誌
- 目白大学短期大学部研究紀要 = Memoirs of Mejiro University College (ISSN:13462210)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.171-184, 2014
1 0 0 0 網膜色素変性患者の白内障手術症例の検討
- 著者
- 髙田 幸尚 白井 久美 岡田 由香 雑賀 司珠也
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床眼科 (ISSN:03705579)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.515-520, 2013-04-15
要約 目的:白内障手術を受けた網膜色素変性患者の術前の期待や術後の感想の調査報告。対象と方法:過去5年間に両眼に白内障手術が行われた網膜色素変性患者7例を対象とした。男性3例,女性4例で,年齢は39~71歳である。手術に至る経緯と動機,術後の視機能や感想につき,手術から平均2年後にアンケートで調査した。客観的な視機能は診療録などで調べた。視力はlogMARで評価した。結果:平均矯正視力は術前1.25±0.71,術後1.11±0.85であった。5例が眼科医に手術を勧められた。全例が術後の視機能の改善を期待し,5例で視機能が改善した。手術を後悔している症例はなかった。結論:網膜色素変性患者での白内障手術では,高い満足度が得られた。術前に詳細な説明をすることで,満足度がより高くなることが期待される。
1 0 0 0 OA 肢体不自由特別支援学校におけるタブレット端末の活用
- 著者
- 白石 利夫
- 出版者
- 日本デジタル教科書学会
- 雑誌
- 日本デジタル教科書学会発表予稿集 日本デジタル教科書学会第7回年次大会 (ISSN:24326127)
- 巻号頁・発行日
- pp.35-36, 2018 (Released:2018-10-03)
- 参考文献数
- 2
障害を持つ児童生徒にとってICT機器は、学習や生活の幅を広げる大きな力になる。しかしながら、効果的に利用するには、どのように利用するかを検討していく、フィッティングが大変重要である。本発表では、肢体不自由児が機器の利用の仕方を自分で比較検討を行うことができるようになることを目的として教員と一緒に利用の仕方を考えていく、学習会を行ってきた実践について報告する。
1 0 0 0 ARを用いた仏像の模刻制作手法の確立とその教育的効果の研究
平成29年度はARのソフトウェアにおける精度検証や、様々なデバイスでの動作検証を行った。iPad、iPhoneといったタブレット用のソフトウェアも今では充実し、簡易な操作でARを試すことが可能になった。特にその中でENTiTiというソフトウェアを利用し検証を行った。まず実際の像と3Dデータの位置が正確にマッチングするかどうかの精度検証を行った。不規則な模様をプリントしたものをターゲットとして実際の像の下に配置し、同様に3Dデータ上でも同じ位置にくるようにターゲットをセッティングする。その設定でARとして実写と3Dデータを合成してみると、ターゲットに近い下の方は問題ないが、上部に行くにつれて誤差が大きくなっていくのが確認できた。つまり床置きの平面のターゲットの場合、高さ方向に対してのパースの歪みは補正することができないことが原因だと考えられる。今度ターゲットの置き方やマルチターゲットといった機能について今後研究を進めていく必要がある。またヘッドマウントディスプレイHTC社ViveやMicrosoft HoloLensにおいても本研究で使用可能性かどうか検討を行った。Viveは実写合成を行ってはいないが、任意視点や空間移動にまで対応しており、デバイスを付けたり外したりするわずらわしさがあるものの、実際の像と3Dデータの確認は可能ではある。HoloLensではそれに加えてデプスセンサーや環境認識カメラを用いて3D空間をスキャンすることで空間認識しており、より高い精度で表示することが可能であると考えている。
1 0 0 0 OA 深層学習に基づく迅速評価手法を用いたダイズ個葉の気孔密度に関する遺伝的変異の解明
- 著者
- 和田 武真 松尾 彰文 白井 克佳 冨田 智子 岩間 秀子 平野 一成 佐藤 秀明 堀居 昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.58, 2007
1 0 0 0 OA 高齢入院患者における血清アルブミン値と発熱頻度及び死亡率との関連
- 著者
- 池松 秀之 鍋島 篤子 山家 滋 山路 浩三郎 角田 恭治 上野 久美子 林 純 白井 洸 原 寛 柏木 征三郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.12, pp.1259-1265, 1996-12-20 (Released:2011-09-07)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 5 4
高齢長期入院患者における発熱や死亡のハイリスクグループのマーカーを検索するために, 観察病院において1年以上入院した患者478名を対象として, 血清アルブミン値と発熱及び死亡との関連について検討を行なった.対象の平均血清アルブミン値は3.79g/dlで, 加齢と共に漸減傾向を示した.延べ504,189日の発熱の調査結果より得られた各患者の平均年間発熱回数と血清アルブミン値の関連は, 血清アルブミン値4.1g/dl以上の群の平均発熱回数が最も低く1.8回/年で, 血清アルブミン値の低下に従って段階的に上昇し, 3.0g/dl以下の血清アルブミン値著明低下患者では5.3回/年であった.年齢補正後の死亡率は, 血清アルブミン値3.0g/dl以下の群が40.4%で, 他の3群の13.0%~19.8%に比し著しく高率であった.血清アルブミン値3.0g/dl以下の群では死亡率はどの年齢層においても高率であったが, 他の3群においては, 80歳以上で死亡率が高かった.血清アルブミン値4.1g/dl以上の群をcontrol群として求めたrelativeriskは, 血清アルブミン値3.0g/dl以下の群では発熱で2.9, 死亡では2.0であった.以上の結果より, 血清アルブミン値は, 高齢期入院患者における, 発熱や, 1年後以降に生じる死亡の予測因子として有用であり, 特に血清アルブミン値3.0g/dl以下の患者は発熱, 死亡のハイリスクブループであると考えられた.
1 0 0 0 OA ストレス・コーピングと飲酒行動(1997年/第38回日本心身医学会総会/東京)
- 著者
- 白倉 克之
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.301-308, 1998-06-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 13
近年わが国のアルコール依存症者数の増加傾向が指摘され, 依存症者およびアルコール関連問題を有する患者数は, 全国で約230万ないし250万人に達すると推定されている.事実アルコール依存症者像についても, 30数年前の中年ブルーカラー男性という固定したイメージは払拭され, 産業メンタルヘルス領域で問題とされる「職場の3A」の一つとして, ホワイトカラー族はいうに及ばず, キッチン・ドリンカーという造語にみられるように家庭婦人やOLなどの女性患者, 最近では未成年者や高齢者にもその急増が指摘されるなど, アルコール依存症ないしアルコール関連問題を抱える患者層の多様化が顕著となっている.一方では近年の国民医療費の急増, 高齢化・少子化現象に基づく就労人口の激減などに直面している事実に鑑み, アルコール問題は早急に解決されなければならない焦眉の社会問題の一つといっても過言ではない.厚生省も従来の成人病という概念を修正して, 1996年より生活習慣病という概念を導入し, がん・脳血管障害・高血圧症・糖尿病などとともにアルコール症についてその対策や予防に全力を傾けている状況である.以上のような状況に鑑み, 本稿では前半でアルコール医療について簡単に解説するとともに, 後半ではストレス・コーピングの立場から飲酒行動について述べてみたい.
1 0 0 0 OA 中国支部だより 海底ケーブル調査の精度向上に向けた取組み
- 著者
- 白井 秀幸
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.10, pp.748-749, 2014-10-10 (Released:2014-10-24)
1 0 0 0 OA 無機材料の組成式を元にした物性予測のための記述子開発
- 著者
- 佐方 冬彩子 小寺 正明 田中 健一 中野 博史 浮田 昌一 白沢 楽 冨谷 茂隆 船津 公人
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会・情報化学部会
- 雑誌
- Journal of Computer Aided Chemistry (ISSN:13458647)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.7-18, 2018 (Released:2018-09-27)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 5
材料開発において未知の材料を効率的に探索するには、組成の情報のみから物性を予測する手法の開発が必要である。本研究では、無機材料の組成式を記述子に変換して説明変数とし、物性との関係を表す回帰モデルを構築した。さまざまな物性の予測に対応できるよう情報を損失なく変換するために、組成式中の各元素の個数や割合を表す記述子、原子量、原子半径、電気陰性度といった元素の物理学的パラメータを使用した記述子など、合計387個の記述子を提案した。ケーススタディとして、これらの記述子を用いてRandom Forestによるモデルを構築し、結晶の生成エネルギー、密度、屈折率という3種類の物性の予測を行って R2 値がそれぞれ 0.970、0.977、0.766という結果を得た。また、統計的に選択されそれぞれの物性予測モデルの構築に寄与した記述子が、化学的知見から考えても妥当なものであったことからこの手法の有用性を確認した。