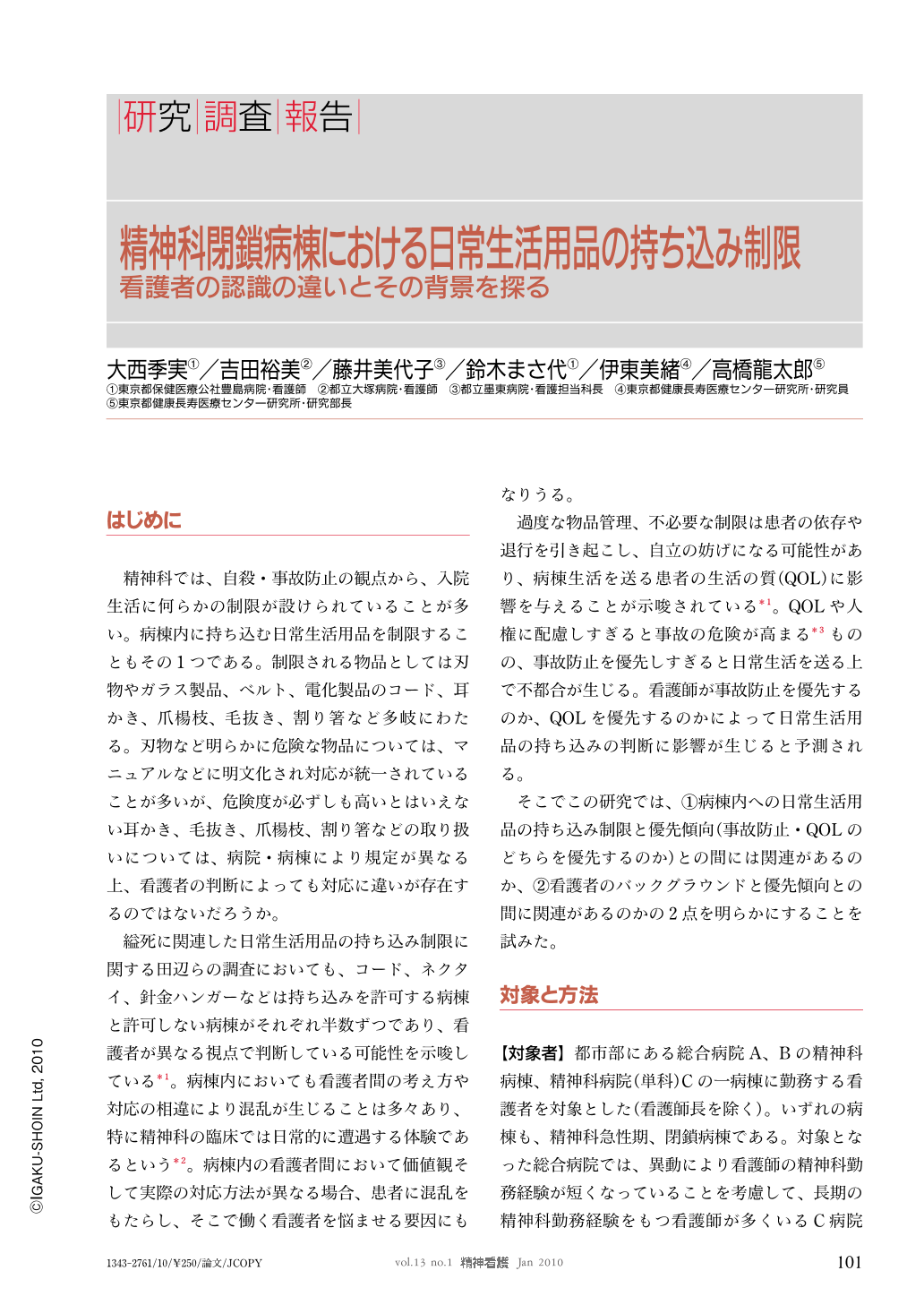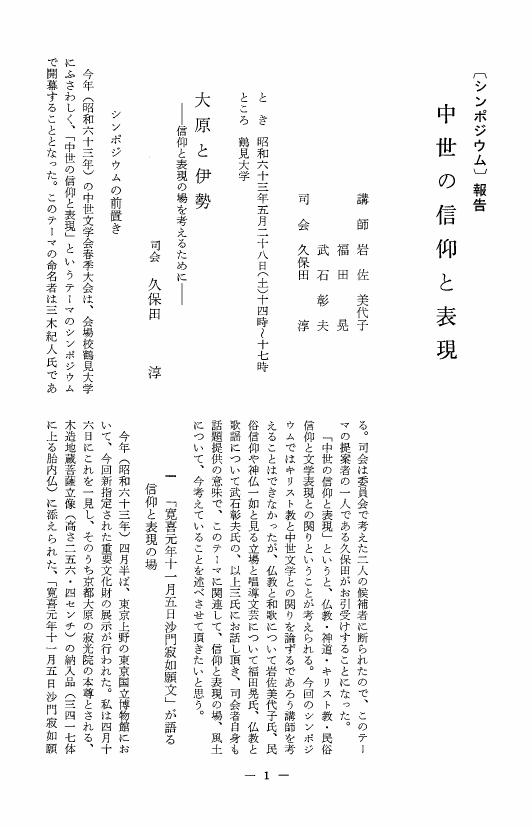1 0 0 0 ささやき声におけるアクセントの知覚的, 音響的, 生理的特徴
1 0 0 0 「出会い」が人生を変える(音叉)
- 著者
- 杉藤 美代子
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.181-182, 2008
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 ストマイのゴム栓利用
みな樣方のお勤めになられる病院の内に,ストレプトマイシンの使用後の空びんを,大切に保存なされる所もあるかは存じませんが,数多い所では,無益にお捨てになる所もあると存じます。当院もその一例にもれません。 その無益に捨てますストマイの空びんを,一寸拾い上げてみて頂きたいのでございます。そう大して時間はかゝりません。空びんの口に挾みを入れてゴム栓をはずしてはがしたゴム栓を,私は血沈用のゴムの代用品に使いました。皆樣方の内には,すでにお気付きでそのようにお使いの所もおありでしようが,もしお知りにならない方は,どうぞ一度試して下さいませ。
1 0 0 0 OA 精神障がいの親と暮らす子どもの日常生活と成長発達への影響
- 著者
- 長江 美代子 土田 幸子
- 出版者
- 日本赤十字豊田看護大学
- 雑誌
- 日本赤十字豊田看護大学紀要 = Journal of Japanese Red Cross Toyota College of Nursing (ISSN:13499556)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.83-96, 2013-03-31
精神障がいを持つ親と生活している子どもの生活と成長発達への影響について、統合的文献検討研究の手法を用いて探求した。29 件の対象文献のほとんどは母親の影響に焦点を当てているが、父親のアルコール・薬物乱用による家族機能の破綻が養育環境を悪化させていた。子どもの成長発達に関する研究報告で共通しているのは、子どもにとって、親が病気であることを知りその病気を正しく理解することが不安を軽減し、生きやすくすることにつながるということであった。しかし現状では大人は子どもに事実を隠し、子どもが聞きたくても聞けない状況をつくりだしていた。親の精神障がいが子どもの成長発達に与える影響は、精神障がいの親の直接的な養育態度のみならず、夫婦関係、他の家族員の健康、経済的状況など、間接的な要因を考慮して捉える必要がある。また、このような親子を孤立させないように、社会と繋ぎ、子どものレジリエンスを活性化できる支援が必要である。
はじめに 精神科では、自殺・事故防止の観点から、入院生活に何らかの制限が設けられていることが多い。病棟内に持ち込む日常生活用品を制限することもその1つである。制限される物品としては刃物やガラス製品、ベルト、電化製品のコード、耳かき、爪楊枝、毛抜き、割り箸など多岐にわたる。刃物など明らかに危険な物品については、マニュアルなどに明文化され対応が統一されていることが多いが、危険度が必ずしも高いとはいえない耳かき、毛抜き、爪楊枝、割り箸などの取り扱いについては、病院・病棟により規定が異なる上、看護者の判断によっても対応に違いが存在するのではないだろうか。 縊死に関連した日常生活用品の持ち込み制限に関する田辺らの調査においても、コード、ネクタイ、針金ハンガーなどは持ち込みを許可する病棟と許可しない病棟がそれぞれ半数ずつであり、看護者が異なる視点で判断している可能性を示唆している*1。病棟内においても看護者間の考え方や対応の相違により混乱が生じることは多々あり、特に精神科の臨床では日常的に遭遇する体験であるという*2。病棟内の看護者間において価値観そして実際の対応方法が異なる場合、患者に混乱をもたらし、そこで働く看護者を悩ませる要因にもなりうる。 過度な物品管理、不必要な制限は患者の依存や退行を引き起こし、自立の妨げになる可能性があり、病棟生活を送る患者の生活の質(QOL)に影響を与えることが示唆されている*1。QOLや人権に配慮しすぎると事故の危険が高まる*3ものの、事故防止を優先しすぎると日常生活を送る上で不都合が生じる。看護師が事故防止を優先するのか、QOLを優先するのかによって日常生活用品の持ち込みの判断に影響が生じると予測される。 そこでこの研究では、①病棟内への日常生活用品の持ち込み制限と優先傾向(事故防止・QOLのどちらを優先するのか)との間には関連があるのか、②看護者のバックグラウンドと優先傾向との間に関連があるのかの2点を明らかにすることを試みた。
1 0 0 0 OA 肩甲骨面上肢挙上角度と肩甲下筋の筋活動の関係
- 著者
- 中山 裕子 大西 秀明 中林 美代子 石川 知志
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A0602, 2007 (Released:2007-05-09)
【目的】肩甲下筋は主に肩甲上腕関節の内旋作用を持つ筋で,回旋筋腱板を構成する重要な筋である.肩甲下筋はその構造や神経支配より,部位による機能の違いの可能性が報告されているものの,上・中・下部に分けた筋活動特性についての報告はみない.本研究の目的は,肩甲下筋の上・中・下部線維の機能的な違いを明らかにすることである.【対象と方法】対象は実験内容を書面にて説明し同意を得た健常成人6名(男性4名,女性2名,平均年齢35.0歳)であった.運動課題は5秒間の肩関節最大等尺性内旋運動とし,筋力測定器(BIODEX)を使用して行った.測定肢位は椅子座位とし,肩甲上腕関節内外旋中間位で,上腕下垂位,肩甲骨面挙上60度,120度に固定した肢位で2回ずつ行い,肩甲下筋の上部・中部・下部線維の筋活動をワイヤー電極にて導出した.電極はウレタンコーティングのステンレス製ワイヤー電極を使用し,電極間距離を5mmとして,肩甲骨内縁から関節窩方向に向けて刺入した.肩甲下筋の上部線維には内角,中部線維には内角より3横指尾側,下部線維には下角より1横指頭側からそれぞれ刺入し,電気刺激を利用して確認した.ワイヤー電極の刺入は共同研究者の医師が行った.筋電図は前置増幅器(DPA-10P,ダイヤメディカルシステムズ)および増幅器(DPA-2008,ダイヤメディカルシステムズ)を用いて増幅し,サンプリング周波数2kHzでパーソナルコンピューターに取り込み,運動開始後1秒後以降で最大トルクが発揮された時点から0.5秒間を積分し,上肢下垂位の値を基に正規化した(%IEMG).統計処理には分散分析と多重比較検定(有意水準5%未満)を用い比較検討した.【結果】肩甲下筋上部線維の%IEMGは,60度挙上位で93.9±11.5%,120度挙上位で79.1±23.6%であり,120度挙上位の値は下垂での値よりも小さい傾向が見られた(p=0.08).中部線維では60度挙上位で119.3±14.9%であり,120度挙上位(93.7±18.4%)より有意に高い値を示した(p<0.05).下部線維では60度挙上位で112.4±11.9%,120度挙上位で129.6±19.4%であり,120度挙上位の値は下垂位の値より有意に高い値を示した(p<0.05).【考察】肩甲上腕関節回旋中間位における等尺性内旋運動において,肩甲下筋上部線維の活動は肩関節面挙上角度の増加に従い減少する傾向があり,中部線維の活動は60度屈曲位が最も大きく,下部線維の活動は120度屈曲位が最も大きいことが示された.このことは上腕骨長軸に対しより垂直に近い線維が最も効率よく肩関節内旋運動に作用することを示唆していると考えられる.
1 0 0 0 OA 学童期の食環境がその後の食嗜好に及ぼす影響
- 著者
- 石川 詔子 五十嵐 益恵 浜野 美代子
- 出版者
- 日本健康医学会
- 雑誌
- 日本健康医学会雑誌 (ISSN:13430025)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.8-12, 2002-08-10 (Released:2017-12-28)
- 参考文献数
- 10
生活習慣病の一次予防の為の食生活を指導するために,学童期での食環境が,その後の食生活に重大な影響を与えると考えた。その事を調べるためアンケート調査を行い検討し,次のような結果を得た。1.学童期の朝食の欠食は,その後も継続して朝食をとらない習慣につながる。2.小学校低学年,小学校高学年,中学校時の学校給食への満足度は高い。3.学校給食で一番好きな食事と,自分が一番好きな食事が同じになる傾向がある。4.複合家族で育った下宿生の自炊の割合は高い。この様に学童期の食環境(特に学校給食)は,その後の食嗜好に大きな影響を与えることが,このアンケート調査でわかった。したがって生活習慣病の一次予防の為には,学童期の食生活指導が重要な意味を持つと考えた。
- 著者
- 高橋 信行 松田 美代子 井上 たかみ 井川 剛 井川 緑 和田 浩一 松友 博史 村上 博 大西 キミ 鎌村 千秋 小田 由美 佐々木 美津代 中田 ひとみ 黒田 かつ子
- 出版者
- 日本ロービジョン学会
- 雑誌
- 日本ロービジョン学会学術総会プログラム・抄録集
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.60, 2005
視覚障害と知的障害を併せ持つ盲学校の生徒について、1 保護者、2 教師、3 寄宿舎指導員がインターネットの掲示板システムを利用し生徒に関する情報を共有しようという取り組みをおこなった。我々は、これを「電子連絡帳」と呼んでいる。電子連絡帳により保護者、教師、寄宿舎指導員の連携が強化され、保護者に対するアカウンタビリティーの向上や生徒に対する教育サービスの向上が期待できると考えている。電子連絡帳の仕組みや実施方法、利点、今後改善すべき点などについて報告する。
1 0 0 0 OA 日本の「声の音楽」の諸相 -共通の歌詞を用いた邦・洋楽の歌唱表現法の比較の試み-
- 著者
- 中山 一郎 天野 文雄 上畠 力 河内 厚郎 小島 美子 小林 範子 杉藤 美代子 高木 浩志 柳田 益造
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告音楽情報科学(MUS)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.14(1997-MUS-024), pp.93-100, 1998-02-13
本稿は、筆者らが遂行している、日本語の歌唱表現法に関する学際的研究の紹介である。日本語を洋楽的唱法で歌唱する場合、日本語としてのニュアンスや自然さが失われ、"何を言っているのか解らない"という深刻な事態を招いている。その克服には、古来、日本語の扱いに工夫を重ねて発展してきた伝統芸能(広義の邦楽)との歌唱表現法の比較が不可欠であると考えられるが、そのための方法論すら無い現状である。本研究は、共通の歌詞を、多数の人間国宝を含む、各ジャンルにおける最高クラスの演者に"歌い分け"を行わせ、得られた高品質の音声試料を音響分析することにより、邦楽と洋楽における歌唱表現法の普遍的な差異、及び同一性を科学的に明らかにすることを目的とする。本稿では、研究の具体的な方法論、予想される結果、及び研究の展望について述べる。
1 0 0 0 OA 細菌汚染調査からみた病室カーテンの適正交換頻度について
- 著者
- 石金 恵子 境 美代子 村藤 頼子 広上 真里子 杉政 美雪 北川 洋子 吉田 郁子 中川 輝昭 田内 克典 水島 豊 落合 宏
- 出版者
- Japanese Society of Environmental Infections
- 雑誌
- 環境感染 (ISSN:09183337)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.177-180, 1997-11-28 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 10
病室内のカーテンの細菌汚染状態を知り, カーテンの適正交換頻度を知る目的で, 10病室 (一般病室4, MRSA隔離室6) のカーテンに付着している細菌をバイオエアーチエッカーを用い1週間隔で5回調査した.その結果, 下記の成績が得られた.1) 4週間を通じてカーテンの付着菌数の累積的増加は認められなかった.2) 分離菌ではブドウ球菌がもっとも多く, ついでグラム陽性桿菌, 真菌の順であった.3) MRSA隔離室のほうが一般病室より多くの菌数が検出された.4) MRSA隔離室6室のうち2室で濃厚なMRSA汚染が認められた.5) 消毒用エタノール噴霧はいずれの細菌の除菌にも有効であった.以上より, カーテンの交換頻度はMRSA隔離室では患者の退室ごとに, また一般病室では肉眼的汚れに応じ, 年3-4回定期的に交換するのが適当ではないかと考えられた.
1 0 0 0 OA 132 女子の運動服の変遷 : 東京女子高等師範学校に関して
- 著者
- 興水 はる海 外山 友子 萩原 美代子
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号 第30回(1979) (ISSN:24330183)
- 巻号頁・発行日
- pp.116, 1979 (Released:2017-08-25)
1 0 0 0 OA 近畿方言2拍単語アクセント型の分析及び知覚
- 著者
- 藤崎 博也 杉藤 美代子
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.167-176, 1978-03-01 (Released:2017-06-02)
For the purpose of elucidating the relationship between the word accent types and the contours of fundamental frequency (F_0-contour), a model has been presented by one of the authors for the process of generating an F_0-contour from "voicing" and "accent" commands, and has been applied to analyze the F_0-contours of word accent types in the Tokyo dialect. The present study was conducted to test the model's validity for the Kinki dialect, which posesses peculiar accent types not found in the Tokyo dialect (Table 1), and also to examine the perceptual significance of parameters of the model. The speech materials were the utterances of two-mora [ame] pronounced in all four accent types of the Osaka dialect (Table 2) by a male informant. Extraction of F_0-contours (Fig. 1) and their parameters were conducted with a digital computer. Using a functional model for generating the F_0-contour(Figs. 2 and 3), parameters were extracted from six utterances each of the accent types, by finding the best match between the observed and generated F_0-contours (Table 3). The close agreement between the observed and generated contours proved the model's validity for the Kinki dialect (Fig. 4). While the magnitude and rate of responses to voicing and accent command are considered to characterize the laryngeal functions of a speaker, the timing parameters of the accent command, i. e. the onset and the end, are found to be specific to each accent type, and can clearly separate the four accent types (Fig. 5). The perceptual relevance of these timing parameters was examined by the identifications tests of accent types using 40 synthetic speech stimuli consisting of both typical stimuli of the four accent types and intermediate stimuli, generated by systematicallyvarying the timing parameters of the accent command. The subjects were 10 speakers of the Osaka dialect and two speakers of the Tokyo dialect. The perceptual boundary between two accent types was determined for each subject (Fig. 6), which was quite clear-cut and almost agreed in all the subjects (Fig. 7), indicating the perceptual importance of these timing parameters in the identification of accent types. Further experiments using stimuli with systematic shifts in the timing of formant frequency patterns indicated that the relative timing of the accent command and the segmental features of a particular phoneme is quite important for the identification of a specific accent type (Figs. 8 and 9), but not necessarily for other types. These results indicate that the perception of word accent requires specification of certain features for temporal units which are smaller than mora, which is commonly accepted as the suprasegmental unit of spoken Japanese.
- 著者
- 石毛 美代子 村野 恵美 熊田 政信 新美 成二
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.154-159, 2002-04-20 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 4 3
内転型痙攣性発声障害 (Adductor spasmodic dysphonia: 以下SDと略す) 様症状を呈する9症例に音声訓練を行った.7段階尺度 (0: 正常~6: 最重度) を用いた訓練前後の重症度評価, および治療効果に対する患者の主観的評価の二つにより音声を評価した.9例中4例では満足すべき結果が得られた.4例中2例は, 初期評価において機能性要因が関与していることが疑われた例であったが, 音声訓練後には正常範囲の音声に回復し, 治療結果から最終的に機能性発声障害と診断された.残る2例は初期評価の一環として行った試験的音声訓練において音声症状の軽減が認められた例であったが, 最終的にSDと診断された.以上より, SD様症状を呈する症例に対する音声訓練は鑑別診断上有効であることが示唆された.また, 音声訓練により症状の軽減が得られる症例が存在することから, 試験的音声訓練を試みるべきであると考えられた.
1 0 0 0 OA 報告 中世の信仰と表現
1 0 0 0 OA 医学生・看学生の喫煙行動とその背景要因
- 著者
- 縣 俊彦 清水 英佑 芳賀 佐知子 桜井 美代子 林 和夫 橋田 ちせ 坂場 秀行 大井田 基
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.6, pp.433-440, 1995-12-25 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 13
都内, 近県の2医科大学生1,470名, 4看護専門学校生692名に対し喫煙に関するアンケート調査を実施し, 次の結果を得た.1) 喫煙率は医学生全学年35.4%, 看学生12.5%, 医学生1~3年28.7%と差があり, 医学生高学年の喫煙率は高く, その要因は不安やストレスと推測した.2) 医学生は喫煙の有害性の知識が禁煙に結びつかないが, 看学生は, 知識を得ることにより禁煙を行った者が多い.3) ブリンクマン指数の重回帰分析の結果, 医学生の場合は, 年齢, 性, 母の喫煙が重要な要因となり, 禁煙運動の推進には, ストレスからの解放, 喫煙率の高い男子学生重点の指導, 母の禁煙が重要であると示唆された. 看学生の場合は決定係数も小さく取り上げられる要因も少なかった.
1 0 0 0 IR 矢内原忠雄の「日本的基督教」 : 土着化論再考
- 著者
- 菊川 美代子
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 基督教研究 (ISSN:03873080)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.91-104, 2011-12
論文(Article)矢内原忠雄(1893-1961)は、無教会主義の創始者である内村鑑三の弟子である。これまでの神学における先行研究では、内村や矢内原の「日本的基督教」構想を分析することで、国家に対して無批判に迎合せず、批判的な距離を保つことのできるキリスト教土着化の望ましいあり方が探られてきた。しかし、本稿では矢内原のそのような「日本的基督教」を分析し、一見超国家的なものとして意識されている、キリスト教という「世界宗教」が、実はいかに国家に根ざしたものであったのかということを明らかにする。Tadao Yanaihara was a disciple of Kanzō Uchimura who founded the Non-Church Movement. In subsequent studies of theology, Uchimura and Yanaihara's "Japanese Christianity" was studied as one of the best hints on how to indigenize Christianity in Japan without justifying a state without any check on its power and on how to keep an appropriate distance from state. Therefore, I analyze the term "Japanese Christianity" and consider how Yanaihara was able to take "Japan" as an object of theology. However I want to prove that Christianity, regarded as one of the world's great religions and super-national, actually arises thorough studying of his idea of "Japanese Christianity."
1 0 0 0 OA 竹むきが記 : 三大危機の只中に立って(<特集>中世・危機と「文学」)
- 著者
- 岩佐 美代子
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.7, pp.33-42, 2006-07-10 (Released:2017-08-01)
西園寺公宗の宝、日野名子の日記「竹むきが記」は、皇統・公家社会・婚姻形態にかかわる三つの危機を乗越え、これに鍛えられた女性によって書かれた作品である。困難きわまる時代の中で、夫を失い、その家に乗込んで遺児を育て上げ、家門を守った彼女は、同時に自らの判断で信仰の道を定め、在俗修行に徹する。中世までの自立性高い女性と、近世の夫に従属し家を守る女性の分岐点に立つ本記は、危機を描く文学として価値高いものである。新たな見直しを期待したい。
- 著者
- 櫻井 美代子
- 出版者
- 東京家政学院大学
- 雑誌
- 東京家政学院大学紀要. 人文・社会科学系 (ISSN:13441906)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.57-68, 2000-07-31
- 被引用文献数
- 1