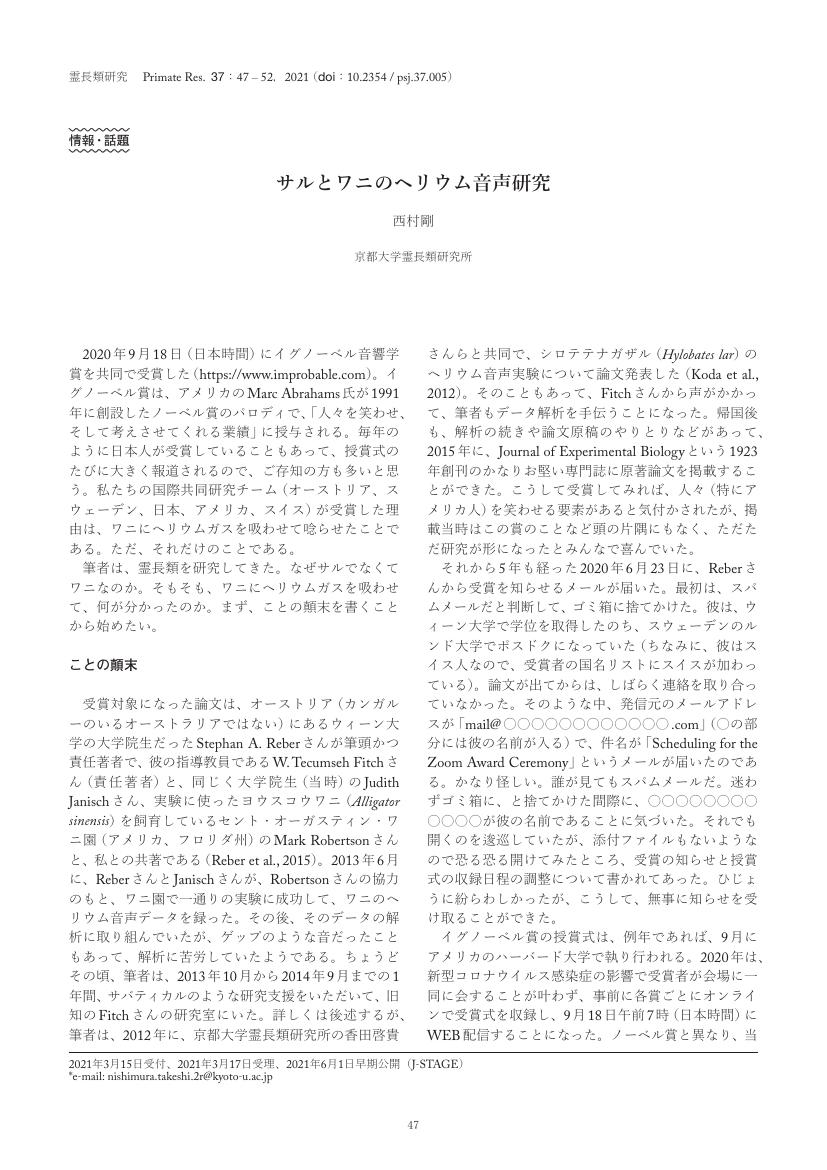15 0 0 0 OA 霊長類の音声器官の比較発達—ことばの系統発生
- 著者
- 西村 剛
- 出版者
- 日本動物心理学会
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.49-58, 2010 (Released:2010-06-25)
- 参考文献数
- 42
The sophisticated feature of human speech allows us to turn much information encoded by language in the brain into sounds and to communicate it with others rapidly and efficiently. Human speech shows highly sophisticated modifications of supralaryngeal vocal tract (SVT) in volume and shape, through voluntary regulation of the vocal apparatuses, which is usually regulated involuntarily in other mammals. Paleoanthropologists have continued to debate the “origin” of language, evaluating distinct morphological features, which are presumed to underlie just human speech, but such continued efforts have no consensus on the age of the origin. On the other hand, recent advances in empirical studies on the development of the SVT anatomy in nonhuman primates endorse the idea that many of the separate biological foundations of speech had evolved independently before the origin of human beings, under different selection pressures unrelated to speech. The efforts have contributed to our better understanding on the mosaic processes of the speech evolution, and could contribute greatly to exploring the long “evolutionary history” of speech.
- 著者
- 仲沢 弘明 池田 弘人 一ノ橋 紘平 上田 敬博 大須賀 章倫 海田 賢彦 木村 中 櫻井 裕之 島田 賢一 成松 英智 西村 剛三 橋本 一郎 藤岡 正樹 松村 一 森岡 康祐 森田 尚樹 占部 義隆 所司 慶太 副島 一孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本熱傷学会
- 雑誌
- 熱傷 (ISSN:0285113X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.1-11, 2022-03-15 (Released:2022-03-15)
- 参考文献数
- 12
壊死組織を除去する手法はデブリードマンと呼ばれ, 深達性熱傷に対して必要な治療法の一つである.最も一般的に行われるデブリードマンは外科的デブリードマンであり, 近年では超早期手術の有用性が報告され広く実施されている.しかしながら, 手術時の術中管理や出血量管理が必要であり, 正常組織への侵襲が不可避であるため患者負担が大きい.一方, 諸外国で承認されている化学的壊死組織除去剤であるKMW-1は熱傷部位に塗布し, 4時間後に除去することで低侵襲かつ壊死組織のみを選択的に除去できることが海外臨床試験にて報告されている. われわれは, 深達性Ⅱ度またはⅢ度熱傷を有する日本人患者におけるKMW-1の有効性を確認し, 安全性を検討するために第3相臨床試験を行った. 主要評価項目である壊死組織が完全除去された患者の割合は88.6%(31/35例, 95%信頼区間[74.05, 95.46])であった.また, 壊死組織除去面積割合の平均値は患者あたりで96.2%, 対象創あたりで97.1%であった.さらに, 壊死組織が完全除去されるまでの期間の中央値は登録時点からが1日, 受傷時点からが3日であった.有害事象の発現割合は85.7%(30/35例), 副作用の発現割合は20.0%(7/35例)であったが, 副作用はいずれも軽度または中程度であった.KMW-1の減量や投与中断, 投与中止を必要とする有害事象は報告されなかった. これらの結果から, 日本人の深達性Ⅱ度またはⅢ度熱傷においても, KMW-1の塗布によって早期に選択的な壊死組織の除去が可能であり, 安全性に問題がないことが確認された.KMW-1は外科的デブリードマンによる超早期手術に代わる治療法となりうると考えられる.
4 0 0 0 OA 兵頭スコアを用いた嚥下内視鏡検査による嚥下機能評価と誤嚥の予測因子の検討
- 著者
- 千葉 欣大 佐野 大佑 生井 友紀子 西村 剛志 矢吹 健一郎 荒井 康裕 田辺 輝彦 池宮城 秀嵩 百足 紘 折舘 伸彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.1, pp.85-86, 2020-01-20 (Released:2020-02-05)
ヒト(<i>Homo sapiens</i>)はその脳サイズから予測されるよりも11ヶ月早く、未熟な状態の赤ん坊を産む。この現象は生理的早産と呼ばれ、ヒトの新生児が出生後しばらく未熟な状態で胎生期の脳発育スピードを維持し、大きな脳を成長させる現象(二次的晩成)と関連している。つまり生理的早産は、ヒトにおける脳進化と直接関連するライフヒストリー上の重要なイベントである。<br> ヒトは直立二足歩行をするため骨盤幅と産道が狭いが、一方で脳を大きく成長させる強い淘汰圧を受けたために、生理的早産および二次的晩成が進化したと考えられている。つまり胎児の脳が大きくなりすぎて産道の通過が不可能になる前に、未熟な状態の赤ん坊を分娩するのである。人類史における生理的早産の起源を探求するため、これまで化石から新生児の脳サイズや母親の産道サイズを推定する試みがなされてきた。しかし不完全な化石の復元や年齢推定の誤差、身体サイズの個人差といった不確定要素があるために、この手法での問題解決には限界がある。本発表では、我々がホモ・フロレシエンシス(フローレス原人)の頭骨化石を研究している際に着想した、新しい研究法の可能性について論じる。<br> フロレシエンシスのタイプ標本の頭骨に認められた変形性斜頭(deformational plagiocephaly:DP)は、現代人にしばしば認められる頭骨変形の一形態で、新生児の頭骨が未発達で柔らかいため、頸部筋群も未発達で頭の位置をうまくコントロールできない赤ん坊の頭が、就寝時に床反力によって歪むことに起因するとされる。そうであるなら、この変形は二次的晩成の進化に伴って顕現してきた可能性が高く、DPの存在は化石人類において二次的晩成が存在したかどうかを吟味する際の直接的指標となる可能性がある。
3 0 0 0 OA 哺乳類の肩甲骨の形態学的研究
- 著者
- 和田 直己 谷 大輔 中村 仁美 大木 順司 西村 剛 藤田 志歩
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement 第29回日本霊長類学会・日本哺乳類学会2013年度合同大会
- 巻号頁・発行日
- pp.80, 2013 (Released:2014-02-14)
脊椎動物の肢は前肢2本,後肢2本の合計4本である.4肢は 動物の体に前後,左右,さらに上下方向に作用する力に対して安定を保つに必要十分であり,また脊椎動物の特徴である体軸の運動を陸上で最大限に活用できる数である.前肢と後肢の機能は動物によって異なる.特に前肢の機能は多様で,動物を特徴づける.前肢は肩甲骨,鎖骨,烏口骨で体幹と連結する.哺乳類は体幹と前肢の連結において特に肩甲骨を発達させた脊椎動物である.肩甲骨の形質は動物の姿勢と運動の特徴を強く反映する.本研究の目的は肩甲骨の外形,力学的特性と動物の形質の関係を理解することにある.本研究の実験方法における課題は機能する肩甲骨の形状をとらえることにあった.そこで骨標本ではなく,全身,または前肢のCT撮影を行い,肩甲骨をPC上で構築し,計測を行った.本学会において,17目 100種の肩甲骨について調査した結果から導きだされた肩甲骨の形状と動物種,身体的特徴と運動との関係について発表を行う.謝辞国立科学博物館 山田格研究室,川田伸一郎研究室,大阪ネオベッツVRセンターのスタッフの方に深謝を.
3 0 0 0 OA 東ユーラシアにおける新生代後半の霊長類進化に関する古生物学的研究
- 著者
- 清水 豊 園田 龍太郎 藤原 康策 西村 剛 帆足 聖治 井上 直己 村上 宏治 田中 伸幸 金子 敦 椎名 哲也 山崎 悦子
- 出版者
- 一般財団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団
- 雑誌
- 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス (ISSN:18846076)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.223-238, 2022 (Released:2022-08-03)
- 参考文献数
- 9
- 著者
- 川竹 基弘 西村 剛 志村 清 石田 良作
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物學會紀事 (ISSN:00111848)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.161-162, 1960
The methods of fertilizer application tested were as follows: 1) Subsoiling, 2) Broadcasting, 3) Drilling beside planting rows, 4) Drilling between planting rows. With corn and oats, the method of drilling beside planting rows brought the best top growth. With immature soybean and common vetch, it was superior by subsoiling. The yield in each crop was similar in tendency to the top growth, except that of common vetch which decreased owing to lodging caused by excessive growth by the subsoiling method. Drilling between rows brought about the most inferior growth and yields in all the crops. Effects of the difference of the method on the root development were recognized with common vetch and oats as differences in distribution of roots around and beneath the fertilizer placed. Subsoiling application promoted the penetration of roots in common vetch only. It was observed that the roots which distributed around the fertilizer were white and fresh. Though no data about the relation between top growth and root weight were obtained in this investigation, the authors assumed detailed studies of quality or viability of root should be important to elucidate such a relation.
1 0 0 0 OA サルとワニのヘリウム音声研究
- 著者
- 西村 剛
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- pp.37.005, (Released:2021-06-01)
- 参考文献数
- 15
- 著者
- 西村 剛 宮崎 祐介 西田 佳史 山崎 麻美 山中 龍宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- バイオエンジニアリング講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.127-128, 2011
1 0 0 0 OA がん免疫療法
- 著者
- 西村 剛志 加納 里志 佐久間 直子 佐野 大佑 小松 正規 折舘 伸彦
- 出版者
- 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科免疫アレルギー (ISSN:09130691)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.237-246, 2013 (Released:2013-12-26)
- 参考文献数
- 77
頭頸部癌患者に対する治療方針を決定する場合,現時点で免疫療法が第一選択の方針となることは極めて稀であるが,手術,放射線治療,化学療法との組み合わせで上乗せ効果を期待できる可能性がある。近年開発の著しい分子標的治療薬にも免疫学的知見が反映されており今後の飛躍的な治療成績の向上もあり得る。Biological response modifier (BRM) 製剤,養子免疫療法,ワクチン療法など現在利用可能と考えられる免疫療法と機序につき簡便に概説した。
1 0 0 0 OA チンパンジー4頭の脳形態の発達
- 著者
- 三上 章允 西村 剛 三輪 隆子 松井 三枝 田中 正之 友永 雅己 松沢 哲郎 鈴木 樹里 加藤 朗野 松林 清明 後藤 俊二 橋本 ちひろ
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement 第22回日本霊長類学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.90, 2006 (Released:2007-02-14)
大人のチンパンジーの脳容量はヒトの3分の1に達しないが、300万年前の人類とほぼ同じサイズである。また、脳形態とその基本構造もチンパンジーとヒトで良く似ている。そこでチンパンジー脳の発達変化をMRI計測し検討した。[方法] 霊長類研究所において2000年に出生したアユム、クレオ、パルの3頭と2003年に出生したピコ、計4頭のチンパンジーを用いた。測定装置はGE製 Profile 0.2Tを用い、3Dグラディエントエコー法で計測した。データ解析にはDr_View(旭化成情報システム製)を用いた。[結果] (1)脳容量の増加は生後1年以内に急速に進行し、その後増加のスピードは鈍化した。(2)大脳を前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分けて容量変化を見ると前頭葉の増加が最も著明であった。(3)MRIで高輝度の領域の大脳全体に占める比率は年齢とともにゆっくりと増加した。[考察] チンパンジーとヒトの大人の脳容量の差を用いてチンパンジーのデータを補正して比較すると、5歳までのチンパンジーの脳容量の増加曲線、高輝度領域に相当すると考えられる白質の増加曲線は、ヒトと良く似ていた。今回の計測結果はチンパンジーの大脳における髄鞘形成がゆっくりと進行することを示しており、大脳のゆっくりとした発達はチンパンジーの高次脳機能の発達に対応するものと考えられる。
1 0 0 0 マカクザルの発声メカニズムに関する実験的研究
- 著者
- 西村 剛 ヘルブスト クリスチャン 香田 啓貴 國枝 匠 鈴木 樹理 兼子 明久 ガルシア マキシム 徳田 功 フィッチ W・テカムセ
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.53, 2018
<p>ニホンザルを含むマカクザルでは,音声行動の研究が精力的に行われており,多様な音声レパートリーが知られている。しかし,その発声メカニズムに関する知見は技術的限界により限られていた。本研究は,声帯振動の様態を声帯を通過する電流の変化により非侵襲的に観測する声門電図(EGG)を用いて,生体の音声条件付けおよび摘出喉頭の吹鳴実験により,音声の多様性をうむ発声メカニズムを明らかにした。生体からは,coo,glow,chirp発声中の計測に成功し,それぞれのEGG信号の特徴を明らかにした。摘出喉頭による実験により,その特徴を生じさせる発声運動を明らかにした。これら3つの音声の声帯振動は,声帯の内外転および呼気流の強弱により調整されており,ごくわずかな変化によって異なる音声タイプへと遷移することを示した。また,その声帯振動は,おおよそヒトの7歳児でみられるものに類似した。これらの結果は,ヒトを含む霊長類における発声メカニズムの共通性を示すとともに,サル類でも発声運動をわずかに変化させるだけで,大きく異なる音声タイプを作り出せることを示した。一方,ヒトとの相異もみられた。吹鳴実験では,マカクザルでは,声帯と同時に仮声帯も振動させている可能性を示した。それにより,音声の基本周波数を大きく下げる効果があることが示された。ヒトと異なり,喉頭室が発達したサル類では,前庭ヒダの自由度が高く,仮声帯も容易に振動し得ると考えられる。本研究は,科研費(#16H04848,西村; #17H06380, #18H03503,香田),APART(Herbst)の支援を受けた。</p>
- 著者
- 石井 雄也 須賀 良介 西村 剛 小野寺 真吾 橋本 修
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. MW, マイクロ波 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.260, pp.47-51, 2013-10-17
一般的に導波管,共振器やホーンアンテナは導電率が高く,低損失な金属で製作されている.しかし,これらは酸化による特性劣化や,装置の大型化による重量化の問題がある.そこで筆者らは金属の代用として,ポリアニリン溶液を用いた低抵抗率の導電性樹脂に着目した.本稿では集光型レンズアンテナを用いて,平面波を樹脂に照射させて透過特性を測定した.その結果,金属と同程度の特性を有していることを確認した.次に,本樹脂を用いた導波管を試作し,電磁界シミュレータHFSSを用いた解析値と比較した結果,樹脂製導波管内の損失は1dB程度であることを確認した.さらに,試作した樹脂製ホーンアンテナの放射パターンを測定した結果,金属の代用としての本樹脂の可能性を確認した.
- 著者
- 川竹 基弘 西村 剛 志村 清 石田 良作
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物學會紀事 (ISSN:00111848)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.161-162, 1960-09-01
The methods of fertilizer application tested were as follows: 1) Subsoiling, 2) Broadcasting, 3) Drilling beside planting rows, 4) Drilling between planting rows. With corn and oats, the method of drilling beside planting rows brought the best top growth. With immature soybean and common vetch, it was superior by subsoiling. The yield in each crop was similar in tendency to the top growth, except that of common vetch which decreased owing to lodging caused by excessive growth by the subsoiling method. Drilling between rows brought about the most inferior growth and yields in all the crops. Effects of the difference of the method on the root development were recognized with common vetch and oats as differences in distribution of roots around and beneath the fertilizer placed. Subsoiling application promoted the penetration of roots in common vetch only. It was observed that the roots which distributed around the fertilizer were white and fresh. Though no data about the relation between top growth and root weight were obtained in this investigation, the authors assumed detailed studies of quality or viability of root should be important to elucidate such a relation.
1 0 0 0 OA 話しことばの起源と霊長類の音声
- 著者
- 西村 剛
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.1, pp.1-14, 2008 (Released:2008-06-30)
- 参考文献数
- 105
- 被引用文献数
- 2 2
ヒトの話しことばにみられる連続的で変化に富んだ音声は,他の霊長類の音声とは異なり,言語で整理された多種多様な情報のすばやい効率的な伝達を可能にする。ヒトは,ヒト以外の哺乳類とは異なり,脳で作られた音声計画に合わせて音声器官の運動を随意に制御し,声道形状を的確なかたちへと連続的に変化させて,話しことばをつくりだす。古人類学的研究では,その話しことばに関連すると考えられる形態学的特徴を探し出し,その特徴に関する古人類の比較形態学的分析を通じて,言語の起源が論じられてきた。一方,ヒト以外の霊長類における音声器官の比較形態学的研究や音声の生物音響学的研究の進展は,話しことばの生物学的基盤は,ヒト系統以前から,それとは関係のない別々の適応を経て現れたというモザイク進化モデルを描き始めた。今後,両研究アプローチによる知見の蓄積とともに,それらが運動学的分析のもとに統合されることを期待したい。それにより,話しことばの解剖学的基盤の何がヒト特異的であるのか,あらためて浮き彫りになるだろう。その実証的知見が古人類学的研究へ還元されるとき,話しことばを含む言語の長い進化プロセスの解明への新たな一歩がふみ出されるに違いない。