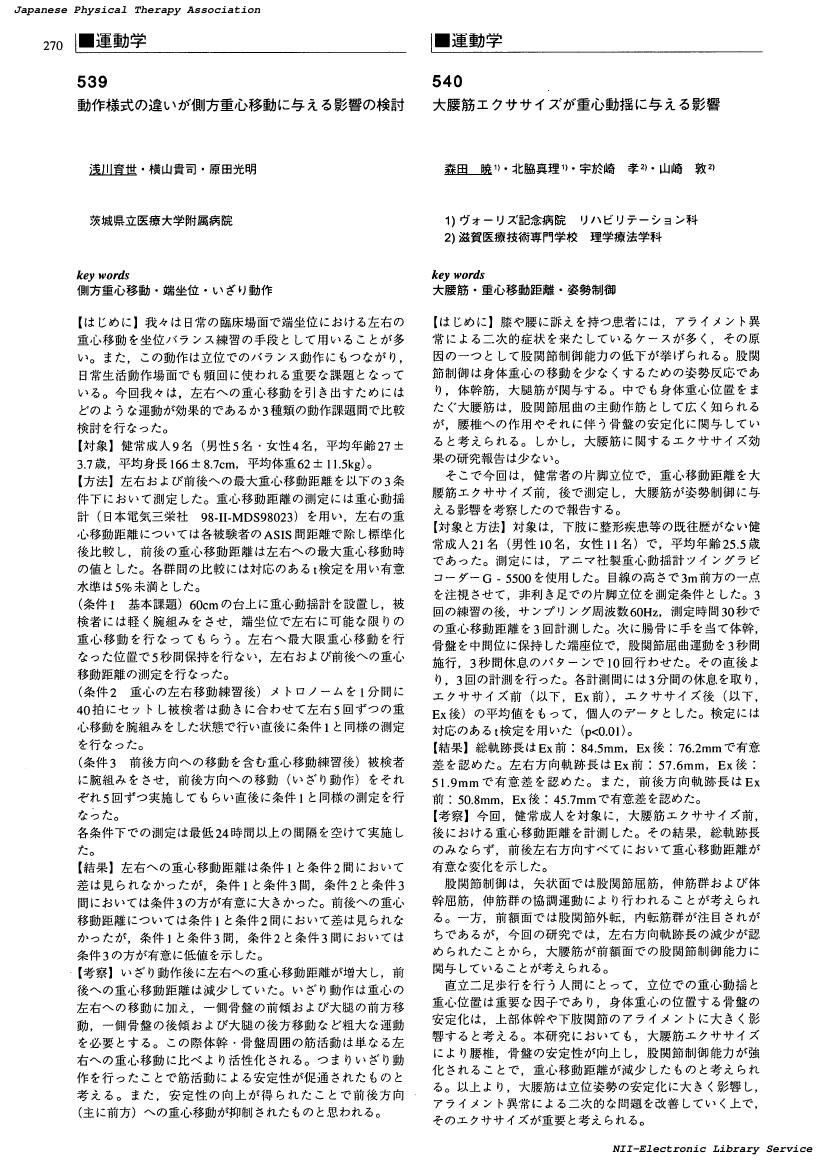1 0 0 0 287. 肩関節挙上角度の変化における胸郭の動き
- 著者
- 遠藤 優 山口 光圀 尾崎 尚代 福井 勉 大野 範夫 山嵜 勉 筒井 廣明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, 1996
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA Draw in を行う条件の相違が腹直筋と内腹斜筋の筋活動量の割合に及ぼす影響
- 著者
- 森山 信彰 浦辺 幸夫 前田 慶明 篠原 博 笹代 純平 藤井 絵里 高井 聡志
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.48101779, 2013 (Released:2013-06-20)
【はじめに、目的】 体幹筋は,表層に位置するグローバル筋と,深部に位置するローカル筋に分類される.ローカル筋は骨盤の固定に寄与しており,下肢と骨盤の分離運動のためにはローカル筋の活動が不可欠である.今回,選択的にローカル筋の活動を促すDrawing-in maneuver(以下,Draw in)といわれる腹部引き込み運動に着目した.主に下肢の運動中にローカル筋による骨盤固定作用を得るために,グローバル筋の活動を抑えながら,ローカル筋の筋活動を高めるDraw inの重要性が知られてきている. 座位では背臥位に比べ内腹斜筋の活動が増加することや(Snijder et al. 1995),腹直筋が不安定面でのバランスに関与することから(鈴木ら2009),Draw inを異なる姿勢や支持面を持つ条件下で行うとこれらの筋の活動量が変化すると考えられる.今回,Draw in中のグローバル筋である腹直筋と,ローカル筋である内腹斜筋を対比させながら,この活動量の比率を求めることで,どのような方法が選択的な内腹斜筋の筋活動量が得られるか示されるのではないかと考えた.本研究の目的は,姿勢や支持面の異なる複数の条件下で行うDraw inのうち,どれが選択的に内腹斜筋の活動が得られるかを検討することとした.仮説としては,座位にて支持基底面を大きくした条件で行うDraw inでは,腹直筋に対する内腹斜筋の筋活動が高くなるとした.【方法】 健常成人男性6名 (年齢25.8±5.7歳,身長173.0±5.2cm,体重65.4±9.0kg)を対象とした.Draw inは「お腹を引っ込めるように」3秒間収縮させる運動とし,運動中は呼気を行うよう指示した.Draw inは,背臥位,背臥位から頭部を拳上させた状態(以下,頭部拳上),頭部拳上で頭部を枕で支持した状態 (以下,頭部支持),足底を接地しない座位(以下,非接地座位),足底を接地させた座位(以下,接地座位)の5条件で行った.筋活動の計測にはpersonal EMG(追坂電子機器社)を用い,下野(2010)の方法を参考に腹直筋,内腹斜筋の右側の筋腹より筋活動を導出した.試行中の任意の1秒間の筋活動の積分値を最大等尺性収縮時に対する割合(%MVC)として表し,各条件について3試行の平均値を算出した.さらに,腹直筋に対する内腹斜筋の筋活動量の割合(以下,O/R比)を算出した.5条件間の腹直筋および内腹斜筋の筋活動量と,O/R比の比較にTukeyの方法を用い,危険率5 %未満を有意とした.【倫理的配慮、説明と同意】 対象には事前に実験内容を説明し,協力の同意を得た.本研究は,広島大学大学院保健学研究科心身機能生活制御科学講座倫理委員会の承認を得て実施した(承認番号1123).【結果】 背臥位,頭部拳上,頭部支持,非接地座位,接地座位での腹直筋の%MVCはそれぞれ28.0±24.2%,46.4±29.0%,23.0±22.0%,13.2±7.2%,10.6±5.9%であった.頭部拳上では,非接地座位および接地座位より有意に高かった(p<0.05).内腹斜筋の%MVCはそれぞれ48.7±44.1%,49.0±36.9%,47.9±40.8%,45.4±32.1%,50.6±28.4%となり,各群間で有意差は認められなかった.O/R比はそれぞれ2.67±3.10,1.31±1.52,2.58±2.74,3.33±2.62,4.57±2.70であり,接地座位では頭部拳上より有意に高かった(p<0.05).【考察】 内腹斜筋の活動量には条件間で有意差がなく,今回規定した姿勢や支持基底面の相違では変化しないと考えられた.腹直筋は,頭部拳上では頭部の抗重力位での固定の主働筋となるため,筋活動量が他の条件より高いと考えられた.さらに,有意差はなかったが背臥位では座位に比べて腹直筋の活動量が高い傾向があった.背臥位では,頭部拳上の条件以外でも,「お腹をへこませる」運動を視認するために頭部の抗重力方向への拳上と軽度の体幹屈曲が生じ,腹直筋の活動が高まった可能性がある. O/R比は腹直筋の筋活動の変化により,条件間で差が生じることがわかった。背臥位で行うDraw inでは,腹直筋の活動を抑えるために,頭部の支持による基底面の確保に加えて,頭部位置を考慮する,もしくは座位で行うことが有効であると考えられた.【理学療法学研究としての意義】 Draw inを行う際に背臥位から頭部を挙げる条件では,内腹斜筋の活動量が同程度のまま腹直筋の筋活動が高まり,結果としてO/R比が低下するという知見が得られ,効果的に行うためにはこのような条件をとらないよう留意すべきことが示唆されたことは意義深い.
1 0 0 0 手関節伸筋群のストレッチ肢位の検討
- 著者
- 高崎 博司 村木 孝行 宮坂 智哉 韓 萌 宮本 重範 青木 光広 内山 英一 村上 弦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, pp.C0330, 2005
【目的】テニス肘に対する理学療法、またラケットスポーツの障害予防として手関節伸展筋群のストレッチが行われている。手関節伸展筋群のストレッチに関して、諸家により様々な方法が紹介されている。しかしながら、実験的にどの肢位が最も伸張されるのかは検討されていなかった。本研究の目的は、肘関節に起始する手関節伸筋群に対しどの肢位が最も効果的に筋肉を伸張しうるかを新鮮凍結遺体右上肢を用いて定量的に検討することである。<BR>【対象】実験標本は、胸郭・上肢付の新鮮凍結遺体右上肢5肢とした。<BR>【方法】実験は、新鮮凍結遺体の肩甲骨をジグに固定し、右上肢を他動的に動かして行った。測定は、前腕中間位・肘45度屈曲位・手関節中間位・指伸展位(以後基本肢位と呼ぶ)から、肘関節45度屈曲位・最大伸展位の2パターン、前腕は中間位と最大回内位の2パターン、手関節は中間位から最大屈曲位・最大屈曲尺屈位・最大橈屈位の3パターンの合計12肢位で行った。これらの肢位における各筋の伸張率は、線維方向に沿い筋の中央部に設置したLEVEX社製パルスコーダーを用いて測定した。測定値は基本肢位からの伸張率で表した。測定筋は長橈側手根伸筋(以後ECRL)・短橈側手根伸筋(以後ECRB)・尺側手根伸筋(以後ECU)・総指伸筋(以後EDC)の4筋とした。<BR>【結果】筋の伸張率が最大となる肢位はECRL とECRBで肘関節伸展・前腕回内・手関節屈曲尺屈位であり、平均22.7%と18.7%であった。ECUは肘関節45度屈曲・前腕中間・手関節橈屈位で平均3.52%、EDCは肘関節45度屈曲・前腕回内・手関節橈屈位で平均7.93%であった。ECRLは前腕回外よりも回内位で伸張され、肘関節伸展位でさらに伸張され、手関節が屈曲尺屈位で最大の伸張率を示した。ECRBは肘関節伸展・前腕回内位で伸張率が高く、手関節は屈曲位と屈曲尺屈位の差は無かった。EDCとECUは各肢位での差は少ないが、ECUは手関節橈屈位で伸びる傾向があり、EDCは肘関節伸展位、前腕回内位、手関節橈屈位で伸張率が大きい傾向があった。<BR>【考察】ECRL・ECRBは肘関節伸展・前腕回内・手関節屈曲尺屈で大きく伸張した。これは、肘関節屈伸の回転中心が両者の後方に位置し、また両者が前腕回旋軸の橈側に位置する身体運動学的所見と一致した。肢位の違いによるEDCの伸張率の差が少ない理由は、EDCが肘関節回転中心、前腕回旋機能軸に沿って走行していること、指関節の可動性が加味されたためと考えられる。ECUの伸張率は他の前腕伸筋と比較して明らかに小さく、ECUは手関節の運動よりはむしろ安定化に寄与する筋であると考えられた。<BR>【結論】肘関節伸展・前腕回内位でのストレッチ肢位が効率よく手関節伸展筋群をストレッチできることが示唆された。
1 0 0 0 OA 高齢者の頭部前方突出姿勢が舌筋力に与える影響
- 著者
- 小串 直也 中川 佳久 宮田 信彦 羽崎 完
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0712, 2016 (Released:2016-04-28)
【はじめに,目的】高齢者の多くは加齢に伴い特有の不良姿勢をとり,その中でも頭部前方突出姿勢は臨床において頻繁に観察される。頭頸部は嚥下機能と強く関係していることから,頭部前方突出姿勢は嚥下機能に影響を与えると考える。また,嚥下時の食塊移送には舌の運動が重要であり,舌筋力の低下は嚥下障害の原因のひとつである。しかし,高齢者の頭部前方突出姿勢が舌筋力に与える影響についての報告はない。そこで,本研究は高齢者の頭部前方突出姿勢が舌筋力に与える影響について検討した。【方法】対象はデイサービスを利用している神経疾患の既往のない虚弱高齢者16名(平均年齢85.6±7.7歳)とした。使用機器は舌筋力計(竹井機器工業株式会社製)と舌圧子(メディポートホック有限会社製)を用いた。測定は舌突出力と舌挙上力の2項目とし,各2回ずつ測定した。舌突出力の測定は口唇に舌圧子を当て,舌を最大の力で突き出させた。舌挙上力の測定はまず被験者に開口させ,口腔内で舌圧子を固定し,舌を最大の力で押し上げさせた。また,被験者の第7頸椎棘突起にマーカーを貼り付け,測定中の頭頸部をデジタルビデオカメラ(SONY社製)により撮影した。その後,Image Jにて第7頸椎棘突起を通る床との水平線と第7頸椎棘突起と耳珠中央を結んだ線のなす角を計測し,舌突出力測定中および舌挙上力測定中の頭蓋脊椎角(以下CV角)を算出した。測定肢位は端座位とし,頭部をアゴ台(竹井機器工業株式会社製)に固定した。分析は各々2回の平均値を代表値とし,舌筋力とCV角の関係を明らかにするために,Spearmanの順位相関係数を求めた。【結果】舌突出力は平均値0.23±0.10kg,舌突出力測定中のCV角は平均値29.50±5.79°となり,相関係数R=0.70で有意な正の相関を認めた(p<0.01)。舌挙上力は平均値0.22±0.09kg,舌挙上力測定中のCV角は平均値29.57±5.74°となり,相関係数R=0.72で有意な正の相関を認めた(p<0.01)。【結論】今回,高齢者の舌筋力とCV角の間に有意な正の相関を認めた(p<0.01)。このことから,高齢者の舌筋力と頭部前方突出姿勢は関係していることが明らかになった。舌筋力の低下は嚥下障害における原因のひとつであり,実際に嚥下障害患者に対して舌負荷運動が実施される。また,舌と姿勢の関係について頸部の屈伸や回旋が舌運動や舌圧に与える影響については報告されてきた。しかし,高齢者の頭部前方突出姿勢と舌筋力の関係については報告されていなかった。CV角は頭部前方突出の程度を表現しており,加齢とともに小さくなる。頸椎の過剰な前彎を伴う頭部前方突出姿勢では舌骨下筋群が伸張され,舌骨を下方に引くと考える。舌骨には舌筋の一つである舌骨舌筋が付着しており,舌骨の下方偏位は舌の運動を阻害するため,舌筋力とCV角の間に有意な相関を認めたと考える。したがって,舌筋力の向上には姿勢の改善が必要であると考える。
- 著者
- 矢口 拓宇
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Ea1018, 2012
【はじめに、目的】 転倒恐怖感を測定する方法にTinettiらの開発したFall Efficacy Scale(以下FES)がある。FESは10項目の日常生活活動を転倒なく行う自信があるかを問うものであり、対象者が日常生活のどの場面で転倒恐怖を感じるのかを知るのに有効な手段として使用されている、しかし、実際には行わない活動については想像で答えを要求するため、入院や入所中の方、家事を行わない男性などには使いにくい場面もある。また、10項目の質問項目は時間もかかるという欠点がある。そこで、より簡便でほぼ誰にでも使用可能な評価方法として歩行自己効力感尺度Walk Efficacy Scale(以下WES)を開発した。本研究の目的はWESとFESの関係を明らかにし、WESが転倒恐怖感の尺度として用いることができるかを検討すること、WESと身体機能評価、精神的健康感との関連性を調査し、WESの臨床応用を検討することである。【方法】 対象は当施設併設の通所リハビリテーション利用者86名(平均年齢77.5±9.5、男性31名、女性55名)とした。認知症はあっても軽度で、意思疎通が問題ない者であった。WESとFESは質問紙にて配布し回答を得た。WESは「屋内を転倒なく歩く自信があるか」と「屋外を転倒なく歩く自信があるか」の2項目からなり、それぞれ「とても自信がある」を4点、「まあまあ自信がある」3点、「あまり自信がない」を2点、「全く自信がない」を1点として2項目の合計点を8点満点で算出した。FESは入浴や着替え、買い物など10項目の日常生活活動を転倒なく行える自信があるかを上記と同様4段階で回答を求め、その合計点を40点満点で算出した。また、86名中37名(平均年齢76.9±9.4、男性13名、女性24名、身長154.2±9.9、体重57.4±9.6)について身体機能評価とアンケートを行った。身体機能評価は握力、30秒間立ち上がりテスト(以下CS-30)、Functional Reach Test(以下FRT)、5m歩行時間及び歩数を測定した。また、質問紙にて過去3ヶ月間の転倒経験及び精神的健康感の尺度としてWHO5について回答を求めた。統計学的処理はWESとFES及び各身体機能評価、要介護度、WHO5との関連をspearmanの順位相関係数にて求めた。また、過去3ヶ月間の転倒経験から対象者を転倒群と非転倒群に分け、上記と同様の項目について対応のないT検定を行った。有意水準は5%未満とした。【倫理的配慮、説明と同意】 対象者には本研究の意図を十分に説明し、書面にて同意を得た。【結果】 統計学的処理の結果、WESとFESに有意な正の相関が認められた(R=0.72)。その他にWESと相関が認められたのは、CS-30(R=0.35)、FRT(R=0.57)、5m歩行(R=-0.36)、歩数(R=-0.35)、要介護度(R=-0.42)WHO5(R=0.37)であった。FESと各測定項目との相関は認められなかった。転倒群は非転倒群に比べ5m歩行時間において有意に高い値であったが、その他の項目には有意差は認められなかった。【考察】 本研究において新たに開発されたWESと従来から用いられてきたFESの結果に有意な中等度の相関が認められたことから、WES結果が転倒恐怖感を示す尺度として用いることができると考えられる。樋口らはバランス能力、歩行能力、下肢筋力とも転倒恐怖感に関連性がみられなかったと報告している。Wolfらも、バランス機能が有意に改善しても転倒恐怖感には影響がなかったと述べている。本研究においてもFESと身体機能との関連性は認められなかった。しかし、WESはCS-30、FRT、5m歩行などのバランスや歩行能力についても関連性が認められた。本研究により、歩行に特化して質問するWESを用いることで、歩行中の転倒恐怖感と身体機能に関連があるという可能性が見出された。これは、バランスや歩行能力の改善を目的とした理学療法が歩行という課題における転倒恐怖感の改善につながるかもしれないという新たな可能性も感じられる結果となった。転倒群と非転倒群における比較ではWESとFESともに有意差は認められなかったため、転倒恐怖感と実際の転倒との関連性は低いと考えられる。本手法はまだ開発されたばかりで、信頼性や妥当性の検討はまだ不十分である。今後のさらなる検証が必要である。【理学療法学研究としての意義】 WESは歩行における転倒恐怖感尺度として用いることができ、身体機能や精神的健康感と関連付けて評価できる可能性のある方法である。
1 0 0 0 OA 遠位脛腓関節におけるモビライゼーションの方向・強度の検討
- 著者
- 藤井 岬 宮本 重範 村木 孝行 内山 英一 鈴木 大輔 寺本 篤史 青木 光広
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.C0995, 2007 (Released:2007-05-09)
【目的】足関節周囲の骨折や靭帯損傷による固定や不動により生じる足関節拘縮は,歩行動作に影響を与え,日常生活動作や社会活動に大きな影響を及ぼす.関節拘縮に対する理学療法手技の1つに関節モビライゼーションがあり,足関節背屈制限に対して距腿関節,遠位脛腓関節へのモビライゼーションが治療として用いられる.臨床では距腿関節モビライゼーションが多く用いられているが,遠位脛腓関節に対する治療手技の効果について詳細は明らかにされていない.本研究の目的は,生体に近い未固定の遺体を用いて遠位脛腓関節の運動学的な特性を把握し,足関節拘縮に対する効果的な治療手技を検討することにある.【方法】実験には生前同意を得られた新鮮遺体標本7肢(男性5名,女性2名,平均死亡年齢79.9)を用いた.下肢標本を足底接地させ,中足骨と踵骨で木製ジグに固定した.近位の固定を行う前に足関節の背屈可動域,腓骨の運動を磁気センサー3次元空間計測装置(3Space Tracker System)を用いて計測した.次いで,足関節底屈10°を保持して大腿遠位部をジグに固定した.モビライゼーション手技を想定して腓骨外果を4方向(後方,後上方,上方,後外側)に,それぞれ19.6N,39.2Nの強度で牽引し,腓骨の変位をX(前後方向),Y(内外側方向),Z(上下方向)成分に分けて測定した.【結果】足関節の背屈可動域は平均13.25°±4.85であった.4つのモビライゼーション方向(後方,後上方,上方,後外側)の腓骨外果の変位はそれぞれ,X軸上で0.13±0.10,0.19±0.11,0.09±0.08,0.48±0.16,Y軸上で0.19±0.12,0.13±0.11,0.04±0.04,0.22±0.20,Z軸上で0.09±0.06,0.07±0.06,0.05±0.04,0.20±0.10であった.二元配置分散分析を用いて検定したところ,3軸方向成分全てにおいて牽引による変位量は統計学的に有意であった(X:P<0.0005,Y:P=0.005,Z: P<0.0005).牽引強度による変位量の比較ではX成分でのみ有意に39.2Nで大きかった(P<0.0005).方向と強度の相互作用については有意差が認められなかった.方向についてBonferroniの方法で多重比較したところ,X,Z成分では後外側とその他の方向,Y成分では上方とその他の方向のモビライゼーション間で有意差がみられた.【考察】以上の結果より,後外側方向へのモビライゼーション手技は腓骨を前後・上下方向へ大きく動かすことが明らかにされた.また上方向への手技では内外側への動きが少なかった.更に前後方向への変位にのみモビライゼーション強度が関与することが判明した.従って,足関節背屈制限に対する遠位脛腓関節のモビライゼーションにおいては,腓骨の後外側方向への滑り運動手技が有効であり,強い強度を用いた方がよいと考えられる.
1 0 0 0 OA 変形性股関節症患者の臼蓋形成不全は腸腰筋の筋萎縮と関連する
- 著者
- 南角 学 柿木 良介 西川 徹 松田 秀一
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0526, 2014 (Released:2014-05-09)
【目的】臨床場面において,臼蓋形成不全によって股関節痛を伴う股関節疾患に対して,大腿骨と臼蓋の安定化を図りながら,動作の改善を目指すことは多い。臼蓋形成不全による骨形態の変化は,大腿骨と臼蓋の構造的な安定性の破綻をきたすとともに股関節の安定性に関わるその他の因子の機能にも影響を及ぼす。特に,股関節周囲筋の筋出力や筋張力によって大腿骨頭に加わる力の大きさや方向が変化することで股関節の安定性に関与することから,これらのメカニズムを考慮しながら理学療法を展開していくことは重要である。しかし,臼蓋形成不全と股関節の安定化機構に関わる股関節周囲筋の関連性を検討した報告はなく,不明な点が多い。そこで,本研究の目的は,変形性股関節症患者における臼蓋形成不全と股関節周期筋の筋萎縮の関連性を明らかとすることとした。【方法】対象は片側の変形性股関節症患者44名(男性6名,女性38名)とした。測定項目は股関節周囲筋の筋断面積,脚長差,Central-edge angle(以下,CE角)とし,測定には当院整形外科医の処方により撮影されたCT画像と股関節正面のX画像を用いた。股関節周囲筋の筋断面積の測定は,Raschらの方法に従い,仙腸関節最下端での水平断におけるCT画像を採用し,画像解析ソフト(TeraRecon社製)を用いて各筋群の筋断面積の測定を行った。対象は梨状筋,腸腰筋,中殿筋,大殿筋とし,得られた筋断面積から患健比(患側筋断面積/健側筋断面積×100%)を算出した。また,股関節正面のX画像から,小転子先端から涙痕先端までの距離を計測し脚長差を算出するとともに臼蓋形成不全の評価としてCE角も算出した。その他の運動機能の評価として,IsoForceGT330(OG技研社製)にて膝関節伸展筋力を計測し,トルク体重比を算出した。さらに,臼蓋形成不全の診断基準値に準じてCE角が20°未満(臼蓋形成不全症例:以下,A群)と20°以上(以下,B群)の2群に分け,各測定項目の比較を行った。統計処理は,両群間の比較には対応のないt検定とMann-WhitneyのU検定を用いた。さらに,臼蓋形成不全の有無を目的変数,両群間で有意差を認めた項目を説明変数としたロジスティック重回帰分析を行い,統計学的有意水準は5%未満とした。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は京都大学医学部の倫理委員会の承認を受け,対象者には本研究の主旨ならびに目的を説明し研究への参加に対する同意を得て実施した。【結果】A群は24名(年齢:61.1±8.6歳,BMI:22.0±3.6kg/m2),B群は20名(年齢:65.9±10.7歳,BMI:23.0±3.0kg/m2)であり,年齢とBMIについては両群間で有意差を認めなかった。A群の梨状筋は60.8±14.5%,腸腰筋は62.2±10.5%,中殿筋は65.0±12.7%,B群の梨状筋は83.1±13.6%,腸腰筋は83.2±12.7%,中殿筋は84.6±8.3%であり,これらの筋についてはB群と比較してA群で有意に低い値を示した。一方,大殿筋(A群:76.3±11.0%,B群:83.1±8.4%)と膝関節伸展筋力(A群:1.31±0.56Nm/kg,B群:1.28±0.62Nm/kg)に関しては,両群間で有意差を認めなかった。また,A群の脚長差(23.9±9.9mm)は,B群(8.3±5.5mm)と比較して有意に大きい値を示した。さらに,ロジスティック重回帰分析の結果より,変形性股関節症患者の臼蓋形成不全と関連する因子として,脚長差と腸腰筋の筋萎縮が有意な項目として選択された。【考察】腸腰筋や梨状筋などの股関節の深部にある筋群は,それぞれの筋機能のバランスを保つことによって臼蓋と大腿骨頭の適合性すなわち股関節の安定化に寄与すること報告されている。また,中殿筋の後部線維は筋線維方向が頚体角と同等であることから股関節を求心位に保持する機能があることも報告されている。本研究の結果より,臼蓋形成不全症例では脚長差が大きく,大殿筋や膝関節伸展筋よりも股関節の安定性に関わる腸腰筋,梨状筋,中殿筋により顕著な筋萎縮を認めた。さらに,重回帰分析の結果より,臼蓋形成不全の影響を最も受けやすい筋は腸腰筋であることが明らかとなった。腸腰筋は大腿骨頭を前方から押さえることで臼蓋と大腿骨頭の安定性を向上させる作用があることから,臼蓋形成不全が大きい症例では股関節の前方への安定化がより欠如している可能性があり,これらのことを考慮した介入が必要であると考えられた。【理学療法研究としての意義】本研究の結果より,変形性股関節症患者の臼蓋形成不全は股関節の安定性に関与する筋群の萎縮と関連することが明らかとなり,理学療法において効果的なアプローチ方法を立案していくための一助となると考えられる。
- 著者
- 川島 康洋 湯浅 敦智 遠藤 昭 伊藤 俊一 隈元 庸夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.C0329, 2007
【目的】近年,急性期から実行可能なエクササイズとして腰部安定化エクササイズがあり,世界的トピックとなっている.McGillらは筋電図学的検討結果から腰部安定化エクササイズの一つとしてサイドブリッジを推奨している.しかし,本邦においてサイドブリッジの筋活動を詳細に検討したものは見られない.本研究の目的は,サイドブリッジ時の体幹筋群筋活動量と体幹筋持久力を筋電図学的に解析し,腰痛症者に対するより効率の良い筋力強化法の一助を得ることである.<BR>【方法】対象は,健常男性10名(年齢25.6±4.5歳,体重58.3±6.8kg)とした.表面筋電図の測定には,Noraxon社製筋電計Myosystem2400を用い導出筋は,左右内腹斜筋,左右外腹斜筋,左右多裂筋,右腹直筋,右脊柱起立筋の8筋とした.測定肢位は右側臥位から右肩90度外転・内旋位,肘90度屈曲位,左上肢は右肩を把持し,股関節中間位,膝90度屈曲位にて体幹を中間位で保持(以下膝屈曲位),上肢の肢位は変えず股関節中間位・膝関節伸展位にて,体幹を中間位で保持(以下膝伸展位)の2肢位とし各試行を3秒間保持させた.また,DanielsのMMTの抗重力肢位で各筋の最大等尺性収縮を施行しMVCを算出した.持久力における測定課題は膝伸展位肢位での保持とし,背部が真っ直ぐ保持できなくなったところで終了とした.表面筋電計から測定したデータはNoraxon社製筋電計MyoSystem2400 EM224にてサンプリング周波数1,500HzでA/D変換し,解析用パーソナルコンピューターに取り込んだ.波形解析はNoraxon社製MyoResearchEM123にて解析し,バンドパスフィルターは35~500HZとした.これらのデータより各筋の中間周波数と(MF)と,筋積分値(%MVC)を算出した.MFは開始後3秒後からの3秒間を初期,持続中間の3秒間を中期,終了前3秒間を終期とし経時的変化を検討した.<BR>なお統計処理には,Wilcoxonの符号順位和検定を用いて有意水準を5%未満とした.<BR>【結果と考察】サイドブリッジにおける筋活動量に関して,膝伸展位では右内腹斜筋,右外腹斜筋において50%MVC以上の高い筋活動を認めた.また膝屈曲位と比較し,膝伸展位の方が右内腹斜筋,両側外腹斜筋の有意に高い筋活動を認めた.持久力に関して,MFにおいては腹斜筋群で初期と比べて終期で有意な低下を認めた.なお,保持時間は平均90秒以上の保持が可能であった.本研究の結果,腹斜筋群の筋力訓練としてサイドブリッジは有用であると考えられる.また,腹斜筋群に対する持久力評価としても有用となる可能性が示唆された.今後,筋電図学的検討を加え,腰痛症者でも検討することでより効率の良い評価・治療方法の選択肢となる可能性があると考えられる.<BR><BR><BR>
- 著者
- 尾崎 尚代 千葉 慎一 嘉陽 拓 大野 範夫 鈴木 一秀 牧内 大輔 筒井 廣明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.C0889, 2007
【はじめに】腱板完全断裂症例に対する理学療法の目的は、疼痛の除去および残存腱板や上腕二頭筋長頭腱での代償作用を引き出し、肩関節の運動能力を改善することにある。しかし、広範囲断裂や長頭腱断裂を伴う症例の中には、これらの代償作用を得られずとも上肢挙上が可能となり、ADL上の支障がなくなる症例を経験する。そこで、理学療法を実施した腱板完全断裂症例について追跡調査し、若干の知見が得られたので報告する。<BR>【方法】対象は、当院にてMRIまたはMRAで腱板完全断裂と診断を受けて理学療法を行い6ヶ月以上の経過観察が可能であった20例20肩(男性11肩、女性9肩)であり、外傷歴は有11例・無9例、断裂部の大きさは3.5mm未満6例・3.5mm以上14例、単独断裂11例・複数腱断裂9例である。これらの症例に対しJOA scoreの推移とレ線的検討を行った。尚、治療開始時年齢は平均67.35歳、発症から当院初診までの期間は平均17.07ヶ月、経過観察期間は平均15.90ヶ月であり、手術療法に移行した症例は除外している。<BR> JOA scoreの推移は、疼痛、機能、可動域について、初診時、1ヵ月後・3ヵ月後・6ヵ月後・9ヵ月後・1年後・最終診察時の推移を調査した。また、X線的検討はScapula45撮影法での45゜無負荷保持を用い、最終診察時の自動屈曲可動域が120度以上尚且つ30度以上の改善を良好群、それ以外を不良群に分類して、腱板機能および肩甲骨機能について検討した。<BR>【結果】X線所見・関節不安定性を除いたJOA score(80点満点)の推移は、初診時41.93点±14.68から最終診察時67.83点±8.61と有意に改善した(p<0.001)が、初診時と比較して疼痛は理学療法開始1ヶ月後(p<0.01)、機能は3ヵ月後(p<0.02)、可動域は6ヵ月後(p<0.02)以降で有意に改善したものの、外傷歴や断裂腱の数、大きさとの関係には有意差は認められなかった。<BR>またX線的検討の結果、良好群13例(屈曲148.85度±19.49)・不良群7例(屈曲104.29度±22.81)共に肩甲骨関節窩に対して骨頭の上昇が著明であるが、胸郭上の肩甲骨の上方回旋角度は正常値(12.30±4.1)に比して良好群では小さく(2.02±7.01)なり、不良群では大きく(25.53±17.82)なっていた(p<0.001)。<BR>【考察】今回の結果、腱板断裂症例に対しては、疼痛を理学療法開始後1ヶ月以内に、機能を3ヶ月以内に理学療法の効果を出す必要があることがわかった。また、腱板断裂症例の可動域改善には残存腱等での代償動作のみならず、上腕骨に対して肩甲骨関節窩をあわせるような肩甲骨の下方回旋運動が可能である必要性が示唆され、肩甲骨の可動性と共に、いわゆるouter musclesの機能により肩甲上腕関節の適合性を得ることで上肢挙上が可能になり、ADL拡大につながると考える。
- 著者
- 廣澤 隆行 沖田 一彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.C0962, 2007
【目的】我々は第10回広島県理学療法士学会にて,理学療法士(PT)が長期化した外来患者を単に医学的側面からだけでなく,心理・社会的側面を含む複数の視点から捉え悩んでいることを報告した。今回,その結果をもとに,整形外科疾患患者の痛みの訴えに対するPTの認識や悩みについてアンケート調査を実施したので報告する。<BR>【方法】広島県下で整形外科の標榜を掲げる医療機関に勤務するPT 250名に対し,郵送によるアンケートを実施した。質問は,基礎項目および患者の痛みの訴えで悩んだ経験とそれに関わる項目の計21項目であった。返送された126部の回答(回収率50.4%)から,顕著な記入漏れ・ミスがあるものを除外した112部(有効回答率88.9%)を分析対象とした。分析はまず,患者の痛みの訴えに悩んだ頻度(4段階)の差を,性別,婚姻,同居者,勤務地,関わっている診療科,勤務先の変更経験の6項目についてχ<SUP>2</SUP>検定により比較した。次に,年齢,経験年数,学歴,勤務先の規模,常勤PT数,疾患別の診療頻度,重視する専門知識,治療内容と頻度,痛みと理学所見との不一致性,患者‐PT間での認識のギャップ,効果がない場合の治療の継続性,患者の社会的側面への注意の12項目についてSpearmanの相関を調べた。そのうえで,有意差のあった項目を独立変数としたロジスティック解析(漸減法)を行い,悩みの頻度への影響因子を抽出した。<BR>【結果】患者の痛みの訴えに悩んだ経験は「ない」1名(0.9%),「ときどき」25名(22.3%),「しばしば」58名(51.8%),「常に」28名(25.0%)であった。χ<SUP>2</SUP>検定を行ったすべての項目において回答の分布に有意差はなかった。一方,相関を調べた項目については,年齢(r=-0.23, p<0.05),経験年数(r=-0.38, p<0.01),学歴(r=0.23, p<0.05),診療頻度・関節リウマチ(r=0.21, p<0.05),同・五十肩(r=0.21, p<0.05),専門知識・心理学(r=0.25, p<0.05),同・教育学(r=0.21, p<0.05),同・行動科学(r=0.27, p<0.05),理学所見との不一致性(r=0.29, p<0.01),認識のギャップ(r=0.40, p<0.01),治療の継続性(r=0.28, p<0.01)との間に有意な相関を認めた。ロジスティック解析の結果(OR=オッズ比, CI=95%信頼区間),経験年数(OR=0.25, CI=0.11-0.56, p<0.01),行動科学(OR=2.97, CI=1.33-6.62, p<0.01),認識のギャップ(OR=3.08, CI=1.12-8.44, p<0.05)が有意な影響因子として抽出された。<BR>【考察】整形外科疾患患者の痛みの訴えは治療の長期化を招く重大な要因であり,当然PTもその対応に苦悩することになる。今回の結果から,臨床経験が浅く,痛みの改善について患者との間に認識のギャップがあると感じているPTほど悩んでいることが分かった。またそのようなPTは,必要な専門知識として行動科学を重視していると考えられた。
- 著者
- 川野 大二郎 宮下 浩二 井出 善広 増田 清香 岡本 健
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.C3P3432, 2009
【目的】野球肘の発生要因として、投球動作などの個体要因、投球数などのトレーニング要因、使用するボールなどの環境要因が挙げられる.硬式球と軟式球ではボールの重さが異なり、特に成長期の選手における硬式球の使用は経験的に発生要因となることが知られているが、その影響について定性的に分析した研究はほとんどない.そこで本研究では、ボールの重さの違いによる投球時の肩関節と肘関節の運動学的差異を比較することを目的とした.<BR><BR>【方法】対象は中学生の軟式野球選手15名(年齢13.9±0.7歳、野球歴6.1±1.9年)とした.対象に硬式球(146.5g)および軟式球(135.5g)の2条件で投球を行わせ、ステップ脚の足部接地時からリリースまでの肩外旋角度、肘関節外反角度、肘関節外反角加速度を三次元動作解析にて算出し、両条件間で比較した.また、肘関節外反角加速度とボールの質量の積による運動方程式を用い、加速期において肘関節に加わる外反方向への力を求め、軟式球投球時に加わる力に対する硬式球投球時に加わる力の比率を算出した.各角度の両条件間の比較には繰り返しのある二元配置分散分析を用いた.肘関節に加わる外反方向への力の比率の検定にはWilcoxon符号付順位和検定を用いた.いずれの検定も危険率5%未満を有意とした.<BR><BR>【結果】肩関節外旋角度、肘関節外反角度については両条件間に有意な差はなかった.肘関節外反角加速度については、肩最大外旋位からリリースの間で硬式球投球時が軟式球投球時より有意に大きかった.また、肘関節外反方向へ加わる力の比率は、軟式球投球時を1とした時、硬式球投球時は1.8±1.7となり、硬式球投球時には軟式球投球時と比較して約1.8倍の力が肘関節外反方向へ加わっていた.<BR><BR>【考察】野球肘の発生は加速期における肘関節外反ストレスが原因の一つとされており、そのストレスを増大させる要因を明らかにすることが野球肘の予防には重要となる.肘関節外反ストレスは、主に加速期おいて近位部に対して遠位部が遅れる現象、いわゆるlagging backによって生じる.今回、加速期において硬式球投球時には軟式球投球時の約1.8倍の力が肘関節外反方向へ加わっていた.これは硬式球投球時にボールの重さの影響で、ボールを持った手部を含む前腕部の慣性が大きくなり、後方へ残る結果として、肘関節外反角加速度が有意に大きくなったためと考えられる.以上より、硬式球は肘関節外反ストレスを増大させる要因の一つとして考えられ、野球肘発生のリスクとなる可能性が示唆された.
1 0 0 0 投球障害における手内筋の機能不全について
- 著者
- 栗田 健 市薗 真理子 山崎 哲也 明田 真樹 石井 慎一郎 木元 貴之 小野 元揮 日野原 晃 岩本 仁 松野 映梨子 久保 多喜子 田仲 紗樹 吉岡 毅
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.CbPI2254, 2011
【目的】<BR> 投球障害肘・肩の原因は投球フォームの不正や体幹・下肢の機能不全によるといった報告は多く、臨床上これらの問題を有する症例を多く経験する。しかしこれらは、肘・肩双方に関与している要素であり、両関節への病態プロセスは不明な点が多い。過去に手指、手部、前腕部の機能不全と投球障害肘や肩との関連が報告されており、また一般的に投球障害肘のおける手内筋機能の重要性が指摘されている。そこで今回、肘・肩関節より遠位部である手内筋の虫様筋および母指・小指対立筋の機能と投球障害肘および肩との関連を調査したので報告する。<BR>【方法】<BR> 対象は、投球障害肘もしくは肩の診断により当院リハビリテーション科に処方があった24症例とした。肘・肩障害単独例のみとし、他関節障害の合併や既往、神経障害および手術歴を有する症例は除外した。性別は全例男性で、投球障害肘群(以下肘群)13例の年齢は、平均15.1±2.8歳(11歳~21歳)、投球障害肩群(以下肩群)11例は、平均23.5±11.0歳(10歳~42歳)であった。評価項目は、虫様筋と母指・小指対立筋とし、共通肢位として座位にて肩関節屈曲90°位をとり、投球時の肢位を想定し肘伸展位・手関節背屈位を保持して行った。虫様筋は、徒手筋力検査(以下MMT)で3を参考とし、可能であれば可、指が屈曲するなど不十分な場合を機能不全とした。母指・小指対立筋も同様に、MMTで3を参考とし、指腹同士が接すれば可、IP関節屈曲するなど代償動作の出現や指の側面での接触は機能不全とした。また上記結果より肘・肩両群における機能不全の発生比率を算出し比較検討した。<BR>【説明と同意】<BR> 対象者に対し本研究の目的を説明し同意の得られた方のデータを対象とし、当院倫理規定に基づき個人が特定されないよう匿名化に配慮してデータを利用した。<BR>【結果】<BR> 虫様筋機能不全は、肘群で53.8%、肩群で18.2%、母指・小指対立筋機能不全は、肘群で61.5%、肩群で27.2%と両機能不全とも肘群における発生比率が有意に高かった。<BR>【考察】<BR>一般的なボールの把持は、ボール上部を支えるために第2・3指を使い、下部を支えるために第1・4・5指を使用している。手内筋である虫様筋は、第2・3指が指腹でボールを支えるために必要であり、また母指・小指対立筋は、ボールの下部より効率よく支持するために必要である。手内筋が、効率よく機能しボールを把持することが可能であれば、手外筋への負担が減少し、手・肘関節への影響も少なくなる。本研究では、肘群において有意に手内筋機能不全の発生率が高く、虫様筋、母指・小指対立筋の機能低下によるボール把持の影響は、隣接する肘関節が受けやすいことが示唆された。その為、投球障害肘の症例に対してリハビリテーションを行う場合には、従来から言われている投球フォームの改善のみではなく遠位からの影響を考慮して、虫様筋機能不全および母指・小指対立筋機能不全の確認と機能改善が重要と考えられた。しかし本研究だけでは手内筋機能不全が伴って投球動作を反復したために投球障害肘が発生するのか、肘にストレスがかかる投球動作を反復したために手内筋機能不全が発生したのかは断定できない。今後はこれらの要因との関係を分析し報告していきたい。<BR>【理学療法学研究としての意義】<BR> 投球障害肘・肩の身体機能の要因の中で投球障害肘は手内筋である虫様筋や母指・小指対立筋に機能不全を有する比率が多いことが分かった。本研究から投球障害肘を治療する際には、評価として手内筋機能に着目することが重要と考える。また今回設定した評価方法は簡便であり、障害予防の観点からも競技の指導者や本人により試みることで早期にリスクを発見できる可能性も示唆された。<BR>
1 0 0 0 OA 若年者と高齢者における体幹筋の筋厚および筋輝度の比較
- 著者
- 星 翔哉 佐藤 成登志 北村 拓也 郷津 良太 金子 千恵
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0076, 2016 (Released:2016-04-28)
【はじめに,目的】加齢に伴い筋内脂肪は増加するとされている。高齢者における筋内脂肪は,身体機能と負の相関を示すと報告があることからも,わが国の高齢化社会において,体幹筋の筋内脂肪を把握することは重要であると考えられる。また,体幹筋の筋量低下は高齢者のADL低下の大きな要因であると報告もある。このことから,体幹筋の評価において,量と質を併せて検討することが必要であると考えられる。近年,筋内脂肪の評価方法として,超音波エコー輝度(以下,筋輝度)が用いられており,脂肪組織と筋輝度との関連性も報告されている。しかし,加齢による筋厚と筋輝度の変化に着目した報告の多くは,四肢筋を対象としており,体幹筋についての報告は少ない。本研究の目的は,健康な成人女性を対象に,若年者と高齢者における体幹筋の筋厚および筋輝度を比較し,加齢による量と質の変化を明らかにすることを目的とした。【方法】対象者は,健常若年女性(以下,若年群)10名(年齢20.6±0.7歳,身長159.9±5.4cm,体重51.4±4.8kg,BMI20.1±1.5)と,健常高齢女性(以下,高齢群)10名(年齢68.6±3.9歳,身長152.6±8.1cm,体重51.2±3.9kg,BMI22.4±1.7)とした。使用機器は超音波診断装置(東芝メディカルシステムズ株式会社)を使用した。測定肢位は腹臥位および背臥位。測定筋は,左右の外腹斜筋,内腹斜筋,腹横筋,多裂筋,大腰筋とした。得られた画像から各筋の筋厚を測定し,画像処理ソフト(Image J)を使用して筋輝度を算出した。なお筋厚は量,筋輝度は質の指標とした。得られたデータに統計学的解析を行い,有意水準は5%とした。また筋厚および筋輝度の信頼性は,級内相関係数(以下,ICC)を用いて,検者内信頼性を確認した。【結果】ICCの結果,筋厚と筋輝度は0.81以上の高い信頼性を得た。筋厚における若年群と高齢群の比較では,左右ともに外腹斜筋,内腹斜筋,大腰筋で高齢群が有意に小さく(p<0.05),腹横筋,多裂筋は有意な差は認めなかった。筋輝度においては,左右ともに外腹斜筋,内腹斜筋,腹横筋,多裂筋,大腰筋で高齢群が有意に高かった(p<0.05)。【結論】本研究の結果より,外腹斜筋,内腹斜筋,大腰筋は加齢に伴い筋厚は低下し,筋輝度が高かった。一方,腹横筋と多裂筋では,筋輝度は高くなるが,筋厚の低下は生じていなかった。すなわち体幹筋においては,加齢に伴い,筋厚が低下するだけではなく,筋内脂肪や結合組織の増加といった筋の組織的変化も生じていることが明らかになった。しかし,体幹深部に位置し,姿勢保持に関与している腹横筋と多裂筋は,加齢により筋厚の低下が起こりにくいと考えられる。以上のことから,加齢に伴い外腹斜筋,内腹斜筋,大腰筋は量と質がともに低下するが,腹横筋と多裂筋は質のみが低下し,量の変化は生じにくいことが示唆された。
1 0 0 0 上肢支持による前傾立位が安静時の呼吸機能に与える影響
- 著者
- 矢野 雄大 朝井 政治 田中 貴子 千住 秀明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Da0987, 2012
【はじめに、目的】 呼吸器疾患患者が訴える主症状の一つに動作時の呼吸困難がある。呼吸リハビリテーションマニュアルでは患者が動作時に呼吸困難を訴えた際は、前傾座位にて肘や前腕で机などにもたれるような安楽姿勢をとることを推奨している。しかし、この姿勢の効果に関しては一定の見解が示されておらず、実際にエビデンスレベルもGrade D(Thorax;2009)である。また、屋外歩行時などに呼吸困難が生じた際に、そのような姿勢をとることは難しく、臨床的には、肘関節伸展位で体幹を支持する前傾立位をとることが多い。そこで今回、上肢支持による前傾立位を生理学的に検証するため、健常成人を対象として上肢支持による前傾立位が安静時の呼吸機能に与える影響を検討した。【方法】 対象は健常成人20名(男性14名、年齢31.2±7.4歳、body mass index(BMI) 21.5±2.2kg/m2)である。方法は各対象者に直立位、上肢支持による30°前傾立位(上肢前傾立位)の2つの肢位で、安静時の呼吸機能をスパイロメータ(DISCOM-21 FXIII,CHEST社)にて測定した。上肢前傾立位は固定型歩行器に肘関節伸展位で体幹を前傾させる姿勢とした。また体幹前傾角度は大腿骨と、股関節・肩峰を結ぶ直線のなす角を角度計にて測定し決定した。また測定中は体幹や頚部など可能な限り同一姿勢を保持するように各対象者へ事前に説明した。測定項目は肺気量分画、フローボリューム曲線、最大換気量(MVV)とした。各姿勢で2回の測定を同日内に行い、最良値を採用した。測定姿勢の順番は、封筒法により無作為に決定した。姿勢別の各測定値の解析にはデータの正規分布の有無により、対応のあるt検定、Wilcoxonの符号付順位検定を使用した。有意水準は5%未満とした。【倫理的配慮、説明と同意】 対象者には事前に研究に関する十分な説明を行い、同意を得た上で研究を実施した。またデータはすべて暗号化し、個人を特定できないように配慮した。【結果】 姿勢の違いにより有意差のあった項目は、肺活量(VC;直立位 4.13L vs 上肢前傾立位 4.22L)、予備呼気量(ERV;1.93L vs 2.30L)、予備吸気量(IRV;1.62L vs 1.26L)、最大吸気量(IC;2.18L vs 1.92L)、努力肺活量(FVC;4.13L vs 4.24L)、一秒量(FEV1;3.41L vs 3.52L)、最大呼気流量(PEF;7.59L vs 7.86L)、50%肺活量時の流速(V50;3.91L vs 4.37L)、最大換気量(MVV;122.5L vs 128.6L)であった。また一回換気量(TV;0.59L vs 0.66L)、一秒率(FEV1%;82.8% vs 83.6%)でも上肢前傾立位で高値となる傾向を認めた。【考察】 直立位に対して上肢前傾立位では、ERVが有意に高値、かつTVも高値となる傾向を示し、その結果VCも高値となった。またFEV1や中枢気道の流速であり努力依存性のPEF、末梢気道の流速である努力非依存性のV50など呼気に関わる気量と流速も同様に上肢前傾立位で有意に高値を示した。これは体幹前傾姿勢と上肢による支持による効果であると考えられる。体幹前傾姿勢では胸郭の前後方向への重力作用が増加し、高肺気量位の呼吸となることが報告されており、より呼気を促すことが可能となると考えられる。さらに上肢支持が加わる効果として、外腹斜筋の活動量を高め下部胸郭の収縮を促すことが可能となることや、大胸筋なども呼気筋として動員することが可能となるとの報告がある。本研究でも、上肢前傾立位では腹圧を高めやすく、かつ高肺気量位となった結果、ERVやFEV1、PEF、V50などが増加し、それらの呼気能力の向上によりVCやFVCにも増加が生じたと推察される。また上肢支持による前傾立位により最大の換気容量の指標であるMVVが増加するとされているが、本研究でも同様の結果が得られた。これには一回の換気能力の向上が影響していると考えられる。以上より、健常成人では上肢支持による前傾立位では呼気を中心として換気能力を向上させることが示唆された。今後の課題としては、静的な状態での呼吸機能の変化が、運動後など動的な状態にも影響するかを検討していく必要がある。また、健常成人での変化が、慢性閉塞性肺疾患患者などでも同様に認められるかを検証することが求められる。【理学療法学研究としての意義】 臨床的に頻繁に用いられる上肢支持の前傾立位を生理学的に分析し、効果を明らかにすることで、呼吸困難からの回復に有効な安楽姿勢であると明らかにする。
- 著者
- 林 典雄 浅野 昭裕 青木 隆明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.CaOI1021, 2011
【目的】肘関節周辺外傷後生じる伸展制限に対する運動療法では、特に終末伸展域の改善には難渋することが多い。その要因について筆者らは、上腕筋の冠状面上での筋膜内における筋束の内側移動、上腕骨滑車を頂点とした遠位筋線維の背側へのkinkig、加えて長橈側手根伸筋の筋膜内後方移動、上腕骨小頭と前面の関節包と長橈側手根伸筋のmusculo-capsular junctionでの拘縮要因などについて、超音波観察を通した結果を報告してきた。一方、肘伸展制限は前方組織にのみ由来するわけではなく、肘伸展に伴う後方部痛の発生により可動域が制限される症例もまれではない。このような肘終末伸展に伴う後方部痛は、関節内骨折後の整復不良例や肘頭に発生した骨棘や遊離体が原因となる骨性インピンジメントを除けば、後方関節包の周辺組織の瘢痕や関節包内に存在する脂肪体に何らかの原因を求めていくのが妥当と考えられる。本研究の目的は、後方インピンジメント発生の好発域である30°屈曲位からの終末伸展運動における肘後方脂肪体の動態について検討し、運動療法へとつながるデータを提供することにある。<BR>【方法】肘関節に既往を有しない健常成人男性ボランティア10名の左肘10肘を対象とした。肘後方脂肪体の描出にはesaote社製デジタル超音波画像診断装置MyLab25を使用した。プローブは12Mhzリニアプローブを用いた。方法は、被験者を測定台上に腹臥位となり、左肩関節を90°外転位で前腕を台より出し、肘30°屈曲位で他動的に保持した。その後徐々に肘を伸展し、15°屈曲時、完全伸展時で後方脂肪体の動態を記録した。<BR> 画像の描出はプローブにゲルパッドを装着して行った。上腕骨後縁が画面上水平となるように肘頭窩中央でプローベを固定すると、上腕骨後縁、肘頭窩、上腕骨滑車、後方関節包、後方脂肪体、上腕三頭筋が画面上に同定される。その後、上腕骨後縁から肘頭窩へと移行する部分で水平線Aと垂線Bを引き、水平線Aより上方に位置する脂肪体と垂線Bより近位に位置する脂肪体それぞれの面積を計測し、前者を背側移動量、後者を近位移動量とした。脂肪体面積の計測はMyLab25に内蔵されている計測パッケージのtrace area機能を使用した。統計処理は一元配置の分散分析ならびにTukeyの多重比較検定を行い有意水準は5%とした。<BR>【説明と同意】なお本研究の実施にあたっては、本学倫理委員会への申請、承認を得て実施し、各被験者には研究の趣旨を十分に説明し書面にて同意を得た。<BR>【結果】背側移動量は30°屈曲時平均26.7±10.5mm2 、15°屈曲時平均42.2±16.1mm2 、完全伸展時平均59.7±15.5mm2であった。完全伸展時の脂肪体背側移動は、30°屈曲時、15°屈曲時に対し有意であった。30°屈曲時と15°屈曲時との間には有意差はなかった。近位移動量は30°屈曲時平均5.4±2.9mm2 、15°屈曲時平均11.9±8.4mm2 、完全伸展時平均20.6±10.8mm2 であった。完全伸展時の脂肪体近位移動は、30°屈曲時に対し有意であった。30°屈曲時と15°屈曲時、15°屈曲時と完全伸展時との間には有意差はなかった。<BR>【考察】本研究で観察した後方脂肪体は滑膜の外側で関節包の内側に存在する。肘後方関節包を裏打ちする形で存在するこの脂肪体は、超音波で容易に観察可能であり、薄い関節包の動態を想像する際に、伸展運動に伴う脂肪体の機能的な変形を捉えることで、間接的に後方関節包の動きを推察することが可能である。今回の結果より後方脂肪体は、肘の伸展に伴い肘頭に押し出されるように機能的に形態を変形させながら、より背側、近位へ移動することが明らかとなった。この脂肪体の移動は併せて関節包を背側近位へと押し出す結果となり、後方関節包のインピンジメントを回避していると考えられた。我々は以前に後方関節包には上腕三頭筋内側頭由来の線維が関節筋として付着し、肘伸展に伴う挟み込みを防ぐと報告したが、後方脂肪体の機能的変形も寄与している可能性が示唆された。投球に伴う肘後方部痛症例や関節鏡視下に遊離体などを切除した後の症例で伸展時の後方部痛を訴える例では、後方脂肪体の腫脹像や伸展に伴うインピンジメント像をエコー上で観察可能であり、肘後方インピンジメントの一つの病態として認識すべきものと考えられた。<BR>【理学療法学研究としての意義】実際の運動療法技術においては、後方関節包自体の柔軟性はもちろん、肘頭窩近位へ付着する関節包の癒着予防が脂肪体移動を許容する上で重要であり、内側頭を含めた上腕骨からの引き離し操作も拘縮治療を展開するうえでポイントとなる技術と考えられる。
1 0 0 0 OA 大腰筋エクササイズが重心動揺に与える影響(運動学)
- 著者
- 森田 暁 北脇 真理 宇於崎 孝 山崎 敦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.29 Suppl. No.2(第37回日本理学療法学術大会 第29巻大会特別号 No.2 : 演題抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.270, 2002-04-20 (Released:2018-03-06)
- 著者
- 小林 祐太 中井 雄一朗 木勢 峰之 矢口 悦子 米田 香 古河 浩 寺岡 彩那 山﨑 敦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Ab0658, 2012
【はじめに、目的】 股関節疾患患者において、バランス能力低下により立位や歩行での動揺の増大がよくみられる。不安定板上立位での姿勢制御の反復練習にて、より高い姿勢制御能力が獲得される可能性があるとした報告はあるものの、立位や歩行にどのように影響するかの報告は少ない。そこで本研究では、股関節疾患患者に対し不安定な支持面での立位バランス練習にて、実施前後での即時的な重心動揺や歩行の変化について検討する。【方法】 対象者は当院整形外科受診の前期股関節症1名と、変性疾患・外傷により手術治療 (人工股関節全置換術2名、ハンソンピン1名、γ-nail1名)を施行した4名を対象とした。性別は、男性3名、女性2名、年齢67.5±9.1歳とした。立位バランス練習には、株式会社LPNのハーフストレッチポール(以下HSP)を使用した。HSPは平面側を床側にして、規定した幅(身長×0.40÷2)で横向きに並ぶように前後に1つずつ設置した。その上に片脚ずつ均等な荷重で乗せて歩隔は肩幅として立位をとり、5秒保持した後に、15秒休息をとった。次に脚を前後逆にして同様に行い、これを1セットとして、計5セット行った。この運動前後に、小型三次元加速度計(ユニメック社)を第3腰椎の高さに固定し、自由歩行の加速度を計測した。また、フットスイッチを踵部に装着して踵接地を同定した。サンプリング周波数は200Hzとし、アナログ解析ソフトWAS(ユニメック社)にて9Hzのローパスフィルターで処理し、二乗平方根値を歩行速度の二乗値で除した値(以下RMS)を加え前後・側方・垂直成分にて解析した。さらに、定常歩行から得られた患側踵接地からの1歩行周期の加速度波形に対して自己相関係数(以下ACC)の前後・側方・垂直成分を算出した。また、患側上後腸骨棘、大転子、大腿骨外側上顆の3点にマーカーをつけ、加速度測定時の歩行をデジタルカメラで撮影し、ICpro-2DdA(ヒューテック株式会社)にて歩行時の3点間の角度を算出した。この結果を静止立位時と比較して、患側立脚後期の股関節最大伸展角度を算出した。さらに、重心動揺計(ユニメック社)を使用し、運動前後の重心動揺を計測した。開眼・自然立位にて20秒間の測定を行った。指標として、前後・側方方向単位軌跡長を用いた。各々の値は2回の測定結果の平均値を用い、その結果を基に中央値と四分位範囲で表し運動前後を比較した。統計処理にはPASW Statistics 18を用いてWilcoxon signed-rank testを行い、5%未満を統計学的有意とした。【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき、対象者には本研究の目的、内容、個人情報取り扱いについて口頭および書面にて説明し、同意書への署名により同意を得た。また、本研究は当院倫理委員会の承諾を得て行った。【結果】 各項目は運動前→運動後の順に中央値(四分位範囲)で示す。RMSは前後成分0.15(0.08)→0.16(0.17)、側方成分0.14(0.07)→0.14(0.07)、垂直成分0.22(0.12)→0.12(0.12)であったが、有意差は見られなかった。ACCは前後成分0.85(0.15)→0.88(0.07)、側方成分0.67(0.28)→0.76(0.11)、垂直成分0.66(0.17)→0.89(0.11)と3方向において増加が見られ、側方成分には有意な増加が見られた。 重心動揺は前後方向単位軌跡長(mm/s)が9.55 (3.30)→6.70 (4.35)、側方方向単位軌跡長(mm/s)が4.45 (1.85)→4.60 (1.25)と前後は減少が見られ、側方は増加が見られたが有意差は見られなかった。股関節伸展角度(°)は-0.72(2.75)→-5.24(5.76) と有意な減少が見られた。【考察】 不安定な支持面での立位姿勢保持には、効果的に足関節トルクを用いることができず、股関節による制御が行われるといった報告がみられる。今回HSP上で不安定な立位状況を設定することで、股関節による制御が促通されることを仮説として本研究を実施した。今回の結果から、股関節での制御が促通され、歩行時の側方の規則性において有意に改善させた可能性が示唆される。側方の姿勢制御は、足関節に対して股関節が優位とされていることから上記の結果に繋がったと推察される。一方、歩行時の前後方向への動揺性の増加は、立脚後期の股関節伸展角度減少による推進力低下を体幹などで代償した結果、前後方向の動揺性の増加に起因したのではないかと考えられる。今後は、運動時中の筋電図測定なども行い、姿勢制御戦略に影響を与えている因子を検討していく必要がある。【理学療法学研究としての意義】 本研究の運動が、即時効果として立位や歩行時に影響を与えることが確認できた。不安定な支持面で姿勢制御戦略を促通させることは、股関節疾患患者の歩行効率の改善に有効であることが示唆される。
1 0 0 0 下位頸椎伸展可動域と頸部深層屈筋群の関連
- 著者
- 野元 友貴 矢部 綾子 石井 恵美 安彦 和星 本田 篤司 高島 嘉晃
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.CdPF2037, 2011
【目的】<BR> 頸椎は重い頭部を支えるわりに大きな可動性を有し、可動性の確保は頭頸部周囲筋群のバランスが重要視されている。頸部伸展動作では上位頸椎の過伸展、下位頸椎伸展制限(以下、伸展制限)が生じる事が多く、その要因の一つとして頸部深層屈筋群(以下、屈筋群)の機能低下が考えられる。先行研究では頸部痛患者や頭部前方位などの姿勢不良と頸部表層筋群の筋活動増加や屈筋群の機能低下との関連は報告されている。しかし屈筋群の機能低下が伸展制限を起こすとの報告は無く、屈筋群の機能と下位頸椎伸展可動域の関連を明らかにした研究は少ない。その為、本研究ではJullらの屈筋群の評価であるCranio-Cervical Flexion Test(以下CCFT)を用い、圧力量として数値化し、屈筋群と下位頸椎伸展可動域の関連を明らかにする事を目的とした。<BR>【方法】<BR> 頸部に痛みの訴えのない健常成人男性25名、女性15名、年齢25.9±7.0歳、身長166.1±8.0cm、体重63.2±14.4kgとした。頭頸部伸展運動は第3頸椎横突起と肩峰にマーカーを付け、安静坐位にて下位頸椎伸展最終域を矢状面からデジタルカメラ(CASIO社製)で撮影し画像分析ソフトimageJにより角度を算出した(以下、伸展角度)。屈筋群圧力量の測定はベッド上に背臥位となり、後頭下部にアネロイド型血圧計のマンシェットを置き、肩峰と耳垂を結んだ線とベッドが水平となる肢位で行った。CCFTに従い、後頭下部のマンシェットに空気を入れ、圧力計が基準値の20mmHgになるよう調節した。胸鎖乳突筋に筋電計を付け筋活動の観察をしながら頸椎前彎を減少させる様に頭部をうなずいてマンシェットを圧迫してもらった。圧力計が22,24,26,28,30mmHg指すように小さい圧力からうなずいてもらい各目標値を3秒間保持する。その中での胸鎖乳突筋の筋活動が生じない状態での保持可能な最大圧力量を測定した。統計学的検討は保持可能であった最大圧力量と伸展角度に対し正規分布検定を行い、正規分布と仮定した両値の関連性をピアンソンの相関係数を用いて検討した。また各圧力最大値で群分けし、各群の伸展角度に対しノンパラメトリック法の多重比較検定を行った(p<0.05)。<BR>【説明と同意】<BR> ヘルシンキ宣言に基づき事前に被験者に文章と口頭にて実験内容と利益、不利益を十分に説明し同意を得た。<BR>【結果】<BR> 最大圧力量と伸展角度はr=0.66と高い相関を認めた。各最大圧力量の伸展角度は22mmHgでは-6.55±7.50°、24mmHgは2.48±9.40°、26mmHgは6.42±6.74°、28mmHgは9.78±6.16°、30mmHg以上は14.77±5.87°であった。伸展角度は22mmHgと24mmHgの間では有意な差は無く、22mmHg、24mmHgと比べ26、28、30mmHgにおいて有意に増加した。28、30mmHg間での有意な差は無かった。<BR>【考察】<BR> 今回の結果により、屈筋群の機能低下がある場合、伸展制限を有する可能性が高い事が示唆され、また最大圧力量が24mmHg以下の場合に伸展制限がある可能性が高い。これは屈筋群のエクササイズにより頸部伸展可動域が増加するとの先行研究を補足する結果となった。頸部伸展動作は頭部と上位頸椎から動きだし徐々に下位頸椎が動き出す。下位頸椎が伸展する頸部伸展動作の後半では表層屈筋群の屈曲モーメントアームが減少し、屈筋群の遠心性収縮が必要な為、機能低下により伸展制限が生じていたと考える。<BR>【理学療法学研究としての意義】<BR> 今回は屈筋群と伸展制限が関連している事、屈筋群の機能低下が伸展制限として表出する可能性が示唆された。この事から下位頸椎の伸展可動域が屈筋群の機能評価の一つにとなりえる可能性が考えられた。
- 著者
- 遠藤 康裕 中澤 理恵 坂本 雅昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Ca0937, 2012
【はじめに、目的】 中学生年代の野球選手では,骨端線の存在や骨の成長が筋・腱に比べ早いといった特徴があり,身体が解剖学的に未熟で成人より脆弱である.これらの特徴より,Little leaguer's shoulder,Little leaguer's elbowなど上肢の障害が多くみられる.また,投球肩障害の評価項目の一つとして,座位での徒手的肘関節伸展筋力の評価が行われており,これにより体幹・肩甲帯のインナーとアウターの筋機能バランスを評価することができると考えられている.臨床でも肩甲帯,体幹の機能低下により肘関節伸展時,脱力現象がみられるものが少なくない.そこで今回は,姿勢による等尺性肘関節伸展筋力の違いと体幹機能との関連を検討し,体幹機能評価としての肘関節伸展筋力測定の有用性を明らかにすることを目的とした.【方法】 対象は中学校軟式野球部に在籍する男子中学生1・2年生23名(年齢:13.2±0.8歳,身長:157.3±8.6cm,体重:49.6±9.9kg)とした. 測定項目は,等尺性肘関節伸展筋力,体幹stability endurance test(以下,stability test)とし,等尺性肘関節伸展筋力については椅子座位,立位の2条件で測定を行った.等尺性肘関節伸展筋力の測定肢位は壁に正対し,肩関節屈曲90度,肘関節屈曲90度位とし,前腕遠位部の高さに合わせて壁に設置した等尺性筋力測定機器μ-tas(ANIMA社製)に5秒間最大努力で肘関節伸展運動を行った.測定された筋力(N)を体重で除し,肘伸展筋力体重比(以下,肘伸展筋力)を算出した.尚,体幹・下肢の固定は行わなかった.Stability testはサイド右・左,体幹伸展・屈曲の4項目とした.サイド右(左)は右(左)側臥位にて右(左)on elbow,体幹伸展はpuppy positionを開始肢位とし,肩関節・股関節・膝関節・足関節が一直線となるように保持させた.体幹屈曲は,膝立て位から体幹と床面が45度となる姿勢を保持させた.全ての項目で姿勢が保持できなくなった時点の時間を計測した. 統計学的解析においては,肘伸展筋力について各条件内の投球側と非投球側間,および各条件間での比較をWilcoxonの符号付順位検定により検討した.また,各条件の肘伸展筋力とstability test間の関連性の検討のために,Spearmanの積率相関係数を求めて,相関分析を行った.危険率5%未満を有意差ありとした.【倫理的配慮、説明と同意】 対象者全員およびチーム責任者に本研究内容,対象者の有する権利について十分に説明を行い参加の同意を得た.【結果】 肘伸展筋力の測定結果は,座位において,投球側172.7±28.7(N/kg),非投球側164.9±24.9(N/kg),立位において投球側142.1±31.3(N/kg),非投球側133.8±22.9(N/kg)であった.Stability testの結果,サイド右は52.5±23.9 sec,サイド左は55.7±31.4 sec,体幹伸展は103.3±44.1 sec,体幹屈曲は35.5±23.1 secであった.各条件内での投球側・非投球側間の肘伸展筋力の比較では,両条件とも投球側が有意に大きかった.2条件間での肘伸展筋力の比較では,投球側・非投球側とも座位が有意に大きかった.肘伸展筋力とstability testの相関関係は,座位の投球側肘伸展筋力とサイド右,体幹伸展,および非投球側肘伸展筋力とサイド右で有意な正の相関が認められた.【考察】 投球動作の運動連鎖について,先行研究では全身を使って投げた場合に比べ,腕だけで投げる場合約50%の速度しか出ないとされおり,下肢・体幹から上肢への効率のよいエネルギーの伝達が重要であると考えられている.しかし,今回肘伸展筋力については,立位よりも座位の方が大きな結果となった.立位では,肘伸展運動時にエネルギーが放散され,座位に比べ筋力が小さくなったと考えらえる.また,肘伸展筋力と体幹stabilityの関連では座位でのみ有意な相関が認められた.立位時には,下肢・骨盤帯が影響するため,体幹stabilityと相関が認められなかったと考える.本研究より,座位での肘伸展筋力の測定により体幹機能の評価が可能であることが示唆された.【理学療法学研究としての意義】 肘伸展筋力の評価が体幹機能の評価として有効であることが示唆された点,中学生野球選手では下肢・骨盤帯の機能低下が上肢機能発揮低下の要因となることが示唆された点で,成長期の投球障害に対する理学療法評価,アプローチにおける提言として大変意義のあるものであると考える.
1 0 0 0 投球障害における手内筋の機能不全について 第2報
- 著者
- 栗田 健 明田 真樹 森 基 大石 隆幸 高森 草平 小野 元揮 木元 貴之 岩本 仁 日野原 晃 田仲 紗樹 吉岡 毅 鈴木 真理子 山﨑 哲也
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Cb1390, 2012
【目的】 先行研究で投球障害肘群は肩群に比べ手内筋の筋力低下を有していることが分かった。このことは手内筋が効率よく機能せずに、手外筋を有意に働かせてボールを把持することで、手・肘関節への影響が大きくなることが示唆された。しかし手内筋機能不全が投球動作の繰り返しで生じたものか、もともと機能不全が存在したことにより投球障害肘の原因となったのかは不明であった。そこで今回我々は手内筋機能不全が多く認められた投球障害肘群において、投球による影響がない非投球側の評価を行い、両側に機能不全を有する割合について調査したので以下に報告する。【方法】 対象は、投球障害肘の診断により当院リハビリテーション科に処方があった20例とした。対象は肘単独例のみとし、他関節障害の合併や既往、神経障害および手術歴を有する症例は除外した。性別は全例男性で、年齢は、平均16.4±5.1歳(11歳~34歳)であった。観察項目は、両側の1.手内筋プラス肢位(虫様筋・骨間筋)と2. 母指・小指対立筋の二項目とした。共通肢位として座位にて肩関節屈曲90°位をとり、投球時の肢位を想定し肘伸展位・手関節背屈位を保持して行った。1.手内筋プラス肢位(虫様筋・骨間筋)は、徒手筋力検査(以下MMT)で3を参考とし、可能であれば可、指が屈曲するなど不十分な場合を機能不全とした。2.母指・小指対立筋も同様に、MMTで3を参考とし、指腹同士が接すれば可、IP関節屈曲するなど代償動作の出現や指の側面での接触は機能不全とした。なお統計学的評価には、二項検定を用い、P値0.05未満を有意差ありと判断した。【説明と同意】 対象者に対し本研究の目的を説明し同意の得られた方のデータを対象とし、当院倫理規定に基づき個人が特定されないよう匿名化に配慮してデータを利用した。【結果】 投球障害肘の投球側虫様筋・骨間筋機能不全は、65.0%、に発生しており、そのうち健側にも認められたものが76.9%であった(統計学的有意差なし)。投球側母指・小指対立筋機能不全は、65.0%に発生しており、そのうち健側にも認められたものは53.8%であった(統計学的有意差なし)。一方、非投球側での機能障害をみると、両側に発生している比率が、虫様筋・骨間筋機能不全例では90.9%、母指・小指対立筋機能不全例では100%であった(統計学的有意差あり)。【考察】 我々は第46回日本理学療法学術大会において手内筋機能低下が投球障害肩より投球障害肘に多く認められることを報告している。しかし手内筋機能不全が伴って投球動作を反復したために投球障害肘が発生するのか、肘にストレスがかかる投球動作を反復したために手内筋機能不全が発生したのかは過去の報告では分からなかった。そこで今回投球していない非投球側の機能と比較することで投球による影響なのか、もともとの機能不全であるのかを検討した。今回の結果より、各観察項目での投球側・非投球側の両側に手内筋の機能不全を有する割合は多い傾向があったが、統計学的有意差はなかった。一方、非投球側に機能不全がみられた症例は、投球側の機能不全も有す症例が多く、統計的有意差もあることが分かった。このことより手内筋の機能不全は、投球の影響によって後発的に生じるのではなく、もともと機能不全を有したものが、投球動作を繰り返したことにより投球障害肘を発症している可能性が高いと考えられた。そのため投球障害肘の発生予防や障害を有した場合のリハビリテーションの中で虫様筋・骨間筋機能不全および母指・小指対立筋機能不全の評価と機能改善が重要であると考えられた。【理学療法学研究としての意義】 投球障害肘の身体機能の要因の中で手内筋である虫様筋・骨間筋や母指・小指対立筋に機能不全を有することが多いということが分かった。本研究から投球障害肘を治療する際には、評価として手内筋機能に着目することが重要と考える。また今回設定した評価方法は簡便であり、障害予防の観点からも競技の指導者や本人により試みることで早期にリスクを発見できる可能性も示唆された。