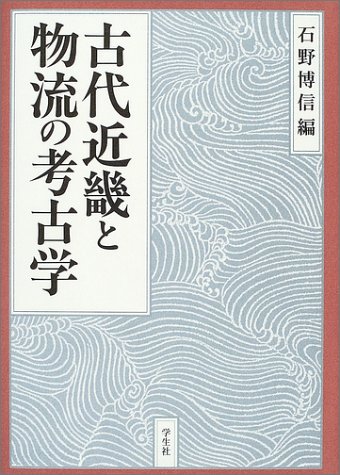1 0 0 0 OA 老執事の旅:カズオ・イシグロの『日の名残り』
- 著者
- 谷田 恵司 Yata Keiji ヤタ ケイジ
- 雑誌
- 東京家政大学研究紀要 1 人文社会科学 (ISSN:03851206)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.37-44, 1992
1 0 0 0 1998年参議院選挙の分析
- 著者
- 高畠通敏 石川真澄 五十嵐暁郎[著]
- 出版者
- 立教大学アジア地域研究所
- 巻号頁・発行日
- 1999
1 0 0 0 OA 新型プリウスPHVのシステム開発
- 著者
- 市川 真士 村田 崇 木野村 茂樹 鈴木 岐宣 三好 達也
- 出版者
- 一般社団法人 日本エネルギー学会
- 雑誌
- 日本エネルギー学会機関誌えねるみくす (ISSN:24323586)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.3, pp.232-238, 2018-05-20 (Released:2018-05-31)
- 参考文献数
- 5
新型のプリウスPHVに搭載されている新開発プラグインハイブリッドシステムは,旧型のプリウスPHVと比べ,よりいっそうの高効率・低損失化と小型・軽量化を目指して開発を推進し,次世代環境車の柱となるにふさわしい省エネ性能を実現した。EV性能は,EV距離とEV出力ともに旧型より大幅アップを実現し,実使用でのEVカバー率の向上が可能となった。さらに,駆動用バッテリの充電は,ACおよびDC充電に加え,世界初のソーラー充電システムを採用した。駐車中のソーラー充電で,日当たり最大EV距離6.1 km分の充電が可能であり,よりCO2フリーなEV走行が可能となった。
1 0 0 0 OA 放射妨害波測定用超広帯域アンテナの設計・開発
- 著者
- 石上 忍 石崎 利弥 小林 圭太 川又 憲 張間 勝茂 祷 真悟
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J105-B, no.6, pp.458-465, 2022-06-01
本論文では,現在の妨害波測定に使用されている市販の広帯域アンテナの使用可能帯域を一つのアンテナで実現するための超広帯域アンテナの設計と開発について述べた.まず本アンテナの原理について述べ,更に試作したアンテナについて,複素アンテナ係数,絶対利得,及びアンテナ反射特性の測定結果を示した.その結果,本提案アンテナは,500 MHzから20 GHzまでEMC用のアンテナとして使用可能であることがわかった.
1 0 0 0 つくはら : 千年家とその周辺
- 著者
- 地主喬 田辺真人執筆
- 出版者
- [出版社不明]
- 巻号頁・発行日
- 0000
1 0 0 0 OA 人間・歴史・世界 自由と必然の問題を中心として
- 著者
- 森 信成
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.10, pp.65-79, 1960-03-31 (Released:2009-07-23)
人間・歴史・世界の問題は言いかえれば自由と必然 (外的必然事としての偶然性をもふくめて) の関係の問題ということになるであろう.そして人間についてはとくに自由が、歴史については必然性が、世界については両者の具体的な関係が、換言すれば理論と実践 (実践のとくに道徳的な理解をもふくめて) の関係が、現実の具体的把握とむすびつけて問題とされていると解してよいであろう.またこの関係において、歴史認識における一元論、二元論、多元論があらわれ、そのことから歴史的発展を動かすもの、窮極原因は何かが問われているといってよいであろう.自由と必然の問題は、それが哲学の根本問題である唯物論か観念論かの問題の直接的表現であるという意味においても、また戦後の思想対立が自由の概念を基軸として、近代主義的エゴの自由と人類と平等に基礎をおく民主主義的自由という二つの自由の対立として展開されているという意味においても.現在きわめて重要な意義をもっている [註] 唯物論と観念論が戦後たがいに交らざる平行線のかたちをとったことの主たる理由は、唯物論が自由の唯物論的把握を積極的に展開せず.観念論の側からの不断の問題提起にもかかわらず自由とは必然性の洞察であるというただそのことだけをくりかえすにとどまってきたところにあったといってよいであろう.
1 0 0 0 OA もやもや病,片側型もやもや病,類もやもや病に関する全国調査
- 著者
- 林 健太郎 堀江 信貴 陶山 一彦 永田 泉
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中の外科学会
- 雑誌
- 脳卒中の外科 (ISSN:09145508)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.179-182, 2012 (Released:2013-03-09)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2 1
Moyamoya disease (MMD) is characterized by progressive occlusion of the internal carotid artery or its terminal branches, associated with formation of extensive collateral vessels (moyamoya vessels) at the base of the brain. Whether unilateral moyamoya disease, confirmed by typical angiographic evidence of moyamoya disease unilaterally and normal or equivocal findings contralaterally, is an early form of definite (bilateral) moyamoya disease remains controversial. Inherited or acquired disorders and conditions may present in conjunction with moyamoya disease. This condition is known as quasi-moyamoya disease (quasi-MMD). We attempted to determine the incidence and total patient number of moyamoya disease, unilateral MMD and quasi-MMD, who were treated during 2005 in Japan. Questionnaires were sent to 2,998 departments, which are listed in resident training programs of neurosurgery, neurology and pediatrics. Totally, 1,183 departments replied, and the response rate was 39.5%. The number of annual first-visit patients of MMD, unilateral MMD and quasi-MMD is 571, 118, and 53, respectively. Thus, the number of annual revisit patients of MMD, unilateral MMD and quasi-MMD is 2,064, 214, and 117 respectively. It is estimated that 6,670.9 MMD patient exists in Japan. The incidence rate of MMD, unilateral MMD and quasi-MMD is 1.13, 0.23 and 0.11/100,000, respectively, and the prevalence is 5.22, 0.66 and 0.34/100,000, respectively. This nationwide study revealed the present epidemic status of MMD, unilateral MMD and quasi-MMD.
1 0 0 0 OA 噴流騒音に対する出口での流れの状態の影響
- 著者
- 坂尾 富士彦
- 出版者
- 社団法人 日本流体力学会
- 雑誌
- 日本流体力学会誌「ながれ」 (ISSN:02863154)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.166-176, 1983-06-20 (Released:2011-03-07)
- 参考文献数
- 17
空気中空気の軸対称・亜音速・常温噴流の発する音が, ノズル出口での流れの状態によって受ける変化を実験によって調べた.流れはほぼ一様な流速で乱れの少い主流と, 境界層とから成り, 境界層の状態は層流と乱流に変えられる.また境界層の近傍の主流中に乱れを導入することもできる.実験の結果, 境界層は層流である場合の方が音が大きくなること, その増加は遷移過程で発生する正弦的速度変動に起因すること, 主流の乱れで層流境界層を揺さぶる状態ではそれに加えて低周波数の音も増加することが分った.また境界層が乱流であるとき, その厚さが増すと音はわずかではあるが減少すること, 主流の乱れは一般に音を増加させることが分った.
1 0 0 0 古代近畿と物流の考古学
1 0 0 0 OA The quilts (Futon) : written by Katai Tayama
- 著者
- 本間 賢史郎 Kenshiro Homma
- 出版者
- 同志社大学英文学会
- 雑誌
- Doshisha literature (ISSN:0046063X)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.41-98, 1966-03-31
1 0 0 0 OA 本邦における抗体及び抗体関連医薬品のバイオシミラー採用及び処方に関する医師の意識調査
- 著者
- 青木 良子 佐井 君江 勝田 由紀子 鈴木 美佳 鈴木 康夫 石井 明子 斎藤 嘉朗
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, no.5, pp.547-560, 2022-05-01 (Released:2022-05-01)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
Biosimilars are less expensive than their originators, and Japanese government policies call for their development and promotion. However, the adoption and prescription of some biosimilars, especially antibody/its-related ones, have been delayed for use in Japan, possibly due to concerns on the differences in quality attributes such as glycan structures between the originators and their biosimilars, and that clinical efficacy/safety studies are conducted for usually one disease and its results extrapolated to other indications. We conducted a questionnaire survey among physicians in four disease areas (hematology, medical oncology, rheumatoid arthritis, and inflammatory bowel disease), where biosimilars of antibody/its-related drugs have been approved, regarding their thoughts on the adoption and prescription of biosimilars in Japan from January to April 2020. We received totally 1024 responses. When adopting biosimilars and explaining them to patients, physicians requested specific information including the comparative results of phase III clinical trials and quality characteristics between biosimilars and their originators; the results of clinical studies on switching from originators to their biosimilars; and a comparison of the estimated cost on patients in consideration of the high medical cost payment system. Priority differed depending on the studied disease areas. In terms of post-marketing information, physicians requested a variety of information. When explaining biosimilars to the patients, physicians would like to use general material from government describing the comparability between originators and their biosimilars. These results suggest that physicians sought more comparative information on the quality, efficacy, and patients' cost between originators and their biosimilars when adopting or prescribing biosimilars.
1 0 0 0 OA 日露協働によるシベリアの環境変化研究
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.165-168, 2022 (Released:2022-06-11)
1 0 0 0 OA 海岸部における構造物の例 本州四国連絡橋における美観・景観対策
- 著者
- 木村 博司
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.7, pp.90-97, 1986-07-01 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 17
- 著者
- 小澤 朗人 内山 徹
- 出版者
- 関東東山病害虫研究会
- 雑誌
- 関東東山病害虫研究会報 (ISSN:13471899)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.66, pp.100-105, 2019-12-01 (Released:2021-03-23)
- 参考文献数
- 21
From March 2016 to March 2017, we investigated seasonal population dynamics of the exotic predatory mite, Phytoseiulus persimilis estimated to have colonized tea fields in Shizuoka Prefecture, Japan. Species of phytoseiid mites in the tea field investigated were P. persimilis, and native species: Amblyseius eharai, A. obtuserellus, Neoseiulus womersleyi, and Euseius sojaensis. The percentage of P. persimilis in the species composition were 5.6% (2 Jul.) and 26.0% (6 Sept.). P. persimilis adults with eggs were found on 23 Mar for the first time. The two peaks of occurrences were observed on 25 Apr. three weeks after the peak of Tetranychus kanzawai, and on 23 Aug. two weeks after the peak of T. kanzawai. P. persimilis was not observed after the middle of Sept.. Primary dominant species of native phytoseiid mites was A. eharai, they occurred during most of the seasons. The peaks of native phytoseiid mites were observed on 24 May and 9 Sept., after the peaks of P. persimilis. Indices of ω proposed by Iwao (1977) which indicates a special association between two species were calculated among T. kanzawai, P. persimilis and Amblyseius spp. The indices between T. kanzawai and P. persimilis changed plus (coexistence distribution) to minus (exclusion distribution) around Apr. - May. These results suggest that P. persimilis strongly depends on T. kanzawai, while P. persimils does not significantly affect the populations of native phytoseiid mites in tea fields.
- 著者
- 山口 杲
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.173-180, 1960-12-25 (Released:2016-09-05)
1958, 1959両年度にわたり, 京都市北区において, タケノホソクロバArtona funeralis(Butler)の生活史を, 野外観察と飼育実験の両法によつて追究した.結果を以下に要約する.1.本種は1年間に3世代を営み, 第3世代の蛹態で越冬する.2.越冬蛹は5月中旬〜6月中旬に羽化, 産卵し, 第1世代は5月下旬〜7月中旬, 第2世代は7月下旬〜9月上旬に営まれ, 第3世代は10月下旬に蛹化して越冬にはいる.3.卵期間は各世代間にあまり差がなく, それらを平均すれば7.3日であつた.各世代の平均孵化率は, それぞれ85%, 80%, 80%であつた.4.幼虫期は5令で, 各令の平均所要日数は, 第1世代の第1令5.8日, 同第2令5.3日, 同第3令5.2日, 同第4令6.1日, 同第5令7.4日, 第2世代ではそれぞれ, 4.7日, 4.0日, 4.9日, 6.0日, 8.4日, 第3世代ではそれぞれ, 5.5日, 6.6日, 8.9日, 7.9日, 11.5日であった.全幼虫期間の平均所要日数は, 第1世代29.8日, 第2世代28日, 第3世代40.4日であり, 蛹化率は夫々55%, 65%, 57.5%であつた.5.前蛹期は第1世代1.1日, 第2世代1.1日, 第3世代2.2日, 蛹期はそれぞれ11日, 11日, 187日(越冬)であつた.羽化率はそれぞれ, 47.5%, 56%, 11.5%であつた.6.雌成虫は原則として羽化後1日経つてから交尾し, さらに1日経過してから産卵する.成虫期の寿命は雌1〜6日, 雄1〜9日, 平均寿命はそれぞれ3.5日, 4.0日であつた.雄は雌より1〜2日早く羽化する.7.卵はタケ或いはササの葉裏に整然と並べて産みつけられ, 卵数は第1世代20〜182(平均90), 第2世代20〜268(平均140), 第3世代26〜145(平均81)であつた.8.幼虫は第1〜2令は完全な集団をなして行動し, 第3令に達すると分散し始め, 第4, 第5令では概ね単独に生活する.9.蛹化は腐竹, 腐木の内側, 板塀, 軒先等で行われ, まゆは濃褐色, 扁平楕円形の薄い蝋質の板で, 皿を伏せたような形に蛹を被う.10.本種幼虫が野外でイネを食害する例を観察したし, また飼育室内でも本種成虫はイネの葉に産卵し, それから孵化した幼虫はイネを食べて終令に達し得ることが確認された.11.以上の他, 成虫の交尾習性, 幼虫の移動性, 眠性, 卵内発生に及ぼす湿度の影響等を観察記載した.
1 0 0 0 OA ジャコウアゲハの幼虫における体色決定の要因(<特集>昆虫少年・少女を育てよう)
- 著者
- 宇佐美 賢祐
- 出版者
- 日本鱗翅学会
- 雑誌
- やどりが (ISSN:0513417X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.230, pp.22-23, 2011-10-10 (Released:2017-08-19)
1 0 0 0 OA 症例 急性心筋梗塞を発症し原発性抗リン脂質抗体症候群と考えられた若年者の2例
- 著者
- 菊地 淳一 小山 滋豊
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.37-42, 1999-01-15 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 16
急性心筋梗塞を発症し,経過から原発性抗リン脂質抗体症候群と考えられた2症例を報告する.症例1は42歳,女性.脳梗塞,自然流産の既往あり.胸痛のため入院した.喫煙歴あり.心電図上II,IIIでST上昇,V3~V5で陰性T波を認めた.心筋逸脱酵素上昇あり.血小板数減少,APTT延長,抗カルジオリピンβ2-glycoprotein I複合体抗体上昇,抗核抗体陽性.左室造影上心尖部が心室瘤様,心室中隔が低収縮,冠動脈造影では狭窄や閉塞を認めなかった.症例2は25歳,男性.胸痛のため入院した.喫煙歴あり.肥満傾向.心電図でII,III,aVFに異常Q波および陰性T波,I度房室ブロックを認めた.心筋逸脱酵素が軽度上昇.血清梅毒反応生物学的偽陽性,抗カルジオリピンβ2-glycoprotein I複合体抗体上昇,抗核抗体陽性だった.左室造影上,左室壁運動低下,冠動脈造影で右冠動脈近位部完全閉塞を認めた.2例とも抗血小板療法および抗凝固療法を行った.若年発症の急性心筋梗塞例では抗リン脂質抗体症候群の存在を疑い,血栓症の再発予防に努めるべきと考えられた.