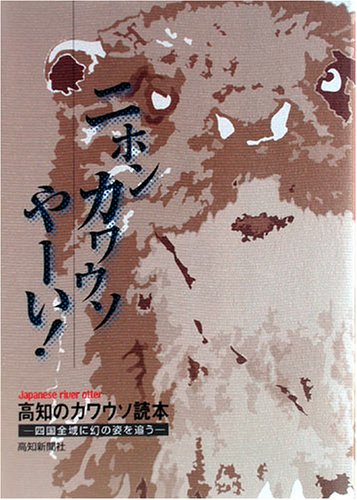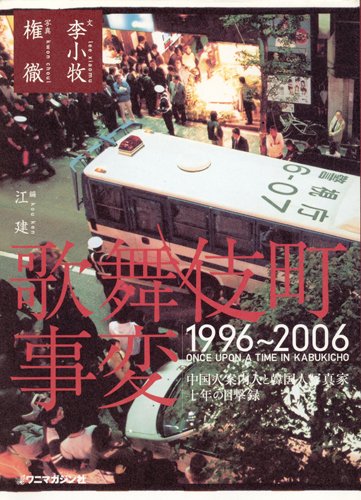- 著者
- 高知新聞企業出版部編集・制作
- 出版者
- 高知新聞企業 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 歌舞伎町事変 : 1996-2006
1 0 0 0 OA 失語症者における項目間の意味的関連性を統制した非言語性意味判断課題の成績
- 著者
- 津田 哲也 中村 光 吉畑 博代 渡辺 眞澄 坊岡 峰子 藤本 憲正
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.394-400, 2014-12-31 (Released:2016-01-04)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 1
項目間の意味的関連性を統制した非言語性意味判断課題を用いて, 失語症者の意味処理能力を検討した。対象は右利き失語症者 35 例 (平均 65.4 歳) および同年代の健常者 10 例 (統制群)。課題では提示された目標項目に対し, 対象者に 5 つの選択肢のなかから, 最も意味的関連性が強いと判断する 1 項目を指すよう求めた。選択肢は質的に異なる 2 つの意味的な関連性 (状況関連性と所属カテゴリー関連性) の有無を基準に設定した。例えば, 刺激項目が「犬」の場合, 状況と所属カテゴリーもどちらも関連する項目 SC (猫), 状況的関連のある項目 S (家), 所属カテゴリーが関連する項目 C (象), 生物・非生物のみ一致するが状況・カテゴリーの関連性はない項目 N1 (鯛), いずれも関連のない項目N2 (消しゴム) の線画を提示した。その結果, 統制群・失語群いずれも全反応中に占める比率は SC が最も多く, 次いで S または C の順で, N1・N2 は最も少ない反応であった。また, 失語重症度別・聴覚的理解力別での反応に有意な偏りを認め, 重度群・理解不良群は軽度群・理解良好群よりも全反応中の N1・N2 の比率が有意に高かった。失語症者において重症度・聴覚的理解力と非言語性意味処理には一定の関連があることが確認された。以上より, 多くの失語症者は非言語性意味判断において, 状況関連性やカテゴリー関連性という判断基準を利用できることが示された。
1 0 0 0 OA 二つの保健医療社会学をめぐって——学際ジャンルをメンテナンスする多様性と継続性——
- 著者
- 佐藤 哲彦
- 出版者
- 日本保健医療社会学会
- 雑誌
- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.32-39, 2020-07-31 (Released:2021-08-06)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
本稿の目的はこれまで保健医療社会学論集が果たしてきた役割について明らかにすることである。そこで本稿は、主として保健医療社会学会名義の諸研究と保健医療社会学論集に掲載された論文を題材として、日本における保健医療社会学というジャンルの成立経緯について考察し、これまで指摘されたことのない日本の保健医療社会学のローカルな発展経過を明らかにした。そしてその発展過程を明らかにする中で、これまで日本でしばしば用いられてきたSociology in MedicineとSociology of Medicineの対立とは別の形で展開したローカルな分割を、あえて保健医療社会学Aおよび保健医療社会学Bと名づけることで浮き彫りにし、その分割の存在それ自体が、多様性と継続性という点から、保健医療社会学論集および保健医療社会学会自体の活性化に果たしてきた役割を論じた。
1 0 0 0 OA 阪神・淡路大震災Q&A (その4)
- 著者
- 福島 順一
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.81-82, 1996-02-01 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 生活困窮者支援における「市民福祉」の制度化をめぐる一考察
- 著者
- 堅田 香緒里
- 出版者
- 福祉社会学会
- 雑誌
- 福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.117-134, 2019-05-31 (Released:2019-10-10)
- 参考文献数
- 21
1980 年代以降,現代福祉国家の多くでは「新自由主義的な」再編が進められてきた.規制緩和と分権化を通して,様々な公的福祉サービスが民営化・市場化されていったが,福祉の論理は一般に市場の論理とは相容れないため,福祉サービスを市場経済のみにおいて十分に供給することは難しい.このため,次第に福祉サービス供給の場として「準市場」が形成され,その受け皿としてNPO 等の市民福祉が積極的に活用されるようになった.また近年では,市民福祉が,さらに「地域」の役割と利用者の「参加」を強調するような新たな政策的動向と結びつけられながら「制度化」されつつある. 生活困窮者支援の領域においても同様の傾向がみられる.その際,頻繁に用いられるキーワードが「自立支援」であり,そうした支援の担い手として市民福祉への期待がますます高まっているのである.本稿は,このことの含意に光を当てるものである.そこでは,「市民福祉」の活用が公的責任の縮減と表裏一体で進行していること,そして貧者への「再分配」(経済的給付)が切り縮められる一方で,「自立支援」の拡充とともに経済給付を伴わない「承認」が前景化しつつあり,両者が取引関係に置かれていることが論じられる.
1 0 0 0 OA Webコンテンツを用いたなぞかけ自動生成の提案と評価
- 著者
- 内村 圭佑 灘本 明代
- 雑誌
- 研究報告データベースシステム(DBS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009-DBS-148, no.25, pp.1-6, 2009-07-21
「なぞかけ」 とは 「A とかけて B ととく.そのこころは C+D.」 という定型句に,ある程度の関連性を持った単語を当てはめて楽しむ日本に古くからある言葉遊びの一種である.本研究では Web を利用してこのなぞかけ文を自動生成するシステムを提案する.我々の提案する,なぞかけ自動生成システムは入力単語を A と D とし,各々に関連する単語 B と単語 C を自動抽出しなぞかけを生成する.具体的には,入力された単語 A (名詞) と単語 D (形容詞) から関連する動詞 C を Web より取得する.そして,その動詞と同音異字にある単語 C’ を用いて,それに関連する名詞 B を Web から取得する.単語 A と単語 B との意味距離を Wikipedia を用いて計り,この意味距離が離れているとき,なぞかけを生成する.
- 著者
- 生駒 歩 戸田 竜哉 長崎 哲新 河村 功一
- 出版者
- 一般社団法人 日本魚類学会
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.7-20, 2022-04-25 (Released:2022-05-06)
- 参考文献数
- 59
Genetic characteristics of the Japanese torrent catfish Liobagrus reinii in the Miya River and neighboring drainages were investigated, using mtDNA and eight microsatellite (MS) markers, to evaluate the effects of man-made river structures on the distribution and genetic structure of the species. A total of 23 mtDNA haplotypes were detected, forming a star-like haplotype network, in which the population in the upper reaches (URM) formed a unique group. Many populations in tributaries of the middlelower reaches (MLRM) included unique haplotypes, although they shared a common haplotype located at the center of the network. MS markers indicated that genetic diversity tended to decrease upstream in the tributaries, coupled with a decline in effective population size and the existence of genetic bottlenecks. These phenomena were especially evident in tributaries isolated with weirs or dams. The fixation index RST, the values of which were smaller than FST, indicated isolation by distance (Mantel test), genetic differentiation among populations having occurred in recent years. Although a Bayesian-based assignment test showed unique clusters in the populations of isolated tributaries, including the URM population, many MLRM populations shared an admixture of multiple clusters, probably resulting from the dispersal of L. reinii. These results indicated that L. reinii in the Miya River included two conservation units, in the upper and middle-lower reaches, respectively. Man-made river structures seem to have caused fragmentation of the distribution of the species, resulting in small tributary populations suffering from genetic deterioration. In drainages neighboring the Miya River, the Isezi River population of L. reinii seems to be indigenous, owing to unique genetic characteristics in mtDNA and MS, whereas the sharing of genetic characteristics with the URM population of the Miya River indicated that the Akaba River population is likely to have been introduced from the Miyagawa Reservoir.
- 著者
- 村上 覚史 朝原 崇
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.5, pp.e91-e101, 2022 (Released:2022-05-14)
- 参考文献数
- 108
1 0 0 0 OA 普通列車グリーン車の導入が混雑および社会厚生に与える影響の分析
- 著者
- 森岡 拓郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本交通政策研究会
- 雑誌
- 自動車交通研究 (ISSN:21896968)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, pp.32-33, 2018 (Released:2018-12-12)
- 著者
- 戸田 光彦 Toda Mitsuhiko
- 出版者
- 金沢大学
- 雑誌
- 博士論文本文Full
- 巻号頁・発行日
- 2014-09-26
博士論文本文Full
1 0 0 0 OA 日露戦争と日本外交
- 著者
- 伊藤之雄
- 出版者
- 防衛省
- 雑誌
- 戦争史研究国際フォーラム報告書
- 巻号頁・発行日
- vol.第3回, 2005-03-31
- 著者
- 松本 涼佑
- 出版者
- 日本交通学会
- 雑誌
- 交通学研究 (ISSN:03873137)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, pp.71-78, 2020 (Released:2021-04-12)
- 参考文献数
- 11
普通列車グリーン車の価格は、グリーン車自体の需要を左右することに加えて、同じ列車に併結される普通車両の需要にも影響を及ぼすと考えられる。そのため特に混雑が問題視される平日朝の通勤において、グリーン車価格の変化が需要に与える影響は重要な研究テーマである。そこでグリーン車の価格が営業キロ51kmを境に210円変化する2段階の価格体系に着目し、Regression discontinuity designを適用することによって、平日朝の通勤におけるグリーン車需要の価格弾力性を推定した。分析の結果、価格弾力性は有意に1を超え、価格感応度は高いことが分かった。適正な価格設定は、本価格弾力性の推定値、および現状の普通車両とグリーン車の混雑度を基に、慎重に検討される必要がある。
- 著者
- 安藤 英由樹
- 出版者
- 大阪大学
- 雑誌
- 戦略的な研究開発の推進 戦略的創造研究推進事業 RISTEX(社会技術研究開発)
- 巻号頁・発行日
- 2016
情報技術は人間の知的作業に効率性をもたらす一方で、ユーザーの心的状態への負の影響も指摘されており、効率性とは異なる視点から、心の豊かさをサポートする情報技術の設計指針が求められている。欧米で現在採用されている個の主観的幸福に着目したWellbeingの設計指針だけでなく、本プロジェクトでは、日本特有の価値体系(人間同士の関係性やプロセスから生まれる価値等)に着目し、それを情報技術にどのように取り入れるか、また、日本特有の問題に情報技術がどのようにアプローチできるかという点を重視した情報技術ガイドラインの策定・普及を行う。そして、このような取り組みを通して、真に現代社会に馴染む情報技術を創発するプラットフォームの構築を目指す。
1 0 0 0 民藝の100年 : 柳宗悦没後60年記念展
- 著者
- 東京国立近代美術館 [ほか] 編集
- 出版者
- 東京国立近代美術館 : NHK : NHKプロモーション : 毎日新聞社
- 巻号頁・発行日
- 2021
1 0 0 0 OA Tsallis の非加法的統計力学と純電子プラズマ
- 著者
- 阿部 純義
- 出版者
- 社団法人 プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌 (ISSN:09187928)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.1, pp.36-44, 2002 (Released:2005-12-08)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 5 5
Boltzmann-Gibbs statistical mechanics is known to exhibit fundamental difficulties when a system under consideration contains long-range interactions. Tsallis' nonextensive statistical mechanics offers a consistent theoretical framework for treatment of such a system. In this article, an approach to statistically describing pure-electron plasma based on the Tsallis entropy is reviewed and related problems are discussed.
1 0 0 0 OA ストリーミング技術を用いたオンライン授業の教育効果
- 著者
- 秋山 秀典 寺本 明美 小薗 和剛
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌A(基礎・材料・共通部門誌) (ISSN:03854205)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, no.8, pp.782-788, 2006 (Released:2006-11-01)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 3
A conventional lecture on Laser Engineering had been done in a lecture room till 1999. A content using on-demand streaming method was made for an online lecture of Laser Engineering in 2000. The figures and equations used on the conventional lecture and the voice recorded for the online lecture were converted to the real media. Then an online lecture has been provided to students by using a Helix Universal Server. The trial of the online lecture was done only for the students who wanted to take the online lecture course in 2000. The online lectures have been recognized as the credits for graduation by the change of a law since 2001. About 100 students have registered the online lecture of Laser Engineering every year since 2001. Here, three years' questionnaire surveys of the online lecture are summarized, and results of examinations on the conventional lecture for two years and on the online lecture for three years are compared. It is recognized for the lecture of Laser Engineering that the educational effect of the online lecture is comparable to or better than that of the conventional lecture.
1 0 0 0 OA 鉄道統計年報
- 出版者
- 日本国有鉄道事務管理統計部
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和38年度 第1編, 1964
1 0 0 0 〈消費社会論〉というジレンマ
- 著者
- 石川 洋行
- 出版者
- 日本社会学理論学会
- 雑誌
- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.107-112, 2020