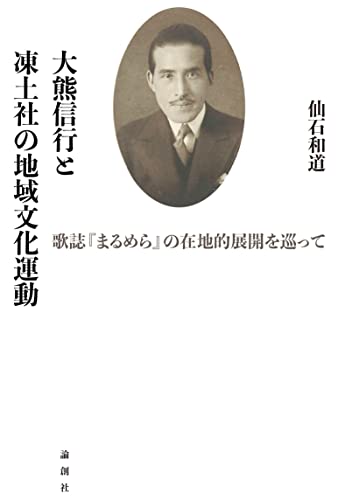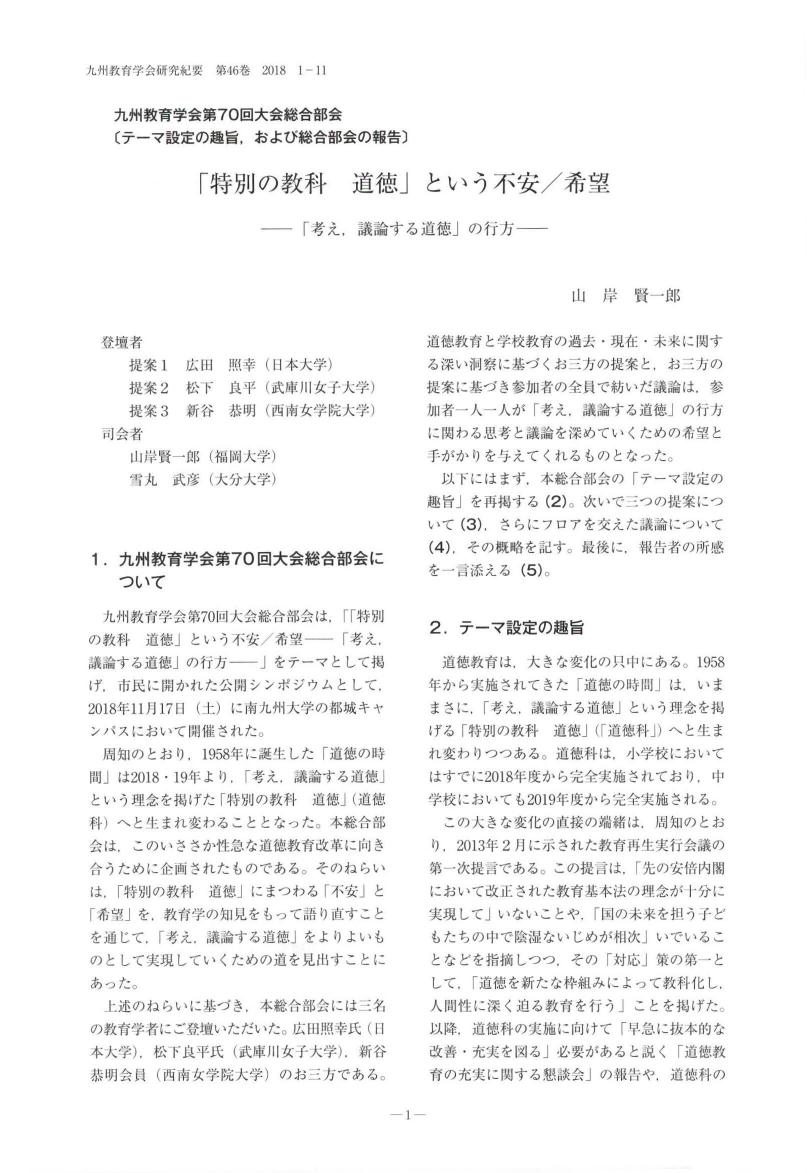1 0 0 0 OA 歯ブラシにおける毛先形状の違いがプラーク除去に及ぼす効果
- 著者
- 竹下 萌乃 岡澤 悠衣 加藤 啓介
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.84-91, 2022 (Released:2022-05-15)
- 参考文献数
- 16
これまでに,さまざまな歯ブラシの臨床研究が報告されているが,試験群間で毛先形状以外の歯ブラシの仕様が異なるものが多く,毛先形状のみ異なる歯ブラシを比較した臨床研究は少ない.よって本研究では,毛以外の因子を揃えたうえで,毛先形状の異なる歯ブラシにおけるプラーク除去効果の比較を行い,ブラッシング圧の測定も併せて行った. 成人男女61名を無作為に,研磨処理によるテーパード毛(研磨処理毛),化学処理によるテーパード毛(化学処理毛)および先丸毛をそれぞれ同一のハンドルに植毛した歯ブラシを使用する3群に割り付けた.各群3分間/回,3回/日のブラッシングを3週間実施した.0日目および3週間後の時点で被験者にブラッシングを実施させ,プラーク除去率を算出した.ブラッシング圧は,全員同じ歯ブラシ(ガム・デンタルブラシ#211)を用いた時と,試験品を用いた時の2回測定した. その結果,0日目,3週間後それぞれのプラーク除去率は,研磨処理毛群62.5%/55.4%,化学処理毛群42.8%/40.1%,先丸毛群65.0%/55.9%であり,研磨処理毛群と化学処理毛群の間,先丸毛群と化学処理毛群との間に有意な差が認められた(p<0.01).ブラッシング圧は3群間に有意な差は認められなかった. 以上のことから,研磨処理毛と先丸毛は,化学処理毛よりも高いプラーク除去効果を示す可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 米中の農薬残留実態(1995年4月∼2005年3月)
- 著者
- 小林 麻紀 高野 伊知郎 田村 康宏 富澤 早苗 立石 恭也 酒井 奈穂子 上條 恭子 井部 明広
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.35-40, 2007-04-25 (Released:2008-04-28)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 3
1995年4月から2005年3月に東京都内で市販されていた玄米を中心とした国産米および輸入米375検体について残留農薬調査を行った.その結果,国産米では343検体中47検体から,有機リン系,有機塩素系,カルバメート系,ピレスロイド系,含窒素系農薬および総臭素が検出された.輸入米では32検体中18検体からジクロルボスおよび総臭素が検出された.農薬を検出した米について国民栄養調査の食品群別摂取量から農薬の摂取量を算出し,おのおののADIと比較した.算出された農薬の摂取量はADIの17/10,000∼2/5といずれも低く,通常の喫食状況からみて特に問題となるものはなかった.
1 0 0 0 OA 家事提要
- 著者
- 後閑菊野, 佐方鎮子 著
- 出版者
- 目黒書房[ほか]
- 巻号頁・発行日
- 1902
小腸内分泌L細胞(以下、L細胞)は、消化管内の栄養素、腸内細菌代謝産物、血液中のホルモン、神経伝達物質などを感知し、グルカゴン様ペプチド-1(glucagon-like peptide-1: GLP-1)を分泌する。GLP-1は膵β細胞からのインスリン分泌を促進するほか、摂食行動を抑制するため、内在的なGLP-1分泌能を改善することで糖尿病などの代謝疾患治療に結びつくことが期待されている。アルギニンバソプレシン(arginine vasopressin: AVP)は、腎臓からの水の再吸収に加えて社会行動や血糖値制御にも関与するホルモンである。申請者はAVPがGLP-1分泌を制御し血糖値調節に関与している可能性を提唱し、AVPおよびAVP受容体によるGLP-1分泌調節機構、およびその破綻が生体に及ぼす影響の解明を目的とした。まず、マウスL細胞由来細胞株GLUTag細胞にAVPを投与し、ELISA法によりGLP-1分泌量を測定したところ、細胞内Ca2+濃度およびGLP-1開口分泌回数の上昇を引き起こす濃度で分泌量が有意に上昇した。ここから、AVPによりGLP-1分泌が促進されることが確かめられた。次に、3種のAVP受容体遺伝子欠損マウス(V1aR-/-、V1bR-/-、V1a・V1bR-/-マウス)を用い、安静時および摂食時の血中GLP-1濃度を測定した。摂食条件としてグルコースやアミノ酸などの栄養成分を経口投与したが、マウスでは経口投与によるGLP-1分泌促進効果が低く、分泌能をより正確に解析できるようにするため、小腸への直接注射による投与方法を確立している。また、細胞内の代謝を制御する分子であるATP濃度変化を可視化できる蛍光タンパク質センサーMaLionを開発したほか、グルコース可視化センサーGreen Glifonの開発にも成功した。
- 著者
- 青柳 宏 AOYAGIHiroshi
- 出版者
- 宇都宮大学教育学部
- 雑誌
- 宇都宮大学教育学部紀要. 第1部 = Bulletin of the Faculty of Education, Utsunomiya University. Section 1 (ISSN:24238554)
- 巻号頁・発行日
- no.65号, pp.1-15, 2015-03-02
1 0 0 0 OA 本邦心理学の創始者元良勇次郎の足跡を辿って
- 著者
- 大山 正 大泉 溥
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.258-272, 2014 (Released:2018-07-13)
1 0 0 0 OA 大学院における周麻酔期看護師育成のための教育課程の教育内容および設立経緯の報告
- 著者
- 赤瀬 智子 伊吹 愛 池谷 真遵 大山 亜希子 周藤 美沙子 槇原 弘子
- 出版者
- 横浜市立大学医学部看護学科・大学院医学研究科看護学専攻
- 雑誌
- 横浜看護学雑誌 (ISSN:18828892)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.36-41, 2018-03
1 0 0 0 OA 女性史研究とオーラル・ヒストリー
- 著者
- 倉敷伸子
- 出版者
- 法政大学大原社会問題研究所
- 雑誌
- 大原社会問題研究所雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.2007年(11月), no.588, 2007-11-25
1 0 0 0 OA 2.2型糖尿病における異所性脂肪の役割
- 著者
- 田村 好史 筧 佐織 竹野 景海
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.11, pp.730-733, 2016-11-30 (Released:2016-11-30)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 無機リン酸代謝調節における分子栄養学研究 (平成22年度日本栄養・食糧学会学会賞受賞)
- 著者
- 宮本 賢一
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.137-149, 2011 (Released:2011-08-09)
- 参考文献数
- 91
- 被引用文献数
- 2 1
リンは生体に広く分布しており, 細胞内シグナル伝達, エネルギー代謝, 核酸合成および酸-塩基などに関与している。リン代謝調節機構は, その破綻が低リン血症や高リン血症から生じる病態によって明白なように生命維持に必須である。低リン血症はクル病および骨軟化症を引き起こす。一方で, 高リン血症は心血管疾患に深く関与している。血中リン濃度維持の中心臓器は腎臓であり, また腸管および骨の三つの臓器が協調してリン代謝を制御している。生体には3種類のナトリウム依存性リントランスポーター (SLC17, SLC20, SLC34) が, 腎臓に発現している。我々は, これらリントランスポーターの同定や機能解析, またノックアウトマウスを作製して, その役割を明らかにした。一方で, 低リン血症や高リン血症を示す疾患の解析から, 新しいリン代謝系 (FGF23/klotho) が明らかにされた。 FGF23/klothoの発見は, 慢性腎臓病に伴うリン代謝異常の病態を理解する上で重要な知見をもたらした。また, 早期慢性腎臓病における心血管障害と食餌性リン負荷との関係も明らかにされつつある。本総説では, 我々の知見をもとに, リントランスポーターの役割と新しいリン代謝系の発見について, 最近の進歩を概説した。
1 0 0 0 IR 御守袋文書にみる徳川家光の心理
- 著者
- 井澤 潤 Izawa Jun
- 出版者
- 駒沢史学会
- 雑誌
- 駒沢史学 (ISSN:04506928)
- 巻号頁・発行日
- no.75, pp.36-79, 2010-10
1 0 0 0 IR 東照大権現祝詞にみる徳川家光の東照大権現崇拝心理
- 著者
- 井澤 潤 Izawa Jun
- 出版者
- 駒沢史学会
- 雑誌
- 駒沢史学 (ISSN:04506928)
- 巻号頁・発行日
- no.79, pp.59-87, 2012-11
1 0 0 0 OA 日本漢方医学の伝承と系譜
- 著者
- 山田 光胤
- 出版者
- 社団法人日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋醫學雜誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.505-518, 1996-01-20
医療は専ら西洋医学を修めた医師によって行うこととし, 漢方を学んでも医師の資格は与えないという明治政府の処置によって, 明治16年 (1883) 以降漢方医学を学ぶ者は次第に絶え, 我が国の伝統医学・医療は絶滅に瀕した。 これは, 日本人の特に当時の政府人の西洋崇拝, 伝統蔑視の思想が強く関与しているものと思われた。 このような風潮は, 現在でも引き継がれていると考えられる。 しかし, 幕末から明治にかけて, 日本漢方を西洋医学と対比するに, 外科手術の面は別として, 内科的治療のレベルは, むしろ日本漢方が優れていた。 この具体的な症例を, 浅田宗伯は著書『橘窓書影』の中に記録している。 そのような時流の中で, 東洋医学を学んで医師となった和田啓十郎は, 漢方医学の有用性・重要性を唱えて, 明治43年 (1910), 『医界之鉄椎』を著した。 この書は実に, 漢方医学復興の一粒の種子となった。 金沢医専出身の医師・湯本求眞は, この書によって啓発され, 和田門下となって生涯を漢方医学の究明と, それによっての患者の治療に尽し, 昭和2年, 『皇漢医学』3巻を著した。 この書は, 西洋医学の知見を混えて, 傷寒諭, 金匱要略の解釈を中心にした, 漢方最初の現代語による解説書である。 湯本の『皇漢医学』は, その後の我が国に於ける漢方医学の復興に, 大きな影響を及ぼしたのみでなく, 中国に於ても, その伝統医学の温存にカを与えたといわれる。 ともあれ昭和年代初頭では, ごく僅かな生き残りの漢方医と数名の医師によって, 漢方医学が伝承されていたが, やがて, 漢方復興の機運が, 次第に醸成され, 種々な運動が起こった。 昭和11年 (1936), 当時新進の漢方医学研究者が志を同じくし, 漢方医学復興を目指してその講習会を開催した。 偕行学苑と名付けられたが, 翌年より拓大漢方講座と名を改めた。 この漢方講座は, 昭和19年 (1944) 迄8回, 毎回約3ヵ月乃至4ヵ月間ずつ開催され, 第2次大戦後の昭和24年 (1949) に, 第9回紅陵大学漢方講座として15日間開催された。 通算9回, 700名以上の有志が聴講し, 中からはその後, 漢方医学界の柱石となる人物も輩出した (筆者も, 戦後の第9回講座を, 医学生の身分で聴講した)。 第2次大戦前の昭和16年, 南山堂より『漢方診療の実際』という書が発行された。 この書は, 従来の「証」に随って治療する漢方の本質から一歩踏み出して, 現代医学的病名に対して, 使用した経験のある漢方処方を列挙して解説している。 当時とすれば画期的な漢方医学の解説書であった。 そして, 第2次大戦後, 昭和29年 (1954) に改訂版が発行された。 さらに昭和44年 (1969) に発行された『漢方診療医典』(南山堂)は, 漢方診療の実際を大改訂した書である。 これらの書を通じて解説された, 現代医学病名に対応して用いられる漢方処方の延長が, 現在の日本で, 大量に使用されている漢方製剤の応用なのである。 これらの書が, 現代日本漢方に及ぼした影響は多大なものがある。 その『漢方診療の実際』初版は, 大塚敬節, 矢数道明, 木村長久, 清水藤太郎の共著となっている。 これらの著者達こそ, 拓大漢方講座講師団の中核であって, その後の漢方復興運動を成し遂げた人達である。 それらの人達の系譜こそはまた, 現代日本漢方の正統でもある。 即ち大塚敬節は, 湯本求眞門下の古方派の学統を継ぎ, 木村長久は, 明治の大家・浅田宗伯の直門・木村伯昭の嗣子で折衷派の学統を継ぎ, 矢数道明は, 大正時代に活躍した漢方医・森道伯の流れを汲む後世派・一貫堂の後裔であった。(敬称略)
1 0 0 0 OA イオン交換樹脂を用いた硫酸水溶液からのスカンジウムの回収
- 著者
- 渡邉 寛人 早田 二郎 浅野 聡 邑瀬 邦明
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)
- 巻号頁・発行日
- vol.138, no.5, pp.51-59, 2022-05-31 (Released:2022-05-13)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
Ion-exchange process with chelating resins was investigated for recovery scandium from sulfuric acid aqueous solutions. An iminodiacetic acid type chelating resin, Diaion CR11, had a higher Sc adsorption selectivity than other elements. Diaion CR11 had high trivalent ions adsorption, and almost divalent ions other than nickel were not adsorbed. The adsorbed metal ions were eluted with sulfuric acid, and scandium was separated from aluminum, nickel and chromium. Only iron (III) showed a behavior similar to scandium and was difficult to separate with Diaion CR11. The elution behavior was related to the stability constants of the complex of iminodiacetic acid and metal ions.
1 0 0 0 OA フランス革命におけるバッツ男爵とブノワ
- 著者
- 小林 良彰 Yoshiaki Kobayashi
- 出版者
- 同志社大学商学会
- 雑誌
- 同志社商学 = Doshisha Shogaku (The Doshisha Business Review) (ISSN:03872858)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.58-77, 1978-07-25
研究
1 0 0 0 OA 『二コマコス倫理学』における愛
- 著者
- 赤間 脩人
- 出版者
- 茨城大学大学院人文科学研究科
- 雑誌
- 茨城大学人文科学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-17, 2011-02-28
アリストテレスが論じた愛(philia )について、それが何を意味するものだったのかを検討する。アリストテレスが愛において中心的に論じているのは自己愛である。その自己愛の理論をエゴイズムとの相違から検討することによって、最も優れて自己といえるものとは何かを明らかにした。それは自己の理性的部分である。自己を愛するとは理性(logos )を重視し、それが告げるように、あるべき仕方で行為することである。アリストテレスの愛は、現代ではその代替となるものが見られない程日常的で普遍的なものである。その本質が理性の重視にあるのならば、現代においても十分に顧みるべき価値のあるものである。
1 0 0 0 OA 空想傾性(Fantasy Proneness)研究の動向と展望
- 著者
- 山崎 有望
- 出版者
- 東洋大学大学院
- 雑誌
- 東洋大学大学院紀要 = Bulletin of the Graduate School, Toyo University (ISSN:02890445)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.37-63, 2021-03-15
- 著者
- 那須 識徳 山根 伸吾 小林 隆司
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- pp.21029, (Released:2022-05-16)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
目的:高齢になり運転などの移動手段を変更する必要がある場合に,個人の感情面や態度の準備状況を把握するための自記式質問紙としてAssessment of Readiness for Mobility Transition(ARMT)がある.本研究ではARMT日本語版(ARMT-J)の言語的妥当性を検証することを目的とした.方法:「尺度翻訳に関する基本指針」を参考にして「順翻訳,調整,逆翻訳,逆翻訳のレビュー,認知的デブリーフィング,認知的デブリーフィングのレビュー,校正,最終報告」を実施した.順翻訳と調整は国内の作業療法士3名が行い,逆翻訳は翻訳会社に依頼した.逆翻訳のレビューと認知的デブリーフィングのレビューは開発責任者に依頼し,認知的デブリーフィングは地域在住高齢者5名を対象に行った.結果:順翻訳では5項目,逆翻訳のレビューでは3項目で意見の相違が確認された.特に項目11の原文である「Moving to a retirement community is too restrictive for my desired mobility.」の中の「retirement community」は日本では普及しておらず,翻訳者間で日本語訳に相違を認めた.海外では「retirement community」は高齢者のための居住地域または建物と定義されており,翻訳にかかわった作業療法士3名と開発責任者にて協議のうえ,日本語訳は「高齢者のための住宅」とした.さらに,開発責任者に確認を行い,加齢のため移動手段を変更せざるを得ない場合,居住地域を変更する必要があるという意味が含まれているという補足文書をつけ,ARMT-Jを完成させた.結論:本研究ではARMT-Jの言語的妥当性を検討し,妥当と思われる日本語訳を作成した.
1 0 0 0 OA 「特別の教科 道徳」という不安/希望-「考え,議論する道徳」の行方-
- 出版者
- 九州教育学会
- 雑誌
- 九州教育学会研究紀要 (ISSN:02870622)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.3-40, 2019 (Released:2021-04-08)